
荒巻義雄 『小樽湊殺人事件』 : さよなら、荒巻義雄
書評:荒巻義雄『小樽湊殺人事件』(小鳥遊書房)
荒巻義雄は、小説を読み始めた高校生の頃に読んで、好きになった作家だ。
最初に読んだのは、筒井康隆選『実験小説傑作選』(集英社文庫・1980年)に収録されていた、荒巻のデビュー作短編「大いなる正午」だった。
なにしろ『実験小説傑作選』というくらいだから、基本的に変わった小説が集められているわけだが、この「大いなる正午」などは、冒頭からいきなり、何が書いてあるのかさっぱりわけのわからない描写が続いて、ひどく面食らったものだ。
だが、読み進めていくうちに「異次元空間でのダム工事」か何かを描いた作品だというのが徐々に分かってきて、「ああ、こういう書き方もあるんだな」と感心した記憶がある。
だからその後は、冒頭部が「意味不明」に近い、いかにも「難解」そうな作品に行き当たっても、「しばらく我慢して読み進めていけば、そのうち世界観がつかめてくる」といった読書の要領を、この作品で会得することができた。
最近読んだ、グレッグ・ベアの中編集 『鏖戦/凍月』 の「鏖戦」の出だしも「なんだこれ?」というような作品だったが、「大いなる正午」の経験が役立って、冒頭部分で怯むようなことはなかった。
しかし、荒巻義雄の「ファン」になったと言えるのは、短編集『ある晴れた日のウイーンは森の中にたたずむ』(講談社文庫・1980年)に収められた、表題作においてであった。
この作品は、たしか「失踪した女性画家の影を追って、フランスの地を彷徨う青年の幻想彷徨記」みたいな内容で、現実と幻想と虚構が交錯する「私好みの作品」であり、SFというよりも幻想小説と呼んだ方が、いっそ誤解のない作品であった。
私はそんな「現実と虚構のあわい」を揺れ動くような作品が大好きだったし、本作はとてもロマンティックな作品だったので、高校生の私のナイーブなハートを、ガッチリと捉えてしまったのであろう。
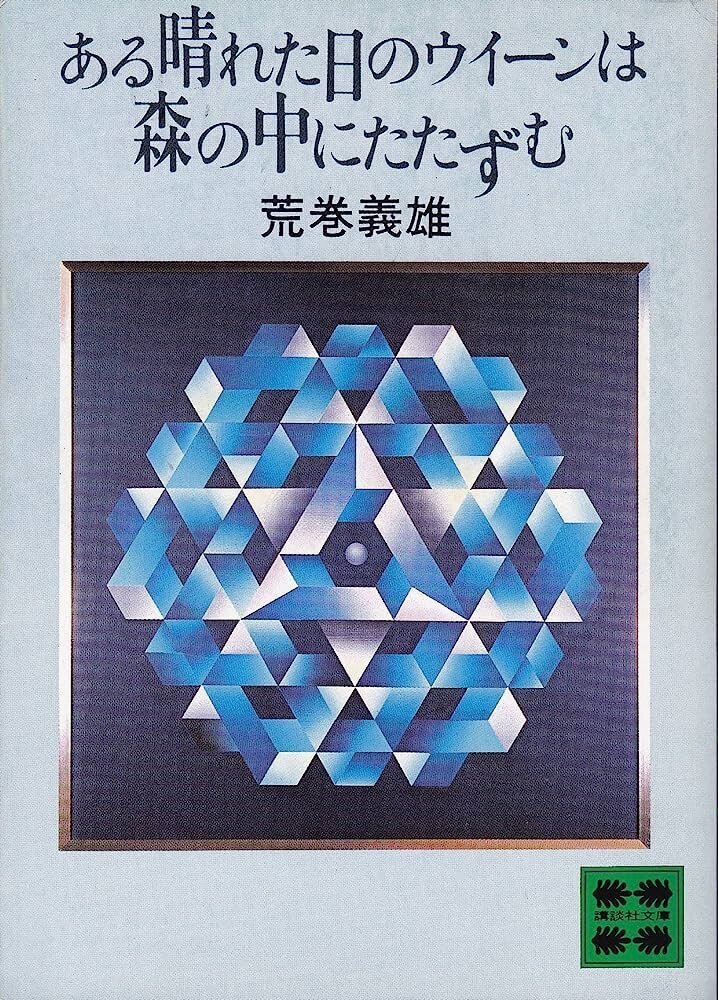
このあと、この「ある晴れた日のウイーンは森の中にたたずむ」が与えてくれたような魅惑を求めて、荒巻の初期短篇のほとんどを読んだはずなのだが、しかし、その期待を満足させるような作品には出会えなかった。
それでも、「ある晴れた日のウイーンは森の中にたたずむ」の長編化作品『白き日旅立てば不死』や、その続編である『聖シュテファン寺院の鐘の音は』には、当然のごとく期待したが、しかし、どちらも期待ほどの作品ではなかった。
しかしまた、若い頃の私は、エッシャーやマグリットの「騙し絵」的な不思議な絵が好きだったので、エッシャーの作品世界を舞台とした連作短編集『カストロバルバ』(文庫では『エッシャー宇宙の殺人』と改題)は、かなり気に入って、主人公名による「織語署名本」を入手したし、文庫化された際に、笠井潔が「解説」を書いていたことにも「さすがは笠井潔」と感心した。


私は、熱心な「笠井潔ファン」から「笠井潔葬送派」に転じたような人間ではあるけれども、笠井の実力は認めていたので、そう素直に感心したのだし、笠井の幻想長編『黄昏の館』を読んだ時は、すぐにこれが、荒巻義雄の『白き日旅立てば不死』を下敷きにした作品だと気づき、前半はその雰囲気をそれなりに楽しんだのだが、最後でいきなり「超能力SF」ものになっていたので激怒した、という思い出もある。

一方、私は「伝奇ロマン」や「スペースオペラ」にはまったく興味がなかったので、荒巻についても、そっち系統のシリーズ作品は1作も読んでおらず、そうこうしているうちに荒巻は「架空戦記もの」を書いてベストセラー作家になったので、個人的には「私の期待する荒巻義雄は終わったな」と、すっかり見放してしまった。
その後、中井英夫の『虚無への供物』や竹本健治の『匣の中の失楽』などに出会い、そこから同世代による「新本格ミステリ」ムーブメントに巻き込まれて、すっかりミステリの方へ転じた私は、それをきっかけに、それまで未読だった荒巻の「伝奇ミステリ」だけは読んでみようと思い、『石の結社』と『天女の密室』は読んだのだが、しかし、これらも、私の期待するような「幻想ミステリ」でもなければ「本格ミステリ」でもなかったため、いよいよ荒巻義雄を見限ることにした。
「もう、荒巻には、初期の傑作短編のような、叙情的な幻想小説は書けそうにない」と、そう断念したのである。


そして、それから20年余の昨日、ひさしぶりに荒巻義雄の新作長編を読むことにした。
その理由は、本作『小樽湊殺人事件』が、どうやら「本格ミステリ」のようだし、何よりも帯に大きく、
『SF作家のメタ・ミステリー』
とあったからだ。
「メタ・ミステリー」には一家言ある私としては、かつて好きだった作家が「メタ・ミステリー」を書いたというのであれば、確認しないではいられなかったのである。
(※ 「自己言及的ミステリ」という意味での「メタ・ミステリー」など、数えきれないほどあるが、「アンチ・ミステリー」とは、「自己言及」に止まらず、さらに踏み込んで、ミステリという形式を批判的に相対化する性格を持つミステリ作品を言う)
だがまた、正直なところ、まったく期待してはいなかった。
なぜなら、若い頃ですら魅力的な「幻想ミステリ」が書けなかった作家が、「89歳の高齢になって、いまさら魅力的なミステリなど書けないだろう」「文章もスカスカになっているんじゃないか」と、そう思ったからである。
で、結果はどうだったかというと、意外にも、読ませる文章で面白く読ませるだけの力を感じさせる作品になっていた。意外にも「老いて枯れた、スカスカの文章」にはなっていなかったのである。
それに、いろいろと工夫の跡も見られて、「これは意外にも、ちょっとした拾い物かもしれないぞ」と期待したのだが、一一最後は「頑張っているけど、これはちょっとなあ」という感じの作品にしか、なっていなかった。
読む前に覚悟したほど酷い作品ではなかったけれど、読み始めてからしばらくのあいだ期待したほどの作品でもなかったのだ。

全体として言えることは「大風呂敷の広げ方は上手い」のだが、その畳み方が「本格ミステリ」としての緻密さに欠けて、いかにも「大味」な作品になっていた。
一応、その「大風呂敷」において読ませるのだけれど、結果としては期待させたほどのものではなく、いかにも「架空戦記ものでベストセラー作家」になった人だ、という感じだったのである。
例えば、著者は高齢であるにもかかわらず、「メタ・バース」だの「画像生成AI」だのといった最新の話題も取り込んでいるし、ジュリア・クリステヴァやミッシェル・フーコーなんかを引用して見せたりして、「おっ、勉強しているな」と感心させられる。
あきらかに、もともと好きな、アガサ・クリスティやコナン・ドイル、あるいは江戸川乱歩といった「古馴染み」だけに自足しない、知的意欲をうかがえる作品だったのである。
ただし、はっきり言ってしまえば、もともと好きなところ以外の知識が、いかにも「付け焼き刃」で「うすっぺらい」。
ミステリ作家だけではなく、エリオットや志賀直哉や森鷗外などの「文学」系の作家にも言及するのだが、その扱いは、あくまでも「知識」レベルであって、「文学的な深み」が無い。
この程度の言及なら、ネット検索して得られるレベルの知識で十分だという、表面的な「読み」の提示にしかなっていない。
そしてこの「表面的珍奇性」というところが、どうやら荒巻義雄の、少なくとも「今の個性」である、というのが窺えてくる。
いろんな知識を意欲的にぶち込んできて、それについてひととおりの見解を開陳するにはするのだが、そうした意見に「深み」が無い。
なるほどこの人は、「理論」には詳しくて、それを「実用的に利用」する「術」には長けているのだろうが、それらのものが、人間にとって持つところの意味を深く考えるというようなところが、まったく無い。
「これはこれに使える、これを使えば、こうした可能性が開ける」といった、いかにも「実業家」的な見解は語れるのだが、それについての「哲学的な思弁性」が、まったく無い。
この人には、「実用性」を超えて、深く物事の本質に迫ろうとする、哲学的思弁性が無く、おのずと人間の内面性に対する深い洞察も無いから、作品の印象として、「文学性」が感じられないのだ。
端的に言ってしまえば、この人の駆使する「知識」や「理論」は、所詮「鬼面人を威す」態の飾りものでしかない。人間の本質に迫る力がないから、もったいをつけているわりには、本質的に「軽い」という印象が拭えないのである。
そして問題は、こうした「総合的な評価」だけでは済まない。
例えば、私が驚かされたのは、自称「メタ・ミステリー」についての、次のような理解だ。
『(〈メタフィクション〉とか〈メタSF〉とか言うが、〈メタ・ミステリー〉は初めてかもしれない。)』(P159)
『 瓜生(※ 主人公)がつづける。「今言われたタイプの他に、これは私が今度の仕事で考えている、いわば私なりのイノベーションですが、〈自己言及的推理小説〉があると思うのですがね」
「なるほど、まさに新機軸ですね」
と、一乗寺社長も話に乗ってきた。』(P212)
もちろん、これは、著者をモデルにした「主人公の小説家・瓜生鼎」の思いや言葉なので、著者の考えそのものではない可能性も、ないではない。
しかし、この主人公は、著者と同じく、昔からミステリを読んできたミステリ・マニアであり、乱歩の『類別トリック集成』にも載っていないような「新規なトリック」のミステリが書きたいと考えるような、著者と同様、すでに何冊ものミステリ作品を書いてきた小説家だ、という設定なのである。
しかも、主人公がこのように考えた「現在時」は、『2002年(平成一四年)』(P173)なのである。
つまり、古株のミステリマニア同士の会話として書かれているはずなのに、この作品の中では、まるで『虚無への供物』(1964年)も『匣の中の失楽』(1978年)も存在しないし、作中のミステリマニアの大学生たちがミステリを語り合うシーンの多かった、初期の「新本格ミステリ」(1988年〜)も存在していない。
それどころか、クリスティやドイルやルルーやクイーンやヴァン・ダインに言及しておきながら、あまりにも有名な「密室講義」を含むカーの『三つの棺』(1935年)が存在していないかのようなのである(なお、ポストモダン・ミステリとしてのメタ・ミステリなどを論じた、ステファーノ・ター二の『やぶれさる探偵 推理小説のポストモダン』は、1990年に邦訳が刊行されてもいる)。


もちろん、そういった名作の存在しなかった「特殊世界」だという設定で書かれているのならかまわないが、そういう記述などまったく無く、驚くべきことに荒巻義雄は、本気で『〈メタ・ミステリー〉は初めてかもしれない。』と思い、さらには『〈自己言及的推理小説〉』が『まさに新機軸』だと思って、本作を書いていたのである(!)。
つまり、著者がひけらかして見せる、あれこれの「知識」とは、所詮「この程度」のものでしかない、ということなのだ。
これでは、いくら著者の年齢が「89歳」でも、大目に見ることはできないだろう。
そして、こんな著者における「知」の質が、どのようなものであるかをうかがわせる描写もあった。
『もっとも、彼の読み方は熟読するのではなく、速読法である。
しかし、『黄色い部屋の秘密』は、速読法では手強い。論理的で、しかも緻密なのだ。文が堅牢なのである。』(P202)
これも、『彼』たる「主人公・瓜生鼎」についての描写なのだが、私は「速読法の小説家」が出てくる小説など初めて読んだし、著者自身が「速読法」を採用しているのでなければ、自分の分身たる作中の小説家を、このように「設定」したりはしないのではないかと疑った。
そして、案の定である。
『画廊の経営など、実業の仕事から手を引いた今の私は、土日、祭日もお構いなしに、PCに向かって文章を書いているし、次々と新刊書を買い込んで、速読、あるいはPCで検索したり、教育系のテレビ番組を観てメモを取ったりしています。』(P431、「あとがきに代えて」より)
やっぱり、そういう「即席もの(の知)」だったのだ。荒巻義雄は「速読をする小説家」だったのである。
無論、「速読」が、いちがいに悪いとは言わない。それは、即席的に「情報を得る目的」での読書にならば、十分に役立つだろう。
だが、「速読」では「論理的で緻密」な本、つまり『黄色い部屋の秘密』のような「本格ミステリ」だけではなく、「哲学」書や、本格的な「思想書」は読めないし、『文が堅牢』な、例えば「文学書」も読めない。緻密な人間心理を描いたような「文学作品」を、「速読」で味わうことなど不可能なのだ。
つまり、それがすべてではないにしても、荒巻義雄という作家の強みは、そうした「表面的な情報の量」であって「練り込まれた、深い思弁や人間洞察」ではない、ということなのだ。
だから、いろいろと知っていて、いろいろと一家言がありながら、全体の印象としては「軽い」し「深みが無い」のである。
だからもう、今度こそ、今度こそ「さよなら、荒巻義雄」だ。
劇場用アニメ『銀河鉄道999』(りんたろう監督)ではないけれど、「さらば、荒巻義雄。さらば、少年の日の幻影…」とでも言わざるを得ない、どうしようもなく悲しい結果(決別)となってしまったのである……。
○ ○ ○
さて、ここからは蛇足的な話になるが、しかし、たぶん多くの人には、こちらの方こそが「衝撃的な指摘」となるのではないかと思う。
何かというと、「ミステリファン」の風上にもおけない、「アンフェア」な行いの疑惑である。
私が、ひっかかったのは、本書に関する、Amazonカスタマーレビューにおける、「K-One」氏の「マニエリスム思考が生んだ傑作ミステリー」と題する「星5つ(満点)」のレビューである。
『 K-One(5つ星のうち5.0)
マニエリスム思考が生んだ傑作ミステリー
2023年2月8日
「SF作家のメタ・ミステリー」と銘うつ本書は、難解なSF、伝奇推理、仮想戦記で知られる荒巻義雄の本格ミステリーである。二〇二二年七月に伝奇推理の復権を目指して超古代史の謎に迫った「小樽湊シリーズ」三部作の完結巻『出雲國国譲りの謎』を刊行したが、本作ではその「小樽湊」を舞台に引き継いで、密室殺人や暗号解読など推理小説の王道を行く重厚な作品に仕上げている。なにしろ昭和二十二年から平成十六年までの五十六年間がつながる殺人事件なのだから、「連続殺人事件」と呼ぶのがいいのか「不連続殺人事件」と称すべきか…。因縁めいた殺人事件は横溝正史の小説の趣もある。
小樽湊は実際の港湾商都小樽をベースに構想された架空の都市だが、戦後から平成にいたる世相の移り変わりや街の空気が活写され、謎解き以外の小説の面白さも味わうことができる。さらに架空都市という設定を生かして、このミステリーにSF作家ならではの〈湊フロンティア計画〉という近未来のメタバース世界の構想を盛り込んでいることは特筆される。荒巻には過去に『カストロバルバ』というエッシャーのありえない世界を舞台とした連作SF推理小説があったが、本作は伝統的な本格ミステリーの形をとってはいても、マニエリスムの「SFする思考」を強く意識することでメタ・ミステリーと呼ぶにふさわしいより豊潤なミステリーの将来をも射程に捉えているのかもしれない。
「小樽湊シリーズ」で定番となった著者による巻末の[用語解説]は、九十歳になる現役作家から若い読者らへの配慮なのだろう。各章の冒頭に付けられた惹句はすべてアガサ・クリスティの諸作から引用され「ミステリーの女王」へのオマージュとなっているが、ほかにもドイル、ヴァン・ダイン、クイーン、ルルーや乱歩まで名作推理小説や研究書への言及も多く、ぼく自身それらに熱中した中学時代を思い出した。また[間奏曲]として挿入される《クリスタル・アート・バー》の大仕掛けは北国ならではの趣向で、どの作も奇想天外なトリックが定評だったデビュー直後の島田荘司の小説を彷彿とさせる。笑ってしまえるような言葉あそびの種明かしまである。付録としてつけられたマニエリスムの教祖高山宏との往復書簡も読みごたえがある。
瓜生夫妻と一色館長をコンビとする次作を期待させる傑作である』
まるで、出版社による「商品紹介文」のような、至れり尽くせりのレビューである。
著者が紹介して欲しいところを漏れなく、紹介してほしいとおりに紹介しているような文章で、まるで「著者の側」の人間が書いた文章としか思えない。
で「こいつは何者か?」と疑問に思い、他にどんなレビューを書いているのかとチェックしたところ、レビューは現時点で5本だけだったが、その内容が次のとおり(ちなみに、全て星5つ)。
(1)荒巻義雄『小樽湊殺人事件』(小鳥遊書房・本書)
(2)荒巻義雄『SFする思考: 荒巻義雄評論集成』(小鳥遊書房)
(3)荒巻義雄『もはや宇宙は迷宮の鏡のように』(小鳥遊書房)
(4)林田こずえ『戯曲絵本 カラクリ匣』(小鳥遊書房)
(5)日野猛之『新型コロナ禍に思うこと』(Kindle版・無料配布)
これを見ただけで、「K-One」氏は、「荒巻義雄」の熱狂的信者か、「小鳥遊書房」関係者か、と疑われる。
では、(4)の、林田こずえ『戯曲絵本 カラクリ匣』は、どんな本かと、同氏のレビューをチェックしてみると、
『 林田こずえって誰? 作者はこの本の出版元・小鳥遊書房の編集者であり、ここ数年の間に話題となった本を自身の手でいろいろ世に送っている。その編集者が満を持して、学生時代に書き下ろして上演した作品を上梓したのだという。』
とある。

このような無名の素人作品を、読むだけではなく、ご丁寧にレビューまで書くというのは、親類縁者か、「献本」を受ける関係者、つまり、完全に「小鳥遊書房」の「関係者」であろうし、この編集者・林田こずえが、荒巻義雄の担当編集者なのであろうことも、容易に推察できる。
なぜなら、『小樽港殺人事件』のレビューで、「K-One」氏が『付録としてつけられたマニエリスムの教祖高山宏との往復書簡も読みごたえがある』と評したのと同様に、本書のレビューでは『幕が閉じたあとには高山宏の解説と作者の言葉が続き』という紹介があって、両者は「高山宏」でつながるのだ。
そして、これは「小鳥遊書房」のこれまでの出版履歴からすれば、「高山宏」を中心にして「荒巻義雄」と「林田こずえ」がいるというよりも、「荒巻義雄」を介して「高山宏」と「林田こずえ」がつながったと見た方が、よほど自然ではあるまいか。
では、「小鳥遊書房」からの刊行物ではない、(5)の日野猛之『新型コロナ禍に思うこと』はどうか?

この作品にも「K-One」氏は懇切なレビューを寄せているが、作品の内容紹介は、次のとおりである。
『 新型コロナの感染が、なかなか収束しません。そして、自宅にいる時間が長くなりました。ふと気づくと、読みかけの本が足元に落ちた音で、目が覚めます。歳のせいか、最近の本は、結論に至るまでの説明が、とても長く感じられます。それで、集中して読み続けることができません。
高齢者は、残された時間が短いのです。すぐに結論を知りたくなります。子供には、絵本があります。ですが、高齢者向けの本が見つかりません。それで、簡潔に書かれた「新型コロナ禍に思うこと」100話を書いてみました。若い人も目を通していただけるならば、望外の喜びです。(まえがき)』
どうやら、著者自身「高齢者」のようである。
そして、この著者には、他に著書があるのかと調べてみると、同じく「Kindle版・無料配布」の『僕の婚約者』というのがあった。

著書は、この2冊だけのようだが、なぜかこちらには、「K-One」氏は、レビューを寄せていない。で、どのような内容の作品かと、「内容紹介」を見ると……。
『 鶴見拓哉が、鶴見探偵事務所を開設して、しばらくは調査の依頼がほとんどなかったが、最近になって、2件の調査依頼が来た。1件目は、日高医院の院長、日高陽一の息子、学からの依頼で、父親の幼い頃の調査である。日高陽一は、認知症を発症しており、古希の祝いの席で、これまで聞いたことのない子供達の名前を叫んで取り乱したという。2件目は、鶴見拓哉が懇意にしている、K警察署の寺崎署長の依頼で、迷宮入りしそうな栗原弁護士殺人事件に関する調査である。この2件の依頼は、当初別々の事案と思っていたが、調べていくと、密接に絡み合っていた。鶴見拓哉は、妻、直子、娘、智子の助けもあって、真相を探り当てる。そこには、日高陽一の幼い頃の微笑ましい過去が隠されていたのである。
著者プロフィール
日野猛之
北海道生まれ
早稲田大学 第二文学部 卒業 』

どうやら「高齢者の登場するミステリー小説」のようなのだが、引っかかったのは、こちらにだけ付されていた、「著者プロフィール」の中身である。
『北海道生まれ』の「高齢者」というと、荒巻義雄に近い人なのではないか?
そこで、荒巻義雄の経歴を「Wikipedia」で調べてみると、
『早稲田大学第一文学部心理学科卒業。』
一一これは、偶然なのか?
たしかに、「第一学部」と「第二学部」の違いはある。だが、荒巻義雄と日野猛之には、『北海道生まれ』の「高齢者」で「ミステリ小説を書く」という共通点があり、さらに言えば「K-One」氏は、有名無名に関わりなく、両者に対して、同様に好意的で懇切なレビューを寄せているのである。
さらに、気になるのは、日野猛之の『新型コロナ禍に思うこと』の方には、あれだけ好意的なレビューを寄せていながら、もう一冊の『僕の婚約者』の方には、どうしてレビューを書かなかったのか?
もしかするとその理由は、『僕の婚約者』の方には、『北海道生まれ』『早稲田大学 第二文学部 卒業』という「著者プロフィール」があったからではないのか?
だとすると、「K-One」氏の「正体」は、「あの人」以外にはいないのではないか?
そう考えれば、本書『小樽港殺人事件』の「あとがき」と、「K-One」氏のレビューは、宣伝臭の強い、その「にぎやかな文体」において、妙に「似ている」と感じるのは、私の単なる思い過ごしなのだろうか?
「K-One」氏は、「文体」が似てしまうほどの熱心な「荒巻義雄ファン」であり、だから、荒巻義雄の新刊だけではなく、その本を刊行してくれている「小鳥遊書房」の編集者の本や、荒巻に「プロフィール」の似た「日野猛之」の本にまで、好意から熱心に宣伝してくれている、ということなのであろうか?
一見したところ、「小鳥遊書房」とは無関係らしい、しかし「プロフィール」的に、きわめて荒巻義雄に近い「日野猛之」とは、何者なのか?
いずれにしろ、「K-One」氏のレビューには、「荒巻義雄」関係者、あるいは「小鳥遊書房」関係者による、ステマ(ステルス・マーケティング)臭がぷんぷんするのだが、もし、これが事実だとすれば、それは「不正なレビュー」ということになるはずだ。
連絡先のわからない「荒巻義雄」は別にして、「Amazon」や「小鳥遊書房」に問い合わせたをしたら、どのような返事が返ってくるのか、とても気になるところである。
(2023年7月14日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
