
笠井潔・野間易通 『3.11後の叛乱 反原連・しばき隊・SEALDs』 & 鹿砦社 特別取材班 編著 『反差別と暴力の正体 暴力カルト化したカウンター - しばき隊の実態』 : 万人に秘められた、暴力性の現実
書評:
笠井潔・野間易通『3.11後の叛乱 反原連・しばき隊・SEALDs』(集英社新書)
鹿砦社特別取材班編著『反差別と暴力の正体 暴力カルト化したカウンター - しばき隊の実態』(鹿砦社)
『反差別と暴力の正体』が暴露したのは、リベラルな反体制運動としてのSEALDsやしばき隊などの市民運動が、その陰に暴力性(テロリズムの肯定)を隠し持っていたという「残念な事実」です。
同書を読んで痛感させられるのは、人間が組織的に動く場所においては、人間の暴力性というのは多かれ少なかれ発現せざるを得ず、その例外は無いという「残念な現実」だと言えるでしょう。
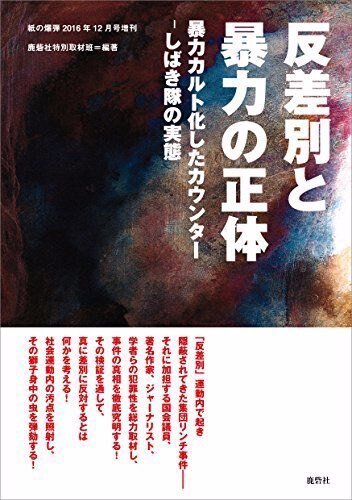
笠井潔と、しばき隊の創設者と呼んでよい野間易通との往復エッセイ集である『3.11後の叛乱』は、当然のことながら「反原連・しばき隊・SEALDs」とつづく、新しいかたちのリベラルな市民運動を肯定的に評価し、一方『反差別と暴力の正体』の方は、そうした新しい運動の陰にも隠されていた暴力性を暴いて、これを批判したものだと言えます。そして両著のAmazonレビュー欄もまた、そうした「政治的闘争の場」と化している観があります(後者支持が優勢だが)。

しかし、『反差別と暴力の正体』が暴いたのは、単に「反原連・しばき隊・SEALDsの隠された暴力性」ではなく、「すべての人に伏在する、人間の根源的暴力性の存在」なのではないでしょうか。
つまり、思想の左右に関わらないのはもちろん、どんな思想や理想・理念を持っているかにも関わりなく、すべての人間があらかじめ秘め持っている暴力性の存在事実なのではないか、ということです。
だからこれは、私自身を含め、すべての人にとって、決して他人事ではない。
どんな理想を掲げている人であろうと、どんな思想を持ち、心からそれを信じていようと、すべての人には暴力性が伏在しており、現実の難問にぶち当たった時に、それが鎌首をもたげてしまう。「この場合、多少の暴力はありだろう(正当化されるだろう)」と考えてしまう。
そして、そうした暴力性というのは、人が二人から始めて集団化するのに比例して、その発現率を高めてしまいます。
くり返しますが、そこでは思想の中味は基本的に関係がない。
では、我々はばらばらの個人として生きればいいのかというと、それは不可能です。人間は社会的な動物だからです。だからこそ私たちは、暴力性を完全に排除することが出来ない。だからこそ国家や戦争を超えることが出来ないのではないか。
私たちは、自分が個人に止まり目立った誤ちを犯さないからといって、集団化による誤ちを犯した人たちを、他人事のように上から目線で批評批判して済ませるわけにはいきません。私たちすべての人間は、間違いなく集団化とその暴力性の恩恵を被りながら生きているからです。
近年キリスト教の問題に興味を集中させている私が、この問題に興味を持つのも、それはこれが「すべての人間」にかかわる問題、つまりクリスチャンをはじめとする全ての信仰者にもかかわる問題だと見たからです。
なぜ、愛と赦しを説くキリスト教が、多くの異端者や異教徒を虐殺する蛮行を犯したのか。
それは彼らもまた人間であり、その限界を、信仰を持ってしてもついに乗り越えられなかったからだと、そう考えるからです。
今は、暴力では対抗できないライバルとしての「国家」が存在するから、その暴力性は前面に出てこないけれど、イスラームであれキリスト教であれ、その暴力性の実力が諸国家の暴力性をしのぐようなことになれば、その暴力性は必ずやまた発現されることでしょう。これは宗教・信仰もまた、思想や理想や理念などと同様に、人間の潜在的本質としての暴力性を乗り越え得ないからです。
では、我々はこの難問に、どのように立ち向かえばよいのか?
その答は、私にはありません。
ただひとつ言えることは、私たち自身の中に伏在する暴力性を、すべての人が自覚し、それと向き合うことが、まずは必要であり、すべてはそこからしか始まらない、ということです。
自身を、暴力性とは無縁な理想を信奉する(無欠な正義の)人間だと思い込んでいるかぎり、その人が自身の暴力性と対峙することが不可能なのは、理の当然なのですから。
『反差別と暴力の正体』の中味にそって言うと、ここには「暴力肯定の新リベラル左翼(反原連・しばき隊・SEALDs)」対「反暴力の旧来の反体制言論左翼(鹿砦社)」という図式が描かれていますが、これまでの議論でも明らかなように、この図式は、人間の普遍的かつ本質的な暴力性の問題を度外視した、表面的かつ一方的な議論にすぎません。「非暴力」を自称しながら「反原連・しばき隊・SEALDs」を批判する側にも、必ずや「語られない暴力性」が大なり小なり存在していることでしょう。その一端が、Amazonレビューの場にもささやかながら発現しています。
笠井潔と野間易通の共著が成立したのも、両者が「反新左翼」という立場で共通したからです。
笠井は、連合赤軍の総括殺人事件を左翼運動に伏在する本質的な問題として捉え、それを乗り越える試みとして『テロルの現象学』を書いて、自らも関わった左翼運動の難問を総括したと主張し、自分以外の大半の左翼活動家たちは本質的総括をやらないまま文化左翼として延命したと批判しました。その代表が、坂本龍一や糸井重里、高橋源一郎などだと、事あるごとに批判しています。
だから笠井潔は、SEALDsやしばき隊を評価しつつも、彼らと連携する左翼文化人や知識人、例えば小熊英二などを批判していますが、その批判の根拠は小熊が高橋源一郎らとも共闘する、同系統の無反省な文化左翼だという位置づけにあります。
知ってのとおり、SEALDsを中心としたリベラルな新社会運動は、旧来の「新左翼セクト」の運動への浸透を警戒し、これの排除に腐心しています。
国会前デモや沖縄での反米軍基地運動でも、新左翼セクトが暴力的な扇動を行い、運動のヘゲモニーを握ろうとしているのが迷惑でしかない、あくまでも自分たちはリベラルな運動に徹したいのに、という趣旨のことを、野間易通をはじめとしたSEALDsやしばき隊のメンバーは語っています。
しかし、暴力悪は、何も新左翼セクトにだけあるのではなく、彼ら自身にもあったことが『反差別と暴力の正体』で暴かれました。結局のところ、彼らの新左翼排除は、暴力の排除ではなく、運動におけるヘゲモニーの争奪戦にすぎなかったということが明らかになったのだと思います。
これは、笠井潔の文化左翼批判と同じで、結局は「あいつらは間違っており、自分が正しい」というアピールによるヘゲモニー争奪戦と同型なのでしょう。だからこそ、笠井潔と野間易通の共著は成立した。
しかしながら、笠井潔は『テロルの現象学』で「自分は左翼運動に内在する暴力性を剔抉し、他の文化左翼はそれをしなかった」と批判したのだから、自身が高く評価したSEALDsやしばき隊でも、同様の内ゲバ的テロリズムの存在が明らかになった以上、笠井はこれの徹底的総括を行わないでは済まされないでしょう。
その意味では、私は古い笠井潔ファンであり「笠井潔葬送派」として、笠井潔の態度に注目したいと思っています。
ともあれ、私が本稿で言いたいのは、SEALDsやしばき隊が隠し持っていた暴力性は批判されねばならないものではあれ、それは「敵」を批判する行為としてではなく、「自身の醜い似姿」を批判するものでなければならない、ということです。
で、なければ、いつかは自分も、同じことをすることになるからです。
初出:2016年12月30日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
・
・
