
笠井潔・ 絓秀実 『対論 1968』 : 笠井潔における 「道具としての他者」
本書は、「1968年」を頂点とした「民衆蜂起」の歴史こそが、日本における「革命」問題の焦点であり、その意義と課題が正しく問われなければ、今後の日本は言うに及ばず、この世界はさらにロクでもないものになるしかない、といった観点から、当時をふり返って検討した対談だと、一一ひとまずは、そうは言えるだろう。
だが、帯にある、
『〈論敵〉の批評家同士による、最初で最後の「対話」』
というほどの緊張感は、まったく無い。
笠井潔の方はいつもどおりに「すべてを見切ったような教説」を繰り返すばかりだし、絓秀実の方は文芸評論家としての仕事も無くなってひさしいせいか、自身の原点である「1968年とは、何であったのか」を研究しつつ、その意義が見失われた現在を嘆いている「反体制老人活動家」という感じで、二人は喧嘩をするどころか、お互いにフォローし合いながら「あいつらはわかってない、こいつらはダメだ」と、評論家的に他者を裁断するばかりなのだ。
ちなみに、笠井潔は当年74歳。絓秀実は73歳である。

笠井潔が一時期、大ブームになっていた「新本格ミステリ」の世界(業界)に入ってきて、かつて新左翼党派のイデオローグ(党派理論家)たりえた、お得意の「扇動者的口説」によって、ミステリ業界を牛耳ろうとしたものの、なまじの成功が仇になって、やりすぎてしまい、最後は業界の多くから疎まれて、そこをさらねばならなくなったというのは、周知のとおり(『容疑者Xの献身』論争=「本格」論争)。
本書に中でも、笠井は、冗談めかしながら、こんな言葉を漏らしている。
『白川真澄がボスだった京大派との闘争に時間とエネルギーを使いすぎて、理想とする〝ルカーチ主義党〟の骨格が整った時には〝68年〟の高揚はもう終わっていた。その後も同じようなことが繰り返されるわけで、何と言うか、我が人生ですな(笑)。いいところまで行っても、最後は元の木阿弥。』(P40)
私の知る範囲で言えば、これは「新本格ミステリ界における、探偵小説研究会」だとか、その後の「ゼロ年代カルチャーを守備範囲とした、限界小説研究会(現・限界研)」のことも含めて言っていると見てよいだろう。
最近の笠井潔は、90年代半ばから10年ほど、自分が「ミステリ界」に関わったのは、それが「この時代」を考えるためのものであった、というような言い方をして、政治思想の現場からすっかり遠ざかっていた事実を、自己正当化している。だが、この言い訳は、本末転倒した話でしかない。
なぜなら、笠井潔の「思想」とはもともと、「世界」や「ミステリ業界」といった「対象」のためのものではなく、端的に、自身の過剰な「支配欲」を満たすための「武器・道具・方便」でしかないからだ。
笠井の場合、実のところ「真理」になど興味はなく、世界を意のままに蹂躙したいという、自身の「欲望」を満たしたいだけなのである。
笠井は、新左翼時代に失敗した「政治党派」の構築を超える、「文化的な覇権の拠点」とすべく、そうした意図を秘めてミステリ界に入っていった。
自分よりひと回り以上年下の「ノンポリ・オタク」作家たちを相手に、「ミステリ」の話に事寄せた「世界史的知識」とその「口説」をもって、彼らをオルグし、「政治利用」しようとしたのだ。
手始めに笠井は、「手駒」を養成するための「探偵小説研究会」を立ち上げ、そこを拠点に、その「党派理論家(イデオローグ)」としての影響力を、新本格ミステリ業界全体にまで広げていった。「本格ミステリ」にご大層な意義を与える、理論的守護神となったわけである。
そして、それが歓迎され、なかなか『いいところまで』いったため、調子に乗ってしまい、さらに広範なミステリ界の「主流派の象徴」と目した、東野圭吾の直木賞受賞作『容疑者Xの献身』に、無理筋の難癖をつけた結果、自爆してしまったのだ。

「世界史」や「政治思想」の話でなら、口を挟むことのできないミステリオタクたちも、ことミステリについてなら、自信を持って、自身の評価や価値観を語ることができた。そこに限定するなら、その知識と理解において笠井にも劣ってはいないという自負を持っていたというのは、オタクなればこそ当然のことだったのである。
だが、笠井は端から「オタクなど、なんとでもできる」と舐めていたから、うかつにも彼らのプライドを逆なでするような「ゴリ押し」をしてしまったのだ。
笠井は、その昔、柄谷行人へのインタビューの中で「党派の仲間の前で、理屈ならなんとでもつけられると軽口を叩いて、顰蹙を買ったことがある」と、冗談めかした「自慢話」をしたような、人を小馬鹿にした、自信過剰気味の「口説の徒」であったから、まさかミステリオタク(の作家や評論家)ごときが、自分の「立論」に反対するなどとは、思っても見なかった。
それで、つい、怒り心頭に発して「信任投票に敗れたからには」ここに止まれないと、「探偵小説研究会」を割って出て、実質的に「新本格ミステリ」界からも去らざるを得なかったのである。

笠井潔が、こうした無責任で自己中心的な「口説の徒」だというのは、次のような言葉にも窺えよう。
『言葉で語られる世界認識なんか、いくらでも変わりうるものです。重要なのは、とにかく路上に出てくること。2011年国際蜂起の総括としてバトラーやネグリが言い始めたように、どんなデモにもアセンブリとして、神的暴力(解放的な暴力)のかけらくらいは宿っているものです。行動がラジカルであれば、認識なんか後からついてくる(笑)。だからしばき隊による排外主義デモとの実力対決と、新大久保一帯の騒乱化を行動的にさらに加速させることが問題だったと思う。香港のようにいかなかったのは、まあ現時点での日本の限界でしょう。』(P242〜243)
『言葉で語られる世界認識なんか、いくらでも変わりうるものです。』『行動がラジカルであれば、認識なんか後からついてくる(笑)。』一一つまり、笠井が望むような「大衆蜂起」が成功すれば、それを正当化する「理屈など、後からなんとでもつけられる」ということであり、要は「勝てば官軍」「歴史は勝者によって書かれる」といったことと大差のない話なのである。
だが、笠井にとっての「大衆」というのは「非人格的なモブ」であり、笠井が望む事態を実現するための「道具」でしかない。
笠井がもっともらしく煽って、それで得られた「成果」は自分のものでもあれば「自慢の種」にもなるのだろうが、それが失敗に終われば『まあ現時点での日本の限界でしょう。』でおしまい。煽った本人は、傷ついた人たちのことなど、まったく意に介さず、責任も取らないまま、あっさりと忘れてしまう。
例えば、『新大久保一帯の騒乱化』が、そこに住む人たちに何をもたらすか、彼らの思いは、などといったナイーブな問題など一顧だにしないし、興味もない。笠井にとっては「騒乱状態になれば良い」と、ただそれだけなのだ。

笠井が「新本格ミステリ」業界を去ったのは、前述のように、驕った笠井の「一人相撲」の結果「居場所がなくなった」というのが主たる要因ではあったのだけれども、しかしそれだけではなく、その頃にはすでに「新本格ミステリ」ブームにも翳りが見え始めていた、ということもある。
だからこそ、「ミステリ」に関しては、譲れぬ自負を持っている「ミステリオタクたち」に、これ以上、無理に迎合する価値は薄く、そこに固執するよりも、当時の流行の最先端であった「ラノベ」や「美少女ゲーム」といった、次世代の文化にコミットした方が、「戦略」的に得策であろうと考えた。
それで、すでに「オワコン」だと判断したミステリ界から昂然と離れて、今度は「限界小説研究会」を設立し、またも懲りずに、若い批評オタクを集めて「党派づくり」を始めた、というわけである。

だが、一度「探偵小説研究会」で失敗している以上、「また笠井が、子分づくり(のためのオルグ)をしている」という印象を与えるようなことはしにくいので、「探偵小説研究会」のとき以上に、「限界小説研究会」のメンバーたちには、原稿料のもらえる仕事という「餌」を分け与え、恩を売って懐柔するという、「ゆるいサークル」的なつながりを作るしかなかったのだろう。
しかしながら、そうなると、若いライターたちの方だって馬鹿ではないから、餌をもらってそこそこ大きくなり、独り立ちできそうになれば、笠井と一定の距離をおくようになる。笠井が期待するような「党派の駒」にはなってくれず、結果としてそこは、相互的な他者利用のための「食い逃げサークル」にしかならなかった。
そして、その代表格が、本書でも非難されている、「左翼リベラル」の人気評論家の一人となった、白井聡だ。

白井の出世作である『永続敗戦論』などは、笠井潔の「二度の敗戦」論の影響がはっきり見てとれる著作なのだが、世間の人は笠井の本など読まないから、誰もそんなことに気づかないし、気にもしない。
一方、白井は白井で、うまい具合に論壇の主流から歓迎されたものだから、評判の悪い笠井潔から距離をおくのが得策だと、対談本(『日本劣化論』ちくま新書、2014年)を1冊出して義理を果たしてからは、笠井と距離をおいたのである。

つまり、笠井潔からすれば、白井聡もまた「恩知らずの食い逃げ野郎」だということなのだ。だから、現「探偵小説研究会」のメンバーなどと同様、許しがたい存在なのである。
だが、以上のとおり、もともとは、笠井潔の方から「子分づくり」のため、つまりは、相手を「利用する」ために、餌をチラつかせて接近したのだから、そんな人間関係(他者利用)においては、相手の方も、笠井を「利用するだけ利用してやろう」と考えても、それは「お互い様」でしかないだろう。
事実、笠井自身、自覚もないまま、自分のことを棚に上げて、こんなことを言っている。
『あの人(※ いいだもも)はそもそも戦中派の世代だし、60年代半ばに共産党を除名されて、だいぶ遅れて新左翼運動に紛れ込んできた人だからね。景気の良さそうな若い世代の運動に乗っかってみたけど、やっぱりダメだったと判断して新左翼を使い捨てたわけだ。』(P187)
もちろんこれは、こう言い換えることができる。
「あの人(※ 笠井潔)はそもそも全共闘世代だし、運動に挫折して国外逃亡してから、だいぶ遅れて新本格ミステリに紛れ込んできた人だからね。景気の良さそうな若い世代のムーブメントに乗っかってみたけど、やっぱりダメだったと判断して新本格を使い捨たわけだ。」
実際、笠井潔の「他者利用」があるからこそ、絓秀実は、今では笠井も表立って批判している白井聡と笠井の関係について、次のようにつぶやいている。
『 しかし……笠井が主催してる研究会(※ 限界研)には白井聡も参加してたわけでしょ。ああいう〝レーニン主義者〟をまさか笠井が評価するとは思わなかった。』(P242)
無論、これに対して笠井は、白井を全面的に評価していたわけではなく、批判もしていたと言い訳をしているが、要は、使えそうな若いやつなら、少々考え方や立場が違っても受け入れたということだ。
しかもそれは、笠井潔には似合わない「寛容(懐の広さ)」などというではなく、誰であろうと、最終的には「言いくるめて取り込める(洗脳できる)」という、イデオローグとしての強固な自負によるものでしかなくて、これまでの「失敗」の数々について、毛ほどの反省も知らない「自信過剰」があったからに他ならない(その意味では、マルチ商法の有能セールスマン、あるいは特殊詐欺の落とし屋的な才能の持ち主だとも言えるだろう)。
また、「笠井潔葬送派」を名乗る私ですら、この対談で初めて知ったのだが、笠井の長年「同志」であったはずの、加藤典洋、竹田青嗣といった人たちとも、「すでに切れていた」そうだ。
『絓 ……全然関係ないけど、笠井が竹田青嗣と訣別したというのは、歳月を感じるなあ。
笠井 最初の亀裂はすでに『村上春樹をめぐる冒険』(河出書房新社、1991年/笠井・竹田・加藤典洋による鼎談)の時にあったんだよ。竹田と加藤は『ノルウェイの森』(講談社、1987年)を評価したからね。』(P167)
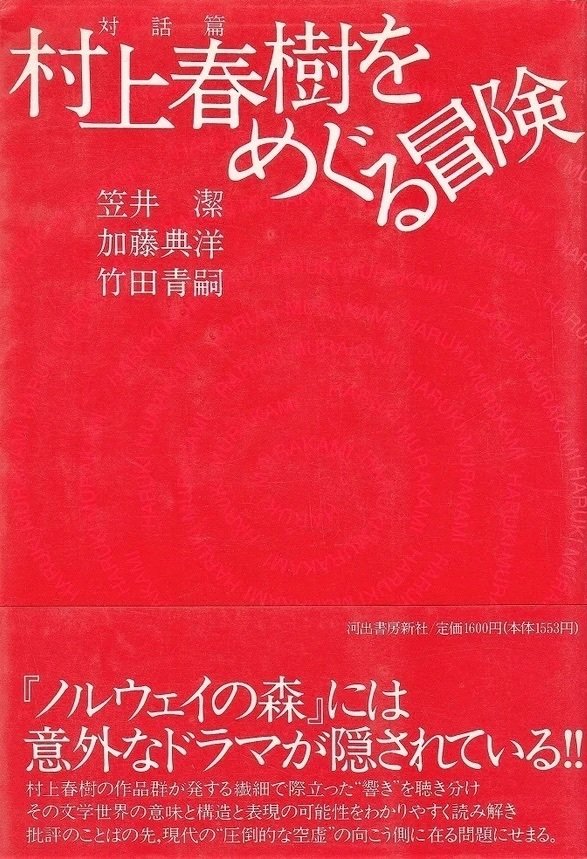
当然、笠井は「まあ、いずれそうなることは、ずいぶん前からわかっていたよ」と言わんばかりの、余裕ぶった口ぶりで、彼らが「新左翼の志しを忘れて、高度消費社会に日和った」から、そうなるべくして「縁を切る」ことになっただけだ、というような言い方をするのだが、普通に考えれば、笠井潔の方が「誰からも」見限られ、距離をおかれた結果でしかない。
今の笠井を相手にしてくれるのは、左翼論壇主流派から外れて「過去の人」になった絓秀実とか、笠井潔や絓秀実あたりであっても、ひとまず「ついていって損はない」ほど無名な、本書の企画者である、若い外山恒一くらいなのである(かつての笠井や絓が、柄谷行人にすり寄ったのと、似たようなことだろう)。
笠井潔は、左翼の「転向問題」に触れて、そこには「日本的な特異性がある」と、次のように指摘している。
『笠井 たしかに〝転向〟はどこの国にもあるよ。ヨーロッパにもコミュニストがリベラリストになったり、ファシストになった例だって珍しくない。しかし〝転向論〟は日本にしかない。
絓 しかしヨーロッパでも〝コラボ〟(第二次大戦下での対ナチス協力者)の問題をめぐって……。
笠井 ヨーロッパ人ならば、コミュニズムが正しいのかファシズムが正しいのか、というのが重要な問題なのであって、〝立場を変えた〟こと自体は思想的主題にはなりませんよ。仮にファシズムが正しいんなら、むしろ立場を変える〝べき〟であって、逆にコミュニズムの方が正しいのであれば、立場を変える〝べき〟ではなかったということになる。それだけのことです。〝転向〟自体が問題だという思考は、ヨーロッパ人にはありません。例えばポール・ニザンが、独ソ不可侵条約に激怒して共産党を脱党をしたことについて、〝裏切り者め!〟という話になることがあるとしても、〝なぜ彼は転向しえたのか?〟みたいな〝転向論〟の議論は起きない。〝なぜ〟って、〝独ソ不可侵条約に激怒したから〟でしょう(笑)。
どんなわけで、日本にだけ〝転向論〟が生まれたのか? あの時代、思想転向そのものが日本に固有の現象だったからですね。ポール・ニザンの脱党は、権力の強制による思考転換という意味での転向ではない。』(P128〜129)
「正しい」と思うものが変わったなら、その判断にしたがって政治的立場を変える「転向」は、何も悪くない。「正しい」と考えるようになった方に変わるのは、当然だ。
ところが、拷問されようが、人質を取られようが「とにかく、立場を変えちゃならん」みたいな(連合赤軍の「山岳ベース事件」的な)意識を前提とした日本の「転向論」は、日本固有の情念のようなものを前提とした議論だと、そういうことだろう。
たしかにそうした側面はあろう。一一だが、いずれにしろ、変わるのなら変わるなりに、少なくとも「変わる前の自分」は何らかの間違いを犯していたのだから、同じ誤りを繰り返さないためにも、それまでの自分を真摯に反省しなければならないはずなのだが、元は「右翼少年」であり、そこから「新左翼活動家」に転じ、さらにはそこから外れて「評論家兼小説家」になった笠井潔は、金輪際、自分の「過去」については、「反省」なんて殊勝なことはしない。
また、当然のこととしての「今の自分を疑う(今の自分だって、間違っている可能性はあると疑ってみる)」ということもしない。だから、平気で他人を巻き込むし、利用することもできるのだ。
笠井潔は、二言目には「親世代が日和って、本土決戦をしなかった(から、我々の世代はこうなった)」と責めるけれど、それだって、一部権力者は別にして、多くの場合は、悲惨な負け戦を目の当たりにして「軍部政府の踊らされていた、自分はバカだった」と、不十分ながらも、それなりに「反省」した上での「転向」だったのだから、その「転向」自体を責めるわけにはいかない。
問題は、その反省が不徹底だったことなのだが、それは笠井潔の「転向」だって同じことではないのか。

結局のところ、笠井と絓がやっているのは、自己正当化ための「過去の美化」でしかなく、そこには反省がまったくない。自分に不都合なことは、口に緘して話さないし、都合よく忘れてもいるのだろう。
例えば、笠井潔はいまだに、全的な破壊願望(「黙示録的情熱と死」の賛美)めいたことを自慢げに話すけれども、自分の妻子のことは、まったく話さない。
すでに後期高齢者である、笠井潔夫妻に「武器を取って、路上に出ろ」とまでは言わない。だが、「ゲーム会社」にお勤めだとかの(限界研にも関わった)息子さんは、リアル「路上」に出ているのだろうか。あるいは、見物くらいはしたのだろうか?

こうしたあたりに、思想として語っていることと現実の生活とに、看過しがた「ギャップ」があるはずなのだが、そこは意識的に隠して、格好をつけるばかりの「他者利用の扇動屋」。それが、笠井潔なのだ。
さすがは、かつて「理屈などなんとでもつく」と豪語したペテン師だけのことはある、と言っても、決して過言ではないはずだ。
笠井から、「そうではない」という具体的な説明をしてもらえるのならば、今更ながらではあろうと、是非とも拝聴したいものだ。
私の認識が誤っていることが明らかになれば、私は認識を改める〝べき〟なのだから、是非そうさせていただくつもりである。
(2023年1月25日)
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
