
竹本健治の〈笠井潔擁護〉
(※ 再録時註:以下にご紹介するのは、私が、2005年8月26日から28日の間、二泊三日で上京し、当時、竹本健治氏が仕事場として使用していた南雲堂の別室スタジオにお邪魔した際に交わした雑談を、土産話として「アレクセイの花園」に書いた報告記である。一一当時の私は、新本格ミステリの理論的支柱の座にあった笠井潔への批判を強め、笠井の文壇政治に協力するかたちになっていた、その周囲の人たちについても、容赦なく批判を加えていた。当時、竹本氏は、笠井潔からの批判の的になりこそすれ、こうした状況から一歩引いた立場にいたので、親しくしてくれていた私に対し「やりすぎではないか」という趣旨の助言を与えてくれたのである。だが、私は、別に人に評価されようとしてやっていたわけではないし、笠井潔批判者は私ただ一人の状態であったから、遠慮する必要などないと、確信犯的に徹底批判を行っていたので、竹本氏の助言には感謝しつつも、それに従うつもりは、まったくなかった。ちなみに、当時の竹本氏は「どんな党派にも属さない」と言って良い人であったが、現在では「変格ミステリ作家クラブ」の世話役をやっているので、このグループに関しては、公正中立だとは言えないだろう)
スタジオで、竹本健治さんと二人で雑談していた時に、どういう話の流れであったか、竹本さんが、ふと「笠井さんが政治力を行使して周囲の人に権力をふるっている、というようなことは、実際のところ、無いんじゃないかな」というような、私の「笠井潔批判」に対する、疑義を呈された。
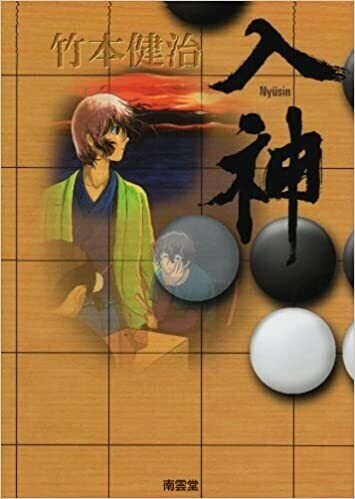
私は、竹本さんの言いたいことは、おおむね理解できると思った。
要は、私の「笠井潔批判」だけを読めば、いかにも笠井さんが「権威主義的な恐怖政治」や「義理人情の文壇政治」を行っているような印象を受けるけれども、じっさいのところ、笠井さんはそうした「押しつけめいた発言」をするわけではないし、周囲の人間も「自己の自由意志」に従って行動しているんだから、私の批判は、事実に反した、憶見にもとづく「レッテル貼り」に近いところがあるんじゃないか、というようなことが言いたかったのではないかと推察した。
だが、私としては、それは物事を表面的に捉えただけの意見であって、人間の「俗物性」というようなものに対する認識が十分ではない、と感ぜられた。
だから、私は「たしかにそうかも知れませんが、明確な押しつけや強制が無くても、人はおかれた環境の中で、何となく無難な選択をするもので、そうした状況が笠井さんによって意図的に作られた部分があるのですから、笠井潔が政治性を行使しているという判断は正しいと思います」というようなことを、もっと下手な言葉で説明した。
そのあと、竹本さんは「前に巽(昌章)さんについても(笠井潔の文壇政治に加担するものだとして)批判してたけれど、巽さんは以前に、ある賞の授賞式でのスピーチで、笠井さんの発言が周囲の畏縮を招くものとして好ましくない、という趣旨の批判発言をして、その場を凍りつかせたことがあるよ」と言って、巽さんまで批判するのは「現実に即さない行き過ぎ」ではないか、というニュアンスのことをおっしゃった。
しかし私は「それは巽さんが、当たり前のことを当たり前に言ったというだけのことじゃないですか。逆に言えば、それまでは、誰もそれを言わなかった。あるいは言えなかったということです。それが、笠井さんの好ましからざる政治的影響力の証だとも言えるんじゃないですか?」と反問しました。
つまり、私が問題としている「政治力の行使」とは、「命令」や「強制」といった、わかりやすい形式のものだけを指して言っているわけないのである。むしろ、そういう形を取らないことによって、陰微に働きかけてくる「政治性」を言っているのだ。
例えば、笠井潔が実質的リーダーをつとめる「探偵小説研究会」には、形式的(実際)には「リーダーは存在いたしない」ということになっている。
しかし、会の成り立ちと、メンバーの年齢や経験・実績などを考慮すれば、笠井潔が『実質的リーダー』だというのは、誰もが認めざるを得ないところであり、すなわちこれは、笠井潔がそこである「明示的に強制」しなくても、その「欲するところ」どおりになってしまうようなことが多々あるのだ、ということなのである。
つまり、ある「枠」や「環境」を作って、そこへ人を加入させれば、建前的には「自由・平等」であるということになっていたとしても、そこには自ずと「力関係による、暗黙の政治力」が働くようになる、ということだ。
もちろん「そんなことは、どこにでもあることだし、好むと好まざるとにかかわらず発生するものなのだから、それを根拠に批判するのはどうか」という意見もあろう。
しかし、そうした意見は、そうした状況が「やむを得ず」発生したような場合(そして、その歪みへの是正が不断になされている場合)についてのみ言うべきことであり、始めからそうなるのを承知の上で、そういう形式を選んだのだとしたら、それは故意に、そういう形式による「政治性の行使」を選択した、と考えるべきなのだ。
しかし、こうした陰微な「関係の政治性」というものは、そういう「組織」「集団」「枠」に属している当事者自身には、なかなか気づかれにくいものなのであろう。
だからこそ、「本格ミステリ作家クラブ」に所属している竹本健治が、「本格ミステリ大賞」の恣意性に気づきにくいというのは当たり前だし、「探偵小説研究会」所属の評論家が、自身の公正中立性(自由意志)を信じていたり、創価学会員が、その自由意志において公明党支援を行っていると信じている等といったことも、彼らの「主観」に立てば「当たり前の事実」なのだとは言えるだろう。
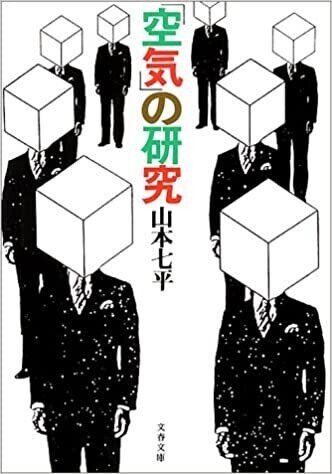
このように、「特殊集団」に属している人たちは、往々、自分の居場所の「空気」を、無色透明なものだと思い込みがちなのだが、それは「外」の者からすれば、まったくの無認識にしか見えない。
例えば、「笠井潔を批判した巽昌章」をして、竹本健治から見れば「だから巽さんには中立客観性がある」ということになるのだが、外部の私にすれば、それは「例外的になされた、当たり前の行動」でしかない。
つまり、それがことさらに目立つのは、それだけその世界が、ある種の色(政治的偏向)に染まっている証拠でしかなく、巽昌章もまた、日頃はそこに馴染んでいる、ということになるのである。
だが、こんな当たり前の事実が、その世界の住人には見えないのだ。
また、ここで『見えない』と言うと、そうした当事者からは「いいや、自覚はあるよ(=見えてるよ)。それを承知で、適切な距離を取りつつ、私はその世界に属しているのであり、君のように、あらかじめその世界を拒絶しているわけではないんだ」というような意見も出てこよう。
しかし、こうした「気づいている私は、客観・中立的な立場にある」という「誤解」については、次のような、意見を参照していただくのが有効かと思う。
azamikoさんのブログ『きびをむく少女の指先傷つきてラムの琥珀酒カリブの海より来たる』の、昨日の日記「カウントを鳴らすのは。」(2005-08-28)に、『猿虎日記』というブログから、猿虎氏の次のような文章が引用紹介されていた(したがって、これは孫引きである)。
『ところで、pikarrrさんの文章で一番面白かったのは「いじめられた小泉が、僕たち国民に泣きついてきたのです。そこに僕たちは哀れみを感じ、いとおしく感じているのです」というところです。実際は、いうまでもなく、小泉こそ、いじめてる張本人なわけですが(例えば在職中に約14万人も自殺とか、7年連続国民所得減少とか、国民生活4年連続悪化とか)、誰もそう思っていない。それは、テレビが、「小泉がいじめているところ」をまったく映さないからです。いやそもそも、テレビに映っていないものは、存在しないのです。「存在するとはテレビに映っているということだ」とかのバークリー僧正も言っています。それどころか、テレビは、まるで「小泉がいじめられている」かのような逆の「絵」(構図)を巧妙に作り出す。すばらしい「演出」です。
しかも、「小泉にいじめられている」のは、実は私たち自身なのですが、私たちはそれに気づかない(あるいは気づかないフリをしている)。私たちは、安全なお茶の間で小泉がフォールされているところを面白がって「観戦」しているつもりなのですが、実は、私たちがいるのはリングの上で、私たちの見えないところ(つまりテレビが映さないところ)では、血しぶきをあげて苦しんでいる人々がいる。気づいた時には、私たちはマットの上で完全にフォールされていて、カウントの声が聞こえるのですが、その時はもう遅いのです。テレ・ビジョンとは、遠隔的にモノを見せる機械ではなく、私たちを見ることから引き離す機械なのです。
というわけで、私たちは「これって演出でしょ? 分かってるよ」と思うことで、小泉やマスコミに対して優位に立っているつもりになっているのですが、実際は違うのであって、私たちは、小泉の強権政治が「演出ではない」ということが「分かっていない」のです。「騙されないよ」と思うこと自体が「騙されている」ことなのです。「わかって騙されているんだ」とさらにメタレベルに立とうとするのかもしれませんが、実はそんなメタレベルなどないのです。端的に騙されているだけなのです。その無力さを認めたくないから「わざと騙されている」と強弁するのです(「それもわかっている」と言い出す人もいるでしょうが、言うまでもなくそれは無限後退に陥ります)。』
(2005-08-28「猿虎M字開脚!」より)
この文章の『小泉』を「笠井潔」、お茶の間の観客を「ミステリ業界の人々」に差し替えれば、私の意見がおおむねご理解いただけよう。
「探偵小説研究会」に所属する評論家はもちろん、「本格ミステリ作家クラブ」に所属する人たちの自己認識は、そこにどっぷり所属しながらも、『「騙されないよ」』というものであり、さらには『「わかって騙されているんだ」とさらにメタレベルに立とうとする』意識の在り方だと言えよう。しかし、それは猿虎氏が指摘しているとおり『実はそんなメタレベルなどない』のである。
外部から見れば、その政治性が露骨で、いかにもうさん臭い「動き」であったとしても、その内部に所属しておれば、その動きは「必然性のあるもの=避け得ざる流れ」と認識されがちだ。だがそれは、戦前の日本やドイツにおける動き(天皇の神格化・ユダヤ人絶滅政策)においても、今ここの日本のミステリ業界においても、まったく同じことなのである。
例えば、たまに新人作家の著作に推薦文を寄せる竹本健治は、推薦文というのは「手放しに誉める」のが当たり前で、誉められないものは推薦しなければ良い、という「常識」を持っていることだろう。
これはこれで間違いではないが、しかし、その昔、新人のデビュー作に付されたベテラン作家の推薦文は、必ずしも「絶賛」ではなく、「……という弱さもあるが、捨てがたい清新さもあるので、○○くんの今後に期待したい」みたいな「批評文的な推薦文」も当たり前にあったのである。
つまり、今、客観的に考えて「当たり前」だと思えることが、当たり前でなかった過去が現にあったり、将来当たり前でなくなる可能性も充分にあって、当然、いま現在においても、内部の人間には認知しえない「非・当たり前」なことも、当たり前に存在するのである(お役所仕事など)。
竹本健治という人は、善かれ悪しかれ「極端には走らない」「政治的にならない」人であり、その意味で「バランスの取れた常識人」として信頼されている。どんな「党派」にも属さず、マイペースの自分らしさに生きているからこそ、竹本健治は多くの人たちから信頼され、その反面、そのノンシャランぶりが、党派人間である笠井潔を苛立たせてきたのでもあろう。
しかし、そうした「自然体」だけで、自身が属している「世界」に対して、適切な距離が取り得ているとはかぎらない。自身を取り巻く「空気の色」は、やはり、そこから出ないかぎり、見えないものなのだ。
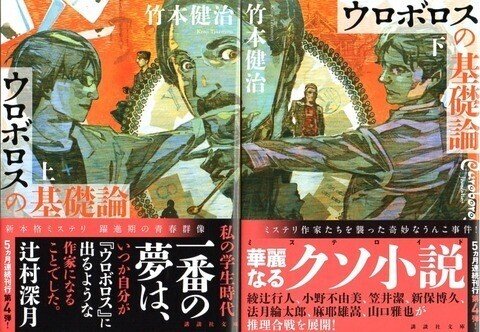
そしてこの問題は、私も登場させてもらった竹本健治の『ウロボロスの基礎論』の中で言及されていた、柄谷行人の「形式化の(徹底の)問題」、ゲーデルの「決定不可能性」の問題ともつながってくるのではないだろうか。
もちろん、その意味では、私も「特権的な外部」に立っているわけではないだろう。だが、むしろ私の場合は、自己の内部性を前提にしているからこそ、しばしば「過剰に批判・否定的」なのだ、とも言えよう。それは私が、自身の内在する「日本」について批判的であるという事実にも、端的に表れていよう。
一一というわけで、私の批評の基本的な問題意識のかたちとは「他所さまのことを言うのは簡単だけど、おまえの周囲はどうなんだ?」というものである。
また、そういう私だからこそ、自身の周囲にも呵責がないのだ。
さて、あなたの周囲は、批判せずとも良い「例外状況」になっているだろうか?
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
