
豊崎由美の〈正直さ〉を 断然支持する。 : 飯田一史の 「俗情との結託」をメッタ斬り!
「書評家が本紹介TikTokerけんごをくさし、けんごが活動休止を決めた件は出版業界にとって大損害」
(飯田一史・12/11(土) 8:37「YAHOO!ニュース」)
(https://news.yahoo.co.jp/byline/iidaichishi/20211211-00272115)
書評家の豊崎由美が、Twitterで次のように書いたことから、その低評価の対象となった、読書系TikTokerの「けんご」が活動の中止を決めた。
そして、このことについて、批評系のライターである飯田一史が、「TikTokerけんごが活動休止を決めた件は出版業界にとって大損害」であるとの趣旨で、豊崎を批判した。

『正直な気持ちを書きます。わたしはTikTokみたいなもんで本を紹介して、そんな杜撰な紹介で本が売れたからって、だからどうしたとしか思いませんね。そんなのは一時の嵐。一時の嵐に翻弄されるのは馬鹿馬鹿しくないですか?
あの人、書評書けるんですか?』

このツイートの問題点は『書評書けるんですか?』という最後の一言である。
多くの人が指摘しているように、「書評が書けなくても、本の推薦をする」のは、「勝手」であり「自由」である。要は「犬でも猿でも、三流書評家でも」人語を操ることさえできれば、勝手に推薦をすれば良いし、その権利と自由はある。
また、人間に限定して言えば、ろくに本を読んでいないだけではなく、読んでもろくに理解できていない、からっきし読解力のない人間でも、現に「図書推薦」を平気でやっている。なぜなら、それがいかに中身のない「オススメ」であったとしても、「オススメ」する「自由」や「権利」はあるからだ。それだけの話なのである。
したがって、豊崎が先のツイートで言いたかったのは、言うまでもなく「読解力のある者だけに、本のオススメをする資格と権利がある」ということではない。
これくらいのことも読み取れない「無能力者」の多くが、豊崎の『書評書けるんですか?』という「勇み足」の一言に、腹を立てているだけなのだ。
要は、その人も「まともな書評」など書く力などないと半ば自覚しているからで、豊崎の一言に、自身の「劣等感」を刺激されただけ。
つまり豊崎は「能力もない人間が、タレント的な人気だけで、その影響力を行使して、本の売り上げに貢献したとしても、そもそも、その選書能力に限界があるのだし、また、そんなもんに簡単に影響されるほうの多くも、創価学会員が喜んで池田先生の『人間革命』(あるいは、幸福の科学会員が、大川総裁の著作)を買って絶賛するのと同様、わけもわからずに買っては喜んでいるだけなのだから、そんな中身のない売れ行きなんか、文芸出版の世界においては、一過性のカンフル剤に過ぎないよ」と、大筋そう言いたいだけなのだ。
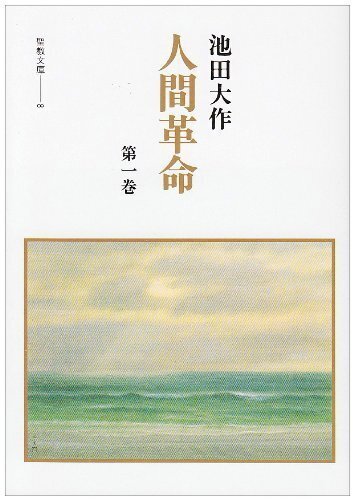

たしかに、「人気タレント」の類いが本を薦めれば、「教祖」が本を薦めるのと同様、日頃はろくに本を読まないその「信者」は、そうした推薦図書を買うだろうし、推薦者の「権威」に目の眩んだ信者たちは、その本の有価値性を「盲信」するだろう。だが、そんな「売れ方」を喜ぶのは、極めて「非文学的」なのである(小林秀雄が、プロレタリア文学ブームに皮肉ったのと、似たような話だ)。

今回の場合だって、「TikTokerけんご」個人の「(流行的)人気」だけではなく、その前に「TikTok」という「新しいメディア」に対する若者の「人気(流行)」において、その推薦書が売れたのであって、「紹介された本の中身」で売れたわけではないだろう。
その昔、ミステリマニアの間で「この味が/いいねと乱歩が/言ったから/サキ、ダールまで/ミステリの内」という狂歌があった。要は、「権威」者が語った評価について、主体的判断能力のない「信者」たちが、それを誤って「盲信」しただけであり、そうした「裏付けのない評価(盲信)」は、いずれ淘汰されて修正される、ということである。
(ちなみに、私が上に書いたことについて、「乱歩の評価が間違っていた」と理解したような、読解力のない読者が少なくなかったはずだ。だが、ここで私が紹介したのは「乱歩の作品評価を、勝手にジャンル分けだと誤解した、読解力のない、権威追従型の読者が大勢いた」という話である)

つまり、今の「出版業界」では、「おべんちゃら」でも「提灯書評」でも「嘘」でも、とにかく「本が売れれば良い」「本が売れなければ、批評もクソもない」というのが「本音」だから、「おべんちゃら」や「提灯書評」や、ほとんど意識的な「嘘」を本音に見せかけて書くような、三流以下の「書評家」や「ライター」(あるいは、三流の「書店員」)の方が、出版業界においては、むしろありがたく重用され、その一方で、豊崎由美のような、「本音」を正直に書くがゆえに「酷評」も辞さない書評家なんかは、逆に、使い勝手が悪いと、冷や飯を食わされることにもなるわけだ。
そして、今回の「飯田一史による、豊崎由美批判」もまた、そうした「出版業界」における「売れてナンボ」という文脈上のことであったればこそ、さも「正論」ででもあるかのごとく語られ得たのである。
これは例えば、かつては「文芸書出版の雄」であった新潮社が、文芸書が売れなくなり「貧すれば鈍」した結果、時流に迎合して「ネトウヨに売れる本」の出版に力を入れ始めたのと、同様の傾向である。
そしてその挙句、「LGBTには生産性がない」などとする「ネトウヨ政治家」の差別論文を載せた結果、数少ないノンフィクション専門誌であった『新潮45』を廃刊しなければならないという憂き目を見ることにもなった。

しかし、それで新潮社が反省したのかといえば、そんなことはまったくない。
現に「新潮新書」では、いまだに「ネトウヨ」評論家(例えば、日大理事長だった田中英寿容疑者子飼いの太鼓持ち教授である、先崎彰容)の本なんかを喜んで出しているという現実があるからで、どうして廃刊騒ぎまで経験しながら反省できないのかと言えば、結局は「読解力の必要な本が売れない」という現実に、何の変わりもないからである。


つまり、豊崎由美が件のツイートで言いたかったのは、視野狭窄で読解力のない読者が理解したような「まともな書評も書けない者が、図書推薦などするな」ということではなく、「中身にかかわりなく、売れたもん勝ちみたいな現状では、いずれにしろ文学は滅びるしかない」ということなのである。
もちろん「文学」が消えてなくなろうと、駄菓子のような本ばかりになろうと、ひとまず「商品」として売れてくれれば、出版界は「商売」として延命できると、そう考えるような出版社や編集者や作家や書評家たちは、本音として、それでかまわないのであろう。
特に、もともと「読解力」もなければ「中身のある文章も書けない」ような三流の作家や書評家にとっては、自分たちの能力が厳しく問われることがなく、ただ世間と出版社に媚びた仕事さえしていれば、なんとか食いつなぐことのできるような出版業界である方が、むしろ好都合なのかもしれない。
しかし、そんなことをしていたら、すでにしてそうだが、「文学」は「水の低きに流れる」がごとく、どんどん「バカでも読める駄菓子本」ばかりになってしまい、志のある作家や評論家の文章は、「ポピュリズム出版界」から、ますます排除されていくだろう。
そもそも「流行りのTikTokerによる、中身のない図書推薦でも、売れたらそれで万々歳」みたいな現状に対して「そんなもんに、なんの価値がある」と毒づく「文学性」が、「売らんかなの商業主義」によって排除されるのなら、日本の文芸書出版界においては、もはや「こき下ろす自由」すらない、と言えるだろう(文学を知らない者は、文学に「毒舌罵倒」の伝統があることも知るまい)。
言うまでもなくこれは、「批評」性の抹殺であり、本物の批評家や書評家の排除に他ならない。そして、そうとなれば、日本の文芸出版界は、さらにゾンビ化するしかないだろう(読解力のない人のために解説しておくと、これは「すでに死んでいるが、動いてはいる」という、皮肉を込めた比喩である)。
○ ○ ○
「TikTokerけんご」にも言っておきたい。
「趣味」でやっておろう(と、カネをもらっていなかろう)と、公に発言をすれば、その発言については、相応の責任を負わなければならず、当然のことながら、批判されることもある、ということくらいは、あらかじめ知っておけ、ということだ。
この程度のことも知らない「お子様」のオススメする本など、所詮は、同レベル以下の視聴者に向けた「駄菓子本推薦」にならざるを得ないのは、理の当然である。


また、仮に、中身のある本を紹介していたとしても、紹介者自身が、その本の中身を十分に理解しないまま「ただ褒めているだけ」でしかない、ということにもなる。
では、本当に中身を理解して褒めているのか、それとも宗教信者のように「訳も分からず感動して褒めているだけ」なのかを区別するには、どうすれば良いのか。
それは、その肯定なり否定なりの「根拠を、論理的に述べる」努力しかない。
つまり、豊崎由美が『書評書けるんですか?』と言ったのは、単に形式上の「書評」(みたいなもの)が書けるのか否か、ということではなく、自分の読解の「根拠を、他者にきちんと説明できるのか」という意味である。
ただ単に「これは素晴らしい」とか「感動した」とか「今年の一番」とか「こんなの初めて読んだ」とかいった、どうでもいい「個人的な印象」ではなく、一つの見解として、「趣味」を同じくしない人をも相応に納得させるだけの中身のある意見を、責任を持って提示できるのか、という意味である。
私は「TikTokerけんご」の「図書推薦動画」を見たことがないから、彼の動画に、そうした「内容」があるのかどうかは知らないが、「TikTok」というのは、現在でも最長3分だというのだから、まともな「論理的説明」などできないのは、明らかであろう。
昔の文学者や批評家などが、呻吟しながら言葉を尽くして語ったことを、その程度の長さの「動画」で語り切れるなどと考えるような人間は、そもそも、まともに本を読んでいない手合いなのだ。
ともあれ、「発言者としての(他者と切り結ぶ)覚悟」が無いのなら、さっさと辞めるのが正解なのである。
○ ○ ○
最後に、前記ネット記事の筆者である「飯田一史」について、ひとこと書いておこう。
そもそも飯田は、まともな「文筆家」なのか。それとも「売らんかな」の業界的需要に媚びることで、「売文芸者」をやっているだけの、いなくても一向に差し支えのない、いない方が良いかもしれない「三流ライター」なのか。
私としては、何度も書いていることなので、同じことを繰り返すのも面倒だから、下の「限界研」関連の記事を参照してもらいたい、とだけ書いておこう。
飯田一史もまた、「笠井潔葬送派」である私が批判した、「笠井潔の子分」たる、藤田直哉や杉田俊介などと同様の、「限界研」関係者である。
そして飯田が、その中での「例外的存在」だとは、到底思えなかったのが、今回の記事だったのだ。

ともあれ、「文学」の世界に関わっていれば、意見の対立による、論争や喧嘩くらいは、あって当たり前。
文筆の世界は、「仲良し幼稚園」であるより「文筆の修羅場」であった方が、よほど健全なのである。
(2021年12月13日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
