
最相葉月 『星新一 一〇〇一話をつくった人』 : 天皇 ・ 星新一ですら 〈ただの人〉であった。
書評:最相葉月『星新一 一〇〇一話をつくった人』(新潮文庫)
私にとっての星新一は、すでに超然として確たる存在であった。
初めてその存在を知ったのは、たぶん中学生くらいの頃だったと思う。ご多聞にもれず、クラスメートの誰か、たぶん女子の誰かが、星新一の新潮文庫を学校に持ってきて、回し読みしていたのではないかと思う。
しかし、当時の私は、まだ活字の本を読んだことがなかったから、興味は持っても、借りて読むには至らなかったはずだ。あるいは、ショートショートなので、ひとつくらいは読んでみて、結局はピンとこなかった、といったことではなかったか。
私が星新一に再会するのは、高校生になって活字本を読み始めてからだ。
本書にも登場するミステリファンのサークル「SRの会」に昨年まで入っていた(会費を払って、会誌だけは送ってもらっていた)が、会合に参加していた二十代の頃、例会などで他の会員に聞いてみると、子供の頃から「子供向けのホームズものやルパンものを読んだ」と言う人が結構いた。そういう人に比べれば、私は10年近く遅れて、活字本を読み始めたことになる。もちろん、マンガならかなり早くから読み始めていたのだが、いつ頃からかは定かではない。
もっぱらマンガとアニメだった頃の私にとって、活字本は見るからに面白くなさそうだった。どう考えたって、絵で見てわかる方がストレートに面白いに決まっている。そう思っていたからである。
中学3年生の頃だったか、読書感想文を書けと言われて、何を読んで良いのか、さっぱりわからなかった。そこで書店に行き、聞いたことのある作品で薄いものと思って、買って帰ってきたのが、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』だった。当然、あっさりと挫折した。
活字本で最初に1冊最後まで読み通せたのは、高校の副読本として課された『古文入門』だった。小説ではなかったが、とにかく活字本を読み通せたというのは自信になった。
その次に最後まで読み通したのは、石津嵐によるノベライズ版『宇宙戦艦ヤマト』だった。ヤマトブームの真っ最中だった。それでも、小説として面白いとは思わなかった。あくまでも、アニメで知っている内容を、小説版で確認して「ここがアニメと違っているな」といった感じで読んだだけだった。
私が、最初に小説の面白さを知ったのは、国語の授業で課された夏目漱石の『こころ』だった。教科書には、三部構成の「中」篇しか掲載されていなかったので、先生が文庫本を買って読めと指示したのである。
『こころ』は、初めて没頭するようにして読んだ活字本である。作品世界に入りきったのだ。
で、何がすごいといって、人間心理の機微の描写が、マンガでは描けないものであり、これが活字の強みだと思った。それから、日本の純文学の有名どころをそこそこ読み、自分に合う作家もいれば合わない作家もいることがわかった。漱石や実篤などの後、自分の好みに合った面白い純文学作家になかなか出会えないうちに、どういう経緯からか、筒井康隆編の『’60年代日本SFベスト集成』(徳間ノベルス)を読んでハマり、同シリーズ『’71年』『’72年』と読んで、すっかりSFに惹かれ、それからは個々の作家の長編を読むようになっていった。
ちなみに、『’60年代』で印象に残っている作品は、豊田有恒の「渡り廊下」、山野浩一の「X電車で行こう」、手塚治虫の「そこに指が」。『’71年』では、梶尾真治「美亜に贈る真珠」、永井豪「ススムちゃん大ショック」、荒巻義雄「ある晴れた日のウィーンは森の中にたたずむ」。『’72年』は、星新一「門のある家」、山野浩一「メシメリ街道」といったところ。要は、叙情性、郷愁、日常から異空間へ、メタフィクション、といった感じで、それが終生変わらぬ私の「趣味嗜好」だったようだ。

このあと、星新一をそれなりに読んでいる。『できそこない博物館』『ボッコちゃん』『ようこそ地球さん』『気まぐれ指数』『ほら男爵、現代の冒険』『ボンボンと悪夢』『悪魔のいる天国』『妄想銀行』『おのぞみの結末』『マイ国家』『エヌ氏の遊園地』『殿様の日』『ノックの音が』、そして『ショートショートの広場』も。

これらは、昭和56年から昭和61年(1981〜1986年)頃に読まれているが、当時の読書ノートによると、必ずしも高い評価を与えていたわけではなく、たぶん「星新一くらい、ひととおり読みたい」と思って、好みのタイトルから手に取っていたように思う。ちなみに、以上の星の著作の中で一番評価が高かったのは、意外にも『気まぐれ指数』でかなり面白かったようだが、内容はすっかり忘れている。
また、星の選んだ作品が収録された『ショートショートの広場』では、60篇弱の収録作の中で、気に入った作品として「最高の喜び」「花火」「不条理な夜にしどけなき猫」「帰郷」「よけいなものが」の5篇に下線を引いている。よくぞ、江坂遊の「花火」を選んだものだと、今なら思う。
しかし、ここまで読んで、以降、私は星新一をまったく読んでいない。昭和60年(1986年)の末に、中井英夫の『虚無への供物』を読んでいるから、そのあたりから徐々にミステリの方へシフトしていたせいではないかと思う。そして、昭和64年(平成元年・1989年)頃からの「新本格ミステリ」ブームによって、ミステリを集中的に読もうと決めたのだった。また、その頃に前記「SRの会」にも入会した。
○ ○ ○
そんなわけで、今頃になって、星新一の評伝、ノンフィクション作家・最相葉月による『星新一 一〇〇一話をつくった人』を読もうと思ったのは、10年ほど前にミステリから遠ざかり、専門的にミステリを読んでいた頃には読めなかった、いわば「積み残し」の純文学の作家を読み始め、さらに買ってはいたが読めなかった日本SFの新しいところも読み始めたからである。そして、特に直接的な動機は、昨年(2021年)10月に、浅羽通明の『星新一の思想 予見・冷笑・賢慮のひと』が刊行されたからだ。

定年を意識し始めたせいで、これまで読み残してきた本を読むようになった私にとって、この本は、星新一を「片付ける」のにちょうど良い、「まとめ」本のように感じられた。しかし、長らく星作品を読んでいないし、作品を読み返すと切りがない。そこで思い出したのが、2007年に刊行されて、とても評判の良かった、星新一の評伝『星新一 一〇〇一話をつくった人』だった。

私は、当時この本を贖っていたが、結局は積読の山に埋もれさせてしまった。だから、今回、この本を読んで、まったく知らなかった星新一の「人の部分」を知ってから、浅羽通明の作家論『星新一の思想』を読めば、これでもう、星新一は片付けたことにできるのではないかと考えて、すでに文庫落ちしていた最相葉月による評伝、つまり本書を読んだというわけである。

○ ○ ○
本書を読んで、まず感じたのは、昨今、歴史書を読んで痛感する「日本史と私は繋がっている」という感慨である。
星新一という特異なSF作家、どこか浮世離れしてポツンと宙に浮いてでもいるかのような印象のあった作家が、実は明治の元勲あたりとつながりのあった父を持ち、森鴎外の妹を祖母に持つと知ったからだ。
星新一が、今はなき「星製薬」の御曹司だったといった話なら、本書の単行本が刊行された当時に仄聞していたが、そもそも、そこで初めて「星製薬」の名を知った私には、当時「御曹司だったのか」以上の感想はなかった。

だが、その後、ネット右翼との喧嘩などを通じて、「日本の歴史(通史、近代史、戦後史)」や「右翼思想(玄洋社ほか)」などの知識の必要性を痛感し、そのあたりの本をそれなりに読むに至り、今の私には、星新一の父親である星一は、わかりやすく日本の近代史の中に位置付けられる人であり、星新一にはその息子であるという新しい位置付けが加わり、同時に私は、そんな星新一(生前)の読者だったという、「ひとつながりの歴史」を実感できたのである。
しかし、こうしたことは、他の作家や有名人にしても同じで、殊更に驚くほどのものではなかった。要は、NHKの人気番組『ファミリーヒストリー』みたいなものである。
したがって、私が、最も興味深く読んだのは、文庫版では下巻に入って、星新一がすでにひとかどの作家となり、日本のSF界が形成されていくあたりからだ。
このあたりになると、前述の『’60年代日本SFベスト集成』に収録されている作家たちが、まずはアマチュアのSFファンとして登場してくるし、私が所属していた「SRの会」の名前も登場する。私が入会した当時に会長を務めていた竹下敏幸氏は、たしか初代会長で、創立メンバーの一人のはずだから、竹下氏と同年輩の古参会員(田村氏、石田氏)たちは、本書で描かれた初期のSF大会などにも参加していたはずである。そして、そんな人たちの下で、若い私は「SRの会批判(内部批判)」などをやったりして、手を焼かせていたのだ。
そんなわけで、今となっては、日本のSF界の草創期というのも、「神話」の世界ではなく、今の私とつながる「歴史」の中で、リアルに存在したもののように感じられるようになった。
本書には、山前譲、新保博久、あるいは中井英夫、宇山秀雄(宇山日出臣)など、直接お会いしたことのある方々も登場してくるから、完全に私の人生とつながってくるように感じられるのだ。
それに私は、いま現在、昨年のSF界で最も注目された作家の一人である、樋口恭介(S‐Fマガジン編集部編『SFが読みたい! 2022年版』国内編第1位『異常論文』の編者)を批判したりしているのだから、SF界の草創期における「人間的」なエピソードの数々は、現在のSF界のイメージとも無縁ではない。つまり、今の人気作家たちも「所詮は人間だ」としか私には思えない、ということだ。
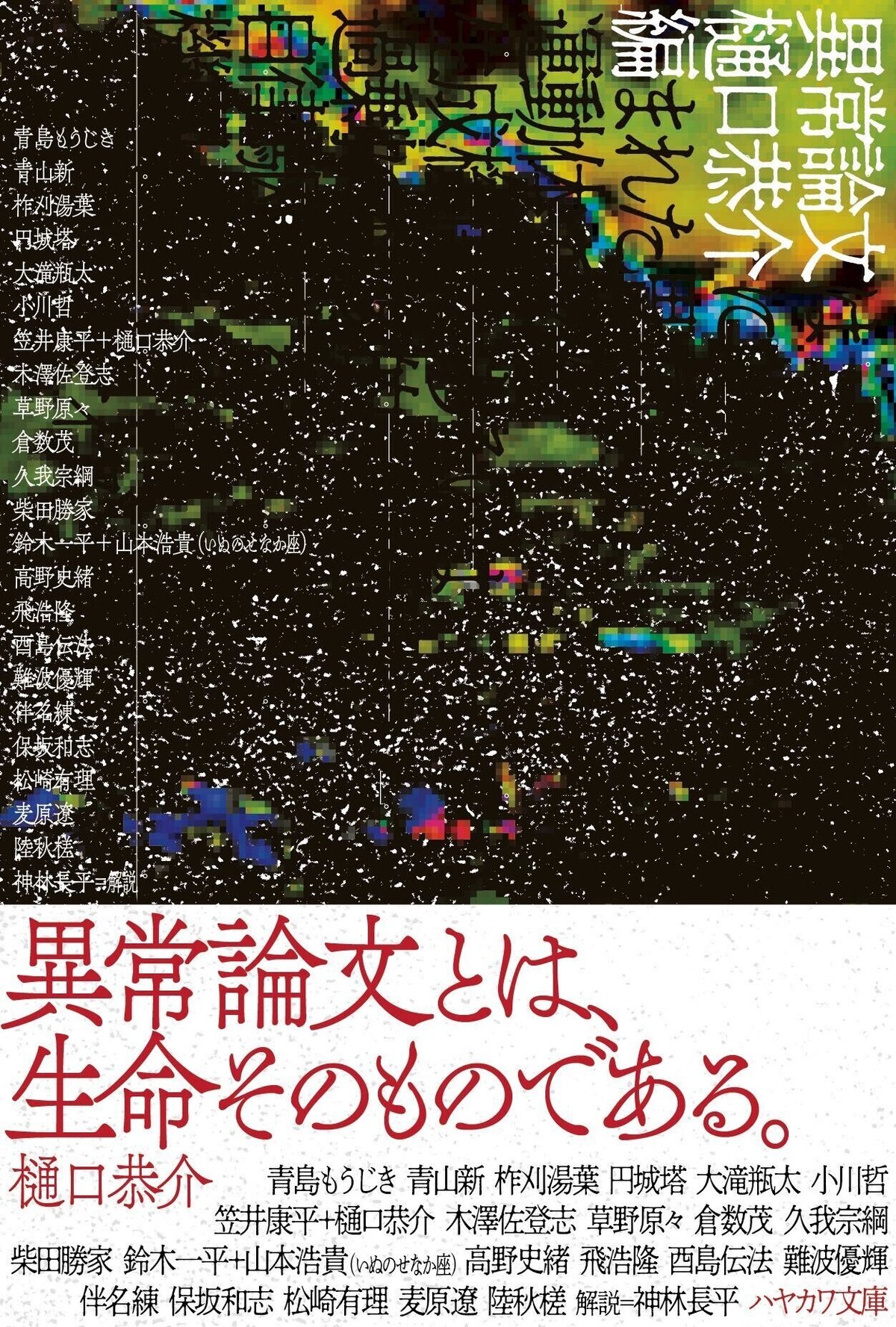
例えば、長らくミステリ畑の人間だった私が、日本のSF界に感じていた「謎」の一端が、本書を読むことで、ある程度は解けたように思う。
つまり「ミステリ界に比べると、SF界は結束が固い。それは、SF大会などのイベントの、安定的な運営などによく現れている」といったことであり「この違いは、何に由来するのか?」という疑問への回答である。どっちも、所詮は、ジャンル小説マニアなんだから、本質的な違いはないはずなのに、どうして、このような違いがあるのかというのは、もう20年来の謎だったのだ。
(1)『 昭和三十八年三月五日夜、日本SF作家クラブの発足準備会が、新宿西口にある台湾料理店「山珍居」で行われた。
参加者は呼びかけ人の福島正実ら十一名。矢野徹、石川喬司、川村哲郎(翻訳家)、齋藤守弘、斎藤伯好、半村良、星新一、森優、光瀬龍、そして大阪から小松左京が夜行列車で十三時間かけて上京していた。
旧式のオープンリール・テープ式のレコーダーで録音された会議の内容を聞いてみると、ようやく世間に認知され始めたSFをさらに発展させるために、作家や翻訳家、ジャーナリストが情報交換し、切磋琢磨する職能団体を参加者たちが必要としていたことがよくわかる。正式名称は日本SF作家クラブ。会員の推薦を得た上で、他の会員すべての賛同があって初めて入会できることとした。月一回あるいは二回の会合を定期的に開催することにした。会社が印刷所を兼ねている半村良が、事務局長に立候補して承認された。
「サンデー毎日」編集部の石川喬司はこの日、オブザーバー兼スポンサーとして参加していた。
「(前略)SFなんて子供向けの読み物だというレッテルを貼られていましたけど、そんな文壇の偏見に対抗してSFを文学運動として打ち出すべきだという福島さんの考え方には大いに賛成だった。当時、プロの作家として確立されていて自由にものがいえたのは星さんだけ。その星さんでさえ、文壇では通俗・大衆小説作家のひとりとしか見なされていなかったんですから」
発足準備会は終始、和気藹藹とした雰囲気で進行した。何かが始まるという期待に、少なからず興奮している様子もある。途中、福島が真面目な口調で強調したのが、プロとアマチュアを明確に区別する、という点だった。
福島がそんな発言をした背景には、(※ 同人誌)「宇宙塵」の柴野拓美(※ 同主催者)との関係があった。そもそもSFの世界ではアマチュアの活動がプロに先行し、「宇宙塵」の存在と影響力が大きかった。星新一をはじめ、SFコンテストの応募者の名前を見てもわかるように同人からプロの作家を次々と生み出そうとしていた。
同人誌とはいえ、会員には作家やジャーナリスト、テレビの制作者などもいて読者層は幅広く、彼らがそこに書かれる同人たちの批評を読み、意識するのも自然なことといえた。まだ学生だった血気盛んな同人たちは、われこそはと怖いもの知らず先鋭的な批評を書く。しかし、そうでなくてもともSFに対する攻撃はすべて自分への攻撃であるかのように一身に受けとめていた福島は、アマチュアの生意気な態度を無視することができなかった。SFのために人生を賭け、生活を犠牲にしているプロと、そうでないアマチュアは違う。厳然と区別されねばならないと考えていたのである。
それは「SFマガジン」創刊当初から福島を抱えていた葛藤をそのまま反映していた。アメリカでは、SFはファンダムを意識する大衆小説として発展してきたが、日本では安部公房が「SFマガジン」創刊に送った祝辞にあったように、新しい現代文学の領域を開拓することを期待された。安部のいう、「文学のなかでの、SF精神の復権」であり、「自然主義文学によって占領された仮説文学の領地を奪回」(『人間そっくり』文庫解説)するものでなければならなかった。アメリカのSFのように大衆的な娯楽作品のままでは困る、SF作家がアマチュアに迎合する通俗作家になってもらっては困るのである。
意気込む福島に対し、光瀬龍や矢野徹は賛同した。小松左京は、SFの市場を考えるとあまり限定的になるのはよくないが、SF以外は読まない、SF以外は文学ではない、とまでいう若い人たちが「宇宙塵」に現れていることを危惧すると発言した。
一方、ペーパーバックのファンで「宇宙塵」に参加するようになった森優は、福島に理解は示しつつも、いたずらに「宇宙塵」と対立を激しくすることは優秀な彼らの才能を押さえることになり、それは逆に将来のSF界にとって大きな損失になると控えめに反対意見を述べている。石川もこの点は森に同意しており、福島と森の考え方の相違は後に早川書房の編集方針、すなわちSF戦略に大きな転機をもたらす一因になる。
(※ 星)新一はといえば、どちらに同意するでもなく議論のなり行方をうかがっている様子だ。』
(文庫版下巻・P69〜73)
(2)『 福島が「宇宙塵」を目の敵にするようになったのは、そもそもここで新一が発言した三島由紀夫の『美しい星』にまつわる一件が引き金となっていた。自分たちを地球の危機を救うべくやってきた宇宙人と信じて疑わない一家を題材に核時代に生きる不安を描いた三島初のSF作品。事の発端は、当時まだ十九歳、早稲田大学の学生だった伊藤典夫が「宇宙塵」に発表した『美しい星』の書評だった。勉強熱心で次々と新たなSF評に果敢に挑んでいた伊藤が、この三島の作品を大上段からばっさりと批判したのである。同人誌の、しかも学生が書いた文章がそれほど大きな影響をもたらすとは考えられない。伊藤もまた、自分の書いたものがどんな波紋を呼ぶかなど想像もしていなかった。
ところが、「宇宙塵」の愛読者だった北杜夫がこれに目を留めて「週刊新潮」におもしろがって紹介したことから話が大きくなった。
(中略)
ただ、(※ 石原の批評を発端にして否定的な評価が広まるも、新進気鋭の評論家であった江藤淳が三島を擁護して風向きが変わり、三島も江藤に感謝したのだが、本来「宇宙塵」を高く評価していた)三島が(※ 本音では)どう思っていたかは、ここではあまり関係がない。それよりも、江藤にこうした(※ 誤った)SF観をもたらした要因は何なのかと福島は考えた。SFを愛好するアマチュアの書き手に、子供っぽさ、無知、思い上がりがあるのではないか。伊藤が三島の作品をどこまで読み込んでいたかはわからないが、攻撃的な批評を書く場合は、批評をする作家の著作や変遷をふまえた上でその文学的価値を理解して挑まなければならない。さもなくば、SFすべてが見下され、これまでこつこつと積み上げてきた福島たちの努力が水泡に帰す。
福島は、伊藤よりも、伊藤の原稿を掲載した柴野拓美の責任を問うた。江藤のような時評が発表されたら、反論を提示できるだけの力と覚悟が必要である。「宇宙塵」ほどの影響力をもつ同人誌であれば、プロではなくアマチュアのたんなるファンだからと逃げるのではなく、それなりの覚悟と高い質が求められる。だが、現状においてその力はない。来る者は拒まないファン雑誌にそこまで求めるかという考え方をの厳然としてある。ならば、彼らアマチュアの行動、彼らが引き起こした問題に対して、SFに命を賭しているプロの自分たちまでが巻き込まれるのは迷惑、と福島は考えた。
(中略)
日本SF作家クラブの設立を機にこの「宇宙塵」問題はしばらく尾を引き、福島と柴野の間のSF界での主導権争いのような状況は続いた。
昭和三十八年五月には、規約に基づき、初代会員十一名の全員の推薦で、翻訳家として独立した伊藤典夫をはじめ、大伴昌司、筒井康隆、手塚治虫、豊田有恒、野田昌宏、平井和正、眉村卓、真鍋博が入会して活動が本格的にスタートするが、柴野は、小隅黎の筆名で翻訳・作家活動していたにもかかわらず、日本SF作家クラブに入会することはできなかった。』(文庫版下巻・P75〜80)
見てのとおりである。
日本SF作家クラブは、つまり、日本のSF界は、設立当初から、すでに「呪われていた」のだ。

前述のとおり、私は長らく、次のような疑問を持っていた。
『ミステリ界に比べると、SF界は結束が固い。それは、SF大会などのイベントの、安定的な運営などによく現れている」といったことであり「この違いは、何に由来するのか?』
その一つの答えが、上に引用した「日本SF作家クラブ生誕時の呪い」である。
SF読者で、柴野拓美の名前を知らない者はないだろう。それもそのはずで、柴野がSF同人誌「宇宙塵」の主催者であったのなら、柴野は「日本SFの産みの親」の一人と言っても過言ではない人物だからだ。
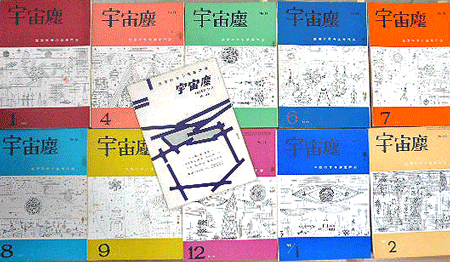
だが、そんな彼が『SFマガジン』編集長であり、いわば「プロの側」の有力者であった福島正実に睨まれたがために、入って当然の日本SF作家クラブの会員になれなかったのである。これでは、柴野自身がどう考えていようと、彼が崇徳天皇や菅原道真のような「御霊」になっていたとしても、何の不思議もないと言えよう。
柴野が日本SF作家クラブへの入会を許されないと知って、当時「じゃあ、私も入会は辞めとくよ」と言った(イワン・カラマーゾフのような)人は、ごく少数ではあれ、いただろうと思う(そう信じたい)。
しかし、そんな人の名前は残らない。なぜなら、友情や恩義さえあったはずの柴野が、むざむざ切り捨てられるのを目の前にしながら、それでも自分一個の利益と世俗的栄達のために、日本SF作家クラブの会員様になりおうせたような者には、当然のことながら、そういう「義の人」がうとましくて仕方がないはずだからである。
つまり、日本SF作家クラブは、多かれ少なかれ、柴野拓美を見殺しにした人たちによって作られ、囲い込まれたと言っても良い。
後には、福島正実の失脚によって、流れが変わるにしろ、恩人を切ってでも、長いものに巻かれることで「世に出る」ことを選んだ人たちによって作られた日本SF作家クラブに対する「呪い」は、たとえ柴野拓美自身がゆるしたとしても、消えて無くなるようなものではない。それこそ、『帝都物語』の加藤保憲のごとく、将門の怨霊を呼び覚まして、帝都に災いをもたらすような魔人は、永遠に生き続けるのである。
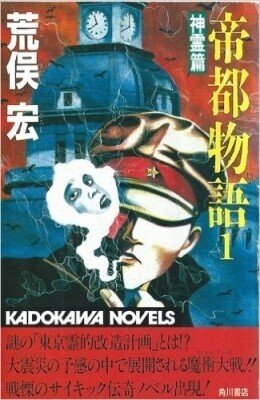
日本SF作家クラブ設立時のこうした揉め事に関して、今の私の立場から「客観的に批評」しておきたい。
まず、ここに登場する人たちは、今から見れば「日本SFの神々」にも見える人たちであり、いわば、こうした「揉め事」ですらも「神話」のようなものとして感じられるだろう。
だが、今年、還暦を迎える読書家の私からすれば、所詮は「思い上がった若造の、マウント奪取合戦」過ぎない。
福島正実だけではないが、福島に賛同した光瀬龍たちが、アマチュアの批評に求めた「理想」とは、所詮は、自分たちの「権益」を守るための綺麗事でしかない。
例えば、
(A)『攻撃的な批評を書く場合は、批評をする作家の著作や変遷をふまえた上でその文学的価値を理解して挑まなければならない。』
(B)『江藤のような時評が発表されたら、反論を提示できるだけの力と覚悟が必要である。「宇宙塵」ほどの影響力をもつ同人誌であれば、プロではなくアマチュアのたんなるファンだからと逃げるのではなく、それなりの覚悟と高い質が求められる。』
といったことは、これを当たり前のことのように感じる人もいるだろうが、基本的には「批評」に対する無知に由来する誤認でしかない。つまり、福島らは、ろくに「批評」「評論」といったものを読んでいなかったのである。
説明しよう。
(A)について。「作品評」というのは、「作家評価」を踏まえる必要はない。なぜなら、作品は作品単体として提供され、売られているものであって、作家を知らなければ、鑑賞してはならない、などという条件が付されたものではないからだ。したがって、その作品だけを読んで、つまらないと思えば、つまらないと評していい。
どんな大作家が書いていようと、書き手の「肩書き」や「権威」に忖度して、評価を矯める必要はない。それに、どんな大作家だって、駄作を書くこともあれば、加齢にともない良い作品が書けなくなっていくなんてことはよくある話。どんなにすごい作家だって、彼が人間である以上、そうしたことは当たり前にあることなのだ。
だからこそ「作品評」は、「作品本位」でなされなければならず、仮にその作品が駄作であった場合、その作品に「作家名」が記されているならば、その作品の制作責任者として貶されることだって、作家は甘受しなくてはならないのである。
(B)について。無論、作品評であっても『批評をする作家の著作や変遷』を踏まえないままの批判的評価は、その評価者自身にとって、リスクの大きなものとなるだろう。と言うのも、その否定的評価への反論が、『批評をする作家の著作や変遷』を踏まえたものであり、より「説得力」のあるものになっていたら、多くの裏付けや傍証を持たないままに否定的評価をした者の方が、結果として、自身の信頼性を損なうことになるからである。
しかしながら、批評というのは「裏付けや傍証」がたくさんあれば、それでいいというものではない。それはちょうど、たくさん読んでいるのに、頓珍漢な評価しかできない人というのが大勢実在していることにも明らかだろう。
つまり、能力が同じなら、「裏付けや傍証」をたくさん持って「脇を固めている」人の方が「勝つ」に決まっているという話であって、これは「裏付けや傍証」をたくさん持っている人の方が「正しい」という話ではないのだ。
それに「アマチュアであっても、批判するからには、反論された時に、再反論くらいできなければならない」というのも、所詮は、ご都合主義的に言っているだけでしかない。
と言うのも、アマチュアにそこまで求めるのなら、「広く世間に文章を売って、影響力を行使しているプロ」ならば、当然、アマチュアの何十倍、何百倍も「発言責任」を負うており、批判に対しては、必ず「応答責任」を果たさなければならない。一一と、そうなるはずだが、実際のところ、彼ら「プロ」が、そうした「責任感」を持っているかというと、そんなことは決してなく、プロだからこそ逆に「いちいちアマチュアを相手になどしていられぬ」と、偉そうに「自己免責」するというのが、今だけではない、昔から変わらぬ「プロらしいプロ」の態度なのである。
また、福島正実らは「ろくに本を読んでおらず、SFがすべてだと思っているような若造に何がわかる」と思っているようだが、前記のとおり、福島ら自身が、じつは、自分で思っているほど、広く深くいろんなものを読んでいるわけではないというのは、彼らの「批評」観の浅薄さにも明らかで、要は彼らが「SFだけではなく、いろんなものを読んできた上で、SFを高く評価している自分たち」という自己認識において「SFくらいしか読んでいない、若いアマチュア読者」を見下すというのは、今の私から見れば、所詮は「五十歩百歩」でしかなく「目糞鼻糞を笑う」に等しい、愚かな傲慢でしかないのである。
そして、そうした「愚かな傲慢さ」による、薄っぺらな「プロであることの権威主義」において、彼らは、「アマチュア」を利用するだけは利用し、最後は柴野拓美という恩人を「アマチュア」として切り捨てたのである。

このように「SFマインド」とか「センス・オブ・ワンダー」とか「SFプロトタイピング」だなどと、新しげで特別そうなことを言っても、所詮、彼らも「ただの人」であるというのは、今も昔も変わらない事実であり、彼らは「神話の中の神々」では決してないのだ。そのように考えてしまうのは、科学的思考能力を欠いた「SF教の妄信者」にすぎないのである。
したがって、『彼らアマチュアの行動、彼らが引き起こした問題に対して、SFに命を賭しているプロの自分たちまでが巻き込まれるのは迷惑』などという福島の発想は、誤った「エリート主義の傲慢」でしかない。
『SFに命を賭しているプロの自分たち』とか言ってみても、それは「自分のSF」であったればこそで、要は「他人のSF」など、どうでもいいわけなのだ。
言い換えれば、これは「SFそのもの」を愛しているのではなく、「自身を権威づけ、金儲けのネタにもなるSF」にだけ、相応に命を賭している、にすぎない。
そしてこの程度の意味でなら、アマチュアのSFファンだって、それなりに「SFに命を賭している」のであり、それはプロとは違って、「見返り求めない純粋なもの」とすら言いつのることだって可能なのである。
要は、プロとアマチュアに明確な線引きなどできず、違いがあるとすれば「業界的な力の有無」にすぎないということなのだ。どちらが「よりSFを愛している」とか「よりSFを知っている」とかいった問題ではなかったのである。
そして、こうした「日本SF界の呪い」は、今も生きている。
私が書いた「樋口恭介関連のレビュー」の中で言及した、山野浩一、梅原克文、瀬名秀明といった人々をめぐる、不可解な「日本SF界の村八分体質」も、こうした日本SF作家クラブの出自を知ってしまえば、「なるほどな」と思えるし、樋口恭介の「SFマガジン〈幻の絶版本〉特集中止問題」について、「SFマガジン」誌の新編集長である溝口力丸が、下の2021年12月25日発売の雑誌「SFマガジン 2022年2月号」の巻頭に掲載した「お詫びと展望」とのメッセージで、
『 お詫びと展望 編集長就任のご挨拶にかえて
12月7日に更新された早川書房公式サイトの〝「幻の絶版本」特集の中止について〟記事にあるとおり、本誌がネット上で発表していた特集企画の内容とその後の対応をめぐって、読者の皆さまから様々なご批判をいただいております。
https://www.hayakawa-online.co.jp/new/2021-12-07-180928.html
このたびは本企画が、読者および作者の方々への配慮を欠いたままにネット上にて進行し、また迅速な管理対応ができなかったことを深くお詫びいたします。文芸誌としてあってはならないことであり、ご指摘を重く受け止めております。
SFは、誰であっても自由に楽しむことのできるジャンルです。しかし、本誌のこれまでの在り方が、性別や年齢などを問わず、本当に全ての読者に開かれてきたかといえば、決してそうではなかったと、これまで本誌に携わってきた者として責任を感じております。
本件を受けて、編集部でも企画の立案や編集活動、SNS上での情報発信に関して、今後の改善に向けて新たなポリシー・ガイドラインの作成を進めていくことになりました。本誌を手に取ってくださった方々を落胆させることのないよう、かつ、国内外の優れたSF作品やその潮流、他メディア・他ジャンルとの接点を幅広く紹介できるように、個々の企画を様々な観点から検討できる体制を強化し、細心の注意とともに熟慮してまいります。
本号の特集は「未来の文芸」。
2020年代を担う書き手による、最新の文芸と、未来への想像力についての特集です。
日本唯一であるSF専門の商業文芸誌の、編集体制が大きく変わった第1号として、新しい風を入れることを考え続けながら編集を行いました。結果として集まった言葉はすべて、この困難な時代にあって、未来を真摯に見据えているものばかりです。
文芸を愛する、あらゆる読者へ多様な作品を届けること。
そのために自らの偏りを自戒し、常に誌面の進歩を志向すること。
開かれた自由な世界へと手を伸ばし続けること。
もちろん時には、過去作品の再発見にも目を向けてまいります。
いま変わろうとせずして、本誌に未来を語る資格はありません。
SFを冠する誌名に恥じないように、今後一層の精進をいたします。
第11代SFマガジン編集長 溝口力丸』
と、今回の問題とは奇妙に「ズレた」かたちで『誰であっても自由に楽しむことのできるジャンル』路線を強調していることの「奇妙さの背景」も窺えよう。

少し説明すれば、樋口恭介の企画に関わる「SFマガジン〈幻の絶版本〉特集中止問題」の問題点とは、要は「絶版本を読まないまま、勝手に内容を想像して作品評を書く」といった「前衛的な企画」が、単純に「絶版本の著者や出版関係者」の感情への配慮を欠いていたという点にあるのであって、決して「前衛的な企画」だったことが問題ではなかった。
なのに、溝口力丸編集長のこのメッセージは、見当違いにも『誰であっても自由に楽しむことのできるジャンル』ではなかった、つまり「前衛的」すぎたところを問題にしている点で、第三者の目には、不思議に見当はずれで不可解なものとしか見えなかったのである。
しかし、日本のSF界が、「文学の前衛足らんとする」派と、アメリカのSF界と同様に「誰であっても自由に楽しむことのできるジャンルであるべき」派との「呪われた抗争」の歴史だと考えれば、溝口編集長のメッセージも、完全に腑に落ちよう。
要は「文学の前衛たらんとする」派の若きリーダーである樋口恭介の失敗を受けて、「誰であっても自由に楽しむことのできるジャンルであるべき」派である溝口新編集長が「そうれ見ろ」と言わんばかりに、上記のような「宣言」をしたのではないか、ということだ。
実際、今の「日本のSF界」というのも、相当に奇妙な世界で、作家と編集者の関係が、実に「反時代的」なのだ。
出版業界の内情を多少なりとも知っている者なら「編集者に対して、作家が威張っている」なんていうのは「昔の話」だと思うだろう。なぜなら、今は「本が売れない時代」であるにも関わらず「作家になりたい人」は山ほどいるので、言うなれば作家は「使い捨て」にされやすい「弱い立場」に立たされているからである。
例えば、私が以前、書評を書いたミステリ作家・倉知淳の『作家の人たち』(幻冬舎)は、そうした「出版業界内幕小説」短編集である。
一時期はチヤホヤされ、編集者からも下にも置かない扱いを受けた作家が、本が売れないとなると、いかに惨めなことになるのかを、自虐的な笑いに変えて書いた小説集だ。
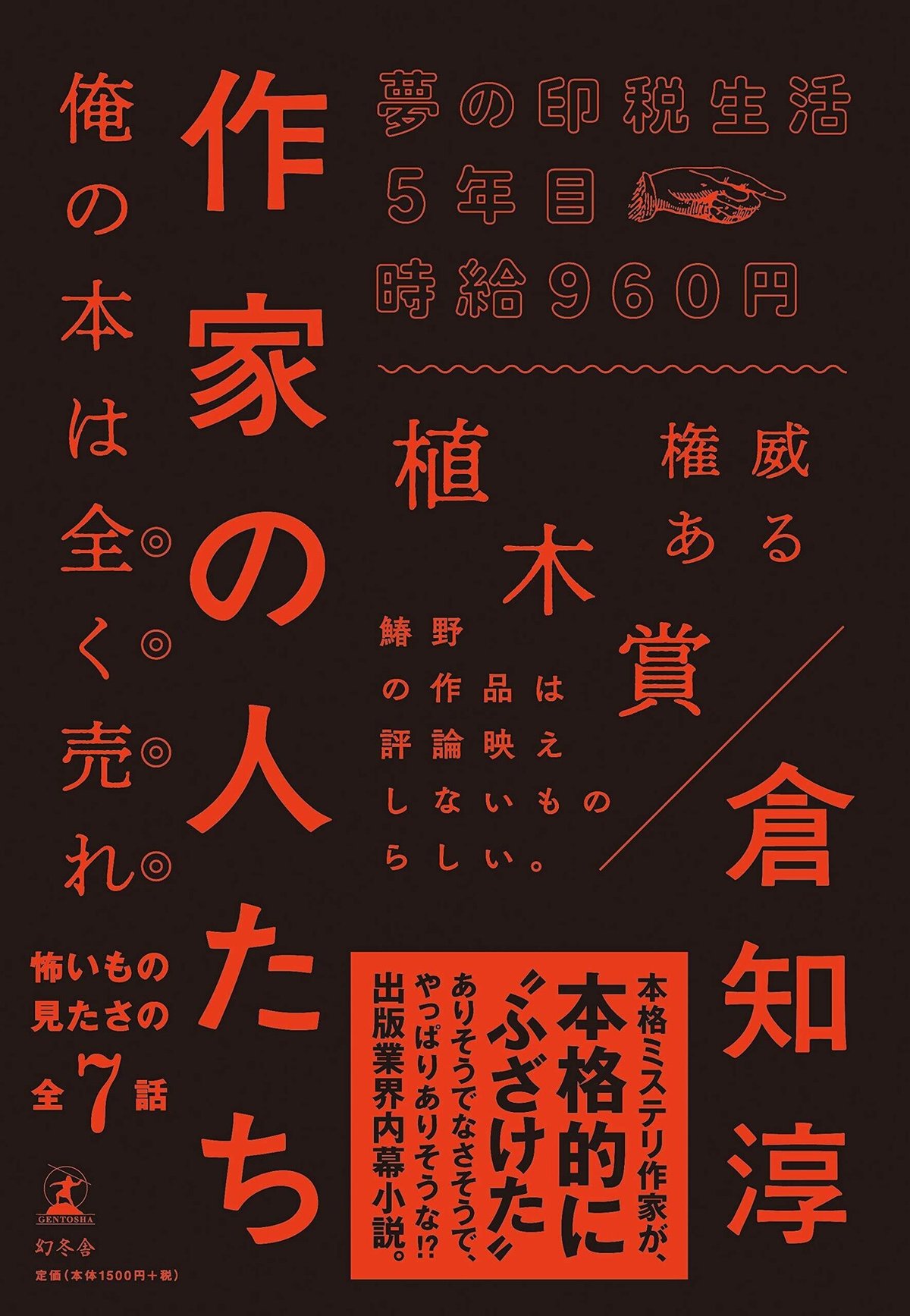
こうした傾向は、まずマンガ業界から始まった。特別な売れっ子マンガ家は別だが、近年は、通常の場合、編集者が作品をリードし、マンガ家はその意向に沿って作品を描く。作家が描きたいものを描くとか、自己表現として描くなどといった「古き良き理想」とは違って、「売れてなんぼ」の世界だからこそ、編集者は「売れるパターンの作品」を特に若手マンガ家に強いることになり、若手は「描かせてもらえるだけありがたい」から、それに従うことになるのだ。
一方、文学の世界は、昔は、作家が「先生」であり、編集者はその創作を補佐する「助手」のような立場で、当然のことながら、その立場は、作家の方が圧倒的に上だった。
ところが、マンガ界と縁の深いライトノベル(ラノベ)がブームになり、その一方「芸術としての純文学」が完全に過去のものになって以降、まずは人気のあるラノベの世界から「作家よりも編集者の方が上」という関係性が広がりだし、今ではミステリ界でも、一部の人気作家を除けば、普通のミステリ作家は「本を出してもらう」立場に立たされている。だから編集者に頭が上がらないのだ。そして、そんな「かつてとは違った状況」を笑いに変えたのが、倉知淳の『作家の人たち』という作品集だったのである。
(ちなみに、ネット時代の現在は、作家も個人的に発信をしているため、売れっ子ではなくなった作家たちが「編集者の手のひら返し」に対する「恨みつらみ」をツイートしたりしているので、作家になりたい人は、こういう現実を知っておくべきであろう。それでも作家になりたいのなら、止めはしない)
そんなわけで、一部の売れっ子作家を除いては、「小説家」は金にならない職業と化している。
前記のとおり、総量として「活字本」は売れなくなっており、売れているのはごく一部の作家に過ぎない。しかも、その「売れっ子作家」の寿命も短い。なぜならば、作家になりたい人は大勢いて、次から次へと才能ある新人が出てくるので、すでに当初の勢いは無くなっているのに原稿料だけは高いベテラン作家を大事にして、書く場を与える意味などないからだ。
したがって、今や売れっ子だって、偉そうにふんぞり返ってばかりもいられない。ベテランはベテランで、編集者との良好な人間関係を保つことによって、少々売上が下がっても、これまでの「義理」と「人情」で使ってもらえるような関係を維持しなければならないからだ。ましてや、売れっ子ではない作家は、もはや言うまでもないことだろう。
ともあれ、出版業界の現状がこのようなものであればこそ、SF界での「作家と編集者」の関係も、当然のことながら、編集者の方が強くなっているのかと思いきや、しかし、どうもそういうことにはなっておらず、SF界は今でも、作家の方が強いようなのだ。
どうして、門外漢の私に、こんなことが言えるのかというと、これも先日レビューを書いた、小川哲・樋口恭介・東浩紀による鼎談「『異常論文』から考える批評の可能性 一一SF作家、哲学と遭遇する」(2021年11月10日開催「ゲンロン・カフェ」)において、小川哲や樋口恭介が、「SFマガジン」誌の前編集長の塩澤快浩はもとより、現編集長の溝口力丸のことを、あいつは全然わかっていない、といった調子で、名指しで何度もこき下ろしていたからのである。

無論、作家が編集者の悪口や陰口を言うことなど、珍しくはないだろう。会社員が上司先輩の悪口や陰口を言うのと同じである。
しかし、小川哲と樋口恭介の場合、ニコニコ動画に生中継として流され、その後も録画が動画サイトで流されるという「公開の場」において、仮にも、天下の「SFマガジン」の編集長を「SFが分かっていない」奴、つまり「いい仕事ができそうにない、ヘボ編集長」呼ばわりをしていたのだ。
これには、さすがの私も驚いた。
SF界というのは、良くて「仲良しクラブ」であり、ベタベタした馴れ合い関係でやっているのだろう、くらいに思っていたのだが、これはどう見ても「作家が上で、編集者は下」という関係なのだ。
鼎談者の3人に酒が入っていたとは言え、樋口が「溝口はダメ」だと身も蓋もなく否定するのを、小川はたしなめようとはしないし、樋口が「なんなら、今からあいつをここへ呼びましょう」などと何度も言うことに対し、東浩紀が言うのは「もう、夜も遅いからダメだよ」みたいなことだけで、「それは迷惑だし、呼びつけるなんて失礼だよ」といったニュアンスのことをまったく口にしないし、それは小川哲も同じなのだ。

この鼎談で、わりあい「良識的な発言」の多かった小川が「編集者は、もっと作品に対して意見を言い、作家に助言をすべきなのに、彼らは何も言わない」という趣旨の批判していたが、このお説ごもっともな正論も、作家がこれだけ威張り散らすような関係では、いやでもそうなって当然ではないか、としか思えない。
そもそも、編集者が本気で作品の欠点を指摘し、ビシビシ書き直しを指摘し始めたら、小川だって「SFや文学のことを何もわかっていないくせに、編集長になったからって、偉そうに言うな」くらいのことを考えるだろうことは、容易に推測できる。だが、小川哲当人は、そんなことにも気づかないくらい、作家の優位性を自明のものとしており、すでにそれが見えなくなってしまっているようなのだ。
どうして、出版業界全体としては「作家の地位」が下落して、作家の雇用者(出版社)側である「編集者の地位」が相対的に高まっているというのに、例外的にSF界だけは、今も「作家の方が編集者より偉い」という関係が続いているのであろうか。
それは、ミステリ出版界を含む、一般のエンタメ小説出版界に比べると、「春の時代」を迎えていると言われる今の日本のSF界ですら、その市場規模はごく小さく、要は、コアなSFファンに支えられた、SFオタクを顧客とした「小さな業界」だということなのではないだろうか。つまり、コアなSFファンに支持されなければ、もともと広く売ることのできないSF小説が、まったく売れなくなってしまうという、そんな不安定な業界だということだ。
そのため、どうしても「マニアうけのする作家」が重用される。そのあたりこそが、狭い「SF村」の中では、同時代的に安定的な「売れ筋」だからである。まただからこそ、作家の方も「マニア受け」のする作家であろうとするし、その意味では編集者の出る幕は少ない。広く売るための助言など、する必要はないし、そもそもそれは業界的には、見当違いでしかないからだ。
しかも、そうした、マニアックな方向性が、ごく稀に世間にも受けてベストセラーを生んだりするものだから、普通の編集者が当然考えるような、SFが『誰であっても自由に楽しむことのできるジャンル』であってほしいというような(『スター・ウォーズ』『宇宙戦艦ヤマト』ブーム的な)方向性は(それが「SF冬の時代」を招いたとも考えられており、戦犯扱いにされて)ほとんど問題にはならず、おのずと編集者は、SF業界内における「売れっ子作家」の下位に置かれることになるのだ。

実際、前編集長の塩澤快浩にしたところで、1968年生まれであり、SF界の神話に絡むような人ではなく、前記鼎談で小川哲が指摘していたとおり、個人的に一番好きな小説ジャンルは「ハードボイルド」といったことなのだろうし、新編集長の溝口力丸にいたっては、まだ三十過ぎだそうだから、1986年生まれの小川哲より年下だろうし、1989年生まれの樋口恭介と同じくらいだから、文才のある小川や樋口にしてみれば、せいぜい「世間の人よりはSFに詳しい、サラリーマン」くらいの感覚しかないだろう。編集長だからといって、特別に持ち上げなければならない存在ではないし、同世代だからこそ、作家と編集者の力関係において「公の場でも、言いたい放題が言えた」のであろう。
まただからこそ、溝口力丸編集長による、前記の「お詫びと展望」は、肝心の樋口恭介には触れないまま、
『SFは、誰であっても自由に楽しむことのできるジャンルです。しかし、本誌のこれまでの在り方が、性別や年齢などを問わず、本当に全ての読者に開かれてきたかといえば、決してそうではなかったと、これまで本誌に携わってきた者として責任を感じております。』
と、「SFマガジン〈幻の絶版本〉特集中止問題」についての「お詫び」としては、やや見当違いに、樋口恭介の「前衛」趣味を批判するような内容になってしまったのではないだろうか。
○ ○ ○
閑話休題。
つまり、日本のSF界には「SFエリートと平民ファンとの相克」という「呪い」が、今もかかっているのである。
本書、最相葉月の『星新一 一〇〇一話をつくった人』によると、柴野拓美を排除して、自分の望むSF界を構築しようとした福島正実は、まさにその欲望によって報いを受けることになる。
(3)『 ところで、講談社の編集者たちが新一のもとを訪れたころ、SF界では厄介な事件が起こっていた。「SFマガジン」昭和四十四年二月号に掲載された匿名座談会をめぐるSF作家たちの叛乱と、編集長だった福島正実の退社に至る一連の騒動である。
「仲良しクラブ」「メダカの学校」などと揶揄されたSF作家の打たれ弱さを露呈した、という意味ではたしかに事件だったのかもしれない。ただ、批判する側が匿名とはいえ、公然と作品を批判されるのは表現活動に携わる者にとっては覚悟しておかねばならないことのはずである。ところが、批判したのがふだんはSF作家たちと親しくつきあっている理解者であるはずの評論家や編集者たち(石川喬司、稲葉明雄、福島正実、伊藤典夫、まとめ役・森優)だったことから事態は予想外の展開を見せた。
批判された作家らが匿名子の犯人探しをし、誌上で反論を行い、「SFマガジン」には金輪際書かないといって去っていったのである。そうでなくとも、作家の原稿を勝手に改竄したり、若い作家たちを自分の持ち物のようにコントロールしたりして、しばしは衝突を起こしていた福島正実への不満が、ここで一気に爆発した。矢野徹が仲裁役となったが、福島が編集長を退任しても収まらず、早川書房を退社して、ようやく事態は収束した。
副編集長だった森優は、両者の間に立ち、悶々とした日々を送った。
「よかれと思ってやった企画だったのにあんなことになってしまって、ぼくは板挟みにあって大変だったんです。両方とも裏切れない。まったくぼくはこうもりみたいで、どっちつかずだと思いました。SF作家に連帯意識があった時代だったので、仲間にうしろから斬りつけられたような気がしたんでしょうね。福島さんはこの事件をきっかけにやる気をなくしてしまった。そういうときに星さんはどうしていたのかというと、恬淡として関わりをもたなかった」
福島に反旗を翻す先頭に立ったのは、豊田有恒だった。
「小松さんと筒井さん、平井とぼくがけなされて、四人でどうしようかと深刻に相談して、これは対抗したほうがいいだろうと話し合ったんです。そこへ星さんがちょっと遅れて来たんだけど、着くなり、こういったんです。飼い犬に手をかまれるっていうのは聞くけど、飼い主に尻をかまれた犬っていうのは初めて聞いたなあ、って。ひでーこというなあっていいながらもみんな笑って場がいっぺんに和んじゃった。こっちが思いつめてるの見て、からかいたくなったんだろうなぁ。星さんにはいつもそういうところがあった」
生まれたての弱小分野だから手をとりあってSFを守り立てていこう。世間の無理解にはともに闘っていこう。日本SF作家クラブにはひとりの反対者がいても入会できないという会則ができたのも、内部の結束力が最優先されたためだった。そのため、たとえ「仲良しクラブ」といわれても、それでよしと彼らは考えていた。ところが、この匿名座談会では、悪い側面がむき出しに現れてしまった。彼らがいかに、仲間内の批判に弱かったを物語っている。
読者として、客観的な立場から見ていた荒俣宏の言葉が参考になる。
「過剰反応はあったでしょうが、おれは作家だとアピールしないと尊敬されないし、配慮もそれないし、という不安があったんじゃないでしょうか。早川書房でリスペクトされないと他の出版社に行ってもただでさえ相手にされないのに、しめしがつかないというのもあったでしょう。今の〝2ちゃんねる〟で交わされている悪口なんか見たら、当時のみんなならとっくに死んでますよ。ぼくはずいぶんあとに『帝都物語』が日本SF大賞をとったから入れということで、八〇年代の後半に日本SF作家クラブに入れてもらいましたが、それまでは入りたくても入れてもらえなかったんです。そのかわり結束がかたいし、悪口なんかタブーという雰囲気でした。そうでないと吹き飛ばされるからでしょう。出版社にも無理が通らないし、丁重に扱ってもらえない。でも、小松さんや星さんの陰にいれば、二人の手前そうなおざりにはできないでしょう。SFは子供の紙芝居みたいにいわれていましたからね。SFというジャンルを認知してもらうには必要だったんだと思います。ジャンルを確立するために血のにじむような努力をしていたんです。星さんと小松さんが裏のものを表に変えた。筒井さんはさしずめ小泉純一郎で、表のものをぶっ壊した」
福島は、事件の対応にはほとほと疲れ果て、「SFマガジン」昭和四十四年八月号に「それでは一応さようなら」という一文を書き、早川書房を退社した。
福島曰く、「強大な政治権力によって、不当に弾圧されている少数民族の、独立をかちとろうとする革命家気どり」の「独立宣言」(『SF入門』)でもあったSF専門誌の創刊から十年。志なかばにして去った福島は、徐々に日本SF作家クラブの公的な活動から距離を置くようになり、やがて自分自身の作家業に専念した。』(文庫版下巻・P183〜186)
これもまた、見てのとおりである。
日本のSF界、特に『SFマガジン』誌には「編集者や評論家が、作家をこき下ろしたがために、人気作家たちが執筆拒否をして、編集長が退社するに至った」という「歴史」が、厳然としてある。ならば、小川哲が「編集者には、もっと意見を言って欲しい。原稿を受け取るだけが仕事じゃない」みたいな「正論」を口にするというのは、端的に言って「日本のSF界の歴史についての無認識」としか言えないだろう。
忌憚のない批判をろくに受けたことのないような「温室育ちの作家」たちが、編集者に「もっと意見を」などと求めるのは、身の程知らずでしかなく、それを言うのであれば、まず自分が、他の作家の作品をこき下ろしてみせろ、ということにもなるのである。
「先生」が、おだてに乗っていい気になり「そち達は遠慮なく、余を批判してよいぞ」などと言い、それを真に受けて批判なんかするのは、世間知らずの馬鹿だけなのである。
○ ○ ○
そんなわけで、ここで問題とすべきは、「今の日本のSF界」は、いまだに「批判に対する脆弱性」を抱えたままの「ムラ社会」でしかない、ということであり、それでいて、その「温室」環境によって、ぐんぐん伸びた「天狗の鼻」によって、自分たちには「未来を見通す能力がある」などという勘違いをしている点だと言えよう。
私が、大森望以下、新井素子、冲方丁、小川哲、高山羽根子、樋口恭介、藤井大洋らによる『世界SF会議』(早川書房)を「SF作家だからといって、何も〈特別〉ではないのだから、もう少し頑張ってほしい。」と題して、注文をつけた所以である。
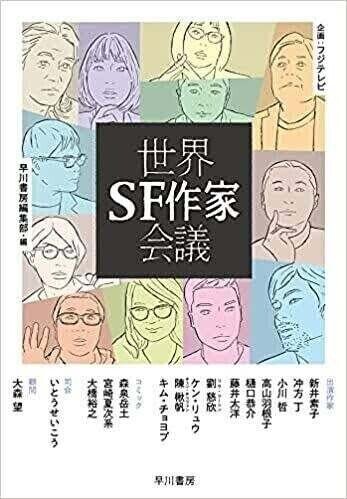
もちろん、「出版不況」の現在、売れっ子がチヤホヤされるのは当たり前であり、そのくらいのことは彼らだって気づいていないわけではあるまい。しかし、どこかで「自分だけは、そんなものに惑わされない」と考える、思い上がりがあるのではないか。
まともに教養のある人間なら「先生の立場になれば、どんな人だって、多かれ少なかれ勘違いするようになる」ということくらいは「歴史」に学んでいるはず(で「権力は必ず腐敗する」の)だから、そうなりたくないと思えば、実際に「偉くはならない=世に出ない=地位や名誉を、意識的に遠ざける」か、傍目にも明らかなくらいに「謙虚」であることを自分に課したはずである。
つまり、逆に言えば、それくらいのことをやらない「普通の有名人」というのは、多かれ少なかれ「思い上がっている」のであり、それに気づいていないのなら、その人は本質的に、馬鹿だということなのだ。
○ ○ ○
例えば、先日、レビュー「小松左京〈利権〉を確保せよ!」で取り上げた『現代思想 2021年10月臨時増刊号 総特集◎小松左京 生誕九〇年/没後一〇年』(青土社)も、基本的には「小松左京は、偉大な作家であった」という「ストーリー」を基軸とした特集で、そこに、二、三の「そんなことはない」という批判的意見を加えることで、「両論併記」の客観性アリバイだけは確保していた。
そして、これに「小松左京は、偉大な作家であった」という「神話」の追認強化的な原稿を寄せたのは、言うまでもなく、SF関係者が中心であり、小松を批判したのは、主に小松の「政治関連(大阪万博、花博など)の動き」を検証した社会学関係の学者たちであった。
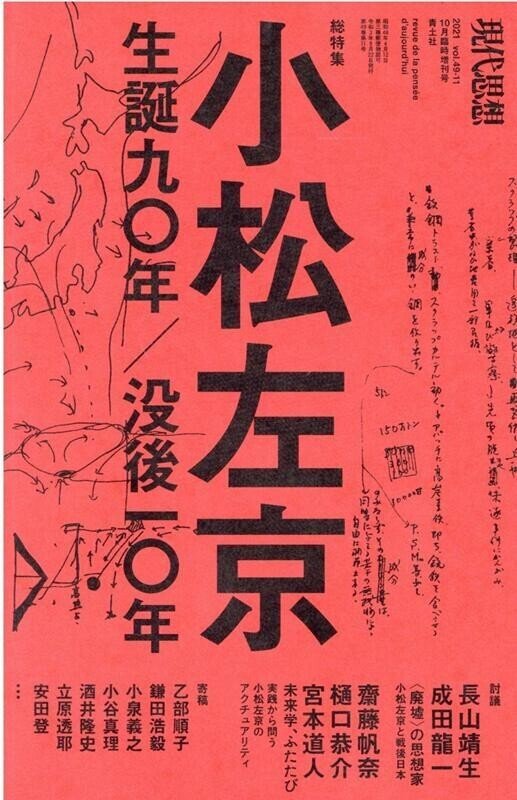
小松の「知識人」としての動き、あるいは「未来学の思想家」としての動きについて、できればそれにあやかりたいと考える人たちは、それを「未来を構想する偉大な仕事」だと褒めたたえ、一方、小松の関わった「政治的大イベント」の陰で犠牲となっていった「名もなき庶民たち=まつろわぬ民」の側に目を向けた者は、小松を所詮は「祭り上げられて、勘違いした作家先生(=御用知識人)」だと見ていたのである。
無論、小松左京という人にも「作家としての評価」と「人としての評価」の二面性があって当然で、どちらか一方であることの方が無理なのだから、小松は「作家としては偉大であったが、人としては先生扱いによる勘違いも少なからずあった」といった評価がなされても、それはなんら矛盾した評価にはならない。そして、そうした「勘違い」の結果が、あの無残な(独りよがり)映画『さよならジュピター』というかたちで「作品」としても具現したのだという評価だって、あながち間違いではないはずなのである。

実際、前述の「匿名座談会」事件に対する、小松らの「ナイーブ」な反応を見れば、当時の小松らが、所詮は「思い上がった、売れっ子作家先生」であり、その意味で「普通の人」でしかなかった、というのは明らかであろう。
荒俣宏が言うように、今の感覚からすれば、あまりにも「ナイーブ」にすぎ、要は「過保護」すぎたのだとも言えよう。つまり、彼らの反応は、アニメ『機動戦士ガンダム』の主人公アムロ・レイの、
『親父にもぶたれたことないのに!』
という有名なセリフ、そのものの「反応」だった。
「誰にも(公然と)批判されたことがないのに!」というわけだったのだ。
そして、こうした日本のSF作家の「ひ弱さ=批評(客観評価)に対する脆弱性」というのは、本書『星新一 一〇〇一話をつくった人』の主人公において、端的に「象徴」されるものだとも言えるのである。
○ ○ ○
さて、やっと星新一である。
前述のとおり、私が星新一を読み始めた頃には、すでに星は「メジャーなSF作家の一人」であり、かつ「超然として、ちょっと特異な立ち位置にいる作家」であった。つまり、SF作家ではあるけれど、星新一は星新一であり、一作家一ジャンル的な作家だという印象があったのである。
そして実際のところ、星新一は、戦後の日本において、SF作家として最初に自立した人であったし、その意味では、小松左京や筒井康隆といった、その後に日本のSF界を代表するようになった作家たちの、「大先輩」でもあった。また、それに加え、星は「星製薬の御曹司」ということもあって、日本のSF界においては、いわば「別格」的な存在として、周囲から下にも置かない扱いを受けてきた作家だった。星自身も、その作風どおりに「生な人間関係」からは数歩下がった位置に立って、ニヒルに様子を窺っているようなスタンスを採り続けた人だったから、一般にも星は「別格」という印象を与えていたのであろう。
しかし、そうした「外見的印象」は、必ずしも「星新一という人」の内面を、そのまま反映したものではなかったようだ。
本書の著者・最相葉月によれば、周囲から「別格」扱いにされていたにも関わらず、星新一自身は、自分に対する周囲や世間の評価に、ついに満足を得られなかったようで、終生「承認不安」にとらわれていたようなのだ。
(4)『 私(※ 星新一)は人生について深く考へる事は余り好きではない。我々の生きている事について、何故とか、何のためとか考えた事はない。そのような事はなるべくそつとしておくことにしている。深く考へることに自分の性格が堪えられるかどうかが恐ろしいのである。』
(文庫版下巻・P163)
これが、星新一を考える上で最も重要なポイントとなる、星の自己認識であろう。
要は「人間(そのもの)については、考えたくない」人なのである。
なぜ、星新一がこうなってしまったのか、そのいちばんわかりやすい説明としては「望まずに星製薬を引き継いだ後に、いやというほど体験させられた、信頼していた人たちの裏切り」により、深く傷ついて人間不信になった、といったことにでもなるだろう。
だが、私の興味は、そうしたところにはない。私の興味は、とにかくこうして本人からも自覚的に語られた「人間不信」が、その後、作家になった星新一に、どのように表れたのかという結果の方である。
(5)『「わが小説」(朝日新聞、昭和三十七年四月二日付)という随筆で新一は、「ボッコちゃん」には「私の持つすべてが、少しずつ含まれているようだ。気まぐれ、残酷、ナンセンスがかったユーモア、ちょっと詩的まがい、なげやりなところ、風刺、寓話(ぐうわ)的なところなどの点である」と書いている。幼児退行の現れだという指摘に対しては、「自分でもその通りと思う」と認め、分別のある大人ばかりの世の中で、自分ひとりぐらい地に足がついていない人間も必要だろうと確信犯であることを表明している。
(※ 「ボッコちゃん」の)お世辞をいわない、という設定がどこから来たのかはよくわかっていない。たんなる思いつきにすぎないのかもしれないが、友人たちが指摘する新一自身の姿が重なって見える。新一が会話のなかでもっとも嫌うのがお世辞だった。自分に対し、心にもないお世辞やおべっかを使う(※ 星製薬の)役員や親族、会社関係者の姿をさんざん見てきたからろうか。新一を星製薬の御曹司と知った銀座のバーの女性たちが、あるいはそうだったのかもしれない。』
(文庫版下巻・P331〜332)
「気まぐれ、残酷、ナンセンスがかったユーモア、ちょっと詩的まがい、なげやりなところ、風刺、寓話(ぐうわ)的なところなどの点」というのは、まさに星新一の作風からもストレートに窺える、星の個性だと言えるだろう。
だが、問題は、こうした個性から、かつての私は、星新一に、ある種の「強さ=強靭さ」を見ていた点だ。
強いからこそ、人の顔色を窺うことなく『気まぐれ、残酷、ナンセンスがかったユーモア』な振る舞いができる、とそう考えた。『ちょっと詩的まがい、なげやりなところ、風刺、寓話(ぐうわ)的なところ』については、直接的な表現を好まない「シャイさ」の表れではないかと、おおむねこのように「好意的」に理解していたのである。
一一ところが、本書で知った星新一という人は、私の期待したような「強い人」ではなかった。
また、星が単純に『心にもないお世辞やおべっかを使う』人を嫌ったとも言えない。つまり、人から「持ち上げられること」自体が嫌いだったわけではない。むしろ、そうした「先生扱い」を求めた人だったのだ。
ただし、それが「心からのもの」であることを、星は求めたのだが、それが「心からのもの」かどうかなど、持ち上げられることを望む当人が、人にそこまで注文をつけるというのは、他人への要求が過大にすぎるのではないだろうか。要は「俺を、心から尊敬せよ」ということなのだから。
(6)『 人前に出るのが苦手でシャイでおとなしくて品のいい人。そんなイメージを抱く人もいれば、「星新一、ありゃあきちがいだ」(安岡章太郎)などと仰天する人もいる。』
(文庫版下巻・P166)
私のもともとのイメージは、前者に近かったと言えるだろう。だが、本書で紹介されたような、ちょっと非常識とも顰蹙ものとも言えるであろう「星新一のジョーク」は、星が、星製薬の御曹司であるとか、日本SF界の第一人者であったからこそ、許された部分が大きかったとしか思えない。
その意味で私は、星新一の「毒舌ユーモア」に、一種の「甘え」を見ざるを得ない。
したがって、星新一の「毒舌ユーモア」は、安岡章太郎が言うような、星の「きちがい(非常識)」から出たものとは、評価し得ない。そうであったならば、常識に抗う「作家的な強さ」としての「毒舌」だと、肯定的に評価することもできるのだが、星の「毒舌ユーモア」は、結局のところ「私だったら許される」という「甘え」の上に成立したものであり、要は、星の「特異な育ち」が、星新一に、ある種の「過剰な甘え=キチガイ」をもたらした結果だと、そう考えるべきなのではないだろうか。
(7)『 有名になることは、外から想像するほど優雅なものでものではない。人気クイズ番組「連想ゲーム」の解答者としてレギュラー出演したときは、戸越銀座を散歩していて、「あ、星新一だ」と子供に指を差され、それがきっかけで突然、テレビに出るのやめてしまった。アンダーシャツ一枚とサングラスで散歩するのが唯一の息抜きなのに、それさえ奪われるのは我慢できなかった。
華やかな出版パーティーで駆け寄ってくるSF作家仲間や編集者に笑顔を振りまいても、パーティー会場を出れば瞬時に真顔に戻った。さっきまで歯を出して大笑いしていたのが、振り返れば、眉間に皺を寄せ足元を見つめていた。』
(文庫版下巻・P167)
私に言わせれば『有名になることは、外から想像するほど優雅なものでものではない。』といった程度の認識は、30歳くらいまでには身につけてほしい話でしかないが、現実にはそうでもないようだ。その意味では、私はわりあい早い時期に「有名人」と接することができ、その実際を知ることができたのは、とてもラッキーだったのであろう。
私がわりあい早い時期に知り得たのは(性格によりけりとは言え、一般に)「有名になるというのは、なった瞬間は嬉しいけれど、あとは重荷になるだけだ」という大方の事実であり、これをより一般化して言い換えれば「地位も名誉も欲しいものも、手に入れた瞬間が最高に嬉しく、そのあとは、それが当たり前の現状になってしまい、さほど嬉しくも面白くもなくなってしまう。だからこそ、多くの人は、新たなものを欲してしまい、欲望は止まるところを知らず、落ち着く先を知らない。したがって、いちばん好ましいのは、心から現状に満足しながらも、理想を持って生きることである」といったことになる。
まあ、一種の「悟り」なのだが、星新一には、こうした「人間にとって、幸福とは何か?」を「突き詰めて考える」習慣が、事実として無かったようである。
(8)『「星氏のショートショートの質は世界的だ」「五百編以上ものバリエーションをもち、そのすべてが水準を保っているのは珍しい」(「週刊サンケイ」昭和四十三年五月六日号)といった、自身もショートショートの書き手である都筑道夫の高い評価もあれば、初期のころから新一の作品を読んでいた推理小説やSFの熱心なファンの中には、昭和四十三年に新潮文庫としてまとまった『マイ国家』前後からマンネリを感じで星作品から離れたと語る者もいる。石川喬司の指摘する「量産によるマンネリ化」は、長年のウォッチャーとしての実感であり、愛情あまっての叱咤激励だったのだろう。
始めのころは新一にも、マンネリの何が悪いと開き直る余裕があった。筒井や平井らSF作家仲間たちが発行する「SF新聞」創刊号(昭和四十一年二月二十日発行)では、批判を逆手にとって「マンネリ」という随筆を書いている。漫画家のチャールズ・アダムズや加藤芳郎、サザエさんの長谷川町子、モーツァルトや眠狂四郎といった名を挙げて絶賛しつつ、「問題点はマンネリにあるのではなく、その質のほうである」「マンネリこそ成功の条件、偉大さの特性ではないか」と指摘。一方で、短編の名手だったシャクリィに対しては、「他人がなんと言おうと、平然と初期のペースを守っていればいいのに」、新分野に挑戦したがために「あまりいい結果ではなかったようだ」とも書いている。
ところが、大阪万博以降、新一周辺のSF界で微妙な変化が生じ始める。
昭和四十五年の第九回日本SF大会で、ファン投票によって選ばれる星雲賞が創設されたが、まずはその結果に顕著に現れた。一九七〇年代は、一部のマニア的読者の知的な読み物だったSFが、商業化の過程で小説ばかりでなく映画、漫画、テレビへと拡散し浸透していき、神戸で開催された日本SF大会「シンコン」(昭和五十年八月)で筒井が「SFの浸透と拡散」と名づけた時代である。星雲賞を企画した伊藤典夫によれば、その過程で、星新一は「偉大なるマンネリ期」に突入し、SFファンの星新一離れが起きていた、というのである。
星雲賞第一回の受賞作は、長編部門『霊長類 南へ』、短編部門『フル・ネルソン』と、いずれも筒井康隆である。第二回は、長編部門が小松左京の『継ぐのは誰か?』、短編部門が筒井の『ビタミン』。昭和四十九年の第五回星雲賞は、四百万部という空前の大ベストセラーとなった小松の『日本沈没』が長編部門に、短編部門が筒井の『日本以外全部沈没』と、やはり小松、筒井が人気を集めており、その間を縫うように、半村良や広瀬正が受賞。SFファンが新一の作品を選ぶことはなかった。』
(文庫版下巻・P204〜206)
『始めのころは新一にも、マンネリの何が悪いと開き直る余裕があった。』一一このあたりの星新一の心の動きは、きわめて凡庸であり、要は、ありがちで、子供っぽい「負けず嫌い」でしかない。
それでいて、そんな自身の「ありきたりな心の動き」に気づかないところに、「人間の心の動きを腑分けする」ような「純文学」的なことを嫌った「星新一の弱さ」が、はっきりと刻印されていたと言えるだろう。
(9)『 のちに「SFマガジン」編集長を務める今岡清は学生時代、星雲賞がスタートした前後から日本SF大会に参加していたが、そのころすでにSF作家としての星新一の魅力はデビュー直後をほどではなくなっていたと記憶している。
「当時は、星さんはSF界の業界の流行とはもう無関係だったんです。SFとしてそれほどユニークだったり実験的だったりはしなかったし、小松さんのように何かが突出して売れたというわけでもない。だらーっと長く売れていて、読者の顔がよく見えない感じだった。青雲賞は時代の雰囲気と同じ流れにあるものを評価して、ファンも投票していたいましたから、星さんにはもう賞をあげるきっかけがなかったんだと思います」
SFを牽引してきたにもかかわらず、SFが盛り上がるころには、SFの読者は自分から離れている。なんとも皮肉な話ではないか。』
(文庫版下巻・P206〜207)
端的に、星新一は、他者からの「(高い)評価」を求めた。「賞賛」を求めた。「別格扱い」を求めたのである。
しかし、他人の「評価」というのは、所詮は「人それぞれ」だし、自分の価値観においての評価を、他人にも求めるというのは、きわめて初歩的な「勘違い」でしかなく、まして自分の価値観を他人に強いるのは「傲慢」でしかない。
無論、自分の価値観に基づく評価は堂々と表明すべきであろう。その上で、それを受け入れるか拒絶するかは「あなた次第ですよ」と委ねることのできる「強さ」が、人には必要であり、それがあってこそ「公正な社会」も保てるのである。
だが、星新一には、こうした「強さ」が無かった。「どうして、ぼくがもっと評価されない」「これだけ貢献したのに」「これだけ高く評価する人もいるのに」「あいつらは開きメクラか」といった苛立ちは、他人は所詮他人でしかないと悟れない、星新一の幼児性を露わにしていると言えるだろう。
だが、無論「こんな人は」多いと言うか、「こんな人の方が」多い。作家などでもそれは同じで、しかも、今も昔も同じなのである。
(10)『 SF専門誌が次々に刊行され、有望な新人がデビューして多くの読者を獲得し、以前は連日のように銀座や六本木で騒いだSF作家仲間たちが忙しくなっていく。もちろん彼らは新一のことが大好きだったし、酒を飲んだり麻雀をしたりすれば、「天皇」「殿さま」といって守り立てる。小松はいついかなるときも、新一を立てた。新一が社会的な地位や礼儀に厳しい人であることを承知していたためである。自分がどんなに売れて忙しくしていても、肩を組み、笑い合う仲間となっても、公の場では常に新一に敬意を表した。それは筒井も同様である。小松と筒井の二人が新一を立てる。その様子をほかの若い作家や編集者は見ている。ならば、誰が星新一に刃向かえるだろう。
「星さんに睨まれたら、作家も編集者も、SFの世界では仕事ができなかった」といった言葉を私はいくつも耳にしている。では、周囲が持ち上げるのは、処世術としての側面もあったのか。たしかに星新一は、新人作家にとっても編集者にとっても、恐れられる存在になっていた。現役の作家というよりも、他人にお墨付きを与える役割を担わされる。四十代にして新一はSF界の長老だった。それは果たして、作家として幸せなことなのだろうか。』
(文庫版下巻・P237)
『小松はいついかなるときも、新一を立てた。新一が社会的な地位や礼儀に厳しい人であることを承知していたためである。』一一といったあたりは、小松左京のソツのなさがよく表れている。
おだてておかないと、へそを曲げてしまう星新一の性格を正しく見て取り、ごく一般的な「社会人の処世」として、「上司」にも等しい「先輩」を、ソツなく持ち上げていたのであろう。
小松のその後の「社会的な成功」は、何も「小説」の力だけに支えられていたのではないということが、ここからもよくわかる。きっと「未来学」関係の諸先生方にも、このようにソツなく接して、関係を築いていったのであろう。その際に「小説家」的な実績は、「名刺代わり」ではあれ、「オマケ」であったはずだ。先生方は「SF」など、ほとんど読んでいなかったはずだからである。

『小松と筒井の二人が新一を立てる。その様子をほかの若い作家や編集者は見ている。ならば、誰が星新一に刃向かえるだろう。/「星さんに睨まれたら、作家も編集者も、SFの世界では仕事ができなかった」といった言葉を私はいくつも耳にしている。では、周囲が持ち上げるのは、処世術としての側面もあったのか。』一一もちろん、そうだ。それがすべてではないにしても、それが「当然の心得」だったというのは間違いない。
『たしかに星新一は、新人作家にとっても編集者にとっても、恐れられる存在になっていた。現役の作家というよりも、他人にお墨付きを与える役割を担わされる。』一一こうした話は、「昔話」として納得しているだけでは不十分だ。
例えば、この「星新一」の位置を、今なら誰が占めているだろうかと考えてみるくらいの批評性は、是非とも必要だろう。それができれば、今の作家たちの「有力者」への「おべんちゃら」に惑わされることもないし、「有力者」の「愚かな人間臭さ」も生々しく実感できるはずだ。それが、「純文学」的な読解センスである。
実例で言うなら、すでに言及した「ゲンロンカフェ」での、小川哲・樋口恭介・東浩紀による鼎談「『異常論文』から考える批評の可能性 一一SF作家、哲学と遭遇する」なんかで、小川と樋口が、東浩紀への「リスペクト」を盛んに口にしているのも、嘘ではないにしろ、「話半分」に聞くこともできるだろうし、それを喜んでいる聞いている東の、「頭の良さ」だけではどうにもならない、度しがたく「満たされない承認欲求」という「人間的な業の深さ」も、より深く感得できるだろう。
この鼎談で自分でも触れているように、かつて東は、「東さん、東さん」と擦り寄ってきた「才能ある若い人」たちに裏切られ、深く傷つく経験をしているのである。それでも、また「褒めてくれる取り巻き」を求めてしまうというのは、なんと「純文学的な現実」であろうか。言い換えれば、なんと「SFとは縁遠い現実」であろう。

(11)『「おもしろいか」「売れるか」
筒井の作品に限らず、新一はこのころから、(※ この当時話題となっていた、筒井康隆の『虚構船団』と同様に)話題になっている本があれば編集者とその二点だけを決まり文句のように訊ねることが多くなった。おもしろいけど売れるかどうかはわからないという返事だと、少しほっとした表情を見せた。
純文学では、おもしろい、という評価は決してほめ言葉ではなく、おもしろいけれどただそれだけ、という否定的なニュアンスで受け止められる風潮があった。文学としてのレベルは低いという意味で、「それはエンターテインメントでしょう」などと蔑む作家や文芸評論家はいまだに存在する。
だが新一は、どんな書評で絶賛されても、純文学の大家が帯に名を連ねてほめ称えても、おもしろくなければ読者は買わないのだし、売れなければ意味がないと考えていた。それは自分の著作に対しても変わりなく、このころ(※ 編集者の)加藤が新一に少年時代を書いてはどうかと勧めているが、「そんなの書いても売れないから」とあっさり断っている。
では、『虚構船団』はどうか。はじめての読者でもすんなり作品世界に入れる小説家といえばそうではない一一新一にはそう感じられたのである。
(中略)
(前略)星新一は、筒井康隆の応援者であり、筒井にとっては発想の泉であり、最大の理解者であったといっても過言ではないだろう。筒井もまた、「先輩としての星新一、小松左京の二巨人を持てたことは、ぼくの大きな幸運であった」「作品の上での影響は自分でも計り知れぬほどである」(『ボッコちゃん』文庫解説)と書く。筒井を担当する編集者はみな、筒井は新一を深く敬愛し、大いに徳としていたと語っている。
(中略)
新一の筒井に対する感情があふれ出たのは、筒井が昭和六十二年に『夢の木坂分岐点』で谷崎潤一郎賞を受賞し、さらに、井上靖や吉行淳之介らが編集委員となった小学館の『昭和文学全集』シリーズに筒井の作品が選ばれることが決まり、新一には声がかからなかったときだった。筒井のパーティーの二次会で、終始不機嫌に酒を飲んでいた新一は、有名人のおもしろい発言を集めた筒井の「諸家寸話」(「野性時代」昭和六十年五月号初出、『原始人』昭和六十二年九月刊所収)に言及し、筒井の妻もいる前でとうとうを口にしてしまった。
「勝手に書きやがって……、人のことを書いて原稿料稼ぎやがって……」
筒井が「諸家寸話」で紹介したのは、二人の間で交わされた次のようなやりとりだった。
貫禄
おれ「(星新一が原稿料の話ばかりするので)大作家ともあろうものが、あまり金の話をしてはいけません」
星新一「大作家だからこそ、平気で金の話をできるんです」
新一の放言は筒井を刺激し、随筆や小説を含め多くの筒井作品に昇華されていた。発想の泉、とはそういう意味だ。「諸家寸話」以前にもいろいろな雑誌で新一のエピソードは書いてきた。筒井が三度の落選を経験した直木賞を揶揄した『大いなる助走』にも、その言動からみていかにも新一とおぼしきSF作家が登場し、銀座の文壇バーで編集者相手に暴れる場面があるが、それとて新一は重々承知であり、筒井の描く星新一像は読者の想像力を刺激し、新一もまたそれでよしとしていた。
だがそれも自分が前を走っていてこそであった。
ショートショート一〇〇一編達成に対しては、結果的に、なんら文学的な評価を得られなかった。記録としては残ったが、それだけだった。もはや賞を与えることのほうが失礼にあたると考えたのか、生前の新一に対しては、日本SF作家クラブさえも授与しなかった。昭和五十九年に北海道で開催された日本SF大会「エゾコン2」で名誉星雲賞を授与するという案が伊藤典夫から持ちかけられたが、「なかったことにしてくれ」と新一側から辞退している。これまで自分を軽視し続けたSFの若い世代に対する静かな講義だったのだろうか。』
(文庫版下巻・P345〜350)
「文壇的権威」を与えられなかったからこそ、『「おもしろいか」「売れるか」』という観点からの自身の優位性に「本質的な価値」を見出すというのは、あまりにもわかりやすい「観念的自己回復」である。あるいは、でしかない。本当に星新一は、「人間の心」について「無知」であり「幼稚」であったと言えるだろう。
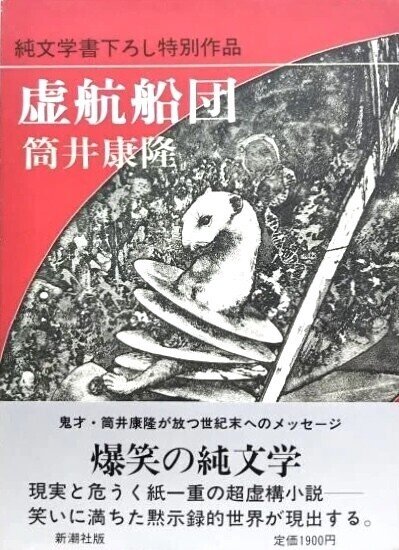
筒井康隆に対する感情も、「(おもしろさと売れ行きにおいて)格下の後輩に先を越された」という、単純な「妬み」でしかない。とてもわかりやすい。わかりやすすぎる。これが、あの「クールな星新一」かと、信じたくない気分になるが、しかし「人間」とは所詮、こんなものなのだ。
引用文(10)に、小松左京や筒井康隆から、星が『「天皇」「殿さま」といって守り立て』られていたとあるが、言うまでもなく、「天皇」は「神さま(現人神)」ではなく、日本の「殿さま」は「王権神授」された存在でもない。つまり、我々と同じ「人間」でしかないのだ。
むしろ、多くのSFファンが、星を「神さま」として「偶像」視していたからこそ『もはや賞を与えることのほうが失礼にあたる』と「妥当」に考えたのであろう。「神さまを人間が表彰するなんて、思い違いも甚だしい」からだ。一一だが、星新一は「平均的な人間」だったから、当たり前に「地位や名誉」や「ほめ言葉」が欲しかった。
そうした心情に、遅まきながら気づいた伊藤典夫が『名誉星雲賞を授与するという案』を星に提示するも、時すでに遅しで、星の傷ついた自尊心は膿み崩れており、「本心を隠し、ニッコリ笑って、お気遣いありがとう、と賞を受ける」なんていう「大人の対応」など、もはやできなくなっていたのである。
(12)『 吉行から「星さんを推薦したい」という連絡を受けていた直木賞の件も、その後なんら音沙汰がなかった。たんにリップサービスだったのかもしれないが、ほのめかされただけ、なおさらこれまで蓋をしていた感情が頭をもたげ、胸底に屈託が張り付いた。一〇〇一編後、映画三昧だった晴れやかな日々は半年も続かず、銀座で吉行や編集者たちに会えば、酒の勢いを借りて愚痴をこぼさずにはおれなかった。
「なんでぼくには直木賞くれなかったんだろうなあ」
賞のことなどとうの昔に乗り越えていると思っていた彼らには、返す言葉もなかった。賞よりも本が売れるほうがいいと公言しながらも、それはまぎれもなく、新一が編集者たちに不満を抱いていることの証でもあった。さんざん自分をおおだてて酷使しておきながら、どこかでショートショートを軽んじている彼らへの抗議のようでもあった。
筒井は、パーティーの二次会でのことを思い出すと今もかなしい、といった。
「屈託は……、ぼくにもあります。腹の立つことを思い出すと眠れない。それはひどかったです。芋蔓式につながって頭に浮かんでくる。星さんの場合、若いころの苦労がありますから、そういうことも全部つながって、夢でも形を変えで出てくる。夢と現実がつながって、目がさめて、また眠れない。よくわかるんだけど、すごくよくわかるんだけど、……たまらんですねぇ」』
(文庫版下巻・P353〜354)

(吉行淳之介)
酒を飲んで「クダを巻く」「泣き言を言う」。なんとも情けない姿だが、これこそが「純文学的人間」であり、中でも星新一の嫌った「私小説」的な人間の姿であったというのは、なんとも皮肉なことである。
ついでに、筒井康隆についても書いておこう。

筒井康隆と言えば「毒のある小説」で売り出した作家である。したがって、昔の私は、筒井の場合も、肯定的に「戦闘的な人」「強い人」「反権威の人」だと思っていた。
だが、私は昔、創価学会員だったので、筒井が創価学会を揶揄った「堕地獄仏法」や「末世法華経」は、そのノリが予想されて読む気にもならず、ただ不愉快な気分にさせられただけだった。
しかしまた、創価学会を辞め、逆に創価学会批判者となった今でも、筒井のこれらの作品を読んでいないのは、これらが所詮は「本格的な批判」ではなく、小説家という優位に立った「揶揄的批判」の域を出るものではないと思うからである。
根が真面目な私は、喧嘩するのなら、批判するのなら、真正面から堂々と、という主義の持ち主なので、筒井の、自身の「人気(頭数)」を後ろ盾にした「揶揄的批判」には、共感しかねたのである。
で、そういうことがあったので、私は後年、直接、筒井康隆に噛みついた。面と向かって、噛みついたのである。
それは平成5年・1993年3月21日、東京池袋「メトロポリタンプラザ」で開催された、「瞠目 反・文学賞」公開選考会の会場においてであった。
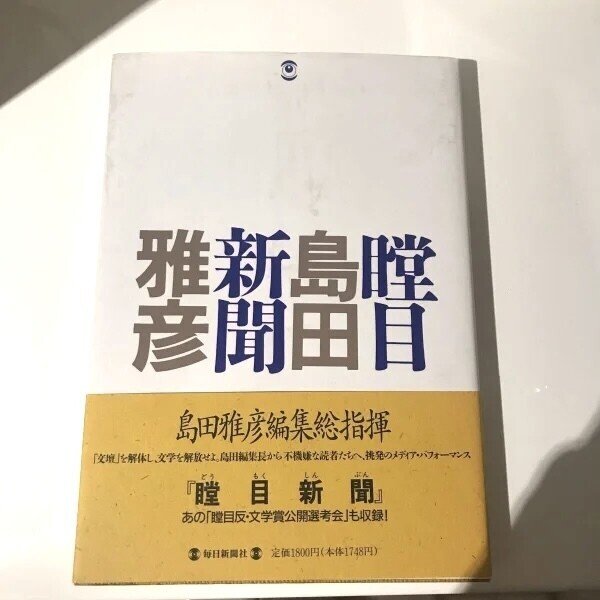
(帯に「あの「瞠目反・文学賞公開選考会」も収録!」とある)
この賞は、芥川賞などの既成の文学賞に不満を持っていた島田雅彦が、「毎日新聞」に連載していた「瞠目新聞」で提案し実現したもので、選考委員は、島田雅彦・筒井康隆・渡部直己の3人だった。
この3人により候補作である、奥泉光「ノヴァーリスの引用」、久間十義「海で三番目に強いもの」、小林恭二『瓶の中の旅愁――小説の特異点をめぐるマカロニ法師の巡礼記』、笹沢佐保『木枯し紋次郎』、中沢新一『森のバロック』、山城むつみ「文学のプログラム」、島田雅彦『彼岸先生』の7作が選ばれたが、『彼岸先生』は選考委員の作品ということで、島田が辞退。残りの6作が、公開選考会の会場で、3人の選考委員の討論(鼎談)に付され、最終的には奥泉光の「ノヴァーリスの引用」が受賞作となった。
当時(も今も)奥泉のファンであった私は、友人とともに会場へ駆けつけた。そして会場の前列2列目の中央の席に陣取った。最前列の席に座れなかったのは、最前列中央は「候補者席」として確保されていたからで、私はその真後ろに陣取ったのだ。
この選考会で、私に火をつけたのが筒井康隆だった。筒井は、笹沢左保の『木枯らし紋次郎』を候補作に推していたのだが、当日いきなり「先輩の作品を、あれこれ評価したりするのは不遜なことだから」と、候補作から取り下げてしまったのである。で、私が「事ここに及んで、いまさら何を言っているのか」と腹を立てた。
受賞作が決まる前、会場からの意見が求められたので、私は真っ先に手を挙げた。その時、周囲はまだ様子をうかがって手を挙げていなかったので、私が指名された。で、私は大筋、次のようなことを言った。
「アンチ文学賞という趣旨の賞であれば、ここで当たり前に優れた作品に賞を与えるのでは、所詮は既成の賞の真似事にしかならない。だから、アンチ文学賞と言うのなら、既成の文学賞こそが非文学的であるという批判を込めて、文学賞の代表である芥川賞と直木賞に、アンチ文学賞を贈呈してはどうか。それと、筒井委員が、笹沢左保の作品を、先輩の作品だからといって、いまさら候補作から下ろしたのは、納得できない。そう思うのなら、最初から候補に推すべきではなかった。これは、他の選考委員やここへ集まった人たちを愚弄する行為ではないのか。筒井選考委員に、そのあたりの説明を求めたい」
もちろん、場は一瞬、凍りついた。筒井の説明もむにゃむにゃ言っているだけの、誤魔化しの言い訳でしかならなかった。
そのせいもあり、私に煽られて、会場からは次々と手が上がり始め、言いたいことを言う人が続いたので、会場からの意見タイムは早々に打ち切られて、受賞作を決定する選考委員による投票に移り、めでたく奥泉の受賞が決まると、筒井はそそくさと逃げるようにして、会場を後にした。
私の感想としては「なんだ、意外にヘタレだったな」というものであった。
ちなみに、公開選考会が始まった際、前記のとおり、候補者席は会場の最前列に準備されていたが、司会進行役の島田雅彦が「せっかくですから、候補者に方にも壇上へ上がっていただきましょう。空いた席は詰めてもらっても結構ですよ」というようなことを言ったので、候補者が壇上に上がると、私は真ん前の「奥泉光様」と書いた紙の貼られていた席へと移動し、文字どおり、最前列中央に陣取った。連れの友人は、たしか隣の久間十義の席に移ったと記憶する。
選考会終了後にサイン会があればサインをもらおうと、私は奥泉作品の中で最も好きな『葦と百合』の単行本を持参していたのだが、どうやらサイン会はなさそうで、選考会が終了すると、選考委員と候補者たちはそのまま舞台の袖へと退場しようとしたので、それまでに何度かファンレターを送っており、会場へも行くと伝えておいた私は、舞台を去ろうとしていた奥泉を呼び止め、名乗った上で、山口二矢ばりに壇上に駆け上がって、無事、奥泉からサインをもらうことができた。
ついでに、座席に貼り付けてあった「奥泉光様」の紙も、記念に剥がして持ち帰り、今もそのサイン本に挟んである。
一一要は、私はそこまでやる人間なので、筒井康隆の「文章上だけの強さ」を、心から見下すことになったのである。
そして、そうした筒井康隆の「世間並みのヘタレぶり」と「権威者へのソツのないゴマスリぶり」を、本書でも再確認できた。だから筒井が、あの選考会のことを、何度でも夢を見てくれていたら「ざまあみろ」なのにと、そう思わずにはいられなかったのだ。
(13)『「星新一」という筆名も、個性のないモノクロームな登場人物たちも、「深く考へる事」や解決できそうにない堂々巡りの問いを遠ざけるための堰だったのだろう。理不尽な死や人間のむき出しの感情に苛まれ、なんとか脱出したいとあがいて来たのに、なぜ再び小説の世界でわざわざ人の感情にぎりぎりと切り込みたいと望むだろうか。過去を思い起こさせる引き金を引くまでもない。処女単行本『生命のふしぎ』には、科学的事実を常に意識におくことができれば、生々しい現実に捕らわれることなくもっと広い時間と空間に自らを解き放ち、死からも自由になれるという新一自身の死生観が現れていた。生死に関わる困難な問いも、科学的、合理的に解き明かすことのできるところまではとことん突き詰め、それ以上は架空の物語に託す。科学的思考と物語は、新一の心の救いであったはずだ。』
(文庫版下巻・P397〜398)
結局のところ、星新一にとっての「SF的に科学的で無機質な世界」というのは「ドロドロとした人間世界」からの逃避だったと言い切っていいだろう。
星新一も筒井康隆も「ブラックな批評性」を持っているように見えたが、それは「攻撃」的なものではなく、その本質は「ヘタレ」の「過剰防衛」によるものだったと考えた方が、事実に即しているのではないだろうか。
無論、作家本人が、現実と格闘できない逃避的な「ヘタレ」であろうと、その作品の「ブラックな批評性」が「ヘタレの過剰防衛」に出たものであろうと、作品は、作品さえ面白ければ、それでいいし、そのように作品自体は高く評価されるべきである。親が出来損ないであろうと、子がその責任を負う必要はない。「親の因果が子に報いる」ような評価の仕方は、間違いなのである。
(14)『 どうしてあの人はこうなのかしら……。
香代子は、新一のショートショートを読み返すたびにそう思う。人がみんないなくなる。世界が滅んでしまう。静寂が訪れる。すると、機械がカタコトと動き出す。そんな物語ばかり。悲観的で、絶望的で、厭世的で、せつなくて、かなしくて。
書斎に入るとこもりきりで、原稿が書けずに苦しんでいる姿は家族にさえ見せたことがなかったが、香代子は今、こう思う。
あの人はきっと、目に涙をいっぱいためながら書いていたにちがいないと。
人を信用しない人だった。編集者ばかりではない。秘書はいない。税理士もいない。育児に追われて家政婦を雇いたいと相談したときも、他人を家に上あげることを嫌い、強く反発された。女性に対してはとくに厳しかった。女だからといって甘えるなとよくいった。泣かせた女性編集者もいたはずだ。親戚でも遠い関係となると警戒した。家で会社や親のことをほとんど話さなかったのも、妻にいえばその母親に伝わり、そこからまた誰かに伝わると思ったからなのだろう。
信じられるのは自分ひとり、だった。
あんなに人が信じられなくて、どれほど苦しかっただろう。』
(文庫版下巻・P409〜410)
同情的に言えば、香代子夫人の言うとおりであろう。
結局、星新一という人は「人としては、凡庸に、弱い人」だったのである。
私を含め、多くのSFファンが抱いていた「超然とした人」という印象や、「SF界の天皇」あるいは「殿さま」といった「圧倒的強さ」を感じさせる評価も、所詮は、本人の演技と、周囲の「ヨイショ」によってでっちあげられた「幻想」でしかなかった。
無論、前述の『世界SF会議』もそうだが、当節、作家というのも(「文士」ではなく)「タレント」みたいなもので、「実質」ではなく「夢=幻想」を売っているようなものなのだから、多少の「大物演出」も悪くはないと思う。
しかし、大根役者では困るのだ。夢を売るのであれば、例えば「高倉健」のように、死ぬまで、そのイメージを守り抜いて欲しかったし、そうあるべきなのだ。「大物」演技も、プロの役者としてやるのであれば、だ。
しかし、それが貫けないのであれば、身の程知らずの「先生扱い」などを求めず、「普通の人」として、ただ「優れた作品」か「喜ばれる作品」かのいずれか、あるいは両方を淡々と書いて、「小説製造業者」として生きればいいだけなのだ。
そうしていれば、「先生扱いされていない」「賞がもらえない」「心から尊敬されていない」などという欲張った望みのゆえに、餓鬼地獄の苦しみを味わうことにならなくても済むのである。
無論「欲をかかない」生き方というのも、簡単なことではない。
だが、ある程度それを目指すというのも、結局は、自分自身の幸せのためであり、他の誰のためでもないのである。
しかし、「人としての幸せとは何か」「人間とはどういう業を抱えた生き物なのか」といった「純文学(あるいは、哲学的)」的な問題から逃避して、自分とは縁遠い「宇宙」だの「未来」だのについてのご高説を垂れ、人からチヤホヤされることで満足しているだけの人には、それも決して到達できる境地ではなかった。
そして、この残酷な事実を、星新一という「日本SF界の象徴天皇」は示してくれた。
しかし、その貴重な犠牲に学んだ者が、どれほどいるのかというと、かなり心もとないというのが「現在のSF界の実情」であり、変わらぬ「人間の現実」なのであろう。

(2022年2月23日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
