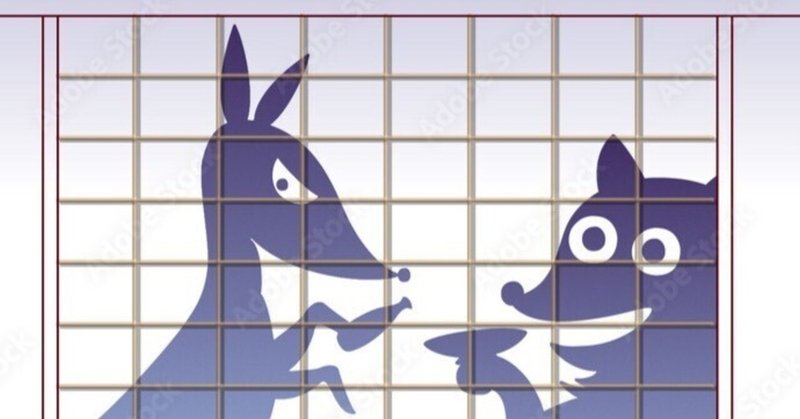
筒井康隆・ 蓮實重彦 『笑犬楼 vs.偽伯爵』 : 狐と狸の化かし合い
書評:筒井康隆・蓮實重彦『笑犬楼vs.偽伯爵』(新潮社)
読んだことのある人なら、両者がともに「クセのある書き手」だということくらいは承知していよう。彼らのファンというのは、彼らの「力量」を認めるだけではなく、その「クセのある個性」が好きだ、という人たちが多いはずだ。
私自身はそういった意味での「ファン」ではないけれども、彼らの「力量」は認めているし、それなりにその存在を気にかけてはいる。だからこそ、この「クセのある書き手同士の初対決」を読むことにもしたのだ。

先に、筒井康隆と蓮實重彦を、「私なりに」紹介しておこう。
「Wikipedia」などには書かれていない、しかし、多くに人と共有できるであろう「評価」だ。
まず、筒井康隆だが、彼はSF作家として出発した人だが、それにはとどまらず、ポストモダンな実験的小説を書いて、数多くの文学賞を受賞し、「SF作家」の枠にとどまらない「文学者」として、高く評価されるようになった。
私は、筒井康隆を、たぶん20冊以上は読んでいるはずで、それは初期中期の「SF作家」時代の短編集や長編、それから、前述のポストモダン的な実験的長編小説である。
「SF作家」時代の筒井康隆の特徴は、その「毒」にあると言えよう。
「スラップスティック(ドタバタ喜劇)」とか「ジャズ」といった、彼の「好み」に傾いた作品も数多くあるが、私はそのあたりには興味がなかったので読んではいない。できるかぎり「当たり前の」SF作品を読もうとしたわけだが、道具立てがどうであろうと、筒井康隆の作品に共通するのはその「毒(攻撃的批評性)」であり、それに由来する「ブラックな笑い」であったと言えるだろう。
しかし、ポストモダンな実験的小説に傾いた中期の筒井康隆からは、そうしたわかりやすい「毒」は薄れて、「文学」というものの形式的限界に挑むような作品が増えたと言えるだろう。
心理学的な知見を導入して描いた一種の幻想小説であるとか、登場人物が自身を登場人物だと自覚している「メタフィクション」だとか、作中世界から「文字がひとつづつ消えていき、それに対応する言葉と物事が消えていく世界」を描いた作品、といったようなものだ。
この対談でも、言及されている、長編『虚構船団』は、「狂った文房具」たちによる、シュールレアリスティックはSF小説である。

で、私は、この時期の作品がかなり好きだった。「メタフィクション」という言葉を知らないうちから、「メタフィクション」形式の小説に惹かれ、例えば、中井英夫の『虚無への供物』、竹本健治の『匣の中の失楽』、都筑道夫の『怪奇小説という題名の怪奇小説』といった作品に惚れ込んでいた。
あとで考えると、私のこうした嗜好は、幼い頃、香川県出身の父が、寝物語として私に「狸の化かし話」をしてくれたからだろうと思う。
旅人が、山中で道を失い、途方に暮れて真っ暗な山道を歩いていると、突然、煌々と明かりの灯された立派な御殿に行会い、やれ助かったと一夜の宿を求めたところ、中からは美女の主人が出てきて、大変な歓待ぶりで、飲めや歌えの夢のような一夜となった。だが、翌朝、寒さに目覚めてみると、旅人は川べりに泥だらけになって寝転がっていた。彼の前には、葉っぱの上に乗せられた泥団子のなどが並んでいた。彼は、狸に化かされていたのだ。一一と、そういったパターンのお話。
つまり、「作品(虚構)世界」の中に「もう一つの別の(虚構)世界」があり、物語が「入れ子構造」になっている「額縁物語」。あるいは「メタフィクション」と言われるようなものを、幼い頃から聞かされ、私はその不思議な世界に魅了されて育ったのだ。
これは、例えば、芥川龍之介「杜子春」などのように、中国の昔話にはよくあるパターンで、有名な「胡蝶の夢」なども同じパターンの傑作だと言えるだろう。
そして筒井康隆中期のポストモダン的な実験小説もまた、小説の物語世界の「虚構性」を強調する作りとなっており、そこが私の「好み」に合致したのだ。
しかしながら、その一方、初期の筒井康隆は、その「毒」性を持って、「堕地獄仏法」「末世法華経」「堕地獄日記」といった作品で、「創価学会」を嘲笑していた。
だから、まだ創価学会員だった若い頃の私は、そうした作品の存在こそ知ってはいたものの、不愉快になるのが嫌で、そうしたいくつかの作品は避けていたのだが、だんだんとその他の筒井作品を読み、文学全般、あるいはそれ以外のいろんな本を読み、さらに自身で批評的な文章を書いて、自己の見識に自信を持つようになると、逆に筒井康隆に対して、徐々に攻撃的なスタンスを採るようになっていった。「そこまで言うのなら、貴方がどれほどの人間なのか、見せてもらおうじゃないか」という気持ちが強くなっていき、やがて、島田雅彦が主催した「瞠目反・文学賞」の公開選考会という千載一遇のチャンスを得て、直接、筒井康隆に噛みつくことになったのである。
一一このあたりは、説明すると長くなるので、下の(最相葉月著『星新一 一〇〇一話をつくった人』の)レビューの最後のあたりを、お読みいただければ幸いである。
ともあれ、そんなわけで、私は筒井康隆の作品は、けっこう好きで、その代表作とは例えば、谷崎潤一郎賞を受賞した『夢の木坂分岐点』や、泉鏡花賞受賞作の『虚人たち』などの「メタフィクション」的な作品なのだが、筒井康隆の人柄については、あまり好きではない。
その「毒」が嫌いなのではなく、作品に表れたほどの「毒」を本人が持っておらず、「実物は、意外にヘタレだな」と評価した点において、そのへんが物足りなくて、嫌いなのだ。
大家ぶって和服なんか着て見せても、所詮は三文役者の「文弱の徒」でしかない奴。一一と、そういう評価である。
さて、次は、蓮實重彦だが、蓮實の著作は数冊しか読んでいないはずだが、その数冊の批評書だけでも、蓮實が批評家として只者ではないというのは容易にうかがえ、その力量には感服していた。例えば、すぐに思い浮かぶところでは、最初に読んだ『表層批評宣言』とか、柄谷行人、浅田彰などとの座談『近代日本の批評』などがある。
ただ、蓮實重彦は、柄谷行人や浅田彰とは違って、しばしば「内心で人を小馬鹿にしているような、独特の嫌味ったらしさ」があって、むしろそこが彼の持ち味でもあれば、その「クセ」こそが、「蓮實節」であり面白くもあった。
そしてそのことは、本書の中でも、自分から「年上の文学者にからむという、次男坊的な悪癖があった」という趣旨のことを語っているとおりである。
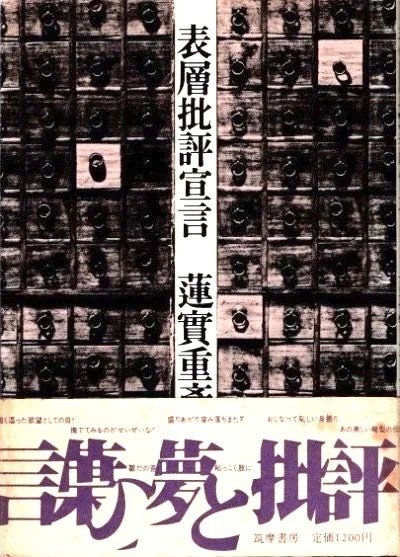
ところが、そんな「上のやつにからむ」というスタンス、言うなれば「反体制」的とも言えた蓮實が、ある時期からうまく立ち回って、「東大総長」になりおおせてしまった。
言うまでもなく、その椅子に座るためには、「上に逆らう」ようなことをしていては到底かなわないので、要は、それまでのスタンスを変えて、要領よく「エライ人に取り入った」ということだ。
だから、私は、いや私だけではないが、蓮實の「反権威」を信じていた多くのファンは、彼に愛想を尽かしたのである。
したがって、今の蓮實ファンというのは、「権威好き」であるか「権威に鈍感なミーハー」かのいずれかだと言っても、大筋で間違いではないはずだ。たぶん、今の蓮實ファンの9割は「映画オタク」であり、その視点からしか蓮實を見ていないのではないだろうか。
(※ 下の「○ ○ ○」記号で上下を括った一節は、私の記憶違いによる誤記述と判明しましたので、記して訂正し、蓮實重彦氏ほか各位にお詫びいたします。
なお、所謂「東大駒場騒動」あるいは「中沢新一事件」の発生は、1987年から1988年にかけてのものであり、一方、蓮實重彦氏が東大総長を務めたのは、1997年から2001年のことです。/2023年8月24日記)
○ ○ ○
また、蓮實が東大総長時代に、中沢新一を教授に迎えようとして教授会の反発により、それを果たせなかった、というような事件もあった(東大駒場騒動)。
その当時は、私も「ポストモダン思想のイケメン人気評論家を、東大教授のお歴々が、そんな色物など認められんと、反発したのだろう」と、どちらかといえば中沢の方に同情的だったのだが、その後、私自身が「宗教批判者」の立場から見て(読んで)、中沢の著作は「うさん臭い」と評価するようになり、そこから遡って、中沢を東大に迎えようとした蓮實の「批評眼」に疑いを持つようになった。
結果としては、教授会の判断の方が正しかったと評価するようになり、「蓮實はあの時、中沢を純粋に高く評価していたのではなく、何らかの学内政治的な思惑で、中沢を引き入れようとしたのではないか」と疑うようになったのである。
○ ○ ○
あと、私が蓮實重彦に教えられた言葉が、「凡庸」である。
蓮實が使っているとおりの使い方をしているかどうかはわからないが、この言葉の持つ「上から目線の嫌味ったらしさ」が面白いと、「駄作」よりもむしろ「存在価値のないもの」を評する時に、この「凡庸」を使ったりするようになった。「凡庸な作品」「凡庸な作家」といった具合である。
そんなわけで、私は、筒井康隆と蓮實重彦の両名について、その「力量」は認めるものの、その「人柄」については評価しないし、「好きではない」ということになった。
ただし、前述のとおり、筒井康隆は「ヘタレ」である分、まだ「可愛気」があるとも言え、その意味では憎みきれないところもあるから「狸」的で、一方、蓮實の方は、そういう「可愛気」のまったくない「ずる賢さ」において「狐」的だと考える。
したがって、本書は「タヌキ対キツネ」の「化かし合い」であり、言い換えれば「ゴジラ対ガメラ」、あるいは「フレディvsジェイソン」(「フレディ対フレディ」か?)のドリームマッチみたいなものでもあるから、これを読まないわけにはいかなかったのだ。

○ ○ ○
さて、本書に内容は、次のとおりである。
(1)筒井康隆による「まえがき」
(2)「大江健三郎」についての、両者の対談(雑誌掲載を収録)
(3)筒井による、蓮實の小説『公爵夫人』についての書評(同上)
(4)蓮實による、筒井の初期長編『時をかける少女』論(書き下ろし)
(5)両者の往復書簡(雑誌連載を収録)
(6)蓮實による「あとがき」
本書を通読してわかるのは、蓮實の方から、事前に若干の接触はあったものの、結局は筒井康隆の方から、おそるおそる蓮實に接近したところ、意外にも蓮實が下手に出て、筒井への「敬意と賞賛」を惜しまなかったので、結果として両者が「意気投合した」かのような、(2)の「対談」であり、(5)の「往復書簡」になった、ということ経緯だ。
しかし、本書のために書き下ろされた(1)を見ると、筒井は、蓮實のそうした態度を、必ずしも真に受けてはいないようだし、一種「感動的」と呼んでいいような部分も無いではない(5)の対談を受けてのものとしては、蓮實による(6)の「あとがき」は、(5)のそれを真に受けて良いものかと疑わせる「含み」が持たされている。
もちろん、本書の読者の多くは、「二人は、齢を重ねて人間も練れ、無用な角もとれて、大成した者どおしの共感に満ちた、真心の語らいをしている。特に、ともに、最愛の息子に先立たれるという不幸を経験しているだけに、そうした思うに任せない人生を生きてきた者同士の、思いやり溢れる往復書簡になっている」と、大筋こんな感じで、(6)の対談、あるいは本書そのものを、「好意的」かつ「ナイーブ」に、捉えたのではないだろうか。
だが、前記のとおり、その(1)「まえがき」や(6)「あとがき」の「微妙なニュアンス」からして、二人が「見せかけどおり」のことを考えて、それを語っていたとは、私は思わない。そうした理解は、あまりにも「ナイーブ」すぎて、きわめて「非文学的」であり、「凡庸」なのである。
齢を重ね、人生経験を積めば、人間が「丸くなる」などというのは、薄っぺらな「紋切り型の思考」に過ぎず、その意味で「非文学」的なものだ。人間とは、そんな単純なものではない。
たしかに、齢を重ね、経験を積めば、人間は「世渡り的に賢く」はなるだろう。つまり「若さゆえの過ち」を犯さない「慎重さ」を身につけるのだが、しかしこれは「人間が練れた(良い意味で成熟した)」とか「丸くなった」ということではない。
そうではなく、「したたかに利口になった」だけであり、不用意に「むき出しにしていた牙」を隠すようになった、ということでしかない。牙が、落ちたのでもなければ丸くなったのでもない。単に、見せつけなくなっただけ、なのだ。
その意味では、賢くも「狡くなった」ということの方が大きいのである。
認知症などの脳機能障害にでもならないかぎり、人間の性格とは、そう簡単に、自動的に、変わってしまうようなものではないし、まして、常に自意識に自覚的である「文学者」であるならば、それは尚更なのだ。そうでなければ、三流なのである。
彼らは、ただ「見せかけ」だけは、馬鹿にでも理解しやすい「好々爺」を演じたりするけれども、その「内面」は、そう単純なものではない。経験を積んだ年寄りを、甘くみてはいけない、ということである。
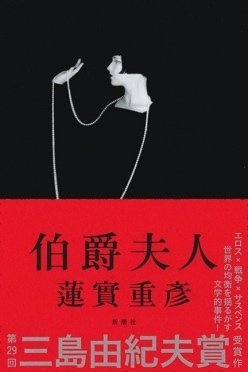
さて、まずは筒井の「まえがき」である。
『 蓮實重彥との初対面は彼が三島由紀夫賞を受賞した時の授賞式と直後のパーティに於てである。すでに彼の受賞作『伯爵夫人』の解説を書かされていたし、評判になった選考会直後の彼の不機嫌な受賞会見をテレビで見てもいたから、一筋縄でいかない人物であることは承知していた。案の定だ。控室で紹介された時には、受賞スピーチで貴方の気に食わぬことを言うかもしれないと宣告され、その通り『伯爵婦人』の解説での見当違いを指摘されてしまったのであった。』
(P5「まえがき」より)
このように、蓮實重彦は、クセのある厄介な人物であり、筒井康隆が警戒しながらも「敵に回してはいけない人物だ」と考えていたであろうことは、容易に推測できるところだろう(そう推測できないのは「読めない読者」である)。
『 恨みというのは昔『虚構船団』を書いた時に蓮實さんが誰かとの対話で口にした「二ページ読んで読むのをやめた」という発言のことだ。「おやおや」と思い、それ以来「おれの作品が嫌いなんだな」と思っていたのだが、ある時対談の相手に指名されてまた「おやおや」と思い「まんざら嫌いではないのかも」と思いながらも、あの発言にこだわってお断りしたのだった。(※ 本書所収の「対談」では)まずはそんな昔話をしてから、例の不機嫌会見を見てご本人に興味を持ち、さらに『伯爵夫人』の書評を頼まれたのを機会にご本人の著作を読んでますます興味を持ったことなどを話した。』(P6、前同)
この「おやおや」が「(読者に対して)余裕がある振りをして見せているだけ」だというのも、容易に読み取れよう。実際には、蓮實に「二ページ読んで読むのをやめた」と言われた際、筒井は「このクソ野郎、絶対に許さん!」と真っ赤になって激怒したと、このくらい誰にでも読み取れる程度の「三文芝居」である。
つぎは、蓮實による「あとがき」。
この「あとがき」は、あとがき本文に「P.P.S.」さらに「P.P.P.S.」が付属する形式になっている。
『 そのほとんどが洋書であるぶ厚く重そうな書物ばかりが並んでいる仕事机の斜め右手にあたる書架のひとすみに、薄いベージュ色のカヴァーがかかった書物が一冊置かれていながら、しばらくの間、あえてそれを目にすることもなく時が過ぎて行きました。そのほとんどが、『ジョン・フォード論』やその他の映画論の執筆のための横文字の参考文献だったからです。
ところが、ついせんだって、その匿名めいた厚い書物にふと手を伸ばし、謎めいた重さを受けとめながらカヴァーを取り払ってみると、何と、それは、筒井康隆コレクションⅦ『朝のガスパール』(出版芸術社 2017)でありました! しかも、その見開きには、大胆かつ繊細な筆遣いの著者の署名が堂々と墨で書き込まれており、虹色の落款まで押されている。それを目にした瞬間、あっけにとられたのはいうまでもありません。いったい、いつ、どんな機会に、この書物が、拙宅の、しかもごく身近な書架に鎮座することになったのか。
もちろん、それを寄贈して頂いた記憶などまったくありません。また、みずから購入したとはどうも思えない。過去半世紀ほど、高級日刊紙の購読をあえて自粛してきたわたくしは、ときおり、地方のホテルに滞在していた折りなど、朝日新聞連載中に大いに盛りあがっていた『朝のガスパール』をちらりと拝読させていただいたりはしたものの、その後、その書物を意図的に手にしたことなどなかったはずなのです。
では、いったいなぜ、筒井康隆コレクション版のその分厚い一冊が、いつとも知れぬ一時期から、目の前の書架に寡黙に置かれていたりしたのか。これは、まったくもって謎というほかない事態なのであります。』
(P167~168、「あとがき」本文より)
『P.P.S.さらに付言させていただくなら、問題のベージュ色のカヴァーのかかった筒井康隆コレクションⅦ『朝のガスパール』に、漠たる記憶がよみがり始めております。とても確かなこととはいいかねるのですが、『伯爵夫人』が刊行されてからしばらくして、三島由紀夫のさる書物の初版本、あるいはせめてその当時の版を目にしたくなり一一読みたくて、ではありません一一、唐突にタクシーを飛ばして神田の古本屋街にまで足をのばしたことがありました。しかし、思っている版がなかなか見あたらなかったことへの腹いせに、途方もない数の新刊書を無差別に買いあさり、ふて腐れて帰宅するしかありませんでした。そのときの無差別買いの一冊が『朝のガスパール』だったことが、どうやら事実なのかもしれぬと思い始めているのですが、それとて、確言しうる事実だとはとてもいいかねます。そもそも、筒井さんの署名と落款に彩られた一冊の手にとって、嬉々としてレジに走って行く自分の姿を想像することなど不可能というに近いことですから、とても確かなこととはいえません。どうやら、わたくしは、「確かなこと」というものにまったく無頓着なまま、後期高齢者の域に達してしまったのかもしれません。
P.P.P.S.さる九月には米寿を迎えられたはずの敬愛する大文豪の筒井康隆さま。お祝いなどという語彙にはとうていおさまりかねる複雑きわまりない心より賛辞を贈らせていただきます。』(P172〜173、前同)
筒井の『朝のガスパール』なんぞ、『(※ 買おうと思って出かけた、三島由紀夫の本の)思っている版がなかなか見あたらなかったことへの腹いせに、途方もない数の新刊書を無差別に買いあさ』った際、誤まって購入したとしか考えられないような、くだらない本だ。その時しか考えられないとは言え、自分がそんなものを買ったなんて、今でも信じられない。買ったとすれば、自分はもう、かなりボケてきているのだろう。一一と、これはそういう強烈な「からかい」なのである。
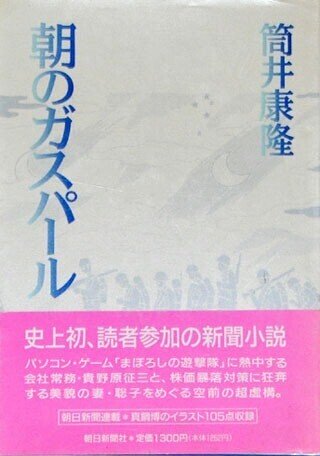
この程度のことも読み取れないで、本書を褒めているような、例えば「Amazonカスタマーレビュー」のレビュアーなどは、ほとんど文盲に等しく、両者のファンを名乗る資格などないと断じても良い。
そして、こんな「頭の悪い読者=耳ざわりの良い話しか受けつけないようなヌルい読者」ばかりが増えたからこそ、おふたりも「好々爺ぶりっ子」しなければならなかったということなのだ。一一そうでしょう、お二方?
『蓮實 大江(※ 健三郎)さんが『筒井康隆全集』の解説の中で「筒井康隆には読者への悪意がある。そこがいいのだ」と書いておられました。その通りだと共感するのですが、どうも最近その種の文学的な悪意が希薄になっているのではないでしょうか。何かしら甘美で風俗的に身近なものを文学に求めるという傾向が村上春樹いらい顕著に認められ、これは非常にいかがわしく、困ったことだと思っております。言葉そのものには惹かれても、書かれていることそれ自体は不快きわまりないということは、古来、文学にはたくさんあるわけです。それを人目から遠ざけることが文学だと人々が思い始めた時代というのは、不幸な時代としか言えませんね。
筒井 昔はこういう時代ではなかった。
蓮実 ええ。少なくとも読者と作者、あるいは書かれているテクストと読む意識との関係は、そこに何らかの葛藤がなければ成立しない。ところが、葛藤がなく、すべてを快く受け入れられるような言葉ばかりが平和に並んでいるのが文学だと思われてしまっている。それは、文学のみならず、社会にとっても大問題だと思います。』(P37〜38)
(2023年2月7日)
(2023年8月23日・お詫びと訂正を追記)
○ ○ ○
○ ○ ○
