
蓮實重彦 『ゴダール革命』 : 〈主人持ち〉の批評
書評:蓮實重彦『ゴダール革命』(リュミエール叢書、ちくま学芸文庫〔増補決定版〕)
私が読んだのは「ちくま学芸文庫」版なのだが、単行本版(リュミエール叢書)についての、Amazonカスタマーレビューがとても参考になったので、両方を挙げておくことにした。
本書を一読して、まず思ったのは「ゴダールというと蓮實重彦」という印象が、映画の門外漢である私にはあったけれど、「ゴダールについて、意外に大した量は書いていないんだな」ということである。
本書を読むまでは、本書が「ゴダールについての長編評論」であり、タイトルからして、蓮實のゴダール論の「中核」をなす本だと思っていたのだが、実際には本書は、蓮實がゴダールについてこれまで書いてきた、いずれにしろ長くはない文章から、めぼしいものを集成したものに過ぎなかったのだ。
中身も、面白いと言えば面白いし、蓮實重彦らしい文章ではあるのだが、いかんせん短いし、その点で、いささか物足りない。
本書には、ゴダールがわからない私のような者を、力でねじ伏せるような迫力が感じられず、「なるほど、蓮實さんはそういう立場なんですね」といった感想を持たせるにとどまっているのである。
これまで、ゴダールの作品を14本観てきて、「これのどこが面白いんだろう? まあ、面白い部分もあるにはあるけれど、文句なしに面白いと言うほどではないし、まして、個性的ではあれ、ゴダールが特別優れた作家だという印象もないけどなあ」と、そんな感じだった私に、「ああ、そういうことだったのか! たしかに私は開きメクラだった…」と言わせるほどのものは、そこには無かった。端的に言って「やっぱり、趣味の違い。映画に求めるものの違いだったんですね」という感じだったのだ。
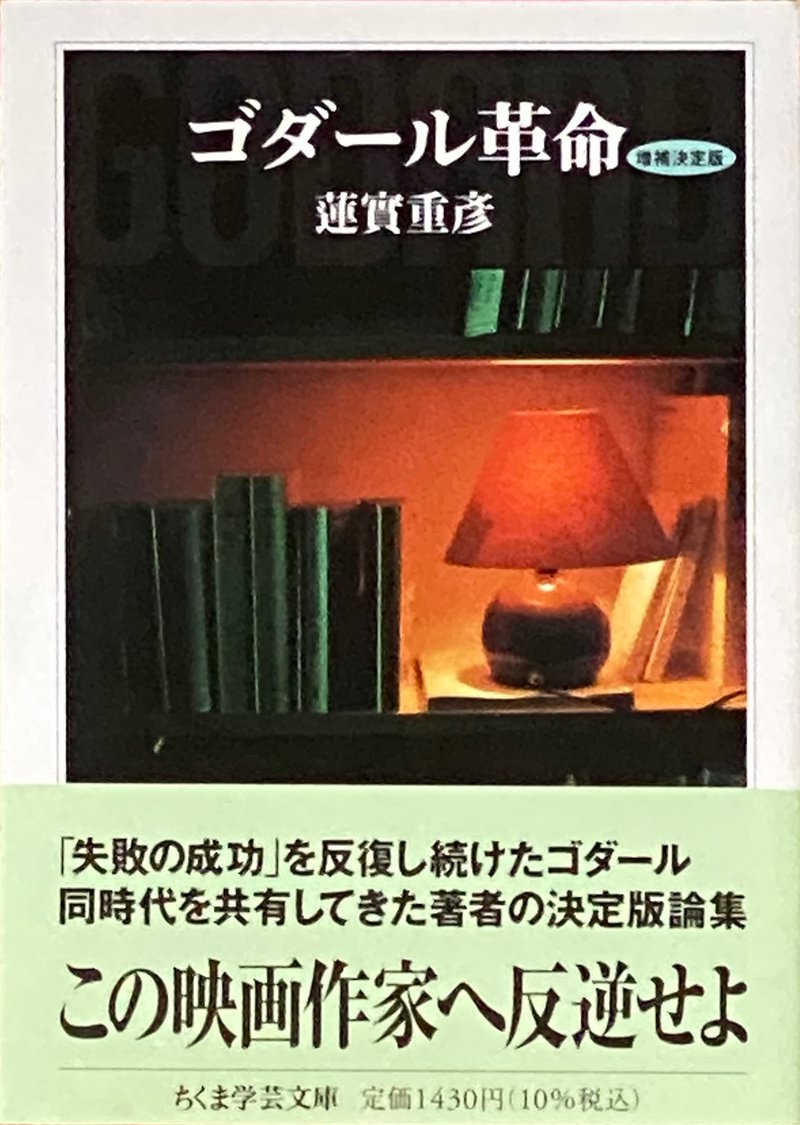
本書における「ゴダール論」の中心となるのは、前書きにあたる「プロローグ 時限爆弾としてのゴダール」の次に収められた、「破局的スローモーション」(初出・1985年)であろう。
この文章が書かれた時期というのは、ゴダールが「ジガ・ヴェルトフ集団」名義で、政治的な映画を撮っていた時期を終えて、再び商業映画界に復帰し10年余、再生ゴダールとして、
勝手に逃げろ/人生 Sauve Qui Peut (la vie) (1980年)
パッション Passion (1982年)
カルメンという名の女 Prénom Carmen (1983年)
ゴダールのマリア Je vous salue, Marie (1985年)
ゴダールの探偵 Détective (1985年)
アリア Aria 挿話「アルミード」Armide (1987年)
ゴダールのリア王 King Lear (1987年)
といった、「中期の代表作」とも呼べる作品をつぎつぎと発表していた、言うなれば充実期のゴダールを論じたものであり、私も『パッション』『カルメンという女』『ゴダールのマリア』『ゴダールの探偵』などは観ているから、前記「破局的スローモーション」での蓮實の議論には、一応のところ納得できる。「ああ、そういうふうに見ていたわけですね」という感じだ。
私個人としては「そういう見方」はしなかったし、するつもりもないけれど、人によってはそういう見方をして、それを面白いと感じることもあるだろうな、とは思ったのである。
で、「破局的スローモーション」の内容だが、例えば次のような部分に、ゴダールについての蓮實のスタンスがよく現れていると思う。
『 ところで、ゴダールは、いささかも個性的な作家ではない。「ゴダール現象」が「黒澤明現象」と異質の水準に位置しているのはそのためである。彼は、個人的な問題の解決のために映画を撮ったりはしない。自分の個性を際立たせるための技法を身につけていて、それを題材に応じて駆使することを、独創的だと思ってもいない。彼は、かつて独創的であろうとしたことはないし、こんごもそうあることはないだろう。「ゴダール現象」があくまでわれわれの問題だという意味もそこにある。われわれが映画を撮るのは、個性的であろうとする意志を放棄しえないからにほかならない。映画を撮る以上は、スピルバーグでさえ、個性的たらざるをえないのだ。『スワンの恋』のシュレンドルフを見よ、『アマデウス』のミロス・フォアマンを見よ。こうした作家たちの映画の退屈さは、彼らの個性や独創性が画面を彩っているからにほかならぬ。
ジャン=リュック・ゴダールは解決すべき問題を持たない。天才とは、きまってそうしたものなのだ。その周囲には、「ゴダール現象」というわれわれの問題しか存在しておらず、しかも彼はそこから徹底して自由である。もちろん、自由とは、傲岸さをいうのではない。恩寵の同義語であるところの優雅さこそが自由にほかならぬのだ。ゴダールは、雅やかな寵児である。それ故に、彼は歓ばしき知と戯れる特権を持つ。にもかかわらず、その振る舞いがときとして傲岸無礼なものに映り、傍若無人な映画的身振りとして人をいら立たせたり、それを独創性の名において許容するといった事態が起こるのは、われわれが「ゴダール現象」から逃れえずにいるからなのだ。そして、ゴダールその人が、われわれの問題にほかならぬ「ゴダール現象」を、われわれになり代わって 解決してくれるのではないかなどとつい、期待してしまう。だが、恩寵である優雅さ、あるいは優雅であるところの恩寵を期待しながら映画を見たりすることほど、怠惰な振る舞いもまたとあるまい。いずれにせよ、期待とは、誤った問題なのである。恩寵とは、優雅さとは、期待の地平に形成されたりはしないし、期待を充たすという機能などもともと持ってはいないのだ。「ゴダール現象」とは、解決されることをいささかも求めはしない問題である。より正確にいうなら、隠された部分が徐々に視界へと浮上したり、未知の領域へと視野をを誘ったりすることがなく、わたくしの、あなたの、あの人の、つまりはわれわれ全員の瞳におのれを万遍なくさらけ出した記号だというべきだろう。だから、それを問題と呼ぶのは語法の誤りだというに等しく、ほとんど問題ではありえないものこそが「ゴダール現象」なのである。われわれが 彼にその解決を依頼したり、自分の手で解決しようとしてはならないのは、そうした理由による。
にもかかわらず、「ゴダール現象」が問題としてわれわれの前に提供されているかにみえるところに、「ゴダール現象」の微妙な難解さが存している。問題は、問題と呼べないはずのものを問題だと勘違いさせ、その解決に専念することがゴダールにふさわしい振る舞いだと思わせてしまう何かが、そのまわりに絶えず交錯しあっているからだ。ゴダールが厄介な作家であるのはそのためであり、彼が難解な問題を提起するからでも、それを独創的に解決してみせるからでもないことは、いまや明らかだろう。』(P23〜25)

難しい話をしているわけではない。ただ、華麗なレトリックによって、即物的、むき出しに書くことを避けているだけだと言えるだろう。上の言葉に「補足注釈」を加えることで解説すると、次のようになる。
「 ところで、ゴダールは、いささかも個性的な作家ではない。「ゴダール現象」が「黒澤明現象」と異質の水準に位置しているのは、(※ ゴダールが、いわゆる「人間的な個性」の魅力で、観客を魅了しようとしているような、ありきたりな作家ではない)そのためである。彼は、個人的な問題の解決のために映画を撮ったりはしない。つまり、(※ 自分の問題意識から、何かを訴えようとか、何かを伝えようなどとは考えていない。)自分の個性を際立たせるための技法を身につけていて、それを題材に応じて駆使することを、独創的(※ であり、そこに価値があるの)だと思ってもいない。彼は、かつて独創的であろうとしたことはないし、こんごもそうあることはないだろう。(※ そもそも彼は、「個性」や「独創性」なんて、ケチなことにはまったく興味がないのだ。)「ゴダール現象」があくまでわれわれ(※ 受け手)の問題(※ であり、ゴダールの主体的な問題ではないの)だという意味もそこにある。われわれ(※ 凡人であり俗物、そして他の映画人)が映画を撮るのは、(※ いつだって)個性的であろうとする(※ 自己表現により承認欲求を満たしたいという)意志(※ つまり、強い意識的な欲望)を放棄しえないからにほかならない。映画を撮る以上は(※ 普通は)、(※あの、お客様に奉仕することしか考えていないような)スピルバーグでさえ、(※ やはり、自身を表現するという欲望を抑えられず、そのせいで否応なく)個性的たらざるをえないのだ。『スワンの恋』のシュレンドルフを見よ、『アマデウス』のミロス・フォアマンを見よ。こうした作家たちの映画の退屈さは、彼らの個性や独創性が(※ 「私の非凡な才能を見よ!」と、にぎにぎしく)画面を彩っているから(※ であり、その暑苦しい俗物性にウンザリさせられるから)にほかならぬ。
(※ しかしながら、例外的にも)ジャン=リュック・ゴダールは解決すべき問題を持たない。(※なぜなら彼は、もとから解放されている、自由な存在だからだ。)天才とは、きまってそうしたものなのだ。その周囲には、「ゴダール現象」というわれわれ(※ 俗物由来)の問題しか存在しておらず、しかも彼はそこから徹底して自由である。もちろん、自由とは、傲岸さをいうのではない。(※生まれながらに惠まれた存在としての貴人が、他人に何かを求めるような、物欲しさを持たないのと同じように、その俗物性からの自由とは)恩寵(※ であり、そ)の同義語であるところの優雅さ(※であり、そうした特権性)こそが自由にほかならぬ(※ ということな)のだ。(※ したがって)ゴダールは、雅やかな寵児である。(※ 神に選ばれて恩寵を賜った、特別な天才なのだ。いっそ、人間の「魂」などもたぬ「天使」と言っても良い。)それ故に、彼は歓ばしき知と戯れる特権を持つ。(※つまり、俗物=人間、としての重力に縛られることなく、彼は自由に非地上的な、特権的な知と、戯れ続けることが許されている。)にもかかわらず、その振る舞いがときとして傲岸無礼なものに映り、傍若無人な映画的身振りとして人をいら立たせたり、それを独創性の名において許容するといった事態が起こるのは、われわれが(※ 重力に縛られた俗物であり、にもかかわらず、ゴダールを同じ人間として理解しよう、彼を地上に引きずりおろそうとする)「ゴダール現象」(※ という俗物性の発露)から逃れえずにいるからなのだ。そして(※ 地上的に愚かなわれわれは)、ゴダールその人が、われわれの問題にほかならぬ「ゴダール現象」を、われわれになり代わって 解決してくれるのではないかなどとつい、期待してしまう。(※ なぜなら、「同じ人間なんだから」と考えるからだ。)だが、恩寵である優雅さ、あるいは優雅であるところの恩寵を期待しながら(※ 物欲しげに)映画を見たりすることほど、(※ 与えられることだけを期待する乞食のごとき)怠惰な振る舞いもまたとあるまい。いずれにせよ、期待とは、(※ 地上性であり、そんなものを持たない天上性に対するものとしては、明らかに)誤った問題(※ 意識)なのである。恩寵とは、優雅さとは、(※ 人間を満足させるための)期待の地平に形成されたりはしないし、期待を充たすという機能などもともと持ってはいないのだ。(※ それは、われわれとは関係なしに、独自に、自由にはたらくものなのだ。)「ゴダール現象」とは(※ 本当は)、解決されることをいささかも求めはしない(※ 何かを与えられることを必要とせず、何も欲しない、そんな)問題である。より正確にいうなら、隠された部分(※ 神秘の領域)が徐々に視界へと浮上したり、未知の領域(天上性)へと(※ 俗人の)視野を誘ったりすること(※そんなストリップのごとき、思わせぶりなところなど一切)がなく、わたくしの、あなたの、あの人の、つまりはわれわれ全員の瞳に(※ なんのこだわりもとらわれもなく、自由奔放に、自然に)おのれを万遍なくさらけ出した記号(※ それが、ゴダールであり、ゴダールという現象)だというべきだろう。だから、それを問題(※ つまり、誰かに対して与えられた問いででもあるかのように「問題」)と呼ぶのは語法の誤りだというに等しく、ほとんど問題ではありえないものこそが「ゴダール現象」なのである。(※ したがって)われわれが(※ 見当違いにも)彼にその解決を依頼したり、(※ 愚かにも、地上的な)自分の手で(※ 「ゴダール現象」という、われわれの側の問題を、勝手に)解決しようとしてはならないのは、そうした理由による。(※ つまり、そんなことは原理的に不可能なのだし、それをやれたつもりになったのだとしたら、それは必ず誤りでしかあり得ないのだ。)
にもかかわらず、(※ 本質的には、幻想であり誤認でしかない)「ゴダール現象」が問題としてわれわれの前に提供されているかにみえるところに、「ゴダール現象」の微妙な 難解さが存している。問題は、問題と呼べないはずのものを問題だと勘違いさせ、その解決に専念することがゴダールにふさわしい振る舞いだと思わせてしまう何かが、その(※ 人、ゴダールの)まわりに絶えず交錯しあっているからだ。ゴダールが厄介な作家であるのはそのためであり、彼が難解な問題を提起するからでも、それを独創的に解決してみせるからでもないことは、いまや明らかだろう。(彼は、何かのために、何かを求めて、何かをしようとしているのではない。ただ、恩寵による天命によって定められたところを、ただ、している、だけなのだ。)」
○ ○ ○
私は以前、蓮實の著書『ゴダール マネ フーコー 思考と感性とをめぐる断片的な考察』のレビュー「これは フィクションである。」において、蓮實にとっては、ゴダールは「神」であり、蓮實は、その神の存在と正当性を弁証するための「神学者」であると指摘した。
しかし、そこでも論じたとおり、ゴダールは「神」ではないし、蓮實も本気で、ゴダールを「神そのもの」だと思っているわけではない。あくまでもレトリックとしての「神のよう(に自由)な人」であり、その意味でゴダールは「稀有な才能の持ち主(天才的な、人間)」なのだから「彼を擁護しなければならない」と蓮實は考えて、ゴダールをあえて「神格化」して見せているにすぎないのだ。
だから、本書単行本版のAmazonカスタマーレビューにおいて、レビュアー「本という物」氏が、そのレビュー「何も、、、、」において、
『著者の映画に関する文章は、ただただ映画に仕えるために書かれたものなので、その点さえ見失わなければ難解なことはないでしょう。』
と言うのは、まったく正しい。
ここで言う『ただただ映画に仕えるために書かれた』というのは、蓮實重彦が、「映画」はもとより、「ゴダール」について書いた文章において、「映画」の、そして「ゴダール」の価値を弁証するための、(ためにする)「神学者」の立場をすすんで引き受けているという意味であり、要は、蓮實は「客観的な評価者」ではなく、「党派理論家(イデオローグ)」でしかない、ということなのだ。
だから、蓮實重彦は、ゴダールの魅力が「わからない人」に対して、それがわかるように説明することができない。
「わからない人」の地平に、いったん立ってしまえば、それはもう「好み」に規定された上での「能力」の問題でしかないから、そうした人を説得するというのは原理的に不可能だからで、例えて言うならば、「生まれついての盲人に、絵をイメージさせるのが不可能」だというのと同じことであり、言い換えれば「いわゆる健常者には、盲人が見ている繊細かつ豊かな世界が見えない」というのと同じことなのである。つまり、住んでいる世界が、そもそも違うということなのだ。
したがって、蓮實自身も「ゴダールがわからない人」を説得することなどできないというのは、よくわかっている。だから、説得しようとはせずに、「断言」することで、それがさも「自明な事実であるかのように」語るという戦略を採るのである。
だから「ゴダールがわからない人」の一人なのであろう、レビュアー「kppyz」氏が、そのレビュー「ゴダールの斜め読み」で、次のように書いていることも、おおよそ正しい。
『「何も書いてない」というのが、通読後の私の感想だ。文章量に比して、情報量が少ないのだ。
だいたい、このハスミという人は、「斜見」という字を当てるべきヒネクレ者で、「〜というのは間違いだ」「〜ではない」と、考えうる限りの堅実で常識的な意見をにべもなく切り捨てた後で、半分正しく半分デタラメな著者独自の意見を独断的に述べて読者に刷り込むという、優れてゴダール的な人物なのだ。
真正面からゴダールを論じたい人は別の文献を当たった方が良いだろう。』
蓮實が、「kppyz」氏の指摘するような「高圧的な決めつけ」によってゴダールを論じているに過ぎない、というのは、まったく正しい。
ただし、蓮實が、なぜこのようなスタンスを採るのかということについては、「kppyz」氏は、まったく理解が及んでいないのである。
本書も、後の方の文章を読めばわかるとおり、蓮實重彦だって、ゴダールが徐々に変わっていっているという事実は了解しているし、それがしばしば「人間的な方向への変化」であることも理解している。その上で、蓮實はそれを否定するのではなく、肯定的「追認」しているのだ。
しかし、ゴダールが「人間的」な方向に変化しているのであれば、先に引用した蓮實の「ゴダール寵児論」からすれば、その変化は「堕落」あるいは「失寵」ということにならなくてはおかしい。つまり、ゴダールの変化を「批判」しなければならないはずなのだが、蓮實がそれをせずに「追認」していくのは、結局のところ、当初からの方針として、ユニークな映画作家であるゴダールを「擁護」するというのがあり、その基本方針に沿って、理解されにくいゴダールの「人間としての個性」を「恩寵的(天上的)」というレトリックで「擁護」し、地上的な、つまりは当たり前の立場からの「批判」を、あらかじめ封じようとしたためなのであろう。
したがって、ゴダールを高く評価する人というのは、蓮實重彦と同様に「地上的なもの」にウンザリして「天上的なもの」を求めている人たちであり、それを「ゴダールという人間」に仮託し、幻視している人たちだと言えるだろう。つまりは「信仰者」である。
彼らは、実在しない「神」を、「書物」や「絵画」の中に発見し、それに憧れて、それが実在していると思い込もうとしている「現実逃避者」に過ぎない。言い換えれば、ゴダールは「神として祭り上げられた人間」に過ぎない。要は「ひとつの偶像」に過ぎないのである。無論、「よくできた偶像」とは言えるのかもしれないが、所詮「偶像」は「偶像」であって、「神」ではないのだ。

ただ、こうした「信仰者」の中にも、本気でゴダールを「神」だと信じているような「素朴盲信者」もいれば、蓮實重彦のように「この世に神が実在しない以上、われわれは、それをでっち上げるしかない」と考えているような「虚無主義者」もいる。だから、その違いは、しっかりと区別すべきだろうが、いずれにしろ、ゴダールが「神」ではなく「(ひとりの)人間」であるという事実だけは揺らがないのだ。
言い換えればこれは、「ゴダール現象」が「黒澤明現象」(あるいは「スピルバーグ現象」「シュテンドルフ現象」「ミロス・ファオマン現象」)などとは、たしかに「異質」な「部分」があるとはいえ、しかし、その「異質」性というのも、所詮は、この地上性という「地平」を逃れうるものではない、ということなのだ。
なるほど、ゴダールは、「寵児」ではあるかもしれない。しかし「寵児」とは「神の恩寵を受けた人間」のことであって、「神」や「天使」のことではない。「神」や「天使」は、もともと「恩寵」を必要としない超越的な存在だからである。
したがって、ゴダールは「ひとりの寵児」ではあろうが、「寵児」は、この地上において「大勢いる」ということになる。したがって、蓮實重彦個人としては認めたくなくても、他の者から見れば、黒澤明も、スピルバーグも、シュレンドルフも、ミロス・ファオマンも、それぞれに「ひとりの寵児」に他ならない、ということなろう。
蓮實が、本書を『ゴダール革命』と題したのは、「ゴダールが映画に革命を起こした、などという言い古された意味ではない」と、いつもの調子で断った上で、自身の意味するところは「ゴダールを超えていくという方向で更新されなければ、映画はダメになる」という意味においてである、という。

たしかに、今の映画は「視聴者中心」のテレビの影響のもとに、かつての「映画芸術」的な独自性を失っており、そこに古い映画ファンである蓮實が、危機感を募らせているというのは、ほぼ間違いのない事実だろう。
だが、だから「ゴダールを超えていく方向でしか」という言い方は、ある種の「ショック・ドクトリン」であり、要は「危機便乗政治」でしかないのではないだろうか。
つまり、たしかに「映画の危機」は訪れているし、その危機はなんとかして乗り越えられるべきではあろうが、その方向性が「ゴダールを乗り越える」という方向だというのは、なんら具体的な裏付けのない話、いつもの「断言」にすぎないのではないか。
もちろん、そうした方向も考えられて然るべきではあろうけれども、しかしそれが「ゴダールを乗り越える方向で」と特定された時に、それは「映画の危機」に便乗して、「抱き合わせ」で「売れ残り商品」を売り込こうとするような身振りなのではないか。
以上のような私の批判が、間違い、あるいは誤解であるというのであれば、蓮實重彦は「断言で切り捨てて排除する」という権威主義的な態度ではなく、「地上の言葉」で私を反駁すべきであろう。
そして、それができないのだとしたら、蓮實重彦の、「映画についての言葉」あるいは「ゴダールについてに言葉」は、やはり「護教的」な「神学者の言葉」でしかないと、厳しく批判されるべきであろう。
○ ○ ○
ちなみに、私はこれで、ゴダールや蓮實重彦を「片づけた」というつもりはない。
たぶん、基本的な方向性が覆ることはないとしても、もっともっと、しっかりと裏付けをとって、ゴダールなり、蓮實重彦なりの「地上的な真相」を確かめたいと考えている。
なぜなら、それが「無神論者」である私の務めだからであり、同時に私が、シモーヌ・ヴェイユ的な信仰者でもあるからなのであろう。
(2023年9月13日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
