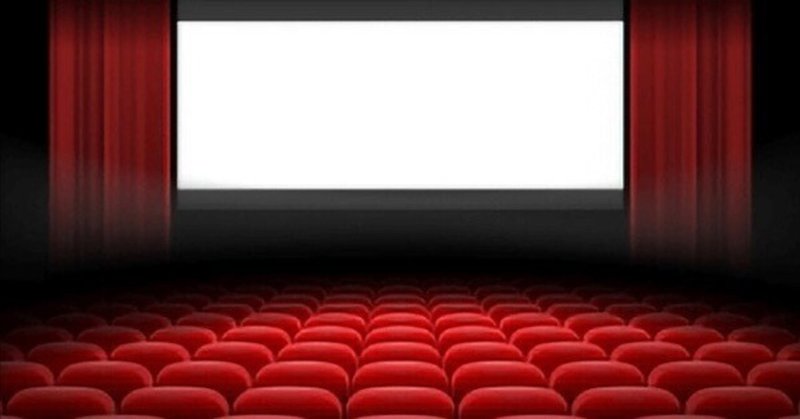
蓮實重彦 『見るレッスン 映画史特別講義』 : 小手調べに読んでみた
書評:蓮實重彦『見るレッスン 映画史特別講義』(光文社新書)
昨年退職して自由になる時間が増えたので、これまで自制してきた映画鑑賞に時間を割くようになった。
例えば、ゴダールなんて人の名もたまに耳にはしていたけれど、そもそも映画より優先する読書の方で、読みたいし、読まなければならない作家・文筆家が山ほどいる。
また、ゴダールの作品が難解だと言っても、そんなもの、難解な書物に比べれば多寡が知れている。書物の世界には、手も足も出ないようなものがいくらでもあって、しかしそちらの方がよほど気になったのである。

だから、退職していなかったら、ゴダールの追悼映画祭なんてものに脚を運ぶこともなかったのだが、時間の余裕のおかげで「ちょっと覗いてみるか」という、気楽な気持ちで観てみたのである。一一で、思ったのは「なんだこれ?」であった。
そのあたりに、正直な感想については、すでに2本のレビューを書いているから、ここでは繰り返さないが、要は、予備知識と言えば「ゴダールは巨匠である」「蓮實重彦がゴダールを高く評価している」といったことくらいで、そもそもゴダールがどこの国の映画作家かも知らなければ、「ヌーヴェル・バーグ」という言葉も知らなかったので、ほぼ「臆見」なしの鑑賞だったのだが、その結果は「何が面白いの?」「この監督は、何がやりたかったのか?」ということに尽きよう。
しかし、私は、年季の入った読書家だし、狭い世界に引きこもって「この世界こそが一番に決まっている」などと言っているような「田舎者」でもなければ「オタク」でもなかったので、「自分のわからないものは、つまらないもの」だなどとは考えなかった。それほど馬鹿ではないということだ。
だから、ゴダールを観て「わからなかった」のも、それはゴダールが「難解だから」ではなく、私がこれまで映画や文学などに求めてきたものとは、大いに違った価値観において撮られているからであろうと、そのように察し得た。平たく言えば、「価値観の相違」である。
しかし、理解できない対象について、ただ「価値観の相違」だから「仕方がない」などというのは、「自己慰撫のための自己正当化」でしかないから、そこに止まってはいけない。
そこで大切なのは、その「理解不能の対象」をわざわざ作った作者が、どのような「価値観」や「美意識」で、それを作ったのか、それを大筋においてでもいいから理解することであり、それこそが「知的」ということである。
もちろん、そうした「知的な理解」は、たいがいは「知的理解」の範囲に止まって、「完全な理解」には届かないだろう。
しかし、それはやむを得ないことなのだ。
最近の私の表現で言うならば「私とて、万能ではない」ということになる。
「万能の神」でないかぎり、すべてを正しく理解できる者など、この世には存在しないし、ましてや、そんな人間は存在しない。そんな人間がいると思うのなら、それはその信者の「信仰的幻想」に過ぎない。
例えば、「青色と赤色のどちらが好きか?」という問いに対して、「正解」はない。
「青色の方が好きか、赤色の方が好きか、の違い」はあっても、どちらかを「正しい」とする「合理的な根拠」など存在しない。一一これも平たく言えば、「好み」の問題でしかなく、「正邪善悪良否」の問題ではないということだ。
人間であれ、動物であれ、個体的な特性を突き詰めていけば、結局は「それに惹かれるから、好きだ」ということにしかならない。「甘いもの」と「辛いもの」のどちらかがより好きだとしても、より好きな方が「正しい」という、究極的な根拠など無い。
突き詰めて言ってしまえば、この宇宙に「善悪」は存在せず、こうした「価値判断」は「人間が生き残るために生み出した、ご都合主義的産物」に過ぎないのだ。好みの違いだって、絶滅を防ぐための「偏差」でしかないとも言える。
しかし、だからこそ「なんでもあり」だというのではない。
人間であれば、可能なかぎりにおいて「頭をつかうべきだ」し、それが「正しい」と言いたいのである。
したがって、ゴダールの作品を「好き」になる必要なはい。
ただし、時間の許すかぎり、その特性を「知的に理解すべき」である。「理解」が進んで、それが「好き」に転ずるようなこともあるかもしれないが、別にそうならなくてもいい。つまり「ゴダール的な趣味嗜好」を理解する「因子」を持っていなくて良い。頭では理解できても、それを「面白いとは感じられない」としてもかまわない。ゴダールだって、わからないものは山ほどあるわけだし、彼も特別頭が良いというわけでもないのである。



ただ、わからないものを「わからなくてもいい」と言い訳して放置するのは「逃げ」であり、「誤魔化し」である。その対象が「なぜ、わからないのか」、その理由くらいは考えてみるべきだ。
人間は思考する動物であり、本能的直観と経験による判断だけしかないような、単調な動物ではないのだ。
その上で「ああ、この作品が、体現していたのは、こうした欲望だったのだな。しかし、私の欲望の方向性は、そっちには向いていなかったから、それを求める情動が起こることはなく、それに惹かれることがなかったのだな。つまり、面白いとは感じなかったのだな」と、これくらいのところまでは、「知的」に確認すべきなのだ。
無論、「そんな知的探究に費やしている時間などない」というのであれば、そこで「わからない」と降参すべきであろう。そして、戦うことをしなかった者が、降参をしておいて、後で「本当は俺の方が強いんだけどな」などと言うのは、愚かでもあれば、見苦しいことだ。
そんなわけでは、私は「ゴダールのわからなさ」を、ひととおり追求してみることにした。
無論、本質的には「たぶん、わからないだろう」とは思っているが、「なぜわからないのかは、わかりたい」からである。
それで、前記のレビューで言及した、昨年の「ゴダール追悼映画祭」で、
(1)『勝手にしやがれ』
(2)『気狂いピエロ』
(3)『女は女である』
(4)『女と男のいる舗道』
(5)『パリところどころ』
の5本を観たあと、それに止まらず、今年も開催された「追悼 ジャン=リュック・ゴダール映画祭」で、次の9本も観た。
(6)『小さな兵隊』
(7)『カラビニエ』
(8)『はなればなれに』
(9)『ウイークエンド』
(10)『パッション』
(11)『カルメンという名の女』
(12)『ゴダールのマリア』
(13)『ゴダールの探偵』
(14)『ゴダールの決別』
昨年の5本の中では、私は『気狂いピエロ』が良かった。何が良かったかというと、「絵」が良かった。他の作品では、ゴダールは「女」を撮るのが好きなんだなというのもわかった。

だが、全般に言えることは「筋がつまらない」か、「まともな筋が無い」というところで、つまらなかった。この人は「筋」の面白さには興味がないようだと、そう感じた。
今年の、9本については、『気狂いピエロ』ほど面白いと感じた作品は、ひとつもなかった(あえて言えば、『ウイークエンド』の「メタフィクション」性が、私の好みではあった)。
もちろん、相対的には、面白いのもあるし、つまらないものもあるが、総じて言えば「つまらなかった」し、やはり、ゴダールは、本質的に「私には合わない」というのを確認することができた。

ともあれ、代表作と思しきものを14本も観たら、「観るべきものを観ていないから、理解できないのだ」ということにはならない。ここまで確認すれば、「ゴダールは、私には合わない」と、そう言っても間違いにはならないだろう。
ならば、次の段階である。「ゴダールを高く評価する人は、ゴダールの何を高く評価しているのか?」を探ることだ。
もちろん「良いものは良い」とか言っているような、頭の悪いゴダールファンは相手にする必要はない。
そんなものは、「神は存在する」と断言している盲信者と、なんら選ぶところはないのだから、私が相手にすべきは「ゴダールの、どこがどのように素晴らしいのか」ということを「論理的に説明できる」人間である。一一そして、それは誰かと言えば、まずは蓮實重彦。そして、二番手が、四方田犬彦ということになるのだろうか。
どちらも、「映画評論家」であるだけではなく、「文芸評論家」として顔を持っているから、私は多少なりとも二人の書いたものを読んだことがあるけれども、それは「映画論」以外、であったから、今回は、これまで興味のなかった、彼らの「映画論」、中でも当然「ゴダール論」を読むことにした。
そして、まずは、なんと言っても、蓮實重彦である。
蓮實重彦の「映画論」や「ゴダール論」、そしてゴダール自身の「映画論」あたりを読み、それに『ユリイカ』誌のゴダール特集などで「その他の人のゴダール論」を読めば、ゴダール信者が、ゴダールの何を評価し、信仰しているのかが、大筋でわかるはずだと考えて、最初に手に取ったのが、いかにも読みやすそうな、本書『見るレッスン 映画史特別講義』だったというわけである。
○ ○ ○
本書を一読して、まず感じたのは「分かりやす過ぎる」ということである。
蓮實重彦の文章は、これまでいくらか読んでいるけれど、こんなスカスカではなかった。その意味では、あまりにも「入門書すぎる」といった印象で、いささか肩透かしであった。

これは蓮實自身が「あとがき」で明かしているとおり、折にふれて「質問されたことに答えていたら、それがいつの間にか本にされてしまった」という経緯で作られたものだからのようだ。
つまり、蓮實重彦は「文章を書いていない」から、お得意の「レトリックを駆使することができなかった」のである。
しかし、こう書くと「それだからこそ、蓮實の考え方の骨格の部分を知ることができて、効率の良い本なのではないか」と考える人がいるかも知れないが、これは「本を読まない人」の、浅見である。
物事の「本質」というのは、必ずしも「骨格」の部分に宿っているわけではなく、むしろしばしば「表面」であり「細部」に宿るものである、といった理屈くらいは、蓮實重彦を読まなくても、常識として知っておいてもらいたい。

例えば、娯楽小説においては「筋」が重視されるが、「文学作品」においては「文章・文体」が「すべて」だとまで言われたりする。その場合、「骨格としての筋」は、「本質としての文体」を盛るための「器」に過ぎないのである。
無論、美味しい料理も、不細工な器に盛られたのでは台無しだから、「器などどうでもいい」というわけではないのだが、少なくとも「料理=文学」においては、「料理=文体」が主であり、「器=筋」は従である、ということくらいは、最低限、理解していないと、味わうべきものを味わわないまま、器に感心したり、器にケチをつけたりしておしまいという、「味覚オンチ」の反応しかできないことになってしまう。しかも、そのことに無自覚なままだ。
したがって、「レトリック」を駆使できなかった本書においては、蓮實重彦の本領は発揮されていないと、そう考えるべきである。こんなものを読んで、蓮實重彦を理解した気になるのだとしたら、その人はそもそも「読む」という行為、言い換えれば「鑑賞する」という行為が、まったくわかっていない、ということになる。
なぜ、「レトリック」が必要なのか。
それは「(特に)甘いものが好き」というのを説明するのは、論理的には不可能だからで、比喩を駆使するレトリックを使わないことには、趣味を同じくしない他人には、自分の感じていることを、イメージ的にしろ、伝えることができないからだ。だからこそ、レトリックは、ロジックでもある。レトリックは、「欺瞞」ではなく「表現」なのだ。
そんなわけで、当然のことながら、本書を読むと、蓮實は「やたらに断言しているだけ」という印象を受けてしまう。なぜ、そうなるのかと言えば、レトリックという「肉質」を欠いていて、蓮實の骸骨がカラカラと踊っているだけだからである。
だから、本書を読んでも容易に理解できる、蓮實の「表層重視」の根拠は、理解のしようがない。
「なぜ、筋ではなく、絵(ショット)を重視しなければならないのか?」という疑問に、本書はまったく答え得ていない。
しかし、薄っぺらい新書1冊読んだくらいで、そんな「個性的な主張」の根拠を理解できるなどと思う方が、愚かなのである。
つまり、本書には、皮肉屋で韜晦癖のある蓮實重彦らしからぬ、素直さと分かりやすさがあって、その点では、容易に「共感できる」部分もあるけれども、むしろ、そこは重要ではない。蓮實自身も、
『 つまるところ、わたくしたちが映画を見るのは、驚きたいからです。ところが、同時に安心したいという気持ちもある。驚きというのは安心とは逆のものであり、こんなものを見たことがないというような不思議な世界に連れていかれることですが、同時に、不思議な世界というのがことによったら、どこかの何かに似てるかもしれないと思わされるのが映画です。驚きと安心とか巧みに塩梅されているものが映画なのだと思います。
ところが、安心だけで映画を見る人、驚きだけで映画を見る人がいますが、驚きだけ求めるならのブニュエルの『アンダルシアの犬』(1929)で十分なわけです。ところが映画の本質はそうではなく、驚きが安心であり安心が驚きであるような不思議な世界というものが、実はキャメラを通じて作られる映画というものの表象性を支えているのだと思います。
だから、驚き、かつ安心する。安心というのは、「もうこれでいいや」というのではなく、「ああ、こんな驚くべき光景を見られてよかった」という安心感なのです。そして、どれほど皆さんが映画に驚きを求めているのか、その驚きが見たことのないSFXで得られるものなのか、それともそうではないごく普通の対象にも備わっているかという問題を、もう一度みんなしっかりと考えてみる必要があると思います。』(P189〜190)
と書いているとおりで、私たちが、求めなければならないのは、「異和をともなった理解=驚きをともなった安心」なのだ。なぜなら、「驚き」の最大のものとは「理解不能なものの存在」であり「それを楽しめる感性の実在」だからで、だから「面白い」。
蓮實も書いているとおりで、大衆は、あまりにも「安心」ばかりを求めすぎる。
同じようなものばかりを「消費すること」で、安心を得ている。「安心」こそが目的になってしまっている。
だが、「わかるもの」「好きなもの」だけを求めるのならば、「知性」はいらない。それは、単なる「動物」のやっていること、そのままでしかない。
私たち人間は、「わからないもの」「嫌なもの」の中にも「快楽」を求めることのできる「知的な変態」あるからこそ、自然を超えた「人間」存在なのである。
だからこそ私は、「ゴダール」という「如何物」食いを、楽しむつもりなのだ。
(2023年7月1日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
