
小津安二郎は「変態」である と、 蓮實重彦は言った。
先日、映画監督・黒沢清と、黒沢に大学で「映画表現論」を指導した、言うなれば黒沢の「映画の師匠」である蓮實重彦との対談本『東京から 現代アメリカ映画談義 イーストウッド、スピルバーグ、タランティーノ』(青土社・2010年刊)を読んで、そのレビューをアップした。
はっきり言って、馴れ合いの師弟対談にすぎなかったし、それゆえ蓮實重彦の「嫌味ったらしさ」も、わかりやすく全開になっていたから、そのあたりの発言を引用して、蓮實という人が、いかに嫌なやつであるかを懇切丁寧に説明しておいた。
そのため、同レビューは、言うなれば「蓮實重彦批判」という形式での「蓮實重彦論」にはなったのだが、肝心の対談本の内容については、あまり書くことができなかった。
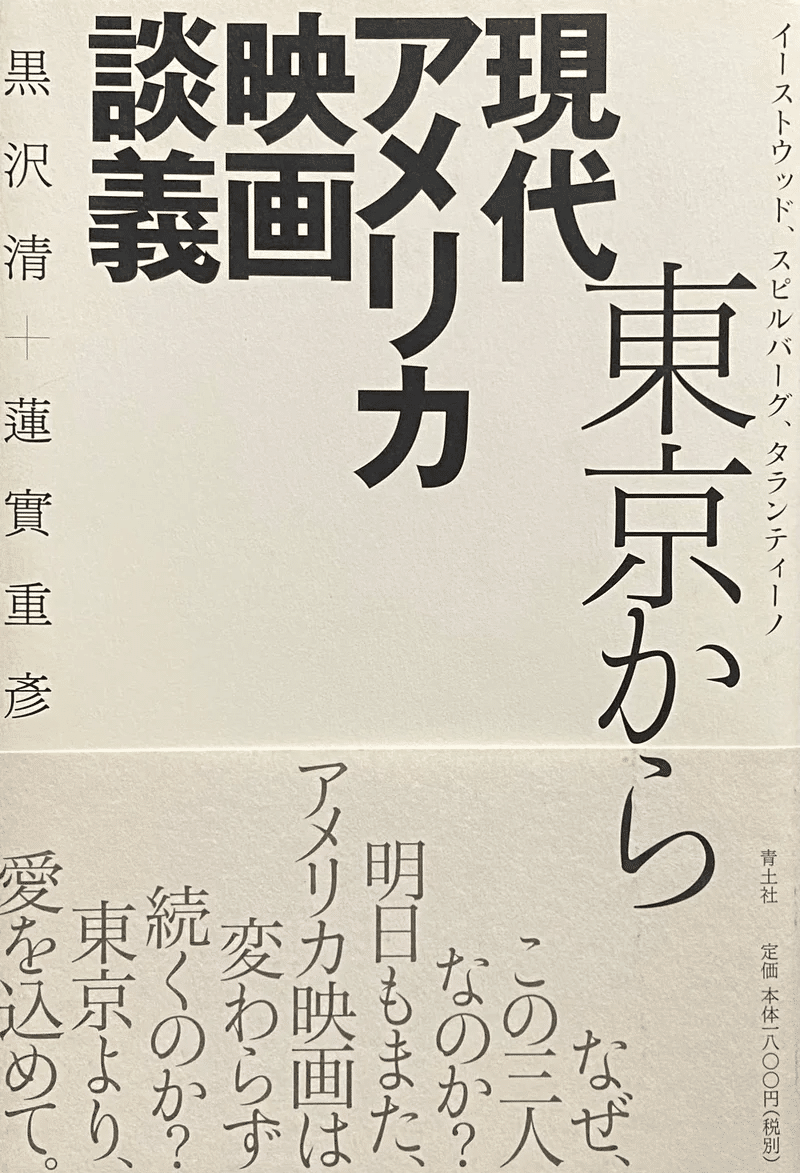
そこで、この本稿では、同対談集の中では最も面白かった、クリント・イーストウッドの関わる部分に触れつつ、抱き合わせで言及されていた「小津安二郎」について書きたいと思う。
結論から先に書いておくと、要は、
「イーストウッドは、イメージとは違って変態作家だが、それは小津安二郎も同じことである。小津は、一見したところでは、静謐で端正な作風の作家だと思われがちだが、その理解は表面的なものに止まるつまらないものだ。じつのところ、小津安二郎もまた、本質としては変態なのである」
というのが、蓮實重彦の小津安二郎理解なのである。
○ ○ ○
「黒沢・蓮實対談」で、私が最初に感心したのは「イーストウッドは変態である」という、意想外の指摘だった。
私の世代だと、クリント・イーストウッドと言えば『ダーティ・ハリー』(ドン・シーゲル監督)のイメージが強い。気難しい変わり者の、一匹狼のアウトロー刑事である。
つまり、イーストウッドと言えば、当然のことながら「俳優」だ、というふうに理解していた。『ダーティ・ハリー』のほかに浮かぶのは「西部劇」のガンマン姿だし、どっちにしても銃をぶっ放す、ちょっとクセのあるヒーローを演じる二枚目俳優だと思い込んでいたのである(声はもちろん、山田康雄だ)。

ところが、イーストウッドは、「西部劇」俳優として人気が定まった後、『ダーティ・ハリー』と同年の1971年には、すでに監督作第1作の『恐怖のメロディ』を撮っている。
そしてそのあとは、「主演・監督作品」が大半だとはいうものの、「主演のみ」作品と「監督のみ」作品を同程度に撮っており、要は、映画監督としても、かなりのキャリアを持つ人なのだ。
だが、子供のころテレビで映画を視る際には、主演が誰かは気にしても、監督の方はまったく気にしない。監督で作品を視るようになったのは、アニメを自覚的に観るようになった高校生くらいになってからで、実写映画の方にはさほどの興味もなく、イーストウッドが主演するような映画をテレビで視ることもなくなっていたのである。
そんな私が、イーストウッドの監督作品として初めて映画館で観たのは、作品賞、監督賞、主演女優賞、助演男優賞の4部門を受賞した、アカデミー賞受賞作『ミリオンダラー・ベイビー』(2004年)であった。
これだけの受賞作だから、当然のことながら当時は大変な評判になっていたので、私は「へえーっ、あのクリント・イーストウッドが監督としてアカデミー賞を取ったのか」と感心したわけだが、この時すでにイーストウッドには30年以上の監督歴があるということなどまったく知らず、「歳をとってから監督業に目覚め、いきなり才能を発揮した」というくらいの理解だったのである。そして、そうした意味で、古馴染みのイーストウッドに対し、お気楽にも「おめでとう!」という感じだったのだ。
で、この作品は、若い女性ボクサーが試合中の事故で全身不随になるお話だということくらいは、知っていた。結末の方は知らなかったのだが、あのダーティ・ハリーのイーストウッドが監督した作品なのだから、きっと最後は「立ち上がって」再起するのだろうと思い込んでいたのである。
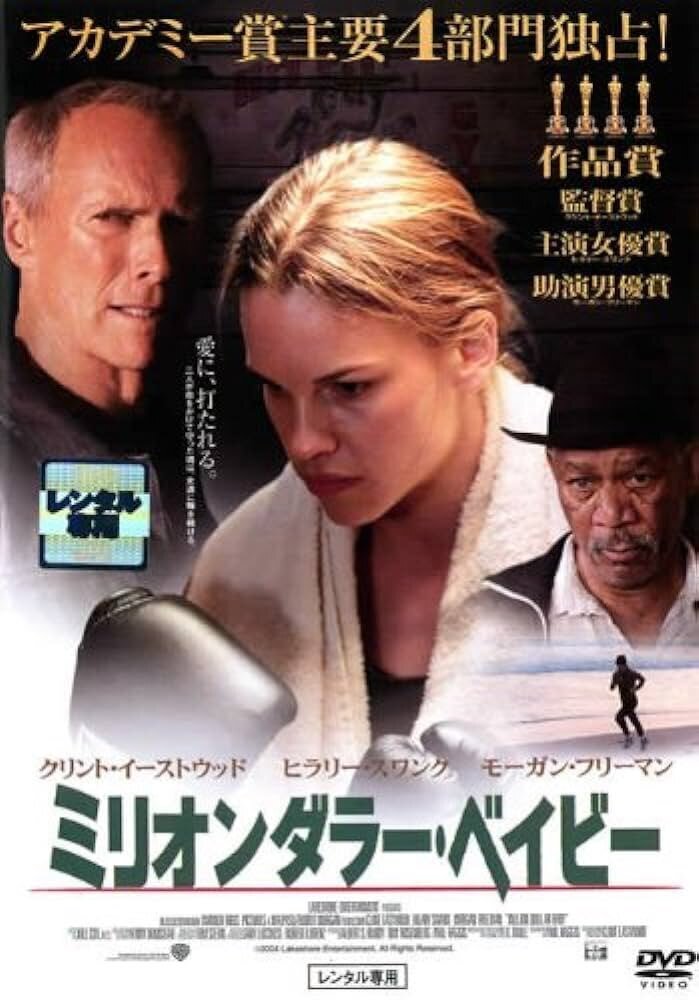
ところが同作のラストは、彼女を娘のように愛し、その事故の結果に深く心を痛めていた、イーストウッド演ずるところのトレーナーが、自分では死ぬことさえできない彼女を憐れに思い、「安楽死」させてやる、というものだったのである。一一まさに「えっ?」だ。
で、当時の私としては「それはないだろう」と、どうにも納得できなかった。
たしかに現実には、そういうことも十分あり得ることだし、登場人物の気持ちもわかるが、しかし納得がいかない。裏切られた気がする。
つまり、イーストウッドに期待していたものとは、180度違った作品だったので、当時の私は、イーストウッドに「騙された」ような気になったのであろう。
ところが、「黒沢・蓮實対談」を読むと、イーストウッドというのは、もともとそういう「変なことをやる監督」なのだと語られていた。
私は、どうしても役柄のイメージに引っ張られてイーストウッドを見ていたのだけれど、イーストウッドその人は、当然のことながらハリー・キャラハンそのものではありえない別人であり、そんな「人間」クリント・イーストウッドは、常識では測れない人、変なことをする人、つまり「変態」だったのだと、蓮實重彦は言うのである。
そして私は、この紹介を読んで、初めて『ミリオンダラー・ベイビー』のラストが、わざとやった「嫌がらせ」だったのを理解した。
あれは、当たり前の「ハッピーエンド」に異を唱える作品だったのである。「これが現実なんだよ」と、そう観客に突きつけるための作品だったのだ。だからこそ、批評家ウケも良かったし、アカデミー賞も受賞できたのだ。
イーストウッドが、ハリー・キャラハンのそのままの人(アウトロー)だったら、決してアカデミー賞を受賞できるような作品を撮らなかっただろうと、今になって、やっと理解し、納得することができたのである。

『蓮實 でも黒沢さんがおっしゃるとおり、なにもそこをしっかり撮らなくても、という妙な場面が(※ イーストウッドの監督作『チェンジリング』には)たくさんありますよね。まあ、私も混乱したままで、それについて意味のあることなどとても言えないのですが。ただ確実に五年後一〇年後に見直さないといけない映画でしょうね。そして何よりも驚くのは、これを撮っている時、彼はすでに『グラン・トリノ』を構想していた(笑)。
黒沢 そうなんです。彼にとって自分が主演する映画というのはやはり少し違ってくるのかもしれませんね。『真夜中のサバナ』がまさにそうだったように、監督するだけだと思いっきり大胆な構造の物語を持ってくるけれども、自分が出演するとなると『ブラッドワーク』にせよ『スペースカウボーイ』にせよ多少違う構造の映画にしようとする………。と言ったそばから違う気もしてきました(笑)。自分が主演しておきながら相当妙な映画もありますよね。最初にそれを感じたのは『ホワイトハンター ブラックハート』で、イーストウッドが主演なんだけど明らかに、何なんだろう、これは、という違和感を発している。最後のシーソーあのモデルはジョン・ヒューストンだそうですが一一で、イーストウッド演じる映画監督がまた撮影現場に連れ戻されて、しばらくうなだれたあとにふと顔を上げて「アクション」と言う。それがすごく嫌そうな顔で(笑)。これから映画を撮り始めようというのだから、ある意味で気持ちよく終わっていいはずなんですが、言いようのない拒絶感に満ちていて、とっても嫌な終わり方になっていた。しかもそれが自分の顔のアップで終わる(笑)。
蓮實 なぜあれが撮りたかったのかは、いまだに謎ですね。単にアフリカに行きたかっただけではないのかという気もしますけど(笑)。ジョン・ヒューストンが背景にあったり、彼なりの思い入れもあったのでしょう。そう考えると、イーストウッドが観客を拒絶する映画はここから始まったのかなという気もします。
黒沢 ちなみに蓮實さんが最初にイーストウッドをいいと思われた作品はなんだったんですか。『恐怖のメロディ』の時から、これぞと思われたんでしょうか。
蓮實 そうです。その頃はまだあまり批評を書いていませんでしたから、ただこれを見ろと会う人ごとに吹聴していました。はっきりと発言し始めたのは『ガントレット』の頃からです。
黒沢 あんなにバスに弾が撃ち込まれているのに、タイヤだけにはなぜか当たらないんですよね(笑)。痛快な活劇以外のなにものでもないんだけど、あちこちに奇妙な過剰さがある。
ラストシーンだけでなく、いたるところで警察の発砲の量が度を越しているし、あと、イーストウッドとソンドラ・ロックがヘリコプターに追われながらバイクで逃走するシーンで、確かトンネルを三つ連続で抜ける。三つもです。だのに何も起こらない(笑)。
蓮實 また音楽をジェリー・フィールディングがやっていて、物語は殺伐としているのに、ジャジーな雰囲気が漂っている。そこがとても好きでした。それまではジョン・ウィリアムズ(『アイガー・サンクション』)とかミシェル・ルグラン(『愛のそよ風』)のような作曲家を使っていたのが、フィールディングを経て、近年はずっとレニー・ニーハウスを起用しています。ニーハウスもジャズ系の人らしいので、やはりそういうティストが好きなんでしょうね。でも、ジョン・ウィリアムズやモーリス・ジャール(『ファイヤーフォックス』)ともできるんだから、めちゃくちゃな人ですよね(笑)。
黒沢 音楽もめちゃくちゃですけど、そのあたりは『アイガー・サンクション』とか『ファイヤーフォックス』とか『ガントレット』とか、でたらめと言っていいフィルモグラフィで、しかもこれ全部監督主演ですからね(笑)。
蓮實 『スペースカウボーイ』などもその流れですよね。あのくらいになったら、演出は誰かに任せてもいいはずなのに。
黒沢 つくづく変わってますよねえ。』(P40〜43)
『蓮實 ショットの切れ味という点ではまったく小津と違うのに、ある意味で小津に似ていないともいえなくない。『グラン・トリノ』は葬儀一一小津は法事ですが一一で始まり、葬儀で終わるわけです。(以下略)』(P47)

『 変態する変態(※ 見出し)
蓮實 ある時期までなら、ドン・シーゲルの『白い肌の異常な夜』やイーストウッドの処女作『恐怖のメロディ』における倒錯的な被虐嗜好を知っているわれわれは「どうせイーストウッドは変態だから、それぐらいはやるさ」と思っていたわけです。彼は持って生まれた変態ですよね。自分の体をしたたかに傷つけるという倒錯性を隠そうとするどころかそれを聖痕として顕示する人で、『ブラッド・ワーク』では嬉々として女医のアンジェリカ・ヒューストンに自分の心臓を手術させるということまでしていたわけだから。
黒沢 医者にかかるという設定が本当に好きですよね(笑)。自分は横たわっていて傷口を縫われたり、といったシーンが必ず出てきます。
蓮實 ですから、「変態イーストウッド」ということなら理解できていたのですが、今回は、この人はもう変態を超えてしまったという感じがします(笑)。でも、『グラン・トリノ』はアメリカでもフランスでも大ヒットしているらしいじゃないですか。ということは、これまでの「変態イーストウッド」を 知らない人たちが大挙して見に行っているわけです。いったい彼らは何を感じ取っているのでしょうか。
黒沢 まったくわからないですね。『真夜中のサバナ』のように見に行った人が全員途方に暮れたというのならわかるのですが、これが大ヒットしているというのは本当にわからないです。』(P49〜50)
『黒沢 いやあ(笑)。俳優としてのイーストウッドについてですけど、やっぱりかなり変わっていると思います。まず、基本的にどこを見ているのかわからない。もちろんあの独特のしかめっ面がそうさせているのですが。時々ぎろっと振り向いたりしたときだけ目線がわかって、見ているこっちもはっとなる。しかめっ面をしていると、瞳そのものがどこにあるのかわからないので、彼が今何を見ているのかが読めない。リー・マーヴィンとかもそうなのですが、その手の俳優って元々そういう顔の作りをしているという場合がほとんどなのですが、イーストウッドは、本来は甘い二枚目で、普段は普通に目を開いていて、しかもにこやかに微笑んだりしている。それが、スクリーンでアップになったりすると急に目線の読めない不可思議な人物に変貌する。それを売りにしてあそこまでスターを続けているというのは、かなり珍しいと思います。日本人としてはあの目線がはっきりしないところに好感を持つんでしょうか。女性が彼を男性としてどう見るのかは、さっぱりわかりませんが。
蓮實 異性を見て、その目の力によって異性が彼に近寄ってきたり、そのことで唇を重ねるということを、ほとんど拒絶してきた人ですよね。だから、見ていなくても、構図=逆構図で見ているように見せてしまうというようなことはしてこなかった人です。
ところが、既に別のところでも話しましたが、『グラン・トリノ』では低い音楽を流してモンタージュするシーンがありますね。少年が庭師として一所懸命庭を造っているのをイーストウッドがテラスでタバコを吸いながら見ている。するとそこに音楽が流れて、イーストウッドの顔にズームアップするのですが、そんなことはイーストウッドの映画ではないはずのものです。見ていない振りをしながらタバコを吸って、しかも雨がザァーッと降ってくるところを雨滴ごしに彼の顔をクローズアップで写したりして、つまりあそこでははっきりと彼が少年を見ていることになっている。そんな演出をイーストウッドはこれまであまりしたことがないでしょう。
黒沢 メロドラマですよね。
蓮實 ものも言わずに目だけでモン族の少年に対する愛情を表現し、しかもそこに音楽まで流すなんて、変態らしからぬまっとうな演出ではないですか(笑)。なおかつそれを異性ではなくて少年相手にやるわけです。
黒沢 ただそれをやられても、イーストウッドとモン族の少年との間にどのような共犯関係が成立していたのかがわからないんですよね。でも、どうも何かが二人のなかで成立はしているらしいことだけが伝わってくる。
モン族の少年を散髪屋に呼んで一人前の男にしてやるという場面も奇妙でした。イーストウッドと散髪屋には絶妙な共犯関係が既に成立していて、その様は見ていて本当に気持ちがいいのですが、そこにモン族が迎え入れられて、散髪屋への入り方を何度か練習しているのを、二人してジーッと見ている。このシーンは本当に変で、『ペイルライダー』にも出てきた西部劇の定番としての散髪屋をパロディーにしたと考えればいいのか、それとも単にユーモラスなシーンとして撮ったのか、戸惑いました。』(P52〜54)
ここまでの引用でわかるのは、イーストウッド監督が「普通では考えられないようなことをやる、独特のセンスの持ち主」であり、その意味で「変態」だということである(そして、それは彼の被虐趣味とも関連するのかもしれない)。
で、ここまでなら、小津安二郎との共通点は「変な形式性にこだわる」といった部分だけのように思えるだろう。

だが、私は本書を読む前日に、小津を論じた私のレビュー「小津安二郎の精神分析:『晩春』『東京暮色』『麦秋』ほか」のコメント欄で、私の「note」をフォローして下さっている「广瀬アリスワンダーランド」氏と、小津をめぐって、拙論を前提とした次のようなやりとりを交わしていたのである。
(なお、(※)内は、後から付した補足注釈。投稿者名のあとの数字は「発言番号-発言者-発言者の発言番号」である)
广瀬アリスワンダーランド(※ 01-H-1)
2024年1月20日 13:32
この映画(※ 『晩春』)、GHQの検閲対象になっていたようですがそれ以前に小津の日本敗戦の惨禍は死んでも描かないという強い意志を感じますね
小津の自己愛性の形式主義は嫌いじゃないんですが、ここまで徹底的に隠されると逆に何かあるんじゃないか?と勘ぐりたくもなります
(※ 「小津の自己愛性の形式主義」とは、私が上記のレビューで指摘した点である)
年間読書人(※ 02-N-1)
2024年1月20日 14:07
『死んでも描かないという強い意志』というところまでは感じないんですよね。
紀子が服部とサイクリングをするシーンで、コカコーラの看板が出てくるんですが、あれは何なのか? 何らかの意味があるのは間違いないと思いますが、(※ 戦勝国アメリカへの好意と悪意の)どちらにでも取れる。また、このサイクリングのシーンはとても綺麗に、ファンタジックなまでに綺麗に撮れてるんですが、これが皮肉なものとも思えない。
私の感じでは、小津安二郎って、口では頑なですけど、けっこうブレてる人なんじゃないかという気もします。『東京暮色』の失敗とか、かなりいろいろ迷いがある感じがしますね。
ただ、最終的には、あまり冒険はしない人だと思います。『東京暮色』の失敗も、本人としては、失敗するなんてカケラも思ってなかったんじゃないかな。
あと、長らく、母と二人だけで生活したわりに、母を描かないところも、現実逃避傾向のように思います。だから「弱さ」があると書いたんですよ。

广瀬アリスワンダーランド(※ 03-H-2)
2024年1月20日 14:32
確かに“強い意志”というのとは違うかもですね
『東京物語』なんかも親が子どもに邪険にされて最終的に母親の方が死ぬという悲しい話で、敗戦後の人心の荒廃を描いた作品ともいえるので
ただ『東京物語』がアップされたYouTubeのコメントをみるとこの頃の日本は良かったってものが多いんですね
本当に観たのか?って疑っているんですが笑
まあそう見えてしまっているんだからしょうがないんですけど
あと小津の自己愛的なこだわりが海外の映画監督からは一種の作家性のように解釈されて評価が高くなっているのかもしれませんね
作家性というものが当人の性癖的なものの発露であることはままあることですが…
年間読書人(※ 04-N-2)
2024年1月20日 17:43
「この頃の日本は良かった」って評価は、じつのところ、監督が作り上げた「願望としての幻想」に酔わされているということで、その意味では間違ってないんですが、願望と現実の過去の区別がついていないところが問題なんですよね。
わかってて酔うのはかまわないんだけど、「昔は良かった」式の言い方をする人は、現実逃避傾向があるから、だいたいわかっていません。
現実なんて、今も昔も、だいたい碌なもんではないんですよ。だから、昔は良かったとか言いたがる人は、だいたい今がダメなやつ(笑)。


年間読書人(※ 05-N-3)
2024年1月20日 18:14
あと、「性癖的なものの発露」ということですが、フィクションを作る場合は、それは絶対に必要なものなんですね。逆に言えば、「理屈」や「思想」や「イデオロギー」なんかだけで作ってしまうと、必ずどこかご都合主義的な、無理のある世界観の作品しか作れない。
「性癖的なもの」というのは、単に「性癖的なもの」というよりも、「体質的なもの」とか「願望的なもの」とかを含めた、良かれ悪しかれ、その人の本質的なところから出てきたものだから、その世界観によって作られたものは、自然であり破綻が無い。それが、正しかろうが間違っておろうが、です。
だから、フィクション創作においては、この両者が必要なのですが、これがなかなかね。
例えば、ヘタレの作者がヒーローに憧れてヒーローものを作る。この際、自身の現実を直視した上で、自分がそうではあり得ないヒーローに理想を託すというのなら良いのですが、自分がヒーローになったつもりの勘違いで描くと、碌なものにはならない、というようなことです。
广瀬アリスワンダーランド(※ 06-H-3)
2024年1月20日 18:33
確かに現実なんてものは古代から現代まで延々とずっとひどいままですね
多少便利になったとは思いますが本質的に進歩しているとは思えません
印象に残ってるのは晩年の小津が癌に罹って放射線治療でコバルトの針を体に刺されるんですが「なんで俺がこんなに苦しまなきゃいけないんだ、何も惡いことしてないのに」といったというエピソードなんですね
ただ三度、軍隊に召集されて大陸で毒ガス部隊に配属され当然、南京虐殺も戦時性奴隷も見聞していた人物の発言としてはあまりに幼児的というか自己愛的だなあとは思いましたね
小津の自己イメージは惡いことを一切してない人だったんですね
仮に民間人の虐殺に関与していたとしてもそれは変わらなかっただろうと思います
まあ戦争を抜きにしても俺は何も惡いことをしていないといえちゃう神経は結構エグいなと
ここまで痛いのは自分が何か惡いことをしたからではないか?と考えがちですからね

年間読書人(※ 07-N-4)
2024年1月20日 18:34
いま思いついたんですが、例えば松本零士ですね。
自分が、サルマタに埋もれて生活している負け組だと自覚しながら、ハーロックやエメラルダスを願望的に描くなら、それらのヒーローは生きてくる。
ところが、作者が「ハーロックは私だ」とか言い出すと、だいたい作品もダメになっている。
願望は必要だけど、願望と現実の区別がつかないというのは、それ自体が「弱さ」であり、作品の「弱さ」にもなってしまう。
「ナルシシズム」は、現実逃避としてはダメですが、自分を愛するとか信じるという意味では必要なものなんです。
そのあたりの区別とバランスが重要なんですよ。フィクション制作においては。特に

年間読書人(※ 08-N-5)
2024年1月20日 18:41
すれ違いになりましたね。
小津のそのエピソードは、とてもわかりやすい。
要は、小津安二郎は「被害者意識」の人だったということであり、「被害者意識のナルシスト」。
だから、「俺は何も悪くないのに、どうしてこんな目に遭うんだ。みんな酷いことばかり言うんだ。正しく評価してくれないんだ」とか思ってた、作家には、よくあるタイプですね(笑)。
ただ、ナルシストの作品って、アルコール度が高いから、人を酔わせる力は強いんですよ。そのかわりに依存症にもなりやすい。いくら小津安二郎が「気持ちよく」ても、ほどほどにね、ということでしょうね。
年間読書人(※ 09-N-6)
2024年1月20日 19:21
ほんとですね。
Wikipediaの、小津の「生涯」の部分は、長いから読んでなかったんですが、毒ガス戦もやったと書いてあるから、よく戦争犯罪人にならなかったものですね。階級が低かったからかな(※ 毒ガス戦部隊のことは、戦後も長らく隠されていたからであろう)。
ともあれ、小津の頭には、殺された戦友のことはあっても、殺した相手のことは無かったようです。
「俺も、行きたくて戦争に行ったんじゃない。配属だって、望んだわけじゃない」というような「被害者意識だけ」だったんでしょう。
Wikipediaも、事実を伝えつつ、なるべく小津を責めず「小津に罪はない」と言いたげですね。いかにも日本人的な、身内贔屓の自己保身です。
年間読書人(※ 10-N-7)
2024年1月20日 19:26
あと、(※ Wikipediaに)
『1920年、学校では男子生徒が下級生の美少年に手紙を送ったという「稚児事件」が発生し、小津もこれに関与したとして停学処分を受けた。さらに小津は舎監に睨まれていたため、停学と同時に寄宿舎を追放され、自宅から汽車通学することになった。』
とあるように、小津には同性愛傾向があったのかも知れませんね。その意味で、私の感じたことは正しかった。小津は「男の子」が好きですからね(※ 小津作品では、「女の子」より「男の子」の方が圧倒的に登場数が多いし、生き生きと描けてもいる)。
ただ、(※ 小津と同様に「男の子」好きでも、それを隠さない)私とは違って、それを隠してしまうところが、(※ お上品ぶった)小津調ということでしょう。
それと、もしかすると、小津なら「昭和天皇」を理想の父と見て、心酔してた蓋然性は、十分にありますね(※ 久世光彦『陛下』参照)。
ところで、ここでの、广瀬アリスワンダーランドさんとの一連のやりとりを、そのまま記事にまとめても良いですか?
きっと、小津安二郎ファンにとって古傷を抉られるか、無知の頭を引っ叩かれるような、面白い記事になると思うのですが(笑)。


广瀬アリスワンダーランド(※ 11-H-4)
2024年1月20日 19:26
確かに僕も『男おいどん』までは面白く読んでた記憶があります
それ以降のは右翼臭くてダメでしたが
广瀬アリスワンダーランド(※ 12-H-5)
2024年1月20日 19:42
そうなんですね
日本語のウィキペディアの記事は小津も惡くないし日本人も惡くないという感じの編集になってますね
海外にもフォロワーの多い小津ですが中国で毒ガスをまいてたことまでは知らないでしょうね
あるいは知ってたとしてもそれと小津の芸術は一切関係がないと思ってるような気もします
ヴィム・ヴェンダースなんかは知らないはずないんですが

年間読書人(※ 13-N-8)
2024年1月20日 19:55
所詮、プチブルですから、映画作家なんて。お互いの権威を高め合うことしかしませんよ。
アニメ『SHIROBAKO』でも描かれているとおりで、アニメとか映画というのは、制作に金がかかりますから、スポンサーには逆らえない。
だから、ジャンルを総体として批判するようなことは、なかなかできないんですね。そのため、良いところだけを見て褒めるということになりがちです。それなら、完全な嘘ではありませんから。
今日(※ DVDで)『劇場版 SHIROBAKO』を観たんですが、作品がヒットして「巨匠」気取りになってる(※ アニメ作家の)元同僚のことを、困ったもんだねという調子で噂してるシーンが(※ テレビシリーズ版の方に)あり、そうなんだろうなと思いました。
新海誠なんか、今や「世界の巨匠」扱いだけど、あれは「ドル箱」だからで、みんな本気で褒めてるわけじゃない。それがわかってないのは、見る目のない「庶民」と当人だけですよ。
「あのオタクが、よくも出世したよな」と、このまんまのことを言った人は、日本だけでも千人は下らないでしょう(笑)?(※ 「?」は「。」の変換ミス)
广瀬アリスワンダーランド(※ 14-H-6)
2024年1月20日 20:07
小津の同性愛的な傾向は僕も感じました
稚児事件もありますし女性とつきあってた形跡があまりないんですね
のちに佐田啓二の奥さんになる人物を私設秘書にしていたようですが性的なものは感じません
まあその事実のみで同性愛者と決めつけるのも危険ですが
ただ男の恋人がいたという話も聞かないので、小津のリビドー的なものは映画にすべて昇華されていたのかもしれませんね
小津の場合、異性愛にも同性愛にもいかない独特の何かがあった可能性もありますね
コメントは引用してもらって結構です
そっちの記事も楽しみにしています
年間読書人(※ 15-N-9)
2024年1月20日 20:18
同性愛者じゃないかと推測すること自体は、何も悪いことではないんですよね。異性愛者じゃないかと疑うことが悪いことではないように。だから、そんなこと遠慮する方が間違っているんです。(※ つまり、同性愛者であることは、異性愛者であることと比べて、なんら恥ずるべきことではない以上、差別意識なく、「あの人は同性愛者かな?」と疑うことは、「あの人はアメリカ人かな?」と疑うのと同様で、侮辱ではなく、単なる懐疑推測にすぎない。したがって「同性愛者だと疑うことは、相手に失礼だ」という発想は、その人の性差別意識の反映だと見られても仕方がない)
小津の場合は、たぶん、自分も「可愛がられる美少年」でありたかった人だろうし、その自分を投影したものとして、「男の子」とその「庇護者としての男性」が好きなんでしょう。
ただし、彼は気が小さくて、被害者意識の強い人ですから、基本的には保身第一で(※ そうした性的指向を)隠します。だけど、好きなことってのは、隠して隠し切れるものじゃないんですよね。特に「表現者」は。
だから「子供が好きで何が悪い。手を出さなきゃ良いんだろう」(思想信条趣味嗜好の自由)と開きなおれればいいんだけど、なかなかそれができる人はいません。
まして今のような「頭の悪い建前社会」(※ 「悪いことは、頭の中で考えるだけでも悪い」と考えるような、頭の悪い、綺麗事の建前だけの社会)では、(※ 「男の子が好き」という)それだけで社会的に抹殺されかねませんからね。
ここでのやりとり、近々、おまけをつけて、まとめることにします。有効なプレゼンテーションを考えたい(笑)。
つまり、このやりとりでは、小津安二郎の「変態性」が指摘しされているのであるが、それは無論、単に「小津安二郎の同性愛傾向=少年愛傾向」を言っているのではない。
私自身、同性愛者ではなくても、少年愛趣味のあるのは否定しないからだ。
だから、小津の「変態性」の問題とは、例えば、戦時中に「毒ガス戦部隊に所属し、南京攻略時の日本軍による民間人虐殺事件(南京大虐殺)や、あるいは従軍慰安婦なんてことも体験的に直接見聞しているはず」なのに、そうした加害体験をすっかり忘れて、「放射線治療で針を刺される」なんてことについて子供みたいな泣き言を言ったり、私はもっぱら「戦争の被害者です」みたいな顔をしてたりするというのは、どうもそれが「本気」らしいからこそ、そこからは「当たり前の(ノーマルな)良心的な呵責」が感じられず、その意味で「かなりの(精神的な)変態だ」という意味なのである。
つまり、私がレビュー「小津安二郎の精神分析:『晩春』『東京暮色』『麦秋』ほか」で指摘した「小津安二郎の潔癖症」というのは、どうにも「自分勝手なもの」であり「現実逃避的」であり「自己正当化」目的の「潔癖症」なのではないか、ということである。もしかすると「無自覚」でやっている、「天然」なのかもしれないが、ということだ。
また、私も、小津の『父ありき』は「反戦映画」だと思ったのだが、あれも「自分のことは棚に上げて」のそれだとすれば、評価を改めざるを得ないだろう。
ともあれ、以上のような、「广瀬アリスワンダーランド」氏と私との議論を踏まえて、次の「黒沢・蓮實」のやりとりを読んでもらえば、蓮實重彦が、小津安二郎を「変態」だと思っているという事実も、容易にご理解いただけるだろう。
『蓮實 ストーリー的な山場と感情的な芝居の一致というのは現代のハリウッド映画の定型のようなものですけど一一日本のテレビドラマはほぼそれしかありませんが(笑)一一、そうすると、イーストウッドは非常に反時代的なことをしているわけです。そこが小津に近接していくところなんでしょうね。
黒沢 小津も作品によりますけど、意外に感情的な芝居をさせてますよね。原節子が急に感情をあらわにするシーンがあったりする。笠智衆がことさら淡々としているので、あれが小津を代表していると思われがちなんですが、けっこう感情的な瞬間があるのではないでしょうか。
蓮實 ええ。私もニューヨークの小津百年シンポジウムで「憤る女性たち」というスピーチをしたり、「『とんでもない』原節子」という文章を書いたりして、小津は感情的な演技をさせているということを強調しています。しかし、それをけっして作品の調子と一致させない。
黒沢 そう思うんです。もう、事が終わってしばらくして、急にそれが吐露されたりする。この呼吸はイーストウッドに近い気がするんです。そういうのっておおむね観客を混乱させはするんでしょうが。
蓮實 しかし、小津であれば、感情を爆発させる娘たちではなく、実は淡々とそれを受け止める笠智衆の物語なんだと思い、みんなが結構納得しちゃう。だから、黒沢さんが『チェンジリング』のパンフレットに寄稿した文章で、イーストウッドと小津を結びつけたことは本当に卓見だと思います。彼らは、いわゆる「ドラマチック」ということと役者の感情的な昂ぶりを、感情的な山脈として絶対に一致させず、ズラすわけです。ズラすというか無視すると言ったほうがよいかもしれません。それに思いいたったとき、私は黒沢清によってイーストウッドの秘密の一端に触れた、という感じがしました(笑)。
小津の特徴というと、静かだとか固定ショットだとかいう話になるけれども、被写体としての役者の感情と物語の感情的な起伏を絶対に一致させないというのが一貫してあるわけです。それゆえに、物語はわかっても映画の力はなかなか伝わらない。その意味で小津がまともに理解されているかどうか、いまだにわからないところがあるわけですが、その秘密を映画作家・黒沢清はついに見てしまった。それを言葉でどううまく表現したとしても、イーストウッドは「いや、そんなことはないよ」と言うだろうけど、私はあの文章に大変納得しました。
黒沢 お恥ずかしい。思いつきでふと書いてしまっただけで、具体的な例証が挙げられるわけではないのですが。
蓮實 両方とも不気味なんですよね。
黒沢 とくに異常な物語が展開しているわけではないようで、むしろ、すべてクリアに説明されていると言ってもいいくらいなんですけど、明らかにぜんぜん別の起伏、意図、陰謀のようなものがはりめぐらされていて、物語には表れないその巨大な山脈が、ときどきボロッと断片のように目に飛び込んでくる。もちろん全貌なんてまったく見えないし、誰かがひょいと見つけてくれる細部で、ああ、それもそうだったのかとわかってくるという感じなんですが………って、これは全部かつて蓮實さんに教わったことを繰り返しているだけなんですが(笑)。
蓮實 私は、黒沢さんが多くの誤解を与える覚悟の上で「小津」と口にされたことと、イーストウッドがついにその域に達したということに感動しました。今日はそのことへの感謝を最後にあらためて述べておきたいと思います。』(P66〜69)

つまり、ここで蓮實重彦が言っているのは、
「普通の(凡庸な)映画作家であれば、登場人物の感情の起伏と、物語の流れ(起伏)とを一致させて、言うなれば「整った=ノーマル」な映画にしてしまう。
ところが、小津安二郎の場合はそうではない。小津の場合だと、原節子が変なところで感情的になったりするけれど、それが物語の流れの中で、当たり前に収まっていない。つまり、妙に浮いた「変調」になっており、こうしたところが、イーストウッドの「訳のわからなさ」と通じている部分であり、要は、両者は「ノーマル」なセンスの持ち主ではなく「アブノーマル=変態的」な感性の持ち主なのである。だから、この二人は、了解不能性の闇を抱えた『不気味』な変態映画作家であり、その非凡性が素晴らしいのだ」一一と、そういうことなのだ。
で、なにやら「目新しく鋭い」ことを言っているように見えるけれど、こんな見方など、きわめて「凡庸なもの」でしかないし、要は私が、レビュー「蓮實重彦の 「逆張り」という手管:黒沢清・蓮實重彦 『東京から 現代アメリカ映画談義 イーストウッド、スピルバーグ、タランティーノ』」の中で指摘した、蓮實重彦の常套手段である「逆張り」でしかない。
『美はただ乱調にある。諧調は偽りである。』(大杉栄)なんてことは、100年も前から言われていることで、なにも今さら、事新しく「手柄顔で」言うようなことではないのだ。
たしかに、アメリカや日本の映画界は、一般にあまりにも馬鹿正直に「ノーマル志向」なのかもしれないが、所詮、それは「趣味」の問題でしかない。
つまり、蓮實重彦自身はもとより、その弟子である黒沢清なども基本「変態」であるからといって、「変態こそが(非凡だから)素晴らしい!」なんて主張するのは、所詮、単なる手前味噌でしかないのだ。
したがって、小津安二郎やイーストウッドが、蓮實重彦好みの「変態」作家だからといって、それが客観的にも素晴らしいなどということには、まったくならないのである。
つまり、私が「黒沢・蓮實対談」が所詮は「根拠薄弱な放談」にすぎないと言ったのは、そういう意味なのである。
「自分と同様の変態趣味だから素晴らしい」というのは「個人的な趣味(好悪)」を語っているにすぎないのである。
○ ○ ○
ただ、ひとつだけ言えることは、小津安二郎という映画監督は、私から見ても、蓮實重彦から見ても、どう見ても「変態」だということであり、小津安二郎のファンは、この程度の「事実」は踏まえた上で、小津を評価すべきである、ということだ。
つまり、「广瀬アリスワンダーランド」氏も指摘しているとおり、小津安二郎の描く「古き良き日本」なんてものは、「現実」ではなく、「現実逃避の変態的妄想」だということ。
そして、それが「変態的妄想」であるというのを理解し承知した上で、それでも「私はそれを、美しいと感じている」と認めるべきなのだ。
平たく言ってしまうと、小津安二郎が描いた「美しき日本」とは、殺された安倍晋三元総理がスローガンにしていた「美しい国、日本」と同じで、今はもちろん、かつて一度も存在したことのない「願望由来の妄想」でしかないのである。

(2024年1月24日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
