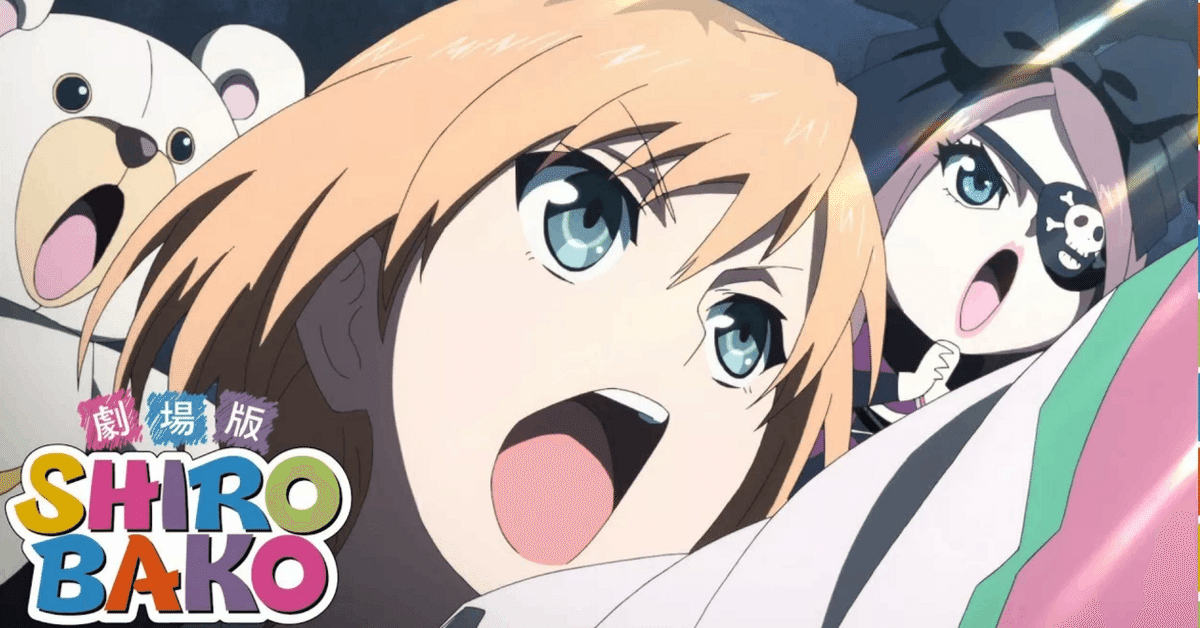
水島努監督 『劇場版 SHIROBAKO』 : 希望という、小さな灯をつなぐ人びと
映画評:水島努監督『劇場版 SHIROBAKO』(2020年)
テレビシリーズから5年の時を経ての「劇場版」である。この作品が、いかにアニメファンから愛されていたかの窺える快挙であろう。だが、現実のアニメ界をあるていど反映した本作の幕開けは、決して甘いものではない。
本作の冒頭部分を、「映画.com」のカスタマーレビュアー「杉本穂高」氏が、レビュー「もの作りは楽しい」で要領よくまとめているので、引用して紹介したい。
『もの作りは楽しい。同時にもの作りで食べていくこと、絶え間なく事業を継続させていくことは大変で苦しい。TVシリーズで上り調子に見えた武蔵野プロダクション(通称ムサニ)は、冒頭いきなりその勢いが見る影もなくなっている。TVシリーズの第一話のように。
たった一度の失敗、それも契約書をかわさずに制作を始めてしまったという業界の慣習から生じる失敗で窮地に立たされたプロダクションを立て直すために、他社が投げ出した映画製作に無謀にも乗り出す。散り散りになったかつてのスタッフを再び集めて、厳しい条件の中で一丸となって完成を目指すその姿は感動的だ。もの作りを仕事にすればいろいろなものに絡め取られる。しかし、この映画の登場人物たちのようにもの作りの衝動という原点を失わずにいればいつか道は開ける、そういう希望を謳った作品だ。
人口減少時代で内需が減少し続ける日本のアニメも、今度どうなってゆくのかわからない。しかし、ここに描かれたもの作りの熱意はきっと消えないのだろうと前向きに気持ちになれた。』

アニメ業界というのは、映画会社「東映」の子会社である「東映アニメーション」などのごく一部の大手を除けば、基本的には「中小企業」である。
なぜなら、それらは、今の「東映アニメーション」である旧「東映動画」や、マンガ家・手塚治虫が設立した旧「虫プロダクション」から独立派生した、下請け「町工場」的な会社がほとんどだからだ。
そうした中小のアニメ制作会社の多くは、大手制作会社からの下請けを行なっており、そうした下請け仕事で実績を積み、体力をつけて比較的成長した会社が、例えば「京都アニメーション」のように自社制作のアニメを制作できるようにもなる。
だが、それとて、自社制作作品がヒットしてこその話で、そこで転ければ、また下請けの仕事に戻らざるを得ないのだ。
そんなわけで、アニメ業界というのは、非常に狭い世界だ。末端のアニメーターはそうではなくても、今の下請け会社の社長クラスというのは、若い頃に「東映動画」や「虫プロダクション」あるいは、そこから派生した会社で、かつて同僚として働いた人たちだから、業界的な仕事の進め方は非常に人間的なものであり、「○○ちゃん、たのむよ」「××ちゃんの頼みじゃ、断れないな」的な雰囲気が残っている。だから、上のレビューで「杉本穂高」氏が書いているような『契約書をかわさずに制作を始めてしまったという業界の慣習から生じる失敗』などということも起こるのだ。
これは、例えば出版業界などでも同じで「○○先生、うちでも書き下ろし長編をお願いします」「わかりました」というのが「口約束」でなされ、「何枚の長編なのか」「納期はいつなのか」「納期に遅れればどうなるのか」といったような細かい取り決めを、事前に交わしたりはしない。
要は「信頼関係」という業界慣習に基づいての、契約書なしでの契約がなされるので、業界自体が好景気で余裕のある時代にはそれでも良かったのだが、不況になってかたがた余裕がなくなってくると、それが元でトラブルに発展することも、ままあるのである。

つまり、アニメ業界も、そうした「古き良き」時代の慣習を残しているために「融通がきく」反面、「立場の強いものの無理が通ってしまう」ということにもなる。
言うなれば、経済的に力の弱い者同士が助け合うことで成立していた小規模経済の業界に、資本の豊かな大会社が「金儲け目的」一本で入ってきて、札束で頬を叩くような態度で、しかしそれほどの金も出さずに、下請けを好きにこき遣うというようなことも起こるのだ。
本作『SHIROBAKO』のテレビシリーズを論じた拙レビュー「水島努監督『SHIROBAKO』:アニメ・クリエイターたちの、熱き息吹を感じよ!」で、アニメ業界における、巨大スポンサー企業の「専横」ということを紹介したけれども、本作『劇場版 SHIROBAKO』の冒頭でも、それに類した事件せいで、テレビシリーズの成功で上り調子に見えた「武蔵野アニメーション」は、一転、社長が引責退任し、共に闘った仲間の多くも外部に出ざるを得なくなるという大打撃を受けたあとの、なんとも寂しい社内風景が描かれる。
本作の冒頭で描かれるこの事件とは、大手制作会社が「テレビシリーズ」の制作を請け負い、そこで企画を立て、そこの監督が基本的な方向性を決めて、その後の制作実務を下請けに配分して制作させる、という制作体制の下で起こった。
つまり、テレビアニメではよくあることだが、「各話」制作を、下請け会社のあちこちに外注して、実質的な制作を下請けに任せるというかたちである。
ところが、製作の発注元であるテレビ局などの都合で、その作品の制作が丸ごとキャンセルされる。すると、制作を請け負った会社も損害を受けるが、その皺寄せは当然のことながら下請けにも及ぶ。
元請け会社が、発注元から、なにがしかの補償を受け取ったところで、すでに制作を始めていた下請けの被害までは、とうていカバーしきれない。そもそも、そんな事態など想定していないから、そんなことになってしまえばお手上げで、「ごめんなさい」とひたすら頭を下げてまわるしかないということになる。
下請けとしてすでに制作作業に入っていた「武蔵野アニメーション」も、社内での制作作業はすべてストップし、すでに仕上がったものさえすべてがゴミとなる。またそれに止まらず、孫請けとして外部発注していた仕事についても、十分な補償ができないという事態に立ち至ったため、責任を取って社長が退任し、さらにこの事件で会社としての体力を大きく削がれた「武蔵野アニメーション」は、正社員として抱えるスタッフを減らさざると得なくなったのである(つまり、社員スタッフが、独立して外注プロダクションをつくったり、よそへ移ったり、個人事業主になったりしたわけだ)。

毎日行われていた「武蔵野アニメーション」の朝礼は、テレビシリーズの終盤では、社長以下のスタッフ十数人のにぎやかものであったのに、本作では、その朝礼に集まるスタッフが半分ほどになっており、「制作進行」のチーフになっていた主人公の「宮森あおい」は、その寒々しい現実に呆然としている。
「あんなに頑張ったのに」「成功をみんなで喜び合ったのに」「何も悪いことなんかしていないのに」、その結果がこれだなんて、あんまりだ…。
意気消沈するあおいに対し、残ったベテランスタッフは「落ち込んでいる暇はない。今はまた、ここからやれることをやっていくしかないんだ」と励ますが、あおいのショックは、それでも晴れない。
元社長の「丸川正人」は、趣味を生かしてカレー屋になっていたが、その店を訪れたあおいは、丸川の懐かしいカレーを食べながら、思わず涙をこぼしてしまい、「社長が戻ってきてくれたら」などと、つい弱音を吐いてしまうが、丸川はそれを諌めて、これからは君たちがアニメの火を引き継いでいかなければならないんだと励ます。
そんな折に持ち込まれたのが、劇場用長編アニメーションの企画である。ただし、これは曰く付きの作品だ。
公開日の決まった作品の制作を受けた元請け会社で脚本作りが進められていたが、これが押しに押して、公開まで残すところ1年しかなくなってしまった。普通なら2〜3年かかる作業を残して元請けが投げ出してしまったこの仕事を、丸ごと引き受けるか否かということになり、現場の責任者として、その判断を委ねられたあおいは、この作品に会社の再起をかけようと決意し、かつて一緒にテレビシリーズを作ったスタッフを結集して、タイトなスケジュールでの制作に挑み、そしてそれを成し遂げる。一一本作は、そんなお話である。

途中、完成も見えてきた段階で、もともとこの「劇場用アニメ」を受けていた元請け制作会社のプロデューサーから、いまさらのように「作品タイトルをそのまま使うのなら、うちの制作ということにしてもらわないと困る。そうでないのならタイトルを変えろ」という難癖がつけられるというピンチがある。
なぜ、タイトルをそのまま継承したのかといえば、それはすでに数年も前に、そのタイトルで「予告」の打たれた作品だったからで、そのタイトルを活かした方が良いだろうという判断から、元請け会社のつけたタイトルだけを引き継いだのだ。
元請け会社は、自分たちが投げ出した作品が、そのタイトルで制作されるということを当初から承知しており、その時は何も言わなかったのに、作品が完成しそうだとなると、いきなり「もともと、うちの作品だ」と、上前を撥ねるようなことを言い出したのだ。
この件については、いかにも「ドラマ的」なかたちで、気持ちよく解決するのだが、本作を観ていても思うのは、今回もやはり「資本主義リアリズム」という現実の「いやらしさ」である。
テレビシリーズでの「スポンサー企業」の無理難題描写についても、私は、前記レビューで、
『結局、このオーディション会議は、上のストーリー紹介にあるとおり、ベテラン「音響監督」の誠実で説得力ある「一言」で決着がついたかのようにここでは書かれているが、じつは、正確にはそうとばかりは言えない本編描写になっている。
と言うのも、この会議は10時間以上も続いて紛糾した結果、スポンサー企業の面々が疲れ果てて、妥協的に諦めたという描写がなされており、「音響監督の一言」はあくまでも、作劇上のアリバイにすぎなかったのだ。要は、制作サイドの粘り勝ちだったというのが実際のところだし、だとすれば、現実のこうした会議では、いつもこううまく「粘り勝ち」できるわけではないだろうなと、その「苦労」が容易にしのばれたのである。』
と書いて、「現実には、いつもこうは、うまくはいかないのだろうな」ということを指摘したのだが、それは、この『劇場版』での「大手制作会社」の無理難題でも同じことだ。
下請けが、こうした大手やスポンサー企業の横暴に、現実においてもどれほど苦しめられているのかと思えば、胸の痛みを禁じ得ない。
本作には、少々話題になった、あおいの妄想である「ミュージカルシーン」がある。
「あおいの妄想」というのは、テレビシリーズからあったもので、要は、あおいのマスコット人形である「ミムジー&ロロ」(ゴスロリ少女とシロクマのぬいぐるみ)が、あおいが一人のシーンで動き出し、その時のあおいの内的葛藤を代弁するのである。
ミムジーが「こんなことやってられるか!」というような毒舌ツッコミ役で、ロロがそれをなだめる役柄なのだが、本作『劇場版』では、そうした「ミムジー&ロロ」のやり取り(小芝居)には止まらず、この一人と一匹が、あおいとおなじ人間大にまで巨大化すると同時に、そのほか、テレビシリーズで「作中作」として登場した『山はりねずみアンデスチャッキー』の動物キャラクターなどが多数登場して、あおいらと共に歌い踊るという、そんな「妄想シーン」だ。

これは「劇場版アニメ」の始動にあたっての、あおいの「心象風景」だと考えて良いはずなのだが、これが必ずしも、目標が定まって「やったー!」とか「やるぞー!」といった、わかりやすく「明るく前向き」なものとは、ちょっと違う印象を与える。
あえていうなら「躁」状態、という感じなのだ。
このことを、アニメ系VTuberでライターの井中カエルが、ネット記事「『劇場版 SHIROBAKO』は時代を表現する作品に 水島努監督の作家性を3つのポイントから探る」の中で、次のように書いている。
『 (※ 本作「劇場版」の)2つ目の魅力は映像と音楽の合わせ方だ。水島努作品からは一種の狂気ともいえる迫力を感じることがあるのだが、それは今作でも健在。中盤のミュージカル描写では、過去の名作アニメやアイドルアニメなどの特徴を捉えたオリジナルキャラクターたちが、TVアニメ版でも話題となったエンゼル体操を踊っている。何十人ものキャラクターが一斉にうさぎ跳びをしながら歌う姿は、冷静に考えてみるとなかなか奇怪な映像になっている。何も知らずにそこだけを抜き取って鑑賞した場合には、コメディシーンや、あるいはホラー描写のように見えるのではないだろうか? しかし本作を鑑賞している最中では感動シーン、あるいはワクワクするような喜びの多いシーンとなっている。』
そう、「狂気」じみていて、どこか「不穏な空気」さえ湛えたシーンになっているからこそ、井中は『ホラー描写のように』も見えると書いているのであろう。
つまり、この時のあおいは、実際のところは、ギリギリに追い詰められているのである。
「劇場版」の制作というのは、今の「武蔵野アニメーション」にとっては、言うなれば「大博打」だからだ。これで失敗したら、今度こそ「社長交代」では済まず、会社自体が倒産の危機にさらされるかもしれない。
そんな「大博打」を、あおいは自分の判断で引き受けたのである。だから、彼女のこの時に気持ちは、単純な「やったー!」とか「やるぞー!」といったものではあり得ない。
ドストエフスキーの『賭博者』だったか(阿佐田哲也の『麻雀放浪記』か)で、覚悟の賭けに出た賭博者の手が痺れるといった描写があったと思うのだが、この時のあおいの頭の中は、言うなれば、このような「しびれ」にとらわれていたということなのではないだろうか。
もう、嬉しいのか悲しいのか、楽しいのか怖いのかよくわからない。それでも過剰に感情の亢進した状態である。そんな心理状態を、あの「人間大になった擬人化された動物たち」と、あおいたちが踊り狂うミュージカルシーンというかたちに表現していたのではないだろうか。
だからこの物語も、最後はハッピーエンドで終わるのだけれども、それだって、そう一筋縄ではいかない。
なんとか、納期内に完成させ、それなりの作品に仕上がったのだが、監督の表情が今ひとつ冴えない。あおい自身も何か物足りないものの残るラストになってしまっている。
それで、ついにあおいは、監督に「これで本当にいいのですか。監督はこれで納得しているのですか?」と詰め寄り、監督もついに「完全に納得しているわけではないけど、でもこれ以上、自分の勝手でみんなに無理を言うことはできない。みんなに迷惑をかけることはできないよ」と漏らすのだ。
当然、そこで、あおいを中心に「やろう。ギリギリまで粘ろう」ということになって、ラストの部分が作り直され、今度こそ満足のいく作品を仕上げることになるのである。

で、その作中作『空中強襲揚陸艦SIVA 』のラストシーンなのだが、これは「大勢の子どもたちを乗せた宇宙船を脱出させるために、迫り来る多勢の敵を、主人公たちが体を張って食い止める」というものだ。
動物キャラやロボットキャラを含む5人ほど主役キャラは、何百人という敵を食い止めるべく体を張って戦う。そのために、明らかに動物キャラやロボットキャラは深手を負って、いかにも戦死しそうな描写だし、メインの二人(人間とウサギキャラ)が、子供たちの乗った宇宙船が無事出航するのを見届けるのものの、子供らを乗せた宇宙船の脱出した後の、「宇宙基地」(?)の大爆発が描かれる。つまり、主人公たちは、たぶん、全員死んだのであろうということが暗示されるラストなのだ。
で、水島努監督と同世代のアニメファンである私には、こうしたラストに、いくつもの既視感がある。
例えば、テレビシリーズ『無敵超人ザンボット3』(富野喜幸監督)の最終回。あるいは劇場版長編作品である『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』(舛田利雄
ほか監督)。
いずれも、大切なものを守り「未来に希望をつなぐために」、あえてその身を犠牲にする、ヒーローたちの姿を描いた作品だ。

だが、これは、言うなれば「武蔵野アニメーション」を存続させるために、引責辞任をした丸川社長と同じことなのではないか。
若いスタッフたちを守るために、その責めを一身に引き受けて、現場を去っていったのである。
だがまた、このラストが意味するのは、単に、本作中の丸川社長ひとりの話ではなく、過酷な環境にある下請けアニメ制作の現状を、象徴した「ラスト」なのではないだろうか。「夢をつないでいくために、誰かが犠牲にならなければならない」という「現実」である。
つい先日レビューを書いた、『ジャイアントロボ THE ANIMATION −地球が静止する日』(今川泰宏監督)の作中で問われていたのが、まさにこの「時代は、犠牲なしには越えることができないのか?」ということであった。
そして、この名作を残し、一時期は大変な活躍を見せた今川泰宏監督が、今では「どこで何をしているのだろう?」と噂される存在になってしまっている現実に、私は、アニメ制作の現場において「夢を追う」人たちの、厳しい現実とその運命を見ずにはいられない。
一部には、作品が大ヒットして「巨匠」呼ばわりされ、潤沢な資金を得て大作を作り、それがまたヒットしてという人もいる。
だが、そんな人が、今川監督や本作の水島監督より、特に優れているようには、私には見えない。
テレビシリーズ『SHIROBAKO』を論じた前期のレビューでも書いたとおり「良い作品が、必ずしもヒットするわけではない」し、たった一度の興行的失敗せいで、活躍の場が奪われたのではないかと思える優秀な作家が思い当たらないでもない。そんな現実が、たしかにあるのだ。
よく「政治経済」の世界では「経済的二極化」ということが言われる。「1%の大金持ちと、99%の貧乏人」社会である。
だが、これは何も、一般社会だけではないのではないか。アニメ制作の世界だって、ごく一部の人が持て囃され、潤沢な資本が投入される一方、大半のアニメ制作者たちは、いまだに低賃金に甘んじて、ささやかな「夢をつないでいる」という現実がある。

宮崎駿の新作も良いだろう。新海誠に新作も良いだろう。だが、そうした華やかな表舞台の影には、99倍では済まない数のアニメ制作者たちの自己犠牲的な奮闘のあることを、少なくとも「アニメファン」だけは心に留めて、応援し続けなければならないのではないだろうか。
○ ○ ○
今年4月から、水島努監督の新作テレビシリーズ『終末トレインどこへいく?』が始まるという。これも『SHIROBAKO』と同様、オリジナル作品だ。

そして、作品の公式ホームページの末尾には『作品利用、コラボ等のお問い合わせはこちら』という「お問い合わせフォーム」へのリンクがある。
私はこれを見て「ああ、こうして地道に資金集めをしているのだな」と、ため息をついてしまった。
いま流行りの「クラウドファンディング」でも、それなりの資金は集まるかもしれない。しかし、それはたぶん「一度きり」のことだろう。それでは「希望を未来につなぐこと」はできない。だから、このような地道な資金集めがなされているのではないだろうか。
このホームページで現在公開されている「PV第2弾」のラストは、主人公の次のようなセリフで締めくくられている。
『いいことも悪いことも、これまでのことは今につながっててて、これからのことになるんだよ。』
「終末トレイン」とは、もしかすると、今の終末世界を生きる「アニメ制作会社」の比喩なのかもしれない。
一一だとすれば、その行先が明るいものであらんことを願わずにはいられないのである。
(2024年1月23日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
