
メタ・フィクションとマゾヒスト:サド、澁澤龍彦、中井英夫、大西巨人
(※ 再録時註:「知識人はマゾヒストである」とは、いかなる意味か?)
今日は、なぜ私が『虚無への供物』(中井英夫)、『匣の中の失楽』(竹本健治)、『陰獣』(江戸川乱歩)、『宇宙戦艦富嶽殺人事件』(辻真先)、『怪奇小説という題名の怪奇小説』(都筑道夫)といった「メタ・フィクション(入れ子構造の自己言及的作品)」に惹かれるのか、一一この謎について、常日頃から「知識人はマゾヒストだ」と言って、冗談半分ながらも表明している、私自身の「マゾヒスト」性の側面から、その深層を究明してみたいと思う。

……とは言っても、これは、以下に引用する澁澤龍彦(あるいはジル・ドルーズ)の言葉に、その大半は説明し尽くされている。
『 しかし(※ ジャン・)ポーランの主張にもかかわらず、少なくとも小説家としての(※ マルキ・ド・)サドには、マゾヒストの特徴はまったく現われていないと私は考える。ジル・ドルーズが『マゾッホ紹介』で明らかにしてように、サドの小説のなかで次から次と矢継ぎ早に展開される残酷場面には、宙吊りを好むマゾヒストの想像力が楽しみを味わっている余地がほとんどない。サドの作中のリベルタンたちは、あたかも自動人形のように機械的に残虐行為を反復実践して、飽くことを知らないのである。ドルーズは次のように述べている。
「マゾッホにおける審美的かつ演劇的な宙吊りは、サドに現われているがごとき機械的かつ累積的な反復とは対立している。誰でも読めば分るだろうが、宙吊りの芸術は必ず読む者を犠牲者の側におき、犠牲者との一体化を強いるのに対して、反復を積み重ね、その速度を早めるというやり方は、むしろ読む者を拷問者の側に押しやり、サド的拷問者との一体化を強いるものなのである。」
これはなかなか注目すべき指摘で、おそらくサドの小説を読んで不満を感じるところの、多かれ少なかれマゾヒスティックな資質をもった人間の気持を、的確に代弁しているのではないかと思う。サド裁判に出廷した証人たちの証言にもはっきりと現われていたように、サド文学を春本から遠ざけているのは、その哲学的な長広舌もさることながら、何よりもまず、その「機械的かつ累積的な反復」なのだ。同じことの繰り返しに、たいていの読者はいい加減うんざりしてしまうのである。』
(澁澤龍彦『サド公爵 あるいは城と牢獄』所収、「サドとマゾッホ」より)
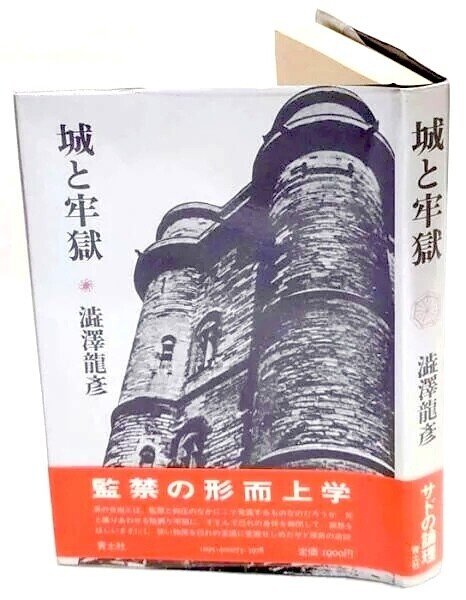
私の「知識人はマゾヒストだ」という言葉を、もうすこし丁寧に言いなおすと「想像力に乏しい知識人などありえない。したがって知識人はマゾヒスト的である」ということである。
では、「マゾヒスト的」とはどういうことなのかというと、それはジル・ドルーズも指摘しているとおり「眼前の現実に没入するのではなく、その向こう(彼岸=彼方)を想像力によって幻視して、そこに自身を賭ける人間」の態度だということになるであろう。
つまり、サディストというのは「目の前の快楽」に没入することができるから『機械的に残虐行為(※ 性的な行為)を反復実践して、飽くことを知らない』でいられるのだが、マゾヒストは常にその向こうを見てしまうので、すぐに退屈してしまうのだ。まただからこそマゾヒストは、常に眼前の事実を「想像力によって補完」しなければ、満足を得られないのである。
例えば、一般に想像されるであろうマゾヒストの典型は「女王様に鞭打たれて、被打の快感にのたうちまわるマゾ奴隷男」といったパターンであろう。
だが、この場合、マゾ奴隷役の男性は、決して「鞭の痛み」を「そのまま快感」として感じているわけではないし、まして女王様役の女性を、その力関係において「恐れている」わけでもなければ、彼女に「服従している」わけでもない。
そうではなく、むしろマゾ奴隷役の男性がそこ(=局限化された演技)に見い出しているのは、「達成されない愛(=快感)」という物語(フィクション)の快楽なのである。
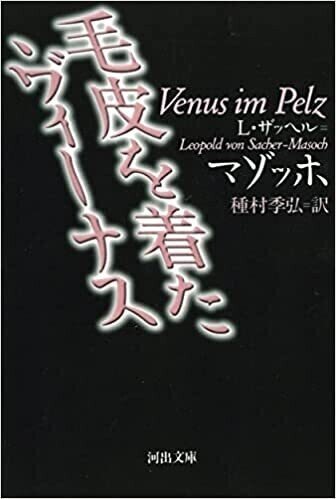
言うまでもなく、「快感」というものは一般に「達成してしまえば、それでお終い」だ。
だから、その事実を想像的に先取りしてしまう彼は、「性的行為」の現実においては、「欲望充足」を可能なかぎり遠ざけ(=「自分は見苦しい(鞭打たれるべき)豚である」から「貴い女王様には触れられない」等の受苦的禁止を自らに科し)、欲望の充足が達成されないことによって、逆にその想像(=性的妄想=性的快感)を強化して楽しむのである。
だから、SMプレーにおける「女王様」とは、その見かけに反し、所詮は「マゾ奴隷男」に従属し奉仕する、「脇役」に過ぎないのだ。
ともあれ、「理想状態」を「遠ざける」ことによって純化し、その上でそれを享受しようという、マゾヒストの想像力は、文学においては、おのずと「決定不可能性」という性格として現われてくる。そして、そうした性格を端的に体現する形式こそが、他ならぬ「メタ・フィクション(入れ子構造の自己言及的作品)」なのだ。
例えば、メタ・フィクションの典型的な形は、私が最初に列挙した『虚無への供物』や『匣の中の失楽』などに代表される「私が登場する小説を書く私、が主人公である小説」というパターンであろう。
このような形式を採った場合、今ここの「私」は、果たして「作中の私(小文字の私)」なのか「作外の私(大文字の私)」なのかが、にわかに決定不可能となってしまう。なぜなら、少なくとも「作中の私(小文字の私)」は、「作外の私(大文字の私)」が意図的にそうさせないかぎり、「作外の私(大文字の私)」を認識することが出来ない。事実、「作中の私(小文字の私)」に、作中人物だという自覚を与えうる(神のごとき)作中の作者である「作外の私(大文字の私)」も、自分が「本当の作者」によって想像された虚構でしかないという事実を認識することはおろか、疑いを抱くことすらできないのだ。
そうすると、今ここでこの文章を書いている私や、この文章を読んでいる貴方が、我々には認識し得ない(非知の)存在、「神」とも呼ぶべき実在によって、好きなように動かされているだけの「作中の駒」でしかない、という可能性を否定しさることが、果たして可能なのであろうか。
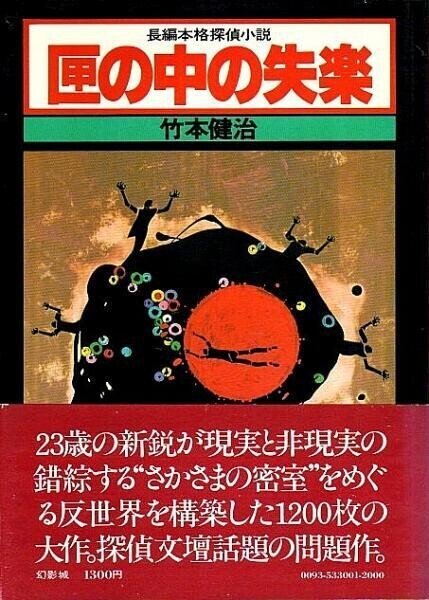
つまり、このような状態こそが、ジル・ドルーズのいう、マゾヒストにおける『審美的かつ演劇的な宙吊り』なのだ。
自身から着地点(=支点)を奪い、その『宙吊り』の苦しみに喘ぐことで、現実に堕することを退け、理想を幻視し続ける。それが、典型的なマゾヒストの態度なのである。
例えば、私はしばしば他人を厳しく批判するので、人によっては私のことをサディスト的だと思うだろう。
だが、私が厳しく批判するのは、たいがいは、想像力の欠落した人間であり、そうした意味で、私の批判対象こそがサディスト的な人間なのである。その証拠に、私はしばしば「そういう自分はどうなのだ?」という形で、批評者に(逆ねじ的に)「反省」を促す。私にすれば、彼らは眼前の対象に没入し過ぎるために、自分を顧みるということがまったく出来ておらず。そのあたりが、私の勘に触るのである。
具体例を挙げれば、私の「大西赤人批判」などもそのようなパターンで、あの場合、大西赤人本人とすれば、映画『スターリングラード』において「不当に悪者として描かれたソ連軍」を、彼は擁護したつもりなのであろう。
しかし、私にすれば「では、貴方はこれまで、さんざ悪役を押しつけられてきたドイツ軍を、少しでも擁護したことがあるのか」ということになるのだ。
で、結局、私には、大西赤人の「弱者擁護」の批評は、「眼前の事実に縛られて、自己の姿を顧みない」、遠近感を失ったサディストの批評でしかない、と映るのである。

だから、マゾヒストたる私が、批評者・批判者(あるいは『読者』)に要求するのは、被擁護者としての「弱者・被害者」との同一化なのである。一一批評者・批判者(あるいは『読者』)は、一方的な「優位」に立ってはならない。ジル・ドルーズの言ったとおり、マゾヒストである私は『犠牲者との一体化を強いる』のである。
私が、オタク的な『視聴者=特権的な批評者=享受者』というお気楽な立場に、強い不快感を覚え、これに「おまえは何様のつもりだ?」と(『新世紀エヴァンゲリオン』のラストにおける庵野秀明的に)反発するのも、同じ理由だ。
マゾヒストたる私は、常に相手に対し「自己言及」としての「反省」を促し、「眼前の対象への没入」に冷水をかけようとするのである。
だが、その結果、そんな私の態度が、サディスト的な印象を与えるものになるのだとしたら、それはいささか皮肉な逆説だと言えよう。
しかし、サディスト的外見によって批判されやすい立場におかれるのであれば、もちろんそれはそれで、マゾヒストたる私の望むところでもある。「私についての私の理解」など信用するに足りないとする「マゾヒスト」的決定不可能認識(=自己懐疑)に立つ私は、だからこそ他者からの批判(=鞭)を喜んで受けうるのである。
澁澤龍彦は、私の尊敬する作家の一人だが、彼の偏愛するマルキ・ド・サドの小説は、私にはまったく理解不能なものであった。
しかし、上に引用の一文によって、私は、なぜ自分がサドを理解できなかったのかを悟ることが出来、それと同時に、私が澁澤龍彦の何に惹かれてきたのかも、はっきりさせられた。
澁澤龍彦が、サド的なものに惹かれるサド的人間だとすれば、私が彼に惹かれるのは、自身との共通点ではなく、その反対の「相違点」によってであろうことは、容易に推測できよう。
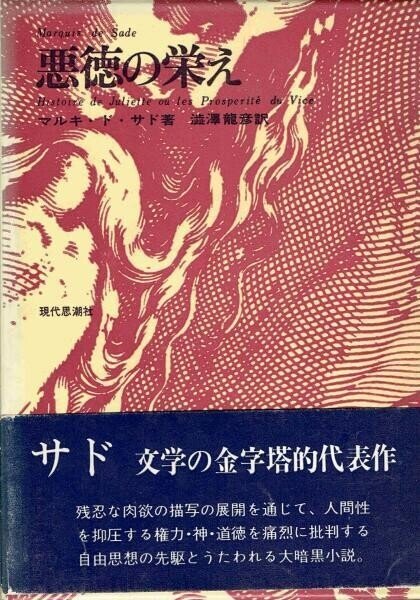
では、私は澁澤龍彦の何に惹かれたのか?
一一それは、彼自身の言う「幾何学的精神」なのである。つまり、曖昧さを排して、明確な輪郭に象られた、知性・精神。曖昧な(肉質の)生物(生命)よりも、硬い鉱物(死物)に惹かれる精神。澁澤龍彦の精神・知性とは、そういうものであり、それは私のマゾヒスト的(抽象思弁的・非決定的)精神の中には、存在しないものなのである。つまり私は、澁澤龍彦という「彼方」に惹かれていたのだ。

しかし、ここには、「自己言及的」に自身を懐疑し、「決定不可能性」に固執するマゾヒストだからこそ持ちうる、「反対物」希求という美質も見て取れよう。
これは、サディストにはとうてい持ち得ないもので、事実、澁澤龍彦は「もっと幾何学的な精神を!」と他者に要求する自己主張はあっても、「曖昧な抽象的思弁」や「決定不可能性」を自身に科するようなところは、ほとんど見受けられない。そして、そここそが、私が澁澤龍彦に「疑問と不満」を感じるところでもあったのだ。
たしかに、澁澤のクリアな認識や態度には、一種の憧れを感じる。けれどもその一方で、私は「そんなに簡単なものでもないでしょう、澁澤さん?」という気持ちも否定できなかったのだ。
私が、まず中井英夫に惹かれたのは、彼が徹底的にマゾヒスト的な人間だったからであろう。そして、近年、私が(中井英夫とは対照的な)一見「ゴリゴリの現実主義者」である大西巨人に惹かれ、「心の師」とまで仰ぐようになったのも、じつは、大西がその「現実主義的論理思考」によって探究する対象が、いつでも(『神聖喜劇』『天路の奈落』『迷宮』『深淵』といったタイトルからも明らかなとおり)「彼方」にあるものだからなのである。
つまり、大西巨人もまた、見かけによらずマゾヒスト的人間であり、またそんな人だからこそ、「狷介孤高」と呼ばれ「厳格主義者」と言われながらも、独りで自分の道を歩んでこれたのであろう。

私は、冒頭に例示したメタ・フィクション小説のなかに、大西巨人の作品を挙げなかったが、これは「一見してそれとわかる作品」を例示したかったからに過ぎず、大西巨人の諸作における「メタ・フィクション」性の存在は、明白な事実である。
例えば、大西作品の主人公は、たいていの場合、大西巨人その人を連想させる人物として描かれている。しかし大西巨人は、そうした自作が、「私小説」的作品だとか「自伝的作品」だと理解されるのを、強く拒む。これは、なぜなのか。
一一思うにそれは、「私小説」的作品や「自伝」的作品というものが、基本的には、「自己言及的」認識や「決定不可能性」の認識、つまり『「私についての私の理解」など信用するに足りないとする「マゾヒスト」的決定不可能認識(=自己懐疑)』を欠落させているが故に成立するもの、だからなのではないだろうか。
マゾヒストは、なぜ『「メタ・フィクション(入れ子構造の自己言及的作品)」に惹かれるのか』。一一この問い方は、たぶん「さかさま」なのであろう。
自己言及・自己懐疑(=反省)を好む精神、つまり「メタ・フィクション」的な態度を好む(演劇的)精神が、性的な想像力の局面では「マゾヒスト的」なものとなる、というのが正解なのではないだろうか。
逆に言えば、『虚無への供物』や『匣の中の失楽』といった「メタ・フィクション」的作品を理解できない人とは、どういう精神の持ち主なのか、一一それも、もはや明白なのではないだろうか。
例えば、澁澤龍彦は、中井英夫の端正な短編集『幻想博物館』所収の諸作などを愛好しながらも、中井英夫の代表作である長篇『虚無への供物』について、あまり積極的な発言をしなかったのように見受けられる。
これはたぶん、基本的には、澁澤が『虚無への供物』の魅力を理解できなかったからだろう。

(『とらんぷ譚』第1部『幻想博物館』、講談社文庫の解説は澁澤龍彦)
澁澤は、『虚無への供物』の細部の魅力は認め得たものの、「メタ・フィクション」としての自己言及性や自己懐疑、特に中井英夫的な「演技過剰とも見える、自己憐憫」的な部分には、うんざりさせられる方ではなかったかと、そう私は思うのだ。
たぶん、人間にはサディスト的な側面(現前への没入)とマゾヒスト的な側面(彼方への希求)という両面があり、どちらも欠くべからざるものなのであろう。
しかし、一般論としていえば、私はやはり「知識人はマゾヒストだ」という主張を、採るものなのである。
(2022年6月27日)
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
