
平山瑞穂 『さもなくば黙れ』 : 家畜たちの 〈安心・安全〉な檻
書評:平山瑞穂『さもなくば黙れ』(論創社)
『何よりもおそろしいのは、普通の人々だ!
コロナ禍から10年が経過した日本の社会--。バイザーを利用した相互監視システムが構築され、どんな理由であれ、適合できない人々は「アンプラ」と呼ばれた。不適合の人々は〝静山泊〟に集まるが、地域住民による排斥運動に悩まされる。彼ら・彼女らの行く場所はあるのか?
人間の馴致しやすさと排斥への欲望を描いた書き下ろし小説。』
(Amazon掲載の内容紹介文より)
装着した者の各種生体情報を収集すると同時に各種の情報を提供してくれる、眼鏡型の端末機、通称「バイザー」。
当初は、任意であったものが、やがて公の場での装着が法的な義務となり、生体情報により「劣性と判断された者」あるいは「バイザーに適応した生活のできない者=接続不適応者=アンプラグド(アンプラ)」は、「相互監視システム」による情報共有によって、社会的に「差別」されるようになる。
簡単に言えば、知的・感情的に「水準に達しない者」、あるいは「安心・安全な社会」の基盤となるバイザーの装着に「適応する能力のない者」は、何をするかわからない「不気味な存在」と見做され、「犯罪者予備軍としての危険人物」と見られるようになっていくのだ。
この物語は、そんな「監視社会化」への警鐘を鳴らすと同時に、内容紹介文にもあるとおり「人間の馴致しやすさと排斥への欲望」を描いた作品だと言えるだろう。

法的建前としては「刑罰を受けて罪を償った者は、完全な人権を保証される」はずなのだが、例えば「前科者」はその「前科」記録において差別されるし、昨今「性犯罪者」などには特に厳しい目が向けられており、罪を償っても再犯の恐れはあるから「GPSを埋め込んでから、野に放て」などという議論も、共感をもって語られる。
実際、幼い子供を持つ親にとっては「小児性愛犯罪者」の存在は、それがほとんど「治らない病気」であるがゆえに、罪を償おうが償うまいが、存在そのものが脅威であり、悪魔や怪物に類する存在だと感じられるのも、あるいはやむを得ないのかも知れない。
しかし、現に犯罪を犯した「犯罪者」と、犯罪を犯すかも知れない犯罪者予備軍としての「危険人物」との同一視が、極めて危険だというのは、ちょっと想像力を働かせさえすれば、容易に気づき得ることのはずである。
一一にもかかわらず、そんな理性的な想像力を働かせることも出来ず、主観的な感情に駆られて「性犯罪者など、全員、断種してしまえ!」などと叫ぶ人は、その「非理性性=感情抑制能力の欠如」において「危険人物」であるから、「犯罪者予備軍」としてマークし、治安のために、世間に知らしむるべきである。
無論、そうした人物の子供は、同様の性格を遺伝的に受け継いでいる蓋然性が高く、事実としてその兆候が「観測」されるならば、その子は「隔離した上で、特別な措置を施し」て「健全な人間」に育てるべきである。一一といったことになったらどうだろう? 「そんなことにはならない」と、本当言えるだろうか?
本書に描かれるのは、統治者としての国家が、国民を支配しやすいよう馴致するために、「便利」あるいは「安心・安全」のためだとして、個人情報の提供を求める。そして、そうして得た情報を国民に提供して、国民どうしの「相互監視システム」を構築することで、国家は懐手にしたまま国民を支配できる。一一そんなシステムが描かれる。
統治者の期待どおりに反応して、「異端者排除」に奔走する「愚かな人たちの群」。
しかしそれは、既にしばしば、私たちの目にするところのものなのではないだろうか。

(在特会のデモ)

(在特会が激しく反応した「カルデロン一家」についての人道報道)
もちろん、本書の視点人物たる主人公は「被差別者=社会的異端者=マイノリティー」の側であり、読者は迫害される主人公の側に同情できるように描かれてはいるものの、現実には、読者の多くは、疑問も持たずに「決まりは決まりだから」と言って憚らない「迫害者」の側の人間であろうし、その事実に気づかないような読者こそが、「迫害者予備軍」あるいは、すでに「無自覚な迫害者」そのものなのではないか。一一少なくとも、そうした自己懐疑を持ってしかるべきであろう。
○ ○ ○
こうした「監視社会」問題を扱った本としては、私は、次の2冊について、すでにレビューを書いている。
(1)はノンフィクション、(2)は「SF」小説であり、無論フィクションである。
(1) 梶谷懐、高口康太『幸福な監視国家・中国』(NHK出版新書)
(2) 小川哲『ユートロニカのこちら側』(ハヤカワ文庫)
(1)で紹介されているのは、すでに中国でかなり進んでいる「監視社会化」であり、この本で問題になっているのは、「中国における監視社会化は、悪いことばかりではなく、各種の便益を伴うために、進んでその庇護化に入る国民が少なくないという現実」である。そしてその意味では、「危険人物情報」を提供してくれる、本書『さもなくば黙れ』で描かれた世界と、本質を同じくしていると言えよう。
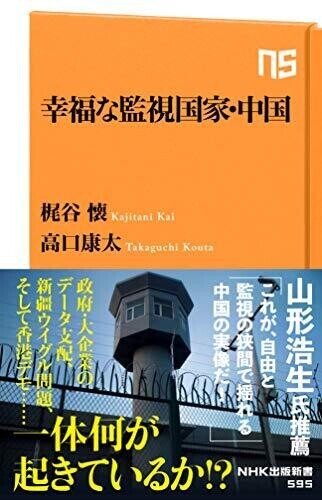
一方、(2)で描かれるのは、「国家が国民を監視化におく社会」ではなく、その「便益」のゆえに「国民の側から進んで監視社会を構築する、下からのディストピア」である。
ここでは、国家はなんら統治的意図を持たず、むしろ国民の方が「完璧な統治=完全に犯罪のない、安楽な社会」を求めているのだ。

このように、「監視社会」化の現実は、ジョージ・オーウェルが『1984年』で描いたような、わかりやすく嫌悪できる「ディストピアとして監視社会」ではなく、むしろ国民が「監視されることを望む」方向、つまり「ユートピアとしての監視社会」へと突き進んでいる。
だが、無論それは、迫害される「少数者」の存在に配慮する知性を持たず、自分の生活さえ安穏であれば、それ以上は何も考えない圧倒的多数の存在、を前提とした社会だとも言えるだろう。
従来は「ディストピア」として描かれたがゆえに批判の対象であった「管理社会」が、テクノロジーの発展によって「強制」を伴わない管理、「ナッジ(間接誘導)」的な管理社会に変わりつつあり、小川哲の『ユートロニカのこちら側』では、主人公たちの、管理社会に対する「人間の尊厳からの抵抗」は、既になかば「意地と諦めのはざま」でしか存在し得ないもののようだ。
だが、平山瑞穂の本作『さもなくば黙れ』の場合は、その視点が徹底して「迫害される少数者」の側にあり、社会がどのような方向に動いていようと、また、勝ち目のない戦いであろうと、それに我が身を投じて、抗い続ける者たちを描いている。
これは、間違いなく平山瑞穂の抜きがたい「個性」なのだろう。この作家にとっては「社会的現実の観察・描写・評価」が問題なのではなく、それに対する「私の感情」が物語を駆動するのだ。
一一そして、ことほど左様に、平山瑞穂は、不器用に「反時代的・反世界的な作家」なのである。
色々なパターンの小説を書くことができる器用さと文章力を持ちながら、しかし、結果として「売れる小説」が書けない、不器用な作家。
それは多分、彼が描きたいのは、本質的にエンタメではないからだろうし、この世界の安住する読者のために物語を紡いでいるわけではないからであろう。
平山瑞穂とは、いつか憧れた「あちら側の世界」からの、孤独な流謫者なのかもしれない。
(2022年3月3日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
○ ○ ○
