
ジャン・コクトー 『コクトー詩集』 : 『僕』を 彼岸へ
書評:堀口大學訳『コクトー詩集』(新潮文庫)
私の耳は貝の殻
海の響きをなつかしむ
(P25)
ジャン・コクトーの詩というと、真っ先にこの「耳」を挙げる人が多いようだ。
たしかに、これなら「詩オンチ」の私でも、素直に「いいなあ」と思える。
だが、詩オンチな私の感じた、この「いいなあ」とは、果たして、正しい鑑賞による「正しい感受」なのであろうか?
「詩を楽しむのに、正しいも間違いもない。良いと思えば、それは正しく鑑賞したってことなんだよ」というご意見もあろう。私もそれが間違いだとは思わないのだが、しかし、ではその反対に「つまらないなあ」「全然わからないなあ」と感じた時、それは「作品」が不出来だから、つまらなかったり、理解不能だったりするのだと、その「責め」を、全面的に「作品」や「作者」に押しつけて良いものなのだろうか?
こう問えば、やはり多くの人は「それは行きすぎでしょう。読者の読解力、鑑賞力が足りないせいで、作品の魅力がわからないというのは、当たり前にあることです」とおっしゃるのではないだろうか。
しかし、だとすれば、コクトーの名作「耳」を「いいなあ」と感じた、その鑑賞は、果たして「正しい鑑賞」だと言えるのだろうか。もしかすると、「好意的な誤読」ということもありうるのではないだろうか。
ことに、コクトーのほかの詩の多くについて「イマイチだ」とか「よくわからない」といった場合、その人は「耳」だけを正しく鑑賞していたということになるのだろうか。それとも、「耳」を「好意的な誤読」をしていただけなのだろうか。あるいは、「耳」が飛び抜けて「よくできた作品」だったという話なのだろうか。

このあたりの判断がつきかねるので、私は、コクトーの詩が「理解できない」と思うのだ。「これはいい」「わかった」と思う作品であっても、その理解が「正しい」という自信が持てないのである。
それにもまして、「詩」作品の多くについて、このあたりの判断がつかないから、私は、自身を「詩オンチ」なのだろうと考えるのだ。
言い換えれば、「小説」や「エッセイ」や「論文」といった散文作品については、こうした「面白いが、私はわかっていないのではないか」あるいは「つまらないが、私がわかっていないだけなのではないか」という疑問が、ほとんど起こらない。それらについては「つまらないのは、これこれの理由があるからだ」と、説明がつくからである。
つまり「作品に、これこれの欠点があるから」とか「読者である私に、これこれの弱点があるから」だと、そうした説明ができるのである。
ところが、詩作品の多くについては、これができない。だから、私は自身を「詩オンチ」に違いないと思うのである。
今回読んだ、堀口大學訳の『コクトー詩集』(新潮文庫)には、次のような、コクトーによる「序」文が付されている。
『 序
詩人が自分のチャンスを試めす種類の詩がある、他の場合、彼はチャンスを延長しているに過ぎない。チャンスの詩は由来稀だ。これは霊媒の口から細胞原形質(エクトプラズム)が流れだすように詩人の手先から流れだす。詩人は片目で眠りながら降下を管制する。
深所の石像、曼陀羅華はこうして生れる。まま醜悪だったりするこの種の詩を集めたり、カットしたり、補強したりする仕事は、とかく徒労に終り易い。理由は読者というものが再認識を愛するからであり、新しい認識は読者を疲労させるからである、読者が或る詩の新味を玩味してくれる場合は極めて稀だ。』
私は、この「序」文の意味であれば、完全に理解できるという自信がある。要は、事実がどうあれ、コクトーが何を言いたかったのかを、正しく理解できたという自信が持てる、ということだ。
試しに、その意味するところを、わかりやすく解説すれば、次のようになる。
「 詩人には、自分の詩人としての独自性を示す類いの詩を稀に書けることがあって、それ以外の場合は、彼(詩人)は、そのチャンスを先送りにしながら、無難に詩作しているに過ぎない。滅多に書けない自分独自の詩というのは、昔から稀なものであり、言い換えれば、大半の作品は凡庸でしかありえない。そうした意味で、自身の独自性を発揮した稀なる詩というのは、霊媒の口からエクトプラズムが流れ出るようにして、詩人の手先から自然に流れ出す類いのもので、詩人は半覚醒の中でその詩を書きながらも、しかし半分は理性によって、その生み出されつつある詩を統御する。その意味で、独自性のある詩というのは、神がかりの中で偶然に生み出されるような類いのものというわけでもない。
滅多に手にすることのできない詩作品というのは、このようにして生れる。それは、かなり多くの場合に読者に醜悪な印象さえ与えるもので、この種の新しい言葉を拾い集めたり、カットしたり、補強したりする推敲作業は、とかく徒労に終わることが多い。なぜなら、読者というものは、知っているもの、見馴れたものを喜ぶもので、新しいもの、未知のものに接するというのは、それらがスッと自分の中に入ってこないものだから、それを呑み下すのに苦労を強いられ、疲れさせられるからだ。したがって、読者が、ある詩作品の新味を深く味わってくれる場合は、極めて稀なのだ。」
一一だとすればだ、多くの人が「コクトーの代表作」のようにして愛する「耳」は、果たして「新味が無いから理解しやすい、素人読者向きの凡作」なのだろうか?
コクトー自身は、この「耳」を、他人がいうほど良くできた作品だとは思っていなかったのだろうか。一一それとも、読者の大半が、この作品に込められた「新味」に気づかないまま、表面的な部分だけを見て、『再確認』の快楽に耽ってしまっているだけなのか。つまり、この作品を「誤読」しているのだろうか。
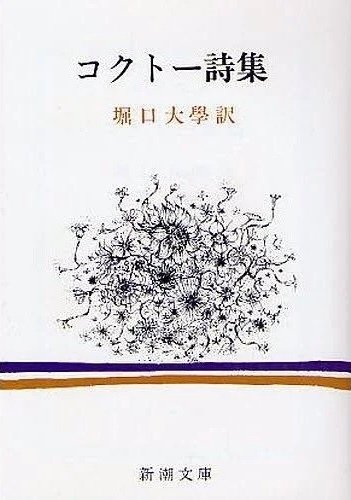
今の日本のご時世であれば「詩は、どう読んでもいいんだよ」という、「物分かりの良い正論」で終わってしまうのだろうが、しかし、そのような、作品「鑑賞」行為についての甘やかしが、今の日本の読者の「幼稚化」を促進している、ひとつの要因だとは言えまいか。
人間だれしも、自身の「能力不足」やその「限界」に直面するのは、つらいものだ。いくら頑張っても、才能がなければ、優れたアスリートや音楽家にはなれない。
それは、文学における「創作」は無論、「鑑賞」においてすら同じで、ある作品を鑑賞して「面白かった・面白くなかった」「感動した・感動しなかった」というような「鑑賞」しかできない読者と、その作品の「表現したもの」を正確かつ詳細に語ることのできる優れた「文芸評論家」とでは、明らかに「鑑賞能力」に差があると言えるだろう。
したがって、「作家」には能力的優劣はあっても、「読者」には優劣はない、などという「気休めの甘やかし」は、事実関係からして、本来は通用しない。
つまり、「面白くなかった」「感動しなかった」のは、必ずしも「作品」や「作者」のせいではなく、単に「読者」の側の「読解無能力」のせいである場合が少なくないと考えるべきなのだ。
だが、こうした「つらい現実認識」は、必ずしも、その「読者」にとっての、マイナス要因ではない。
なぜなら、自身の「弱点」を自覚することは、誤った自信(自信過剰)による失敗を回避させる「知恵」にもなるからである。
「己を知り敵を知れば、百戦危うからず」とは、そうしたことを指していう言葉なのだ。
無論、「弱点」を自覚したなら、そこを補強する努力は必要であろう。しかし、弱点を自覚して、その点についてどんなに努力したところで、才能がなければ、優れたアスリートや音楽家にはなれないのと同様、文学鑑賞においても、努力しても、もともと理解力のある人には及ばないという現実は、厳然としてある、と考えるべきだろう。
ならば、私たち読者は、いたずらに「わからないことの存在」を嘆くのではなく、「わからないことを知っている」ことに満足して、未練がましい自己過信による誤ちを犯さない賢明さを持つべきではないだろうか。そうして、限定された範囲においてさえ、人にできることは無限にあるのだ。
例えば、私は、長らく「詩オンチ」であるとの自覚において、コクトーの詩に接することをしなかった。どうせわからないだろうと思ってきたのだ。
だが、先日、コクトーの映画をいくつか観る機会があったので、そちらからコクトーにアプローチすることなら可能ではないかと考えた。「詩」は十全に理解できなくても、「映画」ならなんとかなるかも知れないと考えたのである。
そして、これは半ば目論見どおりに成功したと思う。
私は、コクトーの映画を通して、コクトーという作家を「ふにゃふにゃした肉質をそぎ落として軽快になった貝殻のように、白く硬質なものを希求する作家でありながら、しかし、その反面、彼の中には、その反対物である、重く暗い肉質を求める部分があったのではないか。つまり、彼の愛人であるジャン・マレーに象徴されるようなものに惹かれる、度し難いホモセクシャルな欲望である」といった具合に「理解」し得たのだ。

そして、今回、コクトーの詩集を読んでみようと思ったのは、「映画」で、ある程度の当たりをつけた分、全然わからないということもないのではないか、と考えたからである。一一で、その判断は間違っていなかった。
しかしまた、だからといって、コクトーの詩が「楽しめた」ということではない。そうではなく、「わからない」が、「わかりはした」に変わったのだ。
わかりはしたが、楽しめたわけではない。わかりはしたが、十全に鑑賞できた(わかった)わけではない、ということだが、この「わかる」ということの違いが、おわかりいただけるだろうか? 要は、「知解」はできたが「感受」しきれなかった、というほどの意味である。
ともあれ、「知解」のレベルにおいては、コクトーという「人」を理解することはできた。
私は、先のレビューで、
『コクトーは、自身が「硬質な軽さ」を求める人間であることを承知しながら、しかしその一方で、『オルフェ』に描かれたような「冥界」に惹かれ、『美女と野獣』で描かれた「毛むくじゃらの野獣」にも惹かれていたはずだ。つまり、「白」ではなく、「黒」にも惹かれた。』
と書いたのだけれど、果たせるかな、この『コクトー詩集』では、「黒奴(くろんぼ)」という言葉を、何度も目にすることになる。
「黒奴(くろんぼ)」という言葉は、今の日本語では「差別語」的な扱いを受けていて、使いづらい言葉になっているが、これを「黒人」などと言い換えることはできないだろう。なぜなら、コクトーがフランス語の「黒人」に当たる言葉を使った際に、その言葉にはたぶん、黒人を(白人より)下に見る「気分」が多少なりとも含まれていたはずだからだ。
だから、堀口大學が「黒奴(くろんぼ)」と訳した、この日本語にも、若干の蔑視的なニュアンスが含まれていたとしても、それはむしろ、正確な翻訳だということになるだろう。コクトーの原文が持っていた、そうしたニュアンスを「脱色」して、無難な日本語にしてしまったならば、それこそ改変的翻訳になってしまうからである。
しかし、私はここで、コクトーの「黒人」に対する蔑視を、批判したいのではない。
そうではなく、コクトーは「黒人」を、「白人のような美しさ」には欠けるものだと思いながらも、それに惹かれている自身を自覚していた、という点が重要なのだ。
つまり、「白人・黒人」という意味ではなく、もっと原理的な意味での「白と黒」。「白が象徴するもの」と「黒が象徴するもの」というレベルにおいて、コクトーは「白が象徴するものを希求しながらも、どうしようもなく黒が象徴するものに惹かれていた」という事実が、コクトーという人の、複雑な本質を理解する上で重要なのである。
『 放 列
太陽よ、僕は君を崇る、
野蛮人のように、海岸に腹ばって。
太陽よ、君は自分の三色版(クロモ)に、
自分の果物籠に、自分の動物たちに、光沢(つや)をつける。
僕の肉体を鞣してくれ、塩漬にしてくれ、
僕の大きな苦悩を追い出してくれ。
歯の光るあの黒奴(くろんぼ)は、
外側は黒く、内側ばら色だ。
僕は内側が黒く、外側がばら色だ、
逆にしてくれ。
僕の体臭を、肌いろに変えてくれ、
ヒヤシンスを君が花に変えた流儀で。
蝉の松の木のてっぺんで怒鳴らせ、
僕にパン窯の匂いをつけてくれ。
正午(まひる)、夜で一ぱいな立木は
夕暮、夜をあたりにこぼす。
太陽よ、アダムとイブの蟒蛇(うわばみ)よ、
僕に自分の悪夢をこぼさせてくれ。
僕を少しは慣らしてくれ、
可愛そうな友人ジャンが殺されてしまったことに。
富籤(くじ)よ、賞品を陳列しろ、
花瓶だの、球だの、庖丁だの。
お前は自分のがらくたを、
野獣の上に、西インド諸島(アンチーユ)の上におっぴろげる。
当地では、最上等の品物を出してくれ、
僕らの眼が悪くなっては困るから。
大口女の見世物小屋、びろうどと
鏡とアルペジオ造りの曲馬館。
黄金車駆る藪医者奴、
荒療治、僕の悩みを抜いてくれ。
ああ、暑い! 正午だからさ。
自分でももう言う事の意味が解らぬ。
太陽よ! 月々の動物園よ、
僕の影はすでに僕の周囲にないぞ、
太陽よ、バファロー・ビルよ、バーノムよ、
阿片以上にお前は酔わせる。
お前は道化だ、闘牛士だ、
お前の時計の鎖は金だ。
お前は、赤道を、彼岸を相手に
拳闘する青い黒奴(くろんぼ)だ。
太陽よ、僕はお前のパンチを怺える、
僕の首へのお前の強打。
そのくせ僕はお前が好きだ、
太陽よ、気持のいい地獄よ。』 (P18〜23)
見てのとおり、この詩は、どう見たって「ホモセクシャル」であることの、苦しみと快楽に揺れ動く心を描いたものである。
だが、ここで注目すべきは、
『歯の光るあの黒奴(くろんぼ)は、
外側は黒く、内側ばら色だ。
僕は内側が黒く、外側がばら色だ、
逆にしてくれ。
僕の体臭を、肌いろに変えてくれ、
ヒヤシンスを君が花に変えた流儀で。』
という部分だろう。
『歯の光るあの黒奴(くろんぼ)は、』というのは、一種「毒々しい」野獣性を表しているわけだが、しかしその「黒」さは『外側』(外見)に過ぎず、むしろ『内側』(心)は、白く輝く『ばら色』であり、そんな『黒奴』(黒人)に対し、白人である『僕』は、『内側』に黒い野獣性を秘めながら、『外側』だけは白く輝く『ばら色』という、ペテン師みたいな存在だから、どうか『僕』の野獣性に汚れた生々しさの臭う『体臭』を、ばら色の肌いろに変えてくれ、無垢な美少年ヒヤキントスの不慮の死を悼んで、光明神である君(アポローン)が、彼を花に変えたように、『僕』も汚れを知らぬ花に変えてはくれないか一一と、そういう意味である。

このように「知解」したところで、しかし、私は、コクトーの詩を十全に理解したことになるとは思わない。なぜならば、こうした「知解」という手法には乗らない作品、つまり「知解」し難い作品がたくさんあるからであり、そうなるのは、結局のところ私が、コクトーの詩の、もっとも重要な部分を理解できない、「感受」できていないからであろうからだ。
だが、私は、コクトーのように、こんな自分を「変えてくれ」とは、あまり思わない。
というのも、「白いものが黒くなった」としても、「黒くなったら、白いもの」を求めるようになるのは、見えた話なのだから、結局のところ、私は私のままで、可能なかぎり、私の可能性を開くしかないと考えるのである。
(2023年2月28日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
