
中井英夫論 「眠り男の迷宮・迷宮の夢」 : 『中井英夫全集[12]月蝕領映画館』月報 所収
【旧稿再録:初出は、2006年1月17日刊行『中井英夫全集[12]月蝕領映画館』。2005年後半に執筆】

(※ 再録時註:本稿は、当時使っていたペンネーム「田中幸一」名義で執筆したものである。原文は縦書きであり、改行も少ないため、ここではウェブブラウザ上の横書き文として読みやすくするために、適宜、改行や1行開けを加えるなどした)

○ ○ ○
眠り男の迷宮・迷宮の夢
田中幸一
武蔵小金井の家で初めてお会いした時か、それとも二度目だったか、今となってはそれも定かではない。けれどもただひとつ、強く私の印象に残ったのは、中井英夫が「オレはね、手かざしができるんだ」と自慢げに語ったことだった。最愛の人、Bこと田中貞夫が癌の激痛に見舞われていた当時、中井が手かざしでその激痛をやわらげたというのである。
その頃、すでに中井はアルコール依存に冒されて、体力的にもめっきり弱っていたから、私はこの話を聞かされた瞬間、中井が「ボケた」んじゃないかと、正直うたぐってしまった。中井のこの思い掛けない言葉は、私の抱いていた中井英夫像から逸脱して、それを大きく揺るがすものだったのである。
例えば『悪夢の骨牌』の「アケロンの流れの涯てに」には、作中人物が『Rはいきなりそんなことをいいました。もともと怪奇なこと幻想風なこと、非現実の世界が何より好きな彼は、理不尽な話となるとすぐ眼を輝かすというふうだったのです。』と友人を評するくだりがある。おそらく、中井自身も「怪奇なこと幻想風なこと、非現実の世界が何より好き」であったのだろうけれど、しかし、ここにはそうしたへ〈嗜好〉を相対化する冷静な眼、科学的な眼があるというのも確かだから、当然、作者である中井英夫は、そういういかにも非科学的なものをそのまま宿じたりはしない人であろうという諒解が、私にはあったのである。
一般的な中井英夫像はというと「狷介にして耽美な美意識の持ち主」といったことになるのだろうが、そのイメージと「手かざし」とには、どうにも非和解的な距離が感じられる。
最晩年の助手であった本多正一さんに聞いてみると、中井英夫にもけっこういい加減なとこちがあったようなので、作品からうける印象ほどには、実物は「輪郭のかっちりした人」ではないのかも知れない。まあ、人間なんてそんなものだ一一という考え方も可能ではあろう。つまり、作品からの印象によって形成される中井英夫像とはべつに「生身の中井英夫」がおり、そちらこそが〈本物〉の中井英夫だ、という考え方である。しかし、生身の方が本物だという保証など、果たして存在するのであろうか。
周知のとおり、中井英夫は作家になる以前から「小説」を書き、「日記」を書いていた人である。「日記」には当然〈自分〉のことが書かれるわけだが、そうすると、そのことによって自分自身が客体化されることにもなり、その「日記者」は〈自分=私〉というものの在り方に、嫌でも敏感にならざるを得ない。つまり、非公開の日記であろうとも、「日記」を書く者はおのずと「自己演出的」にならざるを得ないのだ。
例えば、中井英夫がしたためた戦中日記には、大日本帝国の中枢たる大本営に勤務しながらも、ひそかに「反戦」日記を書き綴る若き日の中井英夫の姿が、輪郭もあざやかに描き出されている。しかし、腸チフスの悪化による意識不明のまま八月十五日を通過したという特殊性はあるにせよ、戦後に刊行された戦中日記『彼方より』(初版)の「あとがき」では、中井は『それにしても、眠り続けている間に、日本には何が起ったというのだろう。その日々があんなにも待ち望んだ輝かしい戦後だとは、到底私には借じられなかった。それとも私は、この日記を書いた青年と同一人物ではなく、ただ彼の記憶を脳の一部に移植されただけなのかも知れない。いずれにしろ私は、また違う罠の中に捉えられた思いで、再びひとりの手記を書き始めるほかはなかった。』と、戦中の反戦青年に一種の〈違和感〉を表明している。戦中の〈私〉と戦後の〈私〉は非連続的であるという感覚は、しかし中井英夫本人だけのものではない。
そもそも、幼時、自分は生まれ落ちる場所を間違えたのだと考え、本来の世界へ戻れますようにと祈った「反世界」的な中井英夫が、戦時、ある意味では典型的反戦青年になったという事実には、理屈はどうあれ、そこに多少の〈違和感〉を覚えないではいられないのではあるまいか。まるで、複数の中井英夫がいるようだ。一一そんな印象をうける読者は、決して少なくないはずである。

私は、中井英夫に感じられるこの〈多重人格性〉を、過剰な自意識による、底なしの演技性に由来するものと見る。もともと「耽美な趣味人」と「社会意識のつよい正義漢」という中井英夫の二面性は、どうしたって非和解的なものなのである。
しかし、中井英夫は、そのどちらか一方を選んで、無難に統一された〈私〉を生きるのを、善しとはしなかった。二人の、あるいはそれ以上の人格を、良い意味で、時と場合に応じて演じ分け、その個々の人格は他の人格に対し、一定の批評的距離を持つことになったのではないか。また、そうした中井英夫の内面を象徴するのが、中井作品に頻出する「ドッペルゲンガー」「もうひとりの自分」「反世界の自分」「鏡の中の男」といったモチーフなのではないだろうか。つまり、中井英夫には、特権的な〈私〉である「本当の私」など存在せず、「あるべき私」が複数存在していただけなのではないだろうか。そして、その複数の〈私〉は、たがいに対する「演技者」であり「演出家」であったのではないか。
たとえば、中井の死後に刊行された『中井英夫戦中日記 彼方より(完全版)』には、最愛の母を亡くして慟哭する中井英夫の姿が『お母様お母様お母様お母様(…)おかあさまおかあさまおかあさま(…)オカアサマオカアサマオカアサマ(…)』と、単行本で延々四ページにわたる、呪文めいたくり返しによって、鮮烈に描き出されている。一一たしかに、中井英夫の母への尋常ならざる愛着と、その死への悲嘆の深さを語ってあまりあろう。とはいえ、改行ごとに漢字・ひらがな・カタカナと書き換えていく〈手法〉には、「表現者」としての、あるいは「演出家」としての〈冷徹な眼〉の存在が否定しがたい。つまり、中井英夫は、最愛の母を亡くす悲嘆のなかにあっても、決して「演技者」であることを止められなかったのである。
多くの読者、あるいは直接つきあいのあった人おのおのに、中井英夫とはこのような人であったという中井英夫像なり中井英夫観があるだろう。それが、おのおの微妙な違いを見せるのも、「観察者」が別人ならば「観察像」が変化するのも、理の当然である。しかし中井英夫の場合、ことはそれほど単純ではない。中井英夫とは、いわば〈私〉の「演出家」であり、「演出家」である〈私〉もまた、別の〈私〉に演技をつけられる「演技者」であった。つまり、中井英夫には、特権的な「本来の私」など存在しなかった。一一私には、そのように思えてならない。
「本当の中井英夫」という〈現実〉を求めてみても、それは背後の背後へと無限に後退したあげく、いつの間にか最初の〈私〉たる中井英夫に回帰して、実像探究の旅はついに堂々回りとならざるを得ない。そして、こうした中井英夫の存在形式こそが、かの『虚無への供物』や『とらんぶ譚』などに典型的な「前言否定」と「円環構造」の手法として、現実に反映されていたのではないだろうか。
「手かざし」ができると自慢した中井英夫は、たしかに「生身の中井英夫」ではあったろう。けれども、それを「本物の中井英夫」だとするのは、たぶん間違いである。「まさか中井英夫が、こんなことを言うなんて思ってもみなかっただろう」。一一奇矯な中井英夫の背後には、その奇矯さをそれと認識しつつ、あえてそうした自己を演出し、陰でほくそ笑んでいる中井英夫が存在する。
けれども、そういう自虐的な中井英夫もまた「演じられた中井英夫」の一人であって、一般的な意味での「本物の中井英夫」は、ついに存在しない。それはちょうど「氷沼家連続殺人事件など、存在しなかった」というのと相同的なのかも知れない。「氷沼家連続殺人事件」が「存在しなかった事件が、さも存在するかのように展開したところの事件」であったとするならば、中井英夫もまた、中井英夫という迷宮だと言えるのではないか。迷宮の深奥のどこかに、迷宮の王としての中井英夫がいる、というのではない。迷宮という構造そのものが、あるいは〈迷宮のみる夢〉が、中井英夫なのである。
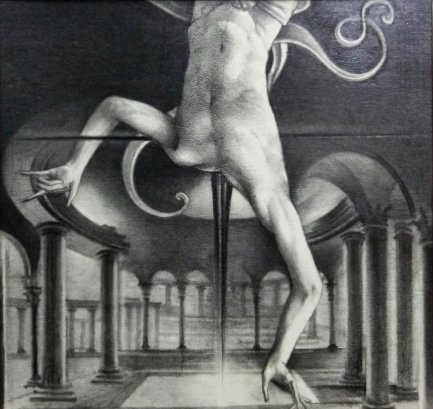
(2024年2月15日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
