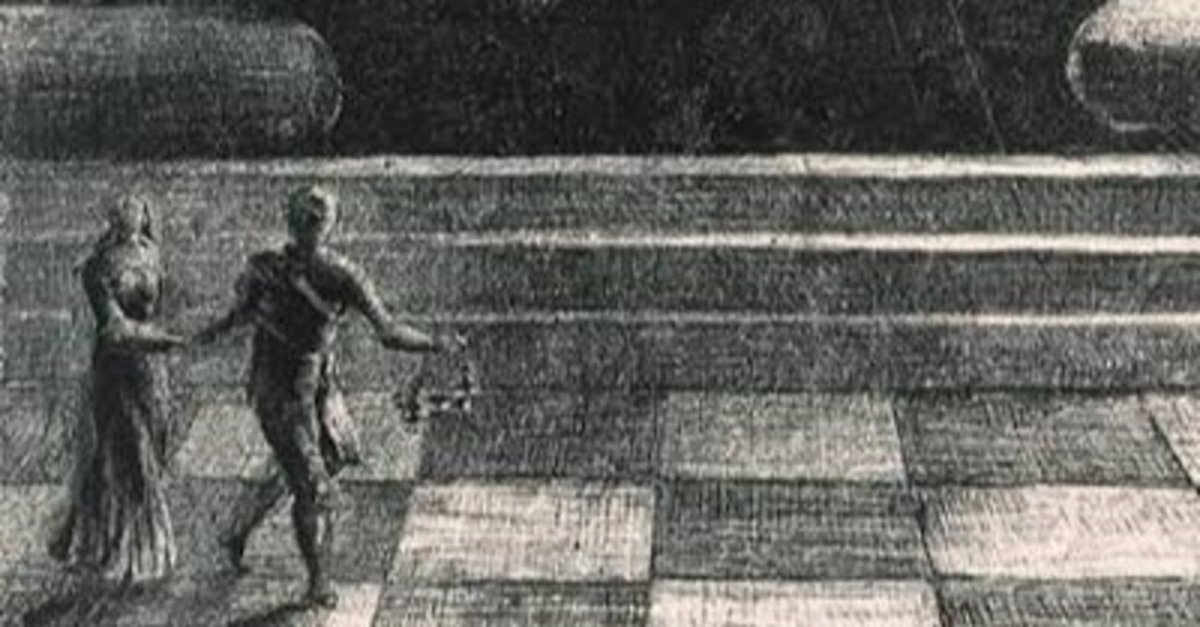
山尾悠子 『山の人魚と虚ろの王』 : 〈醒めない夢〉の回廊で
書評:山尾悠子『山の人魚と虚ろの王』(国書刊行会)
「夢のようなお話」だと言ってしまえば、そうには違いないのだが、これが一般に意味する「たわいもない」というニュアンスは、ここにはない。
じっさい、夢を見ている当人は、その夢のリアルを生きているのだから、それが「たわいもない」ものであろうはずがないし、そもそも夢を見ている当人にとっては、それは「夢」ではないのだ。
山尾悠子の宇宙とは、そんな「夢に似た異世界」だと言ってもいいだろう。じっさいのところ、それが「夢」なのか「異世界」なのかは、読者には判別のしようがない。そのように書かれているのだ。

読者には、その世界が何であるかを決定する権限が与えられておらず、読解によって決定権を握ろうとするその手のひらから、それはすり抜けるようにして逃れていく。山尾悠子は、意図的にそんな作品を書いている。
要は、「意味」に規定されたくないのである。「分類」などまっぴら御免なのだ。「夢」とは、解析しきれないから、必然性に還元できないからこそ美しいのであるし、そうした世界を構築するために、山尾悠子は言葉のかぎりを尽くして、読者を魅了しながら、逃げて行く作家なのである。
帯文には、次のとおりある。
『風変わりな若い妻を迎えた男 秋の新婚の旅は 〈夜の宮殿〉その他の街を経て、機械の山へ 舞踏と浮遊』
『夜の芝地を埋め尽くす不眠の観衆たち』
『幾つかの寝室と寝台の謎 圧倒的なるイメジャリーに満ちみちた驚異と蠱惑の〈旅〉のものがたり』
「お話」としては、この通りなのだが、ここに示された「具象」自体には、ほとんど意味はない。
たとえば「夢」の中で、綺麗な女性あるいは男性が立っているとしよう。この人物が「具象」的にどのようなものであろうと、その夢の世界の「空気」には関係ない。つまり、同じ人物が同じように見えていようと、ある時には、それは胸のときめくような楽しい夢であるし、別の時には不安と恐怖に彩られた悪夢となる。つまり、「具象」にはほとんど意味がなく、先に「感情」あるいは「気分」が存在して、それが「具象」を色付けているのだ。
言い換えれば、「夢」とは、「感情」あるいは「気分」に合致した「具象」の表出、ではない。どんな「具象」でもいいのだ。それがどんなものであろうと、「感情」あるいは「気分」に支配された世界、それが「夢」なのである。

しかし、これはあくまでも「夢」の話であって、それを「文章」という「具象」に移すという作業は、言うまでもなく容易なことではない。「夢」で見た「具象」をそのまま(模)写しても、その「夢」の「感情」あるいは「気分」を再現することはできない。夢の「具象」から、夢の「感情」あるいは「気分」に遡ることは、不可能だからである。
したがって、いかに「夢のような作品」であろうとも、「小説」であるかぎりにおいて、それは「夢に見た具象」を「言葉」にするのではなく、「言葉」によって、「夢」の中で感じられた「感情」あるいは「気分」を描かなくてはならない。つまり、そこに描かれる「具象」は、「感情」あるいは「気分」を喚起するための、ひとつの「材料」にすぎない。言い換えれば、そこで駆使されるのは、「夢」とは逆方向に働く、「現(うつつ)」の論理なのである。
山尾悠子は、「言葉」という「現」の絵筆を使いつつ、その道具的限界から逃れようと工夫する。
「描画」の「お約束」つまり「法則性」に絡め取られないように、通常の「ロジック」は無論、すでに使い古されて手垢にまみれた「詩の論理」や「夢の論理=アナロジー」に頼ることもしない。そうした「形式性」を採用した時点で、すでに「安定的な法則性の宇宙」に安らいでいることになるからだ。
だが、それでは、この「現」の世界の中に、「夢の夢たるもの」を呼び込むことはできない。
本作では、戦前の、大正時代あたりの「古き良き日本の上流階級」を思わせる、中年にさしかかったであろう男性紳士が、語り手の主人公として描かれる。彼の「おさな妻」となった女性も、いかにもそんな時代の雰囲気を漂わせており、どこか戦前の「探偵小説」や、稲垣足穂、久生十蘭のような、いかにもレトロでオシャレな雰囲気がある。
だが、登場人物には「名前」が与えられていないし、具体的な「地名」も描かれない。つまり、この物語が「日本を舞台にした、日本人の物語」だとは決めつけられない。外国の外国人のお話であっても、全く不都合ではない。それはどこか、アラン・レネ監督の『去年マリエンバードで』を思わせるところがある。
また、後半で一つだけ「作中における仮名」が登場するが、この仮名も国籍をうかがわせない、不思議な名前である。

本作は、その大方においては「昔の話」であるようなのだが、一ヶ所だけ、それを裏切る言葉が投げ入れられている。『電子音とともに浴室ぜんたいを』とか『ライトアップもしくはプロジェクションマッピングなどとPたちは言っていた』という、「現代」を舞台にしているとしか思えない描写が、主人公男性の一人称(心内語)で語られる。これは明らかに意図的な「統一感破壊」である。
また、ここに登場する、主たる脇役の『Pたち』の様子だけは、妙に現代的に描かれており、周囲から浮いて、違和感を発し続けている。それはまるで「夢の外から届く声」のようだ。
このような意識的かつ意図的な工夫によって、本作は「夢のようなお話」には収まらず、それを意識的に逸脱して逃げていく。その世界を「理解」しようとする読者の「解釈の網」を破って逃げ去る。「夢」は「理解」されてはならない。「法則性」を見出されてはならないからだ。
だから、じっさいのところ、これは「夜の眠り中での夢」の話だとは限らない。
終盤で、主人公の男性は、妻から、実は列車事故に遭って、あなたはいま瀕死状態にあるのだと明かされる。
しかし、瀕死でベットに横たわっているはずの彼が、ピンピンした状態で、目の前の妻から「あなたは今、ベッドの中でいて、昏睡状態にある」と説明されるのは、言うまでもなく矛盾したことなのだから、この言葉をそのまま信用することはできない。この物語が、事故で昏睡状態にある語り手の「夢」だという可能性は否定できないにしても、そうだと決めつける物証は、どこにもない。妻の言葉は、単なる「夜の眠り中での夢」での、夢の登場人物による「現実」に反する言葉かもしれないのだ。
極端な話、もしかすると、彼はすでに死んでいるのかもしれない。つまり、この物語の世界は「死後の世界」なのかもしれない。
語り手は、永遠の「死後の世界」に生きているのかもしれないし、あるいは、死後の世界で「前世の記憶」を反芻しているのかもしれない。あるいは「転生後の世界」を予告的に体験しているのかもしれない。
いずれにしろ、その世界は、「夢」と同様に、その内部からは、それと確定することはできないし、そもそもそれらが別物であるのか、つながっていないと言えるのかどうかも、私たちには分からず、その世界理解は、私たちの指の間をすり抜けていくのだ。
○ ○ ○
山尾悠子を最初に読んだのは、今から四半世紀以上昔の昭和59年(1984年)のことだ。このとき読んだのは、短編集『夢の棲む街』で、私がまだ二十歳過ぎの若い頃である。
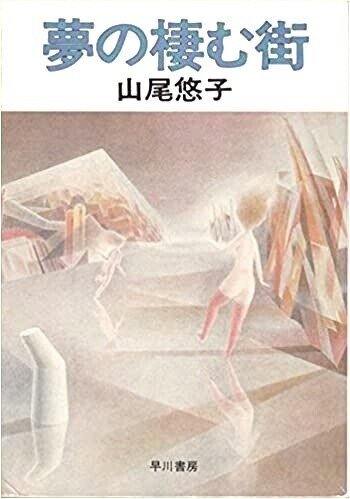
この時の感想は「まったくわからない。硬質感のある特異な幻想世界だが、私の趣味ではない」といったところだった。
悪いとは思わない。確実に独自の世界観を持った作家だとはわかるのだが、いかんせん「私の趣味ではない」ことも明らかだと感じた。
だからこそ、読みはしなかったものの、新刊は買い続けていた。寡作な作家だったから、それは少しも負担にならなかったし、昔から山尾悠子の本は装幀に凝っていたので、持っているだけで、その独自な世界に浸れるような気分がしたのである。
読んでいない本には、無限の「夢」がある。
今回、ひさしぶりに山尾悠子を読むことにしたのは、端的に言って本作が、長すぎも短すぎもせず、だから負担なく堪能できそうな長さだったからである。私にとって山尾作品は、長編はしんどそうだし、短編では食い足りないかもしれない。かと言って、短編をいくつも読むのも疲れそう、とそんな印象があったのだ。
ともあれ、本当にひさしぶりに読んだ山尾悠子には、以前に感じたほどの「硬質感」を感じなかった。読む者との間に一線を画するような「硬さ」は感じず、ずっと柔らかになったように思えた。
これは、山尾悠子が歳をとったせいなのか、それとも私が歳をとったせいなのか。あるいは、その両方なのか。
真相は、誰にもわからないし、そもそも、そこに真相など確定しようもないのではないだろうか。

初出:2021年3月7日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
○ ○ ○
