
竹本健治 『話を戻そう』 : 「奇書」と呼んで、済ませる勿れ
書評:竹本健治『話を戻そう』(光文社)
本書の帯には、『竹本健治は奇書しか書かん。』という惹句が、大きく踊っている。
これを見て私は、いささか、げんなりさせられた。
たしかに竹本健治は、ジャンルのスタンダードからズレた作品を書きたがる作家だし、そもそもデビュー作の『匣の中の失楽』は、「三大奇書」として知られる夢野久作『ドグラ・マグラ』、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』、中井英夫『虚無への供物』に続く、「第四の奇書」と呼ばれることも多いから、そうした意味でなら、大雑把に言って、この惹句もあながち嘘とまでは言わないものの、竹本健治だって、少し変わったところはあっても、かなり端正な「本格ミステリ」だって書いているのだから、決して『竹本健治は奇書しか書かん。』とまでは言えないのである。
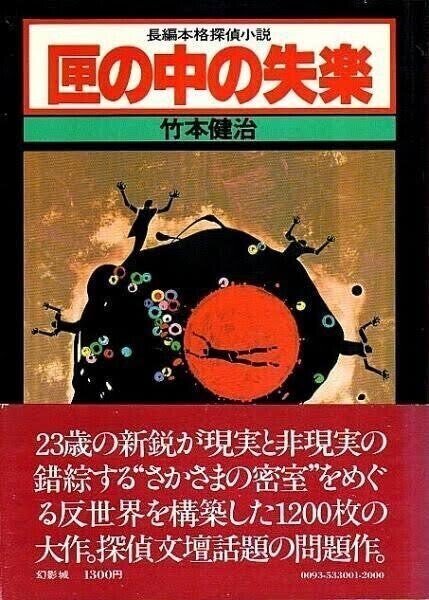
つまり、この惹句は、竹本健治の個性を、いささか「針小棒大」に誇張して語り、それで耳目を惹こうとしたものだと言えよう。
だから年来のファンとしては、こういう、開き直って「少数マニア」を狙ったかのような惹句には、げんなりさせられたのである。
なお、この『竹本健治は奇書しか書かん。』というのは、もちろん「竹本健治は奇書しか書かない。」という意味で、この『書かん』という語尾は、たぶん「佐賀弁」なのであろう。
竹本が、東京都町田市から、妻の実家のある佐賀県に転居して、そろそろ10年ほどになるけれど、佐賀に移ってからの竹本は「佐賀ミステリファンクラブ」や「変格ミステリ作家クラブ」などの立ち上げに関わるなど、佐賀を拠点としてミステリ小説の普及に尽力しており、首都圏にいた頃にはなかった、意外な積極性を見せている。
そんなわけで、この推薦文も、そうした竹本の現状を踏まえた「佐賀弁の推薦文」になっているのであろう、ということで、その証拠に、帯にはこの他に、次のような内容紹介文も刷られている。
(※ なお、引用文中の(※)で括った部分は、帯の惹句では省略されているが、Amazonの紹介文にはあるので、ここでは補って収録しておいた)
『 著者初の偏愛歴史ミステリー
幕末の佐賀藩を舞台に、からくり儀右衛門の孫が冴えわたる機智で怪異に挑むが……話は横道に逸れまくり、なかなかストーリーが進まない!?(※ 膨大な情報量で挿し込まれる史実に話は脱線を繰り返し、ついにはストーリーをも凌駕する!)脱線の先に隠された○○とは?』

『偏愛歴史ミステリー』の「偏愛」の対象とは「佐賀」だということであり、たしかに本作は「偏愛的佐賀歴史ミステリー」と呼ぶことのできる作品なのだが、言い換えれば、これは佐賀県人にはウケても、佐賀に特に関心のない人には、あまり興味の持てない「ローカルネタ」の歴史ミステリーだとも言える。
しかしながら、だからこそ、竹本がなにゆえに、わざわざ「読者を限定するような内容」のものを書いたのか。一一じつはここが、本作の読みどころなのだともいえよう。
こうした「偏り」が、おおむね竹本の「佐賀愛」に発するものだとしても、ここまで「一般性」を欠いた『偏愛』作品を、あえて書いたというのには、単に「佐賀を愛しているから」という理由だけでは済まない何かがあると、私はそう読んだのだ。
○ ○ ○
本書の内容は、すでに紹介されているとおりであると言ってよい。
つまり、次のような「顕著な特徴」を有するということである。
(1)佐賀偏愛歴史ミステリー
(2)佐賀の歴史に関わる「膨大な情報」が盛り込まれており、そのためにストーリーの進行がしばしば滞る。
(3)しかしそれは、単なる『横道』への『脱線』を超えて、『ついにはストーリーをも凌駕する』に至る。
したがって、この作品を、こうした特性を特に気にかけることもなく読んだ場合、多くの読者は「なんだこれ? ぜんぜん話が進まないじゃないか」という「不満」をおぼえることになるだろう。
「ミステリー小説として楽しもうと思ったのに、この作品では、ミステリーの部分は付け足しみたいなもんで、メインは、幕末の佐賀県の歴史に関わる蘊蓄の方じゃないか。そんなのが読みたけりゃ、最初から歴史書を読むよ」と、そう腹立たしく感じるはずである。
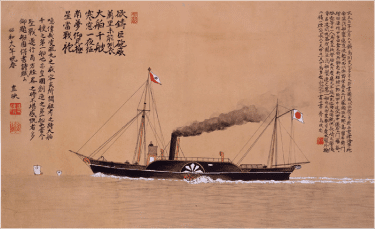
しかし、竹本健治ほどのベテラン作家が、「一般のミステリー読者」がそのような「不満」を抱くであろうことを予想もせずに、このような『話は横道に逸れまくり、なかなかストーリーが進まない!? 膨大な情報量で挿し込まれる史実に話は脱線を繰り返し、ついにはストーリーをも凌駕する』ような作品を書くかと言えば、そんなことは到底あり得ない。そう断じても良い。
つまり、これは「わざとやっている」のである。
言い換えれば、わざと「読みにくい小説」にしたのであり、著者の「狙い」はそこにこそあって、普通の意味での「ミステリー小説として楽しませよう」とか「歴史小説として楽しませよう」とか「ストーリーを楽しませよう」とか、したのではない、ということになるのだ。
事実、竹本健治は、本書の締めくくる文章で、次のように、身も蓋もないことを書いている。
『 さしあたり、もっと江藤新平のことが知りたい方には司馬遼太郎の『歳月』をお薦めしておこう。ただし、氏の作品は膨大な資料の上に成り立っているとはいえ、必ずしも史実のみで構成されているわけではなく、あくまで歴史「小説」であると本人も強調している通りである。久重に関しては林洋海『東芝の祖 からくり儀右衛門一一日本の発明王 田中久重』、直正に関しては植松三十里『かちがらす 幕末を読みきった男』が優れた評伝である。なお、植松氏には、この物語ではふれなかった、佐賀本藩で反射炉建設や大砲鋳造に携わった本島藤太夫ほかの《御鋳立方七賢人》に焦点を当てた『黒鉄の志士たち』もある。
以上、鍋島直正、田中久重、江藤新平といった人物を配し、岩次郎をあまり話を回さぬ狂言回しとして、幕末の佐賀を仰望・鳥瞰しつつ話を進めてきた。やたら情報量の多い、閉じられぬままの挿話もある、いささか歪な物語である。とりわけ、解説が延々と続き、なかなか本筋(?)に戻らないのに面食らわれた向きも多いだろう。ただ、歴史というものが切り取られた空間に収まるような閉じたものではなく、無数の回路によって否応なく開かれた多様体である以上、こういうかたちでの書き方にもそれなりの意味があるのではないだろうか。
そしてここまで来てしまうと、もう話はもとに戻せない。』(P299)
この「締めの口上」を読まされて、唖然とした読者もいるだろうし、腹を立てた読者もいるだろう。当然である。
なぜなら、多くの読者は「ミステリー小説」を読もうと思って本書を購ったのであろうし、そもそも帯には、前記のとおり『偏愛歴史ミステリー』とある。
また、ここで著者が『狂言回し』と表現した、本作の「ミステリーパートの主人公」である「田中岩次郎」は、作中において、いかにも「ミステリー的な謎に挑む名探偵」役を演じてもいるのだから、読者が本作を「ミステリー小説」として読もうとし、そうであることを期待するのは、当然のことである。
またさらに言うと、本書の読者は、基本的に「幕末佐賀の歴史」を勉強したいわけでもなければ「歴史とは何か」という哲学的な問題に取り組みたいわけでもない。
何度も言うようだが「ミステリー小説」を読もうと本書を購ったのだから「ミステリー小説」を期待するのは当然で、最低でも「歴史小説(としての面白さ)」を期待するのだが、この「締めの口上」にも明らかなとおり、著者はその期待を、すべてわざと裏切っている。
要は「期待どおりに、楽しませるつもりなど、最初からなかった」ということなのだ。

では、作者は何をしたかったのだろうか?
この「締めの口上」にあるとおり『歴史というものが切り取られた空間に収まるような閉じたものではなく、無数の回路によって否応なく開かれた多様体である以上、こういうかたちでの書き方にもそれなりの意味がある』と考えて、「歴史が物語(一本のストーリー)には治らない多様体であるという事実」を書きたかったのであろうか?
私は、そうは思わない。
竹本健治が、そんな「当たり前なこと」を書くために、わざわざ一般ウケしないのがわかっている、こんな長編小説1本をまるまる書いたとは、とうてい思えない。
そもそも、締めの言葉である『ここまで来てしまうと、もう話はもとに戻せない。』というのは、「ストーリーの本筋から脱線しては、その度に『話を戻そう。』と言って、それを繰り返してきた、この作品の、定番ギャグのごとき「お約束のパターン」までも、最後の最後で「裏切る」という皮肉なユーモアだというのは、ちょっと読める者には、明らかなことだ。
つまり、竹本健治の「狙いであり本音」は、他のところにあって、それは、あからさまに語られていないと、そう見るべきなのである。
したがって、私たちが、本作から読み取らなければならないのは、(締めの言葉で語られたことではなく)その「隠された狙い(意図)」の方なのだ。
○ ○ ○
竹本健治は、本作で「何をやろうとした」のであろうか?
少なくとも、表向きに語られる「歴史が物語(一本のストーリー)には治らない多様体であり、一本のストーリーに収まるようなものではない」というような「当たり前の話」などではない。
そんなことは、「歴史」というものを、まともに考えたことのある者にとっては、「言わでもがな」な話でしかないからだ。
では、竹本健治は、何を語ろうとしたのか?
私が考えるのは、「ストーリーとは何か」ということであり、ひいては「小説とは何か」という問題である。
前述のとおりで、「歴史は多様体である」というのは、比較的「初歩的な歴史理解」である。
例えば、日本の「戦後史」と言っても、それは「一つのストーリー」ではなく、無限に多様なストーリーを孕むもの(可能体=無限多面体)であり、光の当て方によって、それは正方形にもなれば三角形にも円形にもなるようなものだ。
具体的に言えば、「戦後民主主義的」あるいは「左翼平和主義」的な見方による「日本の戦後史」は、大雑把に言えば「占領軍による民主化と、徐々に進行していった反動としての、戦争のできる国への移行」というようなことになるが、「戦前回帰派」あるいは「保守派」からすれば、日本の戦後史は「占領国による洗脳による自虐史観から、独立心と愛国心の回復へ」というようなことになるだろう。
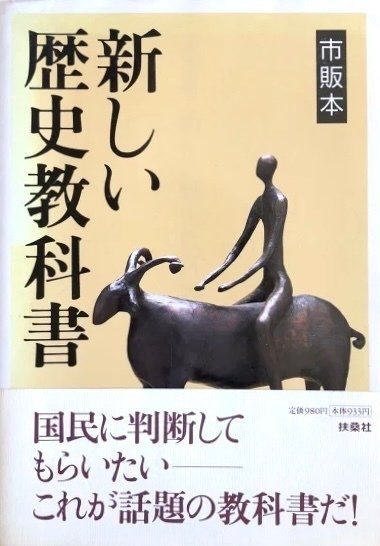
これらは、双方ともに「自分の見方が正しく、相手の見方は間違っている」と主張して譲らないのだが、じつのところ、こうした見方の違いは、どちらか一方が間違っているというよりは、それぞれ「歴史という対象に対する、光の当て方が違う(見る角度が違う=立場が違う)」ということでしかなく、どちらか一方が完全に正しいとか間違っているという話ではない。
どちらも「一面の真実を含んではいるものの、全面的な把握ではなく、必然的に一面的なものでしかありえない」ということなのだ。
しかしながら、人間は、「歴史」だけではなく、「すべての事象」について「全面的に把握する」ということができない。
「万能なる神」とは違い、人間は「一瞬において、すべての角度から対象を認識する」ということができない。
「すべての角度から見て、全体を把握しよう」としても、一瞬にして見ることはできないから、時間をかけて順に色々な角度から見ていくことになるわけだが、しかし「時間」をかけるということは、「対象が変化する」ということであり、観察者が次の角度に移った時には、すでにその対象(の、先ほど観察した側面)は、先ほどのままではない可能性があるのだ。
つまり、人間は「一瞬に、すべての側面を把握認識できない」から「少なくとも、その一瞬においては、対象はこのようなものであった」とさえ、言えないのである。
ましてや「一定の時間的な幅を持つ現象」である「歴史的事実」を迫ろうとしても、それは自ずと「ある時点での、ある側面においての対象の姿を、総合した(繋ぎ合わせた)もの」としてしか認識しえない、ということにならざるを得ないのだ。

そんなわけで、そのようにして語られる「あらゆる歴史」は、すべて「選択的に形成されたストーリー」だと言えるだろう。
人間には「無限分岐する物語」を(SFであろうと)「そのまま描く」ことなどできないのと同様、生成変化する多様体(無限多面体)である「歴史」を、そのまま描く(語る)ことなどできない。
言い換えれば、「語られた歴史」とは、一つの「視点(立場)」によって限定され、それによって「一本の筋」にまとめられた、「ストーリー(フィクション)」に過ぎないのである。
しかしながら、繰り返すとおり、これは「当たり前」の話であって、竹本健治ほどの人が、今更こんなことを語るために、書く方も読む方も面倒な、長編小説1本を書き下ろしたとは、私は思わない。
ならば、竹本健治は、何を語ろうとしたのか?
一一私が思うに、竹本健治が語ろうとしたのは、「小説とは何か」だったのではないだろうか。
○ ○ ○
本作からハッキリと読み取れるのは、「ストーリーが、意図的に蔑ろにされている」ということである。
つまり、普通の小説なら、ストーリーを支えるための、補足的な役割を担うはずの『解説的情報』が、本作では「ストーリー」以上に紙幅を占めて(出しゃばって)、ストーリーの展開を阻害している。
しかし、ベテラン作家である竹本健治は、これを「わざとやっている」のだ。
では、これが何を意味するのかというと、「小説は、ストーリーがメインである、必要はない」という事実の提示である。
こう言うと、読者の中には「そんなことはないでしょう。小説というのは、ストーリーの面白さがメインであり背骨であって、あとの各種情報は、その背骨に沿って配置される肉質なのではないのか」というようにおっしゃる方もいるはずだ。
しかしながら、現実には、「小説」は、そのようなものとは限らない。
例えば、「エンタメ小説」に限って言っても、「キャラクター小説」というものがあって「キャラクターの魅力がメインで、ストーリーはつけたし」だというようなこともあるし、「純文学」だと「テーマ」だとか「人間を描く」とか「文章の魅力」といったことがメインであって、筋は「便宜上存在するだけ」といったものも多い。
また、純文学の中でも、「実験小説」や「ポストモダン小説」と呼ばれるものにおいては、もはや「筋=ストーリーと呼べるようなものが無い」といった作品も散見されるのである。

つまり、「ミステリー小説」を含めた「エンタメ小説」の読者は、その視野の範囲内において「小説とは、ストーリーをメインとする文芸作品である」といったふうに思っているかもしれないが、じつのところ、そうではない。そんな「縛り=限定」など、「小説」には本来は無いのであり、言い換えれば「小説とは、何でもあり」なのだ。
したがって、竹本健治が、本作『話を戻そう』でやったようなことも、「エンタメ小説」の範疇で見れば、たしかに「暴挙」のように映るし、その意味で、本書を「奇書」と呼ぶこともできるだろう。
だが、本書を「文学全般」の中で見れば、本作は一種の「実験小説」や「ポストモダン小説」であり、その意味で「メタ小説=小説とは何かを語る小説」だと考えれば、特別に変わったことをやっているわけではない、とさえ言えるのである。
なのに、本作が「奇書」のように見えてしまうのは、それは本作が「奇書」だからと言うよりは、「そう見えてしまう読者」の「視野が狭いから」に他ならないのだ。
広く「文学」を親しみ、「ジャンルというレッテル」に盲従したりせず、そんな色眼鏡を通して「小説」を読むようなことはしない読者であれば、本書は「ミステリー小説」でもなければ「エンタメ小説」でもなく、ただそうしたものに「擬態」した、「実験小説」や「ポストモダン小説」であり、その意味で「メタ小説=小説とは何かを語る小説」という「ミステリー小説もどき(ミステロイド)」あるいは「エンタメもどき」の、前衛的な「文学作品」であることなど、容易に理解できるのである。
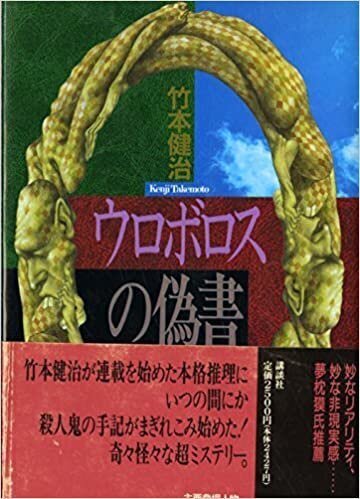
つまり、この作品で語られているのは、あるいは「問題化」されているのは、「小説(とは何か)」であるよりも、むしろ「読者の問題」であり、「読者の小説観」の問題であると言えるだろう。
読者の「小説観」が、きわめて狭く一面的なものであると、当然のことながら「小説の自由」もまた、きわめて狭く限定されてしまう。「こんなものは小説じゃない!」と、あっさりと否定拒絶されてしまうからだ。
しかし、そういうことが「常態化」していけば、当然のことながら、小説はパターン化を余儀なくされて、徐々に貧困化し、いずれその可能性を枯渇させざるを得ないだろう。
だからこそ、竹本健治は、あえて「今の当たり前に反する小説」を書いたのではないだろうか?
「ミステリー小説とは斯くあらねばならない」(例えば『閉じられぬままの挿話』があってはならない)とか「エンタメ小説とは斯くあらねばならない」とか「小説は斯くあらねばならない」とかいった、個人の「狭い了見」で、「小説」というもののあり方を限定してしまうと、小説はいずれ窒息死してしまわざるを得ないのではないか。
そして、竹本健治には、そうした「エンタメ小説」をめぐる「息苦しい」状況が見えているからこそ、言うなれば「炭鉱のカナリア」として、本作を書かざるを得なかったのではないか。
「小説とは、こんなに窮屈で貧困なものだったのか?」と。
話を戻そう。
本作を「ミステリー小説」であり「エンタメ小説」であると限定的に考えるなら、本作は「エンタメを逸脱した小説であり、その意味で、期待はずれのつまらない作品」だとは言えるかもしれない。
しかし、本作は「その読者」にとっては「つまらない作品」かもしれないが、それがそのまま「すべての読者」にとって「つまらない作品」だということにはならない。
そうではなく、「その読者」の視野が狭く、「その読者」が「つまらない読者」だからこそ、本作を「つまらない」と感じただけだ、とも言えるのだ。
竹本健治の作品は、しばしば「オチがついていない」と言われ、本作もそのきらいがあるけれども、そもそも「小説というのは、オチがつかなければならないもの」なのであろうか?
たしかに、オチがついた方が、読者は「スッキリする」だろうし、その意味では「エンタメ性(娯楽提供性)」が高いとは言えよう。
しかし、「スッキリした」瞬間に、その読者の思考は「停止する」。
「考えなくてもよくなる」からこそ「スッキリする」のであるが、しかし、それは読者にとって、必ずしも喜ばしい状態ではないのではないか。
もしも、読者が認知症に罹って、考えられなくなり、いわゆる「恍惚の人」になった時、たしかにその人は「悩み=考えるべき課題」が無くなって楽になり、その意味では「幸せ」になるのかもしれない。一一しかし、本当にそれでいいのだろうか?

少なくとも、「知的であらん」欲するのであれば、「問題」を排除し、そこから目をそらすのではなく、むしろ「問題」をどこにでも発見できる「知性」を持つべきなのではないのか。
本作は、たしかに「エンタメ小説」として見るかぎりは「面白くない」と評価しても、決して間違いではないだろう。
だが、本作を、「エンタメ小説」の枠内に限定しない読者にとっては、本作は「いくらでも深読みが可能な作品であり、その意味で興味深い」という点において、「面白い」作品だと言える。
そして、そんな読者にとって「面白くない」のは、むしろ、本書を「エンタメ小説」というごくごく限られた視点でしか評価できない、「エンタメ読者」の方なのである。
要は、どこから見ても「(ボーッと生きてる)つまんねぇー奴(読者)」ということにしかならないのだ。
(2023年5月2日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
