
高村薫論:見えない情炎
(※ 再録時註:『マークスの山』で直木賞を受賞する直前の1994年に、私は、高村薫氏と直接お会いする機会を得た。それまでに、ファンとして、ファンレターに同人誌を同封して送っていたからだ。初めてお会いした時、高村氏は私を「新本格の人」と呼んだが、私はまったく不満であった)
○ ○ ○
九州の友人から、ひさしぶりに小荷物が届いた。私の好きな作家に関する切り抜きや、お薦め映画の録画ビデオなどをよく送ってくれるのだが、今回送ってくれたのは、高村薫に関する新聞の切り抜きと録画ビデオ『ETV特集 阪神・淡路大震災10年 作家 高村薫 思索の旅』(NHK製作・2005年1月15日放送)だった。
推理小説関係の同人活動で知り合い、文通するようになった十年来の友人だが、彼女は私が高村薫ファンであることを気に止め、折々目についた新聞記事などを切り抜いたりTV番組を録画して、時々送ってくれていたのだ。本当に有難いことである。
『先日、ETV特集で高村薫さんがとり上げられていました。
よろしかったら テープ ごらんになりますか?
もしかしたら TV、 ごらんになってるかも…と 思いつつ
送ります。私は見ていますので 返却の必要はありません…
私は 立木さんとのやりとりが一番興味深かったです。
高村さんは つくづく 〝知〟の人だな… と感じました。
よかったら 感想等 教えて下されば 嬉しく思います。』
○ ○ ○
私は、古い高村薫ファンである。デビュー作『黄金を抱いて翔べ』以来のファンなのだから、それは間違いない。
私は基本的に、小説は本になってから読む方なので、(高村薫には多い)雑誌掲載のまま本になっていない作品は読んでいないのだが、高村薫の著作は『黄金を抱いて翔べ』から『神の火』『わが手に拳銃を』『リヴィエラを撃て』『マークスの山』『地を這う虫』『照柿』『レディ・ジョーカー』『李歐』までの9作すべてを、最初の版で読んでいた(『李歐』は文庫書き下ろし。それ以外は単行本)。
『李歐』の後、2000年に刊行された、高村薫初のエッセイ集『半眼訥訥』は、刊行直後に購入したものの、積読の山に埋もれさせたしまい、昨年古本市の百円均一でたまたま見つけた文庫版で、やっと読んだという次第である。この『半眼訥訥』の次、2002年に刊行されたのが、高村薫の最新長編小説『晴子情歌』で、これが現在のところ、高村の最新著書ということになるのだが、私はこの本も刊行時に購入しておきながら、いまだに読んではいない。
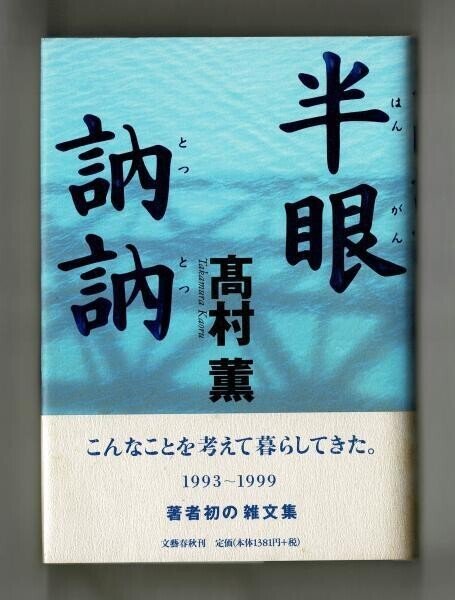

なぜ、『半眼訥訥』と『晴子情歌』に限っては、単行本購入後にすぐに読まなかったのか。
その理由は、前者について言うと、私は高村薫の小説が好きなのであって、エッセイにはあまり興味がなかったからだ、と思う。しかし、そこはコレクター気質の人間なので「それまでの本をすべて所蔵しているのだから、一応これも買っておこう」ということなったのである。
『晴子情歌』については、分厚い上下巻大作で手をつけかねたというのが、まずある。とにかくその頃までの推理小説出版界は、長い分厚い大作が無闇に刊行されていたので、もともと長編作品が嫌いではなかった私も、当時はさすがに食傷ぎみだったのである(※ 東野圭吾の連作短編集『超・殺人事件』には、そのあたりを皮肉った「超長編小説殺人事件」があり、そこにはそうした長編のひとつとして『人間の暗部に迫る超大作 片村ひかる 怒濤の二三〇〇枚』という架空作品の帯文も紹介されている。もちろん『レディ・ジョーカー』のパロディーである)。
それから、『晴子情歌』がミステリではなく、かつ書評によると、あまり私の興味を惹く内容ではないのが窺えたというのも、手をつけられなかった理由のひとつであろう。
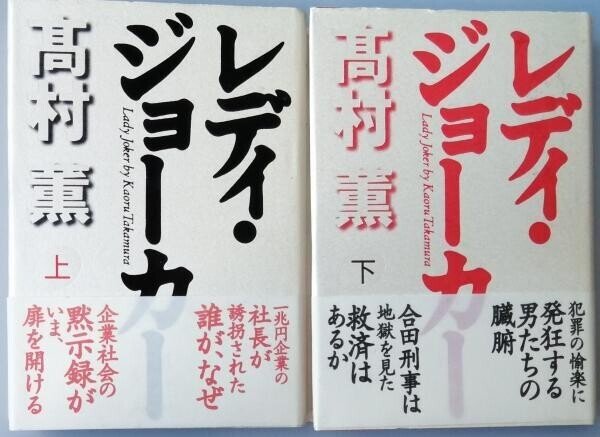
もちろん私は、ミステリ以外の小説も読むので、ミステリじゃないから読む気がなくなった、ということではない。ミステリ・非ミステリに関係なく、高村長編には前例のない、主人公が「女」であるという点に、期待を裏切られるものを感じたのだと思う。
端的に言って、私は『黄金を抱いて翔べ』以来、高村薫の描く、屈折を抱えた暗い男たちが好きだったのだ。だから「老境にさしかかった平凡な女性晴子が、息子への手紙につづる自身の人生と昭和史」といった内容には、まったく惹かれなかったのだ。
『李歐』の刊行が1999年だから、昨年読んだエッセイ集『半眼訥訥』は、じつに4年ぶりに読んだ高村薫の著作ということになる。その間にも、『晴子情歌』に関するインタビュー記事、折々の事件や社会問題に対するエッセイなどで、時々高村の文章には触れていたが、まとめて読んだのはひさしぶりのことだった。
さて、多少の期待をもって読んだ『半眼訥訥』はどうだったのか。一一ハッキリ言えば「ぜんぜんダメ」だった。
高村薫はこのエッセイ集で、生活のことや社会のことをいろいろ書いていたが、いずれもコレといった冴えが感じられない。たしかに真面目な人ではあるから、問題に真摯に向き合い、自分なりの意見を披露しているのだが、どれも「ふーん、なるほどね」の域を出ず、中には「この考え方は、ちょっと困ったものだな」というものも散見されたと記憶する。ともあれ、全体としては「凡庸な社会批評エッセイ」という感じで、その中身はほとんど記憶に残らず、その「凡庸」さだけが「期待外れ」感とともに印象に残っただけであった。
しかし、考えてみれば、高村薫の妙に物足りない「古風さ」「律儀さ」「狭隘さ」を感じたのは、それが初めてというわけではなかった。
以前に同じ友人が録画して送ってくれた『真剣10代しゃべり場 第9期卒業スペシャル』(NHK製作・2003年3月1日放送)の、高村薫が「仕事って何だと思いますか?」というテーマを出したパートにおいて、高村自身の語った、あまりに紋切り型な「仕事観」「大人観」「社会人観」「国家観」に、出演者の16〜18歳の子供たち同様、正直やや辟易させられた記憶があったからだ。
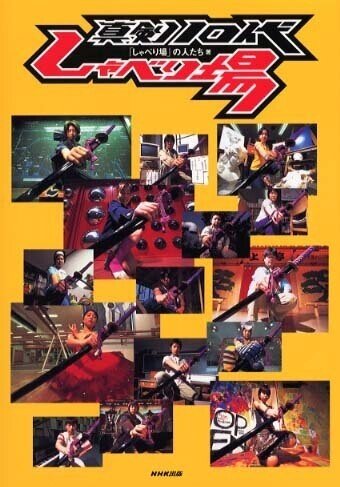
どうして高村薫は、こうも「古風」なんだろうか? 一一しかし、そう思いながらも、私が実際に感じていたのは、どうしてこうも「旧弊」なのだろうか、ということだったのではないか。だからこそ、その「古さ」にまったく魅力を感じず、不満だけが残ったのではなかったか。
高村薫が、真面目すぎるほど真面目すぎる人であるのはよく知っているし、それには好感を抱いている。
また、そうしたことの延長線で、彼女が「庶民」や「職人」といった、「社会の末端の、名もなき人々」に共感を寄せ、その「すごさ」を描こうとしている態度にも共感する。しかし、そうした指向がそのままこのような「旧弊」さに結びつくものなのか? それは必然的な結びつきなのか?
一一そうではない。そうではないはずだから、私はそこに不満を感じたのだ。
それにしても、何が、私にこの「不満」を感じさせたのだろう。
それが、その時(『しゃべり場』を見た時、『半眼訥訥』を読んだ時)の私にはわからなかったのだが、今回送られてきたビデオ『ETV特集 阪神・淡路大震災10年 作家 高村薫 思索の旅』を見て、その正体が判然と了解できたのである。
○
高村薫は『ETV特集 阪神・淡路大震災10年 作家 高村薫 思索の旅』の冒頭で、阪神・淡路大震災の激しい揺れを自宅で経験した時、「死ぬ」と思ったと語る。そして「死に直面する経験」をしたことで「自分のなかで何かが確かに変わった」と語っている。

しかし、同じ大阪で同じ時間に同じ地震を体験した私は、その時「おおっ、今日の地震は凄いなあー」と思っただけで、むしろその揺れを子供のように楽しむ気持ちすらあった。それはそれまで私が、人がおおぜい死ぬような地震の体験をしていなかったからであるし、たまたまその時に寝ていた大阪市内の職場の仮眠室が、堅牢な鉄筋ビルの一階にあり、かつ倒れてくるような家具が一切置かれていなかったという事情もあろう。
だが、そうした諸々の事情の違いはあれ、私は高村薫と同じ震災を体験した一人であることに、なんら変わりはないのである。だから、私が高村薫の「震災」を語る口ぶりに感じた違和感とは、とどのつまり「あなたはそうかも知れないけれど、私はそうではなかった。そして私同様の震災体験者も大勢いただろう」ということなのである。
たしかにあの「大震災」は、多くの犠牲者を出した大きな事件であり、多くの人の心に傷を残していった。それは事実である。しかし、それは「すべての人(体験者)」の心というわけではない、というのもまた事実なのだ。
だが、高村薫の語り口は、まるで「震災とは、それほど大きな体験だったのだ。誰の心にも大きな傷跡を残したはずだ」という、いわば「脅迫的」なものだった。それはまるで「大震災」が、体験者を非体験者と差別化して上位に置く、「特権的な体験」であり「ステグマ(聖痕)」であるかのような口ぶりだったのである。
そこで私は「この言い方は、おかしい」と、まず感じ、そしてその「おかしさ」の正体が「不自然さ」であり、不自然な「大仰さ」、言い換えれば「演技めいたもの」だとわかったのである。
もちろん、私は、高村薫が「意図して」、(自身を含む)震災体験者を「特権化」しようとしたのだとは思わない。むしろ彼女は、その持ち前の「生真面目さ」から、震災の悲惨さを「重く受けとめなければならない」と考え、あのような言い方をしたのであろう。
つまり、彼女は、自分の体験以上のものを「引き受けよう」とした結果、見聞した他人の体験を自分に対して重要なものとして納得させるために、「震災体験」というもの一般を、観念的に特権化したのだ。
事実、この番組で、高村が自分の体験の次に語るのは、震災による「失われた6400人の人命の重み」ということである。
「私たちはその重みをうけとめなければならない」「決してその死を無駄にしてはならない」「少なくとも私は、その死を考え続けることを自分に課している」というようなことを、高村薫は語る。
なるほど立派な心掛けであろう。それは間違いない。しかし、それは本当に「ねばならない」ことなのか? つまり「義務」なのだろうか?

高村薫は、それを震災体験者一般の「義務」だとは、決して言わない。ただ、「私としては」考えないではいられない、と言うに止めている。しかし、この言い方には『論理的、合理的に言って』無理があろう。
「6400人の死を無駄にしてはならない」というのは、いったい「誰」に対しての話なのか?
高村薫は、それを自身の「義務」であるとして、他人に課するつもりはないかのような言い方をする。だが、番組が進んで行くうちに、本音はそうでなかったことがハッキリする。つまり高村は「6400人の死」の重みが「500キロ離れた東京」には伝わっていないと、その苛立ちを露にするのだ。
もちろん、この「東京」というのは、「東京の政治家」に限定されてはいない。「東京の一般人」も含めて言っているのは、高村薫が『レディ・ジョーカー』の執筆の関係で上京した際、「周囲」の反応に「500キロ」の距離を感じさせられた、という証言からも明かである。
つまり、高村薫は「500キロ離れた東京」の人たちの多くが、「失われた6400人の人命の重み」を全然理解していないと苛立っているわけなのだが、当然のことながら、この苛立ちは「500キロ離れた東京」の人たちにも「失われた6400人の人命の重み」を担うべき「義務」がある、という認識を前提としなければ、そもそも発生しないものなのである。

しかし、「500キロ離れた東京」の人たちに、そんな「義務」など、はたして本当にあるのだろうか?
もしも「ある」のだとしたら、もはや日本のどこに居ようと、誰もその「義務」からは逃れられないだろう。いや、事が「実際の距離」に関係ないのだとしたら、その「義務」の範囲を国内に限定する理由すら無くなってしまう。
だが「世界中の人々」に「6400人の死を無駄にしてはならない」義務がある、と言ったのでは、やはり無理があろう。ならば、どこからこのような「無理」が生じてくるのか?
答を言おう。
そのような「無理」が生じるのは、一一ほかならぬ 高村薫自身が、「無理」をして、義務を背負い込んでいるせいなのだ。それゆえの「転倒=倒錯」なのである。
本当は、そんなしんどい「義務」や「使命」など、背負い込みたくはない。しかし、背負い込まねばならない。背負い込まねば「落ち着かない」あるいは「後ろめたい」と感じて、「無理」に背負い込んでいるからこそ、本来「義務」など課されてはいない多くの他人にも、同様に「義務」を課したくなる。
そして、「義務」として「すべての他人」にそれを課するのであれば、その問題は「特別重大で普遍的広がりを持つ問題」でなければならず、「特定の地方の」「体験者だけの」問題であっては「困る」。だから、高村薫は、誰もが軽んじることの出来ない「失われた6400人の人命の重み」という表現で、「阪神・淡路大震災」の問題を、フレームアップしてみせたのだ。

無論、このような心の動きを、高村薫自身は、自覚してはいない。ただ、生真面目な彼女は、生真面目にその問題を担わなくちゃと「考えた」のだろう。
だが、彼女の「本能」であり「無意識」の部分は、やっぱり「そんなしんどいことはイヤだ。どうして私が、あかの他人の死まで担わなくてはならないの」と不満の声を上げたので、彼女は仕方なく「ホントは他の人だってみんな、担わなくちゃならないことなのよ、これは。だから我慢しなさい」と説得せざるをえず、その「無意識の辻褄あわせ」の結果、高村は、「すべての他人」も「失われた6400人の人命の重み」を担うべきだ、と無意識のうちに考え・感じてしまっていたのではないか。
もちろん、その証拠もある。それは、この番組で語られた『あまり大きな声では言えないんです。というのも、自分は家も壊れてないし、家族も亡くなってないのでね。そんな人間がつらいって何事かって言われたら、たしかにそうなんです。』という彼女の言葉である。
つまり、彼女の「責任感」の源泉は、この「後ろめたさ」であり「私は恵まれすぎている(から、みなさんに申し訳ない)」という「劣等感(コンプレックス)」にあったのだ。
○
この番組の録画ビデオを送ってくれた友人は、その手紙に『私は 立木さんとのやりとりが一番興味深かったです。高村さんは つくづく〝知〟の人だな… と感じました。』と書いていたが、このビデオを見て、私が感じたのは「高村薫は、〝知〟から最も遠い人だ。ぜんぜん知的でない人だ」ということだった。
だが、だからこそ彼女は、知的たらんとしたのであろうし、その結果、そのそぶり(だけ)が、まさに殊更〝知〟の人というものになって表われたのであろう。その意味で高村薫を「〝〟」付きの『〝知〟の人』だという友人の評価は、正鵠を射たものだった。
しかし、所詮、高村薫の「〝知〟」は、偽物である。だからそれは、たいがいの人に、透けて見える程度のものでしかない。事実、この番組のなかで、高村薫と(個別に)震災のことに話し合った3人の男性のうちの一人、写真家の立木義浩は、高村薫のその「偽物」性に、厳しく率直に斬り込んでみせた。だからこそ、私の友人は『私は 立木さんとのやりとりが一番興味深かったです。高村さんは つくづく〝知〟の人だな… と感じました。』と書いたのであろう。つまり、立木の「本質」的「実質」的な意見に対し、高村薫はあまりにも無力な観念性を曝して、その「〝〟」付きの『〝知〟の人』ぶりを露呈してしまったのである。
立木は震災の直後に神戸入りして、その惨状を写真に収めたのだが、その時には「人にカメラを向けられなかった」という。ところが、震災から五年後、ふたたび神戸にやってきた立木は、震災から立ち上がった人たちの「明るい笑顔を正面から」写し始めたのである。
高村薫は、立木義浩のこの「心境の変化」に興味をもって対談を申し入れた。震災とその犠牲者のことを考えれば、暗く沈みがちになってしまう自分とは違い、どうして立木にはこんな「明るい写真」が撮れるのだろう。一一高村は、そのことが知りたかったのである。

一一 立木が馴染みにしている神戸のお好み焼き屋で、立木の写真をめぐって。
高村「私たちはたまたま神戸だって知ってるからかも知れないですけれど、笑顔が写真の中に閉じ込められる、永遠に閉じ込められる…。なにかね哀しくもあるんですね」
立木「哀しい?」
高村「私の存じ上げない方ですけど、笑っているこの後ろに、いろんな記憶があるのかなと思ったら」
立木「いや、笑おうが笑うまいが、抱えているものは山ほどあるわけですよ、みんな」
高村「それがたまたま笑顔だから余計に…」
立木「うん、だから、えーっと、悲劇的な事件に青空が似合ったりするのと同じなんです」
高村「ああ、そうですね。……こうー、これだけの数の(※ 笑顔の)写真をお撮りになると、滅入りません?」
立木「滅入って、どうするんですか、僕が? 滅入って、もうやれないというんですか、じゃあ?」
高村「私だったら言ってしまうかも知れません」
立木「高村さんはそうおっしゃってもいいですよ。僕がそう言ってもしょうがないでしょう?」
高村「しょうがない……。そうすると、もうほとんど……なんでしょう?」
立木「それぞれの気持ちの中のものを、そんなに生活の中で出してもよきものか、ってのもあるでしょう? 〈泣くの嫌さに、笑って候〉で生きてるわけです、僕も含めて。そりゃ、泣きたいような話はいっぱいありますよ。事実こう、なんかの切っ掛けでドーッとしゃべってくれるんですよ。と、受けとめようがない。頷くしかない」
---------------------------------------------------------
一一 震災でほとんどの建物が倒壊し壊滅状態になった、在日朝鮮人の多く居住する下町地区とその地元小学校を訪れる立木。(詳細省略)
---------------------------------------------------------
一一 港の岸壁で、神戸での撮影について、スタッフの質問に答える立木。高村は不在の模様。
立木「や、そういう凄さってのがあるじゃないですか。自分はさ、大変なことにあって、ま、十年経ってるとは言え、『(※ 手まねで「あ〜ら」)立木さん、お元気ですか?』って、こういうね、下町のおかみさんのさ、ああーって思うよな。あの元気さ、いいね」
スタッフ「楽しいですね、今日の取材」
立木「いやあ、そんなに深刻にやっちまえばできるけど、それはなんかつまんないでしょ? それは寝る時に思えばいいわけですから」
---------------------------------------------------------
一一 再び、先ほどのお好み焼き屋(続き)。
立木「(…)困った時に、……(※ 自分の)母親もそうだったけど、そのおばあちゃんっていうのも、何かがあると、おにぎり、すぐ作る、おばあちゃんなんですよ。とにかく食べて元気を出そうっていう、そこから始まるという。うん、じつにシンプルな生き方なんですけど、その凄さってのは、やっぱり凄いですよね」
高村「その神戸で、神戸の周辺でね、被災した方、あるいは、その少し外で、まあ地震による経験をした何百万という人が、みんなそれぞれ影響をうけて、その後の人生変わったと思うんですよね。それがね、私にとっては、こうー、この十年、もしもあれがなかったらとかね。ねえー、いつもあまり、こうー、そんなプラスの方に考えなかったんですけど」
立木「プラスでいきましょうよ」
高村「うーん、ですから今日はね、ちょっとホラ、目からウロコ?」
立木「高村さんがその内なるものでいろいろ悩んだり、痛みをすごく敏感に感じたり、いろいろなさっているのを側で見ていると、やっぱり周りもつらいじゃないですか? そういうつらいことっていうのは、いろいろそれぞれあるんだけど、まあ、なんとかひとつ乗り越えるという方法じゃないと、ちょっと、結構しんどいですね。やっぱり、こうー、頑張るってのもおかしいんだけど」
高村「いやまあ、普段はね、けっこう明るく生きているんですけど、だけど…、明るいんですよ」
立木「こと、神戸に関して?」
高村「うん、なんか……つらい」
立木「ね。で、こうー、そういうのって」
高村「うーん、でも、それ、あまり大きな声では言えないんです。というのも、自分は家も壊れてないし、家族も亡くなってないのでね。そんな人間がつらいって何事かって言われたら、たしかにそうなんです。だからー、自分にできるのは、せめて、やっぱ、なんか絶対これを考え続けるだと、それしかできない、と思うんですね」
立木「だから、それぞれが考え続けてください。僕は撮りつづけます、みたいなことしかできないんですけど(笑)」
高村「それはね、たしかにそうなんですけど(笑)」
立木義浩の目に「高村薫の苦悩」がどのように映ったかは、想像に難くない。
立木義浩の根底にあるのは『何かがあると、おにぎり、すぐ作る、おばあちゃん』『とにかく食べて元気を出そう』っていう「庶民の強さへの信頼と尊敬」である。

一方、高村薫がどうかというと、彼女はその対極にある「意味偏重」の「観念的インテリズム」の人でしかない。
だから、立木は高村の「自分のための(アリバイとしての)苦悩」に苛立たされ、「貴方は貴方で悩んでて下さい。貴方が悩もうと悩むまいと、人々はそれに関係なく、自分たちの力で立ち上がっていきますから」というニュアンスで、立場の違いを語らざるを得なかったのである。
もちろん、高村薫は、自分が「知的エリート」や「物書き」であることを鼻にかけて、ことさら知識人ぶった「苦悩ぶり」を見せたわけではない。
前述したとおり、高村は、その「育ちの良さ(=ピアニストを目指したような、お嬢さん育ち=庶民感覚の欠除)」に「引け目」を感じていればこそ「庶民」に憧れ、それとともにあろうとしたに過ぎない。たしかに『自分は家も壊れてないし、家族も亡くなってない』し、その意味で「恵まれている」んだけど、でも「みなさん」と一緒にありたいんです、だから一緒に悩ませて下さい。一一そんな感覚なのである。
だからまた立木も、高村の鈍感さに苛立ちながらも「この人は善意でこんなこと言ってるんだから、あんまり責めちゃ可哀想だ」と思って、多少は言葉に手心を加えていたのである。
しかし、高村薫のこうした「鈍感さ」は骨がらみのもので、立木に少々お説教をされたくらいで治ってしまうような柔なものでない。
例えば、番組は、上のシーンに続いて、次のように進行する。もちろん、現実の時間関係は定かではないが。
一一 神戸・三宮の繁華街を歩く高村。道ゆく人・行き交う車・街の姿に、震災の爪痕は窺えない。
ナレーション「神戸の中心地、三宮。高村さんは、無名の人ひとりひとりに奥深い人生があることを、震災によって、あらためて思い知らされました」
一一 陸橋から街を眺める高村。
高村「街ですれちがう人、あるいは目に見える建物、車、人。そういう目に入るものをそのまま、……えー、なんだ……写真を撮るように眺める? 物書きの目はそういう目ではありませんので、むしろ見えているものの裏、裏側、あるいは見えないものを見ようとする、そういう目だと思います。」
ナレーション「愛する人を亡くした喪失感を抱えて生きる人。住み慣れた地を離れ、孤独に生きるお年寄り。二重ローンを抱えながらも懸命に働く人。一一表面には見えないひとりひとりの哀しみを思う時、想像もできないような奥深い人生が見えてくるのです。一一無名の人々を見つめる。作家高村薫さんの場合、それは作風の変容に現れました。
デビュー以来、高村さんは社会を描く骨太のサスペンス小説を書いてきました。しかし、震災後、高村さんは、人が死ぬようなストーリーを書くことにも、事件を作り出すことにも、まったく興味が持てなくなったのです。
震災後五年の歳月をかけて完成させた『晴子情歌』。一一それまでとはまったく異なる、純文学的な作風。作家高村薫にとって決定的な変容でした」
---------------------------------------------------------
一一 自宅で語る高村。
高村「へんな言い方ですけど、普通の人々の再発見……でしょうか。人間に、本当の意味で人間に目がいくようになったと思います。もちろんそれを表現できるかどうかは能力の問題なんで、別です。自分に、あまりそういう自信もないですし、書けるかどうか、それはまたぜんぜん別なんですけど、人間を見ようとする、その立ち位置と言うんでしょうか、視線は、震災を経験したから、やって来たんだと思うんですよ」
高村が、ここで大真面目に語っているのだというのは、断るまでもなかろう。だが、ひとことで評すれば「まったく、いい気なものだ」。一一人間というものは、そんなに簡単に変わるものじゃないし、第一、高村は震災で、どれほどの体験をしたというつもりなのだろうか。
たしかに「死に直面した」「心のポッカリ穴が開いた」などと自己申告しているが、それがその言葉に値するほど深刻重大なものなのなら、どうして震災で家を失ったり家族を亡くしたりした人たちに「負い目」を感じなければならない?
たしかに、家を失うというのは大変なことだ。家族を災害によって失うのもたまらない経験だ。しかし、そんなことは、なにも「阪神・淡路大震災」だけで起ったことではないし、日本に限られたことでも、現代に限ったことでもない。そんな悲劇(戦争・災害・事故等)は、人間の歴史とともに常に、世界のあちこちであったことであり、例えば「頭数」が問題にもならなければ、「ニュースバリュー」もない交通事故によって、かけがえのない家族を失う人だって、日常茶飯事に存在するのである。そして、無論そうした顧みられない個別の「死」が、震災の中での死よりも「軽い」ということは、金輪際ありえないのである。
だから、高村薫が、真に人生観に変更を来たすような「経験」をしたというのであれば、高村は家を失った人や家族を亡くした人に「負い目」を感じる必要などないし、感じるのは「おかしい(筋違いな)」のである。なぜなら、どうして「個人の苦しみ」を単純に比較考量できるのか、そんな比較考量がそもそも可能なのか、ということだ。
高村薫は、その比較考量の可能性を、安易に無神経に認めていればこそ『自分は家も壊れてないし、家族も亡くなってないのでね。そんな人間がつらいって何事かって言われたら、たしかにそうなんです。』などと、無責任に言ってしまえるのである。
そんなことがもし可能だと言うのなら、「3歳の子供を死なせた親の方が、80歳の親を亡くした子の方よりも、哀しみが深い」などと言えてしまうだろう。高村の言っているのは、所詮そういうことでしかないのである。
しかし、これは明かに間違いである。人の苦しみを比較考量することなど、所詮は不可能だし、それが可能だと考えるのは「傲慢」でしかない。一一ここまで説明すれば、いかな高村でも、己が過ちに気づくはずである。

ならば、高村は、それまで『自分は家も壊れてないし、家族も亡くなってないのでね。そんな人間がつらいって何事かって言われたら、たしかにそうなんです。』などと考えていたことについて、どう反省すればよいのか。
それは、もし高村の震災体験が、真に「死に直面した」「心のポッカリ穴が開いた」と表現するに値するものであるのならば、「自分は、家を無くした人や家族を亡くした人以上に、厳しい体験をしたのだ」と、自分の体験に「持つべき自信」を持ち、そのことで自分の体験に「責任を持つ(担う)」べきなのである。
人から責められないためだけに、その場その場で、重大な体験をしたんだかしてないんだかわからないような、そんないい加減なことを言うのを止めれば良いのである。
もちろん、これは「物書き」「言論人」としての最低限の責任であるに止まらず、それ以前に「一個の人間」としても、当然担うべき責任なのだ。


また、よくよく自分を観察してみた結果、「死に直面した」「心のポッカリ穴が開いた」といった自己申告が、実際のところは、「震災被災者と同苦したい」という願望に由来する、過剰な「思い込み」であることがわかったのなら、自分は「重大な震災体験などしていない」というところから出発して、謙虚に震災に関わっていけば良い。
直接震災を体験しなかった立木義浩でも、あのように立派に震災にかかわっていけたのだから、震災に深く関われるか否かは、自身がそれを体験したか否かで決まるわけではないのである。むしろ、自分はそれを知らないという「現実」を直視し、そこから想像力を働かせてこそ、より深い真実に到り得るのであって、高村のように、現実直視を避けて通った手前味噌な観念優先では、想像力ではなく、(立木を苛立たせたような)自分勝手な「(ロマンチックな)妄想」を膨らませるのが、関の山なのである。
『「(…)『チゴイネルワイゼン』を支えるものも、結局はこれだ。早弾きの即興演奏だけが生みだす、奔放で華麗な旋律だよ。最高にスリリングで、砕いたダイヤモンドのように美しい。しかしオリジナルのエモーションが、西洋流の楽譜主義に隠れてしまって、今までぼくにはよく聴こえなかった。でも何故か今、聴こえるようになったんだ。だから解る。これは南の道を通り、スペインに流れてギターに出遭った者たちの音楽と同じものだ。同じスピリットで、同じ音楽が奏でられていた。今、はっきりとわかったんだ」
どうしたことかキヨシは、今日は妙に興奮していた。
「この曲のあちこちに覗く奔放で華麗な感覚、これを毎度そのまま楽譜通りに演奏するなんてね、なんだか妙な気がするよ、これは当時ハンガリーに存在してサラサーテを打ちのめした、名もなき天才に帰するべき功績だ。彼、……と思うが、彼のアドリブの腕とセンスは、千年先を行っていたんだ。
さすらう民の、虐げられた悲しみの旋律、みんなそんなふうにこれを聴こうとする。ジャズも同じだ、虐げられた南部黒人の悲しみ……、ふん、なんて通俗だ! そんなことじゃない。そんなふうにアプローチしても、決して彼らの音楽は演奏できない。彼らのこれは、スポーツなんだ。バスケットボールと同じ、体が自然に打ちだすリズムだ。これがすべてを、ごく自然体でやってのける。
パワーがプレイの奔放さの理由であり、細かい音符を産む力だ。理論なんてね、後でゆっくり考えたらいい。楽しさなんだ、彼らが目指したものはね、むしろそっちなのさ。悲しみは、彼らの体から滲む汗のひと滴のようなもの、抑えても自然に湧く。悲しければ人は楽しさを求める。彼らが目指していたものは、悲しみなんかじゃない」』
(島田荘司『ネジ式ザゼツキー』より)
『ふん、なんて通俗だ!』一一 高村薫の言う『作家の目』など、所詮は「転倒した自負」の生んだ「妄想」でしかない。
高村は『見えているものの裏、裏側、あるいは見えないものを見ようとする、そういう目』が『作家の目』だというけれど、「表、表側、あるいは見えているもの」を『写真を撮るよう』に見て、正しき認識することのできない人間に、どうして『裏、裏側、あるいは見えないもの』を見ることができると言うのだろう。
一一つまり、高村薫は「斯くあるべき事(あるいは、斯くあってほしい事)」と「斯くある事」の区別すら、満足についてはいないのである。
高村薫のこうした「非論理思考」に寄り添った結果、ナレーションの言葉まで論理破綻を来たしている。
『表面には見えないひとりひとりの哀しみを思う時、想像もできないような奥深い人生が見えてくるのです。』
『思う』ことと『想像』することを、無根拠に「別物」だと語ってしまえる「非論理性」があって初めて、ここで『見えない』ものが『見えてくる』と語り得るのである。
つまり、「思い得る」とは「想像でき得る」ということであり、当然それらの対象は『想像もできない』ものではあり得ない、ということなのだ。
もちろん、同様に高村薫の言う『普通の人々の再発見……でしょうか。人間に、本当の意味で人間に目がいくようになったと思います。(…)人間を見ようとする、その立ち位置と言うんでしょうか、視線は、震災を経験したから、やって来たんだと思うんですよ』という自己認識も、「ロマンチックな妄想」であり「自分勝手な誤認」でしかない。
例えば、高村薫はここで、震災で家や家族を亡くした人たちに「負い目」を感じる程度の震災体験によって「人間が(より深く)見られるようになった」つまり「認識能力が増した」と主張しているわけだが、これが本当なら、高村が交通事故にあって両足を切断する体験でもすれば「神のごとき認識力」を身につけることになるだろう。
つまり、ここでも高村は、自身の震災体験に「過剰な意味づけ」をしたいがために「人間を見る目が変わった」などという誇大妄想を抱くに到っただけなのである。
高村薫ファンなら誰でも知っていることだが、高村薫という作家は、基本的には昔から「人間が描きたい」作家であり、だからこそ『マークスの山』で直木賞を授賞した際、「私が書きたかったのはミステリではなく、人間だった」と、正直かつ無神経な発言をして、ミステリ関係者の顰蹙を買ったりもしたのである。
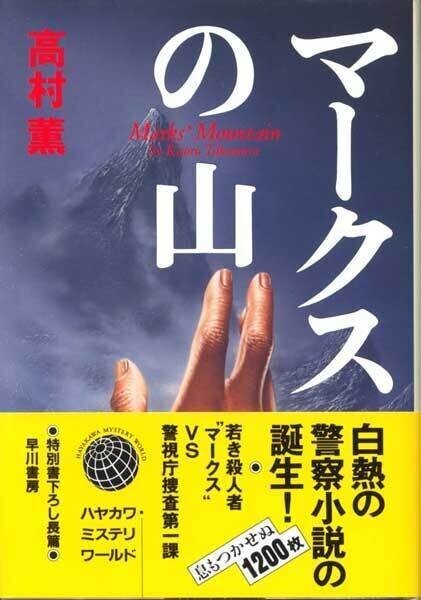

つまり、高村薫という人は、まったく悪気なく、その時その時の思いつきを大真面目に語ってしまう、明晰さに欠ける、無防備(無責任)な人なのである。
例えば、高村はこの番組『ETV特集 阪神・淡路大震災10年 作家 高村薫 思索の旅』の中で、『晴子情歌』が売れなかったことに触れて、でも自分の変化は間違ってはいないと信じているので、売れなくても信念をつらぬいて書いていく、という主旨のことを(ナレーションを介して)語っている。
しかし、2年前の『真剣10代しゃべり場』では、「仕事」ということに関して、子供たちの対し、今のそれとはまったく正反対の考えを語っていた。
すなわち 一一 仕事というのは、基本的にはお給料分だけは最低稼ぐ、それだけは会社に儲けさせるというのが基本である。もちろん、それでは赤字になるから不十分なのだが、原則としてはそういうものだ。物書きだって同じで、本を出してくれる出版社に儲けさせてあげなくてはいけない。それがプロだ。けれども、それは予想される売れ線を狙って作品を書くということではない。そうではなくて、誰もが考える売れ線の一歩か半歩先を行くことで、良い作品を書きかつ売れるというのでなければならない。今までの自分に安住するのではなく、自分を壊し新たに作りながら進んでいくというのが、本当のプロの仕事だ。一一と大要このようなことを語っていた。
この言葉に対し、出演者の女子高生が「でも、その見極めって、とっても難しいんじゃないでしょうか」と〈それは誰にでもできることではないんじゃないか、そんなことを皆に要求しても無理なんじゃないか〉という疑問をにじませて問うたところ、この当然の疑問に対し高村は「それがプロですよ」とあっさり応え、今となってみれば「斯くあるべき事(あるいは、斯くあってほしい事)」と「斯くある事」の区別すら満足につかない、「売れっ子」だった当時の「いい気さ」を見せていたのである。
つまり、高村薫本人としては、売れている当時は「売れるだけの価値のあるものを書いているから、必然的に売れているのだ。売れないものには売れないなりの問題点があるから売れないのだ」と「論理的・合理的」に考えている「つもり」だったのだろう。
だが、世の中そんなに単純なものでないことは、少なくとも世の中の「現実」を直視しておれば、容易に理解できたはずだ。
当時の高村にそれができなかったのは、ひとつには当時彼女が「天狗になって、世間をなめていた」ということもあるだろうし、今も昔も変わらず「現実が見えていない」ということでもあろう。
いずれにしろ高村は、今も昔も「斯くあるべき事」と「斯くある事」の区別がついておらず、そのためにずっと「自身を誤解している」のである。
そして、そんな高村にとっては、「天狗になっているかいないか」などという問題は、非本質的で瑣末なものでしかないと、私は考えるのである。
「物書きとしての自認」にしろ「震災体験者としての自認」にしろ、とにかく高村薫の問題は、「斯くあるべき事(あるいは、斯くあってほしい事)」と「斯くある事」の区別がついておらず、自分を客観視できていないという点に、根本的な問題がある。自分が「何」に衝き動かされているのか、それもわからずに対象に向き合っても、対象を正しく認識することなど、当然のことながら不可能なのだ。
つまり、立木義浩を苛立たせた、高村薫の震災に対する「ピンぼけ」ぶりや「独りよがり」の問題は、高村薫がいかに「理性的」になる得るかにかかっていると言えるだろう。
しかし、ここで重要なことは、「理性的である」=「理性的に自身を保つ」ということは、いわゆる「頭の良さ」だけでも「真面目さ」だけでも、あるいはこの二つが揃っていたとしても、事実と自他に対する「厳格さ」が欠如しているならば不可能だ、という事実である。
そして、高村薫には、この「事実や自他に対する厳格さ」が、決定的に欠けているのだ。
私に言わせれば、高村薫という人は、文字どおり「そこいらにいる(真面目さと学歴だけはある)おばちゃん」と(能力的に)変わりはない、ということであり、そんな人間なら、身の程知らずの「批評家」ごっこは止めておいた方がよい、ということである。
高村薫が自ら進んで、あるいは時に求めに応じて、「事件」や「社会問題」について、書き語ったものは、たいがい凡庸で取るに足らないものだと言えよう。もちろん、まったく取り柄がないとは言わないが、素人が書いたものにだって多少の取り柄はあるのである。
もちろん、高村薫がそれを「商売」だと割り切ってやる分には、私はそれをとやかく言うつもりはない。ただ「駄作は駄作」だと評価するだけで、書くこと自体を非難するつもりは毛頭ないのだ。
しかし、高村薫が、その事実に気づいておらず、自分が何がしか「非凡」なことをやっているのだと勘違いしているのだとすれば、それはファンとして見ていられないから「止めろ、止めてくれ」と言いたいだけなのである。
○ ○ ○
私はこの「高村薫論」と副題した文章で、高村薫が「いかに頭が悪いか」ということだけを語ろうとしているのだろうか?
もちろん、そんなことはない。
私がこの「作家論」で語りたいのは、「高村薫という人は、ここまで頭の悪い人である。しかし、それにもかかわらず高村薫の小説はすばらしい。これは何を意味するのか? その答は、高村薫は、その表面的な知的能力を超えたところから、ああしたすばらしい作品を生み出してくる、生まれながらの天才作家、天然小説家なのだ」ということなのだ。
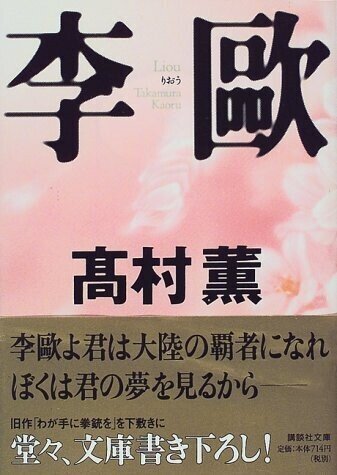
だから、高村薫の小説を(テレビのナレーションでもそう評していたが)「骨太」「論理的」「重厚」あるいは「男性的」などと評するのは、いかにも「皮相的」な評価としか言えない。
高村薫の、真の「美質」とは、そうした「意図した部分」「技巧を凝らした部分」にあるのではない。
そうした「構築物」の下から噴き上げてくる「真っ赤な情念の炎」の非凡な激しさこそが、高村薫という作家の本質的な魅力であり、他者の追随をゆるさない、圧倒的な天性なのである。
そして、当然のことながら高村薫自身は、そのことに気づいてはいない。
だから、自身の創作姿勢について、『ETV特集 阪神・淡路大震災10年 作家 高村薫 思索の旅』の中で、次のように語っている。
一一 『レディ・ジョーカー』の主人公に、ほとんど唐突に「震災」について語らせた理由について、自宅書斎で語る高村。
高村「私の中に地震はあるんだけど(※ 『レディ・ジョーカー』の仕事で上京した際に接した)東京の人の心には地震はない。そのギャップが、私の中でたぶん宙吊りになってたと思うんですけども、だからといって、私の口から地震地震と言うような空気でも、もちろんない。なんかこうー、あまり意識せずに、主人公に、地震のことに触れさせていた。これこそ衝動? ふつう物書きは衝動では書かないんですけど、まあーたまに珍しいことが起る。そうー、最初で最後かなーとも思います。そういう衝動を噴き出させて、それの痕跡をあえて残しておいたというのは。ふつうは後で、本にする時にぜんぶ削るんですね。でもなんか、それはー、なんか私の中で削りたくなかった。衝動だとわかってたんですけど」
ここで高村は、自分は「衝動」で書いているわけではない。むしろ普段は、プロとして冷静に作品を組み上げ、意識的に文章を書きつけていっているのだ、という風に主張している。
もちろん、これは嘘ではない。そのとおりなのであろう。だが、だからこそ、高村薫の小説は「真っ赤な情念の炎」が噴き上げほとばしる作品となりえているのである。それを抑えようとする力が働けば働くほど、それを突き破って噴出する情念の炎は、さらに激しく燃え上がるのである。
『作者個人を上まわる価値を有する著作こそ、優れているといわれていい。』
(榎並重行『危ない格言』より)
つまり、高村薫という「小説家」にとって、自分の実際について無自覚であることは、かならずしもマイナス要因とはなり得ないのだ。
むしろ、生じっか、自分が「情念の作家」だなどと自認して、情念を書きつけようなどとすれば、それは「自堕落な情念の垂れ流し」となり、力のない小説を結果してしまうことになろう。その点高村は、見事なほどに「無自覚」な作家であり、その無自覚さが、自身の「美点」を甘やかさない「禁欲的な自己抑制」となって働いたからこそ、彼女はその「創作」において、彼女の持つ「自覚されていない非凡な潜在力」を、最大限に活用することに成功したのである。
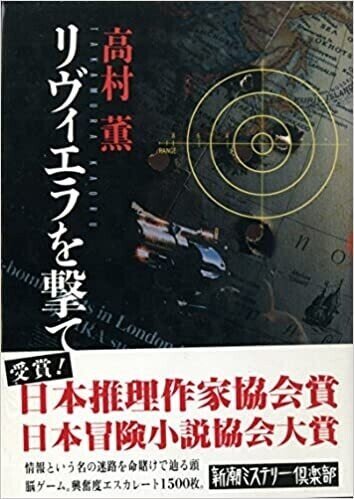
では、無意識のうちに「自らの頭の悪さ」をも利用して自己実現を果たしてみせた、高村薫の「天才」であり「情念」とは、いったいどういうもなのか?
それは、彼女自身が認識し誇示してもいる、表面的・擬似的な個性としての『「骨太」「論理的」「重厚」あるいは「男性的」』という特徴とは対極にある、「繊細」で「直観的(=非論理的=感情的)」で「傷つきやすく=弱い」「女性的」な、一一彼女の、自他に隠された「本性」なのである。
つまり、高村薫という作家は、その見掛けに反して、古風なまでに女性的な作家なのである。
だから、彼女は「愛され」「庇護され」それでいて「過剰に他人に気づかうことなく(小心ではなく)」「自由に生きる」人間を、「孤独に絶えうる」「強い」それでいて「感情的になることを怖れない」人間を(無意識に)描くのだ。
生活の場における自身が、自他から強く束縛されていることを、イヤというほど実感していながら、実際にはそれを振りほどけない「弱い」人間だからこそ、高村薫は想像の世界において、その満たされない欲望をほとばしらせるのである。
もちろん、これは作家として、何ら恥ずべきことではない。
作家・小説家は、その「作品」において自己を実現し、自己を達成すれば良い。
その意味で、高村薫は、天性の小説家。小説家になるために、現実世界における、あらゆる弱さを天から授かった作家だと言えるのである。
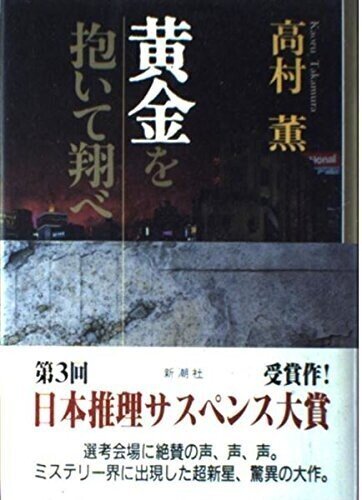
だが、その彼女が今、その凡庸な知恵の導きに従って「普通の人間」を描くことに向かおうとしている。
言うまでもなく、これは危険な選択であり、間違った選択である可能性が極めて高い。
だがしかし、彼女の「秘められた天才」は、そんな凡庸な知性の賢しらな選択など、撥ね除けてあまりある力を持っている。だから、この選択が、高村薫にとって、道を誤った致命的な選択となるかどうかは、まだ判断できる段階にはない。
読者よりもむしろ、高村薫本人にこそ「見えない」、高村薫という作家の非凡な天性。
その「真っ赤な情念の炎」は、きっと「凡庸な評論家」「弱い人間」としての高村薫の統制など撥ね除けて、これからもその炎を、より高く激しく燃え上がらせてくれることだろう。
高村薫という作家は、それほど非凡な作家だと、私は信じるし、そう信じるからこそ、彼女の「非本質的な表層部分」をずたずたに切り刻んで否定することに、なんら躊躇も感じなければ、何を怖れもしかったのである。
秘められたる我が高村薫よ、今またその賢しらな仮面を、再び三たび焼きつくすが良い!
私は、おまえの力を疑いはしない。
2005年2月7日
○ ○ ○
https://www.amazon.co.jp/s?k=高村薫+本
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
