
芦辺拓 『紅楼夢の殺人』 : 捨て去られた 〈リアル〉の価値
書評:芦辺拓『紅楼夢の殺人』(文藝春秋)
(※ 再録時註:本稿の中で紹介している、芦辺拓の『最近の新本格では、そうした作品と現実とのすり合わせ作業がどんどん要らなくなってきているように思えて、その点に強い違和感を感じる』という言葉は、本格ミステリの「ラノベ化」への危惧、と言い換えることができる。つまり、業界的「暗黙の了解=お約束」を踏まえて、説明を省略する傾向である。例えば「なぜ転生したのか?」に説明の必要はなく「転生したのだ」で済まされる。しかし、この便利な「お約束」が、文学にもたらすものとは何なのかというのは、真剣な考慮を要しよう。なぜなら、それは、文学における現実遊離と現実逃避を、無自覚に正当化するものだからだ。言い換えれば、読者に求められる知能の軽量化の問題である)
芦辺拓の『紅楼夢の殺人』(文藝春秋)を読んだ。
周知のとおり、この作品は、昨年の国内の本格ミステリ最高傑作の座を、法月綸太郎の『生首に聞いてみろ』、綾辻行人『暗黒館の殺人』、横山秀夫『臨場』などと競い合った作品である(※「第5回本格ミステリ大賞」のこと)。

私は、まだ『臨場』を読んでいないので、この作品との比較はできないが、既読の『生首に聞いてみろ』『暗黒館の殺人』の両作品と比較するならば、本作『紅楼夢の殺人』は「本格ミステリ大賞」の投票結果どおり、『暗黒館の殺人』を遠く引き離して、『生首に聞いてみろ』とのみ競い合う傑作だったと思うし、個人的な好みで言うならば、「本格ミステリ大賞」の結果に反して、私はこの『紅楼夢の殺人』の方を高く評価したい。
『紅楼夢の殺人』と『生首に聞いてみろ』は、共に「本格ミステリ」と呼ばれるジャンルに属する、極度に「人工的」な小説なのだが、両者の個性を隔てるのが、この「人工性の方向性」の違いであると言えよう。またその点で、読者の「好み」にもとづく評価も、ハッキリと分かれてくるのである。
『生首に聞いてみろ』は、作者と同名の「ミステリ作家にして名探偵」である法月綸太郎が、現代の日本を舞台にして活躍する「本格ミステリ」である。つまり、そこに描かれている「舞台」としての「世界」は、私たちの日常と地続きの「リアルな世界」としての「現代日本」だ。
しかし、その舞台の上に盛られる(事件-解決の)ドラマは同じような意味で「リアル」なものというわけではなく、極度に「人工的」であり、およそ現実には起こり得ないものだと言えよう。
だが、たいていの読者は、法月綸太郎のミステリに、日常的なドラマなど求めてはいない。つまり、名探偵法月綸太郎が「リアルで平凡な強盗事件を、足を棒にした、地を這うような地道な捜査で追い詰める」というような物語を、読者は求めていない。だから、法月綸太郎の作品に求められているのは、あくまでも「非現実的」なまでに「緻密な論理のアクロバット」なのだ。
したがって、『生首に聞いてみろ』にしても、一読してまず感じるのは「よく作り込まれている」ということなのだが、その「作り込み」が丹念・端正であればあるほど、作中に描かれた「事件」や「犯罪」が、「リアル」な現実にはありえない「作り物」としてのカタルシスを読者に与えるとともに、その一方で、作品が描き出した「リアルな世界」との齟齬を際立たせるのである。
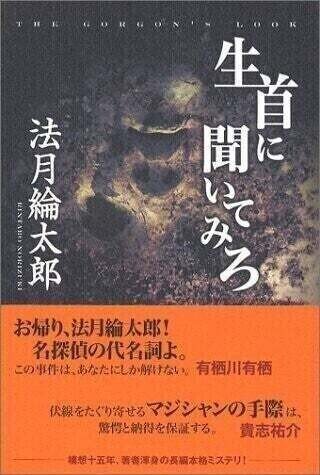
さて、ではこういう「物語(の作り)」と「舞台(の作り)」が、齟齬を来たした作品を楽しめる読者とは、いったい如何なる読者なのであろうか?
それは「本格ミステリとは、もともと独自の世界観をもつ小説なのだから、その独自の美意識において優れておれば、小説としての首尾一貫性は問われない」というような、「誤った了解」を持っている「ミステリファン(マニアを含む)」である。
つまり、『生首に聞いてみろ』のような作品をして「そこに描かれた舞台と事件・犯罪が齟齬を来たしている、というような野暮な評価をするような読者は、本格ミステリというものがわかっていないんだ」と考えるような読者だと言えるだろう。
一一しかし、下記のとおり、私自身は、そのような「野暮な」読者の一人である。
『だが、そのような「玄人好み」の作品が、一般に「面白い」小説となりえているとは限らないし、「本格ミステリ」としては良く出来ていても、「小説」として良く出来ているとは限らない。そうした意味で私は、『生首に聞いてみろ』が「良く出来たミステリ」の域を出ない作品だと評価するのだ。
じっさい、本作のメイントリックは、この作品の作品世界内においても、リアリティーがあるとは言い難い。作中で早々に「ありえない」とされる(捨て)トリックは、たしかに「推理クイズ」的なチャチなものであり、その意味でリアリティーの無いものだが、本作の根幹をなすトリックも、この、わりあいリアルに構築された作品世界においては、「心理的」に無理のある、つまりリアリティーに欠けるものなのだ。
もしもこの作品が、かつての長編のように「家庭悲劇に対する自己投影的な懊悩」に満たされたものであったならば、このメイントリックも幾分かはリアリティーを持ちえたかも知れない。しかし、この作品では、そうした内面描写が排除され、外面的事実を中心とした描写がなされたため、「ふつう、そんなことはしないだろう」という行為(メイントリック)が、そのままそのように感じられるものとなってしまっている。つまりこの作品は、作者の技量は認めるとしても、やはり「リアリティーの無いメイントリックに支えられた、(単なる)本格ミステリ」になってしまっているというのが、私の評価なのである。』
(2004年10月27日「アレクセイの花園」所掲「敗者の栄光」より)
しかし、このように感じるのは、何も私一人ではない。
現に『紅楼夢の殺人』の作者である芦辺拓は、同書(※ 初版単行本)巻末のインタビューの最後で、次のように指摘している。
『【物語至上主義者として一言】
綾辻行人さんの館シリーズでは常に、館と外部の空間が併置されますし、有栖川さんの作品には、大学のミステリ研究会や推理作家が登場する。二階堂氏の場合には、過去に舞台を求める。これらは、作中でミステリ的な出来事が起こっても不思議ではない異空間を作るための作業であると解釈しています。僕の『殺人喜劇の13人』の場合、館の連続殺人を描きたいと思ったとき、そういう館が現存しているとしたら何だろうというところから発想したわけですね。(中略)つまり、館や探偵というものと現実の空間のすり合わせをした結果、ああいう設定になった。ところが、最近の新本格では、そうした作品と現実とのすり合わせ作業がどんどん要らなくなってきているように思えて、その点に強い違和感を感じるわけです。(以下略)』


芦辺がここで指摘している『作中でミステリ的な出来事が起こっても不思議ではない異空間を作るための作業』『館や探偵というものと現実の空間のすり合わせ』というものが、法月綸太郎の作品、特に最新長篇『生首に聞いてみろ』には存在せず、デュパン、ホームズ以来あるいはクイーン以来の「お約束」である「非現実的な名探偵」を、アンバランスなまでに「リアルに書き込まれた現代日本」に、無造作に配置しているのだ。
その点、芦辺拓の『紅楼夢の殺人』は、「舞台」と「登場人物」と「事件・犯罪」を密接不可分な「物語の構成要素」として一体化させ、見事に調和させている。
両者の違いを、料理人に譬えると、法月綸太郎は「手の込んだ料理」を作る「技巧派」なのだが、その料理を盛る「器」にはまったく無頓着な(あるいは、先人盲従)タイプ。
一方、芦辺拓の方は、料理とは「総合芸術」だと考え、料理そのものへのこだわりもさることながら、その料理を最高に生かす「プレゼンテーション」まで考えて、料理を作る(仕切り屋)タイプ、だと言えよう。
こうした意味で、『紅楼夢の殺人』の素晴らしさは、『生首に聞いてみろ』の対極にあって、それは「何にこだわるか」の差から来ているのである。
つまり、作中に描かれた「トリック」だけを取り出してみれば、それは明らかに『生首に聞いてみろ』の方が「緻密」でよく出来ている。
その点、『紅楼夢の殺人』には、その種の「トリック」や「緻密さ」は無いと言っても過言ではなかろう。
だが、それは、それが書けなかったということではなく、作者の興味はそこには無かったということなのだ。芦辺拓が『紅楼夢の殺人』で描いたのは、「緻密なトリック」ではなく、「トリックを弄した理由(動機)のアクロバット性」つまり「なぜそんな凝ったトリックを仕掛けたのか」ということ(心理問題)であり、この場合、作中に描かれるトリックは「見かけ上の趣向さえ凝らされておれば、緻密でも斬新でもなくてよかった」ということになるのである。


したがって、『生首に聞いてみろ』に見られるような「作り込まれたトリック」といった「即物的な部分」に期待した読者は、『紅楼夢の殺人』のそれに、ある種の肩透かしを喰らわされるのだが、そのかわり、その後の最終盤に明かされる「逆転の論理」は(「異世界本格ミステリ」の大傑作、山口雅也の『生ける屍の死』にも匹敵するほどの)実に鮮やかなものなのだ(ただし、『生ける屍の死』という傑作は、『生首に聞いてみろ』的な緻密さをも兼ね備えたその「全円性」において、稀有な作品だった)。
このようなわけで、近視眼的な読者には、『生首に聞いてみろ』の即物的な面白さは理解できても、『紅楼夢の殺人』の面白さは理解できない怖れが十分にあるし、そもそもこの作品は、そのすべてを「最終盤の大逆転」に賭けているという点で、古い「本格ミステリ」性をかたく保持しており、せっかちな現代読者を排除する部分が無いとも言えない。だから、『紅楼夢の殺人』よりも『生首に聞いてみろ』を面白いと感じる人や、高く評価する人がいても、それは「好み」の問題として、何ら不思議はないのであるが、一一もともと「世界を反転させる」ような作品、つまり中井英夫の『虚無への供物』に代表されるような「反世界のリアリティー」を描き出す作品に魅力を感じる私のような読者なら、『紅楼夢の殺人』のような「世界に関する物語」に、強く惹かれざるを得ないのだ。
一一ともあれ、現時点で言えば、本作『紅楼夢の殺人』は、私の昨年のミステリベスト1作品である。
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
