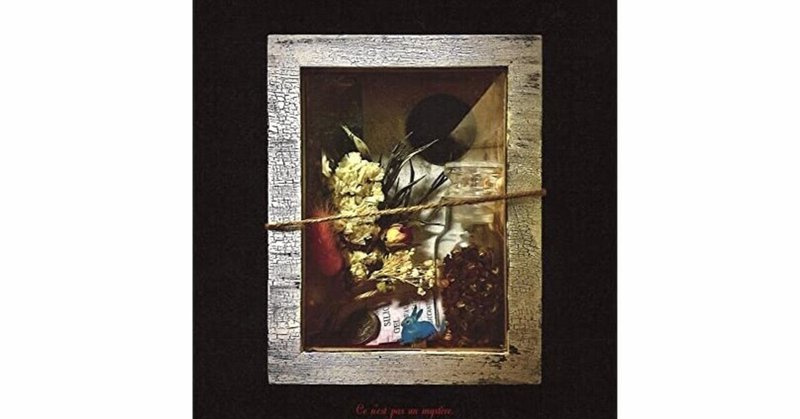
竹本健治 『これはミステリではない』 : 〈見えすぎる眼〉の欲望
書評:竹本健治『これはミステリではない』(講談社)
その頃私は、会社の夏期休暇には毎年、関東の友人の家へ泊まりがけで遊びに行っていた。
そんなある日、友人宅のリビングで、二人でテレビを視ていたところ、あの事件の第一報がニュース番組で報じられた。「小学生児童の切断された首が、小学校の正門前に置かれており、地元新聞社に挑戦状が郵送されたきた」という、後に「酒鬼薔薇事件」「酒鬼薔薇聖斗事件」などと通称され、「神戸連続児童殺傷事件」と呼ばれるようになる、あの事件だ。
私は、そのニュースを視て、そくざに腹を立てた。子供への残酷きわまりない犯行という点が、まず私の逆鱗に触れたし、しかも挑戦状を送りつけるなどという「世間をなめた」としか言いようのない犯人の態度に、とうてい許しがたい怒りを覚えたのである。
そして私は、その怒りを、いっしょにテレビを視ていた友人に伝えた。当然、共感してもらえるものと思って、私の感情をぶつけたのだが、その友人の反応は極めて薄く、あきらかに私のような怒りの感情は無い様子で、どちらかと言えば、その異常な犯人に興味をもって、事件の詳細に耳を傾けているという感じだったのである。
この友人の態度に、肩すかしを食らわされて不満だったのは言うまでもないが、同時に「どうして、こんな犯罪に、こんな犯人に、腹を立てずにいられるんだろう」という、深い「疑念」を覚えたのもまた確かだった。「この人の頭の中は、いったいどうなっているのか」と。
○ ○ ○
本作は、タイトルどおり「ミステリ」ではない。通常の意味では、そうだ。
だが、私は本作を読み終えて、ため息をついた。
一一「やっぱり、竹本健治は天才なんだな」と。
では、そんなため息をつかせた本作は、いったいどのような小説なのだろうか。
いろんな呼び方が可能であろうが、ひとまず私は、本作を「哲学小説」と呼びたいと思う。
無論、「哲学小説」と言っても、哲学者の名前が並ぶような小説といった意味ではなく、ごく当たり前に「人間存在の実相を突き詰める小説」という意味であり、その意味では、ごくごく正統的な「文学」作品だと言えるのだが、その形式は、「本格ミステリとメタ・フィクションを掛け合わせた思弁小説(アンチ・ミステリ)」なんてことで済まされるようなものではなく、むしろ、そうした形式から導きだされる「形式的思考」の罠から、どんどんと踏み外していった先に、隠されていた「人間の実相」であり「世界の実相」を描いた作品だ、とでも言えるのではないだろうか。
例えば、「本格ミステリ」と呼ばれるジャンルは、このジャンルに好意的な人にとっては「純粋論理の小説」だ、ということになるだろう。「純粋論理」だから素晴らしい、と。
しかし、「純粋論理の小説」からは、「不純」なものが排除されている。
その「不純なもの」とは、例えば、「社会問題」もそうだし「恋愛」や「性欲」などもそうだ。つまり、「不純なもの」とは、「人間の中の、動物的なもの」であり、「理性」や「知性」では統御しきれない、「厄介なもの」のことなのである。
言うまでもなく、脳の器質的異常でもないかぎり、すべての人間は、この「不純なもの=厄介なもの」を抱えているのだが、普通の場合、人はその存在をおおっぴらに語ろうとはしないし、殊に「理性」や「知性」に自負を持っている人は、それを逸脱していく「統御不能なもの」の存在を認めたくはないものである。
言い変えれば、「本格ミステリ」とは、そういう「理性」や「知性」によっては「統御不能なもの」の存在を「隠蔽」する、「ファンタジー」だと言えるだろう。
そこでは「思考機械」であることが、誇らしげに語られるのだが、人間の現実はそんなものではないし、作者自身そんな存在であろうはずもない。そんなものではないからこそ、それは「度しがたい欲望」の対象として「神」のごとく求められるのであり、その「欲望」の存在自体を責めることは、誰にもできないのである。
竹本健治の小説が、一見したところ「本格ミステリ」の形式を採りながらも、しばしば、その形式を逸脱したり、その形式を求める「欲望」を逆撫でするようなものを描くのは、竹本が「理性」や「知性」に抗う人間だからではなく、「理性」や「知性」という仮面の下に隠された「度しがたい欲望」の方に興味があり、そちらを追及せずにはいられないという「理性や知性の欲望」に忠実な人だからなのではないか。
例えば、「神戸連続児童殺傷事件」の第一報に接した時の、私の態度というのは、極めて常識的に「倫理的」であり「論理的な」なものであったのだけれど、それはいかにも「表面的」なものでしかなく、「機械論理的(脊髄反射的)」なものでしかなかったのではないか。
事実、私は後に、この事件の犯人である「少年A」について、多くの情報に接するに従い、彼を「倫理的」に責めて済むような問題ではなかったことを痛感するわけだが、たぶん、私の年上の友人は、事件の第一報に接した段階で、すでにその「闇の深さ」の方を凝視していたのではないだろうか。ちょうど、本作における探偵役と言ってよい、マサムネのように。
竹本健治の小説が、「一般うけ」どころか、しばしば「ミステリファンうけ」すらしないのは、竹本の見ているものが、そして描くものが、私を含めた「常識人に好都合な欲望達成」の域を遥かに超えて、「深く」「暗い」ものだからではないだろうか。
私たちが、できれば「見たくない」「考えたくない」と思っている「人間の実相」を描くからこそ、「人間の欲望」に忠実な「本格ミステリ」に対するのとは、真逆の感情を持たれてしまうのではないだろうか。
無論、これは文学としての、あるいは文学者としての誉れであろう。
だが、しばしば「見えすぎる眼」の「欲望」は、その人にとっても厄介なものでしかないのであろう。
書評:2020年7月18日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
○ ○ ○
