
笠井潔 『新・戦争論 「世界内戦」の時代』 : 例外状態・世界内戦・例外社会、 そして オルタナティブ
書評:笠井潔『新・戦争論 「世界内戦」の時代』(言視舎)
本書は、本年(2022年)9月末の刊行で、ひさびさの長編ミステリ『煉獄の時』とほぼ同時に刊行された、笠井潔の「長編評論」である。
「長編評論」だと表現したのは、本書は、いちおうのところ「インタビュー本」の体裁こそ採ってはいるものの、徹底的な加筆によって、インタビュー時の原型をとどめないものになってしまっているだろうからである。
それは、例えば笠井の長編小説『哲学者の密室』(『煉獄の時』もほぼ同様だろうが)が、単行本化された際には、連載時の3倍の長さになっていた、というのと同じことである。
笠井潔は、連載時の原稿に徹底的に加筆して単行本化することで有名な作家だが、インタビュー本である本書もその例外ではなく、インタビュー本来の「応答形式」さえ保てず、最初にインタビュアーの質問事項が列挙されて、あとは笠井が一方的かつ滔々と、何時間も喋ったがごとき、異形の擬似インタビューと化しているのだ。
一一このあたりの「形式」的特徴にも、笠井潔という作家の「特質」を見ていいだろうと、私は思う。笠井は、見かけ上の「形」を徹底的に凝らして、決して「素顔」を見ようとはしない作家なのである。
○ ○ ○
しかし、こうした「いかがわしさ」を勘案考慮しても、本書の内容は、十分に傾聴に値するものとなっている。「絵解き上手」「説明上手」という笠井潔の本領を、存分に発揮した一書となっているのだ。

これまで何度も書いてきたことだが、笠井は「小説」は下手だが、「分析・解説」には抜群の才能を持っており、だからこそ、小説ジャンルの中では「ミステリ小説(本格推理小説=探偵小説)」が向いていたのだ(言い換えれば、純文学的小説や、SFや幻想小説などは読むに堪えない)。
したがって、私は本書に限らず、笠井潔の社会評論書を、多くの人に薦めたい。
小説家としてのイメージだけで、笠井のすべてを判断しては必ず評価を誤るし、笠井個人がどんなに信用のおけない人だとしても、彼個人が責めを負わないで済む「(世界規模の)大状況」などの分析については、政治的な意図的曲解や希望的観測が入らないため、その長所を存分に発揮したものとなっているなのだ。
笠井潔という人は「攻めるに強く、守るに弱い」作家である。
それは、他者を攻めるときには、自分を完全に棚上げにして語れるからであり、逆に言うと、その棚上げした部分を責められると、人を責めた言葉が、もろに自分に返ってくる。
だから、ほぼ無責任に攻めている(他者を責めている)に等しい評論書における分析は、なまじの自己批判などが入らないぶん徹底的であり、その点で面白い。私たちが「反省すべき現実」を、仮借なく剔抉してくれるのである。
さて、そんな魅力を有する本書の内容だが、これを要約するというのは簡単なことではない。笠井潔が、長年、思考を深め、折々に語ってきたことの最新バージョンともいうべきもので、押さえるべき前提が多々あって、それを世間の人々は、ほぼ知らないからである。
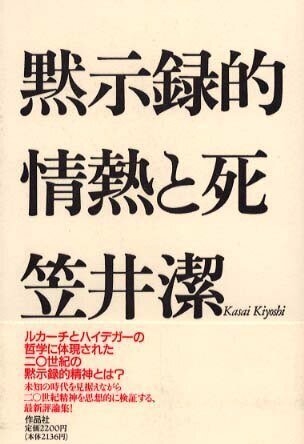
例えば、次のような説明で、意味のわかる人は、笠井潔の読者以外にはいないだろう。
『【世界内戦】とは――国際社会にメタレヴェルの権力を析出することで、国家間の戦争を終わらせ恒久平和を達成しようという世界史的な展望を見失ったまま、泥沼化した戦争が蜿蜒と続いていくのが二一世紀という時代です。しかも戦争は主権国家と主権国家の戦争ではなくなっている。…国家間の取り決めである戦時国際法など完全に無視した、無茶苦茶な軍事行動を平然と続けるようになる。(本文より)』
見てのとおり、これは本書本文から引用された、「Amazon」の本書ページでの説明文である。こんなもので、何がわかるだろうか?
そんなわけで、可能なかぎり大雑把に、笠井の「世界内戦」論のロジックを紹介してみよう。
まず、カール・シュミットから採られた「例外状態」だが、これは本来「法治国家内」の「例外状態」を指す。
「法治国家」とは、文字どおり「法」によって治められている国家のことだが、そうした国家体制を転覆しかけない状況、例えば、戦争、暴動などが発生した場合、国家は法を一時的に停止し、国民の主権を制限して、法に基づかない「暴力行使」により状況を収拾し、その後、法を回復して、通常の状態に戻るのだが、この一時的な「緊急措置としての無法状態」を、法治国家による「例外状態」と呼ぶのだ。
そして、これは「一国」内だけの問題ではない。
近代国家成立前の「戦争」というのは、「宗教戦争」がそうであるように、「神の側vs悪魔の側」「人間vsそれ以外」といったものだったからこそ、仮借のない、何でもありの殺し合いだった。
しかし、本来「利益」のためになされるはずの「戦争」なのだから、どっちも弱ってしまうだけの「潰し合い」では、「お互いの利益」のためにならない、ということで、少なくとも西欧先進国の間では、「国際法」「戦争法」などを定めて、その範囲内で「ルールに基づく戦争」がなされるようになった。
これが西欧世界における「公法秩序」というやつで、わかりやすい例を挙げれば「戦争は兵隊同士が行いものである(民間人を殺してはいけない)」とか「(すでに兵隊ではなくなった)捕虜は人間として扱わなくてはいけない」といったルールだ。つまり、現在のような「(国家総ぐるみの)総力戦」ではなく、「公法秩序」により、「戦争」は限定的な「代表戦ゲーム」となったのであり、それで勝ち負けを決めて、負けた方は、賠償金を支払ったり、領土を委譲するなどすることで、「利害対立」を調停する、といったものとなった。
だが、こうした西欧世界における「公法秩序」が可能だったのは、それが西欧帝国主義先進「国家」間でのみの話でしかなかったからだ。
つまり、この「公法秩序」というのは、植民地化の対象である、アフリカやアジアなどを対象にはしていなかった。それらは「公法秩序」という「人間のためのルール」の「外」にあるものでしかなかったからであり、むしろ、それらの土地や資源について、「西欧帝国主義国家」どおしが、過剰な被害を被らずに、効率的に「分配」するためのルールだったのである。
だが、そうした「人類未踏の地=フロンティア」が無くなってしまうと、当然のことながら、「公法秩序」は揺らぎだす。先進国の分捕り合戦は、すでに、お互いのものとなった国土や利益の、直接的な分捕り合いになったからだ。
加えて、「兵器」の近代化によって、「戦争」は「総力戦」となってしまい、「前線」も「後方」も無くなって、「公法秩序」が崩壊してしまう。
カール・シュミットが嘆いたのは、こういう「西欧先進諸国」の「公法秩序」が失われた、という点にあった。
しかし、笠井潔は、そこから話を進めて、「帝国」間の「公法秩序」が失われて、世界全体が「例外状態」になったしまったため、今度はその「ルールなき世界」にルールをもたらすための「メタ帝国」の析出運動が開始され、それが第二次世界大戦であり、そこで生み出された「メタ帝国」がアメリカであった、という具合に展開していく。
先に引用した、
『国際社会にメタレヴェルの権力を析出することで、国家間の戦争を終わらせ恒久平和を達成しようという世界史的な展望』
のことだ。
「公法」が成立しない世界では、「公法」に変わって、「国々」のメタレベルに立つ「メタ国家」が生まれなければ、世界は、
『世界史的な展望を見失ったまま、泥沼化した戦争が蜿蜒と続いていくのが二一世紀という時代です。しかも戦争は主権国家と主権国家の戦争ではなくなっている。…国家間の取り決めである戦時国際法など完全に無視した、無茶苦茶な軍事行動を平然と続ける』
ようにならざるを得ないのである。
しかし、結局のところアメリカは、完全な「メタ帝国」にはなり損ねた。
アメリカは、第二次世界大戦において、唯一本土戦を経験しなかった大国で、それゆえに、終戦時には、最も強力な国になっていた。
そして、それまでの、非効率な「直接植民地支配」ではなく、アメリカ流の「新植民地支配」、つまり「民主国家の独立を認めながら、それらの国々をアメリカ主導の資本主義体制の網の目に巻き込むと同時に、傀儡政権を樹立し、それを介して収奪する」という形式を、「建前」機関である「国連」などを前面に押し立てつつ展開したのだ。「われわれは、あくまでも民族の独立を支持する、フェアな友人だ」と(※ ここで重要なのは、日本もその例外ではない、ということだ)。
だが、これに抵抗したのがソ連で、ソ連は「資本主義体制の欺瞞と搾取」を批判して「社会主義」体制を押し立て、「社会主義国」の陣営を作って「アメリカ自由主義陣営」と対立し、世界をに二分する「東西冷戦」時代に入った。
しかし、この冷戦体制は、ソ連の「自己崩壊」によって消滅し、アメリカの一人勝ちになった。
そこでアメリカは、それまでは「資本主義国家の子分」たちを手厚く遇していたが、敵がいなくなった途端、その暴君的(ジャイアン的)な本性をむき出しにし始める。例えば、日本に「もっと金を出せ」「もっと身を切れ」といった要求をし始めたのである。
ところが、そんな「世界の警察」を自認する「暴君国家」に対抗したのは、「主権国家」ではなく、「主権国家」的な縛りを持たない、「イスラム原理主義組織」などの「国際ゲリラ組織」であった。
「国際法」に縛られず、「国土」を持たないから、どこにいるのかも特定できない彼らには、これまで「他国家」に対して行ってきた「締め付け」「攻撃」が不可能だったのだ。
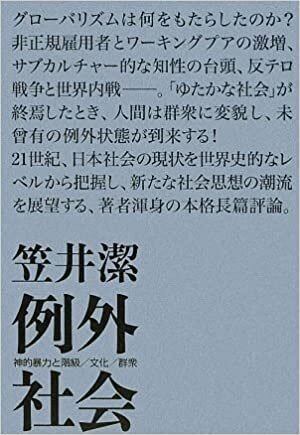
その結果、アメリカの「メタ国家」としての影響力は弱まり、ロシアや中国が、それに対抗する「(メタ国家を目指さない)覇権国家」として巨大化してきたのである。
そんなわけで、「先進国間における公法秩序」の代わりに生み出された「メタ国家による秩序」、つまり「暴君の課する公法秩序世界」すらも不成立となって、今の世界は「例外状態(法が支配しない、弱肉強食の世界)」が常態化し、さらに西側諸国内においても「東西冷戦終結」以降は「中流の崩壊」に見られる不安定な「例外社会」化が進行して、もはや、どこにも「外部」を持ちえない、「世界内戦」の「無秩序な世界」になってしまった。一一というのが、笠井潔の見立てなのだ。
○ ○ ○
私は、この「見立て」を、非常に説得的だと思う。
少なくとも、なんとなく「戦争の仕方が変わってきた」みたいな曖昧な把握ではなく、「戦争」というものの理解が、世界史的なレベルで論理的に説明されており、なるほどと説得させられざるを得ないものとなっている。
もちろん、この「図式」がすべてではなく、他の図式を立てることも可能ではあるけれども、これだけ明晰で説得的な「戦争の世界史的理解(構造分析)」など、ちょっと他にはないのではないだろうか。
こうした「分析・説明」において、笠井潔は天才的なのだが、しかし、私たちの問題は、この捉えどころのない世界の現状と対決するための、「明晰な仮説」としての「世界内戦の時代」という理解を採用した場合、では、その「乗り越え方法」はどういったことになるのか。はたしてそれは、そもそも可能なことのか(存在するのか)、という点である。
本書で笠井潔は、その「問い」に対する「回答」を提出しており、それは、すでに示された「戦争の世界史的理解」に対するものとしては、論理的には「正しい解答」であるように、私は思う。
しかし、現実問題として「それが可能か?」と問われれば、「ほとんど、不可能だろう」という感触しか持てない。理屈としてはわかるけれども、それが実現可能だとは思えないのである。
だが、だとすれば、人類の未来は「絶望的」だということになってしまうのだが……。
笠井潔による「世界内戦の時代」の乗り越え方あるいは、新たな世界ビジョンとは、次のようなものである。
『「一一年」(※ 2011年)以来の広場占拠、街頭占拠、都市占拠という運動形態が意味するのは、当面する要求が反貧困であれ民主化であれ、それは議会外に民主主義空間を創造し、大衆蜂起を自己組織化する以外に実現されえないという確信です。大衆蜂起の自己組織化とは、かつてコミューンやソヴィエト、レーテやフンタと呼ばれた評議会運動、民衆的な自己権力運動の継承でもある。二一世紀の世界内戦と、世界内戦国家の国内体制としての例外社会を超えていく唯一の可能性がここにある。これがオルタナティブです。
大衆蜂起という路上の人民権力がブルボン王政を打倒したフランス革命ですが、絶対主義の産物である主権国家を超えることはできませんでした。君主から人民に看板が掛け換えられても、その存在自体が抑圧的である主権国家の実質はなんら変わらない。連邦制をとったアメリカ革命とロシア革命にしても同じです。二〇世紀、そして二一世紀に入っても、それは幾度となく反復されてきました。例えば一九八〇年代後半に東アジア諸国で連鎖した民主化運動は、開発独裁政府や軍事独裁政権を倒したにもかかわらず、その後はグローバリズムの大波に呑み込まれ、韓国でもフィリピンでも民主化の成果は失われていきます。一九八九年以降の東欧とロシアの民主化運動にしても、民主化も反貧困も一国内で終始するなら、大衆蜂起が下からの自己権力を積み上げていくという展望は空転し、かならず限界にぶつかる。やはり世界同時革命しかない……。
(中略)
わたしが考えていることは、現実性のない夢物語でしょうか。マルクスが一九四八年革命のときに世界同時革命と称していたのは、イギリス、フランス、ドイツの同時革命ですね。マルクスはドイツ人なので、革命の条件などないドイツを無理に押し込んでいるだけで、実質は英仏同時革命です。経済のイギリスと政治のフランスで同時に社会主義革命が起これば、他のヨーロッパ諸国はそれに従わざるをえない。ヨーロッパが社会主義化すれば、植民地はどうにでもなる、という発想です。このヨーロッパ中心主義は、近代世界総体の変革と言う点からして反動的で差別的ですが、世界革命のビジョンという点では参考にならないでもない。
二一世紀の今日、アメリカと中国で同時革命が勝利し、樹立された新政府が国際ルールに合意してしまえば、世界はそれに従わざるをえないことになる。ただし、その新権力は、なにもしません。なにもしないことに意味がある。大衆蜂起の自己組織化運動を肯定し、容認にしているだけでいい。そして大小無数の自己権力体が下から積み上げられて国の規模まで成長し、あるいは国境を超えて横に連合していく過程で、静かに退場していること。なにもしないことを「する」、これが樹立された「革命」政権の仕事ならざる仕事です。フランス革命やロシア革命の時のように、米中両「革命」政権に反革命干渉戦争を起こせる国など存在しませんから、この点でも「革命」政権が下からのコミューン革命を弾圧し、対外戦争に強制的に動員することにはなりません。』(P65〜67)
『一一(杉山)次の質問ですが、ウクライナ戦争が始まったときのぼくの感想は、「逃げればいいじゃないか」というものだったのです。戦争で死ぬのは、民衆であり兵隊なのだから、とにかく死ぬ人間を減らすにはどうしたらいいかというと、停戦に向けて国際社会が全力を挙げるというやり方がいいんじゃないか。どんどん撤退してもいいじゃないか。亡命政府が造ればいいじゃないか。迂闊に言ったら総スカンを食いそうな話ですが、そんなことを考えていたのですがいかがでしょうか。
(中略)
現実的ではないと思いつつ、俺は死にたくないという論理をどこまで貫くことができるのか。それを知りたくてお聞きした次第です。
笠井 自分は逃げる、という人がいていいんだと思います。ある場合には、わたし自身もそう判断するかもしれません。しかし、逃げることを原理化し一般化して、だれもが逃げなければならないというのは倒錯でしょう。』(P185〜187)
要するに、これまでの日本の常識はもとより、世界的な常識とも言える「国民国家」では、「民主主義」だ「議会政治」だと言ったところで、どのみち「市民よりも、(国民の名における)国家」優先の抑圧的社会体制にしかならないのだから、国家のパターリズムなどに依存するのではなく、民衆自身が、自分たちで生活を支える分散的なコミュニティを作り、それが下から積み上げられた集合体になれば良い、ということであろう。
そして、それは簡単なことではないけれども、今の「世界内戦」下に「例外社会」化した社会において、一部の特権階級(強者)から虐げられて生きることから逃れるには、それしかないし、そのくらいの覚悟は是非とも必要だ、ということなのであろう。それが、ベターでもベストでもなく、それしかない。
したがって、それが「大変そうだから」と諦めるのなら、もっともっと、持てる者と持たざる者が二極分化して、持たざる大半の者が酷い目に遭う、ますますひどくなる社会を受け入れるしかない、ということになるだが、「その覚悟があるのか」ということであろう。

たしかに、お説ごもっとも意見で、この世界が、小手先の「民主化」や「自由化」で、一昔前のような「自由で豊かで、比較的平等な世の中」に戻ることはないと思う。
すでに、私たち「先進国」の人間が、無自覚にも搾取してきた「第三国」が存在しない以上、もうわれわれが「もっともらしい正義」を語りながら、それでいて搾取し続けるなどといった「甘い状況」ではないのだと思う。
それに、笠井潔の言う「小さな扶助共同体の緩やかなつながり」といっても、それは「メタレベルの権力=国家権力」が存在しないために、必ずその中に「地域暴君」を析出することを避け得ず、結果として「今よりマシになる」という保証など、まったくないと、私には思われる。
つまり「小さな扶助共同体の緩やかなつながり」による社会が、まともに機能するためには、笠井潔が「ウクライナの戦争」に関して問われて答えたように、その「小さな扶助共同体」が、過剰に「強制的で束縛的なもの」にならないことが必要なのだが、その象徴的事例としての「戦争における、コミュニティからの脱出権」が、現実に保証され得るとは、私には思えない(※ ウクライナでは、成人男性の国外渡航権が制限された)。
笠井潔はここで「逃げれば(家財などのすべてを捨てるに等しく)、二度と戻れなくなるという覚悟がなくてはならず、そんな決断は決して容易なことではないから、結局のところ、出るも地獄、残るも地獄なら、残って戦おうという人も少なくないはずで、その意味では、逃げる権利が認められないといけない」と言うのだが、そうだとしても、やっぱり人は「お前だけが逃げるな!(そんなこと許さん)」と言うだろうし、小さなコミュニティでは、それが実質的には「法」にならざるを得ないと思うのだ。
だから、状況分析は悪くないと思うのだが、それに比べると笠井の示すオルタナティブは、やはり極端に見劣りして、非現実的という印象を否めない。
ただ、ここで言えることは、笠井のオルタナティブに注文をつけるだけではダメで、肝心なのは「では、どうするのか?」ということを、個々が考えるということだろう。
すでに、他人の意見に注文をつけているだけで済まされる、太平楽な状態になど、この世界はないからである。
(2022年12月29日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
