
加藤典洋 『敗戦後論』 批判 : プレ安倍晋三時代の評論家
書評:加藤典洋『敗戦後論』(講談社 → ちくま学芸文庫)
(※ 再録時註:加藤典洋は、過大評価された評論家だった。だが、どんな時代でも、人々は「人気者」こそが「本当に素晴らしいもの」と見てしまいがちであり、それは何も「一般大衆」に限った話ではない。「知識人」と呼ばれる人たちだって、その多くが「同時代的な人気のオーラ」に惑わされ、それに跪拝して見せる。その良い例が、ヒトラーでありスターリンへのそれで、そのささやかな別例が、かつての安倍晋三へのそれだ。歴代最長の政権を誇った彼も、自身の寿命は短かった。かつて夢見られたものが、そのまま未来まで続くという保証など、どこにもないのである)
加藤典洋の『敗戦後論』(講談社)を、やっと読みおえた。
なぜ、こんなに時間がかかってしまったのか。
それは、その内容があまりにも「鬱陶しく」、読む進めるのに、ひどく苦痛を感じさせられたからだ。
何が苦痛だったのかというと、その内容が全面これ「臆面もない自己正当化」であり、しかもその手法が、もろに「俗情との結託」だったからである。
高橋哲哉(『戦後責任論』)などを中心に、多方面からの批判を浴びた、雑誌掲載時の「敗戦後論」(『群像』95年1月号)に若干手を入れ、その1年7ヵ月後に発表された「戦後後論」(『群像』96年8月号)、さらにその半年後に発表された「語り口の問題」(『群像』97年2月号)を加え、さらにまた単行本化にあたって、詳細な自「注」と(13頁にわたる)長い「あとがき」を付したのが、単行本『敗戦後論』(97年8月 初版刊行)である。
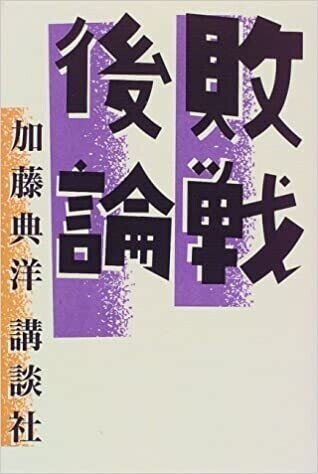
こうした成り立ちからも、なかば窺えるとおり、本書は、高橋哲哉らの批判に即応した反論文(論争文)をまとめたものではなく、批判のほとぼりが冷めたのを見計らって書かれた論文(「戦後後論」、「語り口の問題」)を、「敗戦後論」の「自注(=言い訳)」として「後付けした」ものである。
つまり、この単行本は、冒頭の「敗戦後論」に対する厳しい批判に対して、自己の正当性を語るため(世間に向けて、自己の正当化を図るため)に刊行されたものであって、決して「敗戦後論」の議論そのものを、深める方向で書かれたものではなかった。
前回(2005年5月31日「『靖国問題』と明晰性」)、『今さらながら加藤典洋の『敗戦後論』(講談社)を読んでいる。』と書いた時点では、私は、「敗戦後論」「戦後後論」「語り口の問題」の三論文(と、自「注」「あとがき」)で構成された単行本『敗戦後論』の、冒頭の論文「敗戦後論」をもうすこしで読み終えるといった段階だった。
だから、「戦後後論」以降の展開にはまったく言及しなかったのだが、前述のとおり、「300万英霊の優先的追悼による国家主体の形成」という「敗戦後論」のテーマは、すくなくとも見かけ上は、続く「戦後後論」に、そのまま引き継がれることは、なかった。つまり、「戦後後論」は、「あとがき」で加藤自身、
『 この本は互いに性格の異なる三本の論考からなっているが、わたしのつもりでは、「敗戦後論」が政治篇、「戦後後論」が文学篇、そして「語り口の問題」が、その両者をつなぎ、その他の問題意識と相渉るところで書かれた、蝶番の論である。』(P314)
と書いているとおり、太宰治の「時代への抗し方」を賞揚した、一見「文学論」的な、一見したところの「太宰治論」だったのだ。
だが、この論文が語っていることを簡単に言うと「真に時代に抗することとは、政治的・イデオロギー的に抵抗することではない。文学的な、徹底した個を拠点とし、そこから発する抵抗でなければならない。それしかないのである」というようなことだ。
つまり、加藤典洋は、高橋哲哉の批判が「政治的・イデオロギー的」なものであり、自分の立場が「文学的な個に立つもの」であると、暗に語って、自己の正当化を図っているのである。
こうした「戦後後論」の狙いとは、高橋哲哉から「仮面をかぶったネオナショナリストの論」として批判された「敗戦後論」が、じつは「政治的な発想から書かれたものではなく、個人に立場に徹して書かれたものであった」のが「誤解された」のだと弁明し、自己正当化をはかるところにあったのであり、決して純粋な「文学論」でもなければ、「太宰治論」でもなかったと言えよう。
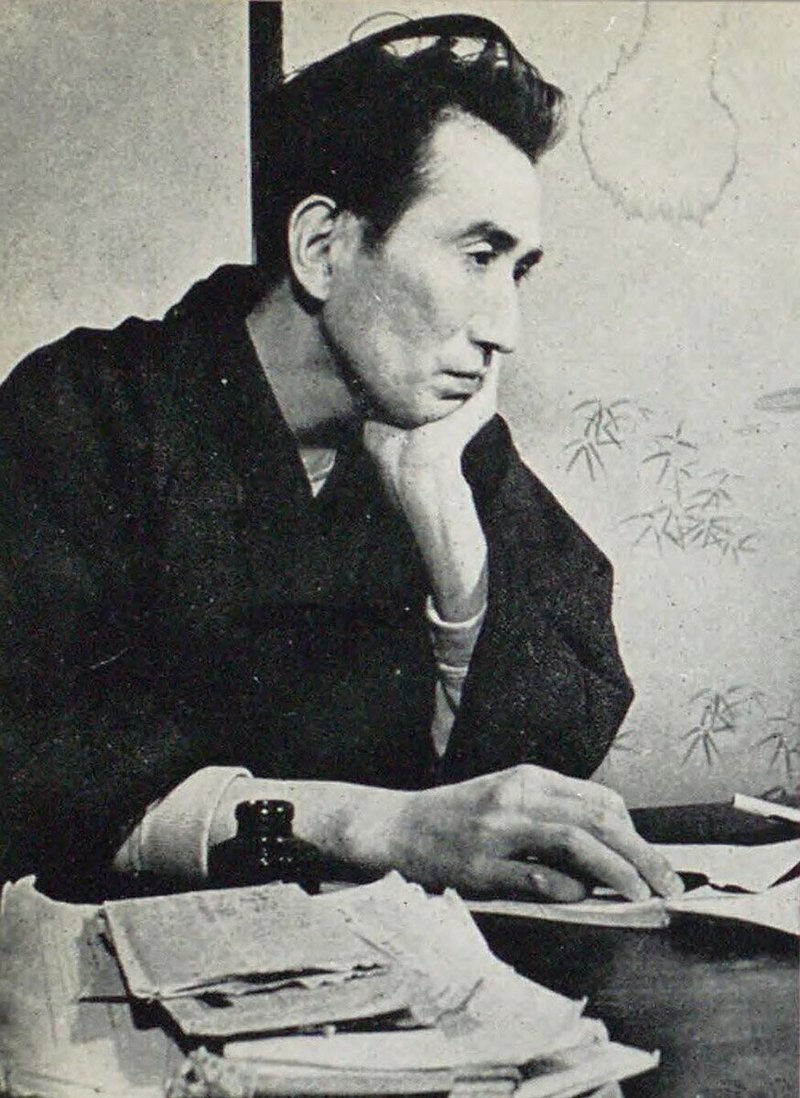
「文学」や「太宰治」は、あくまでも、加藤典洋が自身を正当化するために持ってきた「権威」に過ぎない。
しかも、その「権威」は、「敗戦後論」の際の、中野重治・大岡昇平・福田恒存といった「(信念ある)力強い抵抗」者とはうって変わって、「太宰治」や「文学」に象徴される「文弱の抵抗」なのである。
では、なぜ、ここでは「力強い抵抗者」ではなく、「文弱の抵抗者」が選ばれたのであろうか。
それは、高橋哲哉の批判が(「中野重治・大岡昇平・福田恒存」的に)徹底して筋を通した正論であったからこそ、加藤典洋は自身の立場を「もうすこし微妙で繊細なものだったのだ」というかたちで正当化しようとしたからだ。
加藤は、高橋哲哉の文章について、繰り返しこんな「断言」をしている。
『なぜ人は、たとえば南京大虐殺、朝鮮人元慰安婦、七三一部隊といったようなことがらに関し、「無限に恥じ入り、責任を忘れない」というような語り口に接すると、そこに「鳥肌が立つ」ような違和感を生じるのか。』(P269~270)
はっきり言っておくが、私は『南京大虐殺、朝鮮人元慰安婦、七三一部隊といったようなことがらに関し、「無限に恥じ入り、責任を忘れない」というような語り口』に接しても、べつに『「鳥肌が立つ」ような違和感』を生じるようなことはない。
なぜなら、それは「自国に真の誇りを持ちたいと願う日本人としては、当然のこと」だと思うからである。

もちろん、「自国の汚い過去からは目をそらしたい」と感じている「懦弱な日本人」も大勢いて、そういう人たちは(加藤典洋と同様)、高橋哲哉の突きつけるような物言いに、思わず『「鳥肌が立つ」ような違和感』を生じる、ということもあるだろう。
だが、そういう人が「すべて」でないのは明らかなのに、加藤典洋は、あえてここで『なぜ人は、』と、主語を「人(一般)」に押し広げたのか? なぜ正確に「私(加藤典洋)は、」としなかったのであろう?
無論それは、主語を「人(一般)」に押し広げることで、読者一般に対し「高橋哲哉のような物言いに接した場合、人は一般に、鳥肌が立つような違和感を生じるものなのだ」という「現実には即さない、しかし加藤典洋自身には都合のよい、誤認」を刷り込もうとしたからなのである。
「貴方だって、こういう押しつけがましい言い方をされれば、鳥肌立つでしょう?」と、「懦弱な日本人」読者に媚びてみせただけなのだ。
そしてこれこそが、大西巨人の言う「俗情との結託」というものなのである。

つまり、加藤典洋が「戦後後論」や「語り口の問題」でおこなったのは、高橋哲哉の言い方は『イデオロギー(教条)』的で『旧護憲派』『講座派知識人』に典型的な硬直した『左翼』紋切り型であり、その意味で「高圧的(トップダウン式)」で「思いやりと繊細さに欠ける(愚鈍な)」ものである、というレッテルを貼る一方、自身には、その対極に位置する「文学的」「太宰治的」であり、「個人」に重点をおく「繊細で思いやり重視」の立場だ、という「イメージ」を醸成する(レッテルを貼る)ことだった。
そうすれば、「現実の直視」を避けたがるであろう多くの「懦弱な日本人」が「自分の側につく」だろう、と計算したのである。
したがって、論文「敗戦後論」は、一般的な政治論文(政治に関する論文)だったと言えようが、単行本『敗戦後論』の方は、自分一個の「自己正当化」と「保身」ための「政治的な宣伝本(プロパガンダのための本)」だったと言えるのである。
これを、まとめれば、こうなる。
高橋哲哉が「勇気をもって現実を直視し、自ら重き十字架を背負って歩め。それが誇りある人間(日本人)のすることだ」と強く語ったのに対し、加藤典洋は「文学」の権威を悪用して「そういう勇ましさって、どこか偽善的で気持ち悪いよね。貴方もそう感じるでしょう?」というかたちで「俗情」に媚びた、ということなのである。
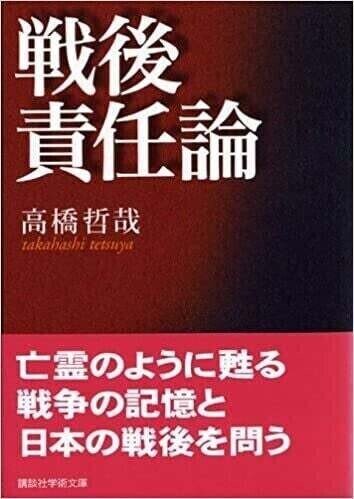
だから、加藤典洋による、ここ(「戦後後論」)での「絶賛」的な「太宰治論」は、所詮、自己正当化のための方法的なものであり、それゆえ「ご都合主義的に一面的」なものでしかなく、さほど深いものではない。
その証拠に、加藤は、太宰を嫌った三島由紀夫について、「注」で次のように語っている。
『38 太宰について、三島由紀夫は、こう書いている。「○君は、私が太宰治を軽蔑せずに、もっとよく親切に読むべきことを忠告する。私が太宰治の文学に対して抱いている嫌悪は、一種猛烈なものだ。(略)私とて、作家にとっては、弱点だけが最大の強味になることぐらい知っている。しかし弱点をそのまま強味へもってゆこうとする操作は、私には自己欺瞞に思われる。(略)太宰のもっていた性格的な欠点は、少なくともその半分が、冷水摩擦や器械体操や規則的な生活で治される筈だった。生活で解決すべきことに芸術を煩わしてはならないのだ。いささか逆説を弄すると、治りたがらない病人など本当の病人の資格がない」(『小説家の休暇』一九五五年)。よく知られた評であり、昔、この評を読んだ時には、なるほどと思ったが、いまは、トーマス・マンに倣い、銀行員のように毎日決まった時間を小説執筆にあてることを自分に課し、多くの仕事をした三島のいわばハードな、自分を持したあり方より、「純白なシーツ」にあこがれながら露路に低回した「薄汚れ」てだらしない太宰のほうが、文学としても、思想としても、広いのではないか、深いのではないか、と思っている。ここにあるのは、非常に大切な問題ではないだろうか。』(P302~303)
読者(の俗情)に媚びる「お涙ちょうだい」の論だが、私からすれば、これは「語るに落ちた」としか言い様のない、お粗末な意見でしかない。
加藤典洋は、ここで自身を太宰治に仮託して、次のように自己正当化している。
「昔、(三島の)この評を読んだ時には、なるほどと思ったが、いまは、トーマス・マンに倣い、銀行員のように毎日決まった時間を小説執筆にあてることを自分に課し、多くの仕事をした三島の、いわばハードな、自分を持したあり方(つまり、まず他者を思いやり自己に厳しくあれ、というような、高橋哲哉的な『いわばハードな、自分を持したあり方』)より、「純白なシーツ」にあこがれながら露路に低回した「薄汚れ」てだらしない太宰(と同様の私・加藤典洋)のほうが、文学としても、思想としても、広いのではないか、深いのではないか、と思っている。(手前味噌な言い分ながら)ここにあるのは、非常に大切な問題ではないだろうか。」
加藤典洋の「論」が、このように「薄っぺら」な「ご都合主義」であるというのは、ここでの極端に一面的で恣意的な、三島由紀夫「評価」にも現れてもいよう。
三島の太宰に対する『一種猛烈な』嫌悪とは、結局のところ、三島が太宰の中に「自分と共通する弱さ」を見ていたが故の「近親憎悪」に他ならない。
だから、そんな三島を『ハード』な人、太宰をそれとは反対の「ソフト」な人とする加藤典洋の作家理解は、「上っ面を掻い撫でにしただけ」の極めて浅薄なもの、としか言えないのだ。
『治りたがらない病人など本当の病人の資格がない』という言葉からもわかるとおり、三島は自身を『本当の病人』だと自覚していた。つまり、『弱点』をたくさんもった「弱い人間」だと理解していたのだ。
だが、だからこそ彼は、心底「強く」なりたかった。「強く」なろうとしたのだ。「ストイック(禁欲的)」なまでに……。
つまり、三島は「強い人」だったのではなく、「強さへのあこがれが強かった人」なのだ。
だから、そんな三島からすれば、太宰は「弱さ」は、半端な偽物でしかなかった。つまり、自身の「弱さ」への徹底した「嫌悪」を持たないからこそ、太宰は、三島のように『純白なシーツ』になる努力をせず、ただ『「純白なシーツ」にあこがれ』ているという「ポーズ」を世間にひけらかしながら、(佐藤春夫や川端康成に泣きついて芥川賞をもらおうとしたり、女に泣きついて心中につきあわせたりして)自堕落に『露路に低回し』『「薄汚れ」てだらしない』生活を続けたのである。
言い換えれば、三島由紀夫という人は「泣きたい時にも笑ってみせることしかできないような、弱い人(不器用な人)」だったのだが、太宰治というのは「さして悲しくない時でも大仰に嘆いてみせ(て同情を買っ)た、強かな人」だったのだ。だから、三島は、太宰を激しく嫌悪し「おまえなんかに、病人を名乗る資格はない」と言ったのである。

つまり、こうした三島由紀夫の「弱さ」や「繊細さ」については、故意に言及せず、太宰の表面的な「弱さ」や「繊細さ」を強調するためにだけに『トーマス・マンに倣い、銀行員のように毎日決まった時間を小説執筆にあてることを自分に課し、多くの仕事をした三島』と、三島の表面的な『ハード』さを強調して見せた加藤典洋には、もともと太宰や三島を「深く」「公正」に評価するつもりなど欠片もなく、ただ自身の「弱さ」「薄汚さ」を正当化するためだけに、太宰の「弱さ」「薄汚さ」という一面をことさら肯定的に言上げして、太宰を利用したに過ぎなかったのだ。
したがって、『敗戦後論』を通読して思うのは、加藤典洋という人は、高橋哲哉が言ったような「自覚を持ちながら、それを隠している、陰険なネオナショナリスト」といったようなものではなく、単に「利口ぶった、目立ちたがり屋の俗物」なのではないか。
つまり、「敗戦後論」という論文は、世間の流れが「反・左翼」に傾くのを感じ取った加藤典洋が、「今、これを書けば、話題にもなるし、世間にも受けるだろう」と考えて書いた「ウケ狙いのトリッキーな論文」に過ぎなかったのではないか、ということである。

(小泉純一郎首相とブッシュJr.米大統領・当時)
例えば、この論文の売り物である、敗戦時における『ねじれ』などという「アイデア」も、「そもそも個人の人生にも、社会の歴史にも、ねじれなどといったものは付きものであり、むしろ何のねじれも存在しないものの方が珍しいだろう」という現実において、取るに足らない、勿体ぶっただけ「空疎な言葉」だと評価し得よう。
具体的に言えば、「日本国憲法は、ありがたい平和憲法だが、アメリカに押しつけられたものでもある」という加藤典洋の強調する『ねじれ』は、「日本国民の誰もが、自分で選んで日本人として生まれたわけではない」という「当たり前の事実」と、なんら変わらない。
つまり、人は(何もかも)自分で選んだからこそ「ストレートに(ねじれなしに)」受け入れるのではない。
先験的な所与のもの(氏素性・容貌・才能)でも押しつけられたもの(各種法律・身分)でも、それが「良きもの」であるならば、人はそれと折り合いをつけて生きるのだ。
また実際のところ、人間にとって大概のことは、与件としてあるのであり、それをいちいち「選びなおさなければ、まともに生きられない」などといったことは、事実としてまったくないのである。
このように、加藤典洋は、それまで主に「政治的リアリズムの世界」で議論されてきた問題について、文学的に「無責任の保証された立場」から、興味本意に「ちょっかいを出してみた」だけなのだ。
ところが、これに対し、予想外に強硬な反論が、真正面からぶつけられてきて、自身の立場が危うくなった。一一と言うか、高橋哲哉の批判に対しては、正面きって反論できないほどの、相当なダメージを受けてしまった。つまり「敗戦」してしまった。
そこで、加藤は、高橋への正面きった反論はせずに(そこを「文学的に」迂回して)、ひたすら自己の「敗戦」の事実を糊塗すべく、「戦後後論」や「語り口の問題」を書いて、問題を「文学」という「自分の土俵」に引き込むことで、読者を煙に巻こうとしたのである。
加藤典洋という人が、自分で言うほど「繊細」でもなければ「弱く」もないというのは、『敗戦後論』の「あとがき」における、その臆面もない「手前味噌な言い分(自己賛美)」に明らかだ。
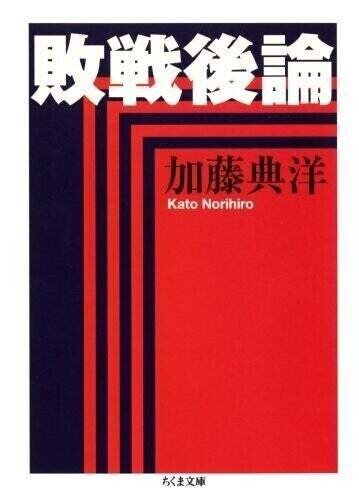
(1)『 イデオロギー的な国民批判とは、国民をまずイデオロギーとしてとらえ、そのイデオロギーとしての国民に対する批判の立場から、いわばトップダウン式に、さまざまな事象に対処していくありかたをさしている。「国民を単位とした考え方は、構造的にナショナルなものへの拝跪を内にひめている。したがって、そのような考え方の枠にとらわれている限り、最終的にはナショナルな戦前的国民観へと帰着せざるをえない」。このような形をとるのが、わたしのいうトップダウン式の考え方だが、イデオロギー的な批判は、必ずこうした、鳥瞰的視点と時間の先取りという二重に先取り的な構造をもち、またそれから自由ではないのである。
では、なぜこうした先取り的な構造ではダメなのか。
国民という考え方は、これだけをとれば、歴史的に、また地域的に、よい側面もあれば、悪い側面もある。イデオロギー的な国民批判は、この、そのつどよくも悪くもある国民という概念を、一色で悪としてとらえ、そこから判断を繰り出す。そのため、必ず、いや、国民というものはいいものだという、これも先回り的で一色の国民賞揚のイデオロギーを、対抗的に産み出さないではいないのである。』(P316)
(2)『 さて、わたしは、日本の戦後の閉塞性を、一つに、岸田秀の指摘している、日本社会が全体として他国に謝罪できない構造になっている状況、もう一つに、日本の中で相対立する意見の間に議論が成立しない状況を見る。わたしの論はここからはじまっている。わたしに対する批判は、このわたしの論が、国民という枠に沿っているといって批判するが、こうした先回りするイデオロギー的な国民批判が、この日本の戦後の手詰まり状況を作ったというのが、わたしの論の出発点なのだから、わたしに対する反論は、もし自分をまっとうにしたければ、このわたしのイデオロギー批判に対し、正面からこたえるものでなければならないのである。
このことと関連してもう一つ、歴史の問題がある。
わたしが、これまでの歴史をきちんと受けとめることのできる主体、というほどの意味で「語り口の問題」で使った「歴史形成の主体」という言葉が、ヘーゲルと結びつけられ、国民の大文字の歴史の創造といったナショナルな主張として受けとめられ、そこから、「歴史主体論争」などという言葉も生まれているが、それは、虚心にこの本を読んで下さった読者には明らかなように、わたしの論とは無関係である。』(P318)
(3)『 したがって、いまわたし達に求められているのは、世界史、自国史のいずれとも自分を関係させ、その双方との関係の中で、その双方をいわば串刺しする形で、これまでと違う歴史との関係を作りだすことだろう。そうでなければ、わたし達に歴史との関係、つまり他者との関係はもてない。わたしは、このことを「敗戦後論」で、自国の死者への哀悼を先にして、そのことが、そのまま、わたし達を他国の死者への謝罪の位置に立たせることへと続くあり方の創出、という主張として語っている。この主張の主旨はどちらが先か、というようなことではなく、この二様の死者の分裂を克服するあり方の創出ということであるから、そのあり方を作り出すうえで、わたしのいう自国の死者を先にするあり方ではうまくいかない、という批判が出てくるのなら、わたしとしては歓迎したい。しかし、本論に触れたように、現在までのところ、現れているのは、このわたしの論の基本的なモチーフを見ない、いずれが先であるべきか、というまたしてもイデオロギー的な立場からの素朴な批判でしかないのである。』(P321~322)
(4)『どうか、このわたしの主張を、イデオロギー的に取らないでほしい。ポストモダン思想と呼ばれた一連の思想は、抜本的なイデオロギー批判の思想として登場した。しかし、困ったことに、今度はそれ自体が、イデオロギー批判というイデオロギーに反転したのだった。わたしのこの論は、これとははっきりと対立している。このイデオロギー批判を、そう、「誤りうる形」に生き生きと保ち続けることが、ここでは徹頭徹尾、極度の細心さで、めざされているのである。』(P323)
(5)『 ゆっくりとした歩みで自分の関心を追ってきたら、ここまできた。歩きはじめたのはポストモダンの流行がはじまろうという時だったが、十二年もたつと、それも終わり、また次の流行が現れようとしている。塙保己一ではないが、「目あきの不自由な」時代は、なお続きそうである。
ヨーロッパに一年を過ごし、ハンナ・アーレントへの関心と、めっぽう好きになったピーター・ブリューゲルの絵に誘われるようにして、ウィーン、プラーグ、ベルリン、ブダペスト、ブリュッセル、デン・ハーグなど、中部ならびに東部ヨーロッパの都市をめぐり、暗い街灯の下、旧ユダヤ人街などを歩いた。ベルリンのザクセンハウゼン強制収容所跡地では取り壊されたガス室跡の前に立った。この十余年、自分なりに考えてきたことが、ヨーロッパに培われた思考の中に、一つの対応した動きをもっていることがわかったことが、わたしの今回の滞在の収穫だった。その嬉しい発見の余韻が、この本に底流するわたしの気分になっている。
今回の本がわたしにとってもつ意味は少なくない。わたしは今回ここに収録する文章を書いていて、「ラディカルな思考」の意味を自分でもう一度更新し、取り戻すことができた。また自分の中の政治と文学の分裂を克服できたし、自分の中の文学の意味をさらに一歩深めることができた。』(P324)
(6)『一九九七年二月、パリ、サン・シュルピス広場、六月、志木、柳瀬川のほとで
加藤典洋 』(P325)
見てのとおりで、この「あとがき」で語られているのは、次のようなことだ。
・「論敵の、私への批判はイデオロギー的なもので、トップダウン式の押しつけ論だ。一方、私の意見はボトムアップ式で、国民の現実を尊重するものだ。つまり、私の論には、鳥瞰的視点も時間の先取りもない(つまり、私には主観的視点と現時点に限定された眼前の事実しかなく、およそ客観視も無ければ予測を立てるということもない)」
・「論敵の思考には自由な柔軟性が無いが、私の思考にはそれがある」
・「論敵の現実把握は、一色で善悪を決めつける態のものだが、私のそれは色彩微妙なものである」
・「戦後の日本では、相対立する意見の間に議論が成立しない状況がある。私と私の批判者との間で、議論のすれ違いが生じているのは、私の論敵がそういう状況に巻き込まれているためであり、私の方はそうしたものに巻き込まれてはいない」
・「私がまぎらわしい書き方をしても、論敵はそれを、私の意図どおりに正しく解釈しなければならない」
・「私の意見をイデオロギー的なものとして読んではならない。それは間違いである」
・「私は、論敵の意見を正しく理解しているが、論敵は私の論を正しく理解していない」
・「論敵は、私を(私の望むがごとく)正しく批判しなければならない。しかし、論敵の私への批判は、すべて見当違いなものである」
・「私の議論は、徹頭徹尾、極度の細心さが目指されているが、論敵のそれは粗雑である」
・「私の思想は、ヨーロッパの深い思想と響き合っている。本書は、そうした深い思想に支えられている」
・「私の思想はラディカルであるが、論敵の思考は教条的に素朴である」
・「私は、世界と自国の歴史を串刺しにして透視する、日本のムラ的な発想の枠を超え出た、世界的な思想家である(私は、ハンナ・アーレントと深いところで響き合う思想家である)」
等々。
一一批判者の「論」への決めつけ的否定、自己や自説の「過大評価」と臆面もない自己喧伝。
よくもまあここまで書けたものだと呆れる反面、個人的には、その臆面も無さ(厚顔無恥さ)において「さすがは、笠井潔のお友達」だと、納得もしたしだいである。
ともあれ、加藤典洋が「戦後後論」や「語り口の問題」で語っている「個々の内容」は、「理想論」的な議論として、さほど大きな間違いはない、とは言えよう。しかし、自身がその「理想論」を体現した論者であるかのように語ってみせるところに、加藤典洋の「詐術」がある。
抽象的に「理想論」を語ることは、さほど難しいことではない。
だが、自身が、その「理想論」どおりの態度で語り行動するのは、決して容易なことではない。
例えば「冷静に客観的に議論しなければならない」と口で言うのは簡単だが、それを実行するのは容易なことではない。
人はしばしば「冷静に客観的に議論しなければならないって、言ってるじゃないか! 君はそんなこともわからないのか、このバカやろう!」などと口走りがちなものなのだ。
一一で、ここでの加藤典洋が、まさにそうした「人間らしい人間」なのである。
加藤は、「理想論」を語り、それを根拠に、相手の言い分に対して「無い物ねだり」をするが、では、自分の意見が、自身が他者に要求したような「理想論」どおりのものなのかといえば、もちろんそういうわけではなくて、加藤の「論」とて「無い物ねだり」ができないほどの「完璧な意見」などでは、決してないのである。
また、事実そういう「不完全な意見=誤解されても仕方のない意見」だったからこそ、批判者の意見は「すべて」誤解であるとか的外れであるなどと「断言」し、そう「決めつけ」ることで、排除しなければならなかったのであろう。
したがって、このような加藤典洋による、このような『敗戦後論』を、高く評価してしまうような人とは、加藤の『虚心にこの本を読んで下さった読者』などといった「媚び」に、ころりと惑わされてしまう「騙されやすい読者」なのだと言えようし、ましてこのような本に文学賞(伊藤整文学賞)を与えるような選考委員の文学者とは、文字どおり「文弱の開き盲」なのである。
○ ○ ○
・
○ ○ ○
(※ 上のレビュー後半で紹介している「西岡昌紀」は、「アウシュビッツは存在しない」論で物議を醸した「マルコポーロ廃刊事件」の当事者である。)
○ ○ ○
・
○ ○ ○
