
北海道新聞取材班 『追及・北海道警「裏金」疑惑』 : シジフォスの裔・ 倒されても、 また立ち上がる勇者たち
書評:北海道新聞取材班『追及・北海道警「裏金」疑惑』(講談社文庫)
本書は、2004年8月に、書き下ろしの「緊急出版」として講談社文庫から刊行されている。
帯の背の部分には『事態は進行中だ』とあるとおり、最初にテレビ朝日の報道番組がスクープして報じた「旭川中央警察署の裏金づくり事件」について、「抜かれ」てしまった立場の地元の「北海道新聞(道新)」は、そのメンツにかけて徹底的に追跡取材をした結果、この問題が全道(つまり、旭川中央警察署だけではなく、北海道警全体)に広がり、さらには全国(つまり、全国の都道府県警察を主導する警察庁)にまで広がりを見せることになった。その「途中経過」を報告したものが、本書である。
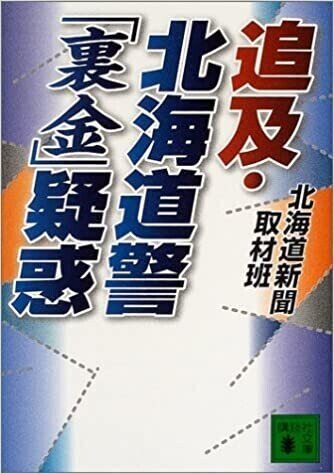
北海道新聞取材班による「旭川中央署の裏金づくり疑惑」に対する調査報道に対し、当初、北海道警察(道警)は、当然のことながら「全面否認」を貫いた。テレ朝の報道番組が証拠として示した「支払報告書」のコピーを「出所不明の文書」だと、近年の「加計学園に関する総理のご意向」問題で、当時の菅義偉官房長官(現総理)が発したのとそっくりな言葉で、この追求をかわそうとしたのだ。
この「捜査協力に対する謝礼の支払報告書」の宛先人物(謝礼をもらったことになっている人)は、じつは書類作成日の5年も前に死亡しており、支払いなどされていないことも、この書類が偽金づくりのために警察内部で「偽造」されたものであることも明らかなのだが、道警は、この書類コピー自体が「でっち上げ」である可能性を示唆して、相手にしない(事実関係の調査をしない)という姿勢を貫いたのである。
しかし、「警察の裏金づくり」問題は、なにも「旭川中央署」が初めてというわけではなかった。それまでにも全国のあちこちで散発的に同じ問題が浮上しながら、いつも警察側の「捜査上の秘密を守るため」という理由による門前払いによって、徹底した調査がなされることなく、時間稼ぎの逃げ切りによる「自然鎮火」という経過をたどっていたのである。
ところが、事実関係の調査から露骨に逃げようとする北海道警察本部長の姿をテレビで視、「道新取材班」の追跡報道に日々接した、多くの道民からの反発はどんどん強まっていった。
そしてついに、元「釧路方面本部長」であった原田宏二が「裏金づくりは、道警本部も含めて、道警全体で行われていたものである」と実名・顔出しで告発的告白するにいたった。

(元「釧路方面本部長」原田宏二の記者会見)
原田が、自身もまた「裏金」の一部をもらう立場にあったという恥さらしな事実を認めてまでの告発に踏み切ったのは、そうした裏金の元となった「捜査協力費」や「出張旅費」といったものは、本来ならば「現場の警察官」に支払われ、警察活動に使われるべきものであったからだ。そうした税金によって賄われている捜査活動資金が「裏金」になるということは、現場の警察官に必要な経費が支払われず、結果として、現場の警察官が自腹を切ったり、知らないうちに「ピンはね」されていたりといったことを意味したのである。
原田は現役時代から、こうした「慣例」を好ましくないものと思い、その廃止を内部で訴えたこともあったが「うちだけで良い子になるわけにはいかない」という趣旨から、原田の正論はあっさりと握りつぶされていたのである。
このようにして作られた、各警察署や地方警察本部の各部局で作られた「裏金」は、その部局の幹部の「交際費」や「転勤餞別」としてつかわれるだけではなく、各警察署から本部へ、本部から警察庁へと「上納」されるものであり、警察庁の主導管理のもとに、長年にわたって行われてきたものだ。
だから、それを内部的に改革しようとすれば、その個人が「干される」「飛ばされる」「冷や飯を食わされる」だけに終わってしまい、決して改革のなされることはなかったのである。
だからこそ、原田は、自身の過去の恥をさらしてまで、自身の知る範囲で「道警全体で裏金づくりが行われていた。これは現場で頑張る同僚警察官を裏切り、道民を裏切ることだから、もはや黙っているわけにはいかなくなったので、自分自身の罪もふくめて告白する」ことにしたのである。
しかし、それでも道警はこれを黙殺しようとした。いくら「元方面本部長」(道警のトップ6に入る立場)の証言だとは言え、個々具体的な証拠の裏付けのない話には、耳を貸さないという態度を貫いたのである。
すると今度は、弟子屈警察署勤務時代に自らが「裏金づくり」をやったと、同署の元副署長が、物証となる「裏帳簿」を持って名乗りを上げた。原田の告発にも、いっこうに態度を改めようとしない道警の態度に業を煮やし「原田さんを一人を討ち死にさせる訳にはいかない」と考えての行動だった。
このようにして、徐々に道警は苦しい立場に追い込まれていった。
当初は疑惑解明に消極的だった、知事や(共産党以外の)道議会や政党各派も、道民の注目にさらされて、黙っているわけにはいかなくなったのだ。
そして、とうとう「裏金づくり問題」は国会でも取りざたされることになり、警察庁にも波及しかねない全国的な問題と化していった。
○ ○ ○
以上が、本書『追及・北海道警「裏金」疑惑』に描かれた「途中経過」である。
その後も追求がなされた結果、道警は、個々の「裏金づくり」については事実と認めて謝罪し、『道警は最終的に3000人余りの警察官・職員を処分し、総額約9億6000万円を国庫などに返納する事態になった。』(「道警は最終的に3000人余りの警察官・職員を処分し、総額約9億6000万円を国庫などに返納する事態になった。」・2021年2月15日「東洋経済ONLINE」より)。しかし、最後まで「警察庁の主導による組織的犯行」という点については認めなかった。いわば、地方警察の署長クラスまでに責任を負わせる「尻尾切り」で、疑惑追及を収束させたのである。

(道警報償費疑惑で陳謝する芦刈道警本部長(右)、中塚道警総務部長(左)=2004年4月6日、道議会)
だが、話はこれで終わらなかった。警察は「裏金づくり」を告発暴露した「北海道新聞」を決して許さず、報復行動に出たのである。
『 03年11月末、テレビ朝日「ザ・スクープ」上で初めて明るみに出た北海道警裏金事件は、大きな波紋を呼び、地元紙である北海道新聞もその後を追って、高田氏の取材班を中心に追及を開始。当初、道警は裏金の存在を否定していたが、1年以上の綿密な取材の結果、最終的に組織的裏金作りの事実を認め、利子も含めた9億円超の資金の返還を行うことになった。高田氏ら取材班は、これら一連の取材で新聞協会賞、菊池寛賞などを受賞。社内外で称賛を浴びた。しかし、そんな栄光もつかの間、道警による逆襲が始まる。
05年、北海道新聞は「道警と函館税関『泳がせ捜査』失敗」(稲葉事件)と題した記事を掲載した。00年、道警が違法なおとり捜査をし、2トンもの麻薬密輸を故意に見逃したとされる事件(裁判ではおとり捜査の違法性は認められず)だが、かつて高田氏の取材班でキャップをつとめた佐藤一記者は、釈然としないものを感じており、改めてこの事件を追及。その記事が道警の反感を買い、裏金事件も合わせ、北海道新聞に対し執拗な謝罪要求を繰り返したのだ。
警察との関係を悪化させると、事件取材に協力を得られなくなる...。圧力に屈した北海道新聞はついに「泳がせ捜査失敗」記事のおわび社告を一面に掲載。不適切な記事であったと謝罪をした。高田氏と佐藤記者は、けん責(始末書を提出するだけのごくゆるい叱責)の懲戒処分となった。だが、記事の誤りを明確にしないおわび社告とゆるい懲戒に道警側は納得せず、北海道新聞に対し提訴。名誉棄損を訴えた。裁判はその後上告を繰り返し、11年、最高裁に上告が棄却されるまで約6年の月日を要した。現在は「民事訴訟において、高田氏が部下に偽証を行わせた」として、高田氏個人が新たに告発され、検察審査会において審議中である。』
(平野遼「警察の不正、新聞社の屈服、現場の敗北...権力に屈するジャーナリズムの真実」・2014年7月28日付「exiciteニュース」より)
このようにして、道警の「裏金づくり」を報じた「北海道新聞取材班」の記者たちは、報復にあった。
同キャンペーンを指揮した、元「北海道新聞編集局報道本部次長」であり、本書『追及・北海道警「裏金」疑惑』の「あとがき」を担当している高田昌幸と、取材班の中心的な存在だった佐藤一記者は、このように「狙い撃ち」にされ、警察に屈した「北海道新聞」によって、「取材班」だったメンバーたちは、同社に居場所を失うことになっていったのである。

○ ○ ○
私が今頃になって、この本を読んでみようと考えたのは、この「取材班」の若手記者の一人であった、青木美希の著書『いないことにされる私たち 福島第一原発事故10年目の「言ってはいけない真実」』(朝日新聞出版・2021年4月刊)を読んだからである。

同書の著者経歴紹介は、次のとおりだ。
『札幌市出身。北海タイムス(休刊)で警察、経済取材を、北海道新聞で北海道警裏金問題などを取材し、2010年に朝日新聞社に入社。東日本大震災を発生翌日から現場で取材し、原発事故を検証する企画「プロメテウスの罠」などに参加。「手抜き除染」報道などを手がける。著書「地図から消される街」(講談社現代新書)で貧困ジャーナリズム大賞、日本医学ジャーナリスト協会賞特別賞など受賞。』
私の頭の片隅には「道警裏金問題」を追求した北海道新聞は、最後は警察の報復にあって屈服させられたという事実を、ぼんやりと覚えていたので、この本の著者の青木が、その時の取材記者の一人であり、今は朝日新聞社に籍を移して、志を貫いているのだな、と感心したのである。
後先になるが『追及・北海道警「裏金」疑惑』の、高田昌幸による「あとがき」には、次のように「取材班の紹介」がなされていた。
『 取材班は、佐藤一のほか、中原洋之輔(サブキャップ)、松本成一、林真樹、峯村秀樹、米林千晴、田中徹、青木美希の八人で構成し、二〇〇四年四月からは新人の内山岳志が加わった。大半は入社十年に満たない若い記者であり、通常の事件事故取材をこなしながら、裏金問題を手がけた。』(P472)
たぶん、記者たちの名前は入社年次順に書かれているのであろう。つまり、青木美希は、後から加わる新人の内山を除けば、最末端の若手記者だったということである。
その若手記者であった青木は、「北海道新聞」が警察権力に屈した後、同社を退社して「朝日新聞社」に就職し、その経歴から明らかなように、「権力」側の欺瞞を暴き、「弱者」に寄り添う報道を貫いてきた。
だが、青木の著書『いないことにされる私たち 福島第一原発事故10年目の「言ってはいけない真実」』のAmazonレビューにも記したように、今度は朝日新聞社社内で、青木は「記事が書けない立場」に追いやられているらしい。
『しかし、本書(※ 『いないことにされる私たち』)でも描かれているとおり、「管理者になるか、現場に残るか」と問われて「現場に残してください」と言っていた彼女(※ 青木美希)が、今は「現場」から外されていると言う。これはどういうことなのか?
「Together」には、次のような「まとめページ」がある。
『日刊ゲンダイが暴露した朝日新聞記者の青木美希さんの配転問題。記事を書かせない部署への配転は報道機関としての自殺行為にほかなりません。新聞社上層部が総理とメシを食ってるのがついにここまできてしまったということなのでしょう。青木さんの配転問題に怒るみなさんの声をまとめました。』
真相はわからない。
だが、「コロナ死者」が見えなくされているように、「原発被災者」や「避難者」が消され続けているように、本書著者のような「国家意志に対して反動的な記者」が「消される」というのは、ごく自然なことであり、疑う根拠は十二分にある。』
(拙レビュー「〈消される現実〉を消させない記者が、消される時代」より)
「権力の横暴と、それに抗おうとする記者たちとの戦い」一一それは、永遠に終わることのないものだろう。
善意のジャーナリストたちは、「権力の横暴」に抗っては、暴力的に叩きのめされ、見せしめにされる。
それでもまた、その重く苦しい宿命を引き受けて立つジャーナリストが現れる。
私は、そんな志あるジャーナリストたちに敬意を表して「シジフォスの裔」と名付けたのである。
初出:2021年6月22日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
再録:2021年7月10日「アレクセイの花園」
(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
