
リドリー・スコット監督 『ブレードランナー』 : レプリカント殺しの 警察官
映画評:リドリー・スコット監督『ブレードランナー』
言わずと知れた「SF映画の金字塔」。
フィリップ・K・ディックの原作小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を元にした、哀愁ただよう「SFノワールアクション」である。
監督は、かの『エイリアン』に次いで、1982年にハリウッドでの2作目として本作を撮った、まだ若手監督だった頃の巨匠、リドリー・スコット。
で、そんな「名作」を、今ごろ観たのである。

先日、これも今頃、サンリオSF文庫の短編集『ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック』第1巻を読んで、そのレビューにも書いたとおり、ディックの作品は長編中心に、かなり以前から読んでおり、『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』も、映画の大ヒットには遅れるものの、その数年後には読んでいた。

アーサー・C・クラークの原作小説を、スタンリー・キューブリック監督が撮った、1968年の『2001年宇宙の旅』に、ぐっと遅れはするものの、いまだに『2001年宇宙の旅』を超える「SF映画」がないと評されるほどの傑作に対し、本作『ブレードランナー』は、私が原作小説を読んだ当時すでに、「SF映画の2大傑作」と並び評されていた。

原作小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を読んだ当時の、原作小説についての私の感想は、「いつもどおりに」面白くはあるものの、この作品がディックの中で、特に優れた作品だという印象はなかった。
個人的な趣味で言えば「ヴァリス3部作」が好きだし、一般的な文学的達成度として言えば『ユービック』の方が「上だろう」という感じだったのだ。
そして、そうした原作の印象と、あちこちで耳にする映画版の評判や、映画のビジュアルイメージからすると「映画の方は、いかにもハリウッドらしく、ビジュアルイメージで圧倒するSFアクション映画になっているようだ」という印象が強かった。
また、当時は日本でも、映画『スターウォーズ』(1977年、ジョージ・ルーカス監督)以来の一大「SFブーム」であったから、そうした時期におけるSFマニアの言説として「SFは絵である」などとも言われてもいたので、この作品が日本でも大変な持て囃されようだったのは、とてもよく理解できはした。
だが、その反面、私は当時から流行りものが嫌いな天の邪鬼の傾向があったので、いずれは観なければならない作品ではあるにしても、すぐに観る必要はなかろうと、そんな感じであったため、観ようと思えばいつでも観られる「名作」たる本作を、(あくまでも、アニメと読書を優先して)これまで長らく放置してきたのである。
さて、今となっては、原作の方の記憶がいささか曖昧で、あまり正確な比較もできそうにない。そこで今回は、原作との比較ではなく、映画そのものについて語りたいと思う。
ただ、この映画自体は、キューブリックの『2001年宇宙の旅』と違い、決して難しい映画ではなく、言うなれば「そこらのSFオタクでも楽しめる作品」なので、さんざ語られ尽くされているであろう本作を、その線で今さら再説しようとは思わない。
ただ、いちおう簡単にまとめておけば、こんな感じになろう。
(1)酸性雨が降りしきって、晴れることのない世紀末的な雰囲気の「2019年のニューヨーク」を、東洋趣味のエキゾチズムにおいて描いた独創性は、驚愕に値するほど斬新なものであり、それでいて、シド・ミードがデザインした未来的なメカなどとも見事に融合させていた点で、この作品は「SFは絵である」を「地で行った」と言うよりも、「SFは絵である」という言葉に、説得力を与えた作品の一つである。




(2)本作は、ディックの原作映画らしく、「模造人間」の問題が扱われている。しかし、原作の方は「本物・偽物」という価値の相対性を問うような哲学的な思弁が前面に出るのに対して、映画版の方はむしろ「心を持った存在への差別」を扱っていて、そこが「人情に訴えて」わかりやすかった、というところがあるだろう。
つまり、原作の方は「人間だって、アンドロイドだって、そもそも作り物であって、どっちが本物も偽物もないだろう」という「そもそも論」だったのに対し、映画の方は「人間視点」で「ほとんど人間同様の彼らアンドロイドを、差別してはならないのではないか?」という、あまり自覚のない「生命の価値判定者たる人間」という意識が、まだ残っていた作品であり、だからこそ「わかりやすい」作品だったのである。
今の言葉で言えば「人工知能が、シンギュラリティ(特異点)を超えて、人間以上となり、しかも自我まで持つようになった場合、人間はどうなるのか。どうすべきなのか」という問題を、もう少し「ヒューマニズム」あふれる作品として描いたのが、リドリー・スコット監督の『ブレードランナー』だったのだと言えよう。



○ ○ ○
で、以上が(たぶん)「一般的な映画評」としての「総括」であり、私の本当の独自評価は、ここからだ。
唐突で恐縮だが、私は、満期定年退職まで約半年を残した昨年(2022年)7月末に、大阪府警察を早期退職して「元警察官」である。
つまり、本編の主人公であるリック・デッカード(ハリソン・フォード)と同じ職業だったわけだが、そんな私から見ると、デッカードは、じつに「凡庸な警察官」であった。

私は、退職するまで「生涯一巡査」であり、デッカードの方は、たぶん「ある種のエリート刑事」の中から抜擢されて「レプリカント専門の捜査官」となった人だから、日本での階級で言うと、たぶん「警部」止まりではあろうものの「捜査官」としては「腕利き」だったということだろう。
要は「全国指名手配犯を見つけて捕まえる」といった「検挙実績」がずば抜けており、かつ「各種格闘術に通じていた」からこそ、いろいろと困難や危険を伴う「レプリカント専門の捜査官」に抜擢されたのであろうというのは、容易に推察できるところだった。
だから、本来なら、私のような「平凡で取り柄のない(元)巡査」が、デッカードのような「エリート捜査官」を捕まえて「凡庸な警察官」だなどと評するのは、身の程をわきまえないにもほどがある、ということになろう。
だが、私がデッカードを、このように「上から目線」で評価できるのは、例えば、現役時代から私が、「署長さん」はもとより、雲の上の「本部長さん」や「警視総監」さえ、「凡庸な人たち」と評価し得たような人間だったからに他ならない。
つまり、私は、彼らを「警察内的基準」で評価したのではなく、「人間的基準」において「凡庸」だと評価していたのである。
私は、警察内で「階級」を求めなかった分、彼らが、足元にも及ばないような「幅広い教養」を身につけ、それによって、彼らを評価したのだ。
「評価」というのは、「警察内部的な、村うちの評価」などより、より高次な「人間的評価」の方が、本質的でもあれば、意味があるというのは、言うまでもないからである。私は、伊達に「昇任試験のための勉強」など一切せずに、ひたすらいろんな本を読んできたわけではない、のだ。
(ちなみに、国家上級職として警察幹部となった上層部の人たち、いわゆるキャリアたちは、学歴エリートではあるが、所詮は大した教養を持てない。なぜなら、教養は、直接的には、出世の役には立たないものだからである)
例えば私が、小説家にして評論家で、著書もたくさんある「笠井潔」をつかまえて、所詮は「才能のある口先男」だなどと評価できるのも、私が「文筆業界内的」評価や、「知名度主義的」評価を採らないからに他ならない。
あくまでも私は、笠井潔と「同じ人間」として「笠井潔葬送派」を名乗り、徹底的に笠井のような「著名人」を批判した人間なのだから、一般的には誰も名前など知らない「署長さん」や「本部長さん」、あるいは「警視総監」さえ、「ただの人」だと評するのは「当たり前」の話でしかない。
そんなわけで、私は「警視総監」よりもさらに上の「警察庁長官」にまで上り詰めた「中村格」ついて、次のレビューの中で「人間のクズ」扱いにしている。
実際、高卒で警察官になった私の、同期3クラス120人ほどの中には、「警視正」になったものも何人かいる。
この、公開されている「大阪府人事異動者リスト」の中の「警視正」にも、私と同じ学級だった、クラス3役(級長・副級長・広報)の一つである「広報」をやっていたクラスメートの名前があり、同期別学級の級長の名前も「方面本部長」のところに記されている。
で、こういう人たちを、私がどう評価するかというと「悪い人たちではないけど、たぶん警察べったりの人生を歩んだ人でしかないだろう。その意味では、つまらない人間なのではないかな」といったことになる。
なにしろ、ここまで出世しようとすれば、常に「昇任」のことを意識して「勉強」を怠らず、同時に「昇任」を意識した「仕事の実績」を出してこなくてはならなかったであろう。無論、上司に好かれる努力もしたはずで、「飲み会」にも喜んで参加しては、お酌などもしていたはずである(そして今年、定年退職して天下りをする)。
だから、こんな人たちも、人間的には「悪い人ではない」とは思うものの、それは要するに「普通程度に、いい人」であり、その意味で「凡庸」な人たちでしかなく、こんな人たちと飲んでも、警察内部の話かしないだろうから「つまらない」としか思えない、ということなのだ。
言い換えれば、今の彼らが、私が「年間読書人=アレクセイ=田中幸一」として、これまでにどんなことを書いてきたかを知ったら、恐ろしくて「腹を割った話」なんてできないはずなのである。だから、つまらない。
テレビには、「元警視」だ「元警部」だといった人たちが登場して「(世間の良識に合わせて)物分かりの良いこと」を話したりしているけれども、彼らの現役時代の階級が高ければ高いほど、それは「外では話せないこと」もいろいろとやっているというのは、まず間違いのないところだ。
だから、警察を辞めてしまって、完全に「同じ人間」になってしまった今となっては、彼らは「笠井潔」の足下にも及ばないほど、個別の批判にも値しない「凡人」だというのが、私の評価なのだ。
で、そうした意味では、デッカードの「エリート捜査官」という評価も、「テレビドラマでもあるまいし、だからどうした」というほどの価値しか持たない。

むしろ「警察」内部で、何の疑問もなく、一所懸命に仕事をした結果、「君は優れた捜査官だから、是非ともレプリカント専門の捜査官になってくれ」などと煽てられ、まさかそれが「レプリカントの始末屋(殺し屋)」だなどとは知らずに喜んで引き受けた結果、その仕事の陰惨さにうんざりし、その挙句、早期退職したつもりでいたら、後任が返り討ちにあって殺されたので、「やっぱり、お前にやってもらう」と否応なく命じられた、というのが「この物語の冒頭である」と、そうまとめることができよう。

つまり、彼は「刑事さん(刑事課捜査官)」だった人が、有能だからというので「思想警察」たる「警備部(公安課)」に引っ張り込まれて「君には、オウム真理教担当捜査官をやってもらう。どんな手段を使ってもいいから、やつらを検挙しろ」と言われて、「転び公妨(※ 自分から転んでおいて、押し倒されたので公務執行妨害だと言って検挙する、公安警察特有の裏テク)」めいたことをやらされて、嫌になった「元刑事さん」みたいなものである、とでも言えようか。

つまり、彼は「刑事さん」としては有能だったし、真面目に仕事に励んだ、評価されてしかるべき人だったのだが、しかし「警察の仕事」が何でもかんでも「すばらしい(倫理的にも価値が高い)」わけではないということを、たぶんよく知らなかった「仕事バカ」だったのであり、およそそれまでは、「レプリカントの人権」なんてことも考えたことはなかったのだろう。
そうした意味で、デッカードは「凡庸な警察官」だったのである。
例えて言うなら、沖縄に派遣された大阪府警の機動隊員が、米軍北部訓練場のヘリパッド建設現場の工事に対し、反対運動をしていた人たちを「土人」呼ばわりしたのと、同じ程度の意識だったわけだ。
まただからこそ、そんなわけで、私のような、いろいろと「警察以外の問題に詳しい」人間は、警察的な見解をナイーブに「内面化」したりはしない。
例えば、大阪府警の採用試験に合格して、最初に入学する警察学校の初任教養科(これは当時の名称。当時は、大卒は半年、高卒は1年間、全寮制で入校した)の学級担任は、警備部出身の「警部補」であり、人柄的には温厚な常識人で、個人的には好感を持っていたのだが、ある時「おやっ?」と思ったことがあった。
当時、初任教養科の学生は、毎日「学生日誌」を書いて「担当教官」に読んでもらうことになっていた。私は文章が書くことが好きだったから、これは苦にはならないどころか、むしろ、かなり攻めた書き方をしていたと思う。
それでも、警察官である以上は、警察組織が明らかに喜ばないようなことは避けていたつもりだったのだが、ある時、日誌に「稀代の大悪法である治安維持法は、戦後廃止になった。私たちは、民主警察として、国民のために働かなくてはならない」といった、自分としては「無難なこと」書いたつもりが、翌日帰ってきた日誌には、いつもの赤ペンで「稀代の大悪法たる治安維持法」の部分に下線が引かれており、短く「そうだろうか?」という感想が添えられていたのだ。
要は、現在では「治安維持法」は、抑圧的で非民主的な「悪法だったからこそ、戦後廃止された」ことになってはいるが、歴史的に見れば、あの法律は「国家転覆」を企む共産党を取り締まるために作られた法律なのだから、いちがいに「悪法」呼ばわりするのは、一種の時代的「偏見」ではないのかと、警備部出身の担任教官は、きっと、そう言いたかったのであろう。
私の方は、当時はまだ「創価学会員」であり、創価学会では「牧口常三郎初代会長と戸田城聖第二代会長は、本山を通して命令された神札の掲示を断り、それを口実に、稀代の大悪法たる治安維持法違反で逮捕され、牧口会長は獄死することになる」などと何度も教えられてきたし、世間一般の書籍や、NHKの歴史スペシャル番組などを視ても、治安維持法だけは、言い訳の余地のない「悪法」であり、戦後も30年近く経った今になって、まさかそうした評価に疑問を呈するような人が、警察の中にさえ、いようとは(当時の若い私には)思えなかったのだ。
ちなみに、この教官が、本当に「いい人」であったのだろうということを示すエピソードを、ひとつ紹介しておこう。
ある時、ホームルームの授業に、教官がカセットデッキを持ってきて「これから皆さんに、私の好きな歌を聞いてもらおうと思います。これは、警察官のあるべき精神を歌っていると、私は思っているのです」と言って、その曲を流した。
その曲とは、テレビ特撮ドラマ『宇宙刑事シャリバン』のエンディングテーマ曲「強さは愛だ」(作詞:山川啓介、作曲:渡辺宙明、歌:串田アキラ)であった。
『 「強さは愛だ」
強いやつほど 笑顔はやさしい
だって強さは 愛だもの
おまえとおなじさ 握ったこぶしは
誰かの幸せ 守るため
倒れたら 立ち上がり
前よりも 強くなれ
苦しみを 苦しみを 越えようぜ
Oh, Yes おれたち男さ 男さ
数えきれない 夜空の星でも
きっと誰かが 夢見てる
おまえとおなじさ あしたが今日より
いい日になれと 祈ってる
悲しみに ほほえんで
よろこびに うなずいて
思いきり 思いきり 生きようぜ
Oh, Yes おれたち仲間さ 仲間さ
倒れたら 立ち上がり
前よりも 強くなれ
苦しみを 苦しみを 越えようぜ
Oh, Yes おれたち男さ 男さ 』
私は今でも、この歌を学生たちに聞かせた教官が、本気でこの歌の歌詞の語るところを信じていたのだろうと思っている。
だが、残念なことに、たぶん彼は、いろいろな「思想」については、警察に入ってから、警察内部で学んだだけなのだろうと思う。
当時の「初任教養科の担任教官」は、せいぜい三十代半ばまでであり、将来出世するであろう優秀な警察官の中から選ばれていた。
しかし、三十代半ばとは、要は学生たちより十いくつ上なだけであり、たしかに「学生運動の残滓」あたりなら目にしたことがあったのかもしれず、それに悪印象があったのかもしれないが、いずれにしろ「思想・哲学」を一方的に断罪できるほどの、幅広い教養などなかったであろうことは、今の私には容易に想像推察できるのだ。
実際、警察の「思想」教育というのは、一面的かつ一方的なものであって、警察学校を卒業して以降も、自身を「内外境界的存在」と規定して教養を深めていった私には、そうした「思想」教育は、なんとも「薄っぺら」なものでしかなかった。
要は「現行法が正しい」「警察は、国家と国民を守るために存在する」といった「当たり前」の話しかなく、例えば「国家と国民が敵対した場合には、警察はどちらにつくのか」などといった高度な議論など、それを教育する側の人たち自身でさえ、想像もできないレベルの話であったのだ。
だから、世界一「民主的」と呼ばれた「香港警察」が、中国本土政府の方針転換によって「民主化運動撲滅」に舵を切った後は、ほぼ無抵抗なまま「国家の忠実な犬」になり下がったというのも、個々の警察官の多くが、所詮は「教えられてきたことを鵜呑みにして、それ以上のことを、自分の頭で考えたことがなかったからだろう」と容易に推察がついたのである。そしてこれは、日本警察でも、まったく同じことなのだ。
例えば、大阪府警の各所轄警察署では、私が警察官になって以降ずっと今でも、毎月「全員教養の日」というのがあって、署員全員が、署長以下、各課長による講義を、全部で3時間前後、聴かされるという慣習的行事がある。
だが、これが毎回、どこの署であっても、代わり映えのしないもので、かなりウンザリさせられるものなのだ。
署長は、基本的には「仕事に結びつく道徳訓話」なのだが、要は「社長さんの有難いお話」みたいなもので、有難いのは最初の数年だけで、ベテランになってくると「その話は、他署でも何度も聞いてるよ。同じ種本で喋ってるんだろう。話すことがなければ、遠慮して、他の課長に時間を譲れよ」などと考えるようになる。
副署長は、自分の役割として「事故防止」の話をする。要するに「不祥事を起こすな」「何か悩みがあれば、すぐに相談するように」といった話で、年頭の教養日では「昨年の大阪府警の懲戒免職件数」の話をしたりする。
各課長は、自分の職掌の範囲で、多くの場合「取締り強化月間」のテーマに合わせた話をする。例えば、選挙の季節が近づくと、選挙を担当する刑事課の課長か、さもなくば直接の担当者である「捜査1係」の係長が、選挙取締りにあたっての注意点を話したりするのだが、要は「公職選挙法」は国会議員自身が作った「ザル法」だから、慎重にやらないとひどい目に遭うから気をつけろという話が中心である。
生活安全課、交通課、地域課といったところは、ぐっと実務的な話しかしないが、問題の「思想警察」たる警備課の講義内容として十年一日なのは「日本共産党の基本的な性格」とか「日共の警察対策について」といった話で、要は「共産党は、今でも暴力革命を捨てていない」とか「共産党は、警察を国家の暴力装置と考え、その無力化のために日々活動しているから、それに取り込まれたりしないようにしなければならない。例えば、日共系の病院にかかったり、生協や文化サークルなどに、迂闊に参加したりしてはいけない。分からなければ問い合わせてください」といった話である。
私は、こうしたものを40年間、繰り返し、ほぼ毎月聞かされてきたのだから、話しているのが「警備課長」(警視、警部クラス)だといっても、心の中では「あんた、絶対『資本論』なんか読んだことないだろう。ま、私もだけど、そんな簡単な話じゃないことくらいは知ってるんだよ」などと思いながら、聞いてきたのである。そして、その結果が、次のようなレビューだ。
○ ○ ○
そんなわけで、デッカードは「仕事熱心な、ナイーブな刑事さん」であり、その意味で「優秀な捜査官」であったために、最後は、愛してしまったレプリカントであるレイチェル(ショーン・ヤング)のために、組織を裏切り、法を犯すことになる。
人間の「奴隷」であることに満足せず、自由を欲して人間の命令に抗った「レプリカント」たちは、危険な存在として「抹殺」されなければならなかったからだ。

つまり、「レプリカント」とは、かつてのアメリカにおける「黒人奴隷」のことであり、今の日本における「外国人研修生」みたいなものなのだ。
彼らは、当たり前の人間としての「人格」や「人権」を認められずに、なかば騙されての「奴隷労働」を強いられ、それに耐えきれずに逃亡すれば、「不法滞在者」や「不法就労者」として「犯罪者」に認定されてしまい、警察から追われる身になってしまう。
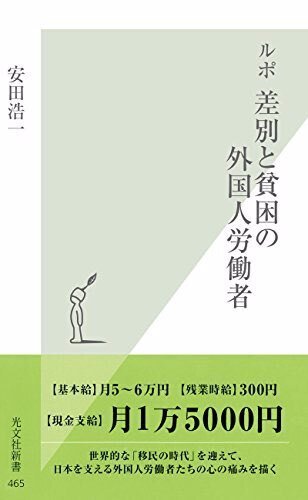
警察が彼らを「犯罪者」として追う理由とは、端的に「(日本の)法律を犯したから」ということでしかなく、その法律の「おかしさ」を問うことはない。
「それは、警察の仕事ではなく、警察がすべきは、現行法に沿って粛々と仕事を進めることだけだ」というわけだが、その意味では「戦時中の特高警察」の発想と、何ら変わってはいないのである。だからこそ、「非人情」にも、彼らを「犯罪者」呼ばわりすることができるのだ。
「国家警察」たる警備警察が、特に顕著なのだが、警察というのは、必要とあれば「法も犯す」ものであり、その実例が、前述の「転び公妨」である。
そして、その意味では、警察幹部の言う「警察がすべきは、現行法に沿って粛々と仕事を進めることだけだ」というのも、所詮は「きれいごとのタテマエ」でしかなく、本音ではない(ちなみに、幹部教養機関である警察大学では「帝王学が教えられる」と聞いたこともある)。
実際、もともと「天下国家」で考えるキャリアは別にして、叩き上げ警察官の限界まで階級を上り詰めるのは、「警備畑」出身者ばかりだ。
もちろん、出世昇任していく過程で、警察業務の基本である「刑事畑」の経験くらいはしているが、「交通畑」や「地域畑」出身の「(都道府県)本部長」などというのは、絶えて存在しないのである(つまり、警備部、刑事部、総務部、警務部、生活安全部など以外の、交通部や地域部の部長止まりだということ)。
で、上がそんな感じならば、下っ端である「地域課警察官(交番のおまわりさん)」の意識も、推して知るべし、だ。
「交番のおまわりさん」が警察組織から求められる、主な仕事は、
(1)刑法犯の職質検挙
(2)交通違反の検挙取締り
(3)巡回連絡の推進
であり、これに日々の事案処理が加わると考えていい。
ただ、日々の事案処理は、相手がいてのことだから、これは「成績」には反映されにくく、前記の「数字」として見えやすい積極的な「実績」が、どうしても問われることになる。
しかし、(2)と(3)は、ある程度「やりさえすれば、結果は出る」のだが、(1)はそうはいかない。
要は、「私は犯罪者です」とか「私は罪を犯してきました」などといった顔をして歩いているものはいないから、「不審者」に「職務質問」をして、その不審点を追求し、それで検挙しなければならないとは言っても、「不審点」なんてものは、そうあからさまに見えるようなものではないからだ。
法律では「不審点があれば、職務質問をして、それを解明しなければならない」と、それが警察官の職務だと規定している。
ところが逆に「不審点」が無ければ「職質」できないとなると、検挙実績は「あがったり」になってしまうから、よぼど目利きの警察官ででもないかぎりは、「ひとまず片っ端から」職質をし、それで経験値を積んでゆき、そのなかで「不審点」についての「着眼力」を身につけていくのである。
だから、「不審でも何でもない人に、職質するのは嫌だ」とか思っていた私のような警察官は、いつまで経っても、検挙実績が上がらない、ということになる。
私はもともと「人に借りを作るのが嫌」な人間だから、「普通の罪なき人に職質をかけて、時間を取らせる」のが申し訳なくて、嫌なのだ。あきらかに、こいつは「犯罪者」や「悪人」だとわかる相手には、誰よりも前に出て「攻撃」を仕掛けるタイプなのは、その裏返しなのである。
つまり、私がネットで、「ネトウヨ」を目の敵にしたのも、わかりやすい「敵」には容赦しない性格だからであり、文章でも「批判においては、相手を筆で殺すつもりで書いている」などと豪語するのも、ハッキリと「問題点」が見えているという確信があってのことだからなのだ。
で、そんな訳で、私は職質が嫌いだし苦手だったので、そこを(2)と(3)でフォローして、何とかクビにならない程度の成績で凌いできたのだが、中には、職質が「面白い」という人もいるし、「面白い」とは思わないまでも、「やり方はある」という人もいる。
「面白い」という人は、職質の経験値を積むことで、自分の力量がアップするのが楽しいし、それで実績も上がり、上司にも褒められれば嬉しいと、そういうわかりやすい話である。それに成績が良くないと、出世もできない。
だが、こういう人は「職質される側」の感情が気にならないタイプなのだとも言えよう。
仮に「何もないことが判明」したら「お時間を取らせて、申し訳ありませんでした」と謝罪しておけば、それで次の瞬間には、すべて忘れてしまえるタイプ。
私のように、無駄に「負い目」を感じるなどという、「警察官」としてはほとんど無意味な感情など持たない、「実務家」なのである。
一方、本当の問題は、職質にも「やり方がある」と考えるようなタイプの警察官だ。
私の同僚の一人に、「外国人」狙いで、職質をする人がいた。要は、この人は「それが効率的だ」と考えたのである。
漠然と日本人を職質しても、なかなか検挙には結びつかないが、外国人なら、軽微な犯罪とはいえ、検挙に結びつく確率が、ぐっと高くなる。ならば「刑法犯ではなく、特別法犯だとは言っても、検挙は検挙だ」と、そう合理的に考えて「不法滞在(不法残留)」の外国人を検挙すべく、外国人狙いで職質をしていたのである。
こうした「外国人労働者」の問題について興味のある人は、すでに新聞やニュースなどでも「外国人に対する、差別的な職務質問」の問題が取り上げられていることを知っているだろう。私の同僚の例がそうであるように、そのように事実は、実際にあると考えていい。
ところが、この同僚や、外国人狙いで職質をする警察官の多くは、実のところ「差別意識らしい差別意識」を持っているわけではなく、単に「検挙実績」を上げるための「経済効率性」から、外国人に犠牲を強いているだけ、でしかない。つまり、「自覚のない差別意識」だとも言えるだろう。
積極的に「差別する気はない」が、結果として「数字を上げるための、犠牲になってもらう」ことについては、ほとんど気にしていないのである。「だって、外国人の方が、犯罪者の比率が高いのなら、外国人を狙うのは当然でしょう」というのが、こうした警察官の「本音」なのである。
つまり、私が言いたいのは、本作『ブレードランナー』の主人公であるデッカードも、こうした「凡庸な警察官」の一人でしかなかった、ということなのだ。
彼はたしかに、与えられた「職務に精励した」のであろう。そして、その結果として、警察組織内では高く評価され、一般にも「優秀な捜査官」と、そう評されて良い実績を残した人だった。
一一だが、ただそれだけだったからこそ、デッカードは「レプリカント殺しの警察官」となってしまい、それに耐えきれなくなって、彼なりの「正義」や「倫理」から、警察から離反することにもなったのである。

彼が、もう少し、世間を広く見渡すことができる人だったなら、彼は、私のように「パッとしない警察官」になっていた可能性も、まったくないわけではない。
少なくとも、命じられて「レプリカント専門の捜査官」となり、何人かの「人間にしか見えないレプリカントたち」を惨殺した後になって、疑問を感じるような「間抜け」なことにはならず、新任務の打診を受けた際には、なんとか口実を作って断るとか、そもそも、そんなものの候補になどならないように「あまり成績は上げないでおく」とか「見逃す時は、黙って見逃す」なんて「要領」を使っただろう。
それで「成績」が上がらず「出世」できなくても、気持ち良く生きられると、そう割り切って。
だから、デッカードは「凡庸な警察官」であったと同時に、「凡庸な人間」でもあった。
そして、そうした「凡庸な人間」というのは、何も「警察官」に限ったことではない。
「外国人研修制度」を悪用して、外国人研修生に「奴隷労働」を強いるような「日本人」経営者は、彼ら「外国人労働者」を「レプリカント」扱いにしており、要は「人間」だと思っていない人たちなのである。
だが、そんな人たちが「冷血な悪人」かと言えば、そんなことはない。
彼らも「そうしないと、経営が立ち行かない」と考えているような、ただそれだけの「凡庸な悪」であることが少なくなく、その意味では「日本人の高齢化が進み、若年層が減ってくれば、若い外国人労働者をもっと積極的に受け入れなければならない」といった「もっともらしいこと」を言っている人の中にも、その「外国人に、日本人並みの待遇を保証する」ものと考えて、そう言っている人がどの程度いるのかは、かなり疑わしい。つまり「外国人労働者に、日本人並みの待遇を保証したら、それこそ元も子もないじゃないか」と考えるような人は、無自覚な「差別主義者」でしかないのである。
そうした意味で、私が今回『ブレードランナー』のレビューとして訴えたい、私独自の理解とは「これは、今の日本の物語である」ということだ。
そして、そのことに、本作『ブレードランナー』を絶賛する、日本人映画ファンも、日本人映画評論家も、日本人SFファンも、まったく気づいていないし、その自覚など、当然ない。
彼らは「レプリカントが可哀想だ」などと、本気で考えるのだろうが、実際のところ、彼らの多くは、レプリカントを犠牲にすることで、自分たちの生活を守ることしか考えていない、「差別主義者」である。
「差別主義者」とは、何も「在特会」とか「ネトウヨ」とかいった、わかりやすい連中のことだけを言うのではない。実のところ、同時代の多数派が、「少数派」に対する「差別主義者」であるというのは、常識に類する話なのだ。
一一そして、今日も日本の各地で、「今レプリカント」たちが、彼らを追う警察と、それを支える日本人社会から、逃げ回っている。自らの、人間としての尊厳と自由を守るために。
(2023年1月9日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
