
映画『スキャナー・ダークリー』 : 私は、私に監視されている。
映画評:リチャード・リンクレイター監督『スキャナー・ダークリー』
SF作家フィリップ・K・ディックの長編小説『暗闇のスキャナー』(邦題)の映画化作品。タイトルは「暗闇の監視者」というほどの意味だ。
ディックの映画化作品といえば、『ブレードランナー』(リドリー・スコット監督)、『トータル・リコール』(ポール・バーホーベン監督)、『マイノリティー・リポート』(スティーヴン・スピルバーグ監督)といったところが有名であろう。
それらの作品に比べると、本作『スキャナー・ダークリー』は、キアヌ・リーヴス、ロバート・ダウニー・Jr、ウディ・ハレルソン、ウィノ・ライダーといった豪華な俳優陣が出演しているわりには、マイナーと言ってもいい位置づけになってしまっているのは、一体どういうことなのだろうか?
私は、原作小説『暗闇のスキャナー』を、30年以上前に読んでいるが、まったく内容を記憶していない。
当時の読書ノートを見てみると「10点満点で7点」という評価だから、全然つまらなかったわけではないようだが「まずまず」といった評価に止まったようで、「面白かった」というわけではなかったようだ。だから、まったく印象に残っていないのであろう。

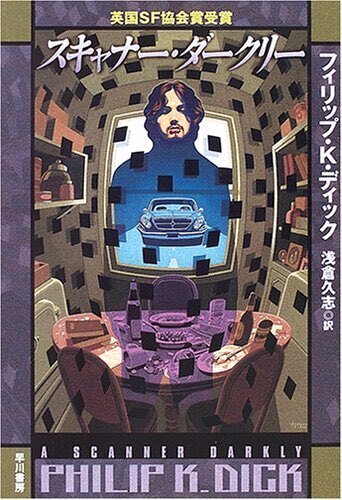
そんなこともあって、私は『暗闇のスキャナー』の映画化作品である『スキャナー・ダークリー』を長らく放置してきたのだし、あとは主演がキアヌ・リーヴスだという点でも、敬遠していたようにも思う。
私にとってのキアヌ・リーヴスは、まずなんといって『マトリックス』(ウォシャウスキー兄弟の監督作品)のキアヌ・リーヴスであり、「SFアクション作品が多い、イケメン俳優」という印象が強かったからだろう。だから、彼が「ディック映画には不似合い」に感じられていたのだ。要は「スター映画」になっているのでないかという印象が、どこかにあったのだ。
無論、この映画は、豪華な俳優陣を使って撮影しておきながら、それをわざわざ、もうひと手間(大変な手間を)かけて「アニメーション化」した作品なのだから、普通の意味での「スター映画」などではない。つまり「スターを見せるための映画」ではない、ということだ。
だが、「印象」というものは如何ともしがたいもので、これらの「マイナス印象」があって、私は『スキャナー・ダークリー』を、これまで「敬遠」してきたのである。
しかし、それでも今回『スキャナー・ダークリー』を観たのは、これまで気になっていながらも観ていなかったディック原作映画を、ひととおり観てしまったからだ。
「それなら、もう観なけりゃいい」という話ではあるのだが、「(アニメーション化という手法を用いた点で)少しだけ気になっていた」から「最後に、これも観ておこう」ということになったのである。
ちなみに、ここでも「アニメーション化」という言葉を便宜的に使っているが、これは本来の意味での「アニメーション化」ではない。
「アニメーション」とは「動かす=命を吹き込む」という意味だから、「アニメーション化」と言うのなら「本来動かないものを動かす」ものでなくてはならない。
ところが本作の場合は、普通に「実写映画」として撮影したものをなぞって「動くピクチャー化」したものなので、本来の意味での「アニメーション化」ではないのである。

この作品で採用された「ロトスコープ」という手法は、実際には、さほど目新しい手法ではない。
アニメーション作品を作るのに、実写映像の「動き」を「下敷き」にするという手法は、ディズニーの初期作品から存在していたものなのだ。
だが、そのようにして作られた「アニメーション作品」と本作との違いは、「アニメーション作品」においては「絵(ピクシャー)としてのキャラクター」を動かすのが目的であり、そのための手法として「実写撮影した映像の動き」をも取り入れたのだが、本作『スキャナー・ダークリー』の場合は、あくまでも「実写撮影したもの」に加える「映像効果」として「ピクチャー化」という手法が採用されている、という点である。要は「どちらが主で、どちらが従か」ということだ。
だが、それにしても、この「ロトスコープ」というのは、予想した以上に「アナクロ」な手法であったことを知らされて、驚いた。
ハリウッドのことだから、実写映像を「ピクチャー化」する特別なソフトでも開発して、それで撮影したとか、撮影後に加工したのではないかと思っていたのだが、なんと実写作品として撮ったものを、事後的に「手作業でなぞって」ピクチャー化していたのである。

つまり、パソコンで一発変換ということではなく、1秒24コマ全部ということではないだろうが、1秒8コマくらいを全部、手作業でピクチャー化したのだから、この作業だけで1年半近くを要したというのも当然で、よくもまあ、こんな面倒な映画を作ったものだと、ほとほと感心させられた。
また、そんなものに協力を惜しまなかった俳優陣にも、頭の下がる思いであった。
彼らの幾人かは、作品が「アニメーション化される」と聞いていたから、わざと大げさ目に演じたというのだから、自分たちの微妙な演技を「そのまま映さない」映画に、とても理解があり、きわめて協力的だったということなのである。
それに「実写映像をなぞる」と言っても、これは決して「単純作業」などではない。
絵を描く人ならわかるだろうが、実写映像をなぞって「テレビアニメのような二次元の絵」にする場合、どこに「輪郭線」を引くかを決めるのは、決して容易なことではないからだ。
三次元の実物には、そもそも「輪郭線」など存在しない。だから、「実写映像」にも輪郭線は無く、物体の陰影と、その動きの変化の中で、見る者は、その形態を認識しているからである。


例えば、人の顔を真正面から捉えた場合、「鼻の輪郭線」というのは、基本的に存在しない。
ところが、その顔が徐々に横を向いていくと、「鼻の線(稜線)」というのが「陰影」の結果として、どこかで出てくるのだが、その「鼻の線」に、二次元作品のように「鼻の輪郭線」を入れるとしたら、どの段階でその「黒い描線」を描き入れるべきなのか?
これは通常だと、「描き手」である「作家」に任されているのだが、しかしだからこそ、二次元のマンガやアニメでは、鼻の描き方(影の入れ方、輪郭線の入れ方)が様々となり、そこが作家の個性にもなる。
だが、本作『スキャナー・ダークリー』の場合は、アニメーター個々の「個性」を出すわけにはいかない。
あくまでも、実写の俳優たちが「アニメーション化されたかのように動く」のでなければならないのだから、「3次元を2次元に落とし込む」ための「輪郭線の選び方」「本来、グラデュエーションである明るさを、段階的に分割するための、境界の確定判断」など、あらかじめしっかり決めておいて、意思統一を図らないと、せっかくの手間も、十分な効果が得られないことになってしまうのである。
で、その結果がどうであったかというと「試みとしては面白いし、その意図と努力は買うが、意図したほどの効果は得られていないだろう」というのが、私の評価だということになる。
たぶん、この作品は、ふつうに実写映画として作ったからといって、「ロトスコープ」を使ったこの作品に、劣る作品にはならなかったのではないだろうか。
○ ○ ○
さて、ここからは、本作の「内容」についてだ。
『「今から7年後」の近未来、〈物質D〉とよばれる強力な麻薬の蔓延が社会問題化したアメリカ、アナハイム。当局が対策に苦慮する一方、ニューパス社による中毒者の矯正が成果を上げていたが、同社には麻薬生産への関与も噂されていた。
潜入捜査官フレッド、本名ボブ・アークター(キアヌ・リーブス)は、情報を掴むため密売人と目される麻薬常習者たちと共同生活を営んでいたが、同居人の一人バリス(ロバート・ダウニー・Jr)の密告により、互いの素顔を知らない上官から「密売人ボブ」つまり自分自身の監視を命じられる。
潜入先で自らも〈D〉に溺れていくフレッド=ボブ・アークターは、やがてその副作用に侵され自己を見失う。』
(WIKIpedia「スキャナー・ダークリー」)
このように、本作は、「筋(ストーリー)」としては「捜査もの」ということになるし、ディックらしいところは「麻薬捜査官が、麻薬密売容疑者でもある自分自身を監視する」といった「メタフィクション」的に倒錯した構造にある点であろう。「私が私を監視する」うちに「本当の私が誰なのかがわからなくなる」という、いかにもディックらしい作品だ。
だが、DVDに付録していた「監督をはじめとしたスタッフやキャストなどによるコメンタリー」によると、この作品の原作である『暗闇のスキャナー』は、きわめて「自伝的」な作品だという。
ただし、本書執筆当時(197O年半ば)、SF作家としては人気作家でも、SF小説自体が「文学」とは認められておらず、低俗読み物と見られていたために、人気SF作家フィリップ・K・ディックであっても、「自伝的な作品」つまり「SF的に不思議な現象も起こらなければ、事件らしい事件も起こらない」ような小説は、書かせてもらえなかった。

そこで、本作は、やむなく「SF的な粉飾を施すことで、書きたいこと(自伝的な物語)を書いた作品」になった、というのである。
つまり、「主人公が捜査官」という設定や「自分が誰だかわからなくなる」といったところは「SF作品にするための粉飾部分」であると言っても良いだろう。では、「自伝的な部分」とは、どういうところか?
それは、主人公が、妻や子供(娘二人)を持ちながらも「当たり前の幸福な生活に飽き足らずに離婚し、仲間とともにドラックにおぼれた共同生活を営む」といった部分である。
アメリカにおける、1950年代以降(つまり戦後の)「ドラッグ・カルチャー」というと、次のように大別できるそうだ(ディック死後の、90年代以降は省いた)。
ジャズ、ビート文化(50年代)→大麻、阿片類
サイケデリック文化(60年代)→LSD などの幻覚剤
ヤッピー文化(70-80 年代)→コカイン
要は、世界大戦の惨禍を体験し、さらにそれにも懲りない祖国アメリカによる「ベトナム戦争」を体験した世代が、そうした悲惨な「現実」を超え出ようと、ドラッグに助けを求めたものであり、それはおのずと「反体制的」なものにならざるをえなかった、ということだ。
上のムーブメントの中で、ドラッグ・カルチャーとして最も広範な広がりを見せたのは、たぶん60年代の「サイケデリック文化」であろう。
「サイケデリック」ブームは、『1966年ごろにヒッピーを中心としてアメリカ西海岸に始まり、1967年にムーブメントのピークを迎えた(「サマー・オブ・ラブ」)。そのスタイルはアメリカ全土、イギリスやそのほかの先進国を中心として、世界の多くの国を席巻したが徐々に縮小し、1970年代半ばに衰退期に入った。』ものであり、ヒッピー文化の中心テーマである「愛」「平和」「自由」、あるいは、現実の「人間的制約」を超えるための「意識の拡張」といった「スピリチュアル(霊性)」指向を、補助的に促す道具としてのドラッグが、若者を中心に広く受け入れられていたのである。

そして、1928年に生まれ1982年に亡くなったフィリップ・K・ディックには、戦時体験があり、こうしたドラッグ・カルチャーの真っ只中で生きてきたため、仲間とともに、自身もドラッグをやっていた、ということである。
とは言え、私自身はこれまで、フィリップ・K・ディックの「自伝的」な部分には、ほとんど興味がなかった。
というのも、私にとって大切なのは、あくまでも「作品」であり、その意味で、作者の「自伝的な情報」というものは、下手に知ってしまうと、そちらに引っ張られてしまう、「偏見」や「思い込み」のタネになる恐れがある、と考えていたからだ。
例えば、ディック特有の「幻想的なヴィジョン」について「ディックはドラッグをやっていたため、こういう描写が可能だったのだ」というような、「安直な説明」である。

無論、そうした側面があったことは否定できないが、しかし、ドラッグをやっておれば、誰でも「ああいうヴィジョンを持てる」のか、それを「個性的に表現できるのか」といえば、無論そんなことはあり得ない。
とするなら、読者であり評論家が為すべきことは、ドラッグの影響や助けがあったにしろ、ディックには、どうして「ああいうヴィジョンの表現」が可能だったのか、ということを読み解くことだろう。
したがって、フィリップ・K・ディックという「人」の「研究者」ではない私は、積極的に「伝記的事実」を知ろうとは思わなかったのである。
しかしながら、本作の場合は、原作小説であれ、この映画であれ、私にとっては、それそのものとしては「ピンと来ない作品」でしかなかった。
だから、それを単純に「失敗作だった」と切り捨てることは容易なのだが、それはそれであまりにも安直な納得の仕方でしかないので、私はいつものように「ではなぜ、私にはこの作品がピンと来なかったのか?」という「謎」について、周辺情報を含めての、「解読」を試みることにしたのである。
例えば、直接的な「自伝的情報」ではないのだが、フィリップ・K・ディックという作家が誕生する「時代背景」として、『ジャズ、ビート文化(50年代)→大麻、阿片類』の時代には、「ビート・ジェネレーション」の作家である、ジャック・ケルアックや、アレン・ギンズバーグ、そしてウィリアム・S・バロウズといった、
『多くの若者達、特にヒッピーから熱狂的な支持を受け、やがて世界中で広く知られるようになった。彼らは、ボヘミアン快楽主義、非同調主義(個人主義)、自発的創造性を追求・開拓した。』
という作家たちがいた、という無視できない事実がある。
例えば、アレン・ギンズバーグとウィリアム・ S・バロウズには、共著『麻薬書簡』があるというのは、ディックを考える上でも、知っていて損はない事実だろう。
私は昔、「サンリオSF文庫」との関係でバロウズにも興味を持って、その何冊かを読み、多くを積ん読の山に埋もれさせてしまったが、その中には、この『麻薬書簡』もあった(ちなみに、装丁は村上芳正であった)。
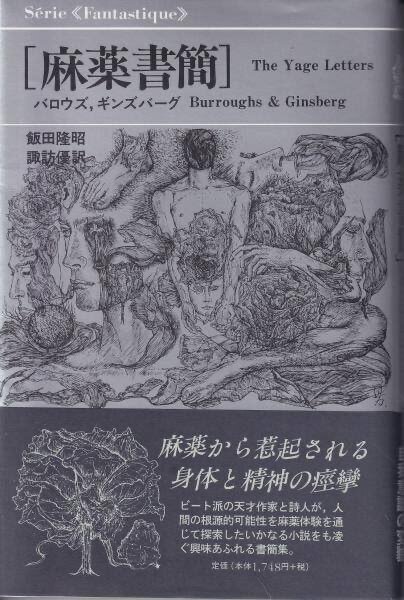
ともあれ、ディックもまた、こうした作家たちの影響を受けて、「文学」を志した若者の一人だったのではないか、ということだ。
だから、もともと「純文学指向」であったディックが意識していた「文学」とは、彼らのような「文学」に近いものだったと推察することも可能だろう。
だが、SF作家としてデビューし、SF作家としての人気は得たものの、所詮は「非文学作家」のレッテルを貼られてしまったディックには、「SF」を抜きにしての小説が求められなかったというのは、前述のとおりである。
だからこそ、ディックは、少なくとも『暗闇のスキャナー』においては、「自伝的な事実」を中心とした作品を書こうとしたのではないだろうか。
そしてそれは、『スキャナー・ダークリー』の制作にアドバイザー的に関わった、ディックの実の娘たちが証言している事実でもあったのである。
『スキャナー・ダークリー』にも描かれているとおり、ディックは、妻と二人の娘を持つ「幸福な家庭」を一度は築いた。しかし彼は、そういう「当たり前の幸福」に飽きたらず、離婚して妻子を捨て、まずは一人暮らしを始め、やがてそこに、同じような「はぐれ者」の仲間が集まってきて、共同生活を営むことになる。
映画では、このあたりは「過去」の回想的(想起的幻覚)シーンとして簡単に触れられるだけだが、主人公であるボブ・アークター(キアヌ・リーブス)が、幸福な家庭を持ちながら、ある日、開いていた戸棚の扉にうっかり頭を打ちつけたのをきっかけにして、もうこんな生活は我慢ならないと、切れてしまうシーンが描かれている。
そういう「過去」があって、「今」は同性の友人たちと同居するようになったというわけだが、彼らはいずれも、程度の違いはあれ「薬物中毒」者だ。つまり、ディックが「幸福な家庭」を捨ててまで求めたものとは、「当たり前の日常」を超えたところにあるものであり、そこにこそ「真実」がある、と感じていたということなのではないだろうか。
言い換えれば、ディックにとっての「幸福な家庭」「当たり前の日常」とは、「制度的で欺瞞的な幻想」に過ぎないと感じられ、それに妥協して「自分を偽りながら生きていく」ことは「もうできない」と、そう思ったのではないだろうか。

したがって、「幸福な家庭」を捨ててまで、ディックが求めたのは、「現世の制度的常識」には囚われない生活であり、言うなれば「遅れてきたヒッピー」的な生活だったのだと言えるだろう。
しかし、この映画のエンドロールの最後の「献辞」にもあるとおり、こうした薬物依存の生活の果てに、ディックは多くの大切な友人を失った。
この原作小説は、薬物依存のせいで死んでいった仲間たちの「思い出」に捧げられた、悔恨をこめた追悼作品だったのである。

原作に、このような「献辞」があったことなど、すっかり忘れていた私なのだが、この原作小説は、その意味ではディックにとって、特別な意味を持つ「自伝的な作品」であったのだ。
無論、ディックは、映画の主人公ボブ・アークターのような「麻薬取締局の潜入捜査官」などではなかった。ディックは、仲間たちとの生活に「潜入」していたわけではなく、当たり前に、その当事者だった。
だから、この「麻薬取締局の潜入捜査官」という設定は、あくまでも「娯楽小説」化するために付け加えられた部分ではあるのだが、しかし、それもまた、まったくの「作り事」というわけではなく、ディック自身も長らく大真面目に「ドラッグをやっている自分たちは、当局から監視されている」という「被害妄想」を持っていたのであり、これはそんな「事実」を基にした「設定」なのだ。
こうした「被害妄想」は、そもそも彼の作品が「反当局的」なものであったからであり、彼が人気作家であったからでもあろう。「だから、私に目をつけたのだ」と、そう考えたのであり、要は、現実としても、ディックは「左寄りの、要注意作家」ではあったのであろう。
したがって、ディックの「確信」は、やや度を越したものではあれ、まるっきりの「被害妄想」だと決めつけることもできない種類のものだったのである。
ともあれ、ディックには、薬物の影響による「被監視妄想」があったのだが、それをそのまま、この作品に反映させたのであり、その意味では、それはきわめて「客観的」な態度であったと言えるだろう。
だがその一方、ディック自身、自分の「現実認識」に、絶対の自信があったわけではない。
むしろその作風からも分かるとおり、ディックは「私の見ているものは、はたして現実(真実)なのか?」という自己懐疑の人であり、その意味で「私が私を監視する」というのは、彼には「当たり前の意識」であったのだから、この作品における「設定」は、いかにもディックらしい「自己批評性」の表れだった、とも言えるのである。
そして、そうした意味では、フィリップ・K・ディックという人は、「当たり前の健康人」よりも、むしろ、ずっと健康的に「自己相対化(客観視)」のできる人だったと言えるのではないだろうか。それで、せっかくの「幸福な家庭」を破壊し、妻子を犠牲にしたとしてもである。
そんなわけで、「自伝的な部分」に重きをおいた本作『スキャナー・ダークリー』は、ディック映画の中でも、おのずと「地味」な作品になっている。
SF的な小道具は出てくるものの、アクションシーンなどはないし、作中で描かれる「幻想」は、あくまでも「薬物」によるものということになっている。

この映画版を観てみると、終盤に一種の「どんでん返し」があって、それはなかなかよく出来ており、「ドラッグによって死んでいった友人たちに贈る作品」としての「悲哀」を、うまく強調するものとなっている。
ただ、この映画のラストを見て「こんなオチだったかな? まったく記憶に無いな」と私が思ったのは間違いではなかったようで、この「最後の一捻り」は、映画オリジナルとして「付け加えられたもの」なのだそうだ。
だが、前記のとおり、この「補足」部分は、この映画をまとまりのある作品にするための効果を上げており、決して原作を台無しにするようなものにはなっていなかったと、私は評価したい。
そもそも、本作の監督であるリチャード・リンクレイターは、自身、熱心なディックファンであったからこそ、このディック作品(小説)の中でも「地味」な部類に属する作品をあえて選び、その「自伝的」な部分、つまり「人間的な部分」を大切にして映画化しようと考えて、遺族にも積極的に働きかけたようである。「自分ほど、ディックの作品を忠実に映画化できる者は他にいない」という自負を持って、それをアピールし、事実そのような作品を作ったのだ。
こうした監督の「ディックオタク」的な情熱があったればこそ、ディックの遺族もこの作品に対して協力的でもあれば、その出来にも納得していたし、有名俳優たちも、自分たちの演技をわざわざ「二次元化」させることにも異を唱えなかったのであろう。
「すべてはディックのために」ということで、意思統一ができていたから、無理も無茶も通ったのである。
そんなわけで、この映画の見所は、「私が私(の心の暗闇)を監視する」といったテーマ的部分ももちろんあるけれども、やはり一番大切なのは、ディックが描きたかった「仲間たちとの、楽しかった思い出」だろう。
この映画では、「ヤク中」同居人たちの間で交わされる「クレージーな会話」が、数多く描かれる。
「コメンタリー」の中でも語られているとおり、こうした部分は「話の筋には、ほとんど関係ない」という理由で、しばしば「カット」の対象になったが、監督は踏ん張って、可能なかぎり、そうした「狂ったコント」めいたシーンの数々を残したのだそうだ。

だが、そうした「内部事情」を知らない「第三者」である私にとっては、それこそ、そうしたシーンは、面白くもおかしくもなかった(ロバート・ダウニー・Jrの演技力を見直したりはしたが)。

これまでのディック関連のレビューでも何度も書いているとおりで、私がディック作品に期待するのは「現実と幻想の境界が溶解していくような、その独特の世界観」であって、「リアルなヤク中のやりとり」などには、まったく興味がなかったからだ。
たしかに、それらは「リアル」であり、「あるある」としての面白さはあったと思う。
例えば、冒頭の「全身に虫が這っている」妄想は、薬物中毒における禁断症状としては、ごくオーソドックスなもので、元警察官である私には、それが「妄想」だとすぐにわかったし、その意味で、特に面白くもおかしくもなかった。

また、薬物中毒者によく見られる「チック症」だとか、論理の飛躍した妄想的な会話だとかいったものも、多少の映画的な誇張があるとは言え、きわめてリアルなものと感じられて、それを「コント」的に楽しむことはできなかった。それは、「リアル」以上のものではない、と感じられたからであろう。
こうしたことは、たぶん原作と映画とを問わず、私に感じられたことだったのではないか。
つまり、ディックが描きたかった「リアル」は、私にとっては「当たり前のリアル」に過ぎて、ディックという小説家に期待したものではなかった、ということだ。
その意味で、本作『スキャナー・ダークリー』は、「ディックが描きたかったことを、可能なかぎり忠実に映像化しようとした作品」としては、高く高く評価して良い作品だと思う。

しかし、それがそのまま「SF作家フィリップ・K・ディック原作の映画」を期待した者を満足させるさせる映画には、なっていなかった、とも言えるのではないだろうか。
私を含めて、多くのディックファンは、「SF作家フィリップ・K・ディック」のファンなのであって、必ずしも、フィリップ・K・ディックという「リアルな人間」そのものの「ファン」だというわけではないのである。
たしかに本作は、監督のリチャード・リンクレイターや、ディックの家族のように、「作品を超えて、作者その人」にこそ愛着を持っている「コアなファン」には、きわめて完成度が高く、良心的な作品だったと言えるだろう。
だが、それと同時にこの作品は、やはり多くの人にとっては「個人的な思い入れ」に過ぎる作品になっていたというのも、否定できない事実なのではないだろうか。
私は、こうした「思い入れに満ちた作品」が作られたことを、とても素晴らしいことだと思う。
しかし、だからと言って、この作品が、「映画作品」として十全に成功していたとまでは言えず、ある意味では「マスターベーションに徹した、潔い作品」とでも呼べるようなものにもなっていたのではないかと、そう評価するのである。
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
