
ロバート・A・ハインライン 『異星の客』 : 「ひとの子」 という言葉
書評:ロバート・A・ハインライン『異星の客』(早川SF文庫)
最近では耳にしなくなった表現だが、かつては「あいつは宇宙人だからな」とか「宇宙人のような人」といった形容表現があった。
要は「変わった人」「何を考えているのかわからない人」を指している。
しかし、だからと言って、「腹に一物ある」というようなことではない。つまり、何かを意識的に隠しているから「何を考えているのかわからない」のではなく、そもそも「モノの考え方が変わっている」から、他人には、その人の「思考内容が推し量れない」というような場合に使う表現だ。
まったく違った身体構造や文化を持つがゆえに、その思考方式や思考パターンが人類とはまったく異なっている「宇宙人(異星人)」みたいなものだ、という意味合いで、「宇宙人のようだ」という形容がなされたのである。

本作の主人公である、ヴァレンタイン・マイケル・スミス(※ マイク)が、まさにそのような人物だった。
しかし、彼の場合は、文字どおり、火星で火星人の中で育ったために、思考方式が火星人のものになってしまい、そのため地球に戻ってくると、およそ何もかもが奇妙で理解不能なもの、あるいは恐ろしいものとしか感じられず、地球の生活環境に慣れるためには、大変な苦労を強いられた。
もちろん、彼と接した当たり前の地球人たちも、当初は、マイクの奇妙な言動に驚いたのだが、彼の並外れた知的能力を知って、彼に地球で生きるすべを授けていったのである。
『宇宙船ヴイクトリア号で帰った“火星からきた男”は、第一次火星探検船で火星で生まれ、ただひとり生き残った地球人だった。地球連邦の法律によると、火星は彼のものである。この宇宙の孤児をめぐって政治の波が押しよせる。しかし、“火星からきた男”には、地球人とは違う思考があり、さらに地球人にはない力があった。“火星からきた男”は地球をゆるがせてゆく』
(本書扉ページ「内容紹介」より)
あらすじとしては、次のようなものである。
マイクを病院に幽閉して利用しようとする政治家たちから、看護婦ジルが彼を脱走させ、変わり者の金持ちで弁護士でもある老学者作家のジュバル・ハーショーのもとへ助けを求めて逃げ込む。
ハーショーは、マイクの子供のように無垢な人柄に興味を持って、彼をなんとか地球で生きていけるように教育してやりたいと思い、彼らを匿うことにする。
自由人ハーショーの屋敷には、彼の仕事をサポートする3人の美女と、男性の雇人も2人いるが、彼らは雇主であるハーショーの好みと方針に応じた、それぞれに個性的な自由人だった。
当初は、病院から逃げ出したマイクを取り戻そうと、武装部隊をハーショーの屋敷に送り込んできた政治家どもだったが、その時、マイクは、彼らを物理的に消してしまう(異空間へ放逐してしまう)という恐るべき超能力を発揮する。
それで助かりはしたものの、この能力が世間に知られてしまえば、マイクがこの地球でまともに生きていくことは不可能だと考えたハーショーは、マイクに「命の危険を感じた時以外は、決してその能力を使ってはいけない」と厳命。一方、マイクが「唯一の火星の所有権者」であるのを盾にとって、実質的に世界のトップである自由世界連邦事務総長で、アメリカ合衆国大統領のジョセフ・エジャートン・ダグラスとの政治的交渉に持ち込み、彼をマイクの後見人につけることに成功する。ダグラス自身は、マイクを個人的な野望のために政治利用するような、ケチな政治家ではなかったからで、マイクへの政治家たちの野望は、あくまでもダグラスの知らないところで行われていたものだったのである。
マイクは、ハーショーの家にある本をものすごいスピードで読破し、その内容をすべて暗記し、自分に理解・認識(grok)できることをどんどんと増やして、ハーショーの屋敷の愉快な仲間たちの下で、急激にたくましい青年へと成長してゆく。
また、そうした中で、彼は「宗教」というものに興味を持つ。それが、自分が火星で感じていた真理に通じるものではないかと感じたからだ。
そして、ついに彼は、父と仰ぐハーショーの許しを得、ジルと共に屋敷から外の世界へと出ていくのである。
彼は、ジルと共に、身元がバレないように、サーカスの手品師などをしながら、世の中についての経験を深めていく。また、興味があった「宗教宗派」にも接近してみるが、現実に接してみたそれは、書物から得た知識で感じられたようなものではないとわかり、マイクは失望した。ハーショーの言っていたとおり、現実の「宗教」は、ほとんどが、その理想とはほど遠いものだったのである。
そこで、マイクは、みずから「宗教団体」を起こし、「宗教」を偽装することで、少しでも「火星人的な、優れて自由な認識」を、地球人たちに広めようと考えた。そのことで、地球人たちを「無意味な囚われ(自縄自縛)」から解放して、幸せににすることができると考えたのだ。
こうして、マイクを教祖とする教団は、徐々に大きくなっていく。
しかし、彼の「宗教」は、「人間解放」を促すものであったために、既成の価値観に縛られた人たちや、既成の宗教教団からは「淫祠邪教」の謗りを受け、憎しみの対象になってしまう。

もちろん、マイクには、超能力があるから、物理的な暴力を恐れる必要は一切ない。逃げようと思えば、テレポーテーションを使って逃げることができるし、他人を操るようなことも容易にできるだろう。だが、マイクは、そんなことがしたかったのではない。教団を巨大化させることが目的ではなく、一人でも多くの人を、無意味な自縛から解放して、幸せにすることが目的だったので、彼は、どうすればそれが正しいやり方でできるのかを、悩まざるを得なくなったのである。
一一このあとは結末だけなので、ここで止めておくことにしよう。
本書は、ハインラインの作品の中でも大部に属する、後期の作品だ。文庫本にして800ページ弱にもなるから、3分冊の『愛に時間を』などに比べればまだ短いものの、一巻本としてはかなり分厚く、他の一巻本に比べると、有名なわりには、あまり読まれていないようだ。
例えば、現時点での、Amazonのカスタマー「評価」件数を見ると、
『夏への扉』 2,296
『月は無慈悲な夜の女王』 681
『宇宙の戦士』 197
『異星の客』 51
『愛に時間を (1)』 28
『獣の数字(1)』 11
『ヨブ』 6
といった具合で、SFファン以外にも読まれている『夏への扉』は別格としても、『月は無慈悲な夜の女王』や『宇宙の戦士』といった一巻本の傑作には、大きく溝を開けられている。

もちろん、後期の大長編や、明らかに宗教色の強く出た作品に比べれば、まだ読まれている方ではあるものの、原書が刊行された1960年代のアメリカにあって、「ヒッピーの聖典」とまで言われて一大ベストセラーになり、多く人に影響を与えた異色の傑作であるわりには、今の日本では読まれていないと言っても、決して過言ではないであろう。
私が購入した「新装版」(中身はいっしょの、第44刷)の帯の表側には、
『ビル・ゲイツが選んだオールタイムベスト』
とあるし、帯の背面には、次のようにある。
『必読書として選ばれた巨匠ハインラインの超大作
作品中に登場する「grok(認識)」という造語が、その後オックスフォード英語辞典に採用されるなど、本誌は時代に多大な影響力を及ぼした。宗教、政治、性、思想と多くのテーマを扱いで、風刺とユーモアが無数にちりばめられた作品として、多くの有識者に支持され、英国紙「ガーディアン」で必読小説1000冊のうちの1作にも選ばれた。ヒューゴー賞受賞作。』
なぜ、ビル・ゲイツが本作を「オールタイムベスト」に選んだのかと言えば、それは無論、彼もかつてはヒッピー的な若者だったのであり、本書の示した「自由」に憧れ、その影響を強く受けた人だったからであろう。
『英国紙「ガーディアン」で必読小説1000冊のうちの1作にも選ばれた』のも、現在の知識層や社会的なリーダーたちの少なくない部分が、かつては同じムーブメントの中にあって、本書の影響を、何らかのかたちで受けた人たちだったからだろうと推測される。
さて、私が本書に興味を持った理由はというと、本書がヒッピーたちに読まれた、1960年代のアメリカを代表する作品である、というのがひとつ。
もうひとつは、次のような事情だ。
私の若い頃、当時大ヒットしていたテレビアニメ『機動戦士ガンダム』に登場する「(ロボットではなく、兵器としての)モビルスーツ」というアイデアに大きな影響を与えた作品として、ハインラインの『宇宙の戦士』(のパワードスーツ)が紹介され、アニメ業界にも近い位置にいた、「スタジオぬえ」所属(当時)のSF作家の高千穂遙が『宇宙の戦士』を絶賛していたために、私も期待して同作を読んでみた。

ところが、そこで描かれているのは「愛国戦士に育っていく、兵隊学校の若者たちの姿」であったため、私は「ハインラインは、くだらない保守思想の持ち主」だと、いっぺんに嫌いになったしまった。
しかし、つい最近読んだ、フィリップ・K・ディックのエッセイで、ハインラインがそんなに単純な(一面的な)人ではないということが、敬意を込めて語られていた。明らかに「左」寄りであるディックがここまで言うからには、1冊読んだだけで、ハインラインを単縦な「タカ派保守」と決めつけるわけにはいかないと、そう考え直したという次第である。
それに「タカ派保守作家」が書いた作品が、それとは真逆なヒッピーに支持されるはずもないから、『異星の客』だけは、(分厚いけれども)読んでおかなければならない作品だと考えたのだ。
○ ○ ○
で、『異星の客』を読んでみてどうだったかというと、たしかにハインラインが「頭の悪い保守思想作家」などではない、というのがよくわかった。
そう単純な人ではないというのがわかると同時に、本作の登場人物であるジュバル・ハーショーと同様、良い人ではあるのだが、なかなか屈折の多い人だとも感じられた。
他のAmazonカスタマーレビューなどをみてみると、どうやら後期のハインラインは、作中に「自身を投影した人物」を登場させ、その人物にあれこれ語らせるというパターンがよく見られたようで、本作もまさにそのパターンの作品であった。
本作がこれだけ分厚い本なったのも、帯の紹介文にもあるとおり『宗教、政治、性、思想と多くのテーマを扱いで、風刺とユーモアが無数にちりばめられた作品』だからで、筋自体は、先に私の紹介したとおりで、さほど複雑なものではなく、それだけなら、こんな分厚くはならなかったはずなのである。
つまり、一言でいってしまえば、本作は「人間というものに、いささか失望したハインラインによる、人類文化についての思弁的批評小説」なのだと言えるだろう。
だから、思弁的な人には面白い小説だが、SFに「科学的なアイデア」や「派手な活劇」を求める人には、まったく合わない作品かも知れない。
さらに言えば、本書における「人類論」の中心的話題となるのが、やはり「宗教」なのである。したがって、そこで読者を選ぶ部分もあるだろう。
ハインラインは、ハーショーの口を借りて、本書の中で「宗教の現実」をクソミソに貶している。
しかし、そんなハーショーが、マイクの「宗教もどき」に理解を示すのは、マイクが目指すものは「宗教」ではなく、「新しい道理」だからである。
しかしまた、この「新しい道理」が可能になるのは、地球人にはない「火星人的な思弁(世界認識)」を、肉体的には地球人であるマイクが持っていたからである。
「火星人的な思弁(世界認識)」が加わって、初めて地球人類は、今の人類の限界を超えて「解放」され得るのである。
つまり、ハインラインは「現実の宗教」には深く失望しており、それに対して批判的なのだが、しかしそれでも、人間を「超越した何か」に対する期待は失っていない。
その「超越的な何か」を、本作の中では「火星人的な思弁(世界認識)」というかたちで描いたのだといえよう。
例えば、ハインラインは本作の中で、「宗教」を批判して、ハーショーに次のように語らせている。
『(略)もしマイクが、乱れたこの惑星をもっとうまくやっていく道を見せてくれるのなら、彼の性生活など、なんの弁明もいらんよ。天才というものは、程度の低い意見をばかにするのは当然だし、いつもその種族の性的習慣なんかには無関心なものだ。彼らは彼らなりのルールをつくるんだ。マイクは天才だ。だから彼は、世間の口なんか無視して、自分のしたいようにやるのさ。
しかし、神学的見かたからすると、マイクの性行動はサンタ・クローズと同じくらい正統的なものだよ。彼は すべて生あるものは、総対的に神であると説いている。つまり、マイクとその弟子たちだけが、この星での自覚をもった神だということになるんだ。つまり、彼には神つくりのあらゆるルールによって、神さまの組合員章があたえられたようなものだ。このルールというのは、いつもその神たちのセックスの自由を、それぞれ自身の判断でしか制約されないものなんだ。
証拠が欲しいかね? レダと白鳥はどうだ? ユアロパと牝牛は? オリシスとアイシスとホルスは? 北欧神話の信じられないような近親相姦は? 東洋の宗教までならべるつもりはない。彼らの神々は、ミンク培養業者でも我慢できないようなことをやっているんだ(※ ミンクは雑婚で知られる)。しかし、西洋宗教が(※ ママ。「西洋宗教で」か?)いちばんひろく尊敬されている三位一体の関係を見たまえ。あの宗教の戒律を唯一神とみなされるもの(※ と)の相関関係と妥協させるただひとつの方法として、神の交配の法則は、人間の法則とちがうものと断定することによっているんだ。ただ、たいていの人はそれについて考えたこともない。彼らはそれを〝神聖にして侵すべからず〟と書いて封印してしまっているんだ。』(P651〜652)
この部分を読めば、本書がヒッピーたちの「フリーセックス」の思想に大きな影響を与えたというのは、想像に難くない。従来の「性倫理(性道徳)」の中には、まったく無意味で非科学的な「単なる慣習」も多く混じっていて、そう大袈裟に騒ぐことではないにも関わらず、そこに「宗教」が絡むことで、単なる「小数例外」が、「神への反逆」扱いにされることになってしまったのである。
例えば、いま私が読んでいる『柄谷行人全発言 対話篇』の中に収録された、柄谷行人と文芸評論家である秋山駿との、夏目漱石に関する対談でも、漱石は「近代化」を受け入れるひとつのかたちとして、西欧的な「恋愛」を描いてみせただが、その中では、日本的な「恋」というものが抑圧されたのではないか、という指摘がなされていた。

江藤淳などが指摘したところだろうが、夏目漱石の小説には「兄嫁への秘められた恋心」が、抑圧されたかたちで反映されていると言われるのだけれども、そうしたものは、漱石が自身に抑圧した、それまでの「大衆小説」的な世界においては、それほど珍しいものでもなければ、抑圧しなければならないものでもない、わりと「よくある話」であり、実際、しばしば描かれてもきたものであった、という。
つまり、「西欧近代」の象徴である「自由恋愛」の中にも、「近親相姦」などを「悪徳」視し、「禁忌」とする「キリスト教論理」が生き残っており、それが漱石の小説では、ある種の「性的な抑圧」として表現されていたのではないか、という議論だ。
つまり、こうした「キリスト教倫理」に縛られない私たち日本人は、元来「兄嫁」への恋や、いっそ「近親相姦」についてさえ、西欧キリスト教圏のような「悪徳」視は持っていなかった。
それは、あくまでも「例外的なもの」ではあれ、「例外的なもの」が「悪」だという感覚ではなかったというのは、例えば、日本における「男色」や「衆道」といった、キリスト教の禁ずる「同性愛」についても言えることだったのであろう。
しかし、上のハーショーの言葉で、さらに注目すべきは、「キリスト教」における「三位一体」の秘儀を、「近親相姦」や「雑婚」的なものと比較して、批判している点である。
「キリスト教が、唯一神の崇める宗教だというのであれば、神には、父なる神と、子なる神イエス・キリストと、聖霊の三者がいるというのは、明らかに論理的な矛盾であり、その明らかな矛盾を、三つの位階(ペルソナ=仮面)を持つ一者だ、などというのは、厚かましい誤魔化しに過ぎない。彼らはそうした厚顔な「説明責任放棄」を、〝神聖にして侵すべからず〟と書いて、例外扱いにし、真理の追求を封印してしまっているんだ」という批判である。
そもそも、キリスト教における「三位一体」の教理というのは、「後付けの屁理屈」にすぎない。
だが、それを、全世界の枢機卿が集まる最高会議である「公会議」において「正統教義」であると合議して決めたから、それはもう問答無用に「正しいのだ」し、それに逆らう者は「異端」であり、排除(教会から破門)し、社会的に抹殺する、としてしまった。当時の西欧世界では、教会から破門されるというのとは、社会的に抹殺されるというのと、同じことだったのである。
そんなわけで、ハインラインは、現実の「キリスト教」には、深く失望している。
「三位一体」説を採っているのは、カトリックもプロテスタントも同じであり、それを採用しないのは「異端」であり、キリスト教徒とは認められない。それが、キリスト教の「現実の姿」なのだ。
しかし、だからと言ってハインラインは、キリスト教異端を支持していると言うわけでもない。
彼は、キリスト教に限らず、多くの「宗教」を研究し、その「現実」を確認した上で、どの「宗教」も、現実の場においては五十歩百歩でしかなく、少なくとも、彼が内心で憧れを抱いているような、イエス・キリスト的な「超越的な愛」を、それらの「世俗宗教」は示し得ていないのだ。
だから、ハーショーは「現実の宗教」を撫で切りに批判するその一方で、マイクの「擬似宗教」を支持するし、それに期待するのである。「人間による宗教」はだめでも、「火星人的思考を持つマイク」による「偽宗教」であれば、それが「宗教」ではないからこそ、期待できると考えているのである。
なお、本作のタイトルについて、翻訳者(井上一夫)により、次のような「解説」がなされている。
『 この作品の題名は旧約聖書から採ったもの。
彼男子(おとこのこ)を産みければ、モーセはその名をゲルショム(客)と名づけて言う。
「我異邦(ことくに)客となりおればなり」と。
(出エジプト記第二章22節)』(P781)
「十戒」で知られるモーセは、エジプトで奴隷になっていたイスラエル民族(ユダヤ民族)を率いて、エジプトを脱出し、神が約束した自分たちの地カナンを目指した際の、イスラエルのリーダーである。彼は大変な苦労の末、イスラエルの民をその地まで導きながら、自分自身はそこに入れなかった、ある意味では悲劇の人でもあった(「申命記」)。
つまり、私が思うには、ハインラインは、本作の主人公マイクを、モーセに準えているのではないだろうか。
モーセも、神に守られていたとはいえ、マイクと同様に(海を割って道を作るなんて)奇蹟をなしたリーダーであり、それでいて、彼自身はカナンの地には入れなかった。

あと、ハインラインが、マイクを、愚かな民衆の無理解によって刑死させられたイエス・キリストに重ねているというのも、間違いのないところであろう。
私が、特に注目したのは、マイクが、自身を『ひとの子』と呼んでいる点である。
『 彼(※ マイク)の服が消えた。彼は群衆のまえに、黄金の若さに美だけをまとって立っていた。ジュバル(※ ハーショー)の心臓が痛むような美しさで、大むかしのミケランジェロが、まだ生まれでない世代のために記録に残すため、高い足場の上からおりてくるかもしれないと思ったほどの美しさだった。マイクがおだやかにいう。
「わたしを見よ。私はひとの子だ」』(P761)
もちろん、ここでは、表面的には、マイクが、自分は火星人の化け物なんかじゃなく「地球人の子だ」ということを示しているかのように読める。
だが「私は地球人だ」ではなく、「私はひとの子だ」と言ったのには、次のようなキリスト教的な含みがあったからであろう。
キリスト教では、イエス・キリストを、旧約聖書(ダニエル書)で「人の子」と呼ばれ、具体的な名前は記されていないが、やがて雲に乗ってあらわれる「メシア(救世主)」のことだと考える(解釈する)。新約聖書でイエスが、自分のことを「人の子」だと何度も言っているのが、その証拠だというわけだ。
つまり、イエスは自分が、旧約聖書に予言された「人の子」であり「メシア」なのだと言った、というわけだ。
『新約聖書では、イエスが「人の子」といわれているところが88回も出てきます。「人の子」の第一の意味は、ダニエル書7章13-14節の預言のことを言います。「私がまた、夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と光栄と国が与えられ、諸民、諸国、諸国語の者たちがことごとく、彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。」 この「人の子」というのは、メシヤの称号です。イエスが主権と栄光と国を与えられたお方です。イエスがこのことばを使われたとき、人の子の預言をご自分に当てはめておられたのです。 当時のユダヤ人には、このことばはよく知られていたもので、誰のことを指しているかもよくわかっていたはずです。イエスはご自分こそがメシヤだと宣言されたのです。
「人の子」の二番目の意味は、イエスが本当に、人間であったと言うことです。神は、預言者エゼキエルのことを「人の子」と、93回も呼ばれました。神は、単にエゼキエルを人と呼ばれたのです。.人の子は人です。 イエスは100%完全に神でした。(ヨハネ1章1節)けれども、イエスは100%完全に人間でもありました。(ヨハネ1章14節)第1ヨハネ4章2節は、「人となって来たイエスキリストを告白する霊はみな、神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。」と言っています。もちろん、イエスは神のみ子です。その要素において神なのです。また、イエスは人の子、つまり、その要素において人でもあります。 つまり、「人の子」ということばは、イエスがメシヤであり、本当に人間でもあるということを示しているのです。』
(サイト「Got Questions」より、質問「イエスが人の子だと言うのはどういう意味ですか?」への回答)

ここで、非クリスチャンには紛らわしいところなのだが、キリスト教では、イエス・キリストは「完全な神であり、かつ完全な人間である」とされている。
つまり、イエスは「父と子と聖霊」という「三位一体」の神なのだから、「完全な神」でなければならない。「神の三分の一」であってはならない。「神」は「完全」なのだから「神」なので、イエスも「完全な神」でなければならないのだ。
その一方、イエスは「完全な人間(ひと)」でなければならない。なぜなら、イエスは「神が人間になって、その人間の体で、全人類の罪を引き受け、全人類の身代わりとして死んでいった」というのが、キリスト教における「贖罪論(人類のすべての罪を、イエスが我が命と引き換えに買い取った)」だからで、この場合、イエスは「完全な人間」でなければ、意味がない。
なぜなら「死にもしなければ、苦しむこともない、完全な存在たる神」が「人間のフリをして、苦しんだフリをして、我が身を犠牲にしたフリをして、死んだフリをして、人間の罪を買い取った」と言っても、それは「猿芝居のペテン」でしかない、ということになるからである。
つまり、「父なる神は、子なるイエスに人間の肉体を与えて、地上に派遣した」というのは、「三位一体」の神である以上は、要は「神は、人間への愛のゆえに、自ら人間となって、人間の罪を贖いたもうた」ということになるのである。
したがって、「神」たるイエスは、「完全な神にして完全な人間(神人)」という矛盾した(どっちにも良い顔をした)存在でなければならないのだ。
で、こうしたイエスの二重性(神にして人)は、当然のことながら、マイクの「火星人にして地球人」という二重性を重なってくる。
つまり、マイクは、本作中における「イエス・キリストの似姿」であり、彼がその「天上性」とも呼ぶべき「火星性」を持って、人々を救うために「天空からやってきた」というのは、彼が「神の使者」であり「メシア」であることを示しているのだとも言えるだろう。
だからこそ、マイクは最後に「ひとの子」を名乗ったのであり、あえて、残酷な運命を受け入れたのである。そのことによって、今は愚かな人類が、いずれは救われると信じて。一一というのが、マイクに「私はひとの子だ」と語らせた、ハインラインの意図だったのではないだろうか。
ことほど左様に、ハインラインは「現実の教会」には、ほとほと絶望しており、その意味での批判に呵責はないが、それでも彼の中には「本物の神」への希求が失われていないというのも、本作におけるマイクの描き方などに明らかであろう。
ハインラインが、今のキリスト教会を批判するのは、教会がイエスの教えを正しく実践できずに、世俗化してしまったからなのであろうし、所詮、人間にできることはその程度だという諦めを持っていたからでもあろう。
しかし彼は、彼の「本当の神」への愛のために、現実の教会に対して、腹を立てずにはいられなかったのである。
ちなみに、こうした観点からしても、ハインラインがキリスト教に深く惹かれていたというのは否定できない事実であろう。
それは、本作以降の作品である、『愛に時間を』『獣の数字』『ヨブ』などの作品タイトルにも明らかだ。
私は、これらの作品をまだ読んでいないから、内容的なことについては何も言えないが、タイトルだけからでも、次のようなことが言えよう。
例えば、『愛に時間を』の「愛」とは、もちろんキリスト教の中心概念ではあるのだが、それについて「時間を」と付け加えるのは、「神の愛が実現され実証されるには、まだしばらく時間が欲しい」ということではないか。
これは、『異星の客』においても、その物語のラストでは「救いの実現」を見ないのと同じで、「救いの実現=神の国の到来」には、しばらく時間が必要だという認識を示しているのではないだろうか。
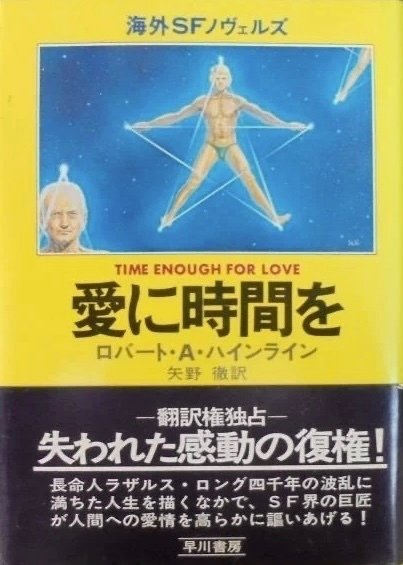
いうのも、イエスの時代では、「神の国は、まもなく来る」とイエスたちには信じられており、「神の国は近い。ゆえに悔い改めよ」と語られていたのである。
ところが、現実には「神の国」が到来するどころか、イエスが刑死させられてしまったから、当然のことながら、イエスたちの言っていた「神の国の到来」というのは、本当なのかという疑問が出てきた。そこで、それを正当化するために作られたのが、イエスの死後の「キリスト教」なのである。
プロテスタントでは、これを「神の国の遅延問題」と呼んで、その意味するところを問うているが、少なくともハインラインは「神の国の到来」に対する希望を、まだ捨て切ってはいない、ということだったのではないだろうか。だからこそ『異星の客』のような作品を書きもしたのではないか。

『獣の数字』は、無論「ヨハネの黙示録」に登場する、神への反逆者たる堕天使サタンを象徴する数字(666)を指していう言葉で、映画『オーメン』(リチャード・ドナー監督・1976年)で、日本でもすっかり有名になったものである。
また『ヨブ』は、言うまでもなく、旧約聖書の「ヨブ記」に由来する作品であろう。
このようなことから、ロバート A.ハインラインが、キリスト教に深く惹かれながらも、現実のキリスト教会や「宗教」には失望している、そんな「屈折を抱える人」だというのが窺えよう。
そして「本当の神」を信じたい彼にすれば、「人間の知恵」というものは、言うまでもなく不完全なものなのだから、「神」を否定する「近代的な理性万能主義(人間主義)」や、まして「無神論」の「共産主義」など、彼の好もうはずはない。つまり、彼は「人間の知恵というものの限界」を強く押し出すという点において、「保守」思想家であり「反共(反唯物論)主義者」だったのではないだろうか。
しかし、彼がいくら「現実の宗教」や「現実のキリスト教会」を批判否定したところで、彼の中には、間違いなく「超越的なものへの希求」がある。
また、彼が、ハーショーの口を借りて、「無神論者」を愚か者だと否定するのは、実際のところ「無神論者」の中にも、なんらかの「超越的なものへの希求」があるのを彼が知っており、にもかかわらず、「無神論者」たちは、そのことに無自覚だからなのだろう。この点については「無神論者」である私も、おおむね同意見である。つまり、「無神論者」にも、自覚されない「神」はあって、それが時に「理性」や「理想」や「イデオロギー」といったかたちを採る(肉化する)ということだ。
そうした意味で、ハインラインの「無神論者」批判は正しいと思うし、本作『異星の客』の中でも、あれだけ宗教を批判するハーショーが、しかし「無神論者」ではなく「不可知論者」だというのも、納得できるところではあろう。
限定された存在でしかない人間には、この宇宙のどこにも「神はいない」などと証明することはできない。したがって「無神論」は間違っており、われわれ人間は「神がいるのかいないのかを知り得ない」という意味で「不可知論者」に止まるしかない、というのは、一見、論理的に誠実であり、正しい自己規定のように見える。
だが、あえて「無神論者」を名乗る私から言えば、「不可知論者」を名乗る者は、基本的に「二股両張りの偽善者」でしかない。
というのも、「究極的な正解は、知り得ない」というのは、何も「神の存在」に限らず、すべてのことに言えることだからだ。
例えば「明日の朝も、東からお日様が登る」というのは「絶対確実な真理」ではなく「ほぼ間違いない事実」でしかないというのと、それは同じことなのだ。
私たちが、あらゆる法則性やモノの存在を信じるのは、「少なくともこれまではそうであったから、これからもそうに違いない」ということでしかない。
つまり、確率論的に「ほぼ確か」であり「蓋然性がきわめて高い」ということでしかないのだけれど、私たちはそれを信じて生きているのであり、そうした態度を「知的に不誠実」だとは、普通は言わない。
「いや、明日は西からお日様が登るかもしれないと、私は本気で疑っている」という人を「知的に誠実」な「不可知論者」とは呼ばないはずだ。
だとすれば、「神」のように、これまで、その存在が確認されなかったし、確認される可能性の極めて低いものを「存在しない」と信じる「無神論者」は、ごく真っ当な「類推確率論者」であって、決して「知的に不誠実な人間」とは呼び得ないはずだ。
反対に、ほとんど無いにも等しい可能性に賭けて「神はいるともいないとも言えない。わたしたちには知り得ない」などと言う「不可知論者」こそ、「知的に不誠実な、自己願望執着者の擬態」なのではないだろうか。
本当は、いないだろうと思いながらも、それでも「信じたい」という気持ちが捨てられないから、その情に流されて「いないとは言い切れない」などと言っているのが「不可知論者」の正体なのではないかと、私はそう考えている。
だから、キリスト教会自身がよく「キリスト教信仰は、宗教ではない」と主張するのと同じで、、ロバート・A・ハインラインもまた、「宗教批判者」ではあっても、所詮は「信仰者」でしかない、と私は考える。
ほぼ間違いなく「いもしないもの」を、それでも「信じたい」と執着しているからこそ、彼は「屈折の多い人」になってしまったのではないだろうか。

(2023年8月30日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
