
笠井潔 『煉獄の時』 : 十余年を費やした、 二段組800ページの力作
書評:笠井潔『煉獄の時』(文藝春秋)
まったく期待していなかったのだが、面白かった。強くお薦めしたい。
私は、法月綸太郎から『笠井潔の弟子』(『創元推理14』1996年秋号)と呼ばわりされたことのある、法月なんかよりも古い「笠井ファン」だったのだが、その後「笠井潔葬送派」に転向したので、当然のことながら笠井を批判することが多くなった。
しかし、私が笠井潔を批判したのは、笠井の「文壇政治性」であり、『理屈なら、どうとでもつけられる』(『柄谷行人 ポスト・モダニズム批判 拠点から虚点へ』)といった言葉に表れた、その「欺瞞的レトリック」と「権力志向型の人間性」であって、その「能力」自体(有能さ)を否定するものではなかった。
(ちなみに、一時期、笠井潔の「子分」に収まっていた、法月自身書いたように、私にとって法月は、笠井の『刺身のつま』でしかなかった)

つまり、笠井潔は、たしかに説得力のある議論を組み立てる才能のある、優れた評論家ではあるし、そこは私も一貫して認めているのだが、その「論理(ロジック)」の根底には、現実認識に忠実であろうとする「人間的な誠実さ」が無い。
笠井は、その時その時の「情勢判断」によって『理屈なら、どうとでもつけられる』才人で、説明や訂正もなしに、前に言っていてことと真逆なことを平然と、しかももっともらしく語れる人であり、さらに言えば「白を黒と言いくるめることのできる」才能の持ち主なのである。つまり、平たく言うなら、「一流のぺてん師」だと言うことだ。
で、ここまで言う「笠井潔葬送派」の私が「面白い」と言うのだから、本作『煉獄の時』は、たしかに面白い。それは保証する。
ただし、ここに書かれていることは、あくまでも「実在の人物や時代背景をモデルにしたフィクション」であって、「(歴史的)現実そのもの」ではないし、「笠井潔が考えていること(本音)そのもの」でもないので、あまりナイーブに真に受けないようにしていただかなければならない。
もちろん、エンタメ小説家は、「心にもないこと」を書いて、ナイーブな読者の涙を搾り取ったり、納得させたり信じ込ませたりするのも「力量のうち」だから、批評の場合とは違って、笠井潔が意図的に「自分のフィルター(偏光レンズ)を通して見た世界」を描いていたとしても、それはなんら問題ではない。
その作品が「現実っぽく書かれたフィクション」や「ファンタジー」であり、そこで読者の「誤解」を招く部分があったとしても、それは作者である笠井の責任であるよりも、むしろ読者の「リテラシー」の方が問われるべき部分であろう。要は「フィクションを、真に受けるな」ということである。
そんなわけで、本作『煉獄の時』は、「フィクション」として面白い。
本作は、小説家・笠井潔を代表する「矢吹駆シリーズ」の第7作目となる作品であり、これまで同シリーズで世評の高かったのは、デビュー作『バイバイ、エンジェル』、第2作『サマー・アポカリプス』、第4作『哲学者の密室』の3作だと言えるだろうが、個人的には、本作を上から三番目に位置づけても良いとまで思っている。
つまり、『バイバイ、エンジェル』や『サマー・アポカリプス』には及ばないまでも、本作『煉獄の時』を、『哲学者の密室』よりも上に位置づけても良いと思うほど高く評価しており、またそうした意味では、笠井潔の(ミステリは無論、SFや冒険小説や純文学もどきまで含めた、全)「小説」において、心から「面白い」と思ったのは、『サマー・アポカリプス』以来の、じつにおよそ40年ぶり、ということにもなるのだ。
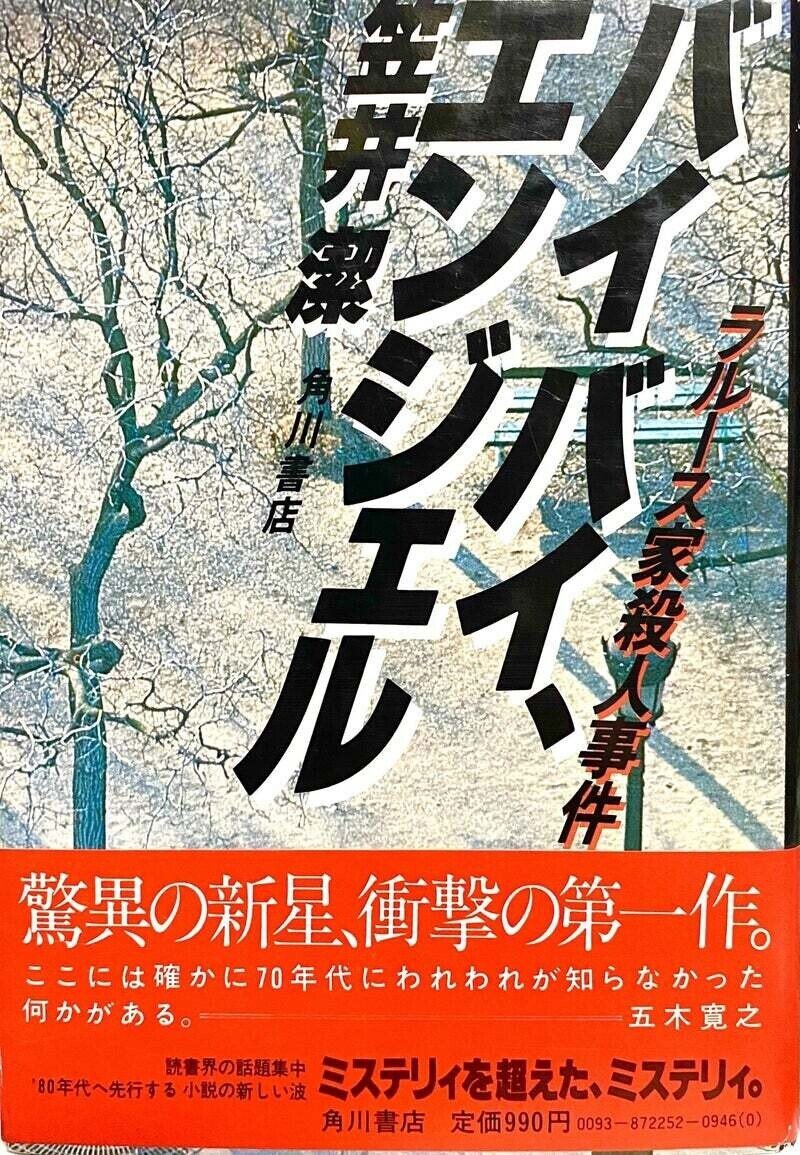
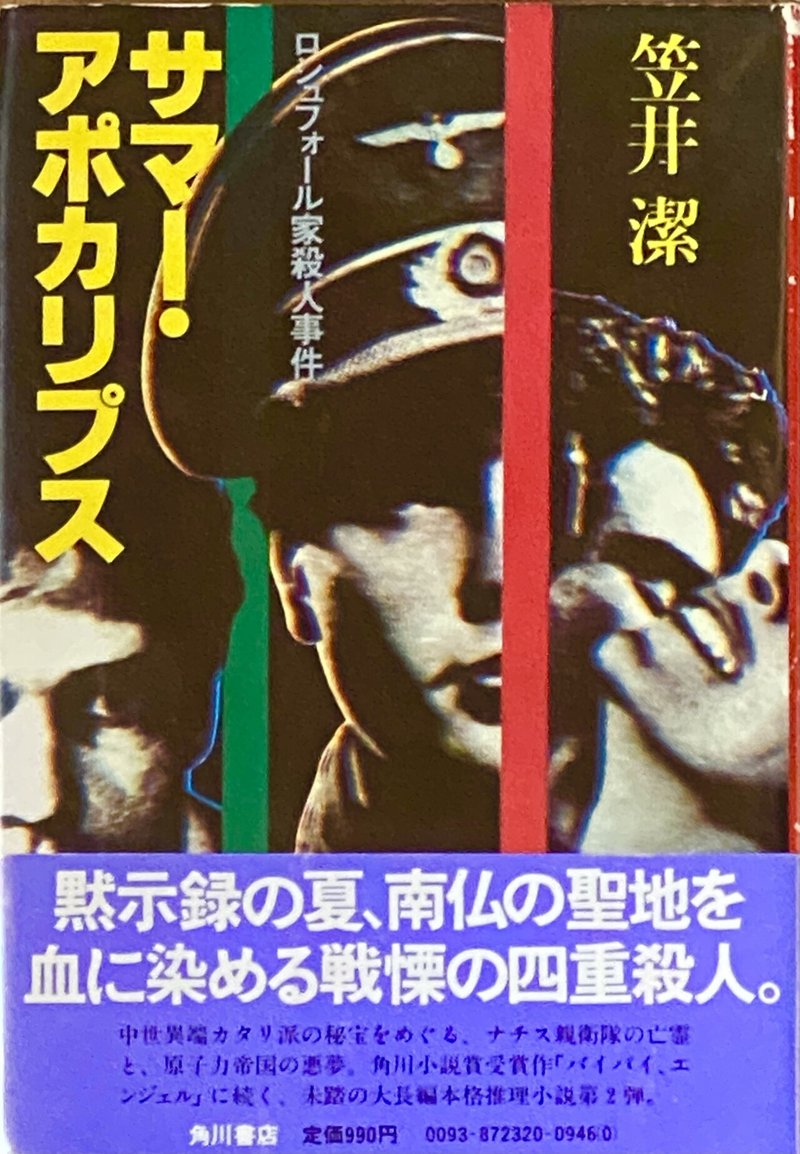
○ ○ ○
『1978年6月。ナディアは著名な作家のシスモンディに、友人・矢吹駆を紹介する。シスモンディのパートナーであり、戦後フランス思想家の頂点に立つクレールが彼女にあてた手紙が消失した謎を駆に解き明かしてほしいというのだ。しかし手紙をネタに誘い出されたシスモンディとナディアは、セーヌ川に係留中の船で全裸の女性の首なし屍体を発見する。事件の調査のためリヴィエール教授を訪ねると、彼は若き日の友人、イヴォン・デュ・ラブナンのことを語り始める。39年前、イヴォンも首なし屍体事件に遭遇したというのだ――。』(『煉獄の時』内容紹介文)
上の紹介文にもあるとおり、本作では「作中の現在時(1976年)」と「過去(1935年前後)」が2つの時期が描かれており、「現在ー過去ー現在」という「過去」をサンドイッチする構成になっている。
要は、現在時に発生した「装飾の施された、異様な首なし屍体事件」とそっくりな未解決事件が、39年前にも(3件)発生しており、どうやらそれが現在時の事件に関係している、というお話になっているのだ。

(ゴダール『パリところどころ』より。『煉獄の時』現在時より約10年前の風景)
そんな本作で、私が特に面白かったのは、主にこの「過去篇」における、社会情勢描写と人々の姿であったと言えるだろう。
つまり、「現代篇」と同じく、フランスを舞台にしたこの「過去篇」で描かれるのは、ナチスドイツの勃興によって、ふたたび「世界大戦」の危機にさらされたヨーロッパにおける、フランスの人々の不安と動揺がリアルに描かれているのだ。
第1次世界大戦の惨禍によって、多くの国民を失いながらも何とか「戦勝国」になったフランスでは、もう戦争は二度とゴメンだという空気が、上下を問わず満たしていた。
しかし、敗戦国であったドイツは、敗戦によって課された過酷な補償金によって社会は疲弊し、国民には暗い不満が鬱積していた。だからこそ、ヒトラーはそうした国民の思いを受けて権力を握ることができたのだし、そんなヒトラーが目指したのは、「平和」ではなく「帝国の復活」であり、要は「復讐戦」だったのだ。
そんな好戦的なドイツと、さらには、革命による混乱によって十分に国力を回復していないとはいえ、ボルシェビキ(レーニン派)が権力の独占的な掌握を果たした共産国家ソ連は、虎視眈々とヨーロッパの共産化を狙っていた。
つまり、第一次大戦での「戦勝国」は「戦争はもうゴメンだ」と思っていたが、戦争に負けた「恨み」を抱えるドイツと、これから「世界同時革命」を果たそうと考えているソ連という「二大独裁主義国家」によって、ヨーロッパの平和は風前のともしび状態であり、またそんな中で、民主的な政治を望んで民衆の立ち上がった「スペイン内戦」も、戦争に懲りた戦勝国の「不干渉」によって見殺しにされてしまった。
こうした暗い予感に満ちた不安な時代状況に、フランスの人々は、そしてフランスの思想家や知識人たちは、どのように向き合ったのか。一一それを描いた部分において、この「過去篇」は、とても面白かったのだ。
周知のとおり「矢吹駆シリーズ」は、単なる「本格ミステリ」ではなく、「思想小説(思弁小説)」的な側面を持つ。
各作品には、実在した思想家をモデルにした架空の思想家が登場して、主に、主人公である矢吹駆と思想対決的な議論を行い、それが事件の本質に関わるものになっているというのが、このシリーズの、他に類例を見ない特色だと言えるだろう。
本作でも、シモーヌ・ヴェイユ、ジャン=ポール・サルトル、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、ジョルジュ・バタイユといった思想家をモデルにした人物が登場して、「現在篇」では矢吹駆と、「過去篇」では、語り手となるイヴォン・デュ・ラブナン青年(『バイバイ、エンジェル』に登場する、マチルド・デュ・ラヴナンの父親)が、思想家たちと、その「時代精神」に関わる議論を交わすのだ。
前述のとおり、私は、この小説に描かれた「思想家」たちが、現実の「シモーヌ・ヴェイユ、ジャン=ポール・サルトル、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、ジョルジュ・バタイユ」といった人たちの思想や人柄を、忠実に描いているとは思わない。
そんな短絡はしないけれども、それでも「作中の思想家」たちの語る思想や洞察は十二分に面白いし、彼らの思想における「時代との対峙」もまた、十二分に考えさせられるものとなっている。

(サルトルとボーヴォワール)
つまり、私が、この小説を「面白い」と思ったのは、「娯楽小説」としてとか「フィクション」としてではなく、「思考実験」小説として、そうだったということだ。
「この時代、この場所に、私がいたとしたら、私に何ができただろう。私はどのような選択をして、どのような生き方をしただろうか?」と、そう考えながら読むことができたので、「面白かった」のである。
しかし、こう抽象的に書いても、ピンと来ない人も多いと思うので、少し具体的に書くと、例えば「私が、第二次世界大戦前夜のフランスに(フランス人として)生きていたら、平和と戦争について、どのように考え、どのような選択をしたか?」
「フランスがドイツに対する無血降伏の占領を受け入れた際、私はレジスタンス(抵抗ゲリラ戦)の必要性をどう考え、必要とあればそれに参加する勇気を持ち得ただろうか? それとも、いろいろ理屈をつけて、保身的な傍観者になっただろうか?」
「仮に、レジスタンスには参加しない一般市民として占領を受け入れた場合、迫害されていたユダヤ人が救いを求めてきたら、私は自らの危険を顧みずに、彼らを匿うことができただろうか?」
「また仮に、レジスタンスに参加したとして、ゲシュタポ(ドイツ秘密国家警察)に捕まり、仲間のことを吐けを拷問をされたら、私は、それにどこまで耐えられただろうか? 小指から、一つずつ生爪を剥がされてゆき、それに耐え切っても、今度は、小指から順に指を切断されていったとしたら、それに耐えきれただろうか? 水責めの拷問にあって、眼球をえぐり取られてでも、私は死ぬまで口を閉ざし続けることができただろうか? きっと出来なかったに違いない」
一一そんなことを考えながら読んだから、この小説に、私は「身につまされた」のであり、その意味で「面白かった」のだ。

言い換えれば、この作品が、単に「思想的あるいは哲学的議論がなされているから、面白かった」とか「ミステリとしてよく書けているから、面白かった」といったことではなかった。つまり、私のそれは、そんなオタク的な楽しみ方ではなかった。
「作者の笠井潔が、現実にこのような試練に晒されたら、どんな態度をとるか」といったこととは関係なく、私自身が「現実にこのような試練に晒されたら、どんな態度をとるか」という問いを痛切に突きつけられ、考える契機を与えられ、考えさせられたからこそ、私はこの小説に「感謝」したいほどの「面白さ」を感じた。

まあ、「たかがミステリ」に対し、こんな奇特な読み方をする人間も珍しかろうが、そういう人間であったからこそ、かつて私は、笠井潔のファンだったのであり、まただからこそ私は、「笠井潔葬送派」に転じもしたのである。
○ ○ ○
では、そうした「個人的な興味」とは別に、「世間一般の読者」が期待しているであろう、娯楽小説たる「ミステリとしての出来」は、どうだっただろう。
これも、決して悪くはない。
事件を、時間的に「二重化」して複雑にするというのは『哲学者の密室』などでも同じであったが、私としては本作『煉獄の時』の方が好みだった。
なぜなら、『哲学者の密室』では「密室」が、『煉獄の時』では「装飾された首なし屍体」などが、事件の本質を象徴するものとして、その「意味するところ」が問われる(本質直観されねばならない対象となる)のだが、本来、本格ミステリにおける「密室殺人」というのは「不可能犯罪」であるところにその魅力があり、読者の興味の中心は「いかにして、密室は構成されたか?」という「謎の解明」にあるのであって、決して「密室の象徴的本質とは何か?」といった抽象議論にはないからで、一方「首なし屍体」の方は、もともと「なぜ、首は切られ(持ち去られ)たのか?」という、その「意味」を問うものだったため、「抽象議論=意味論」の「面白さ」で読ませる「笠井潔の本格ミステリ」では、やはり「密室」よりも「首なし屍体」の方が、(『バイバイ、エンジェル』と同様に)笠井の作風に合致していた、と考えるからである。
つまり、本作『煉獄の時』は、「笠井潔の本格ミステリ」らしい本格ミステリとして、よく出来ていたし、その点で「面白かった」。
ただし、そんな本作の最大の弱点は、こうした「本格ミステリ」を楽しめる知的読者が「いったい、どれだけいるのか?」という問題である。
本作は、昨今流行りの「最後に、アッと驚かせれば、それだけで良し」といった、お手軽なびっくり箱ミステリではなく、複雑に絡まり合った伏線の糸が、物語の最後で、いかにキレイに1本にまとまるか、その「手際の美しさ」を問う作品なので、そもそも「複雑な物語」や「それぞれの現象の意味」といった話についていけないような読者には、能力的に、本作を楽しむことは不可能だ。
例えば、本作の中で、語られる「哲学的議論」を、大筋にしろ理解できる読者が、今時どれほどいるだろうか? そもそも、サルトルやボーヴォワールの名前さえ聞いたことがないという若い読者に、この物語における「哲学的議論」を理解しろという方が、むしろ無理なのではないか。
無論、専門的な哲学的知識がなくても、その「雰囲気」くらいは理解できるように書かれているけれども、「占領」や「レジスタンス」といったことの「リアリズム」を、一度も考えたことすらない者が読んで、それに関する作中での「哲学的議論」の生々しさや切迫性を感じることなど、およそ出来ない相談なのではないだろうか。
一一だとすると、本作の読者は、それなりの年齢に達して、それなりの人生経験を積み、それなりの教養を蓄えた(ことで連想の働く)者だけに限られる、ということにはならないだろうか。
もちろん、少なからぬ読者は「そのへんの小難しい議論は適当に読み流して、あくまでもミステリとしての造りだけを問題にする」といった読み方をするだろう。
そういう読み方も、現にそうとしか読めない者を作ってしまう小説、つまり本作が「読者を選ぶ小説」である以上、避けられないことなのではあろうけれど、しかし、それではこの小説の「面白さ」の、肝心の部分を切り捨ててしまうことにもなるだろう。言い換えればそれは、「首なし屍体」を「普通の屍体」として遇する(評価する)のと似たような、粗雑な読みにしかならない、ということである。
したがって、この作品が、ごく普通のミステリー読者に読まれて、ヒットするといったことはないだろう。
例によって、相応の年齢に達したミステリ作家やミステリマニアたちが、年末のベスト投票などで本書を持ち上げ、それによって初めて注目され、そうした評価に煽られ流された結果として、ある程度は世間的にも「本作はすごい!」という話になるのが、せいぜいのところなのではないかと思う。
しかし、そうした途中経過はどうあれ、本作のような「理解されにくい傑作」が、ひとまず話題にのぼること自体は、決して悪いことではないし、それがきっかけで本作を読む人が一人でも増え、その中から、一人でも二人でも、本作の「思弁小説」としての魅力に気づいてくれる人が出るなら、それは「僥倖」であろう。いずれにしろ、良いも悪いも、そもそも読まれないことには、お話にならないからである。
○ ○ ○
そうした観点から、本作の「ミステリとしての弱点」も指摘しておこう。
それは、本作の「ミステリとしての長所」とも密接に関係するというか、「長所の裏面」でもあるのだが、要は「ミステリとして、過剰に複雑である(シンプルではない)」という弱点だ。
端的に言ってこれは、笠井潔という作家が「トリックメイカー」ではなかったためである。
笠井は、「斬新なアイデア」を次々とひねり出すというタイプの作家ではないので、本格ミステリにおける「シンプルなアイデア」は、ごく初期の作品でネタ切れとなった。その証拠に、初期3作までは、普通の長さ、あるいは少し長めの作品だったのが、約10年の空白を経て書かれた第4作『哲学者の密室』は、驚くべき大作(分厚さ)になってしまった。
これは、ミステリ作家・笠井潔による「ミステリにおける斬新なネタ」は、第2作『サマー・アポカリプス』が最後となったからであり、第3作の『薔薇の女』が、本格ミステリとしては、明らかに「弱かった」ことからもわかる。事実、前作『サマー・アポカリプス』があまりにも素晴らしい作品であったための期待の高さもあって、『薔薇の女』の評判は芳しいものではなかった。「ミステリとしては物足りない」という評価になってしまったのだ。
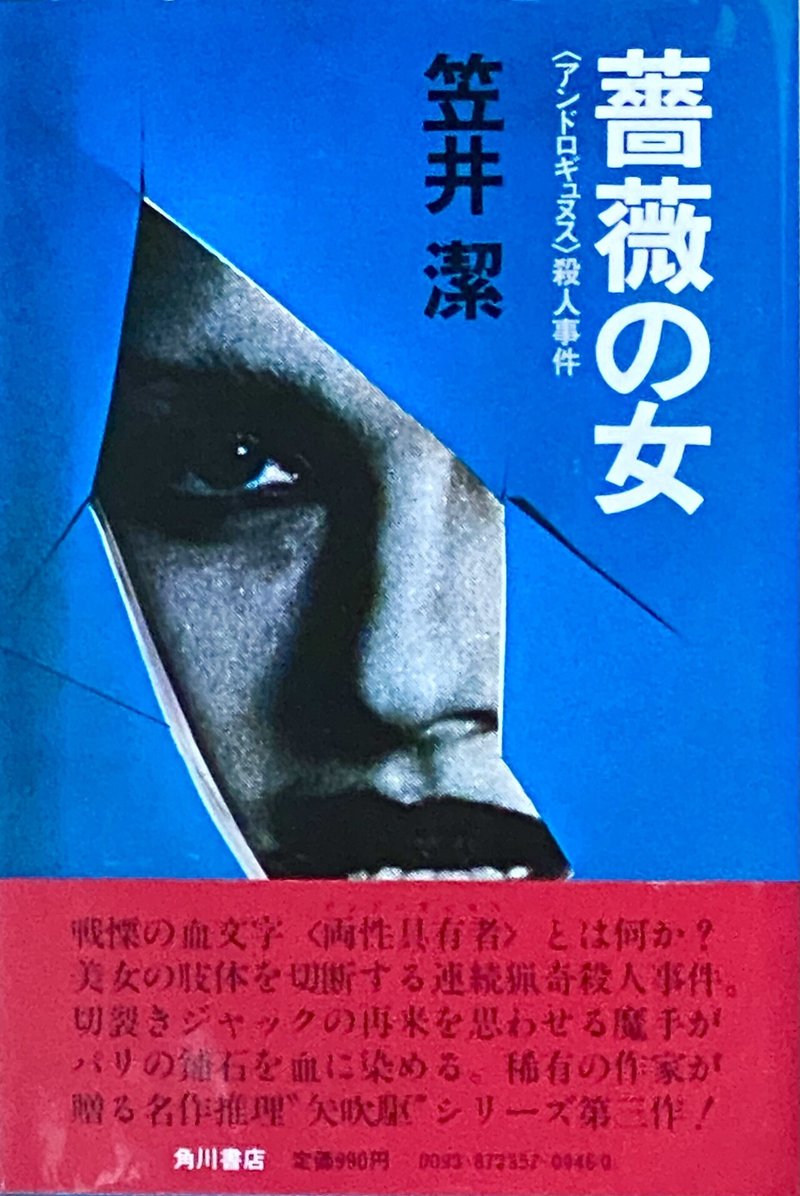
しかし、だからと言って、もともと「トリックメイカー」ではない笠井に、今更「斬新なアイデア」など出てはこない。では、どうするか?
当然、選ばれたのは「路線変更」であり、要は、オーソドックスでわかりやすい「一発ネタの本格ミステリ」ではなく、自らが得意とする「複雑な状況を、一貫したロジックによって説明する(腑分けする)」という「評論家としての才能」を生かせる「路線」に、ミステリの書き方を変えたのである。
通常「評論家(批評家)」というのは、「多様な要素の複雑に絡み合った複合体としての批評対象」の中に、一本の「中心線=背骨=骨格=本質」を見出して、その対象の「構造」を、論理的かつ体系的に説明してみせる。例えば「日本社会」の本質は「空気の支配」だとか「中空構造」だとかいった議論がそれだ。
つまり、こうした「日本社会」論における、評論家の見出した「空気の支配」だとか「中空構造」とかいったものは、「矢吹駆シリーズ」において矢吹駆が、「密室」や「首切り死体」に対して行った「本質直観」によって見出した「本質」と同種なものなのだ。それさえ洞察できれば、あとは事件全体の構造を説明することも、おのずと容易だということになる。
したがって、笠井潔が、オーソドックスでわかりやすい「本格ミステリ的一発ネタ」の案出に、自身の限界を悟ったときに選んだのは、「複雑な状況を架構し、それを鮮やかに解きほぐしてみせる」という「ミステリ作法」であった。だから、自ずと、その作品は「長く」なったのだ。
もともと、「複雑な現実状況」を鮮やかに解きほぐしてみせるのが得意な「評論家」なのだから、「シンプルで意外性のあるものを案出する」よりも、「複雑な状況を作って、それを解きほぐす」方式の方が、自分の特性に合っているとした笠井の判断は、まったく正しかった。
そして、そのような方式を選んだからこそ、『哲学者の密室』以降の笠井の「本格ミステリ長編」、その中でも代表シリーズである「矢吹駆シリーズ」は、例外なく「分厚い大作」になってしまったのだと言えよう(『哲学者の密室』、『オイディプス症候群』、『吸血鬼と精神分析』、本作『煉獄の時』)。

しかし、この方向選択が笠井潔の個性に合致したものとして正しかったとしても、では「複雑な状況を作って、それを解きほぐす」方式で書けば、なんでも面白くなるのかといえば、当然ながら、そう甘い話ではない。
「複雑な状況を作って、それを解きほぐす」方式が決まったとして、次に問われるのは「複雑な状況の魅力」であり「解きほぐし(謎解き)の手際の美しさ」ということになろう。これがなければ、単に「面倒くさく複雑で長いだけのミステリ小説」ということになってしまうからだ。
さて、この「複雑な状況の魅力」と「解きほぐし(謎解き)の手際の美しさ」という「一対のもの」では、特に前者が重要となる。「複雑な状況の魅力」、つまり「複雑かつ魅力的な謎の提示」ができれば、「謎解き」の方もそれなりのものになる蓋然性が高いからだ。
言い換えれば「魅力のない謎を、いくら手際よく解いても」、それは「大長編」作品を支えるものにはならない。例えば、「日常の謎」ものに代表されるような「小さな謎を、手際よく解きほぐす」といった形式は、明らかに「短編」向きであって、同じことを「大長編」でやれば、いくら「見事な謎解き」であったとしても、アンバランスな物足りなさは免れ得ないからである。
したがって、「大長編」においては、その規模に応じた「魅力的な謎の提示」が必須である。
ならば、『哲学者の密室』以降の「矢吹駆シリーズ」においては、そこをどうクリアするのかが課題となるのだが、これがまた、なかなか難問だ。
「複雑な状況を作って、それを解きほぐす」方式というのは、言ってしまえば「マッチポンプ式」なので、よほど「魅力的な謎」を構築しないと、読者はそれに魅力を感じてくれない。
例えば「首切り死体が1万人」とか「衛星軌道上に浮かんでいる怪しい洋館」とか、そういう馬鹿馬鹿しいまでの「派手さ」とは、それだけでは所詮「子供騙し」であって、それ相応の「謎解き」が伴わないかぎり、今どきの読者は誰も感心してはくれない。ならば、どうするか?
そこで笠井潔が勝負できるのは、やはり「思想・哲学」の部分でしかないだろう。つまり、作中の事件に「思想的・哲学的な難問」を象徴的に担わせるのである。
「この事件における難問は、現実の社会における難問を象徴的に反映したものだ」と読者に感じさせ、その「重み」において、「作中の事件を魅力化」するのである。
しかしながら、こうなると問題は、単純な「作中世界(フィクション)」の話では済まされず、「現実の難問」とも拮抗しうる思考を、そこに込めなければならなくなる。となると、当然のことながら、量産は不可ということにもなってしまうのだ。
それでなくても「フィクションは所詮フィクションであって、なんとでも書ける」と軽く見られがちなのだから、それを「現実の難問」と拮抗させようとするならば、それなりの準備と作品的充実が必要となる。単に「複雑な状況を、哲学に絡めて書けば良い」などという安易なものでは済まなくなって、おのずとその作品は「その長さに見合った重厚な中身を持つ、時間も手間暇もかかる作品」にならざるを得ない。
その点、本作『煉獄の時』は、そうした長く困難な時間の中で練り上げられた傑作と呼んでいいだろう。文字どおりにこの作品は、「煉獄の時」の中でこそ生み出され得た作品だったのである。

したがって、本作は、決してサクサクと読める作品ではない。作者が、この作品に注ぎ込んだ心血労苦の、そのせめて百分の一でも自ら担おうとする「積極性」が読者の側にない場合には、本作は「猫に小判」「豚に真珠」にしかならないというのも、致し方のないことなのだ。
最初にも書いたとおり、この作品に「描かれた思考」を、「作者自身の思考」そのものだとは、私は思わない。
だが、だとしても、本作に架構された「思想」や「思考」や「体験」は、読者それぞれの対決に値するものであろうと思うし、その意味で私は、本作を高く評価したい。
本作もまた、間違いなく、読者を選ぶ「反時代的な傑作」なのである。
(2022年10月29日)
○ ○ ○
