
杉田俊介 『戦争と虚構』 : 「享楽」する〈ねじれ〉男の弁解術
書評:杉田俊介『戦争と虚構』(作品社)
これが、日本の批評界の現状なのかと、かなりうんざりさせられた。
私が本書を手に取ったのは、笠井潔がひさしぶりに単著の評論書『限界状態の道化師 一一ポスト3・11文化論』(2020年11月、南雲堂刊)を刊行し、そこに収録されていた9本の書評のうちの1冊が、本書だったからである。
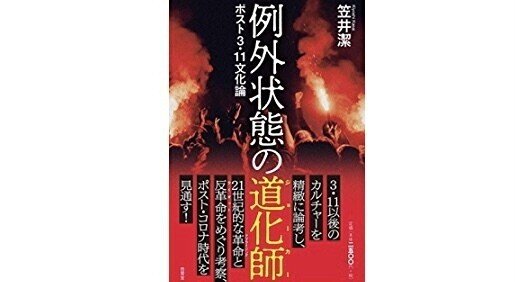
私は、批判的ではあれ、笠井潔の長年の熱心な読者であり、一時期、笠井に近かった法月綸太郎から「笠井潔の弟子」呼ばわりまでされてしまい、「お前が笠井潔の子分だろ」とやり返したような、そんな「笠井潔葬送派」だったのだ。
だからこそ、笠井ひさびさの新刊を読むために、その「下拵え」として、わざわざ未読の9冊を読んだりもしたのである。
本書を読む前に読んだ「9冊のうちの1冊」は、藤田直哉の『娯楽としての炎上一一ポスト・トゥルース時代のミステリ』(2018年9月、南雲堂刊)だった。
私は、藤田直哉が笠井の組織した「限界研」(旧称・限界小説研究会)のメンバーであり、「弟子」だか「子分」だかの一人だと知っていたので、さほど期待せずに読んだのだが、それでもこれは相当に酷い、「ちょっと賢い高校生が書いた評論」程度の、最後まで読むのが苦行なシロモノであった。
同書のレビューにも書いたことだが、私はなにも、藤田が笠井の子分だから貶しているわけではない。有能なら有能で「なんでこんな人が」と考えるだけのことで、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」といった幼稚なことをする必要などないからだ。

ともあれ、藤田に泣かされた後なので、今回が初読となる杉田俊介による本書『戦争と虚構』の方は、苦痛なく読める本でありますようにと、祈るような気持ちで読み始めた。なにしろ杉田も、藤田と同様、笠井潔に近い評論家らしい(「笠井潔入門、一歩前」なんていう、笠井の著書の解説文があるし、限界研にも近ければ、藤田との共著もある)ので、大いに心配したのだが、幸い杉田は「書ける評論家」で、その点はなかなか感心させられた。
まず、とてもよく勉強しているし、基本的に良識派で、ご当人に直に会ったら、きっと「いい人」なのだろうというのが伝わってくる文章である。
そんなわけで「これなら、けっこう面白く読めるかもしれない」と期待して読み進めていったのだが、三分の一も過ぎると、一一残念ながら、藤田のそれとはまた違った意味で、うんざりさせられ、読む進めるのが苦痛でたまらなくなってしまった。
杉田俊介の、いったい何がダメなのか?
簡単に言ってしまえば、この人(杉田)は「評論家であり続けるために、評論を書いているだけ」なのだ。
「評論を書かなければならない」という「内的な衝動」に駆られて書いているわけではなく、文字どおりの「(生活の糧を得るための)仕事としての評論家」なのである。そして、それに付け加えるべきものがあるとしたら、それは「社会的承認欲求を満たすための肩書き」としての「評論家」でしかないのだとも言えよう。
だから、能力や技巧はあるけれども、物書きとしては「空っぽ」であり、杉田の文章は、実のところ「私はこんなに考えている」という「自己アピール」以外は、ほとんど何も言っていないに等しいのである。
○ ○ ○
本書を通読すると、「ねじれ」「享楽」「ポスト・ヒューマン」「パッチワーク」「マジカル」「臨界」「予兆」「挽歌」といった暗示的な言葉の頻出に、誰もが容易に気づくだろう。つまり、こうした「杉田俊介ワード」に、杉田の批評家としての特性が表れていると見て、まず間違いない。
そして、こうした「杉田俊介的ワード」の中でも、特に重要となるのは、うんざりするほど繰り返される「ねじれ」と「享楽」である。
本書に収録されているどの文章を見ても、杉田が対象を論じる際に、着眼点として発見してみせるのは、ほぼ例外なく「ねじれ」である。
加藤典洋からの借用であると見ていい、この「ねじれ」という言葉は、杉田が批評対象のある部分に、「無理」や「不自然さ」を見て取り、そこに「問題の本質」があるとして、その着眼点から「隠された真相(現代的な病巣)」を剔抉しようとする際に使われるものだ。
一方、自身の出自を「非モテ」の「オタク」だとわざわざ告白する杉田は、しかし、自身が「享楽」的な人間であることを否定しないばかりか、むしろ本書において一貫して目指されるものこそ、「享楽の正当化」なのである。
つまり、杉田俊介という評論家の仕事とは、批評対象の中に「ねじれ」を見つけた上で〈その「ねじれ」を是正し、乗り越えるために必要なのは、一般には否定的なものと考えられがちな「享楽」を、むしろ積極的に承認し、それを突き詰め、突き抜けることなのだ〉といったロジックで、「享楽的人間」としての自身を「自己肯定」しようとするものなのである。
喩えて言えば、「変態というねじれを否定するのではなく、変態としての享楽に徹することで、そのねじれを突き抜けて、ポスト・ヒューマン的な実存に達しないかぎり、私たちは形式的かつ通俗的な欺瞞としての倫理によって、問題の直視を避け続けるしかないのだ」といったような議論を展開するのである。
しかし、この一見「批評的徹底性」を感じさせる物言いは、いかにも欺瞞的である。
と言うのも、杉田俊介的な批評的徹底性に対置されるのは、いつでも「浅薄な通俗倫理」でしかなく、「重厚な生活的倫理」ではないからだ。
つまり「出来の悪い敵」を持ち出してきて、相対的に自分たちの立場が、さも「深い真理」ででもあるかのように見せかけるという、よくある欺瞞を弄しているにすぎないのである。だから、その主張に「厚み」がない。
杉田の評論文は、決して難解なものではなく、それでいて露骨に「衒学的」であり、ほとんど必要のない「権威筋からの引用」とその解説に満ち充ちている。つまり、いかにも「着膨れな擬装」が施され、ほとんど「贅肉の思想」と呼んでもいいほどなのだ。
もちろん、「贅肉こそが大切」などといった、かたちばかりの抗弁もできようが、実際にはそれだけの効果はあがっておらず、その文章から、そうしたの擬装を剥ぎ取ったなら、貧相な裸体しか残らないというのが実態だからこそ、杉田の文章は、「迂回」だの「遡行」だのに多くの枚数を費やしている割には、結論として示されるものは、きわめて凡庸な「夢語り」にしかなっていないのである。
杉田は、私たちが現状の「ねじれ」を乗り越えるためには、「享楽」を否定するのではなく、それを加速主義的に強化し、その先にある「ポスト・ヒューマン」的な実存を目指すしかない、というようなことを説く。
しかしながら、言うまでもなく、その「ポスト・ヒューマン」的な実存とは、「言葉」としてのイメージはあっても、具体的なものとしては、何も示されはしない。ただ「このままではダメなので、よくはわからないけれども、ひとまず超越しなければならない」と言っているようなものでしかないのである。
そして、そこには「具体性」が、まったく無いからこそ、杉田は、どんな結果についても、責任を取る必要がない。
好ましいものが出てくれば、それを「ポスト・ヒューマン」的な方向性だと肯定的に評価すればいいし、好ましくないものについては「ポスト・ヒューマン」的な方向に反する、言わば「ベタ・ヒューマン」的なものであると批判しておけばいい。なにしろ、なんの具体性もない空疎な言葉だからこそ、どうとでも言えるのである。
杉田は、本書の中で、何度となく「否定的な自己評価」を表明しており、それが一見したところ「謙虚」ででもあるかのような印象を与えるのだけれど、しかしそれは、決して、そうした自身の弱さを「批判」するものではない。
たしかに、自分の「弱さ」を「否定」しても仕方がないのだけれど、しかし、それが「弱さ」であるという自覚があるのであれば、それは「批判」されるべきだし、すべきなのだが、杉田は「否定」と「批判」を混同することで、「批判」を禁じて、結局のところ、自堕落な「自己正当化=自己肯定」に専念するばかりなのだ。
だから、杉田の「非モテ」だ「オタク」だ「享楽」だといった、一見、自己批判的に見える物言いは、結局のところ、かつての法月綸太郎における「悩める作家」という『芸風』(千街晶之)と、大差のない「自己演出」だと言っていい。
もっとも、法月の場合は、やや自己陶酔的な演技という、文字通りの「享楽」的側面が強かったが、杉田の場合は、もっと「保身的」であり、その意味でも「自覚的な自己欺瞞であり他者への欺瞞」だと理解した方がいいだろう。
杉田は、馬鹿ではないので、自分のやっていること(欺瞞)について、まったく無自覚なわけではないのだが、だからこそ、その自己欺瞞を、自身に信じさせようとして、読者には不必要な、しばしばウザったいだけの「自分語り」を執拗に繰り返して、自己暗示(自己洗脳)を施さなければならないのである。
杉田のこうした、厚顔なまでの「保身性」は、次のような言葉によく表れている。
『 これは批判ではない。皮肉でもない。私のこうした感じ方は、繰り返すが、ごく普通のもの、当たり前のものだと考えている。
しかし、それでも、やはり一一。
震災のスペクタクルな映像を消費しまくってしまう自分の欲望に、嫌な感じがずっとあった。何かが嫌だった。その嫌な感じを問いなおしてみたかった。』(P346)
杉田は、よくいる「良識派」のように、「正論」で他人を「批判」したりしないし、「皮肉」を言ったりもしない。杉田は、自身を、そんな「居丈高で鼻持ちならない、しかし頭の悪い、良識派」ではないと、そう予防線を張りながら、実のところ、手前味噌にも自身を「賢明な批評家」だと位置付けている。
しかしまた「自分は、清廉潔白な人間などではなく、欲望に淫してしまう享楽者であり、その自覚において、自身に居心地の悪さを感じている、と正直に認める人間である」とも自己紹介している。つまり、自分は、あらゆる側面から見て、決して無自覚な「いい気なヤツ」ではないと「予防線」を張り巡らせておいて、おもむろに「欲望の自己正当化」に取り組むのである。
杉田俊介という評論家は、こういう「演技的な自己卑下的自分語り」において、少なからぬ人の嫌悪を掻き立てているのだが、とにかく物量作戦的に徹底した予防線によって、そうした「嫌悪感」は、単なる感情的なものであるかのように、巧みに「演出」して見せる。
杉田の「誠実な苦しみ」が理解できない人というのは、「良識的な倫理主義者」と同様に、「ものを考えない人」ということにされてしまうのだ。
私は先日、東浩紀の新刊『ゲンロン戦記 「知の観客」をつくる』(2020/12/8、中公新書)のレビューで、次のように指摘した。
『本書で語られる著書の半生を簡単に紹介すれば、東浩紀が同世代の仲間を結集した批評誌を作るために会社を設立したものの、会社を経営するというのがどういうことかを知らなかった世間知らずであったために、なんども失敗を重ねひどい目に遭い、それでだんだん世の中の現実というものを学んで「大人」になって、おかげで今では「自分にできる、本当に大切なこと」がわかったので、今ではそれをやってます。一一と、そういう感じの内容だ。
したがって、「あの早熟の英才が、こんなこともわかってなかったのか」と驚かされるし、その一方「こんなに幼稚で愚かな失敗の数々を、よくもまあ正直に綴ったものだ」と感心させられはするのだけれど、しかし、結局のところ「自分は現在、良い場所にたどり着けた」と自己肯定している点では、ある種の自慢話であることも否定できない。最初に落としておいて、あとで上げる、という書き方である。』
杉田が、本書所収の「東浩紀論」で、東にきわめて共感的かつ肯定的なのも、こうした「自己劇化による自己正当化」を好む点で、性格的に似ているからであろう。
一見「自己批判」をし「反省」して見せて「謙虚」ぶりながらも、結局は、その「これ見よがしなポーズ」による自己正当化が目的であって、そこには本当の自己批判は欠けらもない。そんな「卑下慢」において、杉田と東は似ているのだ。
そして、こうした点は、押井守への「過剰なまでの肯定」でも同様であり、結局のところ、杉田が「東浩紀論」や「押井守論」でやっているのは、間接的な「自己正当化」なのである。東や押井を論じる形で、本質的には「享楽的な私」を間接的に正当化し、権威づけてさえいるのだ。
その一方、巻末の「注釈」の中で、論じられている細田守は、杉田たちとは真逆のタイプである。
『 細田は『バケモノの子』を「新冒険活劇」と呼んでいる。それでいえば、細田の作品のモチーフは一一デジタル化/ポストモダン化を受け入れた上での一一「新王道」にある、と考えられるのかもしれない。細田的な新王道。それは、すべてが曖昧になり、フラットになり、足元がふわふわしていく環境の中で、それでもなお、アニメを通して唯一無二のエモーションを表現すること、そしてそれをかけがえのないものとして観客や子どもたちに伝えていくことである。実際に、たとえ少しくらい辻褄があわなくても、無理やりでも、不完全であっても、強引にでも、とにかく、エモーションの力によってすべてを押し切ってしまえ! というパッションが細田作品にはある。
たとえば細田作品の中では、キャラクターたちがよく走る。何だかよくわからないが、とにかく走るのである。よく考えてみれば、『時をかける少女』でタイムリープのを行うのに、全力で走る必要はなさそうに思える。あるいは『おおかみこどもの雨と雪』では、都会から田舎へ移ってしばらくすると、母子三人が雪の中を転げ回り、ひたすら走り回るシーンがある。子どもたちは狼に変身して、木立を抜けると雲一つない青空が見える。あたかも、それまでの都会と田舎、人間と狼、親と子、男と女のあいだの様々な矛盾や、(物語の展開に対する細かい)違和感を吹き飛ばすような、健康的ですばらしい爽快感がそこにあった。』(P382〜383)
一読、「褒めている」という印象を受けるかもしれないが、これは相当に手きびしい否定的評価である。
ここでなされているのは、要は「困難な現実に正面から向き合おうとはせず、勢いで突っ切ってしまおうとする、思考停止の暴力的誤魔化しだ」といった批判なのだ。
無論、細田に対するこうした批判は、必ずしも間違いではないだろう。しかし、それでは杉田や東浩紀や押井守は、本当に「困難な現実に正面から向き合おう」としているのだろうか?
『 (※ 押井守原作・大野安之作画『西武新宿戦線異常なし』の)主人公の青年は、退屈な高校生活を一変させた出来事(※ 政府が非常事態宣言を発令する、何らかの武装蜂起=七日間戦争)の中に決断主義的に飛びこんで、人民のために死を賭して英雄的な革命兵士になりたい、と欲望するが、現地に行ってみても人民などどこにもいない。そして正規軍ではなく、民間人による非正規の革命防衛隊に属さざるをえなくなる。しかもその仕事は、廃品回収やヤミ行為ばかりなのだった。
英雄的な死へと決断主義的に没入するのではなく、非日常の中でもだらだらと生き延びて、役立たずの野良犬的な集団としてのらくらとやっていくこと、都市の廃墟で難民まがいのキャンプ生活をいつまでも続けること。それが革命防衛隊の人々にとっては「革命そのもの」であり、永続革命の実行だったのだ。(「カントク」と呼ばれるリーダーはかっては左翼運動に参加し、そののちに映画監督になった人物であるようだ)。
人類が滅びたかのような都市文明の美しい廃墟の中で、少数の仲間や犬だけが生き延びて、非日常の時間を過ごすということ。それは『ビューティフル・ドリーマー』のイメージそのものであるが、とすればあの作品におけるラムはいわば、『パトレイバー2』の柘植行人のようなテロリストたちの系譜に属する存在だったのかもしれない。テロリストとしてのラム。日常と非日常、現実と虚構がパッチワーク化した時間をできるだけ引き延ばすことがことを彼女は無意識に望んでいたのだから。』(P394)
言うまでもなく、細田守の創作態度は、『西武新宿戦線異常なし』の主人公の青年の「決断主義的英雄主義」と重ねられて、否定されている。
「そんな独りよがりでは、現実の困難に対峙して、それを打倒することなど出来はしない。むしろ、だらだらと続く非日常に耐え続けて、その祝祭空間を引き延ばし、その享楽を味わい尽くすことこそが、(笠井潔的な、バリケードにおける)真の永続革命なのである。その意味で、押井守的な、あるいは東浩紀的な戦い方こそ、真に革命的な闘争なのだ。われわれは、この時代のラムであることを引き受けなければならないのである」と。
つまり、杉田俊介が〈世界の「ねじれ」を前にして、この世界への「挽歌」の向こう側に、「ポスト・ヒューマン」な「予兆」を感じつつ、「迂回」し「遡行」しながら、「享楽」的に世界を「パッチワーク」化するという「マジカル」な手際において、私たちは「臨界」をギリギリで生き抜くべきで、その先にこそ希望がある。〉といった「レトリックの大伽藍」とは、要は「目の前の現実」を迂回するための「弁解弁明」でしかないのである。

「目の前の不都合な他人=リアルな他者」を「批判」したり「皮肉」ったりすれば、手の届く距離なのだから、ぶん殴られるかもしれない。
しかし、「冒険主義的な直言は、むしろ現実逃避だ」などと言いながら、見当はずれな方向に立ち去ってしまうならば、痛い目に負うこともないし、一応「それも迂回的な正攻法だ」と言い抜けることもできるだろう。だが、それだけのことなのだ。
つまり、本書は一冊丸ごと、「私は正しい」と言うための本なのである。
だから、なにがなんでも自身を肯定して欲しいだけの人は、本書著者の読者にぴったりであるし、そうした点において、本書や本書著者は、商品たり得ているのである。ただ、それだけなのだ。
ポスト・ヒューマンだの暴力だのその享楽だのと言い、それを精一杯肯定しながら、自身は決して、わかりやすい暴力には手を染めず、口舌によって確保された陣地の中を、無難に後からおずおずと歩んでいくだけなのだ。
所詮すべては、これ見よがしな「準備体操」。
嘘をつくとは、頭から尻尾まで、すべてを嘘でかためることではない。十のうち九つまでが真実であるからこそ、たった一つの嘘で、結論は嘘になるという詐術こそが、あざやかなペテンのテクニックなのだ。
だから、本書にも読むべき部分、聞くに値する意見は少なからずある。
しかし、「ベタ・ヒューマン」な現実を避けるための「ポスト・ヒューマン」幻想とは、所詮は、キリスト教における「神の国」のようなものである。
生前のイエスは「悔い改めよ。神の国は近づいた」と言ったけれども、結局はいまだに「神の国」は訪れず、実質的にイエスの「預言」は外れている。キリスト教ではこれを「神の国の遅延」と言うが、杉田俊介の言う「ポスト・ヒューマン」な実存の到来など、本人も信じてはいない「延命のための詭弁」でしかないのであれば、そんなもので「批評家たちの小さな祝祭空間の保全」に付き合わさせられる者には、いい面の皮だとしか評しようもない。
延々と「泣き言」を聞かされる読者の立場として言わせてもらば「さっさと死ぬか、本気でぶっ潰しにかかれよ。でなきゃ、黙れ。努力してますというアピールまで、商品にするな」ということにしかならないのである。
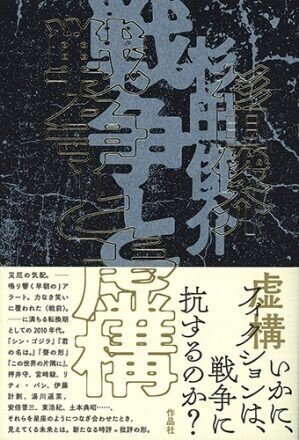
---------------------------------------------------------------------------
【参照資料1】
・ 藤田直哉をめぐる〈トゥルース〉
レビュー:藤田直哉『娯楽としての炎上一一ポスト・トゥルース時代のミステリ』
---------------------------------------------------------------------------
【参照資料2】
笠井潔周辺の雰囲気を伝える法月綸太郎の文章を含む、私の文章を以下に再録しておこう。
なお、法月綸太郎の短編ミステリ「禁じられた遊び」は、その後、名探偵ミステリアンソロジー『名探偵の饗宴』(朝日新聞出版、のちに朝日文庫)に収録されている。

(以下は、BBS「アレクセイの花園」所掲、2006年6月16日付「「現代本格の行方」の余生(3)」より)
-------------------------------------------------------
(略)
以前、私は、竹本健治の『ウロボロスの基礎論』のなかに全文引用された拙論「「得体の知れない怪物のようなもの」の所在」で、法月の「公的意見発表者」としての「覚悟不足」と、それに由来する「無責任」さ、を指摘した。
前記論文で指摘したとおり、法月の『虚無への供物』批判や江戸川乱歩批判、U・エーコ批判は、無批判な(自堕落な、甘えきった)自己肯定と、それに由来する権威者への感情的否定(=権力志向の裏返し)、またそれを糊塗するための「空疎な形式論理」に塗り固められていた。そのくせ小心な法月が、大見栄を切って批判してみせるのは、「故人」「外人」「天皇」といった、こちらの拳が相手に届くこともないかわりに、相手から逆襲される怖れもまたありえないといった「無難な相手」に限定されているのである。つまり、すくなくとも以前の法月は、何のリスクも負うことなく、それでいて自分が否定した相手の名前の権威(ビッグネーム)によって、逆に自己の行為を権威づけようという、じつに姑息なことを、臆面もなく公然とやってのけていたのである。
実際、当時の法月が、「身近な人間」に対しての場合、どの程度のことやれたのか。その実例が『小説トリッパー』(一九九五 冬季号)に発表された、法月の短編小説「禁じられた遊び」(単行本未収録)である。この作品も、ミステリ作家であり名探偵でもある作者と同名の主人公の登場する、シリーズ作品の1篇だが、この作品のなかで主人公は、作家生活の愚痴を(担当編集者に、原稿が書けない言い訳として)次のように語る。
『「エチケット云々とおっしゃるのなら、こっちも言い分はありますよ。そもそも、さいしょにお話があった時、ぼくはスランプで、雑誌の締め切りが守れる自信がない、迷惑をかけることになるだけだから、できればお断りしたいと申し上げたはずです。それで一応、お互いに納得したはずだと思いますが。(中略)そうでしたね。**さんが、おたくの雑誌でミステリー特集を企画すると言い出してから、どんどん調子がおかしくなったのです。(中略)ぼくは**さんにはいろいろお世話になっていますからね。**さんから、こうしろと命令された場合、なかなか首を横に振るわけにはいかないのです」
「しがらみというやつですね」
「(中略)そんなわけで、ぼくはここ一年間ずっと、**さんの命令に従って、一所懸命ご奉公してきた次第です。自分の仕事を犠牲にしてね。**さんは、こっちの都合とか考えないで、勝手に頭越しに話を決めちゃう人ですから――法月君、今度『G思想』で〔メタ・ミステリー〕特集というのをやることになったから、きみは、百枚の評論を書きたまえ。もう編集長に話は通してある。ぼくは対談をやるから。法月君、今度『Y時代』で〔本格ミステリーの現在〕という連載評論の企画をやることに決めたから、第一回はきみが書きたまえ。ぼくは他誌の要約を載せるから。法月君、今度はA新聞が出す『T』という雑誌で〔新本格〕特集をやることになったから、きみは短篇を書きたまえ。いや、もうそういうことに決まったんだ。ぼくはS田荘司と対談をするから――いつもこんな調子でね。もちろん目をかけてもらって、引き立ててくれるのはありがたいと思ってますし、**さんの推理文壇に対する提言のひとつひとつに賛同している人間ですから、ぼくも日本のミステリー文化向上のために、できる限りの努力はしようと思っていますよ。現にそうしてきたつもりです。/だけど、いくら何でもあんまりなんじゃありませんか。だってぼくはここんところ、**さんに命じられた仕事をこなすのが精一杯で、予定の原稿なんか全然書けずにいるんです。そこのところを、もうちょっと考えてほしいなってオモいますよ。ぼくは**さんとちがって、注文に応じていくらでも原稿が書けるような、そんな達者な作家じゃありません。自分ができるからって、ほかの人間もできるとは限らない。**さんは、強制はしていないって言いますけどね、むげにいやだと言ったらカドが立つでしょう? ぼくはもともと、争うごとを好まない、穏やかな人間なんです。(中略)同業者はもっと仕事を選べって言いますけど、そんなに偉くなったとは自分では思っていない。来るものは拒まず、とそういうつもりでやってますよ。だけど、物理的にこなせない仕事はしようがない。前から何度も言ってますが、ぼくは仕事が遅いんです。才能も技術もないから(中略)うんうん言いながら(中略)書いているんです。下手だから。まじめだけが取り柄です。頭に馬鹿がつくって、言う人もいるけど。(中略)一所懸命がんばって少しでもいい仕事をしようって。骨身を削って努力してるんです。それを忘れてもらっちゃ困る」
「なるほど(中略)お話はよくわかりました(中略)――しかし、それとこれとは話がちがいますからね。**さんも関係ありません。当面の問題はこの原稿の続きをどうするのかということに尽きるわけです」』
『**さん』が笠井潔、『G思想』が『現代思想』、『Y時代』が『野生時代』、『A新聞が出す『T』という雑誌』が「朝日新聞が出す『小説トリッパー』」、『S田荘司』が「島田荘司」であるというのは言うまでもない。いずれも、事実に基づいた記述である。
見てのとおり、このような「泣き言(=愚痴)」を臆面もなく公開できる人間だからこそ、私は「最近の法月綸太郎」について、
> なぜ、このところ法月綸太郎は、評論活動から遠ざかってしまったのか、そしてなぜ「現代本格の行方」への執筆がないのか。――答えは明白である。売れている小説家が、わざわざ売れている同業者の売れている作品について、とやかく注文をつける理由も暇もない、ということだ。言い換えれば「金持ち喧嘩せず」である。まして、法月綸太郎は「顔見知りの批判など出来ない小心者」なのだから、同じ関西に住む、現存する(故人でない)ミステリ作家としての先輩である東野圭吾を、批判したいなどと思うはずがない。たとえ、笠井潔から「現代本格の行方」への執筆打診があったとしても、作家的充実期にもあり、「第5回本格ミステリ大賞」を与えられた法月としては、「今は創作に専念したい」くらいの言い訳をしたであろうことは、容易に想像できよう。
と書いたのである。
(以下略)
初出;2021年1月5日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
