
紺野天龍 『神薙虚無最後の事件』 : 洗練のない〈物量サービス作戦〉
書評:紺野天龍『神薙虚無最後の事件』(講談社)
相沢沙呼の『medium[メディウム] 霊媒探偵 城塚翡翠』を、刊行後3年を経たつい先日読み、とても面白かったので、レビューを書いた。
この『メディウム』は、刊行当時からとても評判の良い作品だったのだが、私はその評判を信じなかったため、今ごろ読むことになったのだ。
私が、『メディウム』への反発と不信感を募らせたのは、この本の帯に、先輩ミステリ作家たちの推薦文がズラリと並べられており、いかにも「業界あげて売りにかかっている」という、悪印象を受けたせいである。
しかし、実際に作品を読んでみると、これは大変よくできた「本格ミステリ」であり、先輩作家たちの推薦文も、決して「売らんかなの、過大なヨイショ」ではないことがわかった。そこで「やはり、多くの作家たちが推薦文を書くからには、それなりのものなのかもしれないな」と、多少は反省もした私だったので、同様に、先輩作家たちの推薦文がズラリと並んだ本作『神薙虚無最後の事件』を、今度は刊行と同時に購入し、2ヶ月後の今、期待を持って、やっと読んだという次第である。

で、結果はどうであったか?
結論からいうと、「それなりに楽しめる、努力賞作品」という感じで、先の『メディウム』が5年に一度の傑作だとすれば、本作『神薙虚無最後の事件』の方は、年間ベストテンに「入るかなあ」くらいの作品でしかなかった。
そして、なにしろ直前に読んだのが傑作『メディウム』だったので、個人的には、本作は完全に期待はずれだった、と言えるだろう。
本作『神薙虚無最後の事件』は、作中でも言及されているとおりで、「作中作」の謎について、登場人物たちが自分の推理を次々と披瀝するという、アントニイ・バークリーの古典的名作『毒入りチョコレート事件』(あるいは、アイザック・アシモフの『黒後家蜘蛛の会』)の形式を踏まえた作品である。
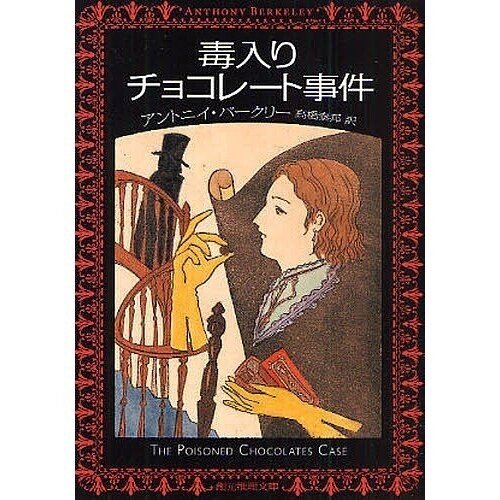

一般に、「先の推理を否定して、さらに信憑性の高い推理が次々と披瀝され、最後は本命の名探偵によって、完全な真相が明かされる」というパターンのミステリを、「多重解決ミステリ」と言う。
このパターンでは、後で披瀝される推理ほど「真相に近い=良く出来ている」という形式なのだが、本作『神薙虚無最後の事件』の場合は、大筋でこのパターンに沿ってはいるものの、どの推理が「真相」なのかは、作中世界でも「確定」されるわけではなく、「一番もっともらしい推理」が「最後に来る」というに過ぎない。つまり「じつは、もっと、もっともらしい推理も可能なのかもしれない」という「余地」を残した作品なのだ。
したがって、本作の魅力は「最後に、神のごとき名探偵が、完膚なきまでに真相を解き明かす」というカタルシスにあるのではなく、「並列的にバラエティーに富んだ推理が語られる、その贅沢さが楽しい」といった作品になっているのである。
つまり、この作品の根底には「物的証拠も残されていない、過去の事件に関する推理なんて、それが真相を言い当てている保証などない」という「リアリズム」があり、だからこそ「おもしろい推理がたくさん味わえるのなら、それで(贅沢で)良いじゃない」というスタンスでの、「娯楽」に徹した作品なのだ。
もちろん、これはこれで、ひとつの立場ではあるのだけれど、しかし、言ってみれば、伝統的な本格ミステリが持っていた「いかに真実らしい嘘を構築し、その嘘をつき通して、読者をねじ伏せられるか否か」といった「真剣さ=大真面目さ」が、本作には無い。
「嘘をつくなら、つきとおせ。それがフィクションの使命だ」というのが「古典的なスタンス」だとすれば、本作の場合は「どうせ嘘なんだから、嘘であることを前提にして、精一杯あれこれ工夫して楽しめばいいじゃない」という「軽い」スタンスなのだ。
つまり、「古典的な本格ミステリのスタンス」が「近代合理主義的権威主義」を反映したものだとすれば、本作の場合は、まさに「ポストモダン時代の本格ミステリ」(「逃げろや逃げろ、どこまでも」浅田彰『逃走論』)であり、「ポストモダン小説としてのライトノベルの時代における本格ミステリ」だと言えるのである。
だから、どちらが「正しい」ということではないのだけれど、しかし、やはり本作には、「どうせ」という構えにおける「弱さ」があるように思う。著者には、読者を問答無用でねじ伏せてしまおうという「迫力」が無く、せいぜい読者を「接待して楽しませよう」という感じなのだ。
したがって、前記の『メディウム』を『「作者と読者の知的ゲーム」としての「本格ミステリ」としては、稀に見る傑作であると断じていい。』と絶賛した私としては、本作『神薙虚無最後の事件』における作者のスタンスは、最初から「物足りない」。こちらはすっかり「真剣勝負」をする気だったのに、結果としては「接待ゴルフ」だった、という感じなのだ。
だから、この作品も作者のスタンスも、否定しないけれども、「いまさらラノベを読む暇はない」というスタンスで読書をしている者としては、本作は、いかにも物足りない作品だったのである。
○ ○ ○

ちなみに、本作に付された、推薦文を紹介して、その解説をしておこう。「嫌がらせ」である。
活殺自在に読者を手玉にとるミステリセンス ーー辻 真先
そうかもしれないが、詐欺と同じで、フェアプレイ精神には薄い作品だろう。「面白ければ、それでいいよ〜♪」的な。(元ネタ・石川智晶「美しければそれでいい」)
多重推理の果てに現れる新たな景色 ーー麻耶雄嵩
まあ、『新たな景色』というのは、作中レベルでは、そうなっていて当然だし、「ミステリとしての新たな景色」という意味なら、それは、そのポストモダン性という意味において「嘘ではない」ものの、「新しいものが、必ずしも良いものだとは言っていない」という「逃げ」が担保されている点で、この推薦文は「叙述トリック」のペテンだとも言えよう。
虚構であろうと虚無ではなく。ただ、万雷の喝采を ーー奈須きのこ
何も言っていない、ただ思わせぶりな文章。奈須きのこらしいと言えば、らしい。
読み進めるうち、この謎に本気で挑戦せずにはいられなかった ーー今村昌弘
まあ、このパターンの作品なら、たいがいはそうでしょうね。
論理遊戯【パズラー】生まれ、戯言拳闘【メフィスト】育ち。擦り切れ方を忘れかけた、ぼくらのための物語 ーー青崎有吾
これは、この作品の「出自の解説」にはなっているが、作品の出来の保証にはなっておらず、「これは推薦文ではない」という、一種のペテンだ。
名探偵の信念と贅沢な趣向。これは、懐かしくも幸福な玩具【おもちゃ】箱だ ーー阿津川辰海
青崎有吾の適切な「解説」に比べると、『懐かしい』というアナクロニズムにおいて、ちょっとズレている。昔、島田荘司が自作『斜め屋敷の犯罪』を「英国の香りのする本格推理物」的な作品だというような自己紹介をして、マニアから「それは違うだろう」とツッコミを入れられたのと同じパターンの「勘違い」。
何と技巧と細工に満ちたデラックスな探偵小説世界か ーー城平京
「サービス満点のコテコテ作品」という意味では、確かにそのとおり。だけど、もう少し「洗練」されていて欲しかった、とは思わなかったのだろうか?
粗削りながら燦然と輝きを放つ才能の原石。瑞々しく魅力的な多重解決ミステリをご堪能あれ ――知念実希人
こないだ出てきたばかりの新人だと思っていたが、すでに中堅くらいにはなっていたのか。このネトウヨ作家さんは。
(2022年8月12日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
