
パトリシア・ハイスミス 『女嫌いのための小品集』 : コワモテのヒーロー
書評:パトリシア・ハイスミス『女嫌いのための小品集』(河出文庫)
パトリシア・ハイスミスを読むのは、1990年に翻訳の刊行された『11の物語』以来だから、じつに30年ぶりの2冊目ということになる。
もともとミステリファンだったから、無論、ハイスミスの名前はよく知っていたのだが、私は「謎と論理と意外性」に重点の置かれた「本格ミステリ」のファンであり、ハイスミスは「感情や情念」に重きを置いた「サスペンス」の作家ということだったので、ハイスミスには、ほとんど興味がなかった。
それに私の場合、女性作家には、ジャンルを問わずあまり興味が持てなかった。
もちろん、アガサ・クリスティやクリスチアナ・ブランドに代表されるとおり、女性の「本格ミステリ」作家というのもいるにはいるのだが、あくまでもそれは「例外」的な存在であって、女性作家というのは、おおむね「情」を重きをおく傾向が強いので、「理屈」を重視する(好きな)私には合わなかったようである。
私が「人間心理」に興味があると言っても、それは「論理的に理解したい(解明したい)」ということであって、「共感したい」ということではなかったのだ。一一したがって、パトリシア・ハイスミスには、これまでほとんど縁がなかったのである。
30年前に『11の物語』(ミステリアス・プレス文庫)を読んだ時も、なぜ読んだのかと言えば、たしか「年間ベストミステリ投票」の先駆けである『このミステリーがすごい!』で、この作品集がランクインしていた(海外編第9位)というのと、短編集だということと、ミステリというよりは「奇妙な味」系の小説集のようであったからだ。
長編を読んで自分に合わなかったら時間の無駄だし、ミステリとしては期待できない。しかし、短編で「奇妙な味」系なら、ミステリとしてではなく、普通の小説として読めるのではないかと、そう考えたのである。
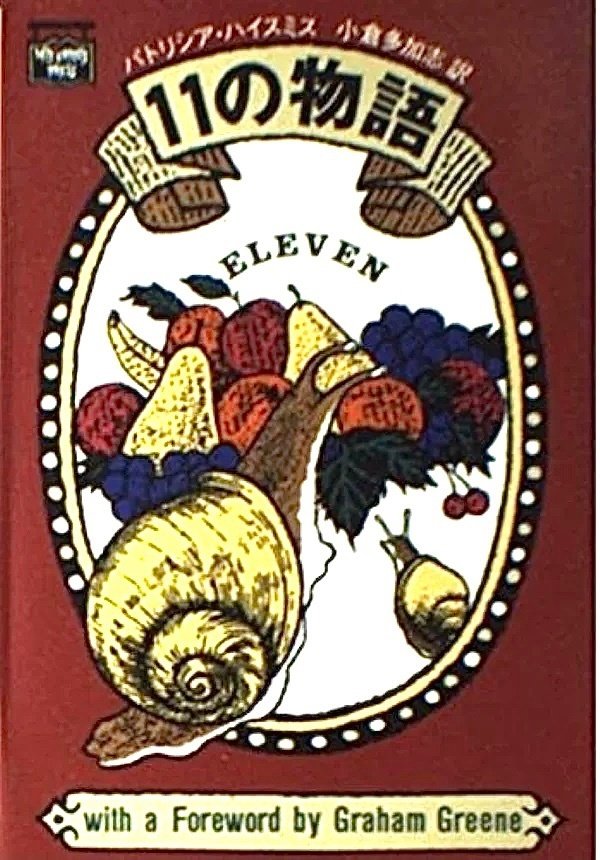
で、結果はというと、たしかに「奇妙な味」系の「変な小説」ではあるのだが、私には、何が面白いのか、ぜんぜんピンとこなかった。「これがそんなにすごいのか? これが面白いと本気で思える人が、そんなに大勢いるの?」と、そんな感じだったのである。
だからこそ、今回『女嫌いのための小品集』を読むに至るまで、じつに30年のブランクがあったのだ。
では、なぜ今さらハイスミスを読もうと考えたのか。
まず最初のきっかけは、私がわりと好きな「精神科医作家」の春日武彦が、その著書の中で、ハイスミスの短編、たしか『ゴルフコースの人魚たち』(扶桑社ミステリー)所収のどれか(タイトル失念)に触れていたからである。つまり、ミステリとしてではなく「奇妙な心理」を描いた作品として、春日はそれに言及していたのだ。
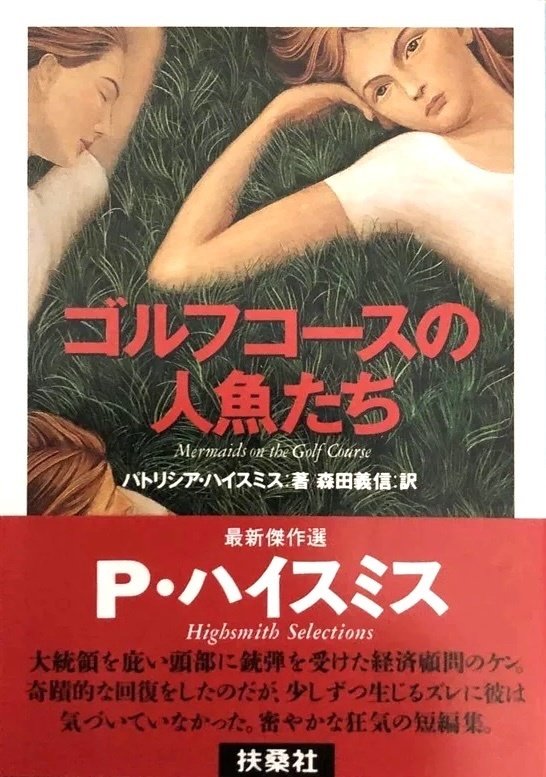
この春日武彦という人は、私の表現で言うなら「趣味で精神科医になった人」で、その種の「小説」を、じつによく読んでいる。
「精神医学」関係の本を読んでいるのは、「読書家」の精神科医なら何も珍しいことではないが、春日の場合は「小説」を、ノンジャンルでよく読んでいるのだ。そして、自身の「精神障害系読み物」の著作の中で、しばしばそうした小説に言及するのだが、SFであれミステリであれ、メジャーな作品とは言いがたい、異常心理を扱った作品、あるいは、それに近い「描写」のある作品をマニアックに紹介してくるので、「人間心理」に論理的な興味を持つ私は、春日の著作に興味があるとともに、そこで紹介されている小説にも、おのずと興味を持った、という次第である。
しかしまあ、興味を持ち、その本を入手したからといって、それだけで、すぐに読むというわけでもなければ、必ず読むというわけではない。
私は、とにかく興味の範囲が広いので、あれこれ興味を持って、あれこれの本を買うため、なかなか読めないうちに、そうした本の半分以上を積読の山に埋もれさせてしまうという生活を、40年以上送ってきた人間なのだ。
だから、春日武彦の著作に触発され、数ヶ月前に「ひさしぶりに、パトリシア・ハイスミスの本を読んでみるか」と思って以降、すでに私は、本書『女嫌いのための小品集』と前述の『ゴルフコースの人魚たち』、それにハイスミスの作品も含まれているアンソロジー『厭な物語』(文春文庫)の3冊を入手していた。
だが、これらはいずれもずいぶん前に刊行された本で、必ずしもいま読まなければならない本でもないから、またもやどうしても後回しにしてしまっていた。

ところが、先日、映画を観に行ったところ、ハイスミスのドキュメンタリー映画の予告編が流れたので、「なんで今時?」とは思ったものの、これは「観なければ」と思った。そしてその前に、小説も読んでおきたいと思い、今回『女嫌いのための小品集』を読むことにしたのだ。『ゴルフコースの人魚たち』より、こちらを優先したのは、こちらの方が薄いし、掌短編集なので、すぐに読めると思ったからである。
ちなみに、問題の映画『パトリシア・ハイスミスに恋して』の公開は、来たる11月3日で、もう5日後に迫っている。
この映画の予告編で、私の興味を惹いたのは、ハイスミスがレズビアン(女性同性愛者)であり、それで若い頃には色々と苦労があったというようなことが紹介されていた点だ。私はそのことを、そこで初めて知ったのだ。
とは言え、私自身は、いま流行りの「百合」にも「レズビアン」にも興味はない。
むしろ「ホモセクシャル(男性同性愛)」の方に、継続的な興味を持ってきた。というのも、私が好きな作家には、中井英夫や赤江瀑といったホモセクシャルの作家がいたからだ。彼らの作風と、その性的傾向が、どのような関係にあるのかという点に興味があったのである。
したがって、パトリシア・ハイスミスについても「レズビアン」であること自体には、さほど興味はなく「まあ、苦労もあっただろうな」という、性的マイノリティーに対する同情こそあれ、作家に対するものとしての興味はなかった。
だが、以前読んだ『11の物語』の「独特な毒や屈折」が、その「性的マイノリティー」性に由来するものなのではないかと、はたと気づいて、ハイスミスという作家に、というよりも、ハイスミスという人に、興味を持ったのである。

だから、もはや、彼女の小説については、小説として「面白いか否か」「私に合うか合わないか」は、問題ではなくなった。
私の興味は「この歪みや苦さは、どのようなところからどのように出てきたものなのか?」というところにあり、それを「論理的」に「謎解き」したくなったのである。
○ ○ ○
そんなわけで、本書『女嫌いのための小品集』である。
本書には3ページほどの掌編から、20ページほどの短編までが収められており、それで「小品集」という名称になったのであろう。
訳者である宮脇孝雄によると、本書は書き下ろしで、ドイツ語に翻訳されてスイスの出版社から刊行された後に、原語本が遅れて刊行されるという変則的なかたちで刊行されたものであり、これは、かねがねハイスミスが、英語版の版元に不満を抱いていたからのようだ(ちなみに、スイスの公用語は、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の4つである)。

これも、宮脇孝雄の「解説」によると、本書の英語原題は『女嫌いのための小品集』ではなく「女嫌いの小品集」ということになるそうだ。つまり、「女嫌いである読者のために書いた」のではなく、「女嫌いの作者が書いた」作品集だというニュアンスのようなのだ。
すると、ハイスミスが「レズビアン」であることを知っている私たちは、「レズビアン」であるハイスミスが「女嫌い?」というところに、当然、ひっかかりを覚えるだろう。一一だが、だからこそ、面白い。
よく言われるように「好きと嫌いは表裏一体」なのだから、好きだからこそ「理想を求め」、それが得られないからこそ「憎む(嫌う)」ということになるというのも、ごく当たり前の心理であるし、だとすれば、ハイスミスが「女嫌い」であっても、なんの不思議もない。
そして、そんな「女が好きだからこそ、女嫌い」なハイスミスであれば、その作品に「独特のねじれや苦さ」があるのも、論理的な必然だとも言えるだろう。
また「女好きだからこそ、女嫌い」などという「屈折した」小説家が、感じの良い素直な小説を書くなんてことの方が不自然だし、「論理」よりも「感情や情念」に傾くというのも、自然なことなのではないだろうか。

で、本書を読んでみると、大雑把に言って「変な女」や「変わった女」「極端な女」たちが語られた作品ばかりであり、脇の男性たちの方は、比較的「まとも」であり、女たちに、いいように振舞わされるというパターンが多い。
つまり、「男性」の登場人物には、作者の「悪意」が向いていない。さらに言えば「興味がない」から、ひと通りの造形しかなされていない、という印象が強いのだ。その意味で、やはりハイスミスは「女が好き」なのであろうし、だからこそ「女が嫌い」であり、かつ「男には興味がない」ということになって、まとめて言えば、これも宮脇孝雄が言うとおりで、ハイスミスは「人間嫌い」だったということになるのではないだろうか。
『 たしかに、「男たらし」「ダンサー」「天下公認の娼婦」「動く寝室用品」「犠牲者」などで描かれた女性たちは性的に放埒だし、「寝たきりの女」「小公女」の主人公は嘘をつき、「陽気な原始人ウーナ」「女流作家」「芸術家」のヒロインたちには芸術が理解できず、「片手」の若い娘はエゴイストで、「出産狂」「沈黙の義母」「純潔主義者」「福音伝道家」「完全主義者」の一見善人風の女たちは、結局、偏執狂である。
そんなところから、表面的な女嫌いのメッセージを読み取ることも可能だろう。しかし、もっと根深いところには、女嫌いではなく、人間嫌いの感情が隠されているように思われる。人間嫌いという言葉を使うと身も蓋もないが、短いがゆえに直截なこの掌編群には、何か孤独に似た赤裸々なものが露呈されてるような気がして仕方がない。もっとも、この著者は、スイスからニューヨークへ飛んで、自分の著書にばりばりサインをするような人物だから、その孤独を楽しんでいるのだろう。』
(P202〜203、「訳者あとがき」より)
そのとおりだと思う。
ハイスミスの面白いところは、「人間嫌いの引きこもり」なのではなく、「人間嫌いの攻撃家」だったようである点だ。
普通の人は、そんな面倒くさい奴は嫌いだと言うかも知れないが、私は、当たり前に「人間嫌いの引きこもり」であるよりは、よほど「人間嫌いの攻撃家」に方が「好み」である。
で、ハイスミスの、その「攻撃性」を示しているのは、上の部分で、宮脇孝雄も言及している、芸術がわからないのに芸術家ぶりたがる女たちへの嫌悪を描いた「芸術家」や、当時、盛り上がっていた「フェミニズム」運動への反感、と言うか、正確には「フェミニストたち」への反感を描いた「犠牲者」だろう。
要は、「わかりもしないくせに、芸術家ぶってんじゃねえ、このバカ女が!」ということであり、「勝手なことをほざいてんじゃねえ、この被害者ヅラしたバカ女が!」というのが、ハイスミスの「正直な気持ち」であり、「芸術」あるいは「芸術家」そのもの、あるいは「フェミニズム」や「フェミニスト」そのものを批判しているのではなく、(同性愛者の苦しみが理解できない、フェミニストや宗教家や芸術家気どりなどの)「わかっていない、バカが大嫌いだ!」ということだったのではないだろうか。
したがって、「人間嫌い」かつ「攻撃的」なハイスミスの作品が、普通に読めば「厭な小説」だというのは、当前の話であろう。
だが、そうした「当たり前の感性」を持っている私とは違い、世間にはハイスミスに共感する読者が、決して少なくないようなのである。
前述のとおり、『11の物語』が「このミステリーがすごい!」で上位にランクされたのと同様、例えば、本書『女嫌いのための小品集』のAmazonページを見ると、1990年刊行の本とはいえ、なんと現時点で166もの評価が寄せられており、しかもその平均点が「5点満点の4点」なのである。一一これは、一体どうしたことなのだろうか?
私が思うに、たぶんこれは、ハイスミスのように毒を吐けない、抑圧された女性たちが、それだけ世には多い、ということなのではないだろうか。
今では、多少なりとも女性の権利が広く認められるようになったとは言え、しかし我が国は、まだまだ女性の社会進出率が、先進国では最低レベルだというのだから、女性の多くは、まだまだ社会的に抑圧されており、言いたいことを言えていない蓋然性が高い、ということである。
つまり、こうした女性たちにとっては、ハイスミスは、自分の想い(怒りや恨みつらみ)を、ズバッと、あるいは、ねっちりと代弁してくれる、一種の「ヒーロー」なのではないか。

タバコを片手に、ジロリと睨んで「レズビアンですが、何か?」なんて感じのハイスミスが、多くの女性の憧れなのではないだろうか。
したがって、ドキュメンタリー映画の『パトリシア・ハイスミスに恋して』というタイトルの意味もまた、そういうこと、なのではないだろうか。
そんなわけで、映画の方も楽しみである。

(2023年10月29日)
————————————————————————————————————————
【補記】(2023年12月5日)
本稿の続編とも呼ぶべき、下の拙稿「映画 『パトリシア・ハイスミスに恋して』 :十字架につけられたパトリシア」
において疑義を呈した、ハイスミスの実像について、「vincent-tenihore」さんという方が、徹底追求した記事「パトリシア・ハイスミスに恋して、恐怖して、困惑して!?」をアップされました。
映画『パトリシア・ハイスミスに恋して』では、ほとんど隠蔽されていたも同然の、ハイスミスの驚くべき実像が、そこでは多角的に炙り出されています。
こうした突っ込んだ内容は、日本語にはほとんど翻訳されておらず、きわめて貴重なものと思いますので、パトリシア・ハイスミスに興味をお持ちの方には、ぜひ読んでいただきたく、ご紹介させていただきました。
(2023年12月5日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
