
麻耶雄嵩 『メルカトル悪人狩り』 : 〈転倒したロジック〉の合理性
書評:麻耶雄嵩『メルカトル悪人狩り』(講談社ノベルス)
麻耶雄嵩については、デビュー作からのつきあいだが、全作品を読んでいるというわけではない。
デビュー作『翼ある闇 メルカトル鮎最後の事件』の初読時の感想は「なんだこれ?」で、変な作家が出てきたな、という以上のものではなかった。しかし、次の長編『夏と冬の奏鳴曲』については、作者が何をしたのか、したかったのかが理解できなかったものの、何かをしているというのはハッキリとわかったので、それが読み解けない自分が歯がゆく、ずっと「いつか解読してやる」と引っかかり続けてきた。
その後の作品も、読んだり読まなかったりだったが、『神様ゲーム』には衝撃を受けた。まさか「ミステリ」に「本物の神様」を登場させるなんて、そんなのありなのかという驚きだったが、しかし、それは痛快な驚きだった。とても私好みの「常道からの外し方」だったのである。
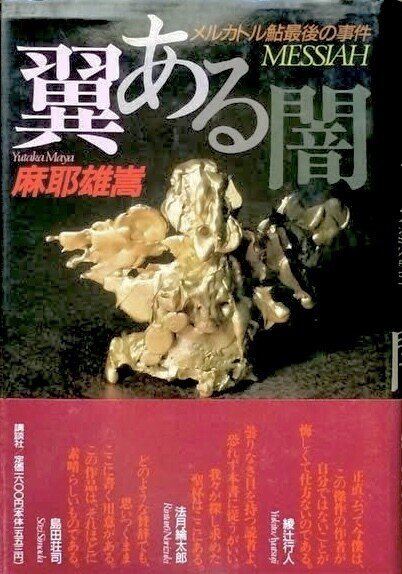
これも、まったくたまたまなのだが、麻耶雄嵩ともミステリとも関係のない動機で、私は「宗教」の研究を始め、その手始めとして、「聖書」の通読から初めて、「キリスト教」の本をあれこれ読んだ。
すると、麻耶雄嵩の作品は「キリスト教」的な概念への言及が多いことに気づいた。「あれっ、麻耶雄嵩って、もしかしてクリスチャン?」。
一一そう言えば、京都大学ミステリ研究会の会誌『蒼鴉城』に掲載された、『翼ある闇』の原型作品のタイトルは『メサイア』(メシア=救世主)ではなかったか。
しかし、麻耶作品は「正統的なキリスト教」のものではなく、その世界に満ちている「聖霊」は、邪悪なもの(闇=見通せない〝気〟)であった。それは、人間に対して、とても意地の悪い「神」であり、言うなれば「邪悪な神」である。
となると、この世界観は「グノーシス主義」的なものなのではないか、と考えた。『神様ゲーム』の「神様」からして、まさにそうではないか。
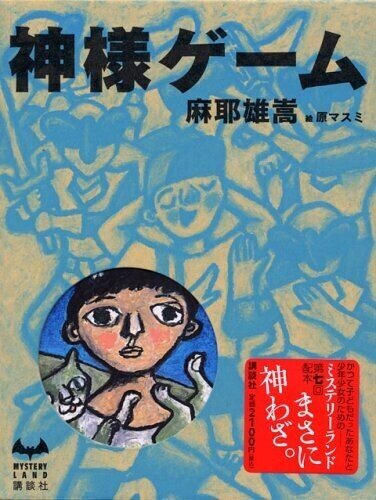
『グノーシス主義には様々なバリエーションがあるものの、一般的に認められるのは、「反宇宙的二元論」と呼ばれる世界観である。
反宇宙的二元論の「反宇宙的」とは、否定的な秩序が存在するこの世界を受け入れない、認めないという思想あるいは実存の立場である。言い換えれば、現在、我々が生きているこの世界を悪の宇宙、あるいは狂った世界と見て、原初には真の至高神が創造した善の宇宙があったと捉える。
グノーシスの神話では、原初の世界は、至高神の創造した充溢(プレーローマ)の世界である。しかし至高神の神性(アイオーン)のひとつであるソフィア(知恵)は、その持てる力を発揮しようとして、ヤルダバオートあるいはデミウルゴスと呼ばれる狂った神を作った。ヤルダバオートは自らの出自を忘却しており、自らのほかに神はないという認識を有している。
グノーシスの神話では、このヤルダバオートの作り出した世界こそが、我々の生きているこの世界である、と捉えられる。』
(Wikipedia『グノーシス主義』・「反宇宙的二元論」の項より)
つまり、「リアルな世界(の現実)」を論理的に理解しようとした場合、「神義論」的に見て、この世界は「正統キリスト教の神=愛の神」が創ったとは、とうてい信じられないという人たちが、今も昔も少なくなかった。常識的・論理的に見て、「この世界」を創った神とは、実は「邪悪な神」なのではないか、と考えた人がいても、なんの不思議もないのである。
今なら「もともと神なんて(善なる神も悪なる神も)いない」とか「もともと、この世界に善悪などない。それは進化論的できあがった、種の保存のための特殊な本能的フィクションだ」と考える人も出てくるが、昔のことだから「なんらかの神はいる」という前提で、「この世界」の現実を「論理的」に説明しようとしたために、「邪悪な神」なんてことを考えなくてはならなかったのである。
○ ○ ○
さて、「宗教」談義はこれくらいにして、本書『メルカトル悪人狩り』について考えてみよう。
本作には、8本の掌・短編が収められているが、いかにも「メルカトル鮎もの」らしい「変な作品」が多い。
何が変なのかと言えば、メルが露骨に「神がかり」なのである。作品の中で、思わせぶりに暗示されるのだが、メルの言動には「事件が起こる前から、結果を知っていた」かのようなところがあり、その点で、当たり前のミステリ読者を困惑させ、その神経を逆撫でする。
その典型的な作品が、本作品集の掉尾を飾る「メルカトル式捜査法」で、この作品はキリスト教の「予定説」のごとく「原因と結果が転倒している」のだが、そこがいかにもメルカトル鮎らしくて、ユニークなのだ。
しかし、これをどう理解すればいいのだろう。
例えば、メルに「囁くもの」が「ヤルダバオート(デミウルゴス)の神」であり、メルの「叡智」とは「グノーシス」だと考えたら、つじつまが合うと言うか、「合理的」に「論理的」なのではないか。つまり、メルとは、「作中世界」に「神から遣わされたメシア=救済者」である。だから彼には「父=神」の声が聞こえるのだ。
無論、われわれの世界における「リアリズム」的に「そんなこと、あり得ない」という意味では、メルの住む世界は確かに「非合理的」ではあるけれども、そもそも「小説の中の世界」が、私たちの「現実世界」と同じでなければならないという道理も義理もない。要は「その世界」の中で、ロジック(論理)が一貫してさえいれば、それは「合理的」なのだ。(だからこそ、ゾンビが登場する本格ミステリだって成立するのである)
そもそも「本格ミステリ」の「世界」とは、狭隘な「お約束」の世界であり、言うなれば「ロジックのファンタジーランド」である。だからこそ「後期クイーン的問題」なんてことも、問題になり得る。
「作中の世界」の外に特権的な「現実の世界(私たち読者の世界)」は存在せず、「作中人物」たちは「自由意志」で「生きて活動している」ことになっている。言い換えれば、「作品の世界」の外に「創造神としての作者」など、存在しないことになっている。それを認めてしまったら、突然、名探偵が空を飛ぼうが、犯人が分裂して100人になろうが、壁抜けをしようが、何でもありだから、「ミステリにおける、自己完結的な形式論理」性が保てなくなってしまうのだ。
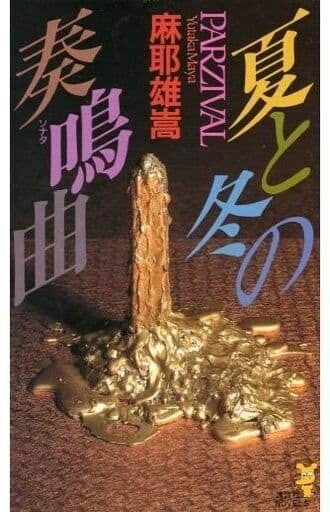
しかし、「作品の外の作者」を認めてしまえば、「ミステリにおける形式論理」は成立しなくなるけれども、論理的な「小説」が成立しなくなるわけではない。いわゆる「メタフィクション」と言われる作品は、「作品の外」の「存在」を、なんらかのかたちで認めた(開かれた)上で、現に破綻なく成立している。
だから、ミステリが「リアルな論理性」にこだわるのであれば、「ミステリにおける形式論理」を否定することは、造作もないことだ。もともと無理のある「お約束の世界における形式論理」だったのだから、例えば「作者という神」の存在を認めた上での「論理的なミステリ」が書かれても、それはそれで、まさしく現実的に「論理的なミステリ」なのである。
言うまでもなく「作中探偵のメルカトル鮎」は、「作者という神」の要請にしたがって行動しており、ただ、その事実を「お約束」破りにも「隠さない」という点が特殊なだけで、それ以外の「内実」は、普通の「名探偵」と何も変わらない。
つまり、メルカトル鮎が、事件の起こる前から「事件の真相」を知っているかのように振る舞うのは、事実「知らされている」からなのである。名探偵も、被害者も、その他の脇役も、実はみんな、「作者」が「あらかじめ決めた」とおりに動くのが、「本格ミステリ」だからだ。
そうした意味で、麻耶雄嵩のミステリとは(アンチではなく)「メタ本格ミステリ」であると言えるだろう。少しひねくれてはいるものの、「本格ミステリ」が好きだからこそ「誤魔化さずに、その真相を明らかにしたい」。だから「名探偵は、論理的に正解にたどりつくのではない。あらかじめ決められたシナリオのロジックを忠実になぞっているだけだ。だが、それが面白いんだろ?」と、「本格ミステリ」の「お約束」をバラしてしまう。これは「好きすぎて、解剖せずにはいられない」といった感覚・衝動なのかもしれない。
ただ、私としては、麻耶雄嵩のこうした「特異性」を「本格ミステリへの逆説的な愛」のかたちだなどと、きれいごとに回収したくはない。
やはり、そこには独特の「歪み」があるし、その作中に「キリスト教的形象」が多用されるのも、単なる「趣味」だとは思わない。つまり、「この世界」の人間である麻耶雄嵩には、「この世界」らしい、なんらかの人間的背景があるはずだと、私はそう推測するのである。
したがって私は、その「作品」を通じて、麻耶雄嵩という「人間」を腑分けしてみたい。
「作品論」でもなければ、ましてや「ミステリ論」などでもない、「作家論」を書きたいと思っているのである。
一一無論、それはまだまだ先の話ではあるにしても。

初出:2021年9月29日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
