
山沢晴雄 (著), 戸田和光 (編) 『山沢晴雄セレクション 死の黙劇』 : パズル小説にこだわり続けた〈紳士〉
書評:山沢晴雄 (著), 戸田和光 (編)『山沢晴雄セレクション 死の黙劇』(創元推理文庫)
「本格ミステリ=本格推理小説」と言っても、決してひと色ではない。「推理=論理」にこだわる小説形式ではあるものの、「論理性」そのものを重視するのか、「論理性」を道具として使うのか、という違いは、たしかに存在する。そして、後者の場合に重きが置かれるのは、「驚き」である。「謎」があって、それが解き明かされた際に示される「真相」とは、前者の場合だと「納得」が重視されるのだが、後者の場合は「意外性」が求められる。後者の場合には「論理的には納得できるが、しかし驚くべき意外な真相であった」という「ギャップ」の存在が肝心なのだ。
つまり、「論理性」と「驚き=意外性」というのは、「本格ミステリ」を二分し得る「二極」ということではなく、すべての「本格ミステリ」作品が、多かれ少なかれ含み持っている「二大特質」であり、作家によって、その成分のどちらに重点をおくのか、ということでしかない。作風によって、二つの成分の「含有比率」が異なるだけなのだ。
山沢晴雄の「本格ミステリ」は、基本的には「論理性」に重きがおかれており、「意外性」は比較的薄い。だから、どうしても地味になってしまって、「新本格ミステリ」風の「驚愕の真相」的な今風の作風ではないのだが、なによりも「論理性」を重視し、エラリー・クイーン流の作風を愛する、古い「本格ミステリ」マニアなどには、山沢晴雄の古風な作風は、きわめて貴重な稀少種として珍重されることにもなる。
もちろん、山沢晴雄は「パズル小説」しか書けないというわけではない。書こうと思えば、そうではない作品も書けるのだが、やはり山沢のこだわりは「論理的なパズル小説」にあり、専業作家にならなかった山沢が、本職の合間に、好きに書いたのは「論理重視のパズル小説」であり、読者にウケの良い「派手な意外性」や「人間ドラマ」ではなかったのである。
しかし、かく言う私自身は、山沢晴雄の「論理重視のパズル小説」の、良い読者ではあり得なかった。
「驚き=意外性」と「論理性」なら、私は「驚き=意外性」の方を欲してしまうタイプ。もちろん、ただ驚かせるだけなら「ホラ話」や「馬鹿話」で良いわけだが、それではぜんぜん面白くない。
私にとっての「本格ミステリ」の魅力というのは、「驚き=意外性」と「論理性」という、本来であれば「相矛盾する二要素」を「曲芸的に両立させる、その非凡な手際」にあると言っていいだろう。「そんなことあり得ない」はずなのに、それを「あり得る」ものとして、論理的に説得してしまう「超絶的なレトリック」に、私は「本格ミステリ」の魅力を感じるのだ。だから、ただ「論理的」であれば良い、ということにはならないのである。
その点、山沢の「パズル小説」は「驚き=意外性」に欠けている。たしかに「不可解な状況=謎」が描かれはするが、それ自体は「驚き=意外性」をもたらさない。肝心なのは、その「謎」が論理的に解き明かされた際の、結果としての「真相の意外性」でなければならないのだ。
しかし、山沢の「パズル小説」の「真相」は、バラバラのパズルピースが「あるべき場所に、きちんと収まって、真っ当な絵柄が完成する」といった態もので、「なるほど、そうだったのか」という「納得」は得られても、「驚き=意外性」には乏しく、そこが、ゴリゴリの「本格ミステリ」マニアではあり得なかった私には、どうしても物足りないと感じられたのである。
○ ○ ○
私は、山沢晴雄の「パズル小説」が、性分的に合わないと早くから気付きながら、それでも、ずっと「理解したい」と願い続けてきた。普通なら「本質的に合わないものは、どうしようもない」と、あっさりあきらめるのだが、山沢晴雄の場合には、それが出来なかった。なぜか? 一一それは、山沢晴雄という人を、直接知ってしまい、その「人柄」に惚れたからである。「この人の作品なら理解したい。そして、心から褒めて差し上げたい」と思ったのだが、それがなかなか叶わなかったので、ずっと引きずり続けたのである。
私が山沢晴雄を知ったのは、ミステリマニアのサークル「SRの会」の例会においてであった(「SRの会」については、本書「解説」を参照されたい)。時期的には、1980年代の末頃だと思うが、山沢がひさしぶりに例会に参加したのだ。
その頃は、まだ山沢晴雄の再評価のきっかけとなった、手塚隆幸による同人誌「名探偵研究シリーズ」も、甲影会の「別冊シャレード」も出ていなかったから、「綾辻行人デビュー以降」の若いミステリファンでしかなかった私は、山沢晴雄という人を、まったく知らなかった。
私も山沢も大阪在住なのだが、初めてお会いした例会が、大阪例会だったのか京都例会だったのかは、記憶力の弱い私には判然としない。
とにかく、古参の先輩会員から、山沢が『別冊 宝石』誌などの公募で入選したり、鮎川哲也の編んだミステリアンソロジーにその作品が収録されたりしている、知る人ぞ知るアマチュアのミステリ作家であるという趣旨の紹介がなされ、その例会で、山沢の書いた「犯人当て」短編小説による「犯人当て」ゲームが行われた。
しかし、その当時すでに自覚していたのだが、私は「犯人当て」を楽しめるタイプのミステリファンではなかった。ミステリを読みながら「こいつが怪しい」とか「ここにトリックが仕掛けられているのではないか」と考えることはあっても、本気で、つまり、理路整然と根拠を示せるかたちで、犯人を当てようとか、謎を解こうなどとは思わなかった。というのも、私には、そういう能力がないし、そういう読み方が楽しいとも思わなかったからだ。
私は、単純に作品を読んでいき、最後に示される真相に驚いたり、探偵の「謎解きのロジック」に関心したりしたかっただけであり、またそれで十分だったのである。
そもそも私は、チマチマしたことは好きではなかった、また、何より「数字」が好きではなく、「数式」だの「方程式」だのといった「形式論理」が好きではなかった。機械的に、正確に論理を追っていけば、おのずと正解に至るようなものは、面倒くさいだけであり、そこに魅力を感じることはできなかったのである。
だから、「時刻表ミステリ」などには、まったく興味がなかったし、「タイムテーブル」が問題になるような「アリバイ崩しミステリ」にも興味がなかった。
おのずと「犯人当て」にも興味がなく、朗読された山沢の「犯人当てミステリ」で「誰それが何時何分にどこそこを出て、何分後に誰それと会った」とかいった話になってくると、その段階で面倒になってしまい、時間関係や登場人物の動きに関するメモを取ることを放棄し、ひたすら作品をボーッと聞くだけの構えに入ってしまった。当然、正解するどころか、解答を書くことさえ、ままならなかったのである。
そして、他の会員たちが、正解かどうかは別にして、それなりに「論理的推理」を構築して見せるのを見て、やっぱり自分は「正統派の本格ミステリマニア」ではないのだな、という思いを強くしたのである。
このように、山沢晴雄の作品に関しては、最初から(「否定的評価」以前の)「無縁」性を感じさせられた。
山沢の作品を楽しめる人は確実にいるし、その意味で山沢の作品に「ある種の魅力」があるのも確実なのだが、それが私にはわからないのだと確信され、だから「無縁」だと考えたのである。
しかし、山沢晴雄その人については、たいへん好印象を受けた。山沢はまさに「紳士」だったのである。
シックなスーツにきちんとネクタイを締め、半白の髪を綺麗に撫でつけて、黒か焦げ茶ブチの眼鏡をかけた中背で痩せ型の山沢は、私の第一印象では「中学の数学の先生」という感じだった。
つまり、きちんとした紳士なのだが、しかし決して硬いとか真面目くさっているというのではなく、じつに和かで、四十近くも年下の私のような若造にも、他の古株会員に対するのと変わらぬ、丁寧な態度で接してくださった。無論、表面的にそのように振舞っていたということではなく、その振る舞いに、人柄がそのまま表れているとわかったので、私は山沢に対して好意を持ったのである。
そもそも私は、根っからの「反権威」人間だから、年上だからと言って、それだけで敬服することなど出来なかった。無論、社会人だから、最低限の礼儀は踏まえていたが、いざ議論となれば、年上であろうが先輩であろうが、情け容赦なく攻撃したのである。
だから、年上だからといって、自明に「上」意識を持っているような人への評価は厳しかったし、そういう目で「目上の人」たちを見ていた。「この人は、どの程度の人間だろう」という目で値踏みし、それに応じて、心の中で相応の評価を与えていたのである。
私は、20代前半でSRの会に入会して、ほとんど間もなく、会誌誌上で論争を始めた。私が問題提起をし、内部批判をし、反論が返ってくれば、相手が何人だろうと、喜んで再反論をした。すでに半世紀を遙かに超えるSRの会の歴史に残る「問題児」であり続けたという自負が、私にはある。
しかし、そんな私でも、心から尊敬する先輩というのが、何人かはいた。
具体的に名を上げれば、ミステリ研究家と知られる山前譲氏などもそうで、最初に全国大会でお会いした時には、ご尊名も存じ上げず、ただ「気さくで面白いおじさん」だと思っていた。だから、後で、すでにひとかどの人だったと知って敬服したし、その後も私の「問題投稿」に、会誌編集人として真摯に対応してくれたことに、心から感謝した。私自身も「こんなのを投稿されたら、山前さんも編集人として困るだろうな」とは思っていたのである。
ともあれ、そんなふうで、簡単には「既成の権威」になど平伏しない私が、心から尊敬した、SRの会の先輩の一人が、山沢晴雄だったのである。
そして、だからこそ「この人の作品なら是非とも理解したい。そして、心から褒めて差し上げたい」と思い、その後、山沢の作品が、前述の同人誌に掲載されたり、鮎川哲也編の『本格推理』に掲載されたりすると、読んでみようと努力したのだが、やはり私には合わないということを確認するに終わり、やがて「理解できないのなら、無理して理解しようとするより、敬意を持って距離をおいたほうがいい」と考えるようになった。だから私は、手塚隆幸による同人誌「名探偵研究シリーズ」も、甲影会の「別冊シャレード」も、その刊行開始当初から、寄稿者として関わってきたけれど、山沢晴雄に関するものには、書きたくても、どうしても原稿が書けなかった。
山沢からは、長い間、律儀に年賀状をいただいていたが、それにも申し訳なさが募るばかりだったのである。
そんなわけで、山沢晴雄の作品が作品集『離れた家』として公刊されると聞いた時には、本当に嬉しかった。だから、刊行即購入したのだが、やはり読むのは怖かった。購入することで最低限の義理を果たすことは可能だが、そこで無理して読んで面白くなかったら、逆に辛いとも思ったのである。
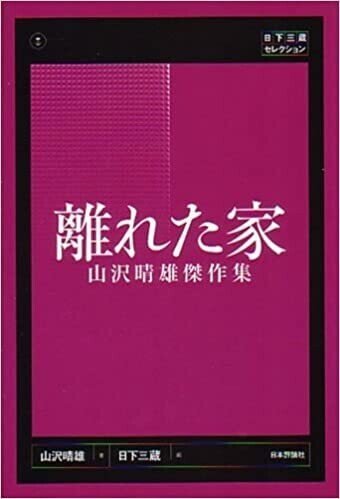
しかし、それでも、無理して読んだ結果としては、『離れた家』を面白かった。
私は、当時の心境を、次のように書いている。
『 商業誌デビューが昭和51年(1976年)というベテラン推理作家、山沢晴雄。その記念すべき第一著作となる『離れた家』(日本評論社)の刊行を前にして、先般、山沢に面識のある「SRの会」のメンバーを中心にした記念パーティーが開催され、私にもお誘いがかかった。だが、私は参加しなかった。できなかったのではなく、すべきではないと考えたから、しなかったのである。理由は簡単。私は山沢晴雄の「よき読者」ではなかったからである。山沢さんについての、私のそれまで評価は、もっぱら「謙虚で誠実な紳士」というお人柄に限定されており、小説については敬して遠ざけさせていただいてきた。昔、SRの例会か何かで山沢さんの出された「犯人当て」が、とにかく複雑難解なものだったので、こんな作風なら私向きではないと、あっさり降参させていただいたという過去があったからだ。
しかし、山沢さんのお人柄にはひそかに尊敬の念を抱いていたので、パーティーには参加しないまでも、『離れた家』は買わせてもらおう、そして読めそうなら読ませていただこう、面白かったならその時初めてその旨を伝えてサインももらおう、しかしまた、面白くなければ、私には縁なきものだったと黙っていよう、と考えた。
書店で『離れた家』を手に取って、ぱらぱらとページを繰ってみると、解説を巽昌章が書いているのが目を惹いた。すこし意外な感じがしたからである。そして読むともなくその解説を捲っていたところ『奇妙な迷宮的感覚』『メタ・ミステリ』『幻想小説』といった、これまた意外な言葉が目を惹いた。私の持っていた山沢晴雄のイメージからは、およそこれほど遠い言葉もないと思われたからである。しかし、山沢晴雄の作品に、そうした側面を読み取ったのだとすれば、巽が解説を書いたというのも充分に頷ける話だし、もしかすると山沢晴雄には私にも読みうる違った顔、山沢の一般的イメージである『難解きわまりない鏤骨の作品を綴る本格の鬼』とはまたひとつ違った顔を持っているのではないかと期待させた。――そして、その期待は裏切られなかった。だからこそ、私はここで山沢晴雄をめぐって何がしかのことを語ろうとしているのである。』
(「知恵の輪の極みに ―― 山沢晴雄をめぐって」、2007年7月17日「BBS アレクセイの花園」掲載より)
山沢晴雄には『難解きわまりない鏤骨の作品を綴る本格の鬼』とはまたひとつ「違った顔」が、確かにあった。そして、それは私にも楽しめるものであった。それを確認できて、私はやっと肩の荷を下ろせたような気分になったのである。
○ ○ ○
そしてこの度、創元推理文庫から「山沢晴雄セレクション」が(全何冊になるかは不明だが)刊行されることになった。その第1弾が、山沢の本領である「パズル小説」を集めた、本書『死の黙劇』である。
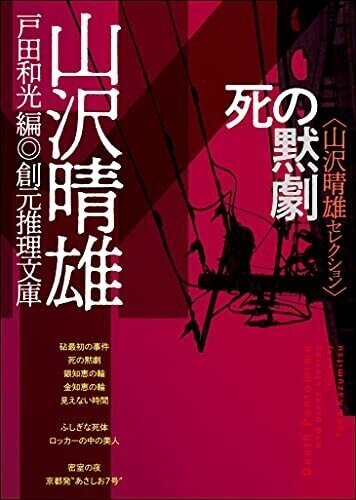
編者は、SRの会の先輩である、戸田和光。
戸田氏とは、その昔SRの会の全国大会で何度かお会いしたが、私とは大違いの「正統派の本格ミステリファン」であったと記憶する。
氏のご尊名は、SRの会の会誌「SRマンスリー」誌上で、ずっと目にしてきたし、手塚隆幸による同人誌「名探偵研究シリーズ」や、甲影会の「別冊シャレード」でも、寄稿者としてご一緒した。長らくお会いしてはいないが、本書の編者に、馴染みの名前を見つけた、ということになる。
で、今回「山沢晴雄セレクション」の第1弾『死の黙劇』が、山沢の本領である「パズル小説」を集めた短編集になっているのは、いかにも戸田氏らしい編集だと思うのだが、正直なところ、危惧するところがないわけではない。
たぶん、氏としては、「山沢晴雄セレクション」の第1巻とも言うべき本巻では、山沢の本領であるところの「パズル小説」を紹介し、続刊では、予告されている長編や「パズル小説」以外の作品を紹介するという、シリーズ構成を考えているのではないだろうか。
その昔、ミステリ評論家として一時代を築いた中島河太郎の編んだ、名アンソロジー「『新青年』傑作選」全5巻は、第1巻から第3巻までが「推理編」、第4巻が「怪奇編」、第5巻が「ユーモア・幻想・冒険編」となっていたが、ミステリ界の伝統からすれば、まずは「ミステリの王道である、本格推理」を紹介し、その後「傍流たる、変格ミステリ」を紹介するというかたちになるのは、ごく自然な流れだったであろう。つまり「山沢晴雄セレクション」の構成も、そうした伝統に倣ったのではないだろうか。
しかし、山沢の本領である「パズル小説」は、「新本格ミステリ以降」の読者には、いささか「敷居が高く、取っつきにくい」のではないかと、私などには危惧される。
すでに刊行されてしまったものに注文をつけても「後の祭」でしかないのだが、新しい山沢読者を開拓するという意図があるのであれば、第1弾には、山沢の多面的な魅力を伝える、各種の作品を入れた方が良かったのではないかと、そう惜しまれた。
だが、だからこそ、読者諸兄に是非とも伝えたいのは、「山沢晴雄セレクション」の第1弾『死の黙劇』だけで、山沢晴雄という作家を判断しないでいただきたい、ということである。
山沢がいちばん書きたかったのは、本巻に収められたような「パズル小説」であったというのは間違いないところなのだが、それが山沢の仕事として、最も優れたものであったとは限らない。じっさい、力こぶを入れて、こだわって書いた作品よりも、片手間に書いた作品の方が、客観的には優れていた、なんてことは、創作の世界ではよくあることなのである(無論、山沢に「片手間で書いた」作品がある、という話ではない)。
だから、「山沢晴雄セレクション」の第1弾『死の黙劇』が(趣味に)合わなかった読者には、このシリーズの第3巻や第4巻といった「パズル小説」以外の部分も読んで欲しいと思う。そうすれば、私の場合と同様に、山沢晴雄の意外な魅力が発見できる可能性も十分にあるのである。
初出:2021年8月18日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
・
・
