
〈宇山秀雄殺し〉の 謎を解く : 『宇山日出臣 追悼文集』の密室
書評:太田克史編『新本格ミステリはどのようにして生まれてきたのか? 編集者宇山日出臣追悼文集』(星海社)
エディターネーム「宇山日出臣」、本名「宇山秀雄」が、「新本格ミステリの仕掛け人」などと呼ばれた名編集者であることについて、ここであらためて説明する必要などないだろう。本書を購読したり、ネットで本書の内容を確認したりするほどの人なら、宇山についてそれなりの予備知識を、あらかじめ持っているはずだからだ。

本書は内容は、次のとおり。
(1)序文(太田克史)
(2)編集者・宇山日出臣の仕事と歴史(佳多山大地)
(3)本書のために寄せられた追悼文
(4)宇山の葬儀での、島田荘司と綾辻行人の「弔辞」
(5)宇山回顧座談会(司会・太田克史)
・ 新本格作家座談会
(綾辻行人・法月綸太郎・我孫子武丸・麻耶雄嵩)
・ 新本格系評論家座談会
(巽昌章・千街晶之・佳多山大地)
・ (再録エッセイ)宇山秀雄「呪縛」
・ 宇山関連編集者座談会
(鈴木宣幸・野村吉克・唐木厚・太田克史)
(6)再録『メフィスト編集者匿名座談会』1〜3
(7)講談社ミステリーランド企画書
(8)グラビア 宇山日出臣の本棚
(9)おわりに(太田克史)
(10)宇山秀雄略歴
(11)追悼文集執筆者一覧
この(5)の「宇山関連編集者座談会」の中でも紹介されていることだが、宇山は、夫人が検査入院中の一人暮らしの自宅で亡くなっている。
しかも、家には内側から施錠がなされていたから、いわば「密室」死であった。
崩れたCDの山に頭を突っ込むようにして、うつ伏せに倒れた状態で、宇山は冷たくなっているのを発見されたのだ。
この、宇山の孤独な死に対し、多くのミステリ関係者は、せめて宇山らしく「これが密室殺人であったなら」などという、いささか不謹慎な「夢想」をしてしまった。
「新本格」の理論的守護神であった笠井潔風に言うなら、それは「観念的自己回復」である。つまり「無意味な死」に、意味を与えることで、その「死」を観念的に乗り越えようとする、代償行為だ。
笠井潔の「大量死理論」に寄れば、二つの大戦間の英米に到来した「本格ミステリの黄金期」は、第1次世界大戦での「大量死」経験によって要請された、社会心理学的な現象だった。
個人の尊厳が失われた、戦場における「大量死」とは違い、探偵小説における「死体」には、殺人者によって施される「トリック」という個別的で特権的な「意味づけ」と、名探偵の「謎解き」による「意味づけ」という、いわば「二重の光輪」が与えられ、そのことよって人間の死は「固有の意味」を回復することになるのだ。
だから、宇山の死が「激越型うつ病」によって弱った体が原因の「悲しくも虚しい、無意味な事故死」などであって欲しくないと、宇山を知る人たちは、思わずそう願い、それを正当化するために「せめて、宇山さんなら宇山さんらしく、密室殺人の被害者という意味を担って死んでくれた方が、むしろ我々も救われるのに」と、そう考えたのである。
だから、この点について、前述の編集者座談会では、次のように語られている。
『鈴木 そう。この座談会が始まる前に太田に提案したんだよ。宇山さんって密室で死んでいたじゃない。
太田 訃報が届いたあの日、僕が宇山さん宅に駆けつけたらすでに菊地(秀行)さんがいらしていて、その後来てくれた(山口)雅也さんが、「密室だ」で呟いていたのを覚えています。
唐木 宇山さんが亡くなったその日に駆けつけてくれたのが、雅也さんと菊池さんでしたね。
鈴木 うーやんが頭をCDの山に突っ込んでいて、唇と鼻のところに血痕が残っていたという怪しい死体なんだから、今回の本ではその謎解きをぜひ誰かに書いてもらいたいと思ったのに、「そんな企画やれるわけないでしょ!」っていちばん傍若無人な太田に叱られちゃった。
太田 わはは。
鈴木 もうひとつ提案。誰か、『犯人は宇山日出臣』っていう小説を書いてくれないかな。ミステリーランドの頃に、宇山さんが断酒道場の病院に入ったじゃない。宇山さん、「ノブさん、ベルトも取り上げられるんだよ」ってニヤニヤしてた。「悲観して首を絞めたりしないように長いものはぜんぶ取られるんです」とかすごく楽しそうに話すんだけど、「よかったですね」とか言うしかなかった。どうも、サナトリウムとか隔離された場所とかいうシチュエーションに自分が置かれたことが嬉しくてしょうがないみたいだった。だから、宇山さんが断酒道場でベルトを取られたうえ絞殺事件が起こる『犯人は宇山日出臣』を読みたい。
唐木 たしかに不可能状況としておもしろいですよ(笑)。
鈴木 宇山さんはたぶんこうやって僕が話すと「いいですね、誰が書いてくれますかね」とか言ってさ、「ボクが死んだ状況は密室だぞ、クックック」って笑いそうじゃない。
唐木 すごい、宇山さんが乗り移ってるみたいな口ぶりだった! 誰が書くといいかな。』(P337)
それなら、私がそれを書いてみせよう、というのが本稿の趣旨である。
ただし、「お遊び」ではなく、大真面目にだ。
そして、私にもその権利は、多少なりともある。
と言うのも、私自身、生前の宇山さん(ここの部分だけ「さん」付けにする)とは最低二度はご一緒して、言葉も交わしているからで、宇山夫人とも、宇山さんの生前と、亡くなられた後にお会いする機会を得た人間だからだ。
無論、一介のミステリファンでしかない私だが、宇山さんを追悼する資格もあれば、その「死の真相」を考え、語る資格はあるだろうし、それは決して故人を冒涜するものではないと確信している。
また、それがその通りだということは、本稿を最後までお読みいただいた方には、おのずと明らかになるはずだと、ここであらかじめ、宣言しておきたいと思う。
○ ○ ○
本書『新本格ミステリはどのようにして生まれてきたのか? 編集者宇山日出臣追悼文集』を手にとって、まず最初に感じる違和感は、このタイトルである。
どうして『編集者宇山日出臣追悼文集 新本格ミステリはどのようにして生まれてきたのか?』ではなかったのか、ということだ。
「新本格ミステリはどのようにして生まれてきたのか?」という、長ったらしくも、追悼文集のタイトルとしては野暮な、この「メインタイトル」は、本書所収の追悼文を読むかぎり、どうやら宇山の「盟友」を自負する、島田荘司の意向に沿ったものようである。要は「宇山秀雄は、まず編集者・宇山日出臣として「新本格ミステリ」の生みの親(の一人)である」ということを強調したかったのであろう。
しかし、実際問題として、宇山秀雄の編集者人生は「宇山日出臣」に限定できるものではなく、事実「宇山日出臣」以前の時期の、編集者としての仕事についても、否応なく本書でも触れざるを得なかった。
要は「星新一を初めて文庫化した」「名刺の最初の一枚を星新一に渡すために、他の作家には、まだ名刺が刷り上がっていないと嘘をついた」「星新一を顕彰する『ショートショートランド』誌を創刊して、多くの新人を輩出した」編集者としての、宇山秀雄である。
宇山秀雄と星新一の深いつながりは、ノンフィクション作家・最相葉月による評伝『星新一 一〇〇一話をつくった人』(星雲賞、日本推理作家協会賞、大佛次郎賞、日本SF大賞、講談社ノンフィクション賞受賞作)で有名になった話だから、編集者・宇山の追悼文集で、こうした「SF編集者・宇山秀雄」を履歴・功績を無視することは、さすがに出来なかったのであろう。

無論、『ショートショートランド』誌でデビューした作家たちの中から、宇山の引きで「新本格ミステリ作家」として再デビューした者も少なからずいるから、その点では、宇山の「SF編集者」という過去は、「新本格ミステリ編集者の前史」と位置付けることも、可能ではある。だが、星新一との繋がりだけは、どうしたって「新本格ミステリ」とは接続できない。
「新本格」の側からすると、宇山は「中井英夫の『虚無への供物』を文庫化するために、かの三井物産を辞して、編集者に転職した」稀有な人ということになっているが、そうすると「なぜ、名刺の最初の一枚を、中井英夫に渡さなかったのか?」という疑問が、どうしたって出てきてしまう。
しかし、「新本格」の側からすれば、そこを追求するのは「やぶ蛇」にしかならないから、関係者は全員、素知らぬ顔でスルーすることになる。
だが、こうした「謎」を放置したまま、「宇山の死」の真相に迫ることは不可能であろう。
普通に考えれば、宇山の「名刺の最初の一枚を星新一に渡すために、他の作家には、まだ名刺が刷り上がっていないと嘘をついた」という話と「中井英夫の『虚無への供物』を文庫化するために、一流商社から編集者に転職した」という話は、明らかに矛盾する。
そして、この謎を解く、いちばん簡単な解答とは「どちらか、または両方が、編集者としてのリップサービスであり、嘘ではないにしろ、誇張された話だった」というものであろう。
そして「新本格ミステリ」の側として考えるなら「宇山は、星新一も中井英夫も両方好きだったのだろう。星の作品集を文庫化したかったのも、中井英夫の『虚無への供物』を文庫化したかったのも、どちらも本音だったのだろう。ただ、その時々、その思いを強調するために、目の前の作家のためにと、片方を強調してみせた、ということなのではないか」といったことになろう。現実的には、この解釈がいちばん自然であるし、私も、これが「現実」ではなかったかと考える。
しかし、この解釈の問題は「宇山は、決して本格ミステリ 一辺倒の人ではなかった」ということになる点である。

本書を企画したのは、明確に「新本格」の側だし、いち編集者としてこのような異例の「追悼文集の公刊」が可能になったのも、それは宇山が「新本格ミステリの仕掛け人」と呼ばれるようになったからであって、「星新一を初文庫化した人」だからでも、『ショートショートランド』の編集長として多くの新人作家を輩出したからでもない。だから、編集者・宇山の実績の重点は、あくまでも「新本格ミステリの生みの親」という点に置くべきであると考えたのは、ごく当然のことだったろう。
だからこそ、本書では、「宇山秀雄」ではなく「宇山日出臣」の表記が「サブタイトル」に使われた。「新本格ミステリ」の側にとっては、宇山秀雄は「宇山日出臣」として意味を持つ存在であり、そのようにして「新本格ミステリ」の側にこそ「囲い込まれてしかるべき存在」だったのである。
したがって、言い換えるなら、宇山秀雄の存在(とその名)は、「新本格ミステリ」のために在る「従たる存在」であって、宇山秀雄自体は「主たる存在」ではない。
だからこそ、本書のタイトルは、島田荘司の意向を受けて『新本格ミステリはどのようにして生まれてきたのか? 編集者宇山日出臣追悼文集』という序列になったのである。

○ ○ ○
実際、本書に収録された島田荘司の「弔辞」には、次のようにある。
『 宇山氏の、並はずれて非凡なところは数々ありますが、何といってもその最大級のものは、本格ミステリーへの強い、そして積極的な愛情が、仕事上の演技でもジェスチャーでもなくて、まるきりの本物であったということです。どこを切っても金太郎の顔が出てくる飴のように、宇山氏の体は、どこを切っても「ミステリーを愛している」という言辞が顔を出したことでしょう。彼がミステリーについて語る時、それは決して給料のためなどではなく、ただひたすらに純粋な心根からでした。私はこういったことを、お世辞の嘘で口にすることはしません。宇山氏は、まったく可笑しいほどに、この通りの人でした。』(P273〜274)
「新本格」の歴史に詳しい者にとって、島田の『私はこういったことを、お世辞の嘘で口にすることはしません。』などという言葉は、まったく余計な「虚言」でしかない。
というのも、島田荘司は「新本格」の新人たちのデビューにあたって、無条件の絶賛を与え、その結果として、少なからぬ読者・有識者から「あんな未熟なものを、そこまで言うのは、嘘としか呼べないだろう。推薦者として、言論人として、あまりに無責任ではないか」という当然の批判にさらされた際に「新人のデビュー作の欠点を論えというのか」と反論して、自己の「仲人口」を正当化すると同時に、必要があれば「公然と嘘もつく」ことを、すでに認めていたからである(このことで、他ならぬ「新本格」作家たちからの批判も浴びた。事実そうであったとしても、嘘なら嘘で最後までつき通すべきではないか、そうでないと島田の推薦文でデビューした者の立場がない、と)。
ともあれ、この「弔辞」にも明らかなとおり、島田荘司は、宇山を「本格ミステリーの人」として描き出そうとしている。
だが、これが正しい「宇山」像ではないというのは、もう一本の「弔辞」、綾辻行人のそれの、次のような言葉にすら明らかであろう。
『 宇山さん。
十九年前、僕の拙い原稿を本にしてくださったのが実質的なきっかけとなって、後年、編集者・宇山日出臣は「新本格ミステリの仕掛け人」とか「新本格の生みの親」とか、そういったフレーズで語られることが多くなりました。それをまんざらでもないふうに受け止めながらも、けれど心のどこかでは、おそらくいつも「何だかなぁ」と首を傾げておられましたよね。
宇山さんが愛してきたもの、育ててきたものは、「本格」とか「新本格」とか、そういうレベルの一言で括れるものたちでは、決してなかったはずなのですから。「ミステリ」とか「SF」とか、「幻想小説」とか「純文学」とかいった、世間的な分かりやすさのためのジャンル概念も、むろんあなたにとって、重要な意味などあるはずがなかった。
宇山さんを深いところで衝き動かしていたものは「宇山秀雄的」とでも呼ぶしか呼びようのない志向性を持った、独自の感性であり、直観であり、美学であり……それらはすなわち、あなたの内なる妖精の声だったに違いありません。
自分と同じようにこの地上に紛れ込んでいる仲間たちを探し出すこと。この地上の現実の、ここに在る限りは決して逃れようのない無粋な引力から、それでも何とかして自由でありたい、少しでも身体を浮かび上がらせたいという叫びを聴き取ること。そうして共にそうあろうと試みること。それがこの世界で、宇山さんが生涯続けてこられた仕事でした。そうですよね。
だから一一。
「新本格ミステリー」云々は一一もちろんそれも、大いに称賛されて然るべき素晴らしい功績でしょうが一一、でもそれだけで語られてしまうべきでは決してない、単に一つの結果であったにすぎないこと、なのです。
ご安心ください、宇山さん。僕は、いえ僕たちは、ちゃんと分かっていますから。』(P285〜287)
「宇山秀雄」の仕事を、島田荘司のように『どこを切っても金太郎の顔が出てくる飴のように、宇山氏の体は、どこを切っても「ミステリーを愛している」という言辞が顔を出』す類のものと語るのは、明らかに「事実に反したこと」であり、結局のところそれは「本格ミステリー」側の、宇山の「囲い込み」でしかなく、綾辻行人が言うところの『この地上の現実の、ここに在る限りは決して逃れようのない無粋な引力』の一つでしかない、ということである。
そして、その意味で、宇山秀雄の愛したものは『「ミステリ」とか「SF」とか、「幻想小説」とか「純文学」とかいった、世間的な分かりやすさのためのジャンル概念』で語れるような単純なものではなく、言うなれば『「宇山秀雄的」とでも呼ぶしか呼びようのない志向性を持った、独自の感性であり、直観であり、美学』だという、綾辻行人の意見は、まったく正しい。

ただし、ここで引っ掛かりを覚える「事実」が、私には一つある。
この「弔辞」で綾辻は、自身を『「宇山秀雄的」とでも呼ぶしか呼びようのない志向性を持った、独自の感性であり、直観であり、美学』によって見出された『妖精』の一人だと位置づけている。
それはいい。それは事実なのだが、しかし、ならば綾辻は、その『「宇山秀雄的」とでも呼ぶしか呼びようのない志向性を持った、独自の感性であり、直観であり、美学』を肯定し、その「美学」を信頼しているはずで、宇山によって見出された人たちを、基本的に「肯定」していなければ、この「弔辞」は「嘘を含んだ、きれいごと」でしかなくなってしまう。
また、そうだとすると、この「弔辞」もまた、宇山秀雄を、自身の側に囲い込んで利用するための『この地上の現実の、ここに在る限りは決して逃れようのない無粋な引力』の一つでしかない、ということにもなってしまうのだ。
だが、そうとしか考えられない「事実」を、私は知っている。
○ ○ ○
『 どちらが本物か?(上) 投稿者:園主 投稿日:2007年6月2日(土)03時02分53秒 (https://8010.teacup.com/aleksey/bbs/1499)
みなさま、一昨々日は、さる5月27日に神田の古書会館で行われた2つの講演会のうち「雑誌『幻影城』と編集長 島崎博」に関するもの方について書かせていただきましたが、本日はもう一方の「編集者 宇山秀雄の仕事と思い出」に関する鼎談の方にかんして書かせていただきたいと存じます。
一昨々日も書きましたとおり、この講演会は、ミステリ作家 綾辻行人、有栖川有栖、およびフリー編集者の東雅夫の3人による鼎談として行われたものでございますが、実際には、定員80名のうちにも、故宇山氏と縁のあった出版業界の方がけっこう含まれており、最終的には百名くらいになったであろう講演会参加者のうち、三分の一はそうした業界関係の方たちだったのではないかと存じます。
ここでその一部をご紹介させていただきますと、まずはご存じ京極夏彦氏、竹本健治氏、喜國雅彦氏、浅暮三文氏、講談社の唐木氏、太田氏などなど。もちろん、宇山夫人もお出でになっておられました。
講演会は、おおまかに言えば、前半が、綾辻・有栖川・東の鼎談、後半は、前記のような宇山氏に縁の合った方たちにマイクを回して、それぞれに思い出を語ってもらうという形で進行いたしました。つまり、感じとしては「講演会」と言うよりも、「故・宇山秀雄を偲ぶ会」という感じで、非常にアットホームかつ濃密な2時間半でございました。
ある人は、その場の雰囲気をして「伝説の一夜にもなるだろう」と書かれておられましたが、まさしくそのような感じでございました。
ですから、この講演会自体は、非常に価値のあるものでございますし、また「故人を偲ぶ会」として、注文のつけにくい性格のものとなってしまったのでございますが、会合そのものの充実度とは別に、私には、すこし引っ掛かったことがありましたので、その点について書こうと思うのでございます。
私が引っ掛かったのは、「綾辻行人の非論理性」ということでございました。したがって、これはこの会合に限定された話ではなく、綾辻行人という人「個人」の問題点なのでございます。
まず、講演会の冒頭、綾辻・有栖川・東による、雑談的な前振りが二三交わされた後、さて本題である宇山氏の話に入ろうとした際、いきなり綾辻は、こみあげてきた感情に絶句し、サングラスの下に隠された涙を拭って「すいません。ちょっと、いきなりきちゃって。人前で泣くことなんかないんだけど、カッコ悪いところを見せてしまいました」と客席に詫びるという一幕があったのでございます(その後は、有栖川の大阪人らしいフォローもあって、無事、楽しい雰囲気の鼎談に移行しました)。
さて、綾辻行人と編集者宇山秀雄との親密な関係を知っている者であればあるほど、このシーンは、本来ぐっと来て然るべきところだったのかもしれません。しかし、私個人は「ちょっと止してくれよ」というのが、偽らざる気持ちでございました。と申しますのも、私は以前より、綾辻行人という人が「自身をめぐる物語に酔ってしまう人」との印象を持っておりましたので、「またか」と、むしろ鼻白む気分にさえなったのでございます。
綾辻行人という人が、基本的には「素直な、いい人」だというのは、まず間違いはございません。そして「新本格の第一走者」として日本のミステリ史にその名を残す人物であるのも間違いございません。また、そうした「人柄」や「史的価値」を抜きにしても、その作品は、作品そのものとして評価されて然るべきものでもございましょう。――しかし、だからと言って、その当の本人がそういう「他者の評価」の中にどっぷりと浸かってしまうのは、傍から見ていて、いかがなものかと感じられることがあるのでございます。
例えば、綾辻行人は昔から「僕の家系は、代々短命なので、僕も長生きはできないと思っています」というようなことを書いたり、話したりしておりますが、私などからすれば「エンターティンメントであるミステリを書く作家が、そのようなことを話すことに、いったい何の意味があるのか」と感じられるのでございますね。これは、読者にそうした「物語」を共有させ(て、そうした個人的な点でも読者を惹きつけ)たいということなのか、それともそのような自覚すらなく、そのような極めてナルシスティックな感情を垂れ流しているだけなのか。
たしか、短編集『どんどん橋、落ちた』には、「若さゆえの鼻持ちならなさはあったけれども、ミステリに対して何の疑念も抱かず、純粋であれたあの頃」の自分自身が、今の自分のところへ訪れ、今の自分のあり方を問う、というセルフパロディー的な作品も収録されていたはずで、私はこの短編を、雑誌発表当時に読んで、そこに綾辻行人の「無垢への意志」を見、高く評価したことがございます。
しかし、これもまた、ある意味では非常にナルシスティックな作品であり、しかも自身の「無垢」を売り物にするという点で、鼻持ちならない作品だと評価しても、それはそれで決して間違いではございません。
また、ある意味では、「無垢への意志」というものは、誰の胸にも多少なりともあるものであり、それをことさら他人に語る者など少ないからこそ、綾辻の当該作品は「ナイーブな感動もの」と受け取ることも可能なのでございます。
私は何も、綾辻行人が自身の「ナイーブ」さを、読者に向けて「自己喧伝」的に語っていると非難したいのではございません。故意に、戦略的に、そのようにしているのなら、それはそれで世間には「ありがち」なことで、特にどうということもないのでございますが、私が嫌になるのは、綾辻のそれには、そうした「方法意識=客観認識」が希薄であり、単に「自己陶酔の垂れ流し」としか感じられないからなのでございます。
例えば、今回の講演会でも、綾辻は宇山氏を「世間に迎合しない、自己の確固たる美学をもって、新たな可能性を見抜く眼力のある人だった」と評して絶賛します。そして、その目で「宇山さんは、誰よりも僕のことをよく理解してくれた」というのでございますね。
しかし、その一方で綾辻は、そういう宇山氏も、その「独自の美学」や「おもしろがり屋」が行き過ぎて、滑ってしまうこともある、それが「清涼院くんなんかの場合なんだと思います」と言うのでございます。もちろん、綾辻は「まあ彼も、もう十年以上も、プロの作家をやっているんだから、宇山さんの評価も、あながち間違ってはいなかったんだろうけど」といったフォローを入れはするのでございますが、いわゆる「ミステリ作家としては」清涼院流水は認められないという意思は、ハッキリとその言動に滲ませておりました。
しかし、綾辻行人がデビューした時だって、綾辻の作品を「素人の小説」として評価しなかった先輩作家は少なくございませんでしたし、今でも綾辻をとくに評価するわけではない作家や読者も少なくございません。ただ、宇山氏の綾辻行人評価が「正しかった」ということに「なった」のは、要は綾辻の作品が売れ、しかもそこから新たなミステリブームが巻き起こったという「大きなおまけ」がついたからで、言うなれば、これは「結果オーライ」なのでございますね。
しかし、こうした現実について、綾辻行人自身は「宇山さんの評価は(客観的に)正しかった」と語って、綾辻を評価しなかった人たちの評価を「時代の美を読みとる能力がなかった」と暗に否定するのでございます。
けれども、こんな「結果オーライ」で良いのであれば、それは清涼院流水の場合についても、公平に適用されるべきではないでしょうか。事実、清涼院流水は、その特異な作風によって、綾辻行人を含む先輩作家から、袋だたきに近いバッシングををうけました。それは、綾辻がデビューの際にうけたバッシングよりも、さらに激しく陰湿なものであったと、当時を知る私は、斯様に評価いたします。と申しますのも、綾辻行人のデビューの際のバッシングは「今どき、こんな時代錯誤の作品を書く素人をデビューさせるのか」というニュアンスのものであったのに対し、清涼院がデビューの際にうけたバッシングは「こんなのが本格ミステリだと思われては困る。こんなのと一緒にされたくない」というようなニュアンスの、非常に「近い距離」から発せられた「近親憎悪」的なバッシングだったからでございます。
ともあれ「デビューに際して、先輩作家からバッシングを受けたけれども、若い読者からの支持をうけて人気作家となり、やがてその影響を受けた作家まで輩出することになる」という一連の流れは、綾辻行人と清涼院流水の双方にまったく同型のものであって、綾辻行人への評価は正しかったが、清涼院流水への(現在にいたる)肯定的評価は錯誤であるというような「ご都合主義」は、(個人的な「主観」の問題を除けば)まったく成立いたしません。なのに、綾辻は、自分を評価した宇山氏の眼力は非凡だが、清涼院を評価した宇山氏の目は曇っていたとしか言い様がないと評価して、何の疑問も持たないようなのでございます。
結局のところ、このような「自己愛的」「自己中心的」な、露骨に客観性を欠く評価が可能なのも、すべては綾辻行人が「自身をめぐる物語」に酔っているからなのでございましょう。
例えば、竹本健治は自作『ウロボロスの偽書』の中で、綾辻行人のミステリ界への登場を、トリックスターとしての「童子」の出現として評価し、その「無垢の力」を強調しております。こうした評価は、綾辻行人本人が「どのような人間か」ということではなく「綾辻行人の登場が、その世界にとってどのような意味を持ちえたか」ということを語るという点では、まったく正しいものだったと申せましょう。しかし、それを綾辻本人が「自分は、本質的にそのような人間(マレビト)なんだ」と本気で思ってしまったとすれば、それは滑稽な誤解でしかないのでございます。
――しかしながら、綾辻行人はそのような誤解をする人であり、また現に自身を誤解している人だとしか、私には見えないのでございます。
それは、先にご紹介した「夭折の宿命」の自己語りだとか、中井英夫に会った時に「反世界的な物語を書くのだぞ、と励まされた」と書いて、まるで中井英夫が綾辻行人をそのようなものが書ける作家であると評価していたかのように(まるで「相伝の儀式」ででもあったかのように)「感動的」に書いてしまうこととか、雑誌『幻影城』の編集長として知られた島崎博との出合いについて、
『 二〇〇六年の秋、招かれて台湾を訪れ、そこで島崎博さんとお会いする機会を得た。
齢七十過ぎにして、実に矍鑠たる風情。とっさに抱いた印象は「魔人的」。とにかくよく食し、よく飲み、よく語られる人で、現地の若手ミステリ作家を従え、こちらが恐縮してしまうほどに熱烈歓迎してくださった。
その席で当然、『幻影城』の話も出た。
もしも『幻影城』がなかったならば、今ここに綾辻行人という作家は存在しなかったと思う。素直にそう云うと、とても嬉しそうに笑っておられた。』(『幻影城の時代』より)
といった具合に書いてしまうところにも、綾辻行人の「自己陶酔(感涙)」傾向は、おのずと明らかでございましょう。
たしかに 『もしも『幻影城』がなかったならば、今ここに綾辻行人という作家は存在しなかったと思う。』というのは、正直な気持ちでもあれば、事実でもございましょう。しかし、それは何も綾辻行人にかぎった話ではございません。それは単に、『幻影城』という雑誌がそれほどのものであった、というだけの話なのでございます。
「綾辻行人ファン」が「もし『幻影城』無かりせば」と言うのであればともかく、ご本人がそれをこのように臆面もなく語ってしまえる神経というのは、「大人」として「社会人」のそれとして、いかがなものでございましょうか。本人にとっては「宿命」と感じられるような事柄でも、他人にとっては別にどうということのない偶然の事実を、プロの物書きたるものが、感情垂れ流し的に書いてしまうというのは、「素直」と言うよりも、むしろ「締まりがない」と言うべきなのではないでしょうか?
しかしながら、綾辻行人が度しがたいナルシストであるというだけならば、それはそれでどうでも良いことなのでございますが、問題は、綾辻がその「酔って舞い上がった高み」から、客観的なつもりで、独り善がりの「ご高説」を垂れてしまう現実なのでございます。そして、その被害者が、清涼院流水であり、彼のファンであり、彼を評価していた宇山秀雄氏に他ならないのでございます。
例えば、綾辻行人は、同じ講演のなかで「評価」ということについて、概ね次のような主旨のことを力説いたしました。
「宇山さんは、面白がる才能のある人でした。これはとても大切なことなんですね。ケチをつけたり、批判したり、あそこがどうここがどうとあら探しするのは誰にでもできる。でも、その作家の良いところを見つけ、そこを指摘し、その作家の可能性を延ばすようなことは、誰にでもできることではありません。僕もミステリの公募新人賞の選考委員をやっているんだけど、粗探しをしたり注文をつけたりすることは簡単です。でも、そんなことはしません。そんなつまらないことをやっても何の価値もありませんから」
見てのとおりで、言うまでもなくこれは、自己を肯定してくれた人を誉め、自己を批判した人たちを否定するために語られた、そしてそのことにすら無自覚な、極めて主観的かつ「自己中心的」な、幼稚な「批評論」だと申せましょう。
言うまでもなく「ケチをつけたり、批判したり、あそこがどうここがどうとあら探しするのは誰にでもできる。」ことではございません。
例えば、綾辻行人が「笠井潔の暴論」に対しては、「ケチ」や「粗探し」は無論のこと、「正当な批判」すらできないという事実からも、「批判は、必ずしも容易なことではない」というのは明らかであり、綾辻がここで「ケチをつけたり、批判したり、あそこがどうここがどうとあら探しするのは誰にでもできる。」と言う場合の批評対象とは、自分よりも立場の弱い者を相手に(批評を)した場合に「限定」されているのでございますね。
つまり、綾辻行人は、宇山氏の「威張らない態度」を賛嘆しつつ、自身は「綾辻行人先生」の立場から物を見、語っており、それでいてそんな自分にまったく気づいておらず、むしろ自分自身も「ざっくばらんな、威張らない人柄」だと、ナルシスティックに自己肯定してしまっているのでございます。
むろん、こうしたナルシシズムは誰にもあることでございますし、目くじらを立てて非難するほどのことではないとも申せましょう。また、大学生の時に作家デビューし、それ以降ずっと「人気作家」として、下にも置かない「先生」扱いを受け続けてきた人であれば、このようになってしまうのも、ある程度はしかたございません。
とは言え、それが傍目には「バカバカしく」もあれば「見苦しい」ものだということを、綾辻行人自身、知っておいても、決して損はございませんでしょう。
若いうちであればともかく、五十を目前にしたいい大人が、「自分は天に愛された特別な存在なんだ」などと思い込み、その気分を、外へも垂れ流してしまうという自制心の無さは、はっきり言って、みっともないのでございます。
綾辻ほどの「立場」を得てしまった「先生」に対しては、誰も率直な本音を面と向かって告げることはございませんし、いくら心の中でバカにしても、それが口に(文に)されることは絶えてない、というくらいのことは自覚して、自分で自分を戒めるのが、地位ある者の採るべき「賢明な態度」だと申せましょう。また「批判者を遠ざけるのは、愚かな権力者の常である」というくらいのことは、歴史に学んでおいていただきたいのでございますね。
文壇で言えば、能天気な渡辺淳一や石原慎太郎といった「お山の大将」と、今の綾辻行人とに、その置かれた「立場」として、いったいどの程の径庭があるのかを考えて欲しい。
たしかに、ある意味では「綾辻行人」は、大きな意味をもった「特別な存在」だと申せましょう。しかし、「何かにとって、その人が特別な存在である」という意味合いでならば、この世に「特別でない人」など一人もいないのであり、綾辻行人個人の「特別さ」も、所詮は、そのような「特別さ」の一種でしかないということを、綾辻は認識すべきなのでございます。
「先生」だの「社長」だのと呼ばれる人たちも、たいがいの場合、自分では「自分は人並み以上の苦労と努力をしてきたから、今の地位にあるんだ」と思っておりますし、「自分は決して偉ぶったりする人間ではない。ただ、尊敬すべき人を尊敬し、軽蔑すべき人を軽蔑しているだけだ」と思っているものでございます。しかし、それらはたいがい、自分でそう思っているだけで、傍から見れば「先生ぶっている」「社長ぶっている」としか映りません。と申しますのも、「私は公正だ」と主張し、そう思い込んでもいるそういう人たちも、自分より「立場が上」の人には「相手の人格にかかわりなく」、現にへりくだり、相手を持ち上げたりするものだからなのでございます。
「権力の魔性」という言葉がございますが、言い換えればこれは「立場の魔性」とも申せましょう。「権力」を得た者、「立場」を得た者は、人並み以上に、自身に懐疑的・批判的、つまり反省的でなければなりません。そうでなければ、その人は「凡庸に無自覚な人」でしかなくなるのでございます。
そして、そんな視点に立ちますならば、綾辻行人と清涼院流水は、その性格に違いはあれ、どちらも「無自覚」という点では五十歩百歩だと、私には斯様に思えるのでございます。』
○ ○ ○
これは、私の電子掲示板「アレクセイの花園」に『2007年6月2日』に、「園主」名義で書き込んだ文章の、全文である。
そして、この文章は、無事、綾辻行人本人にも読まれ、「田中くんの文章は、もう二度と読まない」と言ったという話まで仄聞している。
しかしながら私は、この文章、この「〈宇山秀雄殺し〉の謎を解く:『宇山日出臣秀雄追悼文集』の密室」も、綾辻行人は必ず読むだろうと思って書いている。
私が綾辻行人を批判した文章は、最近のものでも、
・「言葉のおろそかな〈文筆業者たち〉:綾辻行人・知念実希人の事例」(2022年1月6日)
(https://note.com/nenkandokusyojin/n/nd58f91f4eedd)
・「ゾンビからミイラへ:〈言葉〉を失った者たち」(2022年1月15日)
(https://note.com/nenkandokusyojin/n/nc412c5f0277a)
などがあるが、綾辻行人はきっと、これらも読んでいるはずだと思っており、それは私が「綾辻行人とは、そういう(エゴサーチをしちゃう)人だ」と評価している、ということである。
そう思うのは、綾辻行人が、けっこう「感情的・気分的」な人(論理的一貫性がない人)であり、その意味で、無邪気に「なし崩し」をする人だというのを知っているからだ。
具体的にその根拠を示しておくと、まだ新本格ブームのごく初期、インターネットにおいて「ホームページ」を作るのがブームになり始めた頃、綾辻もインターネットを始めたのだが、そこで「自殺をほのめかす」女性からの接触があり、綾辻は、彼女を救うために親身になって助言や慰めの言葉をかけたのだそうだが、のちにこれは、人気作家の気を惹くための「狂言」であったことが判明し、綾辻はそのことに深く傷ついて、ネットを離れてしまった、ということがあった(と、これも仄聞した)。
これだけなら、インターネット普及の初期によく見られた「同情すべき被害」事例だということになるだろう。
しかし、この後、「関ミス連」大会で、サインを求めた旧知の私に対し、綾辻は「田中くん、まだネットで賑やかにやっているようだけど、ネットなんて、ろくでもない世界なんだから、さっさと止めた方が賢明だよ」というようなことを、年長者ぶって言ってきたのだ。
その当時も、今にも増してにぎやかに論争を繰り広げていた私は、自分のしていることを全否定したも同然の、この「人気作家の心からの助言」が、自身のささやかな体験にだけ依拠した、独りよがりの知ったかぶりとしか思えず、「なに言ってやがる、大きなお世話だ。」としか思えなかった。
綾辻行人が、このように考えるようになった理由が、前記の事件だけなのか、そのほかにも色々あったのか、そのあたりの事情はわからない。また、綾辻が私に対しこうした助言をした際、私が前記の「事件」を知っていたのかどうかも、今となっては、その記憶すら定かではない。
だから、綾辻行人が、私に対し、年長者ヅラで、いささか安直な「助言」をしたというだけなら、私も、そんなことなど遠に忘れていたことだろう。
だが、実際には、綾辻は、いつの間にかインターネットを再開して、私への助言など、すっかり忘れたのか、なかったことにしたのか、ともあれ、自身の発言の訂正も撤回もないまま、言行不一致にも、平然とインターネットの世界に舞い戻っていたのである。
だから、私は「なんだ、こいつは。無責任なやつだな」と、そう評価するようになったのだ。
○ ○ ○
したがって、こうした「ご都合主義的発想」からすれば、綾辻の考えが「宇山さんの評価も、私の場合には正しかったが、清涼院流水の場合には間違っていた」というものであっても、なんら不思議ではない。
綾辻行人の場合、自己肯定のためであれば、明らかな「矛盾」を押し通しても、まったく平気でいられるのである。
だが、一人前に、人前で意見表明をする「言論人の端くれ」であるならば、いくら「エンタメ作家」でしかないとはいえ、綾辻行人のこうした「いい加減さ」や「無責任な発言」を放置しておくことはできないと、私は、2007年の段階で、上の文章(「どちらが本物か?(上)」)を公開し、ほぼ間違いなく、綾辻行人は、これを読んだはずなのである。
では、綾辻行人は、私の批判をどう受け止めたのだろうか?
それを考える上で参考となる、本書において「引っ掛かる」箇所を指摘しておきたい。
まずは、本書編者である太田克史による「序文」の、次のような冒頭部分である。
『 綾辻行人、法月綸太郎、我孫子武丸、麻耶雄嵩らを新人として世に問い、新本格ミステリ・ムーブメントを立ちあげ、講談社文芸図書第三出版部の部長時代には京極夏彦を筆頭に数々の人気作家を輩出したメフィスト賞を設立。令和の現在に至るまでの日本のミステリ・シーンを語る上で欠かせない偉大な仕事を成し遂げた名編集者・宇山日出臣。宇山日出臣は、不出世の編集者でした。』(P5)
まず引っ掛かるのは、冒頭の『綾辻行人、法月綸太郎、我孫子武丸、麻耶雄嵩らを新人として世に問い』の部分。
この四人を見れば、綾辻行人を筆頭に「京都大学ミステリ研究会」出身作家を並べたんだなというのはわかる。と言うのも、講談社ノベルス出身の「新本格」作家を、所属に関係なく、綾辻行人から並べれば、麻耶雄嵩の前にデビューした作家は、いくらでもいるからだ。
しかし、「新本格」を「京都大学ミステリ研究会」出身作家で代表させるのなら、どうして「清涼院流水」の名前がないのか、と引っ掛かりを覚える人も少なくないはずだ。

『消失!』の中西智明のように、「京ミス」出身とは言え、1作で消えた作家は別にして、今はミステリ作家をやっていないとは言え、清涼院流水は「新本格」の作家としてデビューし、一世を風靡し、その後に講談社ノベルスからデビューした、舞城王太郎、佐藤友哉、西尾維新といった作家らにも、大きな影響を与えた作家である。
それに、清涼院流水がミステリ作家時代、彼に伴走した編集者は、誰もが知るとおり、本書編者の太田克史なのだから、「新本格」を「京ミス」出身作家で代表させるのなら、清涼院流水まで含めるのが「自然」なのではないだろうか。
のちに、太田克史は清涼院流水とぶつかって決裂したという、いかにもありそうな噂は耳にしているから、それが理由で、ここから外したのかもしれないが、しかし、それにしても、これに続く文章には無理がありすぎる。
『京極夏彦を筆頭に数々の人気作家を輩出したメフィスト賞を設立。』
の部分だ。
これではまるで、京極夏彦が「メフィスト賞」の受賞者のようではないか。
しかし、実際には、第1回「メフィスト賞」の受賞者は、森博嗣(『すべてがFになる』)で、その半年後には清涼院流水(『コズミック』)が第2回受賞者となっており、いずれにしろ京極夏彦のデビューは、それ以前の話である。
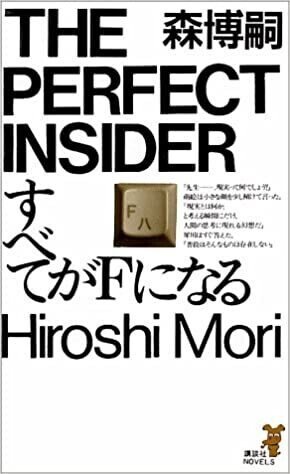

たしかに「メフィスト賞」というのは、持ち込み原稿でそのままデビューした京極夏彦の例がきっかけで設立された賞であり、その意味で京極を「第0回メフィスト賞受賞作家」と呼ぶことは可能だし、そのように呼ばれることもある。
しかし、それはあくまでも「そう言えば、言えないこともない」という程度の話であって、実際の受賞者である、森博嗣や清涼院流水の存在を無視して、京極夏彦に「メフィスト賞」を代表させるこの書き方は、事実関係の問題として、ほとんどペテンであり、レトリックの範疇を超えていると言うべきだろう。
ではなぜ、あえて京極夏彦の名だけを挙げたのか。それは紛れもなく、京極が「新本格第2期」を代表する作家だったからなのだが、それにしても、「メフィスト賞」の代表に、京極を持ち出すのは筋違いであり、ここで森博嗣の名を挙げておけば、それで済んだ話である。なのに、なぜそれをしなかったのか。
それは、宇山の創刊した『メフィスト』誌の後に、「清涼院流水以降」の新世代作家に特化した新小説誌『ファウスト』を立ち上げてヒットさせたのが太田克史その人であり、その場合、太田としては、縁の薄かった森博嗣の挙げても仕方ないし、清涼院流水は第2回受賞者だから、森博嗣をさしおいて名前を挙げることは出来ない。
そんなわけで、二人まとめて省き、京極夏彦と「メフィスト賞」を無理矢理つなげた、ということではないだろうか。

ちなみ本書には、森博嗣の追悼文寄稿はあるのに、清涼院流水のそれはないのだが、これは、清涼院流水にも寄稿を求めたが、本人が断った、ということだろうか。しかし、それは考えにくい。
というのも、本書における、徹底した「清涼院流水外し」を見れば、それがかなりはっきりとした「誰かの意志」に基づくもので、寄稿を断られたから、結果として「許せん」ということで、事後的に、ぜんぶ名前を削った、などという幼稚なこととは考えにくいからだ。
また、その根拠は、後で指摘するように、清涼院流水もまた、宇山が生んだ「新本格」作家の一人であって、太田が勝手に削っていい「宇山の仕事」ではなかったからである。
本書で、「清涼院流水」の名に言及されるのは、「評論家座談会」での佳多山大地による、次のような言及のみである。
『そういえば、先ほど巽さんのおっしゃった「自己破壊」はメフィスト賞のキーワードとしてたしかにありますね。今思い出したんですが、夜の編集部で唐木さんが、「宇山さんはやっぱり変わってる」てしみじみ僕に言うんです。凡百の編集者だったら、新しく京極さんが出てきたら、京極さんを潰そうとすると。ところが宇山さんはその京極さんの側に立って、「京極さんの凄さがわからない人たちはいりません」と言い始めたそうです。唐木さんは「そんな人はなかなかいない」と言ってました。僕自身が宇山さんから伺った体験では、流水さんのときもそうだったんです。ある作家さんが、彼を出すならもう僕は文三では書きませんと言ったところ、宇山さんは即答で「じゃあけっこうです」と言ったそうです。』(P315)
この佳多山大地の発言を読んで、引っ掛かりを覚えた人は、まったく正しい。
「清涼院流水ならいざ知らず、京極夏彦が『姑獲鳥の夏』を持ち込んできたときに、あるいはデビューしたときに、是が非でも京極夏彦を潰そうなんて考えた編集者や作家が、それほどにもいたのだろうか?」という、当然の「疑問」である。
だから、この発言のポイントは、実は「京極夏彦」の方にはなく、ついでのように語られる「(清涼院)流水」の方にあると見て良い。
実際、清涼院流水はそのデビューにあたって、綾辻行人デビュー時などとは比べ物のならないほどの、バッシングに晒された。
かく言う私自身、『コズミック』を読んで、壁に投げつけたくなったし、今でもその評価は変わっていないが、しかし、そんな私ですら、清涼院流水に対するバッシングは悪質なものと感じられたから、その一例である「鮎川哲也賞授賞式の来賓スピーチにおける、山口雅也の発言」を具体的に採り上げて、「新本格」作家たちの「清涼院流水バッシング」を批判したのである。
・「二枚のカード 一一京極夏彦と清涼院流水」(初出:1998年8月15日)
(https://note.com/nenkandokusyojin/n/na1c27c1c030e)
・「宿命的絶対性に抗する道」(初出:上に同じ)
(https://note.com/nenkandokusyojin/n/nad5acca843c9)
山口雅也が、「京大ミス研」出身である清涼院流水のデビュー作を、何の関係もない「鮎川賞授賞式の来賓スピーチ」で、露骨に「笑いもの・晒しもの」にして嘲笑できたのは、事前に、すでにデビューしていた「京大ミス研出身の新本格作家」たちから、清涼院流水の『コズミック』に対する酷評なり嘲笑なりを、聞かされ見せられていたからであろう。そうでなければ、綾辻行人以下の「京大ミス研出身作家」たちに気兼ねして、そんなことは出来なかったはずだからだ。

無論、これは「証拠」のある話ではないが、綾辻行人以下の「京大ミス研出身」の先輩作家たちが、清涼院流水の存在を快く思っておらず「仲間はずれ(ハミゴ)」にしてきたというのは、もはやミステリ業界や読者の間での「暗黙の了解」としての「周知の事実」ではないだろうか(麻耶雄嵩の本音は微妙だが、いずれにしろ「どっちについているか」は明らかだろう)。
本書で、太田克史が「清涼院流水」に言及したのは、司会として参加した、前記「批評家座談会」の次の部分だけである。
『 『コズミック』が出たときに、自分の思いを受け止めてくれたのが大森さん(※ 大森望)だけだったと宇山さんはよく話していました。みんなはわかってくれなかったけど、大森さんはわかってくれたと。宇山さんは100%誰かを好きになったり、逆に100%嫌いになったりもしなかった人なんです。好きな相手にほどいけずを言ったり、嫌っているはずなのに仲良くしたり、そういう複雑な方でした。大森さんに関しては、(※ 清涼院流水をバッシングした)みなさんに対するアンチテーゼとして深い愛情があったと思います。』(P308)
この、太田克史の発言にしても、引っ掛かりを覚えた人は、まったく正しい。
「宇山さんは、全身全霊で清涼院流水を庇った。それは誰にでもできることではない」という「偉大な逸話」に対して、結果としてではあれ、どうして、こんな「ひねくれた解説」をしなければならなかったのか、ということだ。
それは、「偉大なる宇山日出臣」が、綾辻行人以下の「京大ミス研出身の新本格作家」にすら嫌われている清涼院流水を、心の底から「高く評価している」と思われては「困る」と考えたからだ。そこで、宇山を「判官贔屓の、天邪鬼な性格の持ち主」だということにしたかった、のではないか。
つまり、「清涼院流水バッシング」をした「人気作家」たちを「悪者」にしたくなかった。むしろ、宇山に本当に愛されていたのは、「清涼院流水バッシング」をした作家たちの方なんだと、太田はここで無理筋の「フォロー」をした、ということではないか。一一「清涼院流水」という名前は、ひと言も出さないで、である。
本書において、清涼院流水とその作品に触れられるのは、清涼院のデビュー前、「メフィスト賞」にデビュー作『コズミック』の原型が投じられた際の「『メフィスト』編集部座談会」の第3回、つまり本書への「再録」部分(P354〜360)を除けば、以上の2箇所だけである(佳多山大地の発言と、それを受けての太田克史の発言)。
一一これを「不自然」とも感じず、そこに「意図的な無視」が働いているとも考えないのは、むしろ「無理」であり「不自然」なのではないか。
それでは、どうして太田克史は、そこまでの無理を押して「清涼院流水」を、本書から排除したのか?
自分自身が清涼院流水と決裂したから、その個人的な「腹いせ」から、この徹底した「差別・排除」を行ったのだろうか?
私はそうは思わない。
なぜなら本書は「宇山日出臣追悼文集」であり、宇山を追悼するために作られた本なのだから、宇山が身を挺して庇った「清涼院流水」を、個人的な恨みから排除するなどということは、傍目にも出来ないことであるからだ。
つまり、本書において「清涼院流水」排除がなされたのは、太田克史の「一存」ではなく、他からの「強い意志」が働いたからだと考える方が、よほど自然ではないか。
むしろ、太田としては、本書の内容上、清涼院流水に触れないのは不自然だから、個人的には嫌でも、清涼院流水に必要なだけは触れようと考えた蓋然性が高い。
ところがここで、有力作家から「彼を出すならもう僕は、その追悼文集には書きません」と言ってきたならどうだろうか。
その作家が書かないことには『宇山日出臣追悼文集』としての体裁をなさず、刊行がままならないとすれば、太田は嫌でもその意向に従わなければならないのではないか。
その結果、最大限の努力で「清涼院流水」の名前を排除した結果が、あの「不自然な序文」であり、本書に「清涼院流水」の名が出てくるのは「佳多山大地の発言」のみ、ということになったのではないだろうか。
もしかすると「佳多山大地の発言」についても「削除打診」をしたのかもしれないが、このような話題をわざわざ出した佳多山が、そのような打診を受け入れるとはとうてい考えられない。だから、太田は、「佳多山さんに断られました」と「人気作家」に報告をして、「やむを得ないな」と了承されたのかもしれない。
また、再録された「『メフィスト』編集部座談会」の第3回原稿については、太田が自身の実績のベースともなる「メフィスト賞」については、どうしても言及したい一方、同賞投稿者の名前は、デビュー前ということで伏せられており「清涼院流水」という「文字列」は出ないということで、本書への「再録」についても、「人気作家」に対して「宇山さんも参加しており、あくまでも宇山さんの仕事を顕彰するための資料ですから」と、了承を得たのではないだろうか。
以上、このように考えれば、本書において、きわめて不自然に「清涼院流水」の名前が遠ざけられている事実に、得心もいくのではないだろうか。
だとすれば、残る問題は、宇山に対して『彼(※ 清涼院流水の本)を出すならもう僕は文三では書きません』と言った、『ある作家』の正体、ということになろう。
○ ○ ○
この『ある作家』を限定する「要件」はいくつかある。
(1)宇山に対し、「もう書かないぞ」と脅すことができるほどの「人気作家」
(2)わざわざ清涼院流水という、デビュー前またはデビュー直後の新人作家について、そこまでの憎悪を向ける「近い関係性」
(1)については、説明するまでもないだろう。よほど、講談社ノベルズに貢献してきた「人気作家」でなければ、実績ある編集者である「宇山部長」に対し、こんなこと言えないに決まっているからだ。
したがって、この(1)の要件において、「容疑者」は、よほどの「人気作家」だけに絞られる。いくら実力があって、マニアックな評価が高い作家でも、「売れっ子作家」でなければ、宇山部長に対し「上から」こんなことを言えるものではないからである。
つまり、この「人気作家」に「私がこう言えば、さすがの宇山さんでも、私の方を選ばざるを得ないだろうし、選ぶはずだ」という「驕り」があったのは、確実なのである。
(2)についていうと、ここまで清涼院流水を憎む「人気作家」とは、例えば、東京創元社出身の「新本格作家」である有栖川有栖や北村薫や山口雅也などではあり得ない、ということだ。
さらに言うと、まだまだ新人だった京極夏彦や森博嗣だって、こんなことは言えないし、言うわけもない。
また、「新本格」と距離のある内田康夫などの「ベテラン人気作家」は、いくら影響力があったとしても、わざわざこんな「口出し」などするわけがない。まして、「本格ミステリ」以外の作家なら、清涼院流水を笑い者にこそすれ、『彼(※ 清涼院流水の本)を出すならもう僕は文三では書きません』などというわけはないのである。
ちなみに、自覚的にしろ無意識にしろ、この発言者の一人称が『僕』であるというのも、注目して良いポイントだ。この言葉を紹介した佳多山大地にしろ、この座談会原稿を起こしてチェックした太田克史にしろ、「この作家なら『僕』という一人称を使ったはずだ」という意識が働いたから、ここに『僕』と表記されたのであろうからだ。
例えば仮に、山口雅也が想定されていたのなら「俺」か「私」、有栖川有栖や北村薫なら「私」になっていた蓋然性が、きわめて高いのである。
しかしながら、私の絞り込みは、ここまでである。
言うまでもなく、私の頭の中にはハッキリと「犯人」の名前があるのだが、直接証拠はないから、宇山に『彼を出すならもう僕は文三では書きません』といった『ある作家』あるいは、この『ある作家』とはまた別人かもしれないが、本書の編集方針に関して、同様の注文をつけたかもしれない「人気作家」の名前を、状況証拠と「推理」だけを根拠に、公に語ることはできない。
これが「本格ミステリ」であれば、名探偵の「推理」に追い詰められた犯人は、「潔く自供して、自殺する」か、あるいは「どこに、その証拠がある。あると言うのなら見せてもらいたいものだな。実際、その日の僕は、これこれで」といらぬことを喋って自爆してくれるのだが、現実の「犯人」は、前者の「犯人」ほど潔くもなければ、後者の「犯人」ほどバカでもないから、だんまりを決め込むに決まっている。
つまり、作り物の「本格ミステリ」とは違って、「現実」とは、こんなに「非論理的」で「小狡いもの」であり、それは現実の「新本格ミステリ作家」とて、まったく同じであろう、ということなのである。
○ ○ ○
それではそろそろ「宇山秀雄・密室殺人事件」の謎解きに移ろう。
と言っても、私は、その現場に立ち会ってはいないので、私の推理は、あくまでも「アームチェア・ディテクティブ」でしかない。よって、「物的証拠」などなく、きわめて「抽象的な推理」にならざるを得ないということを、読者諸氏にあらかじめお断りして、お許しをいただいておこう。
その上で、私の「推理」の披瀝させていただくと、私が「宇山殺し」の犯人(主犯)と考えるのは、前述の『彼を出すならもう僕は文三では書きません』と言った「人気作家」である。なぜ、彼が「犯人」だと言えるのか?
それは、宇山を殺したのは「うつ病」であり、その「うつ病」へと宇山を追いやった「主犯」が、この「人気作家」だと考えるからだ。
つまり、宇山が「うつ病に殺された」というのは、ほとんど異論の出ない事実なのだが、では「何が宇山を、うつ病へと追いやったのか」という疑問については、「好きでもない管理職になり、そのストレスから」だろうという、きわめて「ぼんやりとした理由」しか語られていない。つまり、誰も責任を問われない、ごまかしの可能性が、そこにはある。
だが、だからこそ、宇山を「うつ病」にまで追い込んだ「問題」とは「何か」と、一度は具体的に問うべきではないか。
宇山をうつ病に至らせた、その「状況」を引き起こした(設定した)中心人物やその関係者は「誰なのか」ということが、これまでは、まったく語られておらず、「禁忌(タブー)」めいたもの、あるいは「意図的敬遠」「口封じ」の対象になって、皆が口を噤んでいる可能性があるのである。
宇山は、編集者という現場仕事に生きがいを感じていた。そんな彼が、自身の望まぬ部長職を嫌々ながらも引き受けたのは、敬愛する中井英夫の別荘「流薔園」に倣って、気の合う仲間が集まるための場所をと考えて、「別荘」を購入したからである。その費用なり借金なりを捻出するためには、部長になって、少しでも稼がなければならなかったのだ。
したがって、部長職が「つまらない」というのは、宇山自身、事前に承知していたことだし、それなりに覚悟もしていたことであった。無論、宇山自身、実際に部長になってみれば、予想したよりもずっと大変だとか、つまらないとかいったことはあったのかもしれない。しかし、それはそれだけのことであり、それが「うつ病」になるほど嫌で嫌でたまらないとしたら、最後は「降格」を申し出て、給料は下がっても、また元の楽しい編集の現場に戻ればよかっただけ、なのである。病気になっては、元も子もないからだ。
だが、宇山は、それをしなかった。一一何故なのか?
単に宇山が、自分の苦しみを自覚がなかった、ということなのだろうか?
しかし、それはない。何故なら、宇山は生前、部長職のつまらなさについては、周囲に漏らしていたからである。
では、なぜ宇山は、部長職を放り出さなかったのか?
それは、宇山を悩ませた「主たる理由」は、「部長職」ではなかったからである。
宇山を徹底的に苦しめたその「悩み」は、部長を辞めて、編集の現場に戻ったところで、消えてなくなるようなものではなかった。つまり、編集の現場にある問題でもあった。
だから、部長職を辞めても、何も解決はしなかったため、宇山は部長職のまま、その「難問」と格闘し、ついに敗れたしまったのである。
では、その「難問として悩み」とは、何か?
それは、自身が育てた「作家内での対立的人間関係」だったのではないだろうか。
宇山としては、『彼を出すならもう僕は文三では書きません』と言った「人気作家」も、可愛かった。自分が育てた大切な作家だった。
しかし、それは「清涼院流水」とて同じことであり、「人気作家」の意を受け入れて、「清涼院流水」を抹殺するなどということは、到底できなかった。
宇山は、綾辻行人が言うとおり、自分の「美意識」に忠実に生きてきた人であり、それは法月綸太郎が本書所収の追悼文で指摘しているとおり、尊敬する中井英夫の「編集者としての仕事」に倣うものでもあった。だから、「有力作家」から『彼を出すならもう僕は文三では書きません』と言われても、ハイそうですかと従うことなどできなかった。宇山の脳裏には、寺山修司たち「異端の新人たち」を身をもって庇い続けた中井英夫の姿が、くっきりと浮かんでいたからである。
だからこそ宇山は、「じゃあけっこうです」と、断腸の思いで「即答」できたのである。

しかし、この問題は、これですべて、カタがついたわけではない。
清涼院流水がデビューし、それなりの人気作家へと育っていっただけではなく、清涼院の小説を支持する若い読者が現れ、その中から舞城王太郎、佐藤友哉、西尾維新といった「人気作家」が生まれてきたのだから、清涼院流水を支持した宇山を責めた「人気作家」やその仲間たちが、これを面白く思うはずがない。
だからこそ、彼らは「あんなものは、本格ミステリではない」と陰口し始めた。
たしかに、清涼院流水の小説は「本格ミステリ」ではないだろう。だがそれは、彼をデビューさせた、宇山をはじめとした「文三」の編集者たちだって、初めから承知していたことだった。
彼らが「メフィスト賞」の新人に期待したのは、巽昌章の言う『自己破壊』だった。
それは、綾辻行人以降の「第1期新本格」作家たちが体現した「ミステリマニアによる本格ミステリ」という「前例」に縛られず、むしろそうした「殻」を打ち破って生まれてくる、「新しい何か」であったはずである。

だから、宇山が、清涼院流水を擁護したのは当然のことだし、清涼院流水の作風を「あんなものは本格ミステリではない」と貶した「本格ミステリ至上主義者」という「権威主義的伝統主義者」たちは、宇山たち編集者の「メフィスト賞」に込めた思いを、完全に読み違えたか、意図的に無視して、それを全否定したのである。
つまり、部長になって以降の宇山を取り巻いていた「環境」とは、「清涼院流水以前」と「清涼院流水以後」の作家たちの「対立的感情」に満ちた、言うなれば、心理的な「修羅場」だった。
それに対し、宇山は、基本的には「中立的」であろうとしただろうが、しかしその一方で、その「中立」とは「ことなかれ」ではなく、「弱い者を守る=強きのイジメに加担しない」という原則を保持したうえでの「中立」であったから、どうしても宇山は「古参勢力(清涼院流水以前の作家)」の側から「どうして、清涼院たちの肩を持つのか」と責められるかたちにならざるを得ず、その不本意な「板挟み」状態によって「心労が絶えなかった」というのは、まったく想像に難くないのである。
つまり、宇山を「うつ病」へと追い込み、死に至らしめたのは、宇山の編集者としての思いを尊重せず「どっちの味方なんですか」とプレッシャーをかけることしかしなかった、従来の「人気作家」たち(清涼院流水以前の、一部の「新本格」作家たち)である、と言ってもいいのではないだろうか。
無論、「うつ病」の原因は「一つではない」という意味において、この「宇山殺し」が「単独犯」によるものだとまでは、私も言わない。
だからこそ私は、「宇山殺し」の「主犯」は、宇山に『彼を出すならもう僕は文三では書きません』と言った『ある作家』だと言うのである。ただし「主犯」の周囲には、少なからぬ「共犯」者たちがいた。だから、宇山は「八方塞がり」の状態に置かれた。
それでも、彼らだけが「宇山殺しの犯人」なのではないだろう。だが、彼らは「主犯」か「主犯に近い犯人(共犯)」であり、「部長職」などというものは、「役職に口なし」で、申し開きすることができないのにつけ込まれ、「全責任をなすりつけられた」もの(従犯)に過ぎないのではないだろうか。
そうした意味で、「宇山殺し」の主犯は、宇山の近い位置にいた「清涼院流水以前」の「人気作家」であり、第三者の目には「宇山の最大の理解者」とも映っているであろう、「意外な人物」なのではないだろうか。
○ ○ ○
では、最後に残った「密室殺人」の謎はどうだろう?
私はこの「密室」を、「囲い込み」の象徴であると考える。
つまり、「宇山秀雄」という編集長を、「自分たちの理解者」であると、世間に向けてアピールすることで、他でもない、自分たちの価値を高めるために、宇山を一方的に、囲い込んだ。
そのことで、結果として宇山は、その「脱出不能な閉鎖空間で死なざるを得なかった」のではないか。
一一これが、「宇山秀雄・密室殺人事件」に対する、私の「本質直観」である。
これが、正しいのか、まったくの見当違いなのか、宇山に近かった人々、容疑者を含めた、関係者の意見を是非伺いたいものと、私は考えている。
もしも「宇山殺し」に、世間では知られていない「真犯人」が存在するのであれば、それは野放しにされて良いようなものではなく、宇山の弔い合戦のために、「真相」は明らかにされなければならないのだ。
『「むろん、探偵小説よ。それも、本格推理長編の型どおりの手順を踏んでいって、最後だけがちょっぴり違う一一作中人物の、誰でもいいけど、一人がいきなり、くるりとふり返って、ページの外の〝読者〟に向って〝あなたが犯人だ〟って指さす、そんな小説にしたいの。ええ、さっきもいったように、真犯人はあたしたち御見物集には違いないけど、それは〝読者〟も同じでしょう。この一九五四年から五五年にかけて、責任ある大人だった日本人なら全部犯人の資格がある筈だから」
「そんなの、嫌だな」』
(宇山秀雄版講談社文庫『虚無への供物』P628)

-------------------------------------------------------------
【補記】(2022年4月27日)
出版社が「追悼本」をクラウドファウンディングで刊行するというセンス
本書『新本格ミステリはどのようにして生まれてきたのか? 編集者宇山日出臣追悼文集』については、言いたいことは山ほどあるが、レビュー本文に関しては、「宇山殺し」の真相推理に限定させていただいた。
しかし、残る多くの問題・疑問のうち、いくつかについては、どうしても指摘しておきたいので、ここに「補記」として書かせていただく(他の細々とした問題については、後日別稿で書くことになるだろう)。

私の、主たる「疑問点」は、次のようになる。
(1)なぜ宇山の「追悼文集」が、没後15年も経たないと刊行されなかったのか? また「なぜ今」なのか?
(2)どうして、この『追悼文集』の刊行に、目標額たった「10万円」のクラウドファウンディングが必要だったのか?
(10万円が集まれば、ソフトカバーがハードカバーになるという説明があるが、10万円くらいなら、誰か恩義のある人が、ポンと出しても良い金額ではないのか。つまり、このクラウドファウンディングは、単なる「商業出版物の宣伝」でしかないのではないか)
(3)追悼文執筆者に「原稿料」が支払われたようにしか見えないが、その理解でいいのか?
(ちなみに、鮎川哲也追悼文集『本格一筋六十年 想い出の鮎川哲也』は、「偲ぶ会」用に、原稿料なしの自費出版で作られ、それが評判となり、一般ファンからの求める声が多かったため、自費出版版を増補するかたちで、一般書籍化された。また、自費出版版では、寄稿されていた山口雅也の追悼文を落とすという編集上の致命的なミスがあったため、それを補うという意味合いもあった。したがって、最初から、原稿料を払って商業出版するというのとは、まったく意味合いが違う)

以上のような「金目の話」をするのは、本意ではない。
しかし、近親者・関係者による「資金提供」「寸志」あるいは「支援金」を募って作るのが「追悼文集」の本来の姿であって、直接関係のない第三者に対し、「掲載原稿の先読み券」だの「有栖川有栖・綾辻行人(有料)対談の無料視聴券」だのを「返礼品」として「支援金」を募るというのは、どこかの「ふるさと納税」にも似て、欲に駆られた、本末転倒のようにも感じられるが、いかがであろう。
果たして、この企画は、後年「新本格の黒歴史」になったりはしないのであろうか。
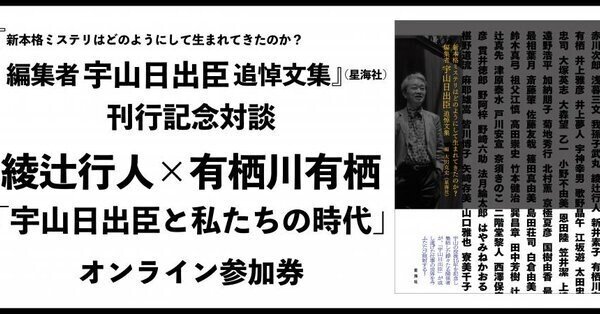
実際、私は「支援金」など出してはいないが、「定価3,180円(税別)」を支払って本書を購入しており、これが宇山氏へのいちばん真っ当な「供養」だと思っているし、この、私の他には誰も書かないであろうレビューを書くのも「供養」だと思っている。
ともあれ、こうして集まった「売上金」や「支援金」を前提として、あらかじめ追悼文執筆者たちに(いつも通りに)「原稿料」が支払われていたのだとしたら、それは単なる「商売」としか思えず、なんとも釈然としない気分が残ることになる。
最初の疑問に戻ってしまうが、宇山氏の追悼文集が、没後15年を経た今頃になって突然作られたこと、本書に宇山夫人の原稿がなく、最後の最後に小さく「スペシャルサンクス」が刷られているだけ、といったことは、こうした私の「疑問」と、まったく無関係なのであろうか?
宇山秀雄をいう「不出世の編集者」の追悼文集であればこそ、私はそれが「権威利用目的の囲い込み」に利用されただけではないのか、という疑念を禁じ得ないのである。
・クラウドファウンディング「人気作家、大集結! 新本格ミステリの父と謳われる名編集者の追悼文集をつくりたい!」
○ ○ ○









(2022年4月27日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

