
ゲームを葬る〈メタ・ゲーム〉 : 小川哲 『ゲームの王国』
書評:小川哲『ゲームの王国』(早川書房)
私は「ゲーム」が好きではない。
と言っても、私の好きではない「ゲーム」とは、伝統的な「ゲーム」のことであり、例えば、囲碁、将棋、コントラクトブリッジといった厳格なルールを持った「知的ゲーム」の話で、アーケードゲームとかテレビゲームなどは、必ずしも嫌いではない。
囲碁、将棋、コントラクトブリッジといった厳格なルールを持った「知的ゲーム」があまり好きではない理由は、ルールを完全に体得して、それを楽しめるようになるまでに、それなりの時間を要し、それまでは、基本的につまらないからである。つまり、面白くなるまで、面白くもないゲームを、練習のつもりでやろうとまでは思わない。私はせっかちなのだ。
その点、習得までに時間のかかる複雑なものもあるとは言え、アーケードゲームとかテレビゲームなどは、ある程度なら最初から直感的に楽しめるものが多いので、むしろ好きと言うよりは、すぐにハマってしまいがちで、それが怖くて、大人になってからは意識的に遠ざけるようになった。
そもそも、いずれにしろ「ゲーム」というのは、やったからといって、何も身につかないのに、「時間」だけはやたらに食う娯楽でしかないから、あまり好きにはなれないし、好きになりたくもない。
(パチンコなどの「カネ」のかかるゲームは論外であり、まして賭博は愚かしい。したがって、課金で金を巻き上げられる類いのゲームも、自制心のない馬鹿のやるものだと思っている)
私は、高校生の頃から読書という趣味にはまり、これまでそれを生涯のものとして、自覚的に楽しんできており、あれも読みたいこれも読みたいと、無闇に本を購入しては、今から10数年も前には、すでに新たに本を買わなくても、死ぬまでに読みきれないほどの未読本を所蔵するに至った。
つまり、それらを読もうと思えば、ゲームなどにうつつを抜かしている暇など一時たりとも無いので、わざわざ、多くの時間を費やしてまでゲームを楽しめるようになろうなどとは思わないし、すぐに楽しめるとしても、あとに何も残らないに等しいゲームに、膨大な時間を注ぎ込むことなど、到底できない相談なのである。
だから私の場合、好きなアニメも含めて、同じ理由で「連続もののドラマ」は、基本的には鑑賞しない。
放映終了後も、よほどの高い評判の続くような画期的な傑作(例えば『新世紀エヴァンゲリオン』『魔法少女まどか☆マギカ』など)ならば、あとでまとめて観ることはあっても、「流行っている最中」の作品は観ない。なぜなら、そうした作品の多くは、放映が終了するとともに、急速に話題にも登らなくなってしまうような「消費的娯楽作品」でしかないからだ。
したがって、私は、ドラマやアニメを見る場合にも、数時間で完結する映画作品などに限定している。それなら、結果として、さほどの作品ではなかったとしても、「時間的被害」を最小限に抑えることができるからである。
では、そんな私が「読書」を生涯の趣味とした理由とは何か。
それは、「読書」の場合そのほとんどで、鑑賞中の「楽しみ」とは別に、自分の「身につく要素」があるからだ。
そしてそれは、単なる「知識」だけではなく、「鑑賞力」「読解力」「思考力」といったものであり、そうしたものは、仮に娯楽小説の鑑賞であっても、一種の「脳トレ」的な要素を持ち、その意味での充実感を伴うのである。
また、言い換えれば、読書の中で、一番つまらないのは「娯楽小説の凡作」の鑑賞だと言えるだろう。それでは、ほとんど何も身につかないからである。
だからこそ、私は「面白いと評判の、やたらに売れている流行小説」というのは、基本的に敬遠する。読んで何かが身につくような作品が、一般大衆的に流行するなどということは、ほぼ無いからである。大衆が娯楽小説に求めているのは、基本的には「現実逃避」と「各種感動によるカタルシス(非理性的浄化作用)」でしかないからだ。
○ ○ ○


本作『ゲームの王国』には、それぞれに違ったかたちではあれ、厳格なルールによって規定された「ゲームの王国」を理想として希求した、二人の主人公、ムイタックとソリアが登場するのだが、前述のような「ゲーム嫌い=純粋遊戯嫌い」の私からすれば、「現実逃避的」でしかない、という点において、どちらも十全に納得しうる主人公ではなかった。
仮に、自分の「理想」を実現できなかったにしろ、その「理想」が「理想と呼ぶに値するもの」であったならば、私はその「未到達」や「中途挫折」もやむを得ないものと考えるし、「理想」を殉じた彼らに同情もしただろう。
だが、ムイタックとソリアの場合は、その「理想」が、もともと無理のあるものでしかなく、作中で描かれるほど「頭が良い」のであれば、もっと早くに、その「無理」に気づいてしかるべきであった。なのに、この二人は、その「趣味的な理想」に趣味的に執着して、必然的な失敗・敗北に終わるだけなのである。
作者は、そんな主人公の二人に同情的であり、彼らの「必然的な失敗・敗北」を、なにやら「美しいもの」のように描くのだけれど、それは私に言わせれば「小説家のレトリック」によるものでしかなく、客観的に見れば、彼らは「それほどのもの」ではない、というのが、私の下した評価であった。
○ ○ ○
本作では、カンボジア現代史における「ポル・ポト政権下の悲劇」が扱われており、その点に多く「好奇の目」が集中したようで、文庫版の「あとがき」でも、著者は、何度も繰り返されるその種の「陳腐な質問」にいささかうんざりして、そうとは気づかれないように回答をはぐらかしてきた、という趣旨のことを書いている。
さて、私はすでに、本作著者である小川哲について、次の三本のレビューを書いている。
(1)『嘘と正典』レビュー「小川SFにおける〈静かな諦観と叙情性〉」(2020年5月4日)
(2)東浩紀・樋口恭介との鼎談レビュー「この平凡な現実:「小川哲×樋口恭介×東浩紀「『異常論文』から考える批評の可能性 ──SF作家、哲学と遭遇する」」を視聴する。」(2022年2月5日)
(3)『ユートロニカのこちら側』レビュー「〈後期クイーン的問題〉の作家・小川哲のユートロニカ」(2022年2月28日)
小川は、(2)の鼎談の中で「両親が、共産党員あるいはそのシンパ」であったという事実を、予防線を張りながらも告白的に語っていたが、私は、そのことを根拠として、(3)のレビューで、笠井潔の『バイバイ、エンジェル』を参照しつつ、次のように書いた。
『「豚のような人民大衆」は、「恵まれた生活環境」という「餌」さえ与えられれば、それで満足してしまうような「尊厳なき存在」なのだ、ということである(※ だから、革命は永続し得ず、必ず裏切られる)。
そんなふうに小川は、両親の「共産党員としての徒労」を通して、『諦観』を育んだのではないか。』
私は、最初に読んだ小川作品である『嘘と正典』のレビューにおいて、小川の「両親が、共産党員あるいはそのシンパ」であったことを知らないままに、その〈静かな諦観と叙情性〉を指摘していたのだが、それが、(2)の鼎談での前記の発言に裏付けられて、(3)での、上記のような「読み」へと発展した。
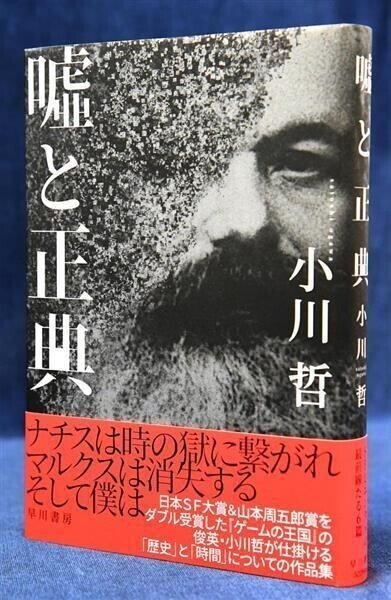
そして、そうした点を踏まえて、本作『ゲームの王国』を読めば、二人の主人公の「理想とその挫折」の物語は、決してわかりにくいものではないし、なぜ「ポル・ポト」を描いたのかも、なんら疑問を残さず解消し得る。
小川のような「経歴」の持ち主が、「共産主義の理想と挫折、そしてその悲劇」を描こうとすれば、作品の舞台となるのは、国内だと「日本共産党の世界同時革命の挫折」とか「左翼学生運動の挫折」などになるだろうし、海外に舞台を移せば「ソ連共産主義の変節」あるいは「フランス革命の省察」みたいなものが考えられるけれど、こうしたものは、ハッキリ言って「いまどき流行らない」。
となれば、すでに過去の事件だとは言え、まだまだ日本では十分に掘り下げられたことのない、大虐殺の惨劇をともなった「ポル・ポト政権下の悲劇」という題材は、マスコミ的には、実に良い着眼であったと言えるだろう。それは、その「オリジナリティ」と「話題性」において、多くの「知識人」の注目を集め得るものだったのである。

(ポル・ポト)

(作中でも描かれる、都市市民の強制移住)
さらに、このような、いささか派手な「舞台」をしつらえた作品であったからこそ、作者個人の内的こだわりである「共産主義運動の挫折=理想の挫折」というものが、うまく韜晦された、とも言えるだろう。
本作『ゲームの王国』は、「ポル・ポト政権下の悲劇」を背景や舞台にしたからこそ、より身近な「共産主義運動の挫折=理想の挫折」を描き得たのではなく、「共産主義運動の挫折=理想の挫折」を描くのに、もっとも陳腐にならない舞台として「ポル・ポト政権下の悲劇」が選ばれた、と考えるべきなのだ。

つまり、『ユートロニカのこちら側』で描かれた、次のような「オマージュ」が、本作では中心に据えられて、全面展開していると読むべきなのである。
『『思い入れがあるのは刑事スティーヴンソン。もともと彼が主人公の長篇を書く予定でしたから。』と(※ 『ユートロニカのこちら側』の著者・小川哲が)答えているからといって、これがそのまま「いちばん共感できるのは刑事スティーヴンソン」だという意味ではない、と考えるべきだろう。
無論、だからと言って、読者を偽るための「フォロー」として言っているだけとも、断じられない。
言うなれば「刑事スティーヴンソン」は、「理想としての共産社会の実現を願った、理想主義者だった両親」への共感と反発、そのアンビバレンツな感情が込められた、愛着ある「敗者」としてのキャラクターだったのではないだろうか
(「〈後期クイーン的問題〉の作家・小川哲のユートロニカ」より) 』
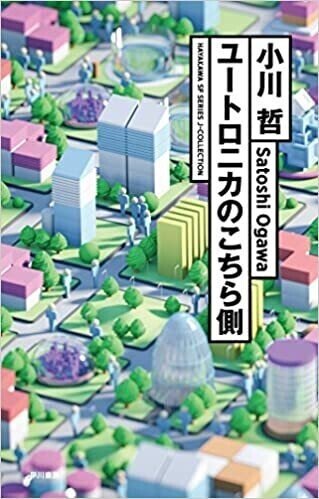
つまり、本作『ゲームの王国』は、ルールの厳守される世界としての「ゲームの王国」を「理想の社会」として求め、その政治的実現に生涯を賭けたソリアと、「現実」を捨象して「純粋な抽象ゲームの世界」に退却して生きようとしたムイタックという、両極端の「理想主義者」が、「現実」の中で敗れ去っていく姿を、「敗者の純粋性」への「オマージュ」を込めて描くことによって、そうした「理想」を「精算・葬送」した。つまり、そのどちらも選ばない著者・小川哲自身は「俗な世界を、俗なままに渡っていく」という、そんな「諦観」に満ちた生き方を選ぶことの「けじめ」として、本作『ゲームの王国』を書き、そうした「夢想=理想」の不可能性を、アリバイに作りとして書いた、といったことなのではないだろうか。
したがって、結局のところ本作『ゲームの王国』は、両親のように「理想を掲げて生き、そして必然的に敗れる」ような「愚かな人生」を選ぶことのできない、「賢い」作者が、「脱理想主義的な人生」を選択したことの「アリバイづくり」のための作品だ、ということになるのではないか。
「理想主義の敗北」をあざ笑うだけなら、「ネトウヨ」のような、知性と想像力を欠いた豚どもにだって可能だろうが、当然、小川は、自身をそのようなものと同列に置きたくはない。
ならば、「理想主義者」たちの想いに理解を示しつつも、しかしそれが、所詮は非現実的であり、その意味で思慮を欠いた「特攻」にも似たものでしかないと考えるから、自身はそれを選ばずに「この薄汚れた世界の中で、薄汚れながら生きていくことを、選択するしかないのだ」と、「アリバイ工作」的に語った作品だ、ということなのではないだろうか。
無論、こうした言い方は、著者に対して厳しすぎるだろう。
そもそも、著者がこうした「現実認識」や「世界観」という「諦観」を持っていたとしても、それはむしろ「正しい」ものであるとも言えるし、私自身、おおむねそのような「悲観的な世界観」と「諦観」を持っている。
しかし、私が、小川哲のこうした「身振り」に批判的なのは、結局のところそれが「賢しらな自己正当化」でしかなく、両親の「愚かな理想主義」への「オマージュ」に見せかけた、「あらかじめの敗者」たる、自身の生き方の正当化でしかない、と感じるからである。
つまり、「薄汚れた生き方」を選んだのであれば、両親のことなど引き合いに出さず、黙って、自らの選んだ生き方の「責任」を引き受けて生きていけばいい。その方が、言い訳がましくなくて潔く、「美しい」ということだ。
ところが、小川の場合は「私も本当は、きれいな理想に生きたいんですよ。ただ、両親の生き方を目の当たりにして、その理想の不可能性を見てきた私としては、もう理想を信じることなどできないから、私は、好むと好まざるとにかかわらず、この薄汚れた世界で、薄汚れて生きていかざるを得ないのです(だから、そんな私を責めないでください)」というような「賢しらな、予防線的言い訳」を、小説というかたちで、世間に頒布して「アリバイ工作」をしているにも等しいと感じられ、私としては、そんな見苦しい言い訳など聞きたくない、ということにもなるのだ。
このような意味で、小川哲という人は「とても頭がいい」というのは間違いない。
しかし、だからこそ、(2)の論文で指摘したとおり、他人を「コントロール」しようとしてしまいがちなのだ。「こう書けば、読者が共感しつつ、こう読むだろう」というのを十二分に考えながら、読者を、自身の「人生観」を肯定する方向に誘導するのである。
無論、小説であれ論文であれ、あらゆる文章は、そうした「自己正当化」と「支持者の拡大」を意図したものであろうけれども、私が小川に反発をしてしまうのは、「諦観」というキーワードに象徴される、いわば「泣き落とし」戦術を、そこに感じるからだ。
ちょうど、エラリー・クイーン作品における「操り」の問題を、真っ先に論じたミステリ作家・法月論太郎の、初期「泣き落とし」小説的な側面を、小川の書きっぷりにも感じるから、私は「そんな泣き落としには乗せられないぜ。そんなものが通用するのは、けんご@小説紹介なんかがオススメの、泣ける通俗小説ばかり読んで、感動消費している、いささか頭の弱い、豚のような大衆読者だけだろう」と考えるからである。
私は、こういう読者について、しばしば、次のような警告を発する。
「あなたがたみたいに、薄っぺらい感動消費に明け暮れているような人間は、そのまま歳をとったあげく、いずれは特殊詐欺の良いカモになるだろう。今でさえ、そんなのなんだから」と。
○ ○ ○
そんなわけで、本作『ゲームの王国』を、「(技術的に)よく書けた小説」だと評価しないでもないのだけれど、その「意図するところ」がいささか卑しいと思うので、本作を絶賛推薦した著名な人気作家たちとは違い、私はこの小説を、無条件に肯定する気にはなれない。


たしかに、現実離れした「理想」の先には、敗北という現実が待ち受けているのかもしれないが、しかし、安っぽい「感動」の先にあるのも、また間違いなく敗北である。
いまどき流行らない、古い格言で恐縮だが、私は基本的に『肥った豚になるよりは、痩せたソクラテスになりたい』という、J・S・ミルに共感する、古い人間である。だからこの格言を、次のように言い換えておきたい。
「感動という投げ与えられた駄菓子に目の眩んだ豚であるよりは、不可能な理想をそれでも凝視する、飢えた狼でありたい」
以下では、本作からの引用を示しつつ、以上の「読み」の根拠を示しておきたいと思う。
したがって、以上の「読み」を、納得できなかった人だけに、お読みいただければ十分であろう。
○ ○ ○
(01)『 闇の中からは、光がよく見える。チョムラウン・ビチァ高校の歴史科教師サロト・サルは、子どものころからその諺を気に入っていた。暗闇から明るいものはよく見えるが、明るい場所から暗闇はほとんど何も見えない。この諺から「輝いているときこそ、足元の落とし穴に気をつけなければならない」という教訓を引きだした国語教師は残念ながら二流だった。正しい解釈は「足元の穴に落ちたくなければ、そもそも輝いてはいけない」ということだ。輝けばかならず闇から撃たれる。それが世の摂理だ。』(文庫版上巻P7)
「サロト・サル」とは、「ポル・ポト」の本名である。
ここでポル・ポトが言っているのは、要は「馬鹿と煙は高いところが好き」ということだ。賢い人間なら「目立ち」たがったりはしない。
もちろん人間だれしも、他人からもてはやされたい、チヤホヤされたいという願望が抜きがたくある。つまり「光の当たる場所」である「高いところ」に立って、注目を浴びたい。そして賞賛されたい。
しかし、他者からの賞賛は、同時に他者からの妬みを、必然的に招いてしまう。
そして何より厄介なのは、「賞賛」や「光」や「高いところ」には、すぐに慣れてしまって、嬉しくもありがたくもなくなってしまう点だ。
だが、自身に向けられた「悪意」や「敵意」といったものの方は、日々新しく、そう簡単に慣れることのできるようなものではなく、主観的には、自身に向けられた、そうした「負の感情」ばかりが、常に意識されてしまう。
だからこそ、賢い人間は、標的になりやすい「光の当たる場所」や「高いところ」に登るのは避けて、その真逆である場所に止まることを、あえて選ぶのである。
しかし、言うまでもなくこれには、非凡な「自制心」が必要だ。わざわざ、泥まみれの塹壕に身を隠し続ける「忍耐」は、誰にでも持てるものではないからだ。
(02)『いかに自分の評判がよかったとしても、そんなものはたった一日でひっくり返る。それくらいよく知っている。現に今日、自分はある人物の評判をひっくり返そうとしている。こういった世界では、風向きが変わってしまえばすべて終わりだ。たった一度の間違いも許されないし、たった一度の不運も許されない。』(文庫版上巻P9)
周知のとおり、これは「人気アイドル」などによくある話だ。
彼や彼女は、所詮「アイドル=偶像」であって、「人間」であってはならない。だから、脱糞してはならないし、セックス中毒であってならないのだ。
だが、彼らとて、現実には「人間」なのだから、その期待に応え続けるのは、しばしば「苦行」以外の何物でもないのである。
(03)『 気をつけるべきは、人間は他人の発言のニュアンスに自分の願望を反映させやすく、それがさまざまな物事を難しくしているということだ。人間の曇った眼は、当たり前の挨拶に知性を見出し、質問の無理解による誤答に詩情を汲みとる。そうやって知性は過大評価をされ、まぐれが実力だと勘違いされていく。誰とは言わないが、そうやって党の内部で影響力を増していった者もいる。しかし今ではそのことをよく知っている。底の浅いまぐれや知ったかぶりに騙されることはない。さまざまな失敗の経験を通じて、ソオンは他人の知性に対しては慎重に判断を行うようになった。それゆえに、数々の奇跡的な体験を経たあとでも、彼の八歳の甥ムイタックが聡明かどうか、その判断は保留していた。』
(文庫版上巻P127〜128)
基本的に、人間の目では「客観的に、完全に正しい評価」というものは、不可能である。あらゆる「評価・判定」は、その評価者・判定者というフィルターを通さないわけにはいかないからだ。これは「機械」であっても同じである。
しかしまた、そうであるからこそ、「アイドル」だの「人気作家」だのといった「美しい夢」も存在しうる。
人々の目が、研ぎ澄まされた哲学者や批評家のそれと同じレベルであったなら、「アイドル」や「人気作家」などという「幻想」は、ほとんど存在し得なくなるだろう。「無知盲目」であるからこそ、天使や天国も、リアルに「夢想」し得るのである。
(04)『「ベンが鬼ごっこに強いのは『足が速い』という評判のおかげだ。この話をひっくり返すと、さらに多くのことがわかる」
「何がわかるの?」
「つまりね、一度足が遅いと評判になった者は、不当に追われ続けるってこと。君は足が遅いわけではないのに、『足が遅い』という評判のせいで、集中的に鬼に狙われている。鬼ごっこは基本的に追いかける側が有利だから、一度狙われれば捕まりやすい。そのせいで足が遅いというイメージが強くなり、さらに捕まりやすくなるってわけ。君だって鬼のときは無意識に『足が遅い』とされている人を探してるはずだよ。豆フムとか、ルットとか、蟹ワンとか。蟹ワンは左足だけ拾った靴を履いているせいで、蟹みたいな走り方をしてるから目立つしね。あいつ、実は結構足速いと思うけど」
「なるほど。たしかにその通りだ。僕はいつも豆フムやルットや蟹ワンを探してる。それに実際には、いつも蟹ワンを捕まえるのに苦労してた」
「この話にはさらに続きがある。この世の中のなんだってそうなんだ。王様だってね。一度偉くなってしまえば、そのおかげでみんな彼が正しいと思いこむ。何か間違ったことをしているように見えても、自分の方が間違っているのではないかと思い直す。そして王様の権威は増していき、本当の実力とは関係のない虚構のイメージが作り上げられていく。そしてそれは、たとえば俊足ベンみたいに、王様がひとりで作り上げるものではなく、周囲と連動して勝手に作り上げられていくものなんだ」』(文庫版上巻P157〜158)
これも、(02)の議論と同じことである。
人々の「見えない眼」があるからこそ「幻想」が成立し、「幻想」があるからこそ、この世の大半の「ゲーム」が成立している。
「完全に透徹した眼」や「悟り」といったものは、「この世(のゲーム)」への関わりを断念させるものになるだろう。「この世界に、意味など存在しない」と。
(05)『 サルは耳が割れそうなほどの拍手の音で我にかえり、ようやく話を終えることができた。
「最初に拍手をやめた人間が粛清される」という党の都市伝説のせいもあって拍手は鳴りやまなかったが、そんなことはどうでもよかった。拍手のひとつひとつの音が光となり、自分の目を潰そうとしてくるようだった。
自分の話が暴走した。コントロールできなかった。こんなことは今まで一度もなかった。これまで、喋りたいことがあれば、他の誰かに喋らせるように仕向けていた。今だって、同じ内容を誰かに喋るように操作することができたはずだ。』
(文庫版上巻P256)
「馬鹿と煙は高いところが好き」と賢く悟っていたポル・ポト(サル)ですら、愚かにもそこに登ってしまい、文字どおり「サル」並みになってしまったという、ありきたりな現実である。
ことほど左様に、能力がありながら塹壕の日陰に踏みとどまるというのは、賢いだけではない、非凡な人間にしかできないことなのだ。
無論、ここでのポル・ポトが、作者である小川哲の、自虐的「戯画」であるのは、言うまでもない。
(06)『「いや、違う。ラディーはそう考えた。まったくもって違う。自分が楽しんでいたのは安全な場所から正義という鉄槌を振り下ろす行為だ。ビルの屋上からスナイパーライフルで一方的に敵を狙撃する。盗みを働いた者を公衆の面前で罵倒する。
資本主義者として共産主義者を拷問する。共産主義者として資本主義者を拷問する。別にどちらでもいい。問題は自分が正義の側にいるかどうかだ。勝ち馬に乗っているかどうかだ。そう、可能であれば、九十九パーセントの勝負がいい。百パーセントこっちが勝つとわかっているとスリルも張りあいもない。だからといって五十パーセントの勝負では負ける可能性が大きすぎる。九十九パーセントだ。圧倒的有利で、およそ間違いなく勝てる状況での勝負がしたいのだ。』
(文庫版上巻P362)
ラディーは、本作における「憎まれ役の悪党」である。
だが、彼のこうした考え方は、誰の中にでもあるものでしかない。だからこそ、彼は「エンタメ」である本作において「憎まれ役」たり得ているのである。彼は、私たち自身の「見たくない横顔」なのだ。
事実、ネットを見れば、こうした輩が山ほどいる。それは、一人では何も言えないくせに、多数派になった途端、「正義」を振りかざして、毛色の変わった人間を袋叩きにするような「雑魚」どもであり、「ネトウヨ」や「炎上事件における多数派」などが、その典型であろう。
(07)『 リアスメイは今にも火が移りそうな距離で焚き火のそばに座り、ぽつりと「どうしてそんなに勝ちたがるのかな」とつぶやいた。「勝ったところで、結局何も変わらない」
「勝つことがすべてだからだよ」
アルンがそう答えた。「勝って名誉を得る。他人に認めてもらう。それがすべてだから。みんな、それぞれのゲームに勝つために生きているんだ。ときどきそんなことを考えるよ。子どもたちは賞金のないゲームに本気になるし、負ければ涙を流す。大人だって同様さ。出世して、権力を持って、なんの意味がある? 意味なんかじゃない。出世や権力そのものが、ゲームの勝者である証なんじゃないか。そんなことを考えたりもする」
「つまり、なんのために戦うのか、その理由なんて必要ないってことか」
「勝利そのものが目標かもしれない」とアルンはつぶやく。』
(文庫版下巻P158)
「勝利そのものが目標かもしれない」というは、「理想」を捨てて「生きる」ことを選んだ、作者・小川哲の、自己批判的な告白であり、同時に、「読者の同情」を買うための、アリバイ工作でもある。「私はこんなに苦しんでいますよ」というわけだ。
だがこれこそが、小川哲の「読者コントロール」の手口(同情喚起)なのだ。
(08)『「『掟を守るために最善を尽くすこと』。これがコーギだ。コーギ違反はもっとも重い罪にあたり、部落からの永久追放という罰を受ける」
「意味がわからないですね」
「話をわかりやすくするために、ソンクローニ族の生活を、あるゲームだと考えよう。トックランはゲームのルールで、ヤンハブはゲームの勝利条件だ。そしてコーギによって、部落の全員がそのゲームに参加することを義務づけられているわけだ。グリーンバーグがソンクローニ族の調査を行ったのは、彼らが近隣の部族の中でも一一というか、全世界の中でも一一きわめて倫理的な生活をしていて、犯罪発生率が非常に低く、個人の幸福度と生産性が高かったからだ。調査を終えたグリーンバーグは、ソンクローニ族の部落を『ゲームの王国』と呼んだ」
「ソンクローニ族は、人生を一種のゲームとして考えている。そしてそれは成功している、そういう話ですか?」
「そういうことだね」と教授はうなずいた。』(文庫版下巻P231〜232)
私は、この「コーギ」が嫌いなのだ。私にとって、「ゲーム」とは基本的に、自己選択的なものでなくてはならない。
例えば、「お前は日本人だ」と決めつけられるのは、嫌だし、お断りだ。だから、そう決めつけられた際には「いや、私は、たまたま日本に生まれただけの、人類の一人に過ぎない」と答えるし、その一方で私は、しばしば「日本人として恥ずかしい」とも言う。この場合、私は、自らの選択で「日本人としての責任」を引き受けて、「日本人というアイデンティティ・ゲーム」に参加しているのである。
(09)『 研究室の帰り道、チャンは、「普通」について考えた。そして、あらゆる美徳の中で、「普通」がもっとも過小評価されているのではないかと思った。個性、オンリーワン、創造性、破天荒、異端児、独創性、型破り、反逆児、前衛的、奇抜、エキセントリック。それらはたしかに重要な美徳かもしれないが、「普通」はそれよりもっと重要だ。
「普通」とは、ルールを守ることだ。そして人々はルールを守らなければ生きていけない。カンボジアにはルールを守らない人間が数多くいて、かくいう自分自身もルールを破ることがあるが、大事なのはほとんどの場合、ルールを遵守しているという事実だ。
「普通」でなくなるのは簡単だ。道端で「殺してやる!」と突然大声を出せばいい。映画のチケットを買う列に割りこめばいい。挨拶を無視して屁をこきながら睨み返せばいい。露店で買い物をしたあと、支払いの紙幣を相手に投げつければいい。裏返しにした服を着て、そのことを指摘されたら相手を引っ叩けば良い。』(文庫版下巻P234)
「普通」でなくなるのが、決して「簡単」ではないことくらいは重々承知の上で、作者はここで、「頭の悪い」人としてのチャンを描いている。一一この程度のこと、読者は当然、気づいてしかるべきである。
そもそも、大半の人は「普通凡庸」であるからこそ、「承認欲求」にかられて、「小説家」などの「有名人」に憧れ、自分もそうなりたがるのである。「光の当たる場所」「高いところ」に登りたがるのだ。
そしてその意味では、「普通」であるというのは、人間が「知性」による「自制心」を欠いた「豚」状態にある、ということでもある。
当然、豚も、本能的に群れたがり、そこでブーブーと自分の権利を主張するが、そうした愚かな集団に悪魔が入り、断崖絶壁に向かって、みずから突進することにもなる。その実例が「ポル・ポト政権下の悲劇」だとも言えるだろう。
(10)『カンの出した最新の結論はこうだった一一朝とはつまり始まりだ。だが、世界が始まっている中で、夜明かしをした自分はひとり終わりを歩いている。その瞬間、自分は世界との決定的な距離を知る。それは優越感ではないし絶望でもない。諦観に近い何か、あるいは「お前は絶対に世界に参加できない」という死刑宣告だ。そして、自分は死者として、あるいは絶対的な他者として、外部から世界が始まる瞬間を目撃する。』(文庫版下巻P243)
これは、作者・小川哲の「諦観」を表現したものと見て良いだろう。
要は「私は世界から疎外されていて、本質的に、世界に関わることができない」という「乖離感」の表明であり、「だからこそ、私の世間並みの生き方は、止むを得ない、方便でしかない」という、責任回避のアリバイ工作でもある。
(11)『ああ、この先の「人生」は下り坂なのかもしれない。そんな不安がよぎった。これからの「人生」は、一度つかんでおきながら結局は捨ててしまった九十一のことを思いながら、それでも五十四を受け入れて生きていくべきなのかもしれない。』(文庫版下巻P270)
そのとおりだが、私の場合は、引いたカードをみずから捨てた結果について、あとであれこれ悔やんだりはしない。捨てる前に、その結果を十分に検討し、その結果責任を引き受けて、カードを捨てるからだ。
例えば、夢を追ってマンガ家やアニメーターになろうとはしない、妻子を養う責任を負うのはしんどいので、結婚はしないし、子供も作らない。基本的に、自分一個の責任以上のものは負わない(し、それを後悔もしていない)。
それ以上の責任は、趣味的にしか負わないから、負いきれなくても、別に無責任ということにはならない。「寄付」などと同様で、できるかぎりのことをすれば、それで十分な「社会貢献」なのである。
したがって、私にすれば、作者の生き方を投影した、ここでの語り手の独白は、所詮「無考えな生き方における泣き言」でしかなく、それで同情を引こうとする、見苦しい所業だとしか思えない。「おまえの選んだ道ならば、泣き言など口にするな」と言いたいのである。
(12)『数字を見た瞬間、リアスメイは運命を受け入れた。
「負けました。でも、大事なことがわかりました」
「どんなこと?」
彼はそう聞いた。
「このゲームが人生に似ているという点です。真理を手にするためには、敗北を受け入れなければいけません」
「その通り」と教授はうなずいた。「君の人生にも、十九枚の紙が山になっている」
「そうですね。もちろん、あなたの人生にも」
「私の人生は、もうすべての数字をめくってしまったよ」
教授が笑った。「もし答えが知りたければ、十九枚すべての紙をめくるまで、抵抗し続けなければいけない。そして、いざ答えを知ってしまえば、すでにその答えが自分の手の届かないところにあるのだと知り、真理という光とともに、深い絶望の中に沈まなければならない」
「私のことです。捨ててしまった九十一について、今でも後悔しています。でも、すべての数字を見なければ、その後悔すら存在しませんでした」
「そういうことだ。もしそれが嫌ならば、答えかどうかわからない何かを手にしたまま、真理のない暗闇の中で、答えを得ることを諦めなければならない一一」』(文庫版下巻P271〜272)
私に言わせれば『真理という光』などというものは、もともと人間には到達不能なものなのだから、与えられた十九枚のカードを全部めくったところで、手には入られないというのは、初手からわかりきった話でしかない。
主観的に「(相対的に)良いカード」を引いたと思えば、残りに、より良いカードが残されている可能性があったとしても、それを承知の上で、そこで断念する(自制心を働かせる)のが、「知性」というものである。
どっちにしろ、残されたカードにも「真理」など隠されてはいないのだから、ことは「程度もの」でしかないからだ。
したがって「欲望のままにカードを最後までめくってしまったあげく、やっぱり真理の光は手に入れられなかった。ならばあの時に、カードをめくるのを止めておけばよかった」などと後悔する者は、端的にいって「自制心という知性に欠けた人間=欲望のままに生きる愚かな豚」でしかない。
「人間って、理想や真理を求めて、どうしても最後までカードをめくりがちですよね」などという、頭の悪い読者の共感を求める目配せなど、反吐の出るものでしかない。
(13)『 ソリアは「虐殺に関わったのは事実か?」と聞かれた場合のことを考えた。イエス。事実だ。「関わった」という言葉の定義によるが、ロベーブレソン制圧作戦には参加した。夫は拒否しようとしていたが、自分が拒否してはいけないと強く言った。あの時点で、すでに自分たちは多くの仲間を見殺しにして、自分たちの地位を築いていた。もはや引き返すことはできないと思った。今でもそうだ。自分を守って暴漢に刺された秘書のことを思った。カンボジアを変えるためには、もう引き返せない。信じてくれた仲間たちのためにも、革命を実現しなければならない。』(文庫版下巻P284)
博打で負けたカネを、博打で取り戻そうとして、さらにカネを注ぎ込む愚か者、そのままである。
そしてこの場合、注ぎ込まれる「カネ」とは、他人の命である。
こんなバカが、なにがしか「同情されるべき理想主義者」として描かれるこの小説は、その意味では、子供騙しのお涙ちょうだい小説でしかない。
(14)『「嘘つき」という呼び方は、嘘の上手い人に対する呼び方ではなく、嘘の下手な人に対する呼び方だった。人間は毎日のように嘘をついている。ありがたくないのに感謝し、嬉しくないのに喜び、おいしくないのにおいしいと言い、好きでもないのに好きだと言う。自分だって、食事に誘われて断るとき、「用事がある」と嘘をつく。正直に「あなたに興味がない」と言えば、相手を傷つけてしまう。
嘘とは曖昧なものだし、一概に悪いことだとも言えない。嘘はナイフだ。誰かを傷つけることもできるし、食材を切りわけることもできるし、自分の身を守ることもできる。誰もがナイフを持っている。使い方が違うだけだ。』
(文庫版下巻P286)
全くそのとおりであるが、ただ、私にとっての本書著者・小川哲は、こうした意味での「嘘つき」でしかない。
著者によって、コロリと騙されてしまう多くの読者にとっては、小川哲は「嘘つき」ではないが、私はそうではないからこそ、小川を「嘘つき」と呼べるのだ。
そしてまた、このように「不味いものは不味い」と言ってしまう私自身も、正直者という「嘘つき」である。
馬鹿正直を「演じる」ことによって、無理をしなくて済むのである。その意味で、私は「嘘つき」なのだ。
(15)『 ボスはこう言いました。「バレずに浮気をする秘訣は、『疑われないこと』と『調べさせないこと』だ」と。つまり、「昨日の夜に何をしていたのか?」という質問をさせなければいい。その質問をされた時点で、嘘をつかなければいけなくなるが、どんな嘘も、相手が本気で疑えばいずれバレる。携帯を調べるなり探偵を雇うなりすれば、どんな嘘上手だって嘘が発覚してしまう。大事なのは疑われないこと、調べさせないことだ。「昨日の夜に何をしていたのか?」と聞かれたら、「そうやって何から何まで調べようとする人間は嫌いだ」って不機嫌になればいい。相手が折れるまで不機嫌な態度をとって、むしろ向こうに謝罪させれるんだ。謝罪させたら「君のことを愛しているし信用している。だから僕のことも信用してくれ」とか適当に言っておけばいい。それが相手を支配するということだ、と言われたんです。』(文庫版下巻P343)
これは、まずまずな「世渡り術」だが、私には通用しない。
このやり方が通用するのは、疑いを持って追求している方の人自身が、疑わしい当の相手に嫌われたくないとか、周囲に嫌われたくない、などと思っている場合に限られる。
つまり、疑われた者が「そうやって何から何まで調べようとする人間は嫌いだ」と不機嫌になった「演技」をするのなら、疑う方は「そういう誤魔化し方をする人間だと、余計に追求したくなるね」と、憎たらしい余裕の笑いを浮かべる「演技」をすればいい。これで、相手の「コントロール」から逃れることができる。
要は、自身の「嫌われたくない」「評価されたい」という欲望を、自己コントロールできない人間だけが、その欲望につけ込まれて、他人に「コントロール」されてしまうのだ。
そして、「嫌われたくない」「評価されたい」という欲望を自己コントロールできる人間とは、すなわち「光の当たる場所」や「高いところ」に出たいという欲望を自己コントロールでき、塹壕の陰に隠れ続けることのできる人間なのである。
(16)『でもやっぱり、インタビューを受けるのって、人々の夢だと思うんですよ。飲み屋とか行けばわかると思いますけど、みんな自分の話をしたがってます。自分の話を聞いてほしいんですよ。実際は誰も聞いてないんですけど(笑)。人間の会話なんて、八割が噛みあってません。お互いが自分のしたい話をするだけです。でも、インタビューされれば、百パーセント自分の話ができますし、相手もそれをありがたく聞いてくれます。それってすごくないですか? 現実ではありえませんよ。ああ、僕も自分の話がしたいのかな。でも普段全然できなくて、だからこうやって妄想でインタビューを受けているのかな。』(文庫版下巻P346)
これは、作者・小川哲の正直な気持ちでもあろう。
事実、小川哲は(01)で語ったように、嫉妬の標的になりやすい「光の当たる場所」や「高いところ」に出てしまうリスクを承知していながら、インタビューを受けるような作家になってしまったのだから、要は、自分には「自制心という知性が足りなかった」という事実を、ここで認めているのである。自分も所詮は、自己コントロールのできない「普通の人=俗物」だと。

まただからこそ、小川哲は、両親のように「理想に生きる」ことなどできない。
世間から「所詮は、人間の現実が見られない、頭の悪い観念論者(=共産主義者)でしかない」と蔑まれながら、それでも「理想を目指す」ことなど、自分にはできない。自分は所詮「薄汚れた俗物」でしかないのだと、小川哲自身もそう気づいているからこそ、本作のような小説を書いて「観念的自己回復」を謀らなければならないのである。
(17)『「眠いから終わらせただけでしょ?」
ソリアはそう反論した。すると父は、「そういうわけじゃない」と反論した。「世の中の出来事をそのまま物語にしたら、本当はみんな、そんな感じなんだ。途中まで面白そうで、何か意味がありそうに見えるけど、最後はだいたい無意味に終わる」
父は「それじゃあ、おやすみ」と眠ってしまった。父の話す物語は、いつもそんな感じだった。父が眠くなると物語が終了する。唐突に川が氾濫して全員死んだり、全員が目的を忘れてどこかで幸せになったり、目が覚めてそれが夢だったとわかったり。そして父自身の人生も、そういう風に、唐突に終わってしまった。』(文庫版下巻P375)
実際、人生とは、そんな「尻切れトンボな寝物語」のようなものだ。
「貧乏な娘は、王子様に愛されて、幸せに暮らしましたとさ」では済まない。娘も王子様も歳をとって、多かれ少なかれ、変わっていくからであり、二人が結ばれた瞬間こそが「幸福の頂点」であるならば、あとは「下り坂」でしかないからである。
例えば、どんな売れっ子作家でも、生涯「売れっ子」であり続ける人などいないからこそ、売れっ子作家でも、売れ続けるための、涙ぐましい努力をしないではいられない。
それでも、ひと昔前なら、人気作家になれば、いちおう食っていくことだけはできたけれども、今時の小説家など、所詮は「いくらでも交換の利く消費財」でしかないから、仮に直木賞を受賞して、売れっ子作家になったところで、それが一生続くわけでもでもなければ、死後にまで、その名声が続くわけでもない。
ほんの5年ほど前にベストセラー作家だった小説家たちを、何人か思い出してみるがいい。彼らの中で、今もベストセラーを出し続けている者が、いったい何人いるだろうか。
(18)『 彼女は人生を、そしてこの世界を一種のゲームだと考えていたのかもしれない。だから、ソンクローニ族の「ゲームの王国」を政治に持ちこもうとした。その認識の違いが、自分と彼女を隔てる大きな壁になっていたのだろう。自分にとって、ゲームのもっとも崇高なところは、勝利以外に何も求めない点にある。それゆえに、人生や世界をゲームだと考えるのはゲームの価値を落とす行為だと思っていた。「権力を得る」という報酬のためにゲームを勝とうとするのならば、それはゲームではない。ゲームを侮辱する何かだ。』(文庫版下巻P382)
これが、ソニアとムイタックの違いであるが、前述のとおり、私に言わせれば、両者は「両極端の理想主義者」という点では、同質である。
つまり、「理想主義的現実主義」も「純粋抽象主義」も、「生活的現実=人間の動物性」への配慮を欠いているという点では、非現実的な「観念」であり、「頭でっかち」の思想でしかないのである。
(19)『 自分はずっと、他人に話が通じないことに絶望していた。人々はいつだって話を聞こうとしないし、他人の価値観を理解しようとしない。彼女も同じように絶望していたのかもしれない。そして、その絶望を糧に、彼女は国家を変えようと努力したのかもしれない。話が通じない人に嘘をついて、自分にも嘘をついて、ようやく権力を得て、自分の理想を実現する一一本当にそんなこと可能だろうか。そんなことは不可能だと思っていたので、自分は逃げ出すことにした。自分の殻にこもった。話の通じる人を相手にすればいいのだ。自分の空間で、好きなことを好きなだけすればいい。世界のことなど気にかけず、自分の世界を作ることに集中すればいい。』(文庫版下巻P383)
後者のムイタックの立場が、作者である小川哲が、当初選んだ生き方である。
しかし、そうした「純粋抽象の世界」への退却が、うまくいかないものだというのを、ムイタックが悟らざるを得なかったように、小川哲も、「フィクション=小説」の世界への退却もまた、この「現実世界」の中のことでしかない、という現実を、否応なく悟らざるを得なかったのである。
だからこそ、小川は「嘘」をつくことを否定しないし、それで他人をコントロールし、利用することも否定しない。なぜなら、それがこの世界の一部であるというのは、否定できない事実だからだ。
(20)『「あとがき」に魅力があるとすれば、「嘘」ばかりで構成された物語の最後に、少しだけ「本当」が顔を出すことだと思っています。本書を未読でもご安心を。このあとがきでは、本書の結末どころか、内容にすら触れません。』
(文庫版下巻P418、著者「あとがき」より)
これも「嘘」である。
ここまで縷々紹介してきたように、本作『ゲームの王国』は、かなりの部分、作者・小川哲の「人生(観)」を率直に反映した作品であり、その意味では、これは「作り事(嘘)」の少ない「正直な小説」なのだ。
そして、それが読み取れないとしたら、それは、作品のせいではなく、読者の無能のせいでしかない。
だが、作者である小川哲としては、本作に、自分の「実人生」など読み取られたくない。
むしろそれは、作者自身が作品に込めたものとして、そこで完結すれば十分であり、阿呆な読者は、本作を「面白いフィクション」としてだけ消費してくれた方が、「本当のこと」を書き過ぎてしまった作者としては、むしろありがたいのだ。
だから、小川はここで、本作の「フィクション性」を強調する「嘘」を、「あとがきでの本音表出」と見せかけることで、読者をコントロールしようとしているのである。
つまりここでは、「嘘と誠(本当)」が、故意かつテクニカルに、転倒させられているのだ。
(21)『 でもその状況は、僕にとってとても不自然です。『ゲームの王国』を書くまでの僕の三十年の人生が「文章とはそういうものではない」と言っているのです。文章とは、お金のためでも、仕事を依頼してきた編集者のためでも、もっと言えば新作を期待してくれている読者のためでもなく、自分が書きたいから書くものなのだ、と。誰かの迷惑とか、誰かを悲しませてしまうとか、そんなことを気にして書いた文章が、他人の人生を変えることなんてできるはずがない。お前が勝手に、好きで書くから価値があるんだろう、と。
『ゲームの王国』を出版したあと、取材で一番聞かれた質問は「どうしてカンボジアを舞台にした小説を書こうと思ったのですか?」というものでした。聞かれるたび、僕は用意していた答えを述べました。どういう答えかは、本書を読めば大方想像がつくと思うし、おそらくそれで合っています。でも、本当のこと言うならば、僕の答えはもっとシンプルです。書きたかったから書いた。この小説を書くことが、自分の救済になると思ったから書いた。自分を救済することが、他の誰かを救済することに繋がると信じて書いた。そして僕は、その答えが正しいと思っています。あらゆる本が、そのようにして書かれるべきだとさえ思っています。』
(文庫版下巻P421〜422、著者「あとがき」より)
ここは、かなりの部分「本音」ではあろうけれど、なぜこんなことを書いたのかと言えば、それはこの言葉が、小川哲が「今後(当面)は、プロの作家として、嘘ばかりを書いていきますよ。この『ゲームの王国』は、ある意味では、これまでの正直な自分との決別の書なのです」という宣言なのだ(もっとも、小川が「純文学」的作品でも食っていけるほどの地位を確保できれば、話は別だ。小川の最終的な希望もそのあたりにあると、私は睨んでいる)。
(22)『 小川哲の課題設定とルール内での動かしかたの巧さは、短編小説で特に顕著だ。デビュー作『ユートロニカのこちら側』も連作短編形式である。そのパズルのような魅力一一厳密な制御や堅牢なロジック一一をあえて活用しない博打に出たのは、作者のファンであれば一層の驚きだったのだろう。』
(文庫版下巻P426〜427、橋本輝幸「解説」より)
ここで解説者の橋本輝幸が指摘しているのは、本作が『厳密な制御や堅牢なロジック』によって鎧うことをしなかったために書きえた、作者・小川哲の「素の顔」を窺い得る「自由な作品」だ、ということである。
もちろん、「窺い得る作品」であるということと、「どんな読者にでも読み取れる」ということは、同じではない。

(2022年5月21日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
