
カート・ヴォネガット・ジュニア 『猫のゆりかご』 : 猫の不在
書評:カート・ヴォネガット・ジュニア『猫のゆりかご』(ハヤカワ文庫)
最初に言っておくと、本作に猫は登場しない。ハインラインの名作『夏への扉』のように、猫好きの期待に応じてくれる作品ではないのだ。
こう書くのも、Amazonのカスタマーレビューで「猫が出てこない」と不満を漏らしていた人がいて、私も読むまでは、猫が出てくる話だと、なんとなくそう思っていたからだ。だが、幸いなことに、私は特に猫好きということではないから、猫を期待して本作を読んだわけではないので、その点で失望したり怒ったりすることはなかった。
では、本作はどういう小説で、そこに猫はどう関係してくるのだろうか?
その答として、あえて猫を絡めて言うなら、本作は「猫の不在」の物語である。「猫はいません」という物語なのだ。
「猫に期待してくださったかもしれませんが、本作には猫は登場しません。期待はずれだった方もいらっしゃるでしょうが、本作中には猫は存在しないので、どうしても猫の登場が読みたいという方は、他の作品を当たってください。例えば、ハインラインの『夏への扉』なんか良いのではないでしょうか。私は読んでいませんが、かなり評判がいいみたいですから、多分おすすめです。きっと、猫好きのあなたは、慰められるのではないでしょうか?」と、そんな作品である。

ちなみに私自身は、大昔に『夏への扉』を読んでいるが、あまり印象には残っていないし、猫の印象もほとんどない。
それでも『夏への扉』に猫が出てくるというのは、ときどき見かける文庫の表紙絵や、あらすじ紹介なんかに猫の登場が語られているため、そんな話だったかなと思っているだけなんじゃないかな。それが無かったら、猫が登場したかどうか、確たる自信は持てなかったはずだ。
で、実際に読んでみると、猫が登場していないので驚いて「おかしいぞ。俺は夢を見ているのだろうか? たしか『夏への扉』には、猫が登場したはずだ」一一なんてことになったら、それはハインラインではなく、ディックになってしまうところだが、たぶん間違いなく『夏への扉』には猫が登場する。ハインラインは、きっと猫が好きだったのだろう。
ともあれ、ヴォネガットが猫好きだったかどうか、あるいは『夏への扉』を読んでいたかどうかは、私は知らない。
ただ、本作における「猫の不在」ということを説明するために、上のような書き方をしてみただけで、ヴォネガットその人を代弁したというわけではないのである。
で、本作における「猫」とは何か?
じつは「シュレーディンガーの猫」のことであるというのは、思いつきの嘘である。
「シュレーディンガーの猫」というのは、箱の中に「生きている状態の猫」と「死んでいる状態の猫」の、どっちか一方が存在しているのではなく、両者が同時に重なっているような「存在」としての猫の話だから、「猫の不在」とは、まったく関係がない。
それこそ「これは、シュレーディンガーの猫の箱ですが、これから猫がどうなっているか、箱を開けて確かめましょう」と言い、箱を開けるそぶりをすれば、「シュレーディンガーの猫」の思考実験を知っている人は、きっと悲鳴をあげるだろう。なぜなら、猫が死んでいるという悲しい可能性も否定できないからである。だから、できれば箱の中など確認せずに、可愛い猫ちゃんが生きているという方を信じて生きていこうと、そう考えるだろうからである。

しかしながら、本作『猫のゆりかご』は、「猫の不在」を描いた作品なのだから、箱を開けても、そこに猫はいないので、猫ちゃんの死骸を見て悲しむことにはならないから、そこは安心して欲しい。
本作においては「猫の死」が語られることはない。なぜなら、そもそも「猫」は不在なんだし、さらにいうと「猫のゆりかご」も登場しない。なぜならこれも、和田誠によるハヤカワ文庫の表紙画で描かれているとおりで、「猫のゆりかご」とは、日本語で言えば「あやとり」のことだからである。
若い方は「あやとり」と言われても、もはや知らない方もいらっしゃるだろうが、要は、輪状の紐を両手の指にかけて、それでいろんな形を作るという「遊び」のことだ。
「ハタキ」だの「橋」だの「東京タワー」だのといったものが日本では有名なはずだが、要は、そういう子供の遊びのことである。
『あやとり(綾取り)は、1本の紐の両端を結んで輪にし、主に両手の指に紐を引っ掛けたり外したりしながら、特定の物の形に見えるようにする伝統的な遊び。地域によっていととり、ちどりなど多くの異称がある。
日本には一人で行うあやとりと二人で行うあやとりがあるが、世界には多人数で行うもの、紐を咥(くわ)えたり手首や足も使う技などさまざまなバリエーションがある。
あやとりは日本のみではなく全世界に存在し、子供の遊びとしてではなく呪術師が占いとして行う地域もある。あやとりの時代的考証について明確にはなっていない。現在ではあやとりは単一の起源を持つ遊びではなく、各地で自然発生したものと考えられている。また世界各地で見られた、文字の発達以前に縄を結んで意思の伝達や記録を行った習慣が関連していた形跡もある。』
(Wikipedia「あやとり」)
つまり「あやとり」で作ったかたちが、たまたま「猫のゆりかご」のように見えたから、そのように通称するようになった地域もあったということである。
したがって、ハヤカワ文庫の表紙イラストのように、そこには両手とそこに複雑に渡された紐によって、なにやらシンプルなハンモック状のかたちが存在する。そんなことから「猫のゆりかご」と呼ぶようになったのだろうが、当然のことながら、そこには「猫」もいなければ、「猫のゆりかご」もない。
ただ、それをやって遊んでいる人には、それが「猫のゆりかご」のように見えているとか、そういう「お約束」だということである。

そして、本書において、この「猫のゆりかご」が、何を象徴しているのかというと、それはもちろん、「神」である。
ある、あやとりの形を「猫のゆりかご」と呼ぶし、そう思ってみれば、そんな風に見えないこともないのだれど、しかし、現実には、そこには「猫」もいないし、「猫のゆりかご」も存在しない。
要するに、「神」の存在とは「猫のゆりかご」と同じようなものなんだよ、というのが本作のタイトルの意味である。「猫の不在」とは、「神の不在」の言い換えなのである。
あやとり遊びをしている人たちは、複雑な「紐操作」をやっているうちに、それがあたかも、「ハタキ」だとか「橋」だとか「東京タワー」だとか「猫のゆりかご」だとかに、見えてくる。
でも、それは所詮、複雑な形を与えられた紐でしかなく、そこには「ハタキ」も「橋」も「東京タワー」も「猫のゆりかご」もなく、当然のことながら「猫」もいない。「猫の不在」とはそういうことであり、本作で語られているのは、そうした「神の不在」なのだ。
○ ○ ○
本作のあらすじは、次のようなものである。
『語り手のジョーナは原子爆弾が日本に投下された日についての本を執筆するため、原爆の開発者である故人フィーリクス・ハニカー博士の息子である小人のニュートに手紙を書く。その後、ハニカー博士の過ごしたニューヨーク州イリアムに取材に赴き、かつての上司ブリード博士から、ハニカー博士はあらゆる液体を固体化するアイス・ナインという物質のアイデアを語っていたと聞く。しかしブリード博士はそんなものは実在しないと語る。
その後、ジョーナはハニカー博士のもう一人の息子、フランクがサン・ロレンゾ共和国という南国の独裁国家の写真記事に写っているのを見つけ、サン・ロレンゾに取材に行く。飛行機の中で、ミントンという新任アメリカ大使の夫婦と、クロズビーという実業家の夫婦、そしてニュートとその姉アンジェラと出会う。サン・ロレンゾはライオネル・ボイド・ジョンスン(ボコノン)とマッケーブ伍長という入植者によって開拓され、ボコノンがはじめたボコノン教が普及している。現在のサン・ロレンゾの独裁者はマッケーブ伍長の元召使であるパパ・モンザーノであり、パパの養女である美女モナにジョーナは一目惚れする。しかしモナは次期国王であるフランクと結婚する予定だった。
サン・ロレンゾに着くと、パパ・モンザーノが病のため倒れる。ジョーナは、慈善病院を経営しているジュリアン・キャッスルと、その息子でホテルの経営者であるフィリップ・キャッスルと出会う。やがてジョーナはフランクに呼び出され、自分の代わりにサン・ロレンゾの大統領になってくれと依頼される。ジョーナは承諾し、モナを許嫁とする。
ジョーナの大統領就任式の直前、病床のパパ・モンザーノはアイス・ナインを飲んで自殺する。アイス・ナインは実在し、ハニカー博士が死んだ際に、3人の子供たちが分け合って手元に持っていたのだった。ジョーナたちは死体を始末し、就任式の前のセレモニーに向かう。しかしセレモニーに使用する飛行機がパパの死体がある城に衝突し、海に落下する。その瞬間、全世界の海がアイス・ナインに汚染され凍りついてしまう。
ジョーナとモナはシェルターに逃げ込む。数日後、地上に出るとそこは生命が死に絶えた世界となっていた。住民たちは皆死んでおり、モナも自殺する。生き残ったのはジョーナの他、クロズビー夫妻とフランクとニュートだけだった。彼らだけの自給自足の生活が6ヶ月続いた後、ニュートと共に車を運転していたジョーナはボコノンを発見する。ボコノンは『ボコノンの書』の最後の章を書いたと語る。』
(Wikipedia「猫のゆりかご」)
こう説明されても、なんだかよくわからない話だと感じられるだろう。事実そういう、すっとぼけた話なのだ。
なにしろ、カート・ヴォネガットの作品なのだから、全体の雰囲気としては「脱力系のユーモアSF」みたいな感じなのだが、しかし、結末は「世界の終り(終末)」である。
そんなわけで、すごいんだかすごくないんだか、よくわからないような小説なのだが、本書の魅力は「凄そうなことを、軽い語り口で語っている」ところだと言えるだろう。だから、本作を「すごいすごい」と誉めたくなる気持ちはわからないでもない。だが、そういうのは、ヴォネガットの最も軽蔑する態度だということに気づいていない人の、頭の悪い態度だとも言えるだろう。
なぜなら、小説が、すごいことを書いているからといって「だからなんだと言うのだ」というのが、ヴォネガットの考え方だからである。
もちろん、そう剥きつけに言ったりはしないけれども、この世には「神様」がいないからといって、そのかわりに小説家を「神様」扱いにしたり、小説を「聖書」扱いにするような輩を見たら、ヴォネガットがどう感じるかは、ヴォネガット読者には明らかなことだろう。
彼だって、そんなふうに誉められれば、きっと、ニッコリと笑い、口では「ありがとう」なんていうかもしれないが、心の底では、うんざりした様子で、読書家なんて「そういうものだ」と呟くのではないだろうか。
本作は、上の「あらすじ」にもあるとおり、かの「原爆」の開発に関わった天才科学者についての本を書こうとしている主人公のジョーナの物語として、幕を開ける。
ところで、私は、長らく読みたいと思っていたカート・ヴォネガット・ジュニアの作品を、退職して時間に余裕ができたのを機に、昨年から読み始めた。
3ヶ月ほど前に、ヴォネガット作品として初めて読んだのが『スローターハウス5』で、その次の読んだのが『タイタンの妖女』。今回の『猫のゆりかご』は3冊目ということになるのだが、偶然なことに、今年は、クリストファー・ノーラン監督の新作映画『オッペンハイマー』が公開される。「原爆の父」と呼ばれた、あのオッペンハイマー博士の伝記的映画だ。

だから、「おお、なんたる暗合!」だと、そう思わないでもないのだが、これはもちろん単なる「偶然」でしかなく、そこに何やら「深い意味」を見たり、「神秘的なもの」を感じたりするのは、錯誤に過ぎない。そんなものに「神の啓示」などを見てはいけないのだ。
だが、人間というものは、そういう錯誤によって、「不在の神」を見た気になるものである。事実、そんな人が大勢いるから、この人間社会には、キリスト教をはじめとした、各種の「宗教」が存在しているのだ。
だが、それらはすべて「猫のゆりかご」でしかない。ニャーンと鳴くこともない。その声が聞こえたら、それは幻聴である。チェシャ猫は存在しないのだ。
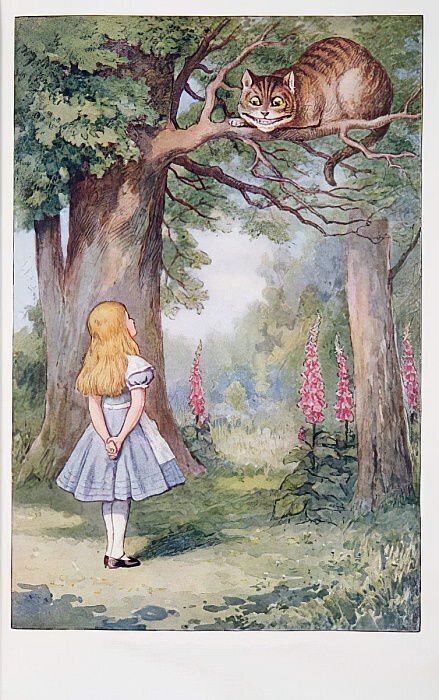
で、本作は、天才科学者だけれど、人間としての常識は完全に欠けた、ただ研究のことしか頭になかった天才博士が、「原爆投下の日」に何を考え、何をしていたのか、そのことを本にしようと考えた主人公が、博士の遺族を訪ね歩いているうちに、カリブ海の島国である独裁国家へ渡ることになり、そこでなんやかやあって大統領になり、なって早々、博士が残した「発明」によって、世界が滅んでしまうという話である。
ただ、この作品で語られているのは「神の不在」ということなのだから、本作に登場するインチキ宗教「ボコノン教」については、ちょっと書いておいた方が良いだろう。
この「ボコノン教」がインチキ宗教だというのは、その宗教の教祖であるボコノンを名乗った人物(ライオネル・ボイド・ジョンスン)自身が、それをインチキだとわかってやっていたからである。
彼は、実のところ、作者と同様の「無神論者」なのだ。私とも同じである。
「あらすじ」にもあるとおり、若い頃の彼は、意気投合した相棒(マッケーブ伍長)と、この貧しい島国(サン・ロレンゾ)に渡って、なんとか人々が幸せに暮らせる国を作ろうという、崇高な志を立てて努力をする。ところが、この島の土地は著しく痩せており、それに比して人口だけは多くて、それやこれやで思うようにはいかない。
で、ひとまず、人々の当面の「希望」であり「心の拠り所」として、ボコノン教を捏ち上げて与えたのだ。それまで存在していた、いくらかのキリスト教の教会は、搾取するばかりだったので、それを追っ払った後に、その代わりとしてボコノン教を国民に与えた。
そして、そのボコノン教にリアリティを持たせるために、二人のうち一方、マッケーブ伍長は「独裁者」となって、ボコノンとその信者を迫害することになった。「宗教」が広まるためには、迫害がないといけないと考えたからだ。
つまり、ヤラセ宗教と、それに対するヤラセ迫害だったのだが、そんなものでも「ないよりはマシ」というのが、この島国の現実だったのである。
で、当然のことながら、これは私たちの「この世界」の比喩である。
私たちは、必ずや自滅してしまうというのが見えていながら、それを見ないようにするために、「宗教」を信じたり、「科学技術」に期待したり、「理想」を掲げたりするけれども、本当のところ、頭の良い人の多くは、それが「気休め」でしかないことを知っているのである。知っていて、それを「信じているふりをしている」のだ。
そんなものを本気で信じているわけではないと認めてしまうと、みんなが絶望してしまい、より酷いことになるから、仕方なしに「偽物の夢」を、つまり「ボコノン教」みたいな「偽の神」を、人々に与えて、自分も信じているふりをしている、というわけだ。一一当然のことながら「小説」をはじめとした「娯楽」も、すべてそうしたものなのである。
だから、本作を読んで、人間がどうあるべきかを考え直すべきだ、みたいな考えは、完全な「勘違い」か、それもまた「ごまかし」にすぎない。本作にそんな「意味」はない。それは「猫のゆりかご」でしかない。
本作にあるのは、ヴォネガットらしい、シニカルな「諦めの境地に発する苦笑」だと言えるだろう。そうした作品なのだ。
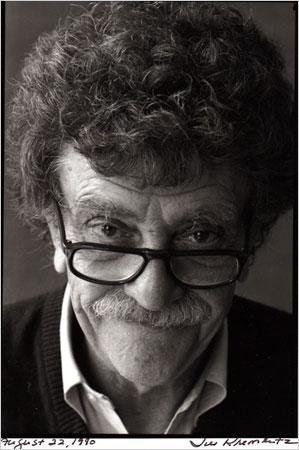
ただ、私のとっての本作が、『スローターハウス5』や『タイタンの妖女』ほど、ピンと来なかった、あるいは、面白くなかったのは、本作には「神様はいない」「科学者なんて、研究バカであり、科学によって人間が滅ぶことはあっても、救われることはない」「宗教なんて、所詮は気慰みの誤魔化しでしかない」「人間とは、そうして誤魔化し誤魔化し生きているだけの、無意味な生き物である」といった、ある意味「当たり前の話」でしかないヴォネガットの見解が、物語に託されて語られているだけで、彼自身が、そうした境地に至った「悲しみ」や「深い絶望」のようなものは、あまり語られてはいなかったからだろう。
本作で、ヴォネガットはメジャー作家になったというけれど、本作がウケたのは、たぶん「科学批判」や「宗教批判」として、わかりやすかったからではないかと思う。
当時の若者たちが、そうした「既成の権威」批判に「僕もそう思う」と共感したからではないだろうか。
しかし、そういう共感によって、その気になれるというのは、やはり、この作品に満ちている「シニカルな諦観」が読み取れていなかった証拠だと思う。本作を、平気で「傑作だ」とか言って盛り上がれる奴こそ「傑作」なのである。
事実、そういう人は、誕生日だの新年だの結婚式だの葬式だのを、疑いもなく受け入れているはずだ。
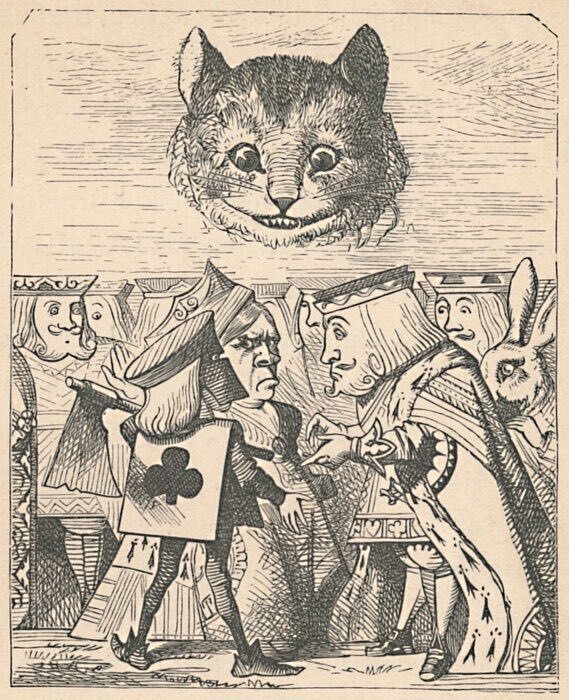
(2024年2月17日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○(国内SF映画)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
