
飛浩隆 『グラン・ヴァカンス 廃園の天使 Ⅰ 』 : 真夏の海辺の〈残酷な恋〉
書評:飛浩隆『グラン・ヴァカンス 廃園の天使Ⅰ』(ハヤカワ文庫JA)
2002年の作品。1992年から2001年にかけて執筆された、約10年がかりの労作である。
飛浩隆は、それまでにもいくつかの短編を発表して高い評価を受けていたが、専業作家ではなかったこともあり、執筆ペースは必ずしも早くなく、この作品に取り掛かっていた間は作品が発表されなかったため、本作は10年ぶりの新作、しかも初長編ということで、SFファンから絶大な支持を受けて、その年の『このSFが読みたい!』の、国内作品第2位にも輝いている。
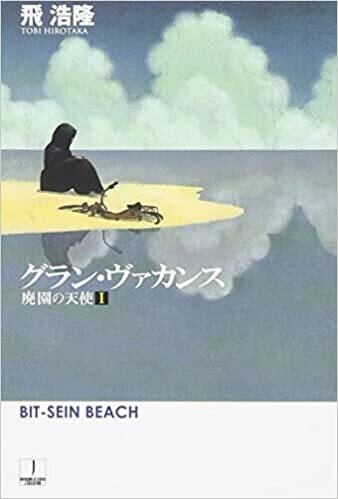
本作は、仮想空間に生きるAIたちの物語である。
本作では、人間は一人も出てこないが、物語の舞台は、人間がレジャーのために作った仮想空間であり、その中で、AIたちが人間の姿を与えられ、「人間的」な生活を営んでいる。ここは、人間が金を払って遊びに行き、映画の中のような世界を楽しむという、「バーチャル・レジャーランド」というわけだ。
今となっては、こうした「設定」自体は、目新しいものではなく、設定の物珍しさを楽しめる作品にはなっていない。
しかし、この設定が考案されたのが、約30年も前であることを考えれば、その先取性は否定できない。
その頃、日本ではまだ「インターネット」さえ普及しておらず、ましてや「人工知能」など、それこそ「SF映画」の中の話だし、「バーチャル・リアリティ」だの「アバター」などといった言葉は、ほとんど誰も知らなかった時代なのである。

ともあれ、本作はそのように先進的で先取的な作品ではあったのだが、こうした「SF設定」部分は、さすがに古びて陳腐化してしまったと言えるだろう。だが、だからこそ、特別、最先端科学技術の世界に詳しいわけではない読者でも、この「世界」を素直に理解して、楽しめるようになったとも言えるのだ。
例えば、(私は視ていないのだが)大ヒットアニメ『ソードアート・オンライン』の世界に馴染んだ世代なら、この小説を読んでも「えっ、ここはどこ? この人たちは何?」ということにはならないのである。
『 南欧の田舎にある港町をイメージしてデザインされた、会員制の仮想リゾート〈数値海岸(コスタ・デル・ヌメロ)〉の〈夏の区界〉には、コンピュータ・プログラムを人間の姿かたちに実体化させたAIと呼ばれる住人が暮らしを営んでいる。この〈夏の区界〉は、ゲストに性的な快楽を与えるために設計された空間であり、その刺激を昂進させるためのお膳立てとして、「素朴で不便な町で過ごす夏の休暇」というテーマが設定されている。
〈夏の区界〉で暮らすAIはゲストに対して精神的に完全に依存するようにプログラムされており、ゲストはAIにどのようなひどい陵辱をくわえることも許されている。だが千年前の「大途絶(グランド・ダウン)」以来、区界を訪れるゲストは完全に絶えている。理由は不明。しかしリゾートは閉鎖されることなく運営され続け、AIたちはただ一人のゲストも迎えることなく、この区界で千回以上も永遠の夏をくりかえしている。
そんな〈永遠の夏休み〉がついに終わり、「大途絶」以来絶えていた外部からの訪問者が千年ぶりにあらわれる。『グランバカンス 廃園の天使Ⅰ』は、〈夏の区界〉を丸ごとの崩壊にみちびくことになる、この運命的な一日のできごとを描いた長編小説である。
主人公は、チェスの天才である十二歳の少年ジュール・タビーと、誰とでも寝る性的な自制のこわれた少女ジュリー・プランタン。年長のジュリーはジュールを「従弟(いとこ)さん」と呼ぶ。ジュリーはちいさな〈硝視体(グラス・アイ)〉のピアスを舌先につけている。硝視体(視体、とも呼ばれる)はゲストの来訪が絶えた後に区界でみつかるようになった物質で、ここに存在する物体や現象に、超自然的な力で働きたいかけることができる。ジュリーはこの視体の優秀な使い手なのだ。』
(仲俣暁生・文庫「解説」P455〜456)
見てのとおり、出だしは「美しい南欧の田舎町での、少年少女の恋物語を描いた作品」のようにして始まるが、その背後には、人間のドロドロとした欲望を反映した「残酷な設定」が隠されており、物語は、徐々に暗転していく。

ゲスト(人間)が訪れなくなってのち、千回もの夏をくりかえしていたこの〈夏の区界〉に、ある日突然、グロテスクなロボット(その形態から〈蜘蛛〉と呼ばれる)が来襲して、〈夏の区界〉の空間とそこに住むAIたちを、食いつくすようにして消していく。後に残るのは、データの消去された真っ黒な虚空間だ。
最初の襲撃で生き残った者は、町の唯一のホテルである「鉱泉ホテル」に避難し、そこでジュリーをはじめとした「硝視体使い」たちが力を合わせ、硝視体による「罠の結界」を張って、〈蜘蛛〉たちを迎え撃つ。
これでうまくいけば、単なる超能力ファンタジーの変型でしかないが、当然ことながら、この防戦は失敗して、ジュールとジュリーの仲間たちは、次々と悲惨な最期を遂げていく。
そして、その敗北の背後には、この〈夏の区界〉の「設定」にまつわる、「因縁」とでも呼ぶべきものがあった。
このように、この作品は、表面上は「報われぬ恋と超能力戦争」的な、いわばありがちな物語なのだが、その背景には、この〈夏の区界〉の「設定」の謎が、そして〈数値海岸〉における「大途絶」の謎が存在する。
「なぜ大途絶は起こったのか?」「大途絶の後、外の現実世界はどうなったのか」「なぜ今頃になって〈夏の区界〉は襲撃されたのか?」「〈蜘蛛〉を操る、ランゴー二の狙いとは何なのか?」一一こうした「世界設定」に関わる「謎」の真相は、本作では描かれず、物語の最後は、ジュールがその「謎」を解くために、〈夏の区界〉から旅立つ(帰還する)ところで終わるのだ。
本作は、サブ(メイン)タイトルにあるとおり、「廃園の天使」三部作の1冊目なのである。
○ ○ ○
見てのとおり、本作『グラン・ヴァカンス』に話を限定すれば、そのSF設定に目新しいところはないのだが、その奥に隠された、さらに大きな「廃園の天使」の世界設定は、未だ謎に包まれたままで、その真相の解明は、三部作の完結を待たなければならないだろう。
「廃園の天使」は、現在『グラン・ヴァカンス』、中短編集『ラギッド・ガール』まで刊行されており、完結編となる予定の『空の園丁』は現在連載中なのだが、完結の目処は立っていない。
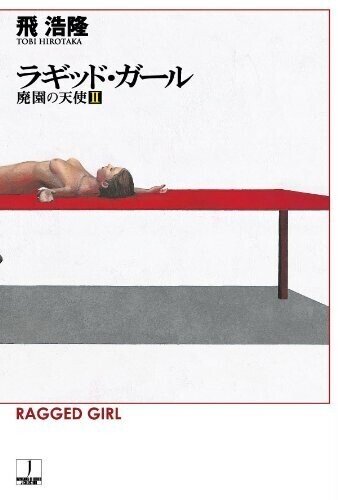

そんなわけで、私自身も、すでに『ラギッド・ガール』を入手しているが、そちらを読む前に、このレビューを書いている。本書(文庫版)に含まれる以上の情報で、本書の価値を論じたくないと思ったからである。
で、そうした観点からすれば、本書『グラン・ヴァカンス』は、SFマニアには「設定」的にはやや物足りないものの、一般読者には「設定」的に開かれた作品だと言えるだろう。新しすぎて、何が書かれているのかわからないという心配はない。
そして、その上で、本書の最大の魅力は、そうした「SF設定」の「新しさ」ではなく、SFでしか「設定」し得ない「残酷な世界観」において、「残酷かつ美しい悲恋物語」を描いた、という点にあると言えるだろう。
「ハッピー」とか「ほのぼの」とかいったものではなく、例えば、かつてのフランス映画にあったような「残酷かつ美しい悲恋物語」を、「仮想空間におけるAI」という「人間の奴隷」を設定することにより、今日では生々しく描くことの難しいであろう物語を、リアルに描いて見せたと言えるのである。
しかしまた本作は、優れて「切ない悲恋小説」であるに止まらず、「SF」らしい問題提起もしている。それは「彼らAIと、私たち人間とに、本質的な違いなどあるのだろうか?」ということだ。
「設定(プログラム)に束縛されたAI」に対し、「自由な人間」を対置することなど、果たして可能だろうか、ということである。
例えば、人間は「本能」という「プログラム」において、その行動を制限されており、決して完全に「自由」なわけではない。また、それに止まらず、法規、倫理、文化、常識といったものにも否応なく束縛されており、それでいて、その自覚が十分にある者など、一人もいないのだ。
一一というのも、私たちが、そうした「束縛」を認知しうるのは、個々に「設定」された「知的能力」の限界内でしかなく、その「遺伝的設定」は、本人のあずかり知らぬところでなされたものであり、生育後の本人の努力にしたところで、それも「努力できる性格」という「性格設定」によってあらかじめ決められている一一としたら、果たして私たちは、本作に描かれた「AI(仮想人格)」たちより、どれだけ「自由」であり「自立(自律)」していると言えるだろうか。
言うなれば私たちは、「神」が作った「生体AI」だとか、「宇宙」が確率的に作った「AI」だと言うことも可能だろうし、そのように考えれば、この物語で描かれているのは、じつのところ「人間」の姿や、その「宿命」であり「悲劇」だと言うことも可能なのではないだろうか。そこに「物語」的な誇張はあるにせよ、だ。

だから、本作は、「人間を描いた物語(文学)」であると同時に、SF(スペキュレーティブ・フィクション=思弁小説)として「思弁」を促す作品でもある。
ともあれ、本作を楽しめるかどうかは、読者個々の「設定」次第だと言っても、あながち間違いではないのである。
(2022年8月27日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
