
カート・ヴォネガット・ジュニア 『スローターハウス5』 : 60年代アメリカの 〈ため息〉
書評:カート・ヴォネガット・ジュニア『スローターハウス5』(ハヤカワ文庫)
カート・ヴォネガット・ジュニアの作品を読むのは、これが初めてである。買ったのも、たぶん初めてだ。
アメリカのメジャーなSF作家の作品は、たいがい買うだけは買っており、ただ、たくさん書いすぎて読めていなかっただけというのが多いのだけれど、カート・ヴォネガット・ジュニアの場合は、買ってもいなかったはずなのだ。
なぜ買っていなかったのかというと、ハヤカワ文庫の和田誠による表紙イラストにも象徴されるとおり、ヴォネガットの作品は「ユーモアもの」ではないかという印象が、まず、あったからだろう。
重厚な作品を好む私は、ジャンルを問わず、ユーモアものの小説はほとんど読んでこなかった。中間小説的な、オーソドックスなユーモア小説はもとより、ユーモアミステリにも、ユーモアSFにも興味がなかった。

ところが最近になって、少なくとも「SF」に関しては、「重厚」であればあるほど私の趣味に合うというものでもない、というのに気づいた。
というのも、「重厚さ」が売りの「ハードSF」というのは、どうしても「科学的な世界観」や「科学的な世界像」というものに重きをおく傾向があるからで、もちろん、それはそれで私の好みに合う作品もあるのだけれど、そもそも私が求めている「重厚さ」というのは、「人間を描く」という側面においての「重厚さ」であって、「世界観」とか「物語」としてのそれではなかったからである。
したがって、今回初めてヴォネガットを読み、たしかに「ユーモアもの」でもあるのだけれど、しかし「深く人間を描いている」という点で、大いに感心させられたのは、そういうことだったのだと、あらためて気づかされた。
私にとって大切なのは、SF独自の「道具立て」や「仕掛け」そのものではなく、それを駆使することで、より鋭く深く「人間を描く」ということだったのだ(例えば、P・K・ディックがそうであったように)。
ミステリの場合だと、人間が描けていなくても、「トリック」などの「アイデア」の部分さえ斬新であれば、それだけで十分に楽しめた。しかし、SFの場合はそうではないし、その点でミステリの場合とは、求めるものがまた違うということに、やっと気づかされたのであった。
○ ○ ○
さて、そんな「私のとってのSF」を誤解していた私が、どうして今頃、ヴォネガットを、と言うか、『スローターハウス5』を読む気になったのかというと、それは、セルゲイ・ロズニツァ監督のドキュメンタリー映画『破壊の自然史』で、ドレスデン大空襲のことを知ったからである。
ドレスデンというのは、ドイツの歴史ある街だ。ところが、この街が、第二次世界大戦中に、連合国軍による徹底的な空爆によって、壊滅的な被害をうけ、多くの犠牲者を出した。
こうした空爆は、ドレスデンに限られたことではなく、ドイツのいくつかの都市に対してもなされたのだが、その中でもドレスデンの被害の甚大さは、それを代表するものだったのである。
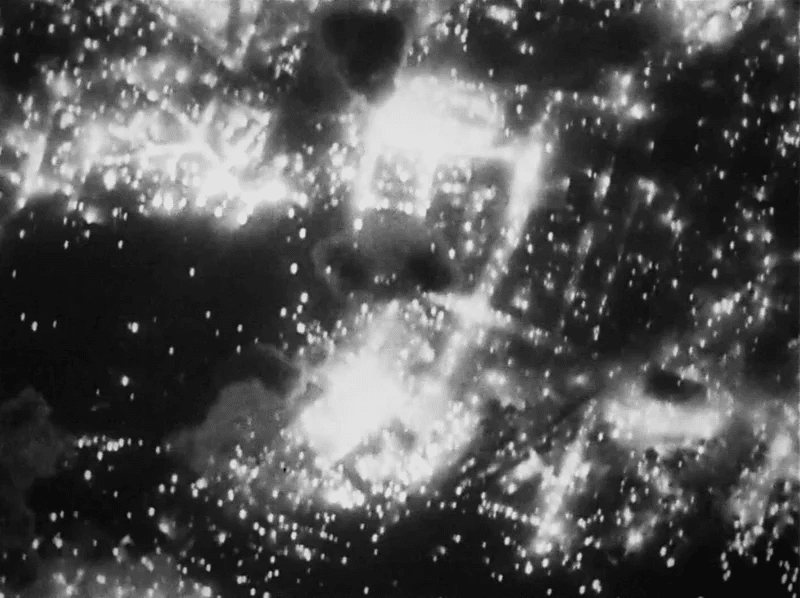
で、こういう「戦争犯罪」が、どうして一般にはあまり知られていないのかというと、それが「正義の連合国」のイメージを損ねる蛮行であったからであり、そのため、本書でも言及されているとおり、戦後長らくこれらの「不都合な事実」については、緘口令がしかれてきたせいである。
もちろん、連合国によってこのような「大規模殺戮」がなされたというのは、先にドイツが「ロンドン大空襲」のようなことをやったからであり、その「報復」の意味合いが大きかった。
だが、問題は「やられたから、数倍返しをしただけだ」では済まない、ということである。戦争中は、それで済んでも、戦後までは、そうはいかない。客観的に見れば「喧嘩両成敗」となるのが当然だったからだ。
だが、連合国は、戦争に勝利した結果、自らの「正義」をアピールしたかったし、しなければならなかった。だから、誤魔化しようもなかった、広島や長崎への「原爆投下」などは「戦争を終わらせるため」という大義名分を掲げて自己正当化した一方、それ以外にも、いろいろ酷いことをやっているという事実は、できるかぎり隠そうとしたのである。
で、前述の映画『破壊の自然史』のパンフレットの中に、ヴォネガットの『スローターハウス5』への言及があった。
ヴォネガットが、捕虜として、ドレスデン大空襲を体験した生き残りであり、その経験を描いたのが『スローターハウス5』だと紹介されていたのである。
もちろん、ハヤカワ文庫版の表紙に「UFO」が描かれているように、この作品は、ノンフィクション小説でも自伝でもない、歴としたSF小説である。
だが、ドレスデン大空襲の地獄を体験したヴォネガットが、その体験をあえて小説化しようというのであれば、それが本質的には、軽い娯楽小説になどなろうはずもない。
ユーモアはあるにせよ、扱うテーマ自体は軽くはないはずだと、そう考えたから、私は本作を読むことにしたのである。
で、こうした予想は的中し、私のヴォネガットという作家に対するイメージは、大きく転回したのであった。
○ ○ ○
本作は、ヴォネガット自身をモデルとした語り手の小説家が「ドレスデン大空襲」体験についての小説を書こうとして、なかなか書けないでいる、というところから始まり、やがて、その作中作家が、自身を投影した人物を主人公とした小説を書く、という展開になる。もちろん、テーマは「ドレスデン大空襲体験」なのだが、それをそのまま書くことは、どうしてもできないので、それをSF仕立てで小説にしたのである。
ドレスデン大空襲を体験した作中作の主人公は、戦後のある時、宇宙人にさらわれて、いろいろといじくり回された結果、タイムトラベルの能力を身につけることになる。
といっても、自分の「今の体」ごと過去や未来に飛んで、過去や未来の自分と同時に存在するというような、タイムパラドックスを伴うタイムトラベルではなく、意識だけが、順不同に、現在過去未来を行きつ戻りつする、意のままにはならない、不便なタイムトラベル能力だ。
どうして、こんな中途半端な能力を身につけたのかというと、主人公をさらったのは、4次元を生きる宇宙人であり、要は「時間を超越した」知的生命体なのだ。
だから彼らには、現在過去未来が、一望のもとに同時に見えているのである。そして、そんな宇宙人の影響を受けたから、主人公は現在過去未来を順不同に体験するようになってしまったというわけなのである。

ここで面白いのは、主人公のこうした「タイムトラベル体験」は、ある意味では「戦場体験型のトラウマ」による「フラッシュバック」に酷似しているという点である。
つまり、あまりに強烈な負の体験をしたために、それを順序立てて想起することができない。どうしても、記憶の混乱や欠落が生じてしまうのである。その反面、思い出したくもないものを、予期せぬ時に想起してしまうという点で「フラッシュバック」と似ているのだ。だから、作中作家が、「ノンフィクション小説」や「自伝」として、「ドレスデン大空襲」を書くことができず、その結果「SF小説」の形式を借りることで、やっとそれを書くことができたというのは、じつに説得力のある説明だし、このことは、作中の作家に止まらず、実在の作家であるカート・ヴォネガット・ジュニア自身にも言えることなのであろう。
無論、実在のヴォネガット自身は、書こうと思えば「ノンフィクション小説」や「自伝」あるいは「エッセイ」などとして、「ドレスデン大空襲」のことを書けたのかもしれない。だが、ここで大切なのは、「ドレスデン大空襲」体験を扱った本作だけの問題ではなく、ヴォネガットにとっての「SF」とは、それ自体が「目的」なのではなく、普通小説の形式では表現しにくいものを表現するための「手法」だった、ということである。
その点で、カート・ヴォネガット・ジュニアという作家は、普通の意味での「SFオタクあがりのSF作家」ではなく、書くべきテーマを、より適切に表現するための手法として「SF」というものを見出した「現代作家」だということになる。SFは好きでも、SFなら何でも好きだというタイプではなかったのではないだろうか。

実際、日本では「SF作家」扱いのヴォネガットだが、本国アメリカでは、その「枠」を超えて、優れた「現代作家」として、多くの読者を持ち、広範な評価を勝ち得ている。
無論これは、「SF作家としてではなく、普通の現代作家として評価された方が、偉い」という話ではない。現代作家にもピンからキリがあり、SF作家にもピンからキリまであるのだから、凡庸な現代作家よりは、非凡なSFプロパー作家の方が価値があるというのは、言うまでもないことだ。
ただ、これも言い換えれば、その評価がSF界に止まることなく、より広く評価されるというのなら、それはそれに越したことはない、ということである。
私が本作を読んだかぎりにおいても、カート・ヴォネガット・ジュニアという作家は、たしかにそういう作家である。
また、だからこそ、「SFとして」という視点でしか評価のできない「文学のわからないSFオタク」は、ヴォネガットの作品に「SFとしては、設定が弱い」とかいった、じつにつまらない注文をつけるかもしれないし、そうした意味で、ヴォネガットが理解できないSFファンというのは、意外に多いのかもしれない。
また、そんなことからか、ヴォネガットは、少なくとも日本のSF界では主流作家ではなく、主流から少し外れた「異色」作家扱いをうけているような雰囲気もあるのだが、だとしたら、それはあまりにも「(文学的に)狭量」であろう。
したがって、すでにわかっている人には常識に類する話かもしれないが、少なくとも日本では、ヴォネガットをまだ「SF作家」という枠で見ている人が少なくないと思うので、そうではない、それに限られるような作家ではないということは、もう少し強調されて良いのではないだろうか。
○ ○ ○
さて、本作『スローターハウス5』だが、前述のとおり、本作は、主人公の意識が、自らのコントロール不能のまま、現在過去未来と行き来する中で、自分の人生をたどりなおす、という物語である。
そして、その中心となるのが「ドレスデン大空襲」の体験だ。
子供時分のことは別にして、主人公の人生を時系列に沿って簡単に紹介すると、主人公は従軍してヨーロッパ戦線に派遣され、そこでの敗走中にドイツ軍の捕虜になる。そして、他のアメリカ軍捕虜たちと共に、ドレスデンにある捕虜収容所に列車移送されるのだが、主人公たちの収用された施設が、もともと「食肉処理場(スローターハウス)」であり、その第5番の建物だったから、そこは「スローターハウス5」と呼ばれた、という次第である。
捕虜の扱いに関する国際条約にしたがって、主人公たち捕虜は、この収容所からドレスデン市内の工場などへ労役に出ていたのだが、そんなある日、件の大空襲に遭うことになる。
主人公ら数名は奇跡的に助かるも、ドレスデンの伝統ある美しい街並みは灰燼に帰して、多くの民間ドイツ人が焼け木杭のような死骸となって、そこいらに転がっているという地獄を目の当たりにする。
そうした光景の中には「給水塔の中で茹で上げられた、女学生たちの大量の死体」を見たという趣旨の凄惨な事実も、淡々と語られる。

その後、主人公はアメリカに帰国し、しばらくは精神の不調で入院するも、やがて退院し、金持ちの娘と結婚して恵まれた生活を送るようになり、一男一女をもうけ、手に負えない問題児の息子も、ベトナム戦争に従軍して戻ってからは、立派に更生する。妻を失った後、主人公は娘夫婦と同居するのだが、ある時から「自分は宇宙人にさらわれて、数十年にわたる異常な体験をしてきたが、しかし、それは4次元生物である宇宙人によるものなので、地球時間では一瞬のことでしかなく、周囲の者には理解してもらえない。しかし自分には、その体験を通して知ったことを、人類のために伝える義務があるのだ」と訴え出して、騒動を起こし、娘からは「ボケ老人」扱いにされながらも、生まれた瞬間から死ぬ瞬間までの、現在過去未来を行き来しながら生きているのである。
このように説明すれば、おおよそのところは理解してもらえるとおり、「宇宙人にさらわれて異星まで行き、時間を超越する能力を身につけた」といったSF的なエピソードは、本作の主筋ではない。
また、それによるタイムトラベルも、それで現実を変えられるわけではなく、ただ「何度も再体験をするだけ」なのだから、よくあるタイムトラベルもののような冒険もなければ、先の見えないサスペンスもない。
あるのはただ「認識はできても、変えようのない現実」への、無力感だけなのである。

「訳者あとがき」(伊藤典夫)にもあるとおり、本作で特に印象に残るのは、作中で何度も何度も、ことあるごとに繰り返される、
『そういうものだ。』
というフレーズである。
この言葉は、主に「不条理な死」にまつわる場合に使われる。
「死とは、そんなものだ」という意味であり、「死の訪れ」というのは、おおむね「不意うち」であり「理由」なんてものはない。「あれをしたから死んだ」とか「こういう理由で死ぬことになったのだ」といった「因果応報」の論理は通用しない。「死」は、善人の上にも悪人の上にも公平に訪れる。なぜならば、死の訪れに「合理的な理由」なんてものはないからである。
しかし、理屈はそうでも、人間という生き物は、そんな「不条理」をそのまま受け入れることができず、つい「どうして、あんな立派な人が、あんな死に方をしなければならないのか?」とか「あんな野郎が、どうしてのうのうと生き延びて、威張っているのか?」と考えてしまう。それが、当たり前の人間の「性質(さが)」なのだ。
だが、ヴォネガットは「ドレスデン大空襲の惨状」を目の当たりにして、そうした「(人間的な)道理」が、この世には存在しないのだということを、嫌というほど思い知らされた。この世界は「そういうものだ。」としか形容しようのないものであることを、否応なく悟らされたのである。

だがこれは、完全な「悟り」としての「諦め=諦念」から出た言葉ではない。
心の底から「そういうものだ。」と思い込めているのであれば、「不条理な死」に直面するたびに、自分に言い聞かせるようにして、この言葉を繰り返す必要などないはずだからである。
だからこそ、この「そういうものだ。」という言葉の後には、「けれども」という「祈りの言葉」が隠されている。
「人間」とは、「この世界」とは、「そういうもの」なのだ。一一けれども…。
この「苦笑まじりのため息」にも似た「苦いユーモア」においてこそ、ヴォネガットの小説は、普遍的な「人間の文学」となり得ているのではないだろうか。
(2023年11月10日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
