
真説・異常論文 : 樋口恭介 編著 『異常論文』
書評:樋口恭介編著『異常論文』(ハヤカワ文庫)
もともと「異常論文」的なものが大好きである。例えば、小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』における名探偵・法水麟太郎の、似非神学的なペダントリーには、たまらなく惹かれた。半分は嘘八百の屁理屈だが、それで「この世の外」にまで連れ出してくれるのだから、壮大にして「もっともらしい嘘」ほど魅力的なものはないし、そもそも「小説」の面白さの最大の要素もまた、この堅牢に構築された「もっともらしい嘘(説得力のある嘘)」なのだと思う。
そんなわけで私は、樋口恭介編の「異常論文」集が刊行されると聞いて、大変楽しみにしていた。と言うか、正確に言うなら、本書の元型となった『SFマガジン』2021年6月号「異常論文特集」も購入していたのだが、雑誌は嵩張るため、読むのを後回しにしていたら、完全版とも言うべき文庫版が出ることになったので、そっちで読むことにしたのである。

さて、前述のとおり、私は『「小説」の面白さの最大の要素もまた、この堅牢に構築された「もっともらしい嘘(説得力のある嘘)」』であると思う。しかしながら、堅牢に構築された「もっともらしい嘘(説得力のある嘘)」が楽しめるのは、それがあくまでも「嘘」であることを公言した上での「作品」であってこそで、それが、さも「現実(非虚構)」であるかのように語られる「正真正銘の(他人を欺くための)嘘」であっては困る。具体的に言えば、「ペテン師の売り込み口上」であるとか「宗教の似非科学的妄説」などがそれだ。
しかしまた、現実の世の中では「嘘であることを自認し公言した上での(娯楽としての)嘘」と「他人を欺いて、不正に利益を得ようとする犯罪的な嘘」との境界は、きわめて微妙であって、明確な線引きなどできるものではない。
例えば、「宗教」における「教義」や「神学」などは、その宗教を信じていない人にとっては、すべて馬鹿馬鹿しくも犯罪的な「嘘」でしかない(例えば「イエスは死後三日目に復活して、その肉体を持って昇天した」「マリアの処女懐胎」といった言明など)。故意か無自覚かは別にして、宗教の勧誘(布教)などで語られる、その宗教の「正当化論」は、その宗教を信じない人にとっては「他人を欺いて、不正に利益を得ようとする犯罪的な嘘」のようにしか見えないのだ(リチャード・ドーキンス『神は妄想である』など)。
しかし、言うまでもなく、その「宗教」を信じている信者にとっては、その「理屈=教義や神学」などは「真理」そのものであり、ただ「世間の人々」には、その「真理」が理解できないだけだ、と認識されている。
したがって、その「理屈」が、「嘘なのか、難解な真理なのか」という判断は、おおよそ、その人の寄って立つ「信念体系」に依存するものであり、言ってしまえば、究極的には「どちらが真理かはわからない」ということになってしまうのである。
しかしながら、だからこそ、この「決定不可能性」につけ込む「ペテン師」や「ペテン師もどき」があとを断たないというのも、残念ながらこの世の偽らざる現実。
「自分はその理屈を、心から信じている」というフリをして、確信ありげに「大嘘」を語り、故意に「他人を欺いて、不正に利得を得ようとする犯罪者」が、そちこちに実在するのである。
だがまた、前述したように、こうした「マユツバな理屈」を語る者たちが、「ペテン師」なのか「盲信者」なのかの判別は困難だ。
そもそも、当人だって、最初は自覚的な「嘘」として語っていたものが、そのうち「本気」になるといったようなことも珍しくないのだから、ましてや他人に、そうした人物の「内心の自己認識」が、正確に判断できようはずがない。
そこで、問題となるのが、本書である。
○ ○ ○
本書に収められている論文の大半が、基本的には「論文形式の小説」であり、その意味で「自覚的なフィクション」であることは、それこそ論を待たない(中には「ここで語られたものは、嘘ではなく、〈もう一つの真理〉だ」と考えるような作者もいるだろうが、まあ、そんな作品も〈フィクション〉の内であろう。)。
しかし、問題なのは、編者である樋口恭介によって「異常論文」と名づけられた、これらの作品群は、はたして「樋口が言うようなものなのか?」という点だ。
つまり、「魚肉」を売るのに「これはめっぽう美味しいよ」と言って売るのは、その「魚肉」が「普通程度の美味しさ」でしかなかったとしても、まあ「主観の違い」ということもあるから「嘘」とは呼ばれず、許容範囲内とされるだろう。
ところが「魚肉」を「牛肉」だと偽って売れば、それは「ペテン」になる。
合法か否かといった「法規制」の問題ではない、「犯罪的故意」の問題として、それは「嘘」だとされ、指弾の対象になるのである。
そこで問題となるのが、本書編者樋口恭介の「売り込み口上」である、本書の「巻頭言」だ。
『 異常論文。
自律駆動する言語空間。
スペキュレイティブ・エンジン。
それらの名を持つ、言葉からなるオブジェクト。
それは加速する思弁が体現する、一つの生命そのものである。
思弁は現実を読み替える。思弁は一つの現実のうちから、その現実にはならなかったもう一つの現実を取り戻す。そのときシニファン・シニフィエ・シーニュと呼ばれる三つの記号の連関は破壊され、言語を起点にあらたな現実が立ち現われる。異常な言語の運用により、再帰が再帰を再帰し続け、分岐は分岐を分岐し続ける。異常論文の中で世界は実在し、書かれた世界は自らを生成する世界へ向かって領域を拡張する。実在しない実在が実在するということ。滅ぼされた滅亡が滅び続けるということ。ここにはない場所を故郷とすること。生まれ続ける生が生き延び続けるということ一一。
異常論文は呼吸する。異常論文は歩く。異常論文は這う。異常論文は走る。異常論文は揺れる。異常論文は震える。異常論文は噛む。異常論文は突き刺す。異常論文は切り裂く。異常論文を破壊する。異常論文は繋ぐ。異常論文は溶ける。異常論文は食べる。異常論文は嘔吐する。異常論文は排泄する。異常論文は血を流す。異常論文は応答する。異常論文は召喚する。異常論文は愛する。異常論文は憎む。異常論文は笑う。異常論文は怒る。異常論文は涙を流す。異常論文は語る。異常論文は叫ぶ。異常論文はささやく。異常論文は殴打する。異常論文は治癒する。異常論文は孕む。異常論文は産む。異常論文は殺す。異常論文は死ぬ。異常論文は蘇る。異常論文を破壊する。異常論文は創造する。異常論文は配慮しない。異常論文はわきまえない。異常論文は何一つとして気にかけることはない。異常論文は自己と他者を弁別しない。異常論文は内もなれば外もなければ外もない。廃墟の中を蠢く無数のオブジェクトたち。彼らによって形成される異形の生態系一一それが異常論文だ。』(P9〜10)
これは「嘘」だろうか、それとも「真実」だろうか。あるいは「本気」だろうか、それとも「自覚的な誇大広告」なのだろうか。
一応の正解としては、「レトリック」だ、と言うべきであろう。
「レトリック」であるからこそ、それは「嘘」でもあれば「真実」でもあり、「真実」として機能する場合もあれば、「嘘」として機能する場合もある。つまり、それは「面白いフィクション」になる場合もあれば、「犯罪」なることもある。
しかし、概して言えることは、「レトリック」は、無責任である。
つまり「レトリックはわきまえない。レトリックは何一つとして気にかけることはない。レトリックは自己と他者を弁別しない。レトリックは内もなれば外もない。したがって、レトリックには「犯罪」と「非犯罪」の区別もない。」だから、それを「表現の自由」と呼んだりするのである。
しかしながら、残念なことに、私たちは「何でもあり」の世界に生きているわけではない。
何者にであろうと、突然「噛まれたり、突き刺されたり、切り裂かれたり、破壊されたり」しては困る。
したがって、残念なことではあるが、一定の事柄については、それが何様であろうと、わきまえるべきはわきまえてもらわなければならないし、気にかけるべきことは気にかけてもらわないと困る。自己と他者、内と外も、基本的には弁別してもらわないと困る。私たちは、そんな世界に生きているのである。
一一そして、本書『異常論文』も、そんな世界に存在しているのであり、レトリックとして「この本は存在しない」と言っても、普通は通らず、下手をすると精神病院送りになってしまうことだってあり得るのだ。
で、そんな「実在」する本書について、「怒り」「噛みつく」人を見かけてしまった。
Amazonサイトにおいて、レビュアー「Black Midi」氏が「ホモソーシャル的痴態が出版されるということ」と題するカスタマーレビューを書いていたのだ。
とても力のある文章だし、私の場合と同様、将来的に削除される可能性もないではないから、念のため、以下に全文を引用しておこう。
『ここに納められた単体であれば称賛に値する"論文"の数々も、「異常である」という宣言 - 砕けた言い換えをすれば悪ノリであるとか自家中毒的、その出自からSNS上での呼びかけで編纂されたホモソーシャル的な寄り合いである事を臆面もなく表明したも同然の - アンソロジーに参加してしまった作家陣の不用意さと愚かさに、まずは天を仰がずにはいられない。編者による手癖と剽窃まみれの序文からしてバベルの混乱もかくや、といった様相を呈している本書だが(加えて2021年の時点で"奇形"という言葉をここまで不用意に扱う著述者を他に知らない)正常であることを理解し得ない者が異常を定義するなど烏滸がましく、型破りならぬ型なしもいいところ。「四角い本の形をしているため・支える/突っ込む/鍋敷に使える」以外に評価する点が見当たらない。何より本書の束見本を売ったほうが効率的だろう。』
要は「編者である樋口恭介を中心とした、仲間内の馴れ合いぶりが、とても気色悪いアンソロジーだ」ということであろう。本書『異常論文』を読む前に、このレビューを目にしてしまった私は「それは十二分にあり得るな」と、少し嫌な気分になった。
と言うのも、本書の執筆メンバーとかなりの部分が重なる人たちによって刊行された『世界SF会議』(早川書房)という「リモート会談本」を読み、私はそこに「身内の馴れ合いめいたヌルさ」を感じて、「SF作家だからといって、何も〈特別〉ではないのだから、もう少し頑張ってほしい。」と題する、批判的なレビューを書いていたからである。
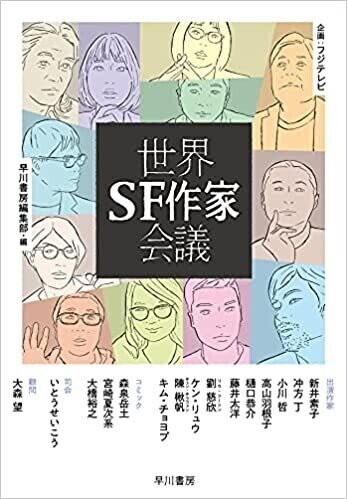
この『世界SF会議』の参加メンバーは、日本側が「新井素子、冲方丁、小川哲、高山羽根子、樋口恭介、藤井太洋、いとうせいこう、大森望」であり、リモートあるいはコメント参加の外国メンバーは「劉慈欣、ケン・リュウ、キム・チョヨプ、陳楸帆」で、簡単に言えば「大森望が高く評価する作家」であり「大森望に近い作家」だということになるだろう。
そして、本書『異常論文』においても、編者の樋口恭介は無論、執筆者の多くが「大森望一派」、と言って人聞きが悪ければ、本書所収の小川哲の短編「SF作家の倒し方」の表現に倣って「裏SF作家界」のメンバーだと言っても、決して誤りではあるまい。
「SF作家の倒し方」は冒頭部で、「裏SF作家界」は次のように紹介されている。
『 読者のみなさんはご存じないと思いますが、デビューしたSF作家は全員、飯田橋のホテルの一室に連れて行かれます。その場所で、SF作家たちはある重大な選択を迫られるのです。
「あなたはSF作家になりますか? それとも、裏SF作家になりますか?」
SF作家の職務は、SFの力を使って世界を良くすることです。人々の想像力を豊かにし、明るい未来の作り方を考える手助けをし、笑顔に満ちた幸福な社会の実現を目指します。それに対して、裏SF作家の職務は、SFの力を使って陰から日本を支配することです。人々の負の感情を呼び起こし、それによって生じた心の隙間にSFを流しこみ、裏SF読者を増やしているのです。
かく言う私も、デビュー後にどちらの陣営につくのか選択を迫られました。池澤春菜率いるSF作家界に加わり、世界を素晴らしいものにしていく手伝いをするのか、それとも、大森望率いる裏SF作家界に加わり、闇の力で日本を支配するか。
私は一切悩みませんでした。なぜなら私は「SFの力を使って世界を良くしたい」「SFの力を使って困っている人を助けたい」「SFの力を使って輝ける未来を作りたい」、そういう強い想いを持って作家になったからです。
しかしながら、裏SF作家界の力は強大です。有力な作家を次々と陣営に引き込み、陰から社会を支配しています。書店には息のかかった裏書店員がおり、裏SF作家専用の店があるという噂もありますし、各紙の書評では裏編集者によって裏SF作家が優遇されることがあると聞きます。また、裏SF作家界のボスである大森望は、創作講座を通じて優秀な裏SF新人作家の発掘、育成もしているようです。』(P239〜240)
まあ、これだけなら、同人誌などによくある「楽屋落ち」の実名パロディー小説ということになるのだが、この短編がウンザリするほど「ホモソーシャル」臭を漂わせてしまうのは、「裏SF作家の倒し方」の具体例として、「柴田秀勝の倒し方」「樋口恭介の倒し方」「高山羽根子の倒し方」「宮内悠介の倒し方」「飛浩隆の倒し方」、あるいは『まだ倒し方がわからない作家』であるため項目としては立てていないものの、『最強の男』として、神林長平に言及していたりするからだ。
要は、これらの作家は「裏SF作家」として「恐るべき強敵」だというかたちで、現実には「大森望一派」の仲間である小川哲が、裏返しの「身内ぼめ」をしているからである。そして、そうした事情の見える人には、この小川の短編だけは、どうにもウンザリさせられざるを得ないのだ。
また、私のこうした「意地悪な見方」を補強したのは、「裏SF作家」である樋口恭介が『未来は予測するものではなく創造するものである 一一考える自由を取り戻すための〈SF思考〉』(筑摩書房)という「SF的思考で、イノベーションを」という趣旨の「ビジネス本」を書いているからで、私は、この本における樋口の「コンサルタント〈口調〉」に心底ウンザリさせられ、そのまんま「コンサルタント〈口調〉が、鼻につく。」と題するレビューまで書いていたからだ。
『本書の本質的な問題は、本書はビジネスコンサルタントによる「ビジネス書」であって、そこには「文学」性など無いに等しい点だ。
その「語り口」は、いかにも「お客様に成功の夢を売るためのもの」であって、「人間の現実と深く格闘するもの」ではないのだ。
樋口は、本書の中で、「明るい未来を信じている」という趣旨のことを繰り返し語っているが、それは、そういう「タテマエ」に立たないことには、そもそも「ビジネスにおけるイノベーション」の探求なんてことに、限定的な興味を持ち続けることなどできないからだろう。
つまり、「現在の悲惨な現実」については、無視しないまでも、ひとまず脇に置いておいて、ともかく「われわれ」は、そうしたものが無くなる「希望ある未来」を構想しましょうよ、という提案しかなされていないのだ。
そしてそれは、樋口が本書において、すでに伝説的な立志伝中の「起業家」と呼んで良いピーター・ティール(決済サービスを提供するアメリカの巨大企業「PayPal」の創業者)を絶賛しているところにも、よく表れている。
たしかにティールは、偉大な起業家であり、人類の未来を開くための一翼を担っている「成功者」だと言えよう。だが、その影に「多くの犠牲者」が確実に存在する、という事実を忘れてはならない。
そうした犠牲が「人類の未来」のためには「必要だ」と考えるのであれば、犠牲者の存在を無視するのも、それはそれで合理的ではあるけれど、そうした「ホンネ」を隠した上で語られる「キレイゴトのご託宣」には、心底うんざりなのである。
私は「宗教」の偽善性とフィクションを批判してきた「積極的無神論者」だが、そうした私からすると、本書での樋口恭介の「語り口」は、あまりにも「コンサルタント口調」に毒されたものであり、あまりにも「非文学」的に過ぎるとしか思えない。』
端的に言って、私は、ニック・ランドと共鳴するようなピーター・ティールの「エリート主義」が好きではないのだが、そんな人物に共鳴する人物にも、あまり好感は持てないのだ。

ともあれ、樋口恭介は、SF作家であると同時に、間違いなく「ビジネスコンサルタント」であり、現物保証のない「良さげなアイデア」を商品とする、「口八丁のアイデア売り込み人」なのである。
そして、こんな「裏SF作家界」ならぬ「大森望一派」の「気鋭の論客」である樋口恭介の編んだのが、本書『異常論文』であってみれば、前記『未来は予測するものではなく創造するものである』でもそうであったように、樋口に「身内ぼめ」を恥じるような奥ゆかしさを求めるのがお門違いだというくらいのことは、ビジネスの世界を知らない人でも、おおよそ見当がつくはずだ。
要は、小川哲が前記の短編「SF作家の倒し方」でやったことを、レトリックが売り物の樋口が、本書の「巻頭言」でやっていたとしても、なんら怪しむに足りないのである。
実際、本書『異常論文』の執筆メンバーは、『世界SF作家会議』や小川哲の短編「SF作家の倒し方」に登場したSF作家を中心として、あとは「仲間に引き込みたい作家」によって構成されており、いずれにしろその「ホモソーシャルな政治的意図」が見え見えのアンソロジーになってしまっているのだ。
(※ 本アンソロジー収録作品、鈴木一平+山本浩貴(いぬのせなか座)の短編「無断と土」に対する、樋口の『現代日本を舞台にしたボルヘス「トレーン」の変奏である、と、ひとまず言ってしまうことができるのだが、思考の深度と情報の濃度、作品構築の緻密さと世界観の強度は圧倒的で、ボルヘスをゆうに超えていると言っても過言ではない。一言付け加えるとすれば、大変な傑作である。』というベタ褒め「紹介文」は、多くの読者がこの短編を優れた作品だと認めても、やはり、それ以上の「意図」を、樋口の言葉に感じずにはいられない。少なくとも、もしボルヘスが日本の現役作家だったなら、樋口はこのようには書かなかったと断じ得よう)
ともあれ、編者・樋口恭介は、本アンソロジーの建前としては『異常論文を破壊する。異常論文は創造する。異常論文は配慮しない。異常論文はわきまえない。異常論文は何一つとして気にかけることはない。異常論文は自己と他者を弁別しない。異常論文は内もなければ外もない。』と、いかにもSFらしく「自由かつ越境的」であり「ベタな人間関係や文壇的政治性」とは無縁なものであるかのように語っているけれども、「人間的現実」の方では、それとは真逆に「日本的なホモソーシャル」臭を濃厚に漂わせてしまっているのだ。
○ ○ ○
だが、幸いなことに、このアンソロジー『異常論文』には、そうした「ホモソーシャル」性を打ち破ろうとするものが含まれてもいる。
それは「和して同ぜず」つまり、そう簡単には「取り込まれない」と考えた書き手もいるということである。
本アンソロジーは、そうした書き手の存在によって、かろうじて「Black Midi」氏が言うところの『束見本を売ったほうが効率的』といった「醜態」をまぬがれ得たのではないかと、私は評価する。そして本書は、案外、人としての、あるいは、物書きとしての「生き方を考えさせる」本になっているのだ。
○ ○ ○
本書『異常論文』における、異常なほどに節操のない「馴れ合い」と「身内ぼめ」を、自覚的に破る作品とは、本書の掉尾を飾る、伴名練の短編「解説 一一最後のレナディアン語通訳」と、その後にくる神林長平の本書解説「なぜいま私は解説(これ)を書いているのか」の2本だ。
「解説 一一最後のレナディアン語通訳」は、アンソロジストとして熱のこもった「長文解説」を書くことで知られる伴名練が、自身の「解説文」のパロディー的な作品として書いた小説だが、その内容はいたって真面目で真摯なものであり、先の小川哲の「真面目をおちょくり倒した芸風」とは対極にある作品だと言って良いだろう。
そして、この作品で語られるのは、まさに一一「SFを利用した犯罪」なのである。
独自の言語である「レナディアン語」を創作し、レナディアン語でのみ書かれうる世界を表現した小説を、自身はもとより仲間も集めて創作し、「クトゥルフ神話」大系の言語版を思わせる、独自の『詩経世界』を展開したSF作家・榊美澄。
しかし、独身だった彼が、自宅に「レナディアン語」しか話せない少女(仮名「A」)を監禁していたことが発覚。「レナディアン語」が、実は少女を監禁しておくために作られた「監禁言語」なのではないかとの疑惑が持ち上がるも、少女が「意味的な指示対象が曖昧な言語」である「レナディアン語」しか話せない点がネックとなって、真相の解明は難航する。しかし最後は、少女が拒絶反応を示す日本語ではなく、中国語を教えたことで、意思疎通における言語的な困難が乗り越えられ、榊の「犯意」が立証されて、その有罪が確定する。
一一そんな、一人のSF作家をめぐる「言語と欲望」の物語を、『レナディアン文学作品集成』の「解説文」として書いたのが、伴名練による本作「解説 一一最後のレナディアン語通訳」である。
伴名は、本書の中で、最後に名前が明かされる解説者「弾さゆり」と、榊から名前すら与えられなかった被害少女「A」に託して、次のように語る。
『 レナディアン語の評価が、「言語SFを得意とする作家の創造した魅力的な架空言語」から滑り落ち「監禁言語」「犯罪者の言語」といったものに固まるのは、中国語によってAが自身の性的被害を語り始めてからのことである。
レナディアン語とは、レナディアン人であるAにとって、「アル(=榊)が神であり父であり母であり恋人である」と予め定義された支配のための言語だったのである。
異常な多義性を持っているのは、Aにとっての、発話によるコミニケーションと、自身が受けている性虐待とを認識上で混同させ、その境界線を心理的にも溶解させるためだった。
語彙や文法が変わっていくのは、言語という意思表示のための道具が榊が司っていることを誇示し、榊に従わねば意思疎通さえ不可能という状態を作って、洗脳を強化するためのものだった。』(P666)
『「榊は、言葉は剣であるべきではないと語りました。綿のように無数の対象を包み込むものでなくてはならないと教えました。
けれど私は、言葉は時に剣でなくてはならないと思います。安らぎと恐怖、快楽と苦痛、親切と悪意、事実と解釈、愛と支配、あなたと私、それを言葉が切り離すことができると知った時に、私は本当にこの世界に生まれたのだと感じます。もし剣と呼ぶのが危ういのならば、暗闇の中に浮かぶ光だと思います。
たとえば夜の道で人の足元を照らし、行く先を示す暖かな街灯の光のような」(A)
(原文は中国語、生田志穂訳)』(P676)
どうであろう。
榊美澄というSF作家は、本アンソロジーの編者である樋口恭介同様に、悪い意味で「レトリック巧者」だったのではないだろうか。
○
そして、本書『異常論文』の解説者である神林長平は、次のように語る。
『 小説ほど自由な文芸分野はほかにない。字数にも書き方にも決まった規則はない。創作物なのだから、本当のことを書かねばならないといった心理的な拘束もない。嘘をつくのが得意な人間はほど入りやすい分野だ。どんなに奇妙な内容であってもかまわない。どのみち想像力を振り絞って嘘を書こうとしたところで、「事実は小説よりも奇なり」という寸言があるように、「事実」の奇妙さにはかなわないのだ。小説家のつく嘘など、たかが知れているということである。
しかし何を書いてもかまわないのが小説だとしても、奇をてらうことが目的ではない。小説という虚構世界の中にその人にとっての真実を表現することが、小説を書くことの意義である。完成した作品が傑作になるかどうかもそこにかかっている。傑作を書くには作者自身も知らない「自己」へとアクセスすることが必要になる。小説における「真実」とは、そこにしかないからだ。』(P682)
私の言葉に言い換えれば、小説は「自他に誠実な嘘」でなければならない、「真実を描くための嘘」でなければならない。
自己を偽り、他者を侮って、その小器用な三百代言的口八丁で、読者をたらし込めれば「こちらの勝ちだ」というような「ペテン師的な不誠実さ」では、レトリックに幻惑された「被催眠状態の読者」を生むことはできても、時を経て残るような「優れた小説」は遺し得ない。
『「誤読」されることのない小説はだれにも読まれず未完のまま放置された作品に等しいことから、「異常論文」を読む際には、意識して「誤読」に努めなくてはならない。樋口恭介が言うところの、「過剰な読解」が必要になる。そうすることで多くのバリエーション=破格が生まれるからである。
豊かなバリエーションを生じさせる作品は生物と同じく、生き残る確率が高くなる。平たく言うなら、さまざまな「読み」ができる小説ほど、強い。「異常論文」は過剰な読解=誤読を要求するが、その事実は取りも直さず、そのような「誤った」読み方によって「強く」することができることを示している。そのような小説は他にない。』(P686〜687)
したがって、私のこの読みほど、本書『異常論文』を総括する読みとして、歓迎されてしかるべき「強い」読みも、またとないはずである。
無論、本稿は、きわめて真っ当な「論文」ではあるけれど、「世界」の方が歪んでいるのなら、この論文こそが、そこでは真の「異常論文」として機能するのだ。
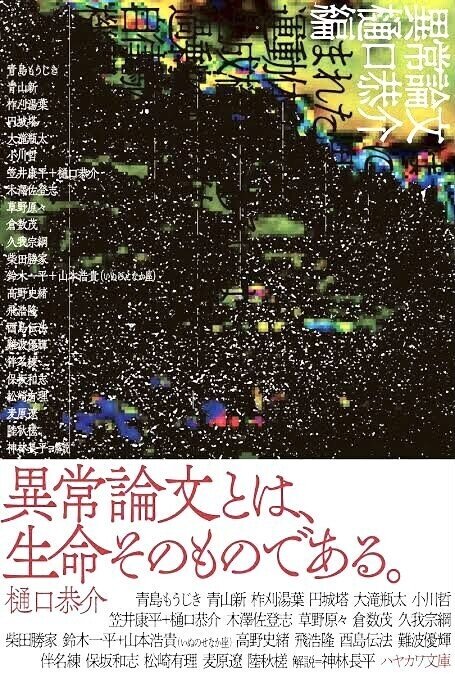
--------------------------------------------------------------------------
【補記】
以上は『異常論文』についての、総論的な感想であったが、収録作22篇の中から、個人的に好きな作品について、短く紹介しておこう。
・倉数茂「樋口一葉の多声的エクリチュール ──その方法と起源」
「異常論文」と言うよりは、まっとうな文芸評論であるが、とにかく面白かった。
「その狙いが面白く、オブジェとして美しい」作品も、それはそれで素晴らしいとは思うが、しかし私は、普通に「理解し得る中身」を求めてしまうので、異次元にまで突き抜けた作品より、こうした作品の方が、個人的には好みなのだ。
初めて読んだ作家だったので、早速、小説作品の方も数冊購入した。
・保坂和志「ベケット講解」
これも「異常論文」と言うよりは、保坂の「いつものエッセイ」であるが、この「自分の感性だけしか信じずに、それにこだり続ける」様子が、なんとも個性的で好きだ。多分に「独りよがり」な部分はあるし、そこは批判したこともあるけれど、それでも、この作家の固有性は、余人を以ては代えがたい。ベケットの『モロイ』も購入した。
・酉島伝法「四海文書(注4)注解抄」
酉島伝法は、『皆勤の徒』を読んで、その「イモムシ好き」的な趣味がイマイチ合わなかったのだが、本作は「狂気」ものであり、稲生平太郎の『アクアリウムの夜』や『アムネジア』を彷彿とさせる「私好みの作品だなあ」と思って読んでいたら、しっかり「横山茂雄」の名前が登場した。ぜひ、この方向で、現代の『ドグラ・マグラ』を書いて欲しいものである。
・伴名練「解説 一一 最後のレナディアン語通訳」
短編集『なめらかな世界と、その敵』のレビューにも書いたことだが、この人は本当にいまどき珍しい「真っ当にまともな人」で、その人間的「誠実さ」に好感を禁じ得ない。
--------------------------------------------------------------------------
【補記2】 SF界のホモソーシャリズムについて
レビュー本文では、「Black Midi」氏の言葉を引用するかたちで「ホモソーシャル」という言葉を、説明ぬきで使っている。
Wikipediaによると、この言葉は、
『ホモソーシャルという言葉は、イヴ・セジウィックによる「男性のホモソーシャル(同性間の結びつき)への欲望」という議論によって普及した。それよりも早い1976年に、ジーン・リップマン=ブルーメンが性的な意味ではなく、社会的な意味での、同性の仲間への選好をホモソーシャリティ(homosociality)と定義している。』
となっているが、本稿で使われているそれは、こうした『同性の仲間への選好』という意味ではなく、「同好の仲間への選好」といった意味であり、「性別」は問題としていない。
そこで、ついでと言っては何だが、私が昔から気になっていたことについて、少し書いておきたい。
それは、SF界におけるホモソーシャリズムの強さと、それと関連するであろう「異質な個人」への排除傾向である。
私はそれを、ここでは、山野浩一、梅原克文、瀬名秀明といった人たちをめぐって生起した問題として想定している。
無論、この3人は、それぞれに個性も方向性も異なる人たちなのだが、SF界の外から、彼らをめぐるトラブル(?)見ていた印象では、「石を持って追われる(追い払われる)」といった、あまり好ましくないものがあったのだが、これは私個人の単なる誤認なのだろうか。
私は長らくミステリマニアの世界に関わってきた人間なのだけれども、少なくとも日本の場合、ミステリ界に比べて、SF界は、良くも悪くもホモソーシャリズムが強いように見える。つまり「身内・仲間」意識が強くて、団結心があるその一方、個人や異論を尊重する気風に乏しい印象があるのだ。
例えば、SF界では「SF大会」のようなホモソーシャルなイベントが昔から安定的に開催され盛り上がるのに、ミステリ界の方では、どうにも散発的で、あまりうまくいっていない印象がある。もちろん、こうした仲間意識による盛り上がりは大いに結構なことなのだが、それが「異分子排除の袋叩き」的なものに転じた可能性もあったのではないか、という疑問が私にはあるのだ。
このあたり、私は「SF業界」の人間ではないから、業界裏事情的なことはわからない。
また、こうしたホモソーシャリズムは、「日本人」一般の傾向のように思うのだが、それがどうして、ミステリ界よりもSF界で強いように見えるのだろうかと、そこがかねてより気になる。
それにまた、近年のわが国では、こうしたホモソーシャリズムが強まっているようにも思えるので、この問題が、ひとつ「SF界」や「大森望一派」にのみ完結するものでもない、と思っている。
(※ ちなみに、レビュー本文では、大森望氏にはあまり嬉しくないであろう「大森望一派」という言葉を使ったが、私は大森氏個人に含むところはない。むしろ、多方面に良好な人間関係を広げつつ、SF界を盛り上げている大森氏の尽力と個性には好意的である、と言っても良いだろう。私が、レビューで批判したのは、大森氏の取り巻きに当たる、一部の人たちである)
例えば、最近見かけたところでは、次のようなものがある。
『 二〇二一年一月十日の朝日新聞では、新型コロナウィルスに関する調査で、六十七%の人が、「健康より世間の目が心配」と回答したと報じています。』
(阿部恭子『家族間殺人』P227)
『望月 (略)ネット用語に「ぼっち」というものがあります。
森 「ひとりぼっち」の「ぼっち」ですか。
望月 森さんも「ぼっち飯(ひとりでご飯を食べること)」とか聞いたことありますよね。それで、同僚のお子さんが高校に入学してから、子供の様子を見ていると、とにかく「ぼっち」になることをみんなが恐れていると。入学式で会う前からクラスのみんながSNSで繋がっているらしく、特に女子にその傾向が強いらしいんですけどね。
森 意外だな。女性のほうが社会性はあると思っていたけれど。
望月 入学してからもぼっち飯にならないように、帰りもぼっちにならないようにと、とにかくぼっちを回避するために全力を尽くす。ぼっち回避のためだけの学校生活は、それはそれで結構きついわけですよね。どこかの集団に常に属していないと、という感覚は強迫観念にもなってしまいます。だから今の若い子たちには、ひとりぼっちというものがとても嫌なものとして捉えられているようです。』
(森達也・望月衣塑子『ジャーナリズムの役割は空気を壊すこと』P171〜172)
前者は、コロナ禍におけるマスク着用率の高さに表れた、日本人には昔から強いとされる「同調圧力」の問題だが、後者の場合は、そうした「同調圧力」がSNSの普及によって強まっているようだという観測に依拠した議論だ。
そして、これを私の『異常論文』レビューに接続すると、少なくとも日本のSF界でも、その傾向(の強まり)があるのではないか、という話になる。
無論、SF界では、昔からホモソーシャリズムが強かったのだが、近年では、日本のミステリ界でもそうした「ホモソーシャリズムな徒党」が増えたように感じられるので、おのずとSF界の方もその傾向が強化増進されているのではないかと推測される。
文学の世界におけるホモソーシャリズムは、日本にかぎっても「漱石山房」の時代からあったものだし、現今の出版不況下における、作家間互助組織の必要性の高まりといったこともあろう。だが、いずれにしろ私の気になるのは「繋がり指向の強まりと文学の質的な関連性」である。
Amazonのカスタマーレビューを見ていても、SF小説に寄せられるカスタマーレビューは、ミステリに寄せられるそれに比べて「人気者への擦り寄り的な媚び」を感じるものが多いように思うのだが、これは私の穿ち過ぎなのか、それともジャンル的な特性なのか。
ともあれ「同調圧力の高まり」とは「個の弱体化」でもあろうから、神林長平が『異常論文』の解説で『小説という虚構世界の中にその人にとっての真実を表現することが、小説を書くことの意義である。』と書いているとおり、何よりも強固な「個」が重要であった文学の世界において、この「個の弱体化」がどのような影響をもたらすのか、あるいは、すでにもたらされているのか、そこが私の気になるところなのである。
(2021年11月4日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
