
浅羽通明 『星新一の思想 予見・冷笑・賢慮のひと』 : 不出来な〈自伝〉
書評:浅羽通明『星新一の思想 予見・冷笑・賢慮のひと』(筑摩選書)
著者は、星新一を「アスペルガー症候群」的であると判定している。
「アスペルガー症候群」とは、
『ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)とは
社会的なコミュニケーションや他の人とのやりとりが上手く出来ない、興味や活動が偏るといった特徴を持っていて、自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群といった呼び方をされることもあります。』
(「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)とは」)
といったようなものだ。
専門的な議論は別にして、ごく大まかに言うと「アスペルガー症候群」とは、生まれ持った脳機能の偏りによって、その能力に偏りが生じ、ある特定の事柄に関しては、非常に優れた能力を発揮するその反面、バランス感覚や対人コミュニケーション能力に劣ることが多く、そこで社会的に差し障りの生ずることも少なくないという、そんな社会適応障害の一種である。要は、能力のバランスが悪く「広く配慮する」というようなことが苦手なのだ。
本書の著者・浅羽通明は、星新一の、冷たくも温かくもない、「人間味」というものの薄い「低体温」で「フラット」な作風は、そうした「人間的感情に対する鈍感さ=共感能力の低さ」と、その反面の、情に流されない「客観的本質把握能力」から生まれてきているのではないかと、おおよそそんな見立てをしている。これを簡単に言うと「星新一は、アスペルガー系の人」だ、ということになるわけだ。
私は、この評価が、まったく正しいと思う。
すでに私は、本書でもしばしば参照される、ノンフィクション作家・最相葉月による星新一の評伝『星新一 一〇〇一話をつくった人』のレビュー「天皇・星新一ですら〈ただの人〉であった。」を書いているが、このレビューでは、星新一その人がどういう人であったかについての、個人的な判断は下していない。
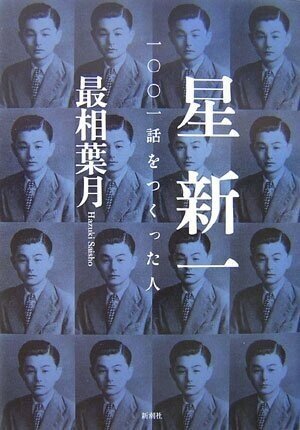
むしろ、星新一をめぐって明らかになった「日本のSF界の生臭さ」の方を問題にしたレビューであったと言えるだろう。だから、私は、こんなふうに書いている。
『(4)『 私(※ 星新一)は人生について深く考へる事は余り好きではない。我々の生きている事について、何故とか、何のためとか考えた事はない。そのような事はなるべくそつとしておくことにしている。深く考へることに自分の性格が堪えられるかどうかが恐ろしいのである。』
(文庫版下巻・P163)
これが、星新一を考える上で最も重要なポイントとなる、星の自己認識であろう。
要は「人間(そのもの)については、考えたくない」人なのである。
なぜ、星新一がこうなってしまったのか、そのいちばんわかりやすい説明としては「望まずに星製薬を引き継いだ後に、いやというほど体験させられた、信頼していた人たちの裏切り」により、深く傷ついて人間不信になった、といったことにでもなるだろう。
だが、私の興味は、そうしたところにはない。私の興味は、とにかくこうして本人からも自覚的に語られた「人間不信」が、その後、作家になった星新一に、どのように表れたのかという結果の方である。』
つまり、星新一の「人間性」については、あまり興味はなく、結果としての「こういう人」が「作家として、どのような個性を発現させたか」ということの方に興味を持った、ということである。
しかしながら、私がこのように考えたのは、ひとつには、最相葉月のこの評伝で描き出された「星新一」像は、非常に「常識的」に「人間的」なものであり、「人間リアリズム」の視点から書かれた手堅いものではあったのだけれど、どこか「当たり前」すぎて、星新一の特異性を捉えきれていないように感じられたからでもあろう。「星新一が、あのような人になったのは、その生まれと育ちにある」といったような最相葉月の評価は、大筋で間違いではないにしても、どこか物足りなかったのである。
そして、その足りなかった部分についての「謎」を、「星新一は、アスペルガーだったのだ」という身も蓋もない評価で、ズバリと解き明かしてみせたのが、本書の著者・浅羽通明だったのである。

○ ○ ○
しかし、ここで、きわめて興味深い、注意すべき点がある。
「星新一は、アスペルガーだったのだ」という浅羽通明の評価に対し、Amazonカスタマーレビューにおいて、レビュアー「天乃川」氏が「決めつけ」と題するレビューで、
『星新一のファンはたくさんいるし、いろいろな意見があって当然だと思う。その意見が自分と違うからといって低い点をつけたのではない。ただ、この本のように、故人の著作、仄聞した言動だけから、医師でもない著者が、星新一をアスペルガー症候群だとにおわせるのは、大いに間違っているのではないか。何らかの症候群とレッテルを貼ってそれに合った星新一の情報だけをピックアップして、他を切り捨てた、ともいえるだろう。何より、これは疾患であり、それに罹患している患者が現実に存在するのに、なぜこんなにも軽々しく素人が「診断」してしまえるのか。出版社もこれをどうとも思わなかったのだろうか(だからこそ出版したのだろうが)。評論以前の問題だと思います。』
と、批判しているのである。
この「天乃川」氏のレビューに対し、かつて筒井康隆を「断筆宣言」にまで追い込んだ、世の良識的な人々を思い出し、反「ポリコレ」的な感情から「なに、優等生的なタテマエを振り回してるんだよ」と批判したくなるというのは、気持ちとしてはわからないではないが、いささか軽率安易である。
なぜなら、医師でもない者が素人判断で「(レトリックであったにしろ)病気のレッテルを貼る」ことの危険性というのは、スーザン・ソンダクが『隠喩としての病い』で問題提起して以来、多くの文筆家には共有された、重要な問題意識だからである。

例えば、私がいま読んでいる、野間宏の『青年の環』には、「ちんば(跛行の身体障害者)」で人格的に問題のある人物が登場し、作中の語り手の一人は、この人物の思想を「ちんばの哲学」と呼んで、内心で分析して見せている。
こうした作品は、現在では、そのままのかたちでは刊行されにくいというのは、ろくに文学作品を読まない人にでも、容易に想像することができるだろう。それは前述のとおり、作中で「てんかん」を描いて問題となり、「断筆宣言」にまでいたった、筒井康隆の先例があるからである。
つまり、安易に「病名」などを「比喩」として使うべきではない。「ユダヤ人は、人類の癌だ」といったような慣習的表現が、人々に与える影響というものを、決して軽く見てはいけないのである。
だが、その反面、そうした「慎重さ」を推し進めていった結果の「言葉狩り」もまた、多くの問題をはらむものであり、「使わなければ、それで問題は解決なのか。むしろ、それは問題の隠蔽でしかないのではないか」という問題を惹起し、昨今では「不適切な言葉は使わない」という当たり前の理想を掲げた「ポリティカル・コレクトネス(政治的妥当性)」の運動が、厳しい逆風にさらされてもいる。
だから、本書『星新一の思想』において、著者の浅羽通明が、わりあい無造作に、星新一を「アスペルガー症候群」「アスペルガー」「アスペルガー系」といったかたちで評していることに疑問を感じ、批判の必要性を感じる人がいるというのは、じつに真っ当なことなのだと言えるだろう。
一一だが、問題は、浅羽通明は「その程度のこと」にも気づかないで、星新一について、無邪気に「アスペルガー」という言葉を使ったのか、という点なのだ。
○ ○ ○
本書を、読んでいてすぐに気づくのは、浅羽通明という人は、実によくいろんな本を読んでいる、ということであろう。
端的に言って「ひけらかしが過ぎる」ほど、いろんなジャンルのいろんな書き手に、意識的言及して、それはまるで「小間物屋の雑貨の如し」と評すべきほどなのだ。
この「いろんな本を読んでいる(そしてそれを見せびらかす)」とは、よく言えば「ジャンル越境的」であり「非専門的」、さらに言うなら、積極的に「反専門」主義の読書(であり文章作法)だと言えるだろう。
そして次に気づくのは、浅羽通明の「物の見方」は、その読書形態に見合って「横に広がっていく」ものであって、「深く掘り下げる」ものではない、という点だ。
つまり、浅羽通明は、対象(本書の場合は星新一だが)を分析評価する場合、星新一という人を、その一点に執着し「腰を据えて、深く掘り下げる」のではなく、ジャンル越境的なその縦横無尽さにおいて、普通は関連付けされることのないようなものをアレコレ引っ張ってきては、それとの「関係性」や「類似性」において、星新一という人の「個性」を浮かび上がらせていくのである。
さて、この二点から、窺えるのは、どういうことだろうか?
それは、浅羽通明自身が「アスペルガー症候群」的な「才人」である、という事実である。

つまり、たいへんな「博捜博識」の人であり、その意味で「非凡」な能力を持っているのだが、基本的に「落ち着き」がなく、星新一と同様に「他者の感情に鈍感」で「内面的な掘り下げを苦手とする」タイプだということだ。
したがって、浅羽通明は、星新一に対し、何も考えずに、あるいは無神経に、「アスペルガー」という形容を奉ったのではないだろう。
浅羽は、自身に「アスペルガー症候群」的な傾向のあることを自覚しており、その視点から、星新一の中に同種の傾向を見(洞察し)、その同類的「共感」から、星新一に対し、意図的・積極的に「アスペルガー」という形容を与えて、暗に「仲間」意識を誇示して見せたのである。
つまり、浅羽通明の星新一に対する「アスペルガー」という評価は、同じ障害を持つ者としての「実感」に即した、きわめて的確な評価だったと言えるだろう。
星新一の苦悩や苛立ちが、浅羽通明には、とうてい他人事とは思えないほどに、ひしひしとリアルに感じられた。だからこそ、浅羽は臆することなく、星新一に「アスペルガー」の形容を贈ったのだ。
当然、浅羽は、スーザン・ソンダクの『隠喩としての病い』くらいは遠の昔に読んでおり、その問題提起の重さも理解していた。しかしその上で、そうした障害の当事者として「これ以外に、どう言い換えろと言うのだ」という、通俗良識への批判の意図を、あえて隠し、確信犯的・挑発的に、「アスペルガー」という言葉を使って見せたのである。
○ ○ ○
しかし、これは、一種の「屈折したエリート意識」でしかない。

浅羽通明という人は、真正面から、こうした「通俗良識」や「左翼紋切り型」に反対するのではなく、「わかる人にはわかる」という隠微なかたちで、つまり「内心で相手を見下しながら」も、それを表に出すことなく、からかう(冷笑する)ことで、我が身の不遇についての「憂さ晴らし」をしているのである。
そんなわけで、本書『星新一の思想 予見・冷笑・賢慮のひと』も、「星新一論」という建前で、星新一を前面に立てるかたちで、じつは、自分自身を語り、自分自身を褒めている、「自慢話の書」なのだと言えるだろう。文字どおり、なかなか「陰険」なのである。
ともあれ、そのために本書は、星新一という人を「客観的かつ多面的に、長所も短所も公平に描こうとした」ものではない。「星新一の長所を最大限に評価する」というかたちで、じつは、(人が語ってくれない)自分自身の「長所美点」を最大限に語ったものなのだ。
だから、こうした「糊塗された自己喧伝」は、本書後半、第5章「「小説ではない」と言われる理由」あたりから、ウンザリするほど現れてくる。星新一に仮託されているからこそ、自堕落な「自慢の垂れ流し」になってしまっているのだ。
この第5章で語られるのは、いわゆる「(純)文学」批判であり、「(純)文学という権威」批判である。
『 星新一作品をつまらないという人はじつは少なからずいます。
おもしろいけれど、小説とか文学とはいえないという人も少なくありません。
例えば文芸評論でも人気の小谷野敦は、その卓抜なSF論「SF「小説」は必要なのか?」(『このミステリーがひどい』の第5章)で、星作品をただただ「面白くはなかった」と断じています。
文学好き、小説通から、「どこがおもしろいの」といわれることはけっこう多い。
最初期の数篇が直木賞候補となった際、選評で唯一触れた源氏鶏太は、「星新一氏の「ショート・ショート」は、実に面白い。しかし、文学的な面白さと思われなかった」としました。
最相葉月の評伝は、新潮社の石川光男の、最初の星新一作品集の企画を出すが、出版部長は「なんだ、それは。小説じゃないじゃないか」とまったく取り合ってくれなかったという手紙を引用しています。
文学部のゼミなどで、学生が星新一を扱うと、あんなもの小説じゃないよと教員にすげなくいわれるというのもよく聞く話です。
最相による評伝が話題を呼んだとき、文芸評論家の川村湊は、「私自身は星新一という作家(文学者)をあまり評価していないので、こんなに大部の評伝が書かれるほど文学史的な位置のある作家なのかという疑問を持った」(「東京新聞」二〇〇八年三月三十日付書評欄「テーマで読み解く現代」)と漏らしました。
しかしこのような否定派の人たちにとって、星新一がどうつまらないのか、どこがどうだから、文学的ではなく、小説とはいえないのかをしっかり論じた例は見当たりません。
つまらなければ無視すればよいわけで、わざわざ論難する手間をかける人もいないのでしょう。
貴重な例外というべきなのが、都筑道夫が、『妄想銀行』文庫版に寄せた解説です。
解説執筆のため『妄想銀行』一冊を読み終えた都筑は、「退屈せずにすらすら読みおわって、はて、これは小説なのだろうか」と思ったといいます。
ストーリーは明快で具体的だが、「それを構成する人物や背景のイメージが、具体的に迫って来ない」。
「小説とは描写なり、という言葉があります。そうとばかりはいえないとも思いますが、こう描写が欠けていると、やはり首をひねりたくなってくる」
こう評したうえで都筑は、重要な指摘をします。
「一行一行の文章そのもののおもしろさが、ないわけですから」と。
一行一行の文章そのもののおもしろさ……。都筑道夫自身は、これを出すために心血そそいできた作家かもしれません。
序盤でじらしつつ気をもたせて、中盤以降の急展開まで読者をひっぱれるかどうかは、文章に喰いつかせられるかにかかっているわけですから。
では、ここでいう一行一行の文章そのもののおもしろさを産む「描写」とはいったい何でしょうか。』(P203〜205)
長々と引用したが、この部分でも、浅羽通明の「文学」嫌いは、わかりやすく伝わってくると思う。
浅羽通明にとって「文学」とは、「たんに面白いものであってはいけないと命じる権威」であり、なにやら偉そうに、上から「合否」を決めつけるもののように感じられている。ところが、その「合否判定の基準」が明確ではない、と感じられてもいるのだ。
そこで、まず浅羽が目をつけたのは、都筑道夫による「文章の力(描写の妙)」といったことであり、上の引用部分の後に「感情描写のない小説」という見出しで、星新一の小説には「感情描写」がないに等しいが、それが果たして欠点だと言えるのか、という議論を展開している。

そしてさらに、見出し「バーチャル恋愛を楽しめない星作品」では、「感情描写」がないに等しい星作品では、当然のことながら、普通の文学作品における魅力の一つである「バーチャル恋愛」が楽しめないわけだが、それが文学として欠点なのかという、同様の議論を展開する。
以上のような「星作品」擁護から浮かび上がるのは、浅羽通明という人自身が、いかに「文学の魅力」を解し得なかった人か、という事実であろう。
「文学」の魅力を論じるのに、「文章の力(描写の妙)」や、「バーチャル恋愛」に代表される「疑似(人生)体験性」を持ち出すというのは、間違いではないけれど、本質を外した「文学」論でもあろう。
「文学」の魅力には、たしかに「文章の力(描写の妙)」や、「バーチャル恋愛」に代表される「疑似(人生)体験性」といったことも含まれる。それは否定できない事実だし、否定する必要もない重要「要素」であり、つまり「要素」でしかない。
「文学」を愛好する者として言わせてもらうなら、「文学」の魅力とは、「文章によって、世界と格闘すること」である、とでも言えるだろうか。
そうしたことの手段として、「物語」があり「ストーリー」があり「描写」があり「疑似(人生)体験性」もあると言って良い。つまり、それらはすべて「文章によって、世界と格闘すること」の「手段」であって、「目的」ではないのだ。
だから、こうした「文学」の本質においては、読者にとって「面白ければ、それで良い」ということにはならない。
「文学」とは、あくまでも「書き手」にとっての「文学」であり、その「優れた結果」が、たまさか「読者の共感」を呼んで楽しませる、ということでしかないのだ。
ところが、本来、書き手のためのものである「文学」が、読者にとっての「娯楽」対象にもなって、「娯楽」商品としての価値を持ってしまうと、そこで、「文学」とは「読者にとっての文学」つまり「娯楽商品」だという認識に転倒してしまう。
これは資本主義社会において、「書き手」も食っていかなければ書くこともできない、という現実における、必然的な成り行きであった。したがって、作家の側でも「自己満足」に終始することはできなくなってしまうのだ。
一一だが、「文学の初志」は「文章によって、世界と格闘すること」であって、「商品価値を持つ文章であること」ではない。結果として、そうなるのはかまわないが、それを目指すことは、本来的には、本末転倒なのである。
ところが、この本末転倒状態が、資本主義社会において当たり前の「常態」になってしまうと、「文学とは、そういうものじゃない」と言われても、ピンと来ない人が出てくるのは必然だ。なにしろ、私たちの前にある「文学作品=小説」は、「小難しい作品」もあれば「単純に面白い娯楽作品」もあるけれど、いずれにしろ「好きな人が選んで買う商品」でしかないからである。
つまり「小難しい作品」が好きな人もいれば、「単純に面白い娯楽作品」が好きな人もいる。結局は、読者(購読者)のそれぞれが「自分の好みにあった(面白いと思える)作品」を買って読むのであって、そこに「上下差別はない」ということになってしまう。なのに「どうして、文学文学と威張るんだ。小説の中に、文学と非文学があるなどと差別しようとするのだ」ということになってしまう。
「所詮は、好みの違いではないか」ということであり、それはそうなのだが、この考え方は、小説が「読者ありき」であることを前提としたものであり、資本主義下における「商品としての小説」であることを、自明の大前提としてしまっているのである。
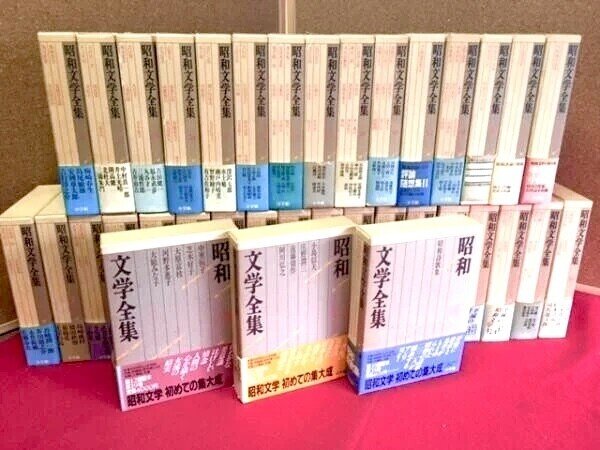
だが、「文学」好きは、そうではない。
「文学」好きの好きな「文学」とは、「読者に媚びない、作者の全身全霊を傾けた、世界との闘争の記録」である。それが、たまたま「小説」という形式を採ることもあれば、「詩歌」「エッセイ」「評論」といった形式を採ることもある、というだけの話なのだ。
そしていずれにしろ、「文学」好きは、そうした「読者になど妥協しない」作品に積極的に食らいついていくことで、その作品を通して、読者自身も「世界と格闘する」のである。当然これは、単なる「娯楽」などではない。
だから、前述のとおり、「文章の力(描写の妙)」や、「バーチャル恋愛」に代表される「疑似(人生)体験性」といったものも、「文章によって、世界と格闘すること」の「手段=武器」として必要なものであっただけで、本来は、それが「目的」ではなかった。
だが、資本主義社会の中で、本来の「ストイックな目的」が見失われていき、「文章の力(描写の妙)」や「疑似(人生)体験性」といった「道具」へのフェティシズムが発生し、そのあげく、それ(道具)こそが「文学」であるという「物神信仰」が広まって、「文学」への誤解が、さらに深まっていったのである。
○ ○ ○
で、こういう「文章によって、世界と格闘すること」などという「抽象観念的」なことは、「アスペルガー」的な人の、最も苦手とするところだ、と言えるだろう。
浅羽通明の「横に広がっていく」傾向も、星新一の『「人間味」というものの薄い「低体温」で「フラット」』という特徴も、要は「表面」がすべてであり、その奥など無い(感じられない)という感覚に由来するものなのだ。
だから、自分とは「異質な他者の内面」などというものはまったく苦手だし、同様に「文章によって、世界と格闘すること」などという「内面的かつ観念的な掘り下げ」趣味など、理解を超えたものなのである。
そのため、浅羽通明には、そして星新一には、「(純)文学」というものが理解できず、それを「実体のない権威主義的幻想」だと、そう決めつけずには、安心していられなかったのである。
『「文学性」という規制を撤廃せよ』という「被害者意識」丸出しの見出しのついた部分で、浅羽通明は、星新一の「コンテスト選評」を引用しながら、「文学」を次のように論じているが、私の「文学」論を読んでいただいた後ならば、浅羽や星新一の議論が、いかに「偏頗」なものであるかが、ご理解いただけよう。
『 しかし、です。
星新一が、一般読者の目線にたって発見した新井素子以下は皆、要するにエンタメばかりではないか。小説は、SFは、それだけで、売れるというだけでよいのだろうか。
そういう疑問が生じてこないでしょうか。
例えば、いわゆる「文学性」の問題です。
ここであのショートショート・コンテストの選評をもう一度、検討してみましょう。
一九八四年度の選評にあった、選者だが一般読者でもあるという一文はこう続くのです。
すなわち、「だから「この文学性が理解できぬのか」と言われても「わからぬでもないが、多くの読者には通じないだろう」と答えるしかない」と。
翌、一九八五年度の選評にはこうあります。
「知人はわかってくれない。選者ならという考えもあろうが、ここでは文学を求めているのではない。一般性のないものは、私もいい点をつけない」
選者なら専門家だから同業者目線でみてくれるだろうという甘えを、星新一はやはり厳しく排しています。
選者だからこそ星新一は、専門家でない一般読者、すなわち「知人」に代表される「めったに感心してくれない他人」になりきって、応募作品に臨んでいるのです。
この厳しさは、自ら実践してきた作家だからこそでしょう。
(中略)
そこまで「他者」「外部」へ届くように心がけていた星新一にとって、選者なら専門家だから文学性に気づいてくれて、内容のおもしろさの欠如を大目に見てもらえるかもといった甘えは許しがたいものだった。
太宰治だって谷川俊太郎だってサービス精神がこもりエンターテインメントがあるとした例の文章は、「文学まがい、散文詩まがいも好ましくない。まがいでなければ、もちろん認める。手におえなくなって、まがいに逃げてはいけない」とした一文に続くものなのです。
面白くなくても、文学性がある。ないというのは、おまえには文学性が理解できないからだといった「文学性」ふりかざしは、ダメな作品を自己正当化する高慢な弁明でしかない。
面白さだってそれなりに相対的ではありますが、文学性のように、問答無用の権威を背負ってはいない。
ありがたがれとは強制できても、面白がれには無理があるのです。
一九八六年度の選評で、「話の不鮮明な、文学ぶりっ子はもいけません」と例によってたしなめた星新一は、「同人誌には、よくあるのだ。金を出してなら勝手だが、ここは商業誌なのです」と続けています。
そして、「面白いものがかければ、ご本人はむろんのこと、読者だって喜ぶのだ。物語の原点は、それですよ」と基本の基本をまたも念をおすように確認しているのです。』(P342〜344)
要は、星新一は「面白い作品=読者を楽しませる作品=娯楽作品」で「なければならない」と考えている。
「文学」は、偏狭にも「文学であらねば」と言うけれども、『物語の原点は、それ(※ 普遍性のある面白さ)ですよ』というわけだ。
けれども、私の「文学」論である「文章によって、世界と格闘すること」が「文学」であると考え、「読者を喜ばすこと」は「余禄」に過ぎないと考えるならば、当然、星新一の議論は成り立たない。
星新一の「小説」論とは、あくまでも「小説」というものが、資本主義社会における「商品」であることを前提とし、「いくら理屈を捏ねたところで、売れたものが勝者だ」という「資本の論理」に立脚したものでしかないのである。
そして、最相葉月の評伝でも語られていたとおり、星新一は「読まれる作家」「売れる作家」ではあったけれど、「文学とは認めてもらえなかった作家」だからこそ、「読まれる小説=売れる小説=広く読者に受ける小説」でなければならないと「自己正当化」的に考えたに過ぎないのであり、「読者第一」というのは、「星製薬」の「(お客様に対する)親切第一」と同じく、「資本の論理」に立脚した上での、所詮は「きれいごとの建前」でしかなかったのだとも言えよう。仮に、星新一自身は、その「建前」を、「真実」だと自己暗示的に、半ば信じ込んでいたとしても、である。

したがって、上の引用部での、「甘えた投稿者」の「文学ぶりっ子」とは、所詮「文学」とは無縁・無関係なものである。
前述のとおり、「文学」とは、そもそも「他人に評価してもらうために書くもの」ではなく「止むに止まれず(まずは自分のため)書くもの」なのである。
だから、そんな「文学」の何たるかを知らない、勘違いの「文学」かぶれが、「文学」でも何でもないものを「文学」のつもりで書いて、「文学」のわかっていない選者に送り、評価されなかったところで、そんな話は「文学」とはまったく無縁な話。
つまりここでは、「文学がわからない星新一」を褒めたい「文学がわからない浅羽通明」が、「文学」でも何でもない「文学もどき」を引き合いに出して、さも「文学」が実のないものであるかのように語っているだけなのだ。
しかしまた、この部分を読めば分かるとおり、そうした点では、まだ星新一の方が慎重であり、自分は十全に「文学」を理解してていないということを、半ば理解してはいた。
だから『「この文学性が理解できぬのか」と言われても「わからぬでもないが、多くの読者には通じないだろう」と答えるしかない』と、奥歯に物の挟まったような言い回しをしたのである。「(私は純)文学を完全に理解しているが、これは売れる商品にはなっていない」と、忖度しない星新一らしくハッキリ言い切ることをしなかったのだ。
『わからぬでもないが』という言い回し(二重否定)は、星が「文学を完全に理解しているというわけではないが」というニュアンスを含ませてものであり、『多くの読者には通じないだろう』という言い方は「通俗性(どんなに読解力のない読者にも理解できる、単純なわかりやすさ)が足りないだろう」という内容の、「見栄えの良い、言い換え表現」に過ぎなかったのである。
浅羽通明はここで『面白くなくても、文学性がある。ないというのは、おまえには文学性が理解できないからだといった「文学性」ふりかざしは、ダメな作品を自己正当化する高慢な弁明でしかない。』と書いているが、これは「文学」が書けていない書き手が、「自分の作品(非文学)」について言っているからこそ『ダメな作品を自己正当化する高慢な弁明でしかない』のだけれども、「文学」そのものについての議論としてなら、「文学がわからない読者=拙い読者」にとっては『面白くなくても、文学性がある』作品は、事実としていくらでも存在するし、それを、そんなものは『ないというのは、おまえには文学性が理解できないからだ』という指摘は、まったく正しい、ということにもなるのである。
それは「事実の指摘」であって『「文学性」ふりかざし』などではなく、「能力のない奴に、能力は無い」という事実を語っているだけで、「文学」権威主義者の『自己正当化』でもなければ『高慢な弁明』でもない。
「人間心理に鈍感」で、「人間を、図式的に理解すれば、それで理解できたなどと思い込むような、文学的単細胞」には理解できず、そのために「面白くない」としか感じられない(文学)作品でも、それが理解できるがゆえに、心底面白いと感じる「文学愛好家」は現にいくらでも存在しており、そうした「読者を選ぶ文学作品」というのも、現に存在しているのである。
浅羽は、「小説」を読むのに「訓練はいらない」かのように匂わすことで、難解な本を読んだこともない、読む努力をしたこともない読者に「媚びて」、そうした「訓練されていない大多数読者」を味方につけようと、姑息な画策しているだけなのだ。
結局のところ、浅羽通明や星新一は、「文学」をどうしても理解することができない「アスペルガー」的な弱点を抱えていながら、それを率直に認める勇気を持たない(病識否認の)ために、自分の手の届かない(能力の及ばない)葡萄は「酸っぱい葡萄」に違いないと決めつけ、レトリックのかぎりを尽くして、あの「葡萄(文学)は酸っぱい」という認識が真実だと、自他共に「思い込もう、思いこませようとしているだけ」なのである。
『「酸っぱい葡萄」(すっぱいぶどう)は、イソップ寓話の一つで、その邦題(日本語題名)の一つ。原題(古代ギリシア語題名)は "Ἀλώπηξ καί σταφυλή" (ラテン翻字:Alópex kái staphylé、和訳:狐と葡萄)、ラテン語題名は直訳した "Vulpes et uva "、英題も直訳した "The Fox and the Grapes " で、邦題にも直訳した「狐と葡萄(きつねとぶどう)」がある。狐が己が取れなかった後に、狙っていた葡萄を酸っぱくて美味しくないモノに決まっていると自己正当化した物語が転じて、酸っぱい葡萄(sour grape)は自己の能力の低さを正当化や擁護するために、対象を貶めたり、価値の無いものだと主張する負け惜しみを意味するようになった。』(Wikipedia「酸っぱい葡萄」)
○ ○ ○
浅羽通明は、本書の中で、たびたび最相葉月の『星新一 一〇〇一話をつくった人』を引き合いに出して、その星新一理解の不十分さ、不適切さを指摘している。
最相が、星新一の「アスペルガー」性にハッキリと気づき得なかったという点で、たしかに浅羽には及ばなかったとは言えるだろう。
しかし、それにもかかわらず、最相が、その「常識的人間観」において星新一を「描写」した結果として、多くの共感を得、高い評価を得たというのは、「読者とは、一般にそういうものを好む(面白いと感じる)」という事実において、理の当然でしかない。
だが、そんな「人間の心理に鈍感」な浅羽通明には、世間の最相評伝への高評価は、「読めていない」不当なものと感じられて、妬みを抱かざるを得なかった、ということなのであろう。
ともあれ、こうした「心根」において、つまり、「アスペルガー」であることの「劣等感」と、「私は、不当にも、適切に評価されていない」という「ルサンチマン」に基づいて書かれた本書だからこそ、星新一を前面に立てながらも、浅羽通明の「自己正当化の自己喧伝」は、後半に行くほど露骨に、うるさくなっていく。
星新一を褒めるかたちさえ採っておけば、いくら自己正当化論を語っても、責められたり嘲笑されたりすることなどない、と高を括っていたのであろう。
以降は、ここまでの「浅羽通明」理解を踏まえ、浅羽の言葉を引用しながら、逐語的に解説していこう。
○ ○ ○
『 ところが文学の領域もまた、そこまで透明度の高い自由市場ではありませんでした。
そのため星新一は、父星一ほどではないにしろ、やはり熾烈な闘いを強いられたのでした。』(P335)
ここには、浅羽通明の、業界における「疎外感」が、星新一に仮託されて、語られている。
つまり、浅羽にとって「文筆業界」は『透明度の高い自由市場』ではない、と感じられており、要は「能力のある者(つまり、浅羽)を適切に評価しない、そのコネ社会」に対し、ルサンチマンを抱えている、ということである。
『 いわば、星新一は、作家(含む志望者)たちに対して、同業者目線、専門家目線としてではなく、未知の一般読者目線、すなわち「他者」のまなざし、「外部」の目で真向かったのでした。』(P339)
要は、浅羽通明は、自分は、馴れ合いの「文筆業界」になど同化せず、孤高にして「外部の目」を保持し、客観的に業界を見ている、という(自己満足的)自己評価である。
『 新井(※ 素子)の作品を読むときも、星新一は、大衆文化の形成に責あるひとりとして、「自分が作家であることを忘れ」、「理屈無用で、楽しさだけを求める者」たらんと努めていたのかもしれません。』(P340)

星新一が『「理屈無用で、楽しさだけを求める者」たらん』としたのは、前に指摘したとおり、自分自身が「楽しさ」が売り物の作家だからに過ぎない。
「楽しさ」こそが最高の価値であってくれないと困るから、他者の作品の鑑賞においても、そこを「重視した」に過ぎないのである。いわばこれは、文学的な価値観における「党派性」の問題でしかないのだ。
『 高千穂遥の異世界ファンタジーをまえに、星新一は一般読者の中の一般読者、小説書きにとって一番怖い読者である「一少年」に還っていたのでしょう。そして、「SFマニア」のフレームを外せず、高尚を好む「おたく」青年たちを、君たち、本当にディックのほうが面白い?と挑発してみせたのでした。』(P341)
要は、星新一は自身が「フィリップ・K・ディックを楽しめなかった(理解できなかった)」ので「君たちも、本当は理解できていないんだろう。理解できたフリをしているだけだろう」と「ケチな勘ぐり」をしただけである。
ハッキリ言わせてもらうが、私は、ディックが大好きであり、特に、一般には難解とされている『ヴァリス』三部作でデイックファンになったような人間である。
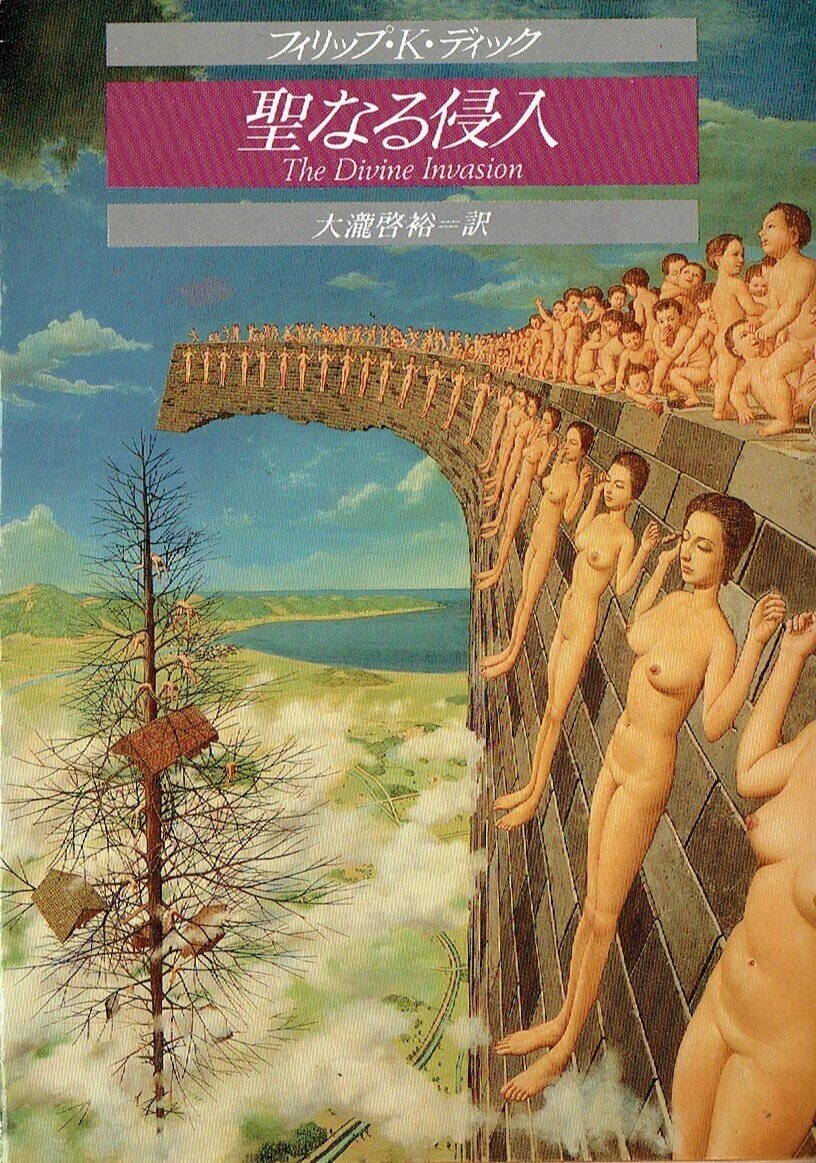
たしかに『ヴァリス』三部作は「難解」だ。しかし、その「難解」さも含めて「面白い」と感じるような人間のいることを、星新一や浅羽通明は、その「わからないは、つまらない」「わかるは、面白い」という「単純な人間理解と価値観」において、理解し得ないのである。
「人間」とは、アスペルガー系の二人にはわかりにくいほど「複雑なもの」なのだ。また、だからこそ、「文学」は、「誰でも楽しめる」という意味での「面白い(娯楽性)」だけでは、済まされない「奥行き」を持つのである。
『 しかし、SF界というところもまた、大きな同人誌のごとき一面を否定できない。
黎明期、それぞれが一家をなすつわものばかりが集った初期「宇宙塵」ならば別ですが。
実際、SF界でも、「文学性」にあたるマジックワードがけっこう飛び交っていました。星新一がニューウェーブを、「もともと、売れない人のやっかみ」(新井素子『今はもういないあたしへ…』解説、『気まぐれフレンドシップPART2』所収)と斬ってすてたのもディックに点が辛かったのも、それがSF販の「文学性」ふりかざしだと解したからだと考えられます。』(P346)
星新一は、ディック作品と同様に「ニューウエーブSF」も理解できなかった人である、ということがここでわかる。
当然、こんな人なら「(純)文学」が十全に理解できるわけもなく、だからこそ前述のとおり『「この文学性が理解できぬのか」と言われても「わからぬでもないが、多くの読者には通じないだろう」と答えるしかない』などと曖昧に誤魔化して、「文学」がわかるフリ、をしていたというのが、ことの真相なのだ。

したがって、こうした星新一の、「酸っぱい葡萄」の狐そのものの「大人気ない」そぶりを、『それがSFの「文学性」ふりかざしだと解したからだと考えられます。』などと、無理にでも「正当化」したのは、浅羽通明自身が、「博識」ではあっても、星新一と同様の「文学オンチ」であり、そのために「評論家業界」内での評価が、本人が自負するほどには高くなかったからに他ならない。要は、単なる「文学オンチ」だとは、絶対に認めたくないだけなのだ
『星新一はサイバーバンクもまた、「わけもなく歩きまわっている」ニューウェーブ同様の「あだ花」だとくさしています。』(P347)
星新一は「サイバーパンクSF」の「面白さ」も理解できなかった。
星新一のこうした「偏狭さ」は、「アスペルガー」的な「他者への理解困難性」に由来するものと見て、間違いはない。

要は「自分の趣味ではないけれど、こういうものを本気で面白いと感じる人(他者)もいるんだろうな」と、実感を持って考える(他者の内心を想像する)ことが、星新一にはできなかったのだ。
「自分とは違う感性」という「他者」を想定できない、頑固なまでの「越境不可能性」こそが「アスペルガー」的な困難であり、弱点なのである。
『 そうした人間関係から、いつしか共有される空気がそこにできあがり、馴れ合いが生じて、遂には「文学性」であれ「サイバーパンク」であれ、「外部の他者」にはさっぱりわからぬ種々の符牒が行き交うようになってゆく空間から、星新一は最も遠いところで執筆していた。
文学賞と無縁だったのも、この立ち位置と無関係ではなかったはずです。
「人間関係でつながる社会は不健全だ。技術でつながる社会にしたい。プロかアマというだけで勝負の決まる世界に」
これは、デビュー当時の星新一に毎月、ショートショートを依頼したただ二つの媒体のひとつ(もう一つは「宝石」)「ヒッチコック・マガジン」の編集長だった小林信彦が一九六六年、五月三日、日記に記した一文です(『1960年代日記』)。
まさに星新一こそは、こういうありかたをつらぬいた作家でした。考えてみれば、小林信彦もまた、その実力、キャリアを知られながら、大きな賞に恵まれなかった非文壇的作家なのです。』(P348)
ここにも「疎外され、不当に低い評価を与えられている私」という「自意識=自己憐憫」と「不満=不遇意識」が露骨に反映されているが、そんな自分を、「星新一」や「小林信彦」などの大物に重ねることで、浅羽通明は自身を「受難不遇の鬼才」だと思い込もうとしているのである(観念的自己回復)。
『 人間関係に庇護されるのを潔しとせず、己が技術、才覚のみを恃んで進まんとするインディペンデントな自営業者。bossとはいってもそのイメージは、いわゆる「文壇ボス」などといわれる類の対極だったといえましょう。
(中略)
ここで大事なのは、文壇ボスの類と違って、こうしたbossは番頭や手代や丁稚をしつけ、叱る場合も、彼らの手に職(技術)をつけてゆくという目的を忘れてはいなかっただろうところです。
それぞれの個性や才能を見出し、「理解と同情」を惜しまず伸ばしゆく方向で技術指導する。可能ならば、かの新井素子のようにめでたく「のれん分け」してゆくその日まで……。
晩年の星新一は、そんな家元だか大旦那だかの重責を、意識不明になるその直前まで、果たし続けたのでした。』(P349〜351)
『人間関係に庇護されるのを潔しとせず、己が技術、才覚のみを恃んで進まんとするインディペンデントな自営業者』などと(かつて笠井潔が言ってたような)勇ましいことを書いているが、これは、本音では「公式な地位(文壇的地位や文学賞)」が欲しくても、自分には与えられないから、「そんなもの、初めから欲しくはないよ」と強がっている、子供の態度と、なんら違いはないものでしかない。
だから、そうしたものが与えられるとなれば、ホイホイ貰いに行くというのは目に見えいるし、欲しいからこそ、このようにグズグズと書いているのである。
また『大事なのは、文壇ボスの類と違って、こうしたbossは番頭や手代や丁稚をしつけ、叱る場合も、彼らの手に職(技術)をつけてゆくという目的を忘れてはいなかっただろうところです。』というのは、「文壇」で評価されないからこそ「他所でボスになりたい」というだけの話でしかない。要は「子飼いの子分」を作って、先生先生と持ち上げられたいだけである。
これは、浅羽通明が、星新一に「忠誠」を誓う「親分子分」的な人間であり、その延長として「読書会」などにおいて、「業界外」で自身の「支持者」を作ろうとしていることにも見て取れる。
こういうアマチュアの子分でも、作っておけば、例えば「Amazonカスタマーレビュー」に「高評価」を書き込んでもらえる、といったメリットがあるからだ。
しかし、所詮はこれも、一種の(下からの)「人間関係による庇護」でしかない。
『文壇世間へのプロテスト』(P351)
これは「見出し」だが、浅羽通明の「自意識」が、ここにも(星新一に仮託されて)語られていると断じてよかろう。ご本人としては「不遇な抵抗者」のつもりであり、一種の「悲劇的ヒロイズム」に酔っているのである。
『 ここまで考察したならば、本章の冒頭で提示したあの謎、最晩年の星新一が、方々の出版社のパーティーにまめに出席し、ぽつんと立ちつくしていたのはなぜかに対して、最相葉月とはまた別の答えが出せるのではないでしょうか。
章のはじめにも登場願った私の知る編集者が、星新一の本をずっと以前に一冊だしただけで、以後はどちらかといえば冷遇している彼の社のパーティーに毎度現れるこの大家の話をするとき、ぽろりと口からこぼれた一言がわすれられません。
「あの人は、要するに新潮社の人だからねぇ……」
作家と出版社、あるいは編集者にも、系列的な関係が出来ている。星新一の場合、主要な作品集をまとめ、文庫に入れてきた新潮社とのつながりが最も強いのは誰もが認めるでしょう。
となれば、編集者との人間関係も新潮社中心となるはずであり、したがって他の版元のパーティーにいっても相手にしてくれる編集者が少ないのはいたしかたない。
(中略)
そんな(※ ジャンル分けにかぎらず、あらゆる物事において、分け隔てをせず、等距離の関係たらんとする)星新一にとって、新潮社も他の版元も何らかわるものではなく、パーティーの案内をよこす以上は皆、対等。同じように出席し、手土産をもらって帰路に就くだけのことでだったのです。
縁うすい版元のパーティーへ出席しても「さみしい思い」をするだけだという思いは、「人間関係」で版元とつながっている凡百の作家と、彼らの相手をするのを疑わなかった凡百の編集者ならではなのでした。
そうした巨大な同人誌のごとき空間を生き続ける我が国文壇の人々に対して、系列など聞いたこともないとばかりに、いずこのパーティーにも飄然と現れ、相手をする編集者の有無などどこ吹く風と、しばし滞空して去ってゆく星新一の端正な長身は、それだけで鮮烈にして颯爽たる社会批評だったとはいえないでしょうか。』(P352〜353)
これは、最相葉月による「老残の星新一」像に対する、浅羽通明の「プロテスト」だが、あまりにも「非現実」的に「願望充足的な妄想」でしかなく、現実的には、およそお話にならない解釈でしかない。
つまりこれも、典型的な「酸っぱい葡萄」的「自己正当化妄想」である。
『「文学的」というのは、星新一にとってはたして賞してもらいたい評言だったのかどうか。』(P354)
手の届かなかった「葡萄」とは、はたして星新一が、真に求めていたものだったのだろうか一一という、誤魔化しである。「私は、もともと、そんなものを求めてはいなかったんだよ」という「後付け」の自己正当化であり、自己美化だ。
『 はるかな未来から、現代をも近未来をも回顧する。それはあらゆる悩み、問題が、なんでもなくなるほど徹底した「価値の相対化」にほかならないでしょう。
英米のSFではちょっとないタイプかもしれません(例外として、E・ハミルトンの短編が挙げられます。「世界の外のはたごや」とか「世界のたそがれに」など)。
未来志向でも前向きでもなく、進歩的でもない。まさしく後ろ向きなのです。』(P 377)
ここで、浅羽通明という評論家が、「保守主義者」であることが明らかになる。
本書を通読すれば、浅羽が高く評価する評論家は、星新一を認めなかった前出の小谷野敦を含めて、山本夏彦(P390)や呉智英(P402)といった「冷笑系」の保守主義者であることがわかるし、後でわざわざ、香山リカ(P402)の否定的評価を語っていることからも、浅羽通明が「進歩的」「左翼的」「リベラル」なものを嫌う「保守主義者」だという事実が、わかりやすく露出している。
そして、この線において、「フィリップ・K・ディック」や「ニューウェーブSF」や「サイバーパンクSF」といった、従来のSFからはみ出す「新しいSF」を嫌った星新一を無条件に支持した、浅羽通明の本質的「心性」も明らかとなる。
浅羽通明は、「古き良きSF」しか理解できず、「新しいSF」への試みは、すべて単なる「新しがり屋のカラ騒ぎ」にしか見えず、要は「他者」が理解できないのである。そういうものを「本気で面白い」と感じる「他者」が、想像し得ないのだ。


『 それでもそのとき、さまざまな読者が、脳内に想定されていなくてはならないでしょう。
固定ファン、マニア、たまたま手に取った読者、男、女、少年少女、学生、若者、サラリーマン、主婦、シニア……。
星新一の場合、ずっと未来の読者も、翻訳でよむ世界の読者も、視野のどこかにはいたはずです。
彼ら彼女らを面白がらせる。そうした心構えで、創作に向かうとき、その発想は、人間が人間であるかぎり免れないだろう、「現実とは、存在とは、人間とはなにかを、ふり出しに戻って考えなおさせられ」るような根源的なテーマから汲みあげられざるをえないでしょう。それこそが普遍だからです。』(P396)
無論、「視野を広く」持つことは、大切である。しかし、人間というのは、すべてのことに詳しくなることはできないので、何かを極めようと思えば、嫌でも守備範囲を「限定」せざるを得ない。
浅羽通明や星新一のように、その「アスペルガー」性のゆえに、自動的に「他者」が見えなくなるのであれば、意識的な「限定」をする必要もないのだろうが、「もっと他者を知りたい」と思い、注力すれば知ることができる能力のある人であっても、すべての「他者」を知ることなど、物理的に不可能なのだ。
さて、ここで浅羽通明は、星新一が「広く配慮していた」ということを強調し、言うなれば「(純)文学」の方は「選民主義」的だという批判を匂わせている。「文学」は「わかる者にだけわかればいいのだ」という「差別主義」であるが、星新一や「幅広くノンジャンルで本を読んでいる私(浅羽通明)」は、そんな「差別主義者」ではない、とそう言いたいのだ。
しかし、何度も書いているように、星新一が「多くの人を楽しませなければ、小説ではない」と考えたのは、所詮、自分の小説が、そのようなタイプであったからにすぎない。つまり、自分の作品の価値を高らしめるために「そのような小説こそが、真の小説だ」と言っているに過ぎないのである。
だが、「文学」というものは、「娯楽小説」だけでもなければ、「小説」に限定されるものでもない。「俳句」や「文芸評論」のように、ほとんど商品にならない「文学」ジャンルも、事実として存在する。言い換えれば「一般受けすること=売れること」だけが「文学」の価値ではないのである。
しかしまた、「自己中心的」に「視野狭窄」になっている、星新一や浅羽通明は、「自分の視点」から「文学」と「小説」を同一視し、「小説」と「娯楽商品」を同一視して、「小説は売れてなんぼ」だなどと言っているに過ぎないのだ。
また、上の引用部後段の「多くの人を対象にするからこそ、普遍的なテーマを扱うことになり、普遍的で高い価値を持つ小説を書くことになる」という理屈も、所詮は「読めない読者」向けのペテンでしかない。
当然のことながら「幅広い読者層」を想定して、その「すべての人に理解してもらえる作品」を書こうとすれば、「誰でも知っていること」しか書けないというのは、理の当然である。つまり、「研ぎ澄まされて先鋭なもの」というのは、そこが理解できる人にはたまらない魅力を持つのだが、理解できない人を多く出すことになる。
つまり、「幅広くすべての人に理解される作品」というのは「角を矯めた」(熱くも冷たくもない)ヌルい作品にならざるを得ず、自ずと「深い」真理になど届くことはなく、「向こう三軒両隣」的な狭い認識でも理解できる「普遍性のない作品」とならざるを得ないのである。
もちろん、こういう「ヌルい娯楽作品」にも存在価値はあるが「文章によって、世界と格闘すること」に「文学」の価値を見出す「文学ファン」は、そんな「離乳食」のような作品には飽き足らなくなり、いずれそうしたものを「卒業していく」というのも、残念ながら「必然的なこと」だろう。
つまり、いつまでも「星新一」作品のような「誰でもわかる作品」だけ読んでいるような読者は、人間として(読書家として)、一向に「深まらない」ということだ。
『 多様な読者を意識しての創作。
そのとき、日常生活においてはその人に生きにくさをもたらすであろう発達障害、アスペルガー症候群(自閉症スペクトラム)的な性格が、かけがえのないほど有利な気質となったでしょう。
健常者ならば何も意識せず、ごく自然に空気を読んで伝えてゆけるコミニケーションが、そうした気質の者には、それが相手に通じるか否かいつもいつも迷いつつ試みるいのちがけの飛躍、はて知れぬ試行錯誤の連続なのですから。』
(P 397〜398)
これは、星新一に仮託して、自分自身の「長所」を、世間に向けてアピールしているわけである。
『「シラカバ派」。これは、純粋まっすぐで清く正しく美しくを望む自分に照れてしまい、偽悪を気取ってしまう近代知識人の宿痾を、呉智英が諷した呼び名です。
筒井は、典型的なシラカバ派でした。彼の過剰にえぐい描写も、鬼畜系の露悪趣味も、形骸化した良識を撃たんがための挑発にすぎません。
その裏側には、「アルファルファ作戦」「わが良き狼」「秒読み」「わたしのグランパ」などを著した、初々しいヒューマニスト、エモくてさわやかな人情家筒井康隆がいるのですから。
この実態は、筒井が例えば寺山修司などと共に、中二病を重症化させた少年少女の知的アイドルにいかにふさわしいかを証しています。
なぜなら思春期に罹る知的中二病患者は、真性の鬼畜系となるわけではないからです(香山リカという人の軌跡はそのよき症例をなしています)。
要するに、小学生以来の優等生然とした自分を恥じる自意識ゆえに、知的ワルを気取ってみなくなっただけ。ダークもエログロも残酷も鬼畜も極悪もじつは、ヒューマンで優しく純粋な自分を防護するためのアリバイ作りなのでした。そうした心理メカニズムがそのまま重なる当代一のシラカバ派筒井康隆こそは、永遠の青春を生きる作家だったのです。
しかし星新一はそうではない。
(中略)
青春の作家は、醜悪な現実に対して、そのヒューマニズムゆえに立ち上がります。筒井康隆はディストピアへの反抗を描き、自らも断筆でポリコレに抗議し、文学者の反核声明に署名しました。
しかし大人からみたら、一文にもならぬ抗議などを企てる暇があったら、過酷な状況を奇禍として一儲けを企み、のし上がる途を考えたほうがいい。
星新一はそんな大人の作家でした。
青春が昂じた少年少女が、星新一を卒業してゆく理由がここにもありそうです。
(中略)
あれから四十年弱、停滞する経済下、格差拡大、ヘイトスピーチ等の台頭を迎え、老いた彼ら(※ ヒューマニストたち)は、そんな現実に対する知的武器が自分たちに欠けていたと気づかされます。
そんな彼らの多くは、筒井康隆の偽悪露悪の裏側をなしていたようなヒューマニズムへ帰還しようとしている。
しかし、そこから帰結する青春の反抗はやはりむなしく敗れるほかはないでしょう。
彼らが還るべきはむしろ、山本光雄が「凡俗醜悪な人生の活図」と呼んだイソップ的現実を踏まえて、たくましく利を得、サバイバルせんとする星新一の世界ではないでしょうか。
圧倒的現実を相手とする正義の闘いを本気で企てるつもりならば、状況につけこんで得た一儲け、のし上がるくらいの武器兵糧なくしては、勝ち目などないのですから。(P401〜403)
「文学」派であり「文壇における成功者」である筒井康隆への、「嫉妬心」を丸出しにした文章である。

要は「清く正しい自分に陶酔して、バカみたいに真正面から戦うな。もっと頭を働かして、うまく立ち回り、結果としての勝利を掴むのが、大人の知恵というものである」という理屈だが、これは山本夏彦や呉智英といった「保守主義者」に典型的な「現実主義者」アピールである。
しかしながら、これは、そのようにして「小狡く」立ち回り、結局は「体制の側」に付くことで「社会的な成功」を現に手に入れた者が言うから、その内容は卑しくても、一定の説得力を持つのである。したがって、「負け犬の遠吠え」ばかりしているような、浅羽通明が言うことではない。
だが、そんなことにも気がつかないのは、浅羽の思考が「自己完結」したものでしかなく、そうした「独り善がり」を見抜くであろう「他者」の存在を想定できない、薄っぺらいものでしかない、証左なのである。
ちなみに私は、最相葉月による星新一評伝のレビューで、実物の筒井康隆について、
『私の感想としては「なんだ、意外にヘタレだったな」というものであった。』
と書いたが、この「意外性」が、何に由来するものなのかが、よくわかった。
つまり、私は筒井康隆を「毒舌の闘争者」だと思っていたのに、「瞠目反・文学賞」公開選考会での筒井の「世間並み」の態度は、私の期待を裏切る、凡庸なものと感じられた。だが、この「なぜ、筒井康隆は、意外に世間並み(のヘタレ)」だったのかといえば、それは浅羽通明が言うとおり、筒井という人はもともと「毒舌の闘争家」なのではなく、それを意識的に演じていた「世間並みの、いい人」だった、ということなのであろう。
そのため、文章上の作られた「イメージ」と、「実物」との乖離が激しく、尖っている方が好きな私には、筒井康隆の「実物」は、完全に物足りなかった、というわけである。
ちなみに、私が、筒井のメタ・フィクション作品が好きなのも、浅羽の指摘どおり、筒井にも愛すべき「普通の文学者」の部分があったからだろう。つまり、筒井康隆は、私にとって「本質的に合わないタイプ」というわけではなかった、ということだ。

『 星新一が尊んだ幾つもの解釈ができる寓話とは、皆で解釈を出し合って議論して、その問題にかかわるあらゆる立ち位置、ステークホルダーを洗い出すことを促すツールなのです。
あらゆる立ち位置を慮る。それはいわゆるDD論(※ 「どっちもどっち」論。つまり、利口ぶっているだけの、責任を負わない第三者的批評)ではないかと非難する向きもありましょう。
しかし、ある思想や政策を支持して推進しようとする場合も、違う立場や相反する相手の者がどこにどれだけ居そうかをあらかじめおおまかにでも把握しておかないと、勝利はおぼつかない。
自分の周辺には与党に投票した人などひとりもいないのになぜあんな高い得票率であいつらが勝つんだという嘆きを、DD論や冷笑系を嫌う人びとから聴きます。それはむろん、全体をつかむ知を働かせるの怠り、自分の周囲だけを全体だと誤認したがためでしょう。
DD論は、高みに立って冷笑するためにも使えますが、異なるいろいろな立ち位置を理解して、全体的視野を獲得するきっかけともなるのです。』(P405〜406)
そもそも「責任を負う気のない者(主体的に闘う気のない者)」が「私なら、全体を見渡して、客観的に評価できますよ」などと言ったところで、そんなものは「保守主義者」によくあるように、所詮は「現状追認」にしか、つながらないだろう。
「左翼的」に「改革」によって「世の中を変える」大事業より、「現状追認」の方が、多くの場合、無難で「有利」に見えるというのは、当然のことだからである。
これは、保守主義者の元祖である、イギリス人思想家のエドマンド・バークからして同じで、彼が『フランス革命の省察』を書いて、「革命」の欠点ばかりをあげつらって批判し、イギリスに革命の火の手が及ばないようにした、その「保守主義」は、星新一の「ディック嫌い」「ニューウエーブSF嫌い」「サイバーパンクSF嫌い」と同様の、「既得権益保守主義」でしかないのだと理解できよう。
「改革」「革命」されてしまって、「自分の地位=既得権益」が相対化され、脅かされては困るから、とにかく「新しい波」や「冒険」を、無難に嫌うのである。

ちなみに、上の引用文後段の『自分の周りには与党に投票した人などひとりもいないのになぜあんな高い得票率であいつらが勝つんだという嘆きを、DD論や冷笑系を嫌う人びとから聴きます。それはむろん、全体をつかむ知を働かせるの怠り、自分の周囲だけを全体だと誤認したがためでしょう。』というのは、わざわざ「頭の悪い左翼」を引き合いに出して、「左翼は、頭が悪い」という、恣意的な印象操作をしているに過ぎない。
頭が悪いということであれば、浅羽通明と同じ「保守主義者」を名乗る「ネトウヨ」たちの方が、はるかに頭が悪いだろうし、浅羽通明自身、星新一に仮託して自分で語っているほどの「悲劇の不遇な才人」などではないのである。
『 このようにいささか都合のよい情報のみをセレクトして創り上げたきらいのある錬金術師像を援用しながら、星新一はSF作家という独特の立ち位置をアピールしてゆきます。』(P412)
これも、浅羽通明自身のことだ。
浅羽の論は、星新一のそれと同様に『いささか都合のよい情報のみをセレクトして創り上げたきらいのある』ものでしかない。
しかも、浅羽は、自身の立論が、実際的な根拠の薄弱な、「博識レトリック(「鬼面人を威す」見せびらかし)」に依存した「空中楼閣」でしかないことを半ば自覚していながら、それを恥じるのではなく、むしろ「どうだ、私の錬金術師さながらの、レトリック力は」と自慢してところが、きわめて不誠実でもあれば、悪質でもあると言えよう。
『 星新一が提示するSF作家と錬金術師の共通項は三つあります。
ひとつ。専門的な学問間の垣根を無視して奇想を生み出している。
ふたつめ。実利するよりも奇想空想の面白さを優先している。
最後の三つ目。治外法権的安全地帯で危険思想を含む奇想に没頭した。
これらです。まず、学問ジャンルの垣根を無視から考えてみましょう。
これは、あの金鉱脈という地質学や鉱山学の知識と、植物学、農学の発想を、勝手に重ね合わせてしまうような発想です。実用になるわけでもなく真理でもないですが、しゃれとしてはけっこうおもしろい。
SF作家もそうした発想が得意です。』(P412〜413)
またも、権威ある星新一に仮託しての「自己賛美」である。
しかし、本人も半ば自覚しているとおり、浅羽通明の根拠薄弱な立論は『しゃれとしてはけっこうおもしろい』レベルのものなのである。
『専門的な学問間の垣根を無視して奇想を生み出している。』なんてものは、ノンジャンルであれこれの作家や学者の名前を持ち出してくる、浅羽通明にこそぴったりな形容であろう。
『実利するよりも奇想空想の面白さを優先している。』というのも、「実利」に結びつかない「自身の芸風」の「自己正当化・自己賛美」に過ぎない。
『治外法権的安全地帯で危険思想を含む奇想に没頭した。』というのは、業界的に不遇であり、業界的には注目されないからこそ、勝手なことが書けていることの、後付けの正当化に過ぎない。
『 さて、このSFに関する両極的見解、いかなる分野とも接触できる点を喜ぶ小松左京と、あらゆる分野から距離をおける点を重んじる星新一とは、ようするに同じことをいっているとはいえないでしょうか。
すなわちどちらも、SF作家の発想が、特定のどの分野にも属してしまわないところで尊んでいるのですから。
異なる分野の発想をジャンルの垣根を越えて結びつけるには、稀代の百科全書的知性小松左京ほどではなくとも、諸分野についてある程度の知識は必要でしょう。
しかし、そうではあっても、星新一ほどきまぐれで軽やかではないにしろ、ある分野を自分の専門だとして固執しはしない距離感もまた不可欠なはずです。』(P414〜415)
これも自慢話である。
「私は、小松左京と星新一の中間を行く、特定ジャンルに縛られない、自由人である」と言いたいわけだ。
『 あらゆる専門分野から等距離を置く時点で、アナロジーの妙、異質なものの組み合わせのおもしろさが生じ、さまざまな「奇想」が湧きあがってくる。』(P418)
これも「自分語り」であるのは、もはや言うまでもない。
だが、「根拠薄弱な思いつき」を「奇想」などと大仰に呼ぶのは、傍目にも恥ずかしいので、是非とも自制していただきたいものである。
『 これもある意味、「歴史に大きく名を残す」という実利を捨てたといえなくもない。
星新一自身は、SF作家として生きる幸福とひきかえに実利を何か捨てたのでしょうか。
特許の案を持っていると書いていますが、ダブル・ミリオンセラー二冊という長者作家の収入を超えるほどの発明かどうかはわかりません。
星新一が、奇想に生きる代わりに諦めた実利。それはあの「文学的評価」だったのではないでしょうか。SFであり通すために、あらゆる分野から一定の距離をおく。その「分野」には文学すら含まれていたのです。』(P420〜421)
「小器用な、なんでも屋」でしかない自分が「歴史に大きく名を残す」ことなど、もうないだろうから、それなら自分から「実利を捨てた」ということにしておくと、格好もつくだろう、というだけの、ケチな話である。
『 あらゆる専門分野を超え相対化してゆくSFの初心のみを結晶化した星作品は、ジャンル化したSFをすら突きぬけてしまっていたのかもしれません。
最相葉月の評伝には、「ぼくは星雲賞もらえないの?」と「宇宙塵」主催者柴野拓実に問い、「ブラッドベリもヒューゴー賞もらってないよ」となぐさめられる会話が採集されています。
例によって最相はかつて自らが開拓したジャンルの隆盛と流行から取り残されてしまった先駆者の悲劇をここに見ています。
だが、はたしてそうか。
錬金術師やケプラーに自らを重ねた若き日の自負を思えば、むしろここからは、一専門分野へと堕しかねない岐路へさしかかった日本SFへの反語的警鐘を汲みとるべきかもしれない。
エンタメ文学として物語性を蓄え、前衛文学としてニューウェーブやディック再評価を追い風として、文学のサブジャンルとしての体制を確立しつつあった日本SF。
そこにはトンデモ本や科学的奇想のいかがわしさや楽しさとお隣さんだったころのバイタリティは見失われつつありました。』(P422〜423)
これも「無理筋の抗弁」である。
それでは、星新一は「SF界に警鐘を鳴らすため」に、ディックやニューウエーブSFやサイバーパンクSFに、わざわざ「難癖をつけた」とでも言うのだろうか? だとすれば、星新一とは、なんと身勝手で傍迷惑な人だったのか。
だが、そうではないだろう。
星新一は、他者の「新しい可能性に賭ける夢」には思い及ばず、単に「自分のわからないもの=面白いと思えないもの」に、自分の「フィールド」を侵されるのを嫌って、「心底からの否定評価を語った」自己中心的な正直者の「保守主義者」であったに過ぎないのである。そう考える方が、よほど「現実的」な人間理解なのだ。
○ ○ ○
以上、細々とツッコミを入れてきたが、ツッコミの入れどころは、他にも山ほどあった。
だが、そんな「すでにわかりきったこと」を繰り返し読まされる方も「面倒」だろうし、私自身も「面倒」なので、これくらいに抑えておいた。
ここまで書けば、浅羽通明が「つまらない保守主義評論家」であり、本書が「星新一はアスペルガーであった」という指摘以外は、特に見るべきところのない「星作品解説書」であったことがご理解いただけよう。

しかし、この程度の「評論書」を読んで、その欠点に気づくこともなく「星新一論の決定版」だなどと評価してしまうような「読めない読者」が少なくない(むしろ、多い)という事実は、それこそが、星新一の意識した「一般読者」の実態を明かすものに他ならない。そんな読者に、「文学」など理解できないのは、理の当然なのだ。
周知のとおり、シオドア・スタージョンには、
「SFの90パーセントはクズである。──ただし、あらゆるものの90パーセントはクズである」
という有名な言葉があるが、言うまでもなく「読者の90パーセントはクズ」なのだから、そんな読者のすべてに伝わるようなものを書こうとすれば、自ずと「敷居を(際限なく)低くする」しかなく、「文学」的に「書きたいことを書く」という全力投球の「死闘」も、おのずと不可能になってしまうだろう。いや、すでにそうなっているのである。
ともあれ、星新一も、この程度の評論家に「理解者ヅラ」されているようでは、金輪際、浮かばれないのではないだろうか。
(2022年4月7日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
