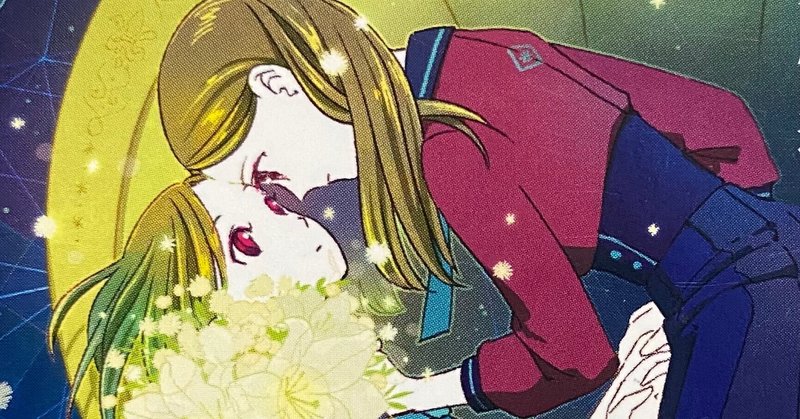
『アステリズムに花束を 百合SFアンソロジー』 : 造反百合は有利であるか?
書評:SFマガジン編集部編『アステリズムに花束を 百合SFアンソロジー』(ハヤカワ文庫)
2019年の刊行だから、もう4年も経つのかと驚きである。
本書を読むのが今ごろになったのは、もちろん「百合SF」なるものに、まったく興味がなかったからだ。というか「百合」自体に興味がない。私は「美少年趣味」の持ち主であって、しかし「BL」にも興味がないし、ましてジャニーズ系の実在少年に興味があるわけでもない。あくまでも、文学作品やマンガなどに登場する、特殊な美少年に惹かれるということであり、「特殊な」という限定は、ただ「美しい少年」という描写がされていれば良いというものではなく、「美少年」という特殊な属性を持っている少年でなければならないからである。

では『「美少年」という特殊な属性』とは何かということだが、これはそういう趣味を持っていない人に対しては、きわめて説明の難しいものだし、このレビューで語られるべきは、「美少年趣味」ではなく、「百合趣味」の方なので、「美少年趣味」の詳しい説明は割愛させていただき、もっぱら「百合趣味」というものを語るにおいて、その比較対照物として、必要な範囲で語ることになるだろう。要は、なんで私には「百合趣味」が無いのかということを語る中で、「美少年趣味」についても、多少は言及することになるかも知れない、ということである。
今は、というよりも、このアンソロジーが刊行された当時は「百合ブーム」だったようだ。それが今でもそのまま続いているのかどうかは、その趣味のない私には正確なところはわかりかねる。ただ、当時よりは落ち着いているように感じるのだが、いかがだろうか?
このように感じるのは、退職後、書店に行く機会がめっきり減り、その種の言葉を目にする機会が減ったということとともに、私個人の考えでは「百合趣味」というのは、「ロリコン」や「BL」に比べると、現実との関わりが薄すぎて、一般への伝搬力や定着力が弱いからではないかと考える。
「ロリコン」というのは、簡単に言えば「大人の女の性というものに恐れをなした、奥手の若者(男性)が、自分が優位に立てる異性として、幼い女である少女を、性的な対象として観念したもの」ということになると思う。
つまり、性体験が乏しさによる、異性との性的な付き合いに対する自信の無さと、それへの欲望の強さを比較した場合、前者の方が強い、要は「変にプライドが高い、頭でっかちの若い男性」が、自分のプライドを傷つけないで付き合える異性として、性的に未熟な「少女=幼女」を、自分が優位に立てる存在、安心して向き合える性的な存在としてイメージしたのではないか、ということだ。

一方「BL(ボーイズ・ラブ)」はどうかというと、これは「男に欲望される対象としての女」という、暗黙の社会規範的なものに疲れた女性が、自分が「欲望する側」になろうとしたものだと言えるだろう。
その場合、その女性は、自身を「男」の側に措き、そして、その欲望の対象さえもが「男」であれば、そこには現実世界における「男女」の、支配被支配関係が消えて「対等の愛」ということになるから、「男同士の愛や性愛」が最も「自由」で「純粋」なものとして、彼女たちには観念されたのではないだろうか。

では、「百合」はどうなるのであろう?
私が考えるに、男性の「ロリコン」、女性に「BL」に共通しているのは、どちらにも「社会的な支配被支配関係」が生き残っているという点である。
「ロリコン」の場合は、弱まった男性の(女性に対する)支配性を温存したいという欲望があり、一方「BL」の方には、現実社会での、女性の被支配性から逃れたいという欲望がある。つまり、どちらも「現実の支配被支配関係」をめぐる葛藤が、そこに隠されてきたのだが、「現実の支配被支配関係」が社会的に弱まってくると、もうそうした「権力闘争」からは降りて楽になりたいと思う者が、「女性同士の愛」である「百合」という、比較的「害の無い」ように見えるものを、再発見した、ということなのではないだろうか。
もともと「支配される側の者(女性)同士の、社会的支配被支配から自由なところでおこなれる、擬似恋愛的なものとしての(女学校的な)憧れ」を、最も好ましい「恋愛」として再発見したのが「百合」だったのではないかと、私はそのような仮説を立てている。

そんなわけで、私にとって「百合趣味」とは、喩えていうならば「マシュマロ」のように「柔らかく甘い」ものである。「百合」を求める人というのは、そうした、「葛藤」を必要としないものとしての「百合」に惹かれているのではないかと思うのだ。
しかし、これは言い換えれば「歯ごたえがない」とか「甘ったるい」ということにもなってしまう。
「ロリコン」や「BL」には、現実世界の押し付けてくるものに対しての、やむに止まれぬ「抵抗」や「反発」や「逃避」という「苦さ」が、深く刻印されていたから、かえってそれは、一定の「強度」を持続することができたのではないか。そこに逃げ込まずにはいられない切迫感が、それらにはあったのではないか。一一ところが、そうした「やむに止まれぬもの」が「百合趣味」にはない。
「百合趣味」とは、きわめて「趣味的」なものであり、観念的なものであって、実際のところ、現実の「女性同性愛(レズビアニズム)」とは、ほとんど無関係な、純粋なイメージの産物なのではないかと私は考える(この点では、BLに近いとは言えよう)。
だから「百合」は、女性だけではなく男性からも好まれることになる。「百合趣味」とは、高度に観念的なものであり、もはや現実社会とのつながりを失ったものだから、誰にでも選びうるし、逃避先でもなくなってしまう。それでなければならない、そこしかないという必然性や切迫性が薄いから、誰にでも選べる反面、簡単に捨ててしまうこともできる、軽い「趣味的なもの」でしかないのである。
一一というのが、ここでの私の仮説だ。
「仮説」だというのは、私はそれらに対して、それほど興味も思い入れもないから、自分の見方にこだわるつもりはないし、間違っていても、訂正すれば済むことだという程度のものでしかないからであろう。
そして、その上で、おまけとして言うならば、私の「美少年趣味」には、それらにはない「毒」がある、ということであろう。
○ ○ ○
そんなわけで、本書『アステリズムに花束を 百合SFアンソロジー』である。(※ 以下『アステリズムに花束を』と略記)

本書は、『SFマガジン』誌の「百合SF特集号」(2019年2月号)掲載作品に、いくつかの書き下ろし作品を加えたアンソロジーである。
ちなみに、『SFマガジン』誌は、2021年2月号でも「百合特集」をやっているが、私は興味がなかったので、本稿を書くためのネット検索をするまで、その存在を知らなかった。これは前回から2年ぶりの特集ということだから、「百合ブーム」が順調に続いているなら、今年中か来年早々にも、3回目の「百合特集」がなされても不思議はないのだが、さてどうだろうか?


本書『アステリズムに花束を』収録作品は次のとおりである。
(1) キミノスケープ 宮澤伊織
(2) 四十九日恋文 森田季節
(3) ビロウトーク 今井哲也
(4) 幽世知能 草野原々
(5) 彼岸花 伴名練
(6) 月と怪物 南木義隆
(7) 海の双翼 櫻木みわ×麦原遼
(8) 色のない緑 陸秋槎/稲村文吾訳
(9)ツインスター・サイクロン・ランナウェイ 小川一水
私が本書を読むことにしたのは、(8)の陸秋槎「色のない緑」を同著者初の作品集『ガーンズバック変換』で読んで、とても感心したからである。
どのあたりに感心したのかというと、その「批評性」にであった。もともと、この人は「ミステリ作家」としてデビューした人であり、日本人でもなかったから、その意味では、日本のSF界においては「異人」的な存在であったため、SFというジャンルを自明視しないそのスタンスが、非常に貴重なものであり、面白いと思ったのだ。
だが、同作については『ガーンズバック変換』 のレビューに詳述しているので、ここではこれでやめておく。
そんなわけで、「百合SFには興味がない」でやめてしまうのではなく、そこからこんな傑作(「色のない緑」)も出てくるのだから、その初出本くらい読んでもいいのではないかと思い直して読んでみた、という次第である。
ではどうであったかというと、さすがは「百合」というだけあって、全体に気持ちよく読める作品が多い。言い換えれば、読者の期待に寄り添った作品が主流で、その点が少々、物足りないと言えば物足りなかった。
今回、再読はしなかった「色のない緑」を別にすると、当アンソロジーの中で、いちばん印象に残ったのは、草野原々の「幽世知能」で、この作品の特徴は、読んだ人ならわかると思うが、「百合」を逆手に取った「アンチ百合」小説とでも呼べる作品になっている点だ。
前に書いたとおり、「百合」作品が『「マシュマロ」のように「柔らかく甘い」』そして「白い」イメージなのだとすれば、本作は、そうしたものを期待する読者に対して、わざわざ「黒くて苦くて口溶けの悪いマシュマロ」を、読者の口に突っ込んでくるような、いささかサディスティックでさえある作品なのだ。だから、私は本作を「面白い」と思ったし、強く印象に残ったのである。

したがって、(7)陸秋槎「色のない緑」、(4)草野原々「幽世機能」、そして最後の(9)小川一水「ツインスター・サイクロン・ランナウェイ」を除く、残りの6作は、楽しく読めはしたけれども、すでに印象が薄れつつあるような佳作であると言えよう。
それらに共通するのは、まず「切なさ」であり「優しさ」であって、それは読者の期待に沿うものだと思う。
しかし、読み捨てにするには、それで十分ではあっても、そうした作品は「消費」されて終わり、でしかない。たしかに読者を楽しませることはできるが、読者に爪痕を残したり、読者の成長を促すような作品ではなく、その点で、私のような「消費としての読書」はしていない人間には、こうした作品は、まったく物足りない。
無論、世の中の大半は、大量生産大量消費の「単なる商品」でしかないのだから、そういうものだったとしても、それはそれで「あり」であり、そうとわかって書くのならいいのだけれど、しかし作者は、本当にそれで満足できるのだろうか。「気持ちよく読み捨てにされる作品」でかまわないと、本気で思っているのだろうか。
ちなみに、(9)の小川一水「ツインスター・サイクロン・ランナウェイ」を、その他の「百合」作品から除外したのは、この作品が「読み捨て作品ではない」からではない。
これはこれで「気持ちよく読み捨てにできる作品」ではあるのだけれど、ただ、その他の6作品とは違って、「百合」読者の多くが求める「切なさ」や「優しさ」を描いてはおらず、作中人物の関係として「百合」を扱っている、ごく普通のSF活劇にすぎないからである。
「ハードSF」の書き手として評判の高い小川一水については、多少の興味は持っていたものの、私自身の「偏見」として、日本人の書く「ハードSF」には、あまり興味が持てなかったから、おのずと小川一水も読まなかった。昔読んだ「日本人のハードSF」が、小説としては、やや退屈だという印象があったせいだろうと思う。
で、今回初めて小川一水の作品を読んでみて驚かされたのは、そのモロに「ラノベ」なキャラクター描写であった。
ラノベを(初期の有名作以外は)ほとんど読んでいない私でも、主人公たちの姿が、即座に「アニメキャラ」として、はっきり立ち上がってきたのである。それは、私の場合、神坂一の『スレイヤーズ』のイラストを担当した、あらいずみるいが描くところのキャラクターと言うか、この原作小説を読んでいない私にとっては、アニメ版『スレイヤーズ』のキャラクターが、即座に浮かび上がってきたのである。

で、この、ハッキリと「絵」を見せてしまう描写力は大変なものであり、「ラノベ」的だからといって、その価値を否定するものではない。こういう小説があり小説家がいても、それはまったく結構なことだと思う。
さらにこの作家の描写力は、ハードSF的なアイデアを、理屈ではなく、生き生きとした「動画」として見せるところが、並大抵のものではないと感心し、なるほど「ラノベ出身のハードSF作家」だと感心させられてのである。一一ただし、やっぱりこの作品で描かれたものは、「百合趣味」の中心的なもの(切なさや優しさ)ではない、とは思ったのだ。

そんなわけで、当アンソロジーは、「百合SF」の長所も短所もその可能性も、すべて見せてくれるという点では面白く読むことができた。
だが、私が「例外的」と見た3作品を除くと、いわゆる「百合小説らしい百合小説」というのは、いかにも狭すぎて、その限界が見えているように思う。端的に言って、これではこの先「似たような作品の再生産」にしかならないのではないか。
それでも、「似たようなもの」ばかりを求めるのが大衆的読者だとは言え、これだけ「狭い」と、早晩飽きられてしまうしかないのではないかと私には思えたのである。
もちろん、以上は「大きなお世話」でしかないから、耳を貸す必要など、さらさらない。
(2023年9月8日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
