
R. D. レイン 『自己と他者』 : むしろ今日的な精神病理論
書評:R.D.レイン『自己と他者』(みすず書房)
『R.D.レインは、1960年代から70年代にかけて精神医学界に旋風を巻き起こした人だ。日本でも、「引き裂かれた自己」、「自己と他者」、「狂気と家族」などの著書が翻訳・紹介され、精神病理学の世界に一定の影響を及ぼした。その基本的なスタンスは、分裂病(統合失調症)に典型的な精神病の患者を、社会から隔離するのではなく、むしろ社会の中で、人間関係にかかわらせることを通じて治療すべきだと主張することにある。何故なら、精神病とは人間関係によって引き起こされる病だ、というのである。』
(壺齋散人(引地博信)・サイト『知の快楽』、「自己と他者:R.D.レインの反精神医学」)
精神病、中でも統合失調症(旧称・精神分裂病)に興味がある人なら、誰でも耳にしたことのあるのが、R.D.レインであり、その著書である『引き裂かれた自己』や本書『自己と他者』であろう。斯様に本書は、古典的名著なのである。

したがって、レインのこの2著は、ずいぶん昔から読みたいと思っていた。だが、翻訳書の版元がみすず書房で、例によってお高い本だったので、古本で安く手に入った時でいいやと思っていたら、やっとこのたび入手できたのが、本書の方であった、という次第である。
230ページほどの、この薄目の訳書は、「1975年9月25日 第1刷」の刊行で、私が読んだのは「2003年1月30日 第23刷」。その「第23刷」の定価が2900円なのだから、古典的名著として読み継がれているというのも、お高い本だというのも、ともに了解いただけよう。
ちなみに、Amazonでチェックしたかぎりでは、『引き裂かれた自己』の方は2017年に「ちくま学芸文庫」に入っているが、本書の方は「版元品切れ」のようである(したがって、古本でしか手に入らない)。
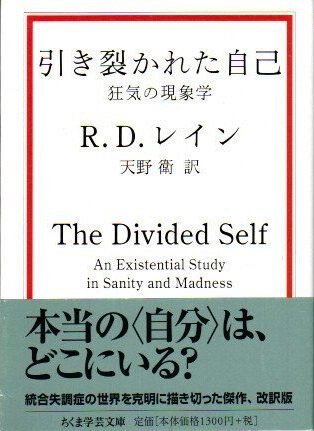
さて、いつものように、著者レインの紹介や、本書の「あらすじ」的な部分は、他の人の要約文の引用で済ませて、私は個人的に興味を惹かれたところについて書こうと、ネット検索をしてみたところ、さすがは古典的名著だけあって、非常にきちんとした紹介文が、すでに存在しており、これを読んでもらえば「あとはもう、何も付け加えることがないや」と思ったのが、本稿冒頭に、その冒頭部を引用させていただいた、壺齋散人(引地博信)氏によるレビュー「自己と他者:R.D.レインの反精神医学」である。
したがって、レインと本書の基本的なところを知りたい方は、ぜひそちらをご参照いただきたい。じつによくまとまった文章である。
で、他に関連するところでは、かのサイト「松岡正剛の千夜千冊」が、レインの自伝『レイン・わが半生』 を採り上げており、レインの理論ではなく、レイン個人のことを知りたいむきには、便利な紹介となっている。
下のようなところからも、気になる人は少なくないのではないだろうか。
『 レインやクーパーの「反精神医学」には、まずサルトルが反応し、ついでドゥルーズやガタリが賛意を示した。レインが精神をどんな器官にも限定せず、どんな機能障害にもあてはめようとしなかったことが、気にいったのだ。またフーコーは、レインが患者を病院から解放しようとしたことにエールをおくった。』
それにしても、レインを取り上げるのに、なぜ『引き裂かれた自己』や本書『自己と他者』ではなかったのかと疑問にも思うが、もしかすると、この代表的二著には、すでに、壺齋散人(引地博信)氏のそれをはじめとした、優れた先行紹介があったので、さすがの松岡正剛も、内容の重複を避けた結果なのかも知れない(要は、ネット上によくある「パクリ」と間違われたくなかったのではないか、ということだ)。
さて、上の二つの文章に書かれたことを避けるだけで、もう私に書けることなど極めて限定的になってしまうので、ここでは話を、ぐっと最近の、身近な話題に引きつけて、私なりに論じてみたい。
一一そんなわけで、本稿のテーマは「ネット社会における承認欲求」である。
○ ○ ○
レインの「反精神医学」運動という「精神病者の隔離収容主義治療への反対」運動は、
『こうした(※ レインの)スタンスの背景には、彼独自の人間観がある。人間というものは、当たり前のことであるが、他の人間とのかかわりあいを通じて、人間としての自己を作り上げていく。西洋の哲学的な伝統が考えているような、まず自己というものがあって、対象的世界があると考えるのは間違いだ。そのような考え方においては、自分とは異なった他の人間も、対象的世界の一つの要素に過ぎなくなってしまう。しかし、実際にはそうではない。人間というものは、他者とのかかわりがなければ、人間となることができないのである。他者とのかかわりあいを通じて、そこからまず、他者の存在を理解するようになり、それとの反照的な関係において、自分の存在を了解していく。人間は、このような他者との強いかかわりあいを通じて、人間となっていく。そうレインは考えるわけなのである。』
と、壺齋散人(引地博信)氏が説明するとおりで、レインの『分裂病(統合失調症)に典型的な精神病』についての考え方も、それに発する「反精神分析」運動も、こうした「人間観」に発したものだと言えるだろう。本書『自己と他者』が、
『これは対人関係論の書である。』(「訳者あとがき」)
と紹介される所以である。
それにしても、私たち日本人にとっては、精神病の多くが「対人関係」に由来するものだというレインの主張は、ある意味で「当たり前」な話にしか聞こえないが、壺齋散人(引地博信)氏も書いているとおりで、精神医学界を含めた当時の西欧世界においては、これは決して、当たり前ではなかった、からである。
ならば、「対人関係論」的なレイン理論を、今日、日本で読む意味などないのではないかと思う人もいるだろうが、そうではない。「訳者あとがき」でも強調されているとおり、本書は、「対人関係論」だとは言っても、そこらにあるような「ハウツー本」とは訳が違って、じつに犀利なものであり、レインの論述についていくのも、なかなか大変だ。
特に、本書冒頭部分は、彼の理論の結論部分が要約的に紹介されているので、とても難しい。だが、そこをわからないなりに読み進めていけば、途中からは、症例分析などの具体例が示されていくから、最後まで読めば、大筋のところで本書を理解することは可能であろうし、そこに学ぶべきこともある。
以前にレビューを書いた、スザンナ・キャラハンのノンフィクション『なりすまし 正気と狂気を揺るがす、精神病院潜入実験』では、レインらの「反精神医学」運動が盛り上がった当時のアメリカで、精神病院内部の惨状を暴くために行われた、精神科医デイヴィッド・ローゼンハンの指揮による「精神病院潜入実験」の実情を紹介していた。
ローゼンハンの実験とは、複数の精神病院に偽患者(スパイ)を送り込んで、病院内部の非人道的な惨状を暴いたもので、これが強く世論を喚起して、アメリカの地から隔離治療のための精神病院を一掃するほどの影響を与えた。また、その成果によって、ローゼンハンはアメリカの精神医学界の重鎮にもなった訳だが、その実験が「どうも怪しい」ということで、調査検証を行った結果を記したのが、スザンナ・キャラハンのノンフィクション『なりすまし』であった。

まあ、それはそれとして、こうして患者の隔離を目的としたのような精神病院が一掃された結果、アメリカでは精神分析が大きな存在となる。
一昔前のアメリカ映画などでは、何かというと、登場人物が精神科医のカウンセリングを受けるというシーンがあったのだが、要は、アメリカでは精神分析が、この時は「一人勝ち」したのである。
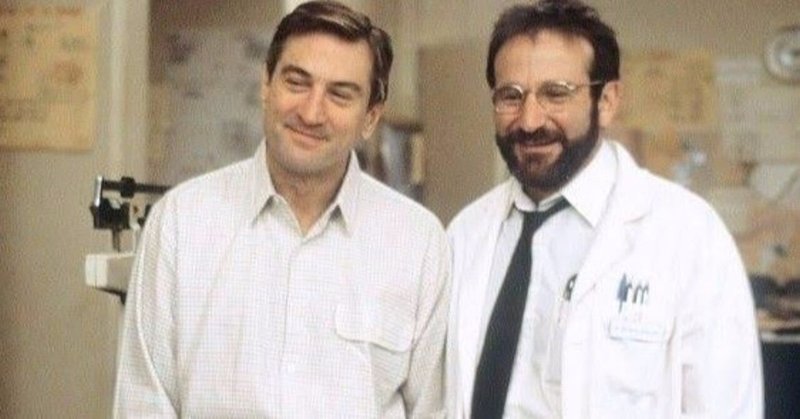
ところが、そんな「精神分析大国」となったアメリカで、今度は90年代に「虚偽記憶」問題が勃発する。
これもよく聞いた話だが、統合失調症などの精神病を病んだ(主に)女性が、精神分析治療を受けた結果、子供の頃に親から性的虐待を受けたという「抑圧されていた記憶」を回復させ、親が刑事告訴される、というショッキングな事件が多発したのだ。
ところが、あまりにも類似の事例が多かったために、その記憶の信憑性が疑われはじめ、よくよく調べてみると、分析治療の過程で誘導的にでっち上げられたも同然の「偽の記憶」だったという事例が少なからず確認された。実の娘に告発されていた親たちが次々と無罪判決を受けて名誉を回復するに至って、アメリカの精神分析界は信用を失墜させ、致命的な打撃を受けることになる。
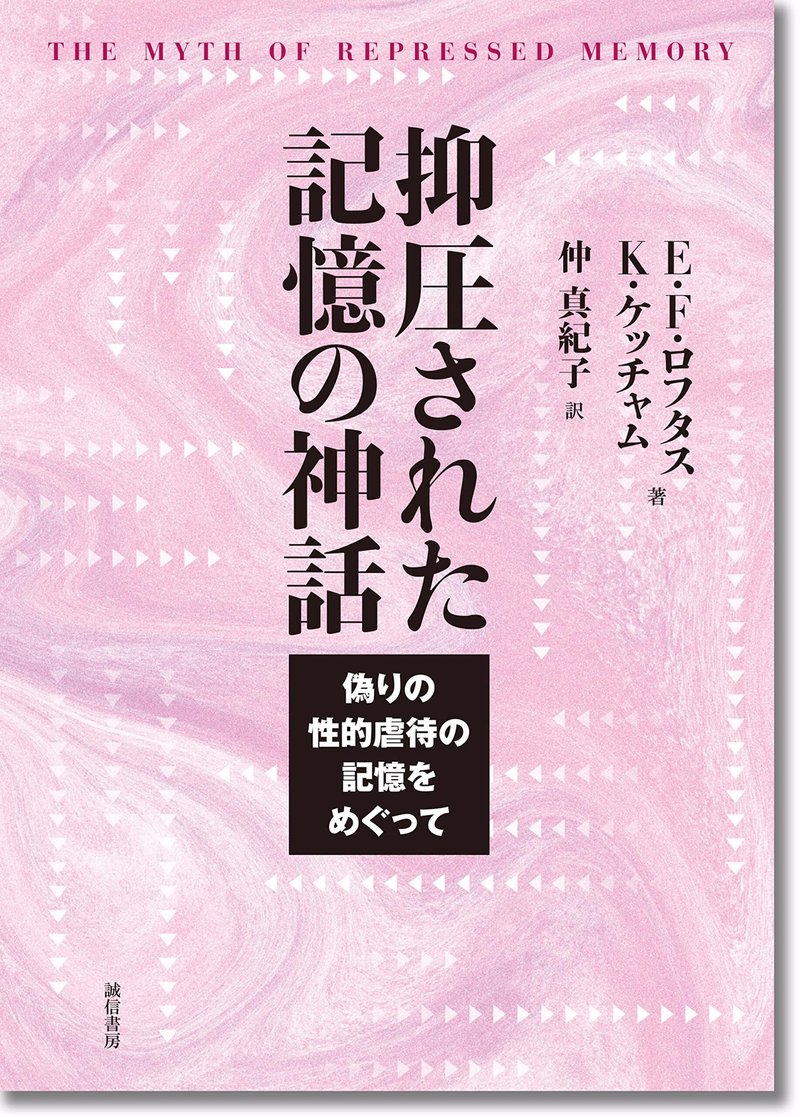
その結果、しばしば語られるようになったのが、「精神分析など、所詮はフィクションだ」「誰も無意識の存在なんて見たこともないし、確認のしようもない」「フロイトやユングなんて信用できない」「精神分析は、エセ科学だ」といった、いまだによく耳にする、「精神分析」不信論である。
で、そうなったアメリカでは、非人道的な隔離治療も時代錯誤で論外だが、「精神分析」も当てにならない、ということで、振り子はまた逆方向に触れて、次に重視されるようになったのは「科学的な薬物治療」であった。
要は、「精神分析」のような「文学的解釈学」などではなく、精神病を「脳の物理的(器質的)障害」ととらえて、それを「薬物で、物理的に治す」という方向に180度転換したのである。
そして、これが今では「精神病治療」の主流であり、当然、日本も右に倣った。
そのため今では、「薬物治療」は、ある程度「保険適用」となっているが、「精神分析治療」は保険適用外のまま。ただでさえ、治療に時間を要する「精神分析」は、今となっては、(他国は知らず、少なくとも日本では)たいへん高価で贅沢な治療法となってしまったのだ。
しかしである、「精神分析治療」に取って代わった「薬物治療」ではあったが、これが主流になると、それはまたそれで問題が出てくる。よく言われるのは「薬物の多剤大量処方に伴う過量服薬」問題だ。
薬物さえ与えておけば、ひとまず患者は「大人しくなる」。それに、薬を出せば出すほど「儲かる」のだから、医師は安易に薬物に頼るようになる。
それに、一度「隔離収容治療」の問題を経ているだけに、病者本人の意志に反する強制入院というのは、よほどのことがないかぎりは、「人権侵害」として認められないから、おのずと在宅治療や通院治療ということになって、患者の面倒をみる家族の負担も大きくなり、ここでもつい薬に頼ってしまうことになる。
つまり、現在の「精神病治療」の問題は、こうした制度的な「薬漬け」による、これもまた「非人間的な治療」になってしまっている点なのだ。
だからこそ、近年は「治療的グループワーク=グループワーク・カウンセリング」といった「精神分析」の流れを汲む治療法が、「人間らしい治療法」として注目を浴びることになった。
「グループワーク」とは、まさに「対人関係における実践的治療法」そのもの。こうした意味合いにおいて、レインの「対人関係論」的な精神病理論は、「むしろ今日的」と言っても良かろう。

もちろん、薬物治療を全面的に否定するわけではない。それも「重要な道具」のひとつとして適切に活用しつつ、しかし、治療の本筋は「人間的関係論」的な治療に置くべきではないか。
実際、「薬物治療」の問題は、「脳の物理的コントロールによる治癒」だけを目指したものだから、一時的な「軽快」(症状が軽くなること)は容易だが、その病を発症させるに至った「家庭環境」や「職場環境」などにおける「対人関係論的な原因」についてはノータッチとなるために、投薬をやめて社会復帰し、しばらくしたらまた再発、といったことを繰り返さざるを得なくなることも珍しくない。
したがって、「対人関係的な原因」によって「損なわれた脳」に対する「対処療法としての投薬治療」が必要であるとしても、それだけで終わってしまっては、不十分。やはり、発症の原因までつきとめ、そこへの対処改善を含む治療こそが、本当の意味での「精神病治療」と言えるのではないだろうか。
そうした意味で、レインの犀利な「対人関係論的精神病理論」は、今日でも決して無価値なものではないはずだ。
例えば、
『 すべての人間存在は、大人であれ子供であれ、意味、すなわち他人のなかでの場所を必要としているように思える。大人も子供も、他者の目の中での〈境地〉を求め、動く余地を与えるところの境地を求める。(略)自分のすることが誰にとっても重大なかかわりがない場合に、誰が自由を選択するだろうか。少なくともひとりの他者の世界のなかで、場所を占めたいというのは、普遍的な人間的欲求であるように思われる。』(P167)
要は、「承認欲求」の無い人間などいない、ということだ。
しかしながら、ネット社会を迎えた今日では、この「承認欲求」が、社会全般に肥大しているように感じるのは、私一人ではあるまい。
『 ある種の人々は、人間として認知されないということに対して、とりわけ敏感である。誰かがこの点できわめて敏感であるなら、彼らが、分裂病者と診断される見込みは大である。フロイトがヒステリー者について述べ、のちにフロム=ライヒマンが分裂病者についていわねばならなかったことだが、彼らは、たいていの人々よりも一層多くの愛情を与えたり受け取ったりする必要があるのである。これはあべこべにいうこともできるだろう。あなたがあまりに多くの〈愛情〉(※ 原注・〈愛情〉ならどんなものでも。)を与えたり受け取ったりする必要があれば、あなたには分裂病の診断をくだされる危険性が高いであろう。この診断は、あなたに、全般的に見て、大人のやり方で〈愛情〉与えたり受け取ったりする能力がないという烙印を押す。そしてあなたがそのような考えを一笑に付するなら、そのことが分裂病という診断を確定させるかもしれないのである。なぜならあなたは〈不適切な感情〉を呈するわけだから。』(P128)
つまり、少なくとも現代の「ネット社会」における「承認欲求」の過度の亢進状態というのは、言うなれば「一億総分裂病(統合失調症)」状態であると言えるのかもしれない。
無論、分母が大きいから症状は見えにくいものなのだが、少なくとも、かつての「健全な精神」の基準からすると、今の世の中は「狂っている」と見られても仕方ないの部分があるのではないか。
だから、そうした意味でも、私たちは、レインの「対人関係論的精神病理論」に学び直すべき部分があるはずで、それこそが「適切な感情(反応)」なのである。
『 そもそもインタビューにしろ記事にしろレビューにしろ、最近は全部が全部チョウチンとヨイショばっかりだ。どんなバンドもミュージシャンも、ことごとく誉めまくられてる。批評や評論じゃなくて、すべてはプロモーションでありPRになってるんだ。(略)
もちろんオレだって人の子だから、誉めてもらえば気分は悪くない。めちゃくちゃ露骨にけなされれば「この野郎」と頭にもくる。でも、「内容のない賞賛記事」と「内容のある批判記事」とだったら、後者の方がずっと好きだね。』
(忌野清志郎『ロックで独立する方法』新潮文庫・P133)
忌野清志郎のような人には、あからさまに見えていた、今の世の中の「気味悪さ」や「異常さ」に、まったく気づかない人というのは、たとえそれが「多数派」であったとしても、やはり「病んでいる」と考えるべきなのではないのか。
そしてそれは、私の指摘した、次のような事例でも、まったく同じことなのである。
○ ○ ○
(2022年11月10日)
○ ○ ○
○ ○ ○
