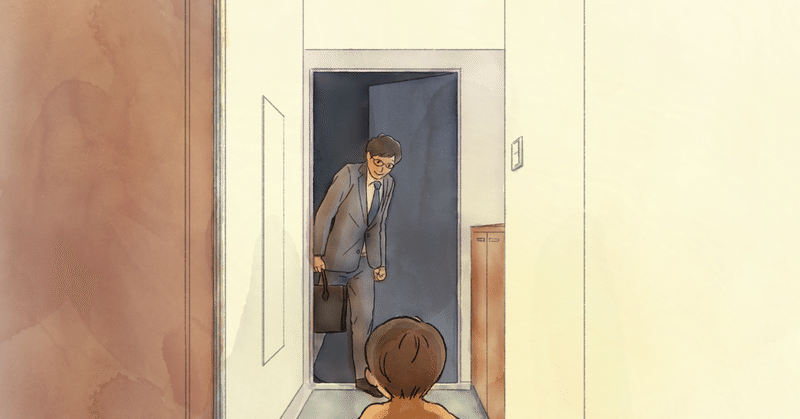#教育
心に留め置いている3つの教え「自分らしい視点」「巨人の肩の上の小人」「わたしを離れて去れ」 #大切にしている教え
お疲れさまです、uni'que若宮です。
日経COMEMOから「#大切にしている教え」というお題が出ておりましたので、今日は僕が大切にしている3つの教えについて書きたいと思います。
「お勉強ではなく、必ず自分らしい視点を付け加えること」僕の「大切にしている教え」は3つあります。思い返してみれば、これらはすべて大学で出会ったことばでした。
1つ目は、大学時代に恩師である美学者の佐々木健一さんに
動物の世界でも、弱者や敗者が生き残る道がしっかり残されていることが、近年わかってきました。
動物行動学の研究者で、生態科学研究機構 理事長の新宅広二氏は、2022年
2月25日、FBで下記の通り、記しておられます(ご本人の了解を得て、転記させていただきます)。
<仮定と現実>
1.家庭に問題があり、度を過ぎた暴力沙汰をくり返す児童がクラスに1人いたとする。
2.彼を除いた学級会で、彼とは話し合わず全員で無視することを決めたとする。もし彼とこっそり話した子がいたら、同類とみなし無視をする
私が「つまらなそう」と思っていた父の仕事
私は昔、父の仕事が不思議だった。
というよりも、正直今思い返すと恥ずかしい限りなのだが、はっきり言って「面白くなさそうな仕事だな」と思っていた。
父は地方公務員で町の役場勤めだった。
役所の仕事をよくもわかってもいない癖に私はなんとなく、その仕事は誰にでもできる簡単なものだと勝手に思い込んでいたのだ。
簡単というか、決められた仕事をこなすような作業ばかりだと想像していた。
私が私としてこの世に
自分「が」主語になると、不器用になる
最近どうしたわけか、教育系雑誌から取材をよく受ける。私が教育者というわけではなく、農業研究者であることを知ったうえで。なんとも不思議な気分。
たぶん、私の表現も悪かったのだろうけれど、取材を受け始めた当初、上がってきた原稿で気になる傾向があった。
「先生が~してあげる」「先生は~すべきである」「先生は~であるべきである」あるいは、先生が親に置き換わっていたり。これらの表現の何が気に入らないかとい
主体性は育むものではありません。
主体性を高める、主体性を育てる、主体性を身につける。
こういう言葉が普通に使われています。
でも、
そもそも主体性というのは健康に身体が動く赤ちゃんであれば、
誰でも持っていて行使しているものです。
(このイグアナだって主体的に動くと思います)
人は誰でも赤ちゃんでした。
つまり、主体性のない人間などいないはずなのです。
それなのに、主体的でない子どもや大人が日本にたくさんいるとしたら、
日本人に対する違和感
前から不思議に思っていたのは、なんで日本人は消費税が上がっても、モリカケ、桜の会にも怒らないのに、芸能人の不倫とか不祥事には気が狂ったように激怒するんだろうね?自分には関係ないのにね。世界でもめずらしい国民だろう。
芸能人の不祥事でアメリカやヨーロッパでも批判が起きることはあるけどごく一部で、全国で集中放火ということはない。日本は全国民から集中放火になる。まあマスコミの問題もあるんだろうけど、マ
「お兄さん、俺、プロになりたい」夢を抱いた少年に背中を見せた2年間と、意外な展開
大学1、2年生の2年間、近所の小学校で毎週末サッカーを教えていた。といっても、コーチという立場ではない。
当時、ぼくは暇があれば小学校のグラウンドへ行って、壁に向かってひとりでシュート練習をしていた。
いつものように練習に打ち込んでいたある日、サッカーチームの保護者の男性から、「良かったらお兄さんも、一緒にゲームに混じりませんか?」と誘われたのが、その少年たちとサッカーをするようになったきっか