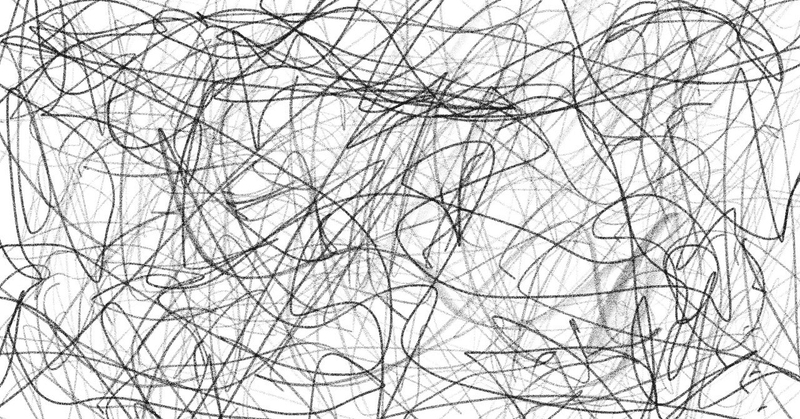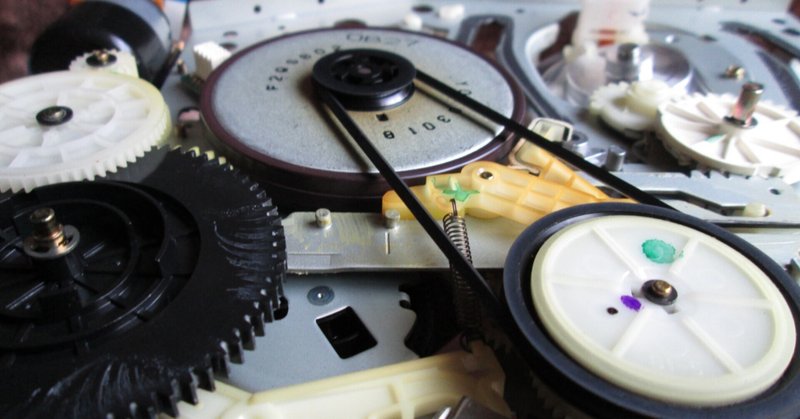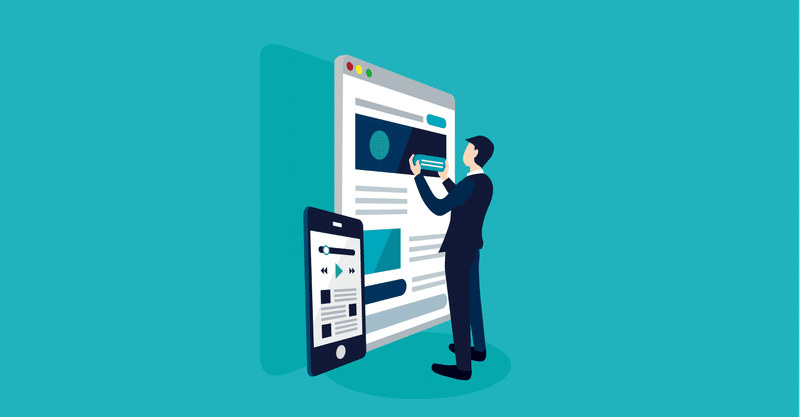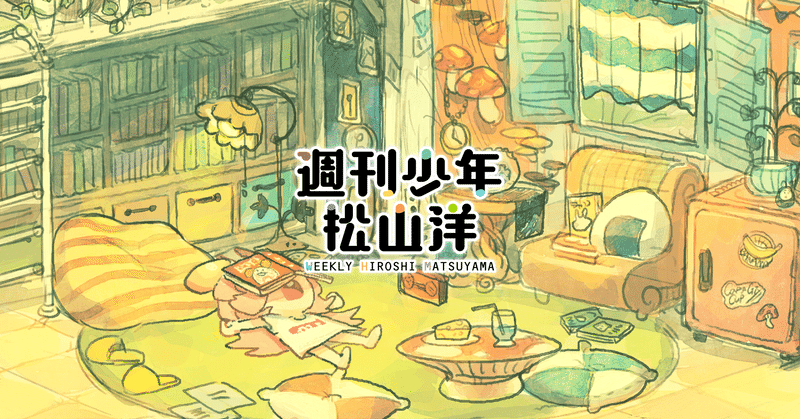- 運営しているクリエイター
#コラム
子どもに怒るのと叱るのは違うと考えるのは危険
少し前に話題になっていてネットで目にしました。子どもが何か問題行動をした時に
怒るは感情が入っているからダメで叱るはしつけだけだから良い
みたいな話でした。色々な議論がなされていましたが、私はこういう考えはとても危険だと感じています。なぜなら一番大切なことが抜け落ちているからです。それは、
子どもから見たらどっちも一緒
っと言うことです。怒られようが叱られようが子どもからしたら一緒ですよ。
人員配置替えのデザイン
いわゆる新年度が始まってひと月が経ちましたね。この春に転居されたという方もいらっしゃることでしょう。一年で最も引っ越しが多い時期が過ぎました。
入学や初就職を機に、という事例が真っ先に思い浮かびますが、それ以外にありがちな「季節的」の事例は、被雇用先での『異動』でしょうか。それをテーマにして記事を書き始めると膨大な内容となってしまいますので、今回は出来るだけ簡潔に表面の要件のみを、と思っていま
仕事への尊敬と成果を出すことへの期待で繋がっているチーム、侍ジャパンが羨ましい
私は永久管理職が牛耳っている組織にいるから、侍ジャパンを見て「若い」なのに「大人」で、羨ましいと思った。
打率が2割程度の村上選手に対し、私が見る限り「そのポディション、自分に譲れ」という選手はなく、チームメイトが打ってくれという期待と懇願の思いで見守っているように感じた。
侍ジャパンの四番、五番を「我こそは」と思う選手がいて、ここでレギュラーの座を奪おうと足を引っ張る選手がいても当然と思うにもか
たった一社だが存在した。ハラスメントのない風通しが良い職場
大学院生のとき、試験結果が出るまでの3週間だけ働きたくて、大手百貨店のお中元カウンターでのバイトを申し込んだ。人員募集を締め切ってはいたが、面接をしてくださることになった。当日、私は店長さんを見たときに、決まったと感じた。
「今は人が決まっていて募集してませんが、少し考えてハガキで返事をします。」
と言われ、2日後、採用通知がとどいた。
……………
全員が20才以上年上のおばちゃん達で初日から兎に
第272号『この世は儀式で出来ている』
これは別に宗教的な意味ではありません。
この場合の『儀式』は仕事上での儀式を指しています。
順にいきますね。
先日こんなことがありました。
*****
弊社内の新人スタッフの中に目まぐるしい成果を上げている人間がいて、それは周りもみんな実力を認めていて久しぶりに「アイツはいいね、これから間違いなくエースになるね」なんて言われるほどの実力者でした。
あまりにも能力が高くそして同年代の他の