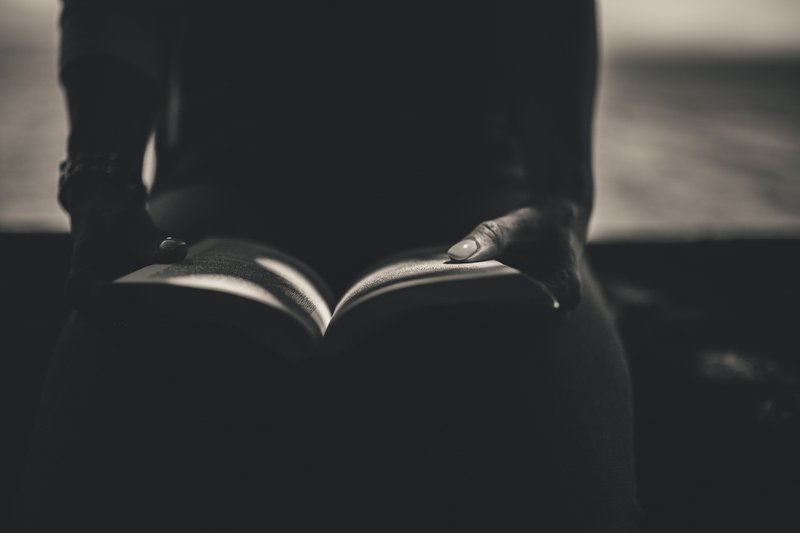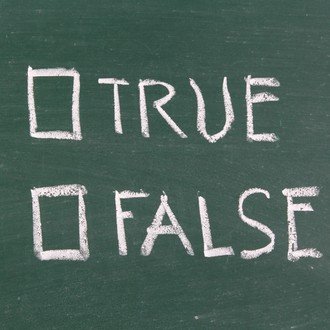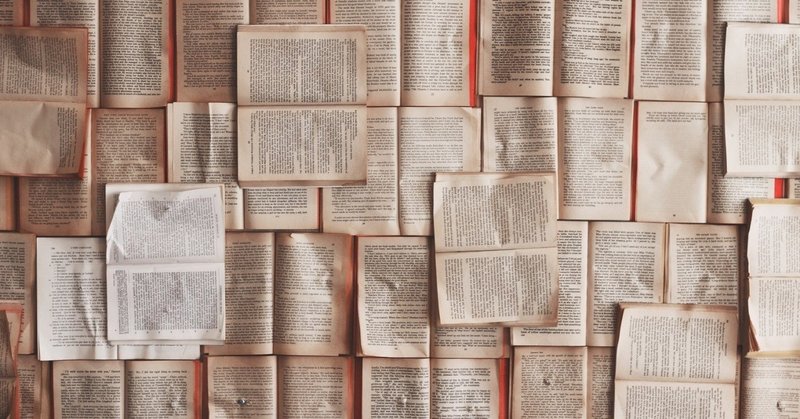#社会
『「いいね!」戦争』を読む(19)人間が「フェイク」化しつつある件
▼ロシアが、たとえば「トランプを熱烈に擁護するアメリカ人」のアカウントを捏造してきたことは、国際的な大問題になったから、すでによく知られるようになった。
筆者は『「いいね!」戦争 兵器化するソーシャルメディア』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」を読んで、2017年にツイッターに登場した「アンジー・ディクソン」という有名な女性女性が、〈ツイッターを侵食し、アメリカの政治対話をね
『「いいね!」戦争』を読む(18) SNSが「グローバルな疫病」を生んだ件
▼『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」では、人間の脳がSNSに、いわばハイジャックされている現状と論理が事細かに紹介されている。
▼その最も有名な例であり、その後の原型になった出来事が、2016年のアメリカ大統領選挙だった。それは、何より「金儲け」になった。本書では
「偽情報経済」(216頁)
という術語が使われているが、フランスでも、ドイツでも、スペイ
『「いいね!」戦争』を読む(17)SNSは「承認」が最大の目的の件
▼前号では、「フェイクニュース」という言葉が広まっただけでなく、「フェイクニュース」の「定義」そのものが変えられてしまったきっかけが、アメリカ大統領選挙であり、なかんずくトランプ氏の行動だったことに触れた。
「フェイクニュース」は、もともとの「真実でないことが検証可能なニュース」という意味から、「気に入らない情報を侮蔑(ぶべつ)する言葉」、つまり、「客観的」な言葉から、とても「主観的」な言葉に変
『「いいね!」戦争』を読む(16) 「フェイクニュース」誕生の論理
▼ここ数年、ネットの中で「嘘(うそ)」が蔓延(まんえん)するスピードが、やたら速くなった。
すでによく知られるようになったある常識について、『「いいね!」戦争』がわかりやすく説明していた。
ちなみに2019年7月10日の21時現在、まだカスタマーレビューは0件。
▼MIT(マサチューセッツ工科大学)のデータサイエンティストたちが、ツイッターの「噂の滝(ルーマー・カスケード)」(まだ真偽が検証
『「いいね!」戦争』を読む(15) 「アラブの春」が独裁に繋がった理由
▼「アラブの春」が、なぜ独裁主義に吸収されてしまったのか。『「いいね!」戦争』は、「確証バイアス」や「エコーチェンバー」現象などの知見を使って絵解きしている。
▼毎度おなじみ、カスタマーレビューはまだ0件だ。2019年7月10日10時現在。
▼以下の引用箇所を読めばわかるが、この経緯から引き出せる教訓は、「アラブの春」だけに限った話ではない。ジョージ・ワシントン大学公共外交・グローバルコミュニ
『「いいね!」戦争』を読む(14) 「確証バイアス」は脳の最悪の衝動の件
▼「インターネットと戦争と生活」について考えさせられる名著『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」は、人間の「脳」をめぐるネット戦略の中間報告になっている。
▼2019年7月8日現在で、まだカスタマーレビューは0件。0件のまま半月も経つと、なんだか面白くなってきた。
▼前回は、記事が真実であるかどうかは重要ではなく、「なじみがあるかどうか」で判断が分かれる、と
『「いいね!」戦争』を読む(13)記事は「真実」でなくても構わない件
▼今号で紹介するのは、「オンラインの生態学」とでもいうべきものだ。
『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」の続き。
▼前号は、最近よく目にする「フィルターバブル」と「エコーチェンバー」の簡単な解説だった。
▼ところで、『「いいね!」戦争』には、まだアマゾンでカスタマーレビューが1件もつかない。2019年7月7日現在。
▼先に「オンラインの生態学」と書いた
『「いいね!」戦争』を読む(12) 「友だち」の数ですべてが決まる件
▼人間には、仲間を求める本能がそなわっている。それが「ホモフィリー」(同質性)だ。前号では、この「ホモフィリー」が、SNSとのつきあい方を考えるキーワードであることにちょっとだけ触れた。
▼『「いいね!」戦争』では、この「ホモフィリー」(同質性)のくわしい仕組みを説明しているが、その説明の中に、さらに2つのキーワードが入り込んでいるので、一つずつチェックしていきたい。
2つのキーワードというの
山室信一氏の「モダン語」研究が「モダン=近代」を相対化する件
▼大きな本屋でしばしば無料で置いてあるので、無料だと思っていたのだが、じつはもともとは有料の情報誌がたくさんある。
岩波書店の「図書」もその一つで、今年(2019年)から始まった山室信一氏の連載「モダン語の地平から」が面白い。
山室氏は「視点」が抜群に鋭くて、近代史の研究者のなかで常に注目している人の一人。いまは「思想連鎖史」を専門としている。最も気軽に手に取れるのは『キメラ 満洲国の肖像』(
ブラウニング『普通の人びと』を読む 虐殺を正当化する論理
▼梅雨時に読むと気が滅入(めい)る本を紹介する。
クリストファー・R・ブラウニング氏の『増補 普通の人びと ホロコーストと第101警察予備大隊 』(谷喬夫訳、ちくま学芸文庫)。1600円+税。
▼それにしても、文庫本はずいぶん高くなった。映画1本と同じ値段である。しかし、出来上がるまでにかかった手間を考えると、本とはずいぶん安いものだ。
▼この本のテーマはとてもシンプルだ。それは、「普通の人
「依存症」は「否認」の病であり、「孤立」の病である件
▼2019年6月8日付の日本経済新聞に、「依存症」を知るための書評が載っていた。評者は松本俊彦氏。見出しは、
〈依存症は他人事ではない/孤立の病との視点が重要〉
筆者なりに一文に要約すると、
さまざまな依存症は「否認の病」であり、「孤立の病」でもある、
ということが書いてある。
▼書評の冒頭を引用する。適宜改行。
〈近年、有名芸能人の薬物事件が起こると報道が過熱しがちだ。ワイドショーは
「平成31年」雑感20 須賀敦子「古いハスのタネ」の続き
▼前回のつづき。
▼須賀敦子のエッセイ「古いハスのタネ」にあった、
散文は論理を離れるわけにはいかないから、
人々はそのことに疲れはて、
祈りの代用品として呪文を捜すことがあるかもしれない。
という一文は、「近代化」された社会の運命を物語っている。
現代の特徴の一つは、人類の歴史のなかで「文書」がこれほど強い権威を持つようになった時代はない。
▼「古いハスのタネ」は1995年の日本で
薬物依存は「病気」である件 フジテレビのタレントたちに学ぶ
■松本俊彦氏の指摘▼清原和博氏のことを書いたついでに、薬物依存に関心のある人は必読だと筆者が思うウェブサイトの記事を紹介しておく。
ちなみに、前回のメモはこちら。
▼きょう紹介するのは、松本俊彦氏の書いた「まちがいだらけの薬物依存症 乱用防止教育が生み出す偏見」だ。
この右上のマークは、薬物に関する「ダメ。ゼッタイ。」という有名なキャッチコピーそのものを使うべきではない、というメッセージで
「平成31年」雑感13 「無差別大量殺人」を忘れ去る国
▼きのうのつづき。
▼『教育激変』のなかで池上彰氏は、いくつかの大学で教えていて体験した、面白い話をしていた。
〈死刑執行後、講義を担当しているいくつかの大学で、オウム真理教について話をしたんですね。「選挙に候補者を立て、負けると自分たちの王国を建設しようとして過激な活動に走っていった」なんてことを言うと、学生たちは唖然(あぜん)、茫然(ぼうぜん)。要するに、なんにも知らないのです。〉
〈愛