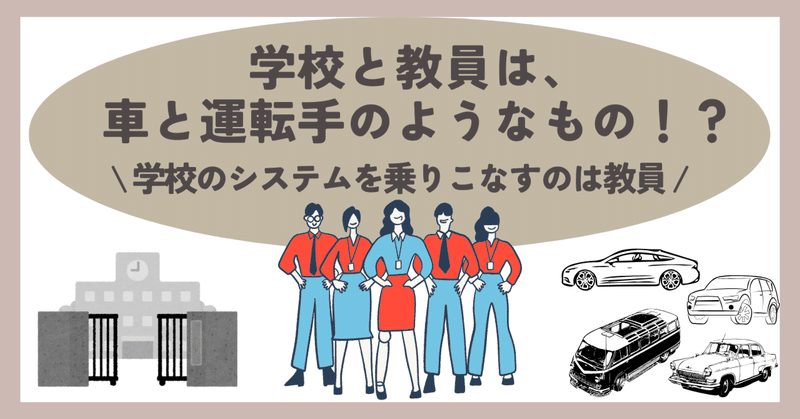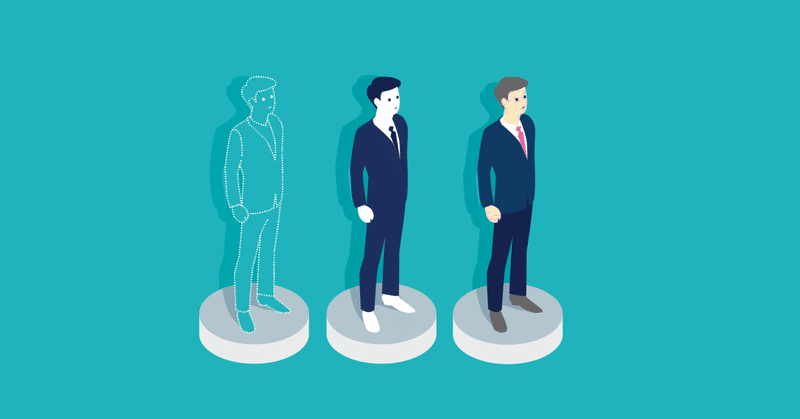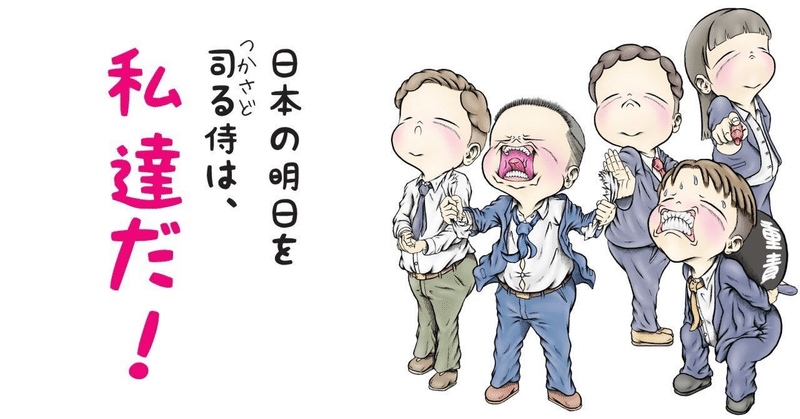#教育
小学校 より良く変えるタイミングは4月第1週!?
もうすぐ新年度ですね
小学校(学校関連勤務全般ですね)勤務の方々は、新年度人事からもろもろの準備、そして学年学級開きという怒涛の1週間が始まろうとしているかと思います。
何でうちの学校は変わらないんだ、もっとこうしたい、ああすればいいのに…
と思っている方々へ朗報です。
より良くしたい!を叶えやすいのは、この1週間!かもしれません!
もちろん、ある程度前年度までに決まっていることや、格子
学校と教員は、車と運転手のようなもの!?~学校のシステムを乗りこなすのは教員~
1.時代の変化と様々なシステム
戦後以来数十年の時を経て、変化の激しい時代であることが再び学習指導要領に明記されて早数年、学校現場の変化も大きいものとなってきました。
世の中はAIの台頭、日本で言えば人口減少や価値観の多様化がより顕著になり、それに伴ってか、様々な学校内の仕組みや教育方法がしばしば注目されてきています。
学校単位の枠組みで言えば、学校再編やカリキュラム・マネジメント
ChatGPTに「学年主任」について質問してみた
先程(2023年3月27早朝)、「学年主任」がTwitterのトレンド入りしていました。
※スクショは撮り損ねました
学年主任の仕事術や配慮すべきことなど、ツイートしてくださる方がたくさんいらっしゃり、ただすごいなぁと思うばかりです。
そんな中、ふっと興味が湧いたので
「学年主任」について、ChatGPTに質問してみました。
自分は小学校勤務が多かったので、今回は小学校の学年主任という設定に
われわれは、未来の世代に対する責任を果たしているか?(「2040年の日本」より)
少し批判的な表現が入ってしまうかもしれないですが、著者の思いの込められた表現を引用する上で失礼の無いようにしたい、そして自身への戒めも込めてという意図であると、ご理解いただければありがたいです。
今回は、野口悠紀雄「2040年の日本」 (幻冬舎新書 2023)で印象的な部分を引用し、少し思いの丈を述べます。
1 書籍&著者紹介
今回、引用させていただくのはこちらの書籍です。
https
磯津政明『2040 教育のミライ』(2022,実務教育出版)に学ぶ
刺さった書籍の読書記録&共有です。
磯津政明『2040 教育のミライ』(2022,実務教育出版)
まず、教育現場にいらっしゃる方にオススメします。現在の教育界を取り巻いている状況の広範囲をカバーしていると思います。
著者の磯津さん、「教育分野における独自のビジネス構想を実現させるため、2015年、ソニーグループ初の教育事業会社・株式会社ソニー・グローバルエデュケーション(SGE)を設立、代表取
世界を変えるのはいつも「新人」だが、大人たちが応援するのは「世界を変えない若者」
「古い世代の人たちに世界を変える力はない。世界を変えるのは、いつも『新人』なのだ」
トーマス・クーン『科学革命の構造』による結論です。
なかなか変わらない世の中…狭い世界で言えば町内会や職場、広く言えば政治や国々…ITイノベーションなどによる大きな変化がある一方、変わって欲しいのに変わらないものは多々あります。
自分がこのフレーズに出会ったのは、原著ではなく、瀧本哲史『ミライの授業』(講談
社会が学校に求める3つの目標と矛盾
すっかり期間が空いてしまいました。
しかしながら、この間にメインの仕事は区切りを迎えました。
同じ仕事をしていらっしゃる方々は、年度末のなんとも言えない貴重な時期かと思います。
組織のミドルリーダーやトップに近い方々は、引継ぎや次年度準備が山積み…という方々もいらっしゃるかもしれませんが…自分も「塩漬け」にしてきた仕事に手を付けています。終わる頃に新年度ですかね笑
今回は、読んでいた本の中で
「ニーズが多様化する学校」×専門職を配置する「チーム学校」=多忙化の促進??
学校のニーズが多様化していることは、教育関係者でなくてもご存知の方も多いかと思います。
学習面だけでなく、生徒指導面、特別な支援を要する子ども、そして近年では貧困の状況も芳しくないことも明らかになっています。
これらの課題を全て、現状の教員で賄うことはもちろん不可能に近いでしょう。
(もちろん、強靭な体力と精神力で、全力で現状に向き合っている方も多々いらっしゃいますが、それを全教員に強
結局プリント学習…オンライン授業実施の「難しさ」
ご無沙汰しております。お久しぶりの記事になりました。
コロナ禍ではありますが、やらねばならぬこと、やりたいと思うことは多々あり、調整すべきことも結構あります。
そして本業は年度末業務が佳境になりつつあります。
それでも以前よりかなり時間にゆとりをもてるようになりました。多少なりとも自身のスキルが向上したという面もあるかもしれませんが、「働き方改革」がゆっくりとですが、多少なりとも浸透してきた
子どもを育てることを何と捉えるか ~「子ども庁」から考える、子どもに関する施策体制のねじれ~
子ども庁の創設について、政府が当初想定していた2022年度から、23年度以降へと先送りされることが報道されました。
1 学校現場で実感する子どもに関する施策体制のねじれ
公立学校であっても私立学校であっても、基本は行政の管轄のもと、教育活動は行われます。学校現場で働いていると、(広い意味での)教育施策について、複雑に感じることがあります。
学校であれば、基本的には文部科学省の管轄で
教育の「不易」と「流行」を問う① ~「不易」の中身は?~
最近の問題意識です。
整理メインの記事ですので、それほど容量はないです^^;
(ぜひご意見いただければありがたいです)
1 教育の「不易」と「流行」が登場する場面
時々目にしたり、耳にしたりする、教育の「不易」と「流行」
どんな場面が考えられるでしょうか?
例えば、最近でいえば、GIGAスクール構想で一人一台タブレットが導入され、「ICT機器は現在の流行だが、教科書を使った学習に
「明るい不登校」を目指すこと
お久しぶり?に不登校関連の記事です。
昨今の多様性を受け入れようとする社会の流れの中で、不登校についての見方もずいぶん変わってきたように思います。
顕著なところでは、(結構前ですが)「登校拒否」から「不登校」へ呼称が変わっているところなど、わかりやすいですよね。
ただ、不登校を許容する社会の流れがある一方、不登校という選択をした場合、あるいは不登校の状態になった場合に、学校の代わりに子