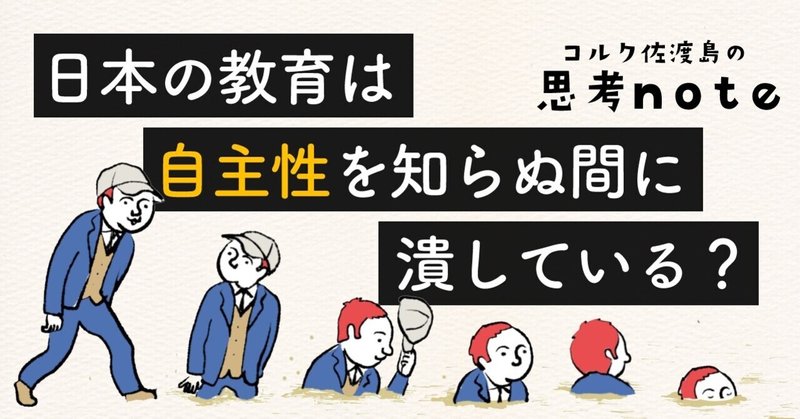#子育て
仕事と育児の共存 〜withworkweek@国際女性デー カンファレンスレポート〜
はじめに5日間のカンファレンスに際して
2022年3月7日~11日の5日間にわたってオンライン形式で開催されたDE&I推進カンファレンス「withworkweek@国際女性デー #キャリアとライフはトレードオフじゃない 」。10のテーマで開催されたカンファレンス、最終日の3月11日のお昼に開催されたセッション内容をレポート形式でお届けします。
・個人と経営双方の視点から仕事と育児の共存をどう実
業界の同質性〜withworkweek@国際女性デー カンファレンスレポート〜
はじめに5日間のカンファレンスに際して
2022年3月7日~11日の5日間にわたってオンライン形式で開催されたDE&I推進カンファレンス「withworkweek@国際女性デー #キャリアとライフはトレードオフじゃない 」。10のテーマで行ったセッションにおける4日目の3月10日の昼に開催されたセッション内容をレポート形式でお届けします。
・業界の同質性をどう捉えているか
・DE&I推進のための
日本人に対する違和感
前から不思議に思っていたのは、なんで日本人は消費税が上がっても、モリカケ、桜の会にも怒らないのに、芸能人の不倫とか不祥事には気が狂ったように激怒するんだろうね?自分には関係ないのにね。世界でもめずらしい国民だろう。
芸能人の不祥事でアメリカやヨーロッパでも批判が起きることはあるけどごく一部で、全国で集中放火ということはない。日本は全国民から集中放火になる。まあマスコミの問題もあるんだろうけど、マ
日本の教育は、”自主性”を知らぬ間に潰している?
「学ぶ」とは、何なのか?
いま、多くの人は「学ぶ」とは、知識を体系立てて吸収することだと思ってる。一方、先週のnoteで紹介した『易経』では、知識の習得は「学ぶ」とされていてない。未知の変化への向き合い方を身につけ、自ら行動していく自主性を育んでいくことが、「学ぶ」とされていた。
江戸や明治の知識人の多くは易経を学んでいた。ぼくらは維新の志士たちが、藩校や私塾で学ぶ姿を想像する時に、ぼくらが通
赤ちゃんの育ちが変わりました
0歳の赤ちゃんの育ちが、
ここ10年でがらりと変わっていることにお気づきでしょうか。
両親で育てるカップルが増えました。
赤ちゃんを早期から保育園に預けるのがあたり前になりました。
赤ちゃんの縦だきが増えました。
赤ちゃんの手足が弱くなりました。
赤ちゃんの発達を阻害する育児グッズが増えました。
食の問題を抱えた赤ちゃんが増えました。
寝返りやハイハイができない赤ちゃんが増えました。
赤ちゃんと
【ゆきnote】先生の言葉をどのように受け止めて、どのように取り組むのが望ましいのだろう?次男の先生の言葉から考えたこと
前回はゆきのさんご長男が小学校に通っていた時の担任の先生に関するお話でしたが、今回はその続きになります!
▼ 長男の担任とはタイプの違う次男の担任
さて次男の先生は、市内の別の小学校に通うお子さんを持つ現役子育て世代。長男の担任だった先生とは親子ほどの年齢差があります。
私たち保護者と年齢が近い分、受け持つ子どもに対しても時には親に近いような目線で見てくださっているようで、よりきめ細かく、子