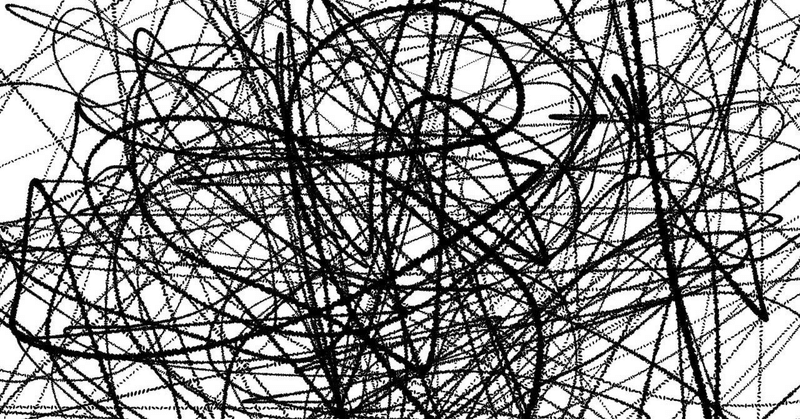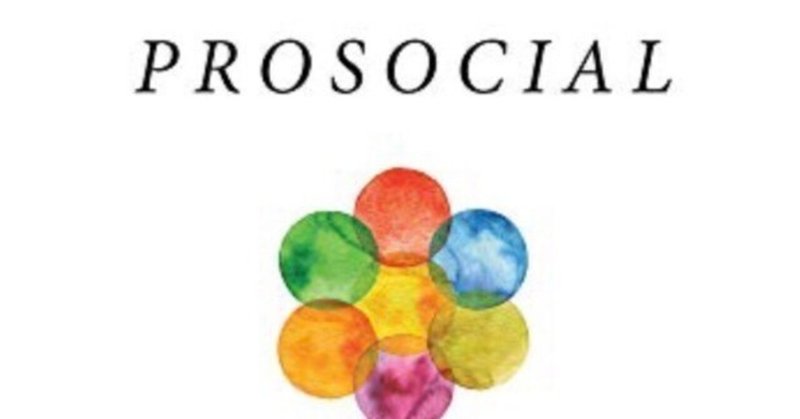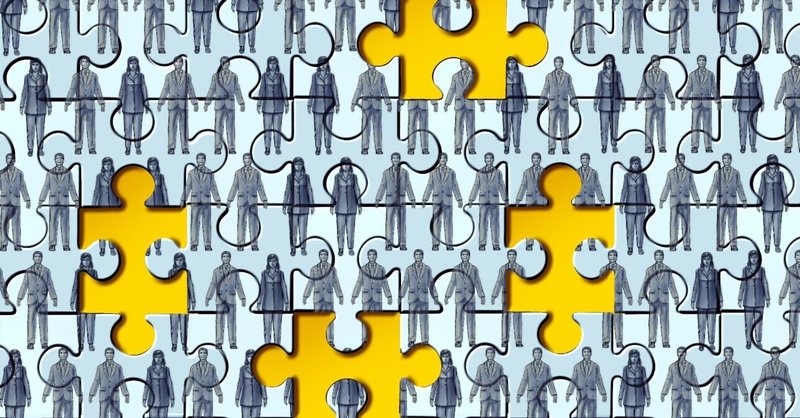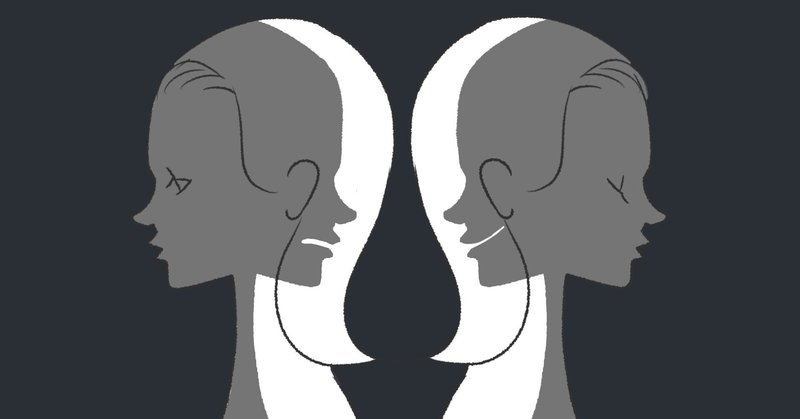記事一覧
壊して見せろよ、そのBad Habit!
りお>
SEKAI NO OWARIの『Habit』まだまだ人気ですよね。
すごく的を得ていて、私もずっと聴いてます。
なんで的を得ていると感じるのか、なぜこれほど共感するのかを紐解いていくことで理解したいと考えています。よろしくお願いします!
りお>
この、分類区別の習性は、生きるために人間が培ってきた脳(本能)が関係している気がします。なぜそんな習性を持つようになったんですかね。
としぞう
大阪のおばちゃんの『知らんけど』の効果
りお>
会社では成果が求められ、売上は全てを潤しますが、故に、無責任な事は言えない!となってしまう場面は、組織がでかくなればなるほど、影響力が大きくなればなるほど増えていく気がします。
でも、そういう組織こそ、大阪のおばちゃんの『知らんけど』みたいなものが必要なのだろうと思うんです。
しかし、知らんけどというスタンスは、無責任にも程があると。
このバランス感覚はどう取ればいいのでしょうか?
とし
心理的安全性と次の時代の採用要件
りお>
Googleの研究、プロジェクトアリストテレスでは、生産性向上に最も関連性の高い要素が『心理的安全性』であるとされました。
しかしこれは、心理的安全性が高いチームが必ず成功すると言っているわけではありません。管理職が心理的安全性を高めることに集中して頑張ったとしてもチームを成功に導けないケースも少なからずあったはずです。心理的安全性が高いとしても、チームがうまくいかないケースというのは、具
『ドラえもん』から学ぶAIとの付き合い方
テクノロジーの進展は、人間の欲を満たし、どんどん社会をよくしていきます。しかし適切にテクノロジーを人間社会に活用し、生態系にとって良い形にしていくためには、何を計測し、何を変えていくかを誤っては本末転倒です。今回は主に、組織開発という視点に立ち、テクノロジーのあり方、計測、定量化のあり方について議論していきたいと思います。
りお>
としぞうさんは、適材適所という決められた正解を目指してしまうと、
『メンタル不調』の科学と指針
りお>
人事をやっていると、なぜか突然、メンタル不調になって、離職・休職になってしまうというケースが散見されます。
なぜ、もっと早く気づいて対応することが出来なかったのかと、とても後悔する気持ちが毎回出てくる一方で、なぜ突然メンタル不調という状況になってしまうのか、理解することもできず、打開策が全く見えず、改善ができず、その状況を受け入れるしかないという状況になっています。
特に最近はリモートワー
『心理的安全性』vs『AIによる適材適所』
『適材適所』というのは人事にとって、非常に大きな論点でしょう。個人や、個人と個人の相互関係において、最適な人材配置を実現させる。これを、例えばAIなどを活用し、ストレス耐性、パーソナリティ、コミュニケーションタイプ、価値志向性の分類などでマッチングすれば最適になる!というサービスや、社会的な動きが一定あるように思います。
しかし、科学的データに基づき導き出された、生産性向上に最も関連性の高い要素
心理的安全性に完成はあるのか?
心理的安全性とは、嫌われることを恐れずに言いたいことをお互いに言い合える雰囲気のことです。
さて、心理的安全性には完成形があるのでしょうか。何をもって完成とするのでしょうか。今回の記事では、そのあたりについて深ぼっていけたらと思います。
心理的安全性の定義の詳細や科学的根拠についてはこちら↓
りお>
心理的安全性の最も難しいところは、それが常に未完成で終わってしまうということかなと思っていま
会議で『本当に言いたいこと』に気づく
心理的安全性を高めるためには、嫌われることを恐れずに言いたいことを言う必要があります。
しかし、『自分が本当に言いたいことは何か』という問いは難しいものです。常に自分が本当に言いたいことはこれであると言えるほど、人の感情や思考は単純ではなく、複雑で曖昧です。
特に、会社で働く時など、自らの意思だけではない外的圧力に従わざるを得ない状況下においては、『自分が本当に言いたいことは何なのか』はより複雑
心理的安全性を阻む脳の中の"原始人"
心理的安全性とは、『嫌われることを恐れずに言いたいことをお互いに言える雰囲気』のことです。
心理的安全性の定義と科学的根拠についてはこちら↓
心理的安全性は、言っていることは超シンプルだけど、心理的安全性が高まるとなんかうまくいかなさそうという感覚と心理的安全性は生産性向上と最も重要な関連を持つという科学的事実の乖離に苛まれてしまうケースは多々あります。その乖離は、現代に生きる我々全員の脳の中
心理的安全性はなぜ重要か
企業という組織にとって、『生産性向上』は最も重要な概念と言っても過言ではありません。生産性の定義を改めて確認すると、
では、生産性向上に最も大きな影響を与える要因は何でしょうか?
実は、それ、しっかり科学で解明されているんです。
この記事を読めば、心理的安全性がなぜこれほど重要視されてきているのか、心理的安全性が生む効果の科学的根拠を理解して頂けると思います。
りお:
最近、やたらと心理的安