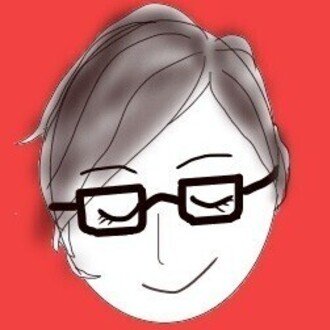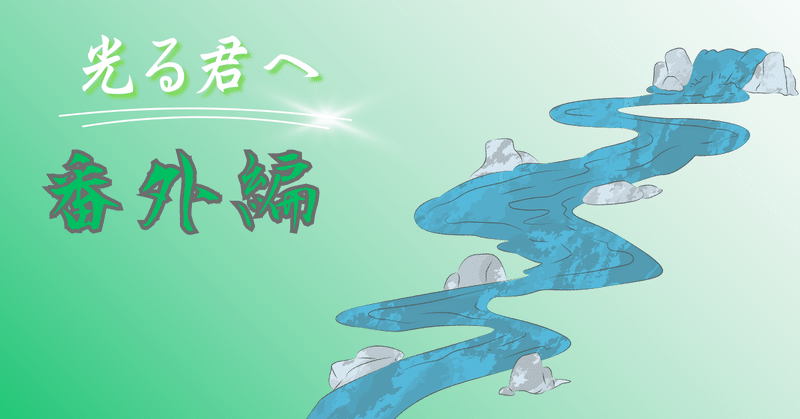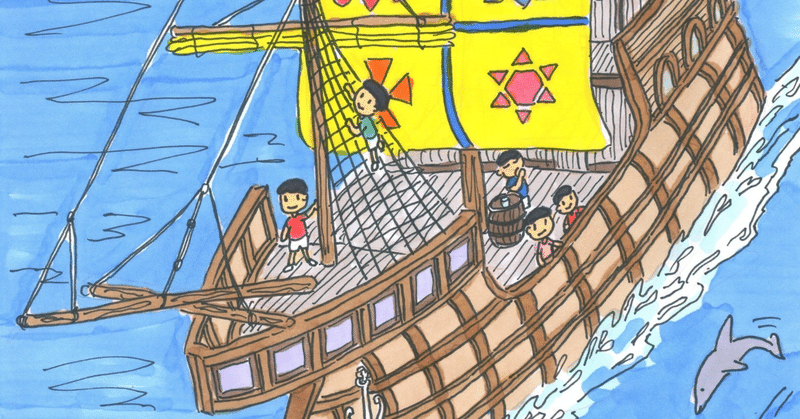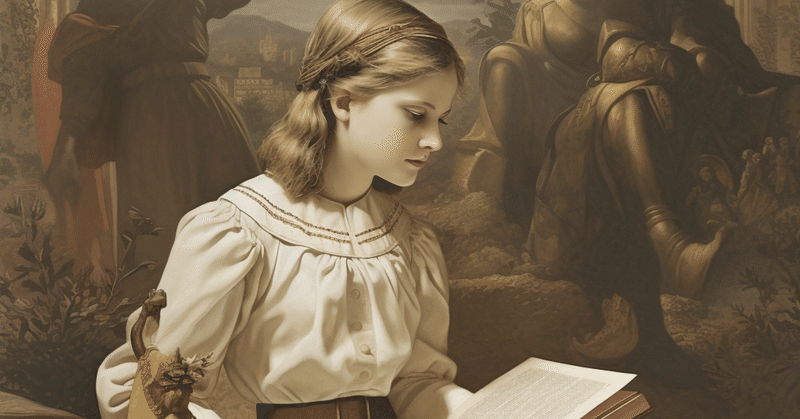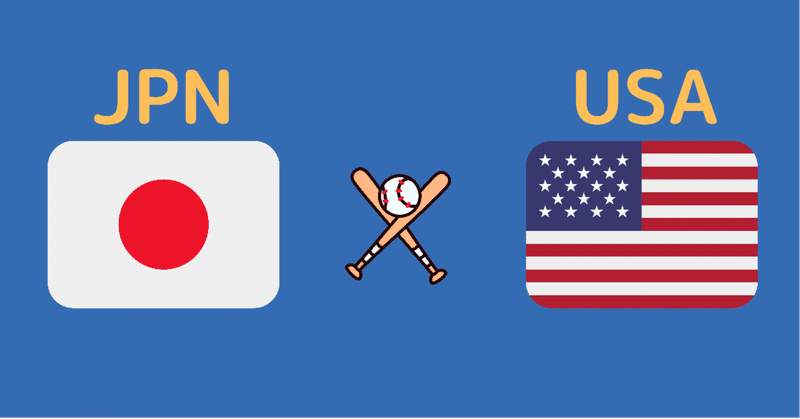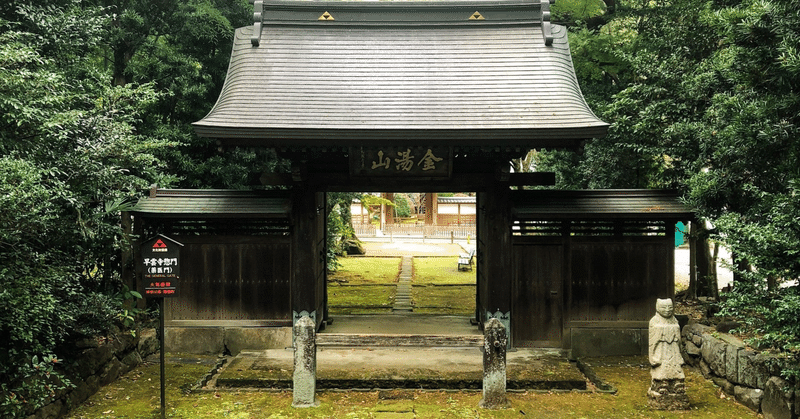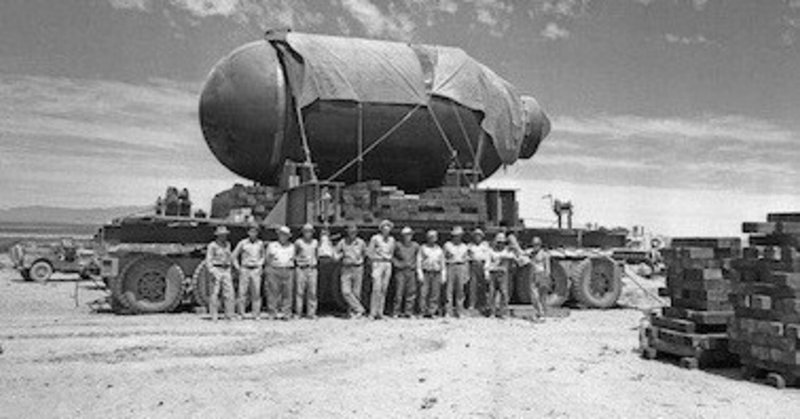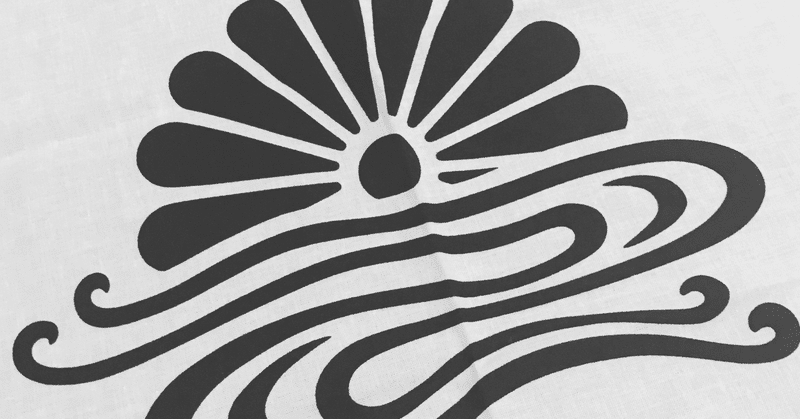#歴史
やっと本編!「光る君へ」の押さえたい見どころ
さて、今回は定子が残した3人の子供たちのその後を中心に今後の見どころポイントをピックアップしたいと思います。
ネタバレではありますが、史実に基づいた事なので、これからの大河の展開を見守るうえで、ドラマの創作具合を図るためにも、ここで整理しておきます。
後ろ盾の無い子らのその後定子は一条天皇の中宮という立場ではあるものの、父は志半ばで病没、兄・伊周と弟・隆家が「長徳の変」を起こしたことで失脚し、
押さえておきたい!日本史を彩った道長の側近たち
「光る君へ」もそろそろ中盤に差し掛かり、いよいよ越前編に突入するようです。
女院・藤原詮子(吉田羊)を呪詛したのは誰?
中宮・定子(高畑充希)が出家?
道長との過去の仲を父の為時に告げたまひろ
などなど、これらの伏線が次週以降の展開に生きてきそうで楽しみです。
さて、父に続いて、兄たちも次々と他界し、氏長者となった藤原道長(柄本佑)。
欲のない発言が目立ちますが、とんでもない。
一躍公卿のトッ
インドのカースト制度は植民地時代に創造された!? 支配者の思惑は分断統治と完全管理。いつの時代もこれからの時代も同じなのである。では、ぼくらはどうしたらいいのかという事を問い続けたいと思う。 タイトルも長いけど本文も長いです💦3,690文字プラスリンク多数!!
前々回記事に(「反集中とは何か?」の記事)ヨガ八支則を載せたところ、note仲間のぼたんさんからこんなコメントを頂いた。
ヨガを日々していくにあたってインドのカーストの事は全く氣にしていなかったぼくははっとした。勿論氣にしなくてもヨガは身体操法技術なので出来るのだが、そこはきちんと理解したいと、ぼくは思う。
時は古代インド紀元前13世紀
西方から移動してきたアーリア人がインドを支配。
バラモ
キャリア・クラッシス④ 北条早雲
◆シリーズコンセプト
https://note.com/pf_cody/n/n5a0786e755b4
【歴史×キャリア】というコンセプトで、現代の私達のキャリア形成の参考にするのが目的です。
過去の関連記事
①藤堂高虎(陸戦・海戦・築城なんでもござれの多能人材)
②豊臣秀長(百姓の次男から天下人秀吉を支えるNo.2へ)
③徳川秀忠(偉大過ぎる父から偉業を引き継いだ名君)
北条早雲(
妄想メモ〜桶狭間の戦い〜
noteでたくさんの知見をいただいている「千世さん」や「はーぼさん」の素晴らしい記事に刺激されて、私にも桶狭間ブームがきました!(笑)
◆千世さんの記事ご紹介
◆はーぼさんの記事ご紹介
https://note.com/think_easily/n/ne083923fb6d6
上記のお二方の記事を読んで、感想コメントを考えていたら、素朴な疑問として、「広い三河領において、なぜ桶狭間だったの
大阪人切望の「楠木正成の大河化」
※歴史上の人物、俳優名は敬称は省いてお伝えしています。
宴たけなわの「鎌倉殿…」ストーリーは史実通りだとわかってはいても面白いですね。
おそらく執権・北条義時の代までしか描かないのでしょうが、その鎌倉幕府にも終わりはあり、次の時代が訪れます。
次の室町時代までのつなぎとも言える南北朝時代は実はとても面白いのです。
しかしその面白みに気付くのは、私も随分とあとになってからでした。
天皇家が