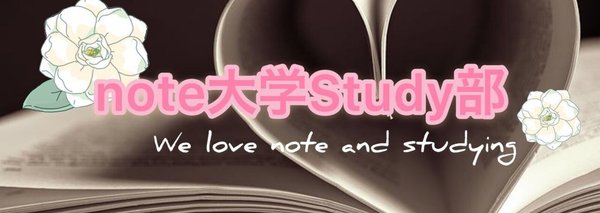三城俊一/歴史ライター
みきしゅんいち/塾講師+フリー文筆業/
歴史系書籍、教材執筆等で実績あり。
専門の教育…
記事一覧
【宣伝】「死ぬまでに攻めたい戦う山城50」(イースト・プレス)
この度、制作に携わった書籍が発売されました。今泉慎一著・三城俊一編「死ぬまでに攻めたい戦う山城50」(イースト・プレス)です。
城といえば、立派な天守と石垣、水堀のあるこんな城を思い浮かべるでしょう。
しかし、戦国時代に主流だったのは自然の地形を生かし、土で守りを固めた山城でした。
著者の今泉慎一さんは、これまで600以上の城を踏破した城マニア。今泉さんに取材し、訪問記録を書き起こし