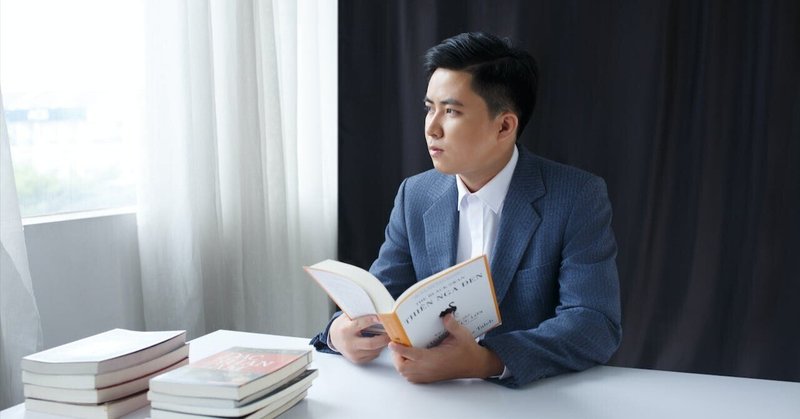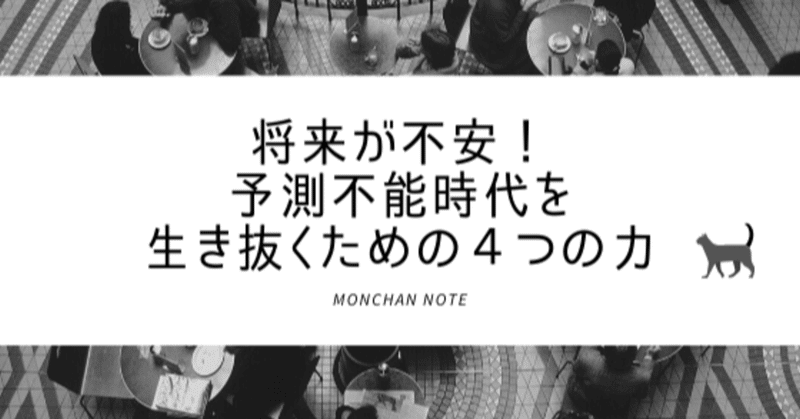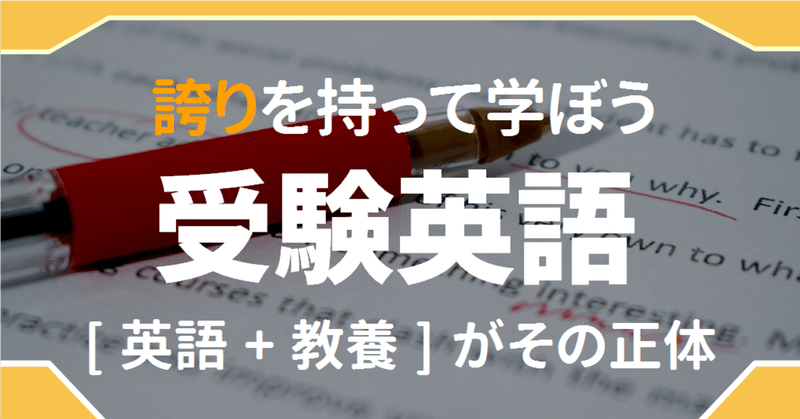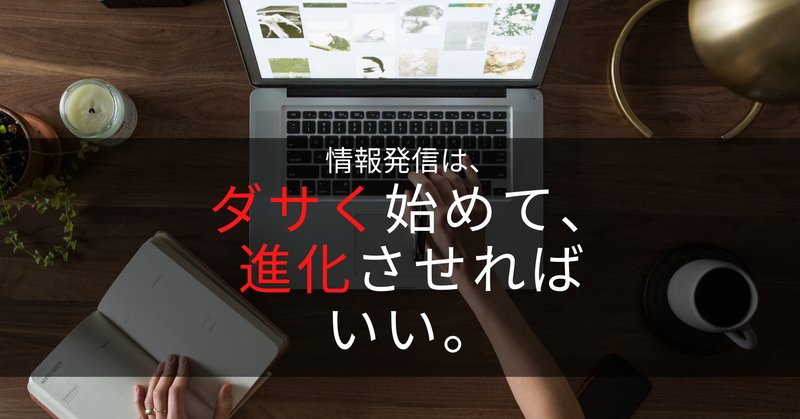#日記
民富を叶える「安心の生産」
column vol.1135
こちらは、中国戦国時代の思想家である孟子の言葉です。
〈東洋経済オンライン / 2023年10月10日〉
孟子といえば、弱肉強食の「覇道政治」ではなく、礼に基づいて行う仁義の政治「王道政治」を目指した偉人として知られていますね。
その孟子は国富ではなく「民富」が大事であると説いています。
つまり、真の国力とは税収の多さである「国富」ではなく、国民の資産であ
テクノロジーから学ぶ「STEM教育」が注目されるわけとは?
今日は世界で今注目の「STEM教育」について書いていこうと思います!
STEM教育とは、一言でいうと「現代のグローバル社会において、科学技術の発展に貢献できる人を育てる」教育のことです。
今の現代の情報社会では、テクノロジーの知識と知恵が生活に必要不可欠となっています。画期的なSTEM教育の体制が学校や企業などに取り入られていることで近年注目を集めているんです。
調べるまでは全く知らなかった
「将来、何になりたいの?」という質問はなくした方がいい
大学時代、私が人から訊かれて一番苦痛だったのが「将来、何になりたいの?」という質問だった。
その問いに爽やかに即答できる人たちのことが心底羨ましかった。
私とは何か ー「個人」から「分人」へー より抜粋
今日読んでいた本にこんな一節があった。やっぱりそうだよな、とすごく考えさせられた。
理由は2つある。
1つ目は、僕自身、つい先日投稿した記事でもまさに同様のことを書いていたということ。
【中高生のみんなへ】受験英語を勉強している自分に誇りを持ってください。
こんにちは、語学の裏設定のゆうです。
今日は受験英語の忘れられている価値についてお話しようと思います。
今、中学生だったり高校生だったりするみんなは、
学校で英語を勉強していてあまり良い気分ではないと思います。
なぜなら、
受験英語は会話につながらないから意味がない、
という大人たちの主張が世の多数派になっていて、
そんな批判の的になっている受験英語を必死に勉強しなくてはならないのですから
情報発信は、「ダサく始めて」進化させればいい。
noteを書き始めて、30記事になりました。ほぼ毎日習慣として朝にアップすることができています。
Twitter、Facebook、Instagram、note、(時々ブログ)、メルマガ、LINE公式アカウント、音声発信。
「たくさんの発信が毎日できるのは、なぜですか?」と聞かれると、「楽しいから」に他ならない。
「情報発信が続かない」
「私も発信したいけど、書けることが何もない」
「やって